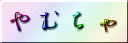 |
|---|
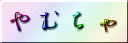 |
|---|
 キネマ霊園
キネマ霊園 キネマフォーラム
キネマフォーラム  掲示板
掲示板
| ぼくを葬る |  |
|---|
|
2005年作品。フランス映画。81 分。配給=ギャガ・コミュニケーションズ。監督=フランソワ・オゾン(Francois Ozon)。製作=オリヴィエ・デルボスク(Olivier Delbosc)、マルク・ミソニエ(Marc Missonnier)。脚本=フランソワ・オゾン(Francois Ozon)。撮影=ジャンヌ・ラポワリー(Jeanne Lapoirie)。プロダクションデザイン=カーチャ・ヴィシュコフ(Katia Wyszkop)。衣装デザイン=パスカリーヌ・シャヴァンヌ(Pascaline Chavanne)。編集=モニカ・コールマン(Monica Coleman)。ロマン=メルヴィル・プポー(Melvil Poupaud)、 ローラ=ジャンヌ・モロー(Jeanne Moreau)、ジャニィ=ヴァレリア・ブルーニ・テデスキ(Valeria Bruni Tedeschi)、父=ダニエル・デュヴァル(Daniel Duval)、母=マリー・リヴィエール(Marie Riviere)、サシャ=クリスチャン・センゲワルト(Christian Sengewald)、ソフィー=ルイーズ=アン・ヒッポー(Louise-Anne Hippeau)、医師=アンリ・ドゥ・ロルム(Henri de Lorme)、ブルーノ=ウォルター・パガノ(Walter Pagano)、ロマン(少年時代)=ウゴ・スーザン・トラベルシ(Ugo Soussan Trabelsi) フランソワ・オゾン監督が、「まぼろし」に続いて描く「死」をめぐる3部作の第2作。今回は「自分の死」を正面から見つめる。31歳の人気ファッション・フォトグラファーであるロマンは、突然医師に末期ガンで余命3カ月と告げられる。ロマンは化学療法を拒み、最後の日々と格闘する。どのシーンも徹底的に考え抜かれ、場面設定が独創的。映像は鋭利で美しく、切ない。音楽を最少に抑え、日常の音を生かすことで、ロマンの孤独が際立っていた。ロマン役のメルヴィル・プポーの熱演は、どれほど高く評価しても足りないほど素晴らしい。監督の持ち味である悪趣味な毒は、ときに辛らつなユーモアに、ときにテーマを掘り下げる激辛スパイスに変じる。 「余命3ヶ月。あなたには何が残せますか?」という宣伝コピーは、この作品の比類なさを見逃している。ロマンは、何も残そうとはしていない。一見、子どもや写真に思いを込めているかのように見えるが、残すことに執着はしていない。もっと自由になっている。 ロマンは、家族や恋人や宗教に頼ることなく、最後まで独りで死と面している。同じテーマを描いた多くの作品と決定的に違っている。そして子ども時代への回帰、自然の摂理への礼節を通じて、死へと身を横たえる。多くの人々、子どもたちで騒がしい海辺で、孤独に死との折り合いをつける。日が沈みかけ、ロマンだけが海辺に残る。太陽がロマンの横顔の上で海に溶ける。なんという崇高なシーンだろう。「見つかった/何を? 永遠を/太陽と溶けあった/海だ」(アルチュール・ランボー「地獄の季節」)。 ロマンが末期ガンであることを家族には隠し、祖母ローラにだけ打ち明けた理由を「僕に似ているから。もうすぐ死ぬんだ」と話したとき、ローラは「今晩、お前と一緒に死にたいわ」と応える。ローラを演じたジャンヌ・モローには、感嘆した。友人であったマルグリット・デュラスの晩年を描いた「デュラス 愛の最終章」(2001年、ジョゼ・ダヤン監督)が、最後の作品になるのかと思っていたが、すごい演技をみせてくれた。 |
| Vフォー・ヴェンデッタ |  |
|---|
|
2005年作品。イギリス・ドイツ合作。132 分。配給=ワーナー。監督=ジェームズ・マクティーグ(James McTeigue)。製作=ジョエル・シルヴァー(Joel Silver)、アンディ・ウォシャウスキー(Andy Wachowski)、ラリー・ウォシャウスキー(Larry Wachowski)、グラント・ヒル(Grant Hill)。製作総指揮=ベンジャミン・ウェイスブレン(Benjamin Waisbren)。キャラクター創造=アラン・ムーア(Alan Moore)、デヴィッド・ロイド(David Lloyd)。脚本=アンディ・ウォシャウスキー(Andy Wachowski)、ラリー・ウォシャウスキー(Larry Wachowski)。撮影=エイドリアン・ビドル(Adrian Biddle)。プロダクションデザイン=オーウェン・パターソン(Owen Paterson)。衣装=サミー・シェルドン(Sammy Sheldon)。編集=マーティン・ウォルシュ(Martin Walsh)。音楽=ダリオ・マリアネッリ(Dario Marianelli)。イヴィー=ナタリー・ポートマン(Natalie Portman)、V=ヒューゴ・ウィーヴィング(Hugo Weaving)、フィンチ警視=スティーヴン・レイ(Stephen Rea)、ゴードン・ディートリッヒ=スティーヴン・フライ(Stephen Fry)、アダム・サトラー議長=ジョン・ハート(John Hurt)、クリーディー=ティム・ピゴット=スミス(Tim Pigott-Smith)、ドミニク警部=ルパート・グレイヴス(Rupert Graves)、プロセロ=ロジャー・アラム(Roger Allam)、ダスコム=ベン・マイルズ(Ben Miles)、バン=ヴァレリー・ベリー(Valerie Berry)、 デリア・サリッジ=シニード・キューザック(Sinead Cusack)、バレリー・ペイジ=ナターシャ・ワイトマン(Natasha Wightman)、リリマン主教=ジョン・スタンディング(John Standing)、エサレッジ=エディ・マーサン(Eddie Marsan) アラン・ムーアとデヴィッド・ロイドが1980年代に発表したコミックを、ウォシャウスキー兄弟が独自に脚本化したサスペンス・アクション。監督は「マトリックス」シリーズなどで第一助監督を務め、本作が監督デビューのジェームズ・マクティーグ。近未来の独裁国家となったイギリスが舞台。1605年に国王の圧政に反発し国家転覆を図り失敗に終わったガイ・フォークスの仮面をつけた男Vは、支配層への復讐と国民の覚醒を目指しテロ行為を繰り返している。国民の恐怖心を利用した支配を強化するアメリカへの批判が前面に出た作品と言える。感情移入ができないという映画評があるが、私は国会議事堂前に集まった群集とともにあった。 イヴィー役ナタリー・ポートマンは、スキン・ヘッドになっただけでなく、これまで見た中で最高の演技。ヒューゴ・ウィービングは仮面をつけたVの悲哀を見事に演じた。終始仮面を付けた演技では「キングダム・オブ・ヘブン」のエドワード・ノートンを思い出すが、ノートンの場合は辛うじて眼の演技が可能だった。V野仮面はまったく表情が変えられないだけに、身ぶりだけの渾身の演技だった。ただ、Vには最後まで孤高のダンディズムを貫いてもらいたかった。ラストのべたべたな愛の告白は、彼にはそぐわない。 イヴィーが「岩窟王」を見ながらVに「ハッピーエンド?」と聞く。Vは「映画だから」と答える。この場面が、自作評だと、あとで気づいた。ウォシャウスキー兄弟の茶目っ気だ。 |
| 寝ずの番 |  |
|---|
|
2006年作品。日本映画。110 分。配給=角川ヘラルド・ピクチャーズ。監督=マキノ雅彦。製作=鈴木光プロデューサー=坂本忠久。林由恵。企画=鈴木光。原作=中島らも『寝ずの番』(講談社刊)、脚本=大森寿美男。撮影=北信康。美術=小澤秀高。衣装=宮本まさ江。編集=田中愼二。音楽=大谷幸。音楽プロデューサー=長崎行男。エンディングテーマ=A・cappellers『Don't Worry, Be Happy』。照明=豊見山明長。題字=緒形拳。録音=阿部茂。橋太=中井貴一、茂子=木村佳乃、橋枝=木下ほうか、橋七=田中章、多香子=土屋久美子、美紀=真由子、小田先生=石田太郎、田所=蛭子能収、バーの女=高岡早紀、元鉄工所の社長=堺正章、橋次=笹野高史、岸部一徳、橋弥=長門裕之、志津子=橋鶴=富司純子、桂三枝、笑福亭鶴瓶、浅丘ルリ子、米倉涼子、中村勘三郎[18代目] マキノ省三が日本で初めて映画撮影を行ったのが1907年の「狐忠信」。残念ながら完成には至らなかったが、2006年はこの年から数えて100年目となる記念すべき年だ。マキノ省三監督を祖父に持つ津川雅彦が、マキノ雅彦を名乗った初監督作品「寝ずの番」。中島らもの短編小説をもとに、上方落語界の通夜で繰り広げられるファンタジーあふれる人情喜劇が誕生した。出演者は、あっと驚く名演技を見せる。 次から次へと飛び出す爆笑エピソード。通夜が艶(つや)へと変ぼうする座敷歌の饗宴。そのテンポ、そのユーモア、ペーソスが抜群に良い。「バチが当たるほど面白い!」という宣伝コピーは嘘じゃない。久しく日本映画が忘れていた、すこぶる粋な「お通夜喜劇」である。お葬式を描いた喜劇には、伊丹十三監督のデビュー作「お葬式」があるが、そのユーモアの質はかなり違う。同じ喜劇でも、「寝ずの番」は柔らかく温かい。ラストの軽さも絶妙だ。 |
| 雪に願うこと |  |
|---|
|
2005年作品。日本映画。112 分。配給=ビターズ・エンド。監督=根岸吉太郎。原作=鳴海章「輓馬」(文藝春秋刊)。脚本=加藤正人。撮影=町田博。照明=木村太朗。編集=川島章正。美術=小川富美夫。音楽=伊藤ゴロー。矢崎学=伊勢谷友介、矢崎威夫=佐藤浩市、田中晴子=小泉今日子、首藤牧恵騎手=吹石一恵、小笠原調教師=香川照之、須藤=小澤征悦、黒川獣医=椎名桔平、大関(シャドーキングの馬主)=津川雅彦、藤巻保=でんでん、加藤テツヲ=山本浩司、富永厩務員=岡本竜汰、湯原厩務員=出口哲也、矢崎静子=草笛光子、丹波=山崎努 帯広在住の作家・鳴海章の小説「輓馬」を読み、ばんえい競馬を見た相米慎二監督が、「風花」に続いて映画化を希望していたが、2001年に他界。根岸吉太郎監督が、その遺志を引き継いだ。東京国際映画祭でグランプリ、監督賞、最優秀男優賞、観客賞の4冠を受賞。日本映画のグランプリ受賞は、相米慎二監督の『台風クラブ』以来の快挙。 悲恋なし、殺人なし、CGなし。ばんえい競馬をめぐる人間ドラマというストレートな物語と気負いのない落ち着いた映像。派手さはない。それでも、物語に奥行きがあり、面白さに満ちている。厳寒の中で走る馬たちの湯気や白い息が、幻想的にスクリーンに立ち上り、さまざまな表情をみせる。厩舎での騒々しくて和やかな食事のシーンは、久々に体験した楽しさ。そして、廃線になった鉄道の石橋(士幌線タウシュベツ橋梁)が、聖地のように凛とした存在感をたたえていたことに感動した。 登場する俳優たちは、名優ぞろいだが、危険を顧みず実際にばんえい競馬のレースを走った吹石一恵の頑張り、馬との交流が、この作品全体を引き締めていた。母親的存在である賄い婦役の小泉今日子は、複雑な歴史を背負った中年女性を自然に演じ、またまた驚かされた。登場人物それぞれに、語らない過去が確かに感じられ、作品を味わい深くしている。傑作というよりも逸品だ。東京での仕事の描き方など、不満がないわけではないが。 |
| ナイトウォッチ/NOCHNOI DOZOR |  |
|---|
|
2004年作品。ロシア映画。115 分。配給=FOX。監督=ティムール・ベクマンベトフ(Timur Bekmambetov)。製作=コンスタンティン・エルンスト(Konstantin Ernst)、アナトリー・マキシモフ(Anatoli Maksimov)。原作=セルゲイ・ルキヤネンコ(Sergei Lukyanenko)。脚本=ティムール・ベクマンベトフ(Timur Bekmambetov)、レータ・カログリディス(Laeta Kalogridis)。撮影=セルゲイ・トロフィモフ(Sergei Trofimov)。美術=ワレーリー・ヴィクトロフ(Valeri Viktorov)。編集=ドミトリー・キセレフ(Dmitri Kiselyov)。音楽=ユーリ・ポテイェンコ(Yuri Poteyenko)。アントン・ゴロデツキー=コンスタンチン・ハベンスキー(Konstantin Khabensky) 、ボリス・ゲッサー=ウラジーミル・メニショフ(Vladimir Menshov)、スヴェトラーナ・ナザロワ=マリア・ポロシナ(Mariya Poroshina)、オリガ=ガリーナ・チューニナ(Galina Tyunina)、ザヴロン=ヴィクトル・ヴェルズビツキー(Viktor Verzhbitsky)、イリーナ=マリア・ミロノーワ(Mariya Mironova)、アンドレイ=イリア・ラグテンコ(Ilya Lagutenko)、アリス=ジャンナ・フリスケ(Zhanna Friske)、イゴール=ディマ・マルティノフ(Dmitry Martynov) ロシアで歴代興行記録を塗り替える大ヒットとなったダーク・ファンタジー。原作は、ロシアで250万部を超えるベストセラーのダーク・ファンタジー3部作「ナイト・ウォッチ」「デイ・ウォッチ」「ダスク・ウォッチ」。映画も原作と同じ3部作として製作され、すでに第2部も完成し、1部以上にロシアで大ヒット。第3部は、ハリウッドで撮影されることが決まっている。これまでのロシア映画のイメージを覆す、キレの良い斬新なヴィジュアル表現が新鮮。 エイプリルフールに観るべき作品。 光の勢力と闇の勢力の長きにわたる闘いというファンタジーではお馴染みの設定。光は闇の監視人「ナイト・ウォッチ」、闇は光の監視人「デイ・ウォッチ」として互いを見張り、その均衡を保っている。特殊な超能力を持つ「異種(アザーズ)」に目覚めた人間は、光につくか闇につくか、それぞれ本人の意志で決めることという規則の必然性が、良く分からない。非常に大きな設定だが、ストーリーは妙にこじんまりした感じだ。 実験的な映像編集とストーリー展開が、ともすれば乖離し、予告編では期待させたCGを駆使したスケール感も、生かされていない。英語の字幕の先駆的なモーション・グラフィックスは、もっと冒険すべきだった。重厚だが真面目すぎるロシア映画と、軽薄だが派手なアメリカ映画の、良い面を両方取り入れようとして失敗したと思う。試み自体は評価するが。 ただ、出だしの魔女のおばあさんと闇の番人の攻防、そしてラストのモスクワで歴史がシンクロする場面は、見ごたえがあった。驚くべきというほどではないが、なかなかのパワーを感じた。
|
| 1996年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2006年 | 1月 | 2月 | 3月 |