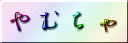 |
|---|
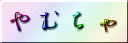 |
|---|
 キネマ霊園
キネマ霊園 キネマフォーラム
キネマフォーラム  掲示板
掲示板
| ハッカビーズ |  |
|---|
2004年作品。アメリカ映画。107分。配給=日本ヘラルド映画。監督=デヴィッド・O・ラッセル(David O. Russell)。製作=グレゴリー・グッドマン(Gregory Goodman)、スコット・ルーディン(Scott Rudin)、デヴィッド・O・ラッセル(David O. Russell)。製作総指揮=マイケル・クーン(Michael Kuhn)。脚本=デヴィッド・O・ラッセル(David O. Russell)、ジェフ・バエナ(Jeff Baena)。撮影=ピーター・デミング(Peter Deming)。美術=K・K・バレット(K.K. Barrett)。編集=ロバート・K・ランバート(Robert K. Lambert)。音楽=ジョン・ブライオン(Jon Brion)。アルバート・マルコヴスキー=ジェイソン・シュワルツマン(Jason Schwartzman)、ブラッド・スタンド=ジュード・ロウ(Jude Law)、ベルナード=ダスティン・ホフマン(Dustin Hoffman)、ヴィヴィアン=リリー・トムリン(Lily Tomlin)、トミー・コーン=マーク・ウォールバーグ(Mark Wahlberg)、カテリン=イザベル・ユペール(Isabelle Huppert)、ドーン=ナオミ・ワッツ(Naomi Watts)
実存主義を説く哲学探偵が登場するが、どうみてもセラピストだ。アメリカにはセラピストがあふれている。もっともらしい説教が鼻につく。ラストは、全体への融合でも孤独な個でもなく具体的な関係性が大切という月並みな結論。ダスティン・ホフマンら豪華なキャストが生かされていないが、シニカルなフランス人思想家カテリンを演じたイザベル・ユペールの存在感だけは、傑出していた。
| ランド・オブ・ザ・デッド |  |
|---|
2005年作品。93分。アメリカ・カナダ・フランス合作。配給=UIP。監督・製作=ジョージ・A・ロメロ(George A. Romero)。製作総指揮=スティーヴ・バーネット、デニス・E・ジョーンズ。製作=マーク・カントン、バーニー・ゴールドマン、ピーター・グランウォルド。製作総指揮=スティーヴ・バーネット、デニス・E・ジョーンズ。撮影=ミロスラフ・バシャック。プロダクション・デザイナー=アーヴ・グレイウォル。編集=ミッシェル・ドハーティー 。特殊メイクアップ=グレッグ・ニコテロ 、ハワード・バーガー。衣装=アレックス・カヴァナフ。音楽=ラインホルト・ハイル、ジョニー・クリメック。特殊メイクアップ=KNB エフェクト・グループ。ライリー=サイモン・ベーカー(Simon Baker) 、チョロ=ジョン・レグイザモ(John Leguizamo)、カウフマン=デニス・ホッパー(Dennis Hopper)、スラック=アーシア・アルジェント、 チャーリー=ロバート・ジョイ、ビッグ・ダディ=ユージン・クラーク、フォトブース・ゾンビーズ=サイモン・ペッグ、エドガー・ライト、 橋守ゾンビ=グレッグ・ニコテロ
高層ビルで安全に暮らす裕福な支配者層、恐怖に怯えて生きるスラム層、その周りにうごめく圧倒的多数のゾンビ。そのゾンビたちが武器を持ち、集団行動をとって要塞都市に侵入、権力者たちを滅ぼす。現在のアメリカの抱える差別や恐怖を反映したストーリーかもしれないが、物語の構造は古くさい。「ドーン・オブ・ザ・デッド」(ザック・スナイダー監督、2004年)の方が、アメリカの抱える恐怖心をストレートに反映していたと思う。登場人物も、誰一人魅力を感じない。デニス・ホッパーはなんでつまらない権力者を演じたのだろう。
| ノロイ |  |
|---|
2005年作品。日本映画。115 分。配給=ザナドゥー。監督=白石晃士。プロデューサー=一瀬隆重(Takashige Ichise)。松本まりか、アンガールズ、荒俣宏、飯島愛、高樹マリア、ダンカン
「禍具魂(かぐたば)」という謎の言葉が、不思議と耳に残る。さまざまな怪奇現象が、下鹿毛村という1978年にダムに沈んだ村で行われていた「鬼祭」につながっていく展開も興味深い。そして、松本まりかの演技は特筆すべきレベルだ。作品のリアリティを支えた。「霊体ミミズ」を警告し全身をアルミで覆った霊能力者・堀光男、かつて鬼祭で「かぐたば」を演じて豹変した禍々しい石井潤子、11歳の可憐な超能力少女・矢野加奈。これらの役を演じた無名の俳優たちにも大きな拍手を贈りたい。それぞれ演技賞ものだ。そうそう、怪奇実話作家・小林雅文役も忘れてはいけない。エンドクレジットが一切ないので名前が分からないが。
| メタリカ :真実の瞬間 METALLICA : SOME KIND OF MONSTER |  |
|---|
2004年作品。アメリカ映画。141 分。配給=パラマウント ホーム エンタテインメント ジャパン。監督=ジョー・バーリンジャー(Joe Berlinger)、ブルース・シノフスキー(Bruce Sinofsky)。製作=ジョー・バーリンジャー(Joe Berlinger)、ブルース・シノフスキー(Bruce Sinofsky)。製作総指揮=ジョン・ケイメン(Jon Kamen)、フランク・シャーマ(Frank Scherma)。撮影=ロバート・リッチマン(Robert Richman)、ウォルフガング・ヘルド(Wolfgang Held)。ジェームズ・ヘットフィールド(James Hetfield)=メタリカ・ボーカル、ギター、ラーズ・ウルリッヒ(Lars Ulrich)=メタリカ・ドラム、カーク・ハメット(Kirk Hammett)=メタリカ・ギター、クリフ・バートン(Cliff Burton)=元メタリカ・ベース(1986年没 享年24歳)、ジェイソン・ニューステッド(Jason Newsted)=元メタリカ・ベース(1986年〜2001年在籍)、ロバート・トゥルージロ(Robert Trujillo)=メタリカ・ベース(2003年加入)、デイヴ・ムステイン(Dave Mustaine)元メタリカ・リードギター(1981年〜1983年在籍)、ボブ・ロック(Bob Rock)=レコード・プロデューサー(アルバム「セイント・アンガー」ではベースも担当)、フィル・トウル(Phil Towle)=セラピスト兼パフォーマンス向上のアドバイザー(2001年初頭にメタリカのマネジメント、Qプライムの要請でバンドに雇われた)
バンドのイメージが壊れることをいとわずに、カメラを回し続け、それを公開するということは、勇気のいることだ。しかし赤裸々に己をさらけだすという点では、ヘヴィメタルの魂と重なる。そして人間的な対立が音楽を通じて和解ヘと至るプロセスは、やはり感動的だ。アルバム制作の過酷な実態も明らかにされる。観終わると、無性にアルバムが聞きたくなる。
| 妖怪大戦争 |  |
|---|
2005年作品。日本映画。124 分。配給=松竹。監督=三池崇史。製作=黒井和男。プロデューサー=井上文雄、清水俊。プロデュース=水木しげる(プロデュースチーム「怪」)、荒俣宏(プロデュースチーム「怪」)、京極夏彦(プロデュースチーム「怪」)、宮部みゆき(プロデュースチーム「怪」)。製作総指揮=角川歴彦。企画=佐藤直樹。脚本プロデュース=荒俣宏。脚本=三池崇史、沢村光彦、板倉剛彦。撮影=山本英夫。特殊メイク=松井祐一。美術=佐々木尚。デザイン=百武朋 (妖怪デザイン)、井上淳哉(妖怪デザイン)、竹谷隆之(妖怪デザイン)、韮沢靖(機怪デザイン)。造型=松井祐一、百武朋。編集=島村泰司。主題歌=忌野清志郎『愛を謳おう』。CGIディレクター=太田垣香織。CGIプロデューサー=坂美佐子。スタントコーディネート=辻井啓伺。音響効果=柴崎憲治。企画協力=郡司聡。照明=木村匡博。操演=鳴海聡。装飾=西尾共未。録音=中村淳。妖怪キャスティング=京極夏彦。 稲生タダシ=神木隆之介、佐田(雨上がり決死隊)=宮迫博之、稲生陽子=南果歩、稲生タタル=成海璃子、「怪」編集長=佐野史郎、宮部先生=宮部みゆき、読書好きのホームレス=大沢在昌、駐在=徳井優、アナウンサー=板尾創路、屋台のオヤジ=ほんこん、よういちの父=田中要次、阿倍晴明=永澤俊矢、大人のタダシ/タダシの父=津田寛治、牛舎の農夫=柄本明、稲木俊太郎=菅原文太、猩猩=近藤正臣、川姫=高橋真唯、川太郎=阿部サダヲ、一本だたら=田口浩正、大天狗=遠藤憲一、砂かけ婆=根岸季衣、ろくろ首=三輪明日美、雪女=吉井怜、豆腐小僧(雨上がり決死隊)=蛍原徹、大首=石橋蓮司、ぬらりひょん=忌野清志郎、油すまし=竹中直人、山ン本五郎佐衛門=荒俣宏、神ン野悪五郎=京極夏彦、妖怪大翁=水木しげる、小豆洗い(ナインティナイン)=岡村隆史、鳥刺し妖女・アギ=栗山千明、加藤保憲=豊川悦司
怖いというよりも、楽しく笑える作品。大半の妖怪たちがやる気がなく脱力しているのがおかしい。ただ好奇心だけはある。妖怪を個性的な俳優たちが演じている。油すましの竹中直人は、そのまんま。ろくろ首の三輪明日美はあたり役。夏の雪女を演じた吉井怜にもにやり。童心に返っていたので、川姫とアギのお色気対決にちょっとドッキリ。神木隆之介は相変わらず上手だが、パワーは川太郎役の阿部サダヲが一枚上だった。ぼけたじいちゃんを演じた菅原文太もさすが。いろいろ笑わせてくれた。ガメラネタをはじめ随所にくすくす笑えるギャグがちりばめられている。ただ、麒麟送子の物語だからといってキリンビールが出てきて、飲むと妖怪が見えるようになるという設定はやりすぎな感じ。そこまでスポンサーに媚びなくても。
| リンダ リンダ リンダ |  |
|---|
2005年作品。日本映画。114 分。配給=ビターズ・エンド。監督=山下敦弘。プロデューサー=根岸洋之、定井勇二。脚本=向井康介、宮下和雅子、山下敦弘。撮影=池内義浩。美術=松尾文子。編集=宮島竜治。音楽=ジェームズ・イハ(James Iha)。主題歌=ザ・ブルーハーツ『終わらない歌』。照明=大坂章夫。録音=郡弘道。ソン=ペ・ドゥナ(Bae Doo-na)、山田響子=前田亜季、立花恵=香椎由宇、白河望=関根史織(Base Ball Bear)、丸山凛子=三村恭代、今村萠=湯川潮音、中島田花子=山崎優子、小山先生=甲本雅裕、槙原裕作=松山ケンイチ、大江一也=小林且弥、阿部友次=小出恵介、石川友康=三浦哲郁、前園トモキ=三浦誠己、恵の母親=りりィ、中山先生=藤井かほり、飯島浩平=浜上竜也、スタジオQの店員=山本浩司、カラオケの店員=山本剛史
韓国留学生ソン役のペ・ドゥナは、徐々に前向きになる少女を好演。うまい。「ローレライ」の香椎由宇も気が短い癖のある立花恵を魅力的に演じた。美形なだけではない。バンド演奏シーンでは、皆がきらきらと輝いている。「ドブネズミみたいに美しくなりたい。写真に写らない美しさがあるから」という「リンダ リンダ リンダ」(1987年)の歌詞のインパクトは、今も失われていない。少女たちが生まれたころに登場し、多くの若者に影響を与えたブルーハーツは、今後も確かに歌い継がれていくことだろう。
| ヒトラー 最期の12日間 |  |
|---|
2004年作品。ドイツ・イタリア映画。155 分。配給=ギャガ・コミュニケーションズ。監督=オリヴァー・ヒルシュビーゲル(Oliver Hirschbiegel)。製作=ベルント・アイヒンガー(Bernd Eichinger)。原作=ヨアヒム・フェスト(Joachim Fest)『ヒトラー 最期の12日間』(岩波書店刊)、トラウドゥル・ユンゲ(Traudl Junge)『私はヒトラーの秘書だった』(草思社刊)。脚本=ベルント・アイヒンガー(Bernd Eichinger)。撮影=ライナー・クラウスマン(Rainer Klausmann)。音楽=ステファン・ツァハリアス(Stephan Zacharias)。アドルフ・ヒトラー=ブルーノ・ガンツ(Bruno Ganz)、トラウドゥル・ユンゲ=アレクサンドラ・マリア・ラーラ(Alexandra Maria Lara)、エヴァ・ブラウン=ユリアーネ・ケーラー(Juliane Kohler)、ヘルマン・フェーゲライン=トーマス・クレッチマン(Thomas Kretschmann)、マグダ・ゲッベルス=コリンナ・ハルフォーフ(Corinna Harfouch)、ヨーゼフ・ゲッベルス=ウルリッヒ・マテス(Ulrich Matthes)、アルベルト・シュペーア=ハイノ・フェルヒ(Heino Ferch)、ハインリヒ・ヒムラー=ウルリッヒ・ノエテン(Ulrich Noethen)、シェンク博士=クリスチャン・ベルケル(Christian Berkel)
この作品は、ドイツ政府が後援している。60年前の戦争の歴史を伝えようとしている。ホロコーストなどが、まったく描かれていないことへの紋切り型の批判は的外れだと思う。とりわけ、イスラエルにこの作品を批判する資格はない。私たちも、現在の道を判断する時、歴史に学ぶしかない。最後に生前のトラウドゥル・ユンゲが登場し、自己批判する姿にうたれた。ヒトラーを俳優が演じた初めてのドイツ映画でもある。ブルーノ・ガンツに拍手。
| チーム★アメリカ/ワールドポリス |  |
|---|
2004年作品。アメリカ映画。98 分。配給=UIP。監督=トレイ・パーカー(Trey Parker)。製作=パム・ブラディ(Pam Brady)、トレイ・パーカー(Trey Parker)、マット・ストーン(Matt Stone)。製作総指揮=スコット・アヴァーサノ(Scott Aversano)、アン・ガレフィーノ(Anne Garefino)、スコット・ルーディン(Scott Rudin)。脚本=トレイ・パーカー(Trey Parker)、マット・ストーン(Matt Stone)、パム・ブラディ(Pam Brady)。撮影=ビル・ポープ(Bill Pope)。プロダクションデザイン=ジム・ダルツ(Jim Dultz)。衣装デザイン=カレン・パッチ(Karen Patch)。編集=トム・ヴォグト(Tom Vogt)。音楽=ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ(Harry Gregson-Williams)。声の出演=トレイ・パーカー(Trey Parker)、マット・ストーン(Matt Stone)、クリステン・ミラー(Kristen Miller)、フィル・ヘンドリー(Phil Hendrie)、モーリス・ラマルシュ(Maurice LaMarche)
トレイ・パーカーの刃は、リベラル派にも向けられ、マイケル・ムーア監督が自爆テロしたり、リベラル派俳優たちが北朝鮮とつながっていたりと、やりたい放題の展開だ。きわどい下ネタ連発で、すべてを笑い飛ばす。血まみれにする。グチャグチャにする。主人公のゲイリーは、すさまじい量のゲロを吐きまくる。18禁なのは、無修正ベッドシーンのためだけではないかもしれない。たしかに手が込んでいて批判も徹底しているが、私は「サウスパーク 無修正映画版」の方に、監督たちの反骨精神を感じる。今回は、高みに立って茶化しているように思う。
| 1996年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 |