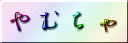 |
|---|
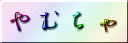 |
|---|
 キネマ霊園
キネマ霊園 キネマフォーラム
キネマフォーラム  掲示板
掲示板
| オランダの光 |  |
|---|
2003年作品。オランダ映画。94 分。配給:セテラ。製作・監督: ピーター=リム・デ・クローン(Pieter-Rim de Kroon)。脚本: マールテン・デ・クローン、ヘリット・ウィレムス。撮影監督: パウル・ファン・デン・ボス。 編集: アンドレ・デ・ヨング+シール・ミュラー。音楽: ヘット・パレイス・ファン・ブム。 クリエイティブ・コンサルタント: ヤン・アンドリーッセ。出演=ヤン・アンドリーッセ(現代美術家)、ロバート・ザントフリート(現代美術家)、ギュンター・ケンネン(気象学者)、ヤン・ディべッツ(現代美術家)、フィンセント・イッケ(天文物理学者)、 ジェームズ・タレル(米現代美術家)、エルンスト・ファン・デ・ヴェーテリング(美術史家)、スヴェトラナ・アルパース(美術史家)、リシュアン・フェレロ(農夫)、アレックス・ビーゲン(モニュメント・ヴァレーのガイド)
フェルメールやレンブラントら17世紀オランダ絵画の特徴の背景となったオランダ独特の光についての美術的ドキュメンタリー。作品は、現代美術家ヨーゼフ・ボイスが、20世紀前半に行われたエイセル湖の開拓が地形に変化を及ぼし、その光が失われてしまったと指摘した点から始まる。「オランダの光」は、すでに失われてしまったのか。なかなか興味深い導入だ。
しかし、その後が続かない。実際の風景を定点観測しながら、オランダ絵画に描かれた光やゴッホやモネらが他地域で描いた絵画の光を比較。アーティストや美術評論家、気象学者、長距離トラックの運転手らが、それぞれオランダの光について、話す。しかし焦点が絞られず、テーマは拡散していく。静かすぎる映像は、ときに睡魔を連れてくる。
オランダの、ぽってりとしながら澄んでいる空気感。クローン監督は、婉曲的にオランダの光は、昔と変化したもののまだ失われていないと主張しているが、切れ味は良くない。オランダ絵画の光の技法とオランダの自然光の関係も、うまく整理されていない。自然光と技法の複雑な影響については、なんとなく分かっただけだ。光自体をテーマするという独創的な作品だけに、もう少しまとまっていたらと思う。だが、写し出される緻密な映像美は、劇場でしか体験できない。フジフイルムが採用されている。実際にオランダに行きたくなるので、巧妙な観光CMといえるかもしれない。
| 亡国のイージス |  |
|---|
2005年作品。日本映画。127分。配給=日本ヘラルド映画、松竹。監督=阪本順治。原作=福井晴敏(「亡国のイージス」講談社刊)。脚本=長谷川康夫/飯田健三郎。音楽=トレヴァー・ジョーンズ。編集=ウィリアム・アンダーソン。撮影=笠松則通。美術=原田満生。録音監督=橋本文雄。「いそかぜ」先任伍長・仙石恒史=真田広之、「いそかぜ」副長・宮津弘隆2等海佐=寺尾聰、「いそかぜ」1等海士・如月 行=勝地涼、「いそかぜ」船務長・竹中 勇3等海佐=吉田栄作、「いそかぜ」水雷士・風間雄大3等海尉=谷原章介、「いそかぜ」砲雷長・杉浦丈司3等海佐=豊原功補、「いそかぜ」掌帆長・若狭祥司=光石研、「いそかぜ」艦長・衣笠秀明1等海佐=橋爪淳、「いそかぜ」海士長・田所祐作=斉藤陽一郎、「いそかぜ」2等海士・菊政克美=森岡龍、「いそかぜ」機関長・酒井宏之3等海佐=中沢青六、「いそかぜ」航海長・横田利一1等海尉=中村育二、 DAIS内事本部長・渥美大輔=佐藤浩市、第204飛行隊・宗像良昭1等空尉=真木蔵人、DAIS局員・小林政彦=松岡俊介、DAIS局員・服部 駿=池内万作、温情のある年配の警官=佐川満男、「うらかぜ」艦長・阿久津徹男2等海佐=矢島健一、防衛庁長官・佐伯秀一=佐々木勝彦、統合幕僚会議議長・木島祐孝=天田俊明、海上幕僚長・湊本仁志=鹿内孝、警察庁長官・明石智司=平泉成FTG・山崎謙二2等海尉/ドンチョル=安藤政信、ジョンヒ=チェ・ミンソ、内閣情報官・瀬戸和馬=岸部一徳、宮津芳恵=原田美枝子、内閣総理大臣・梶本幸一郎=原田芳雄、FTG・溝口哲也3等海佐/ヨンファ=中井貴一
しかし、ベテラン俳優たちが共演し、海上自衛隊が全面協力し本物の艦を使用して撮影した映像は、リアルで緊張感があり、退屈しない。説明不足と思うほど説明を省いているので、押し付けがましさはない。俳優たちは、個性的な演技をみせるが、やはり真田広之の好演が光る。ちょっと良い人過ぎるが、映画の要としてぶれない。最後の緊迫した場面での手旗信号は、シリアスとユーモアの見事な融合だった。
| 皇帝ペンギン |  |
|---|
2005年作品。フランス映画。86 分。配給=ギャガ・コミュニケーションズ。監督=リュック・ジャケ(Luc Jacquet)。製作=イヴ・ダロンド(Yves Darondeau)、クリストフ・リウー(Christophe Lioud)、エマニュエル・プリウー(Emmanuel Priou)。脚本=リュック・ジャケ(Luc Jacquet)、ミシェル・フェスレール(Michel Fessler)。撮影=ロラン・シャレ(Laurent Chalet)、ジェローム・メゾン(Jerome Maison)。音楽=エミリー・シモン(Emilie Simon)。声の出演=母ペンギン=ロマーヌ・ボーランジェ(Romane Bohringer)、父ペンギン=シャルル・ベルリング(Charles Berling)、子ペンギン=ジュール・シトリュク(Jules Sitruk)。声の出演(日本語吹替版):母ペンギン=石田ひかり、父ペンギン=大沢たかお、子ペンギン=神木隆之介
マイナス40度という南極での撮影は、本当に大変だったと思う。8880時間撮影したという。貴重な映像がとらえられている。ペンギン好きには、たまらない作品なのかもしれない。しかし、映像編集にも作品構成にも、工夫が足りない。「ディープ・ブルー」に比べると、かなり水準が落ちる。生態の説明が、やや感情的。ナレーションの過度の擬人化は、逆に作品の感動を弱めてしまった。ただ、皇帝ペンギンの目線での映像は、なかなか新鮮。アザラシがあんなに怖い存在とは。
| 宇宙戦争 |  |
|---|
2005年作品。アメリカ映画。114 分。配給=UIP。監督=スティーヴン・スピルバーグ(Steven Spielberg)。製作=キャスリーン・ケネディ、コリン・ウィルソン。製作総指揮=ポーラ・ワグナー。原作=H・G・ウェルズ(H.G. Wells)。脚本=デヴィッド・コープ、ジョシュ・フリードマン。撮影=ヤヌス・カミンスキー。プロダクションデザイン=リック・カーター。衣装=ジョアンナ・ジョンストン。編集=マイケル・カーン。音楽=ジョン・ウィリアムズ。ナレーション=モーガン・フリーマン(Morgan Freeman)。レイ・フェリエ=トム・クルーズ(Tom Cruise)、レイチェル・フェリエ=ダコタ・ファニング(Dakota Fanning)、オギルビー=ティム・ロビンス(Tim Robbins)、ロビー・フェリエ=ジャスティン・チャットウィン(Justin Chatwin)、メアリー・アン=ミランダ・オットー(Miranda Otto)
トム・クルーズは、絶対に死なない。主人公が幸運が続いて生き残るのは、まあ許されるとしても、あの状況の中で家族全員が無傷で無事というのは、あまりにも不自然すぎる。さまざまな場面でイラクでの空爆を連想させるシーンがあり、スピルバーグの政治的メッセージを深読みすることはできるが、ルーカスほど鮮明ではない。スピルバーグの優柔不断さ、思想的な弱さが見えかくれする。
しかし、トライポッド出現のハラハラ、ドキドキ感の演出は、さすがスピルバーグだ。デザインもなかなか秀抜。平凡な男性、一市民の視点を貫き、妙なヒロイズムがない点も評価したい。子どもたちが聞き分けがないのも、なかなかリアル。ダコタ・ファニングのパニック症候群による叫びは名演だが、神経を逆なでされた。炎の暴走列車、地下室で目隠しされて童謡を歌うダコタ・ファニングの横顔など、記憶に残るシーンもあった。
| 1996年 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1998年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 1999年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2000年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2001年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2002年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2003年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2004年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 2005年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |