|
2004年作品。イギリス・イタリア・南アフリカ合作。122 分。配給=メディア・スーツ=インターフィルム。監督=テリー・ジョージ(erry George)。製作=テリー・ジョージ(Terry George)、A・キットマン・ホー(A.Kitman Ho)。製作総指揮=ハル・サドフ(Hal Sadoff)、マーティン・カッツ(Martin Katz)。脚本=テリー・ジョージ(Terry George)、ケア・ピアソン(Keir Pearson)。撮影=ロベール・フレース(Robert Fraisse)。美術=トニー・バロウ(Tony Burrough)、ジョニー・ブリート(Johnny Breedt)。衣装=ルイ・フィリップ(Ruy Filipe)。音楽=ルパート・グレグソン=ウィリアムズ(Rupert Gregson-Williams)、アンドレア・グエラ(Andrea Guerra)。ポール・ルセサバギナ=ドン・チードル(Don Cheadle)、タチアナ・ルセサバギナ=ソフィー・オコネドー(Sophie Okonedo)、ジャック・ダグリッシュ=ホアキン・フェニックス(Joaquin Phoenix)、オリバー大佐=ニック・ノルティ(Nick Nolte)、デュベ=デズモンド・デュベ(Desmond Dube)、デイヴィッド=デヴィッド・オハラ(David O'Hara)、パット・アーチャー=カーラ・セイモア(Cara Seymour)、ビジムング将軍=ファナ・モコエナ(Fana Mokoena)、ジョルジュ・ルタガンダ=ハキーム・ケイ=カジーム(Hakeem Kae-Kazi)、グレゴワール=トニー・キゴロギ(Tony Kgoroge)、オーナー=ジャン・レノ(Jean Reno)
配給元ライオンズ・ゲート社が日本国内の配給会社に買い付けの打診をしたが、米アカデミー賞にノミネートされたことで映画の付加価値が上がり、高い提示額を示したため、日本側はその金額で採算を取るには難点があると判断し、買い付けを申し出なかった。2005年6月8日に、ソーシャルネットワーキングサイト「mixi(ミクシィ)」で水木氏が「ホテル・ルワンダ」が上映されないことを掲示板で呼び掛けた。掲示板をきっかけに、全く面識のなかった映画ファン7人が19日、東京都新宿に集まり、「『ホテル・ルワンダ』日本公開を求める会」を結成。6月24日にサイトを開設、7月1日から署名活動を開始。ネット上の口コミで署名活動は急速な広がりを見せた。10月、メディア・スーツの配給で2006年正月第2弾作品として、日本での公開が決まった。署名は4595人に上った。会は、『ホテル・ルワンダ』日本公開を応援する会として、作品を応援している。作品とともに、日本公開までのいきさつが注目された。
1994年にアフリカの小国ルワンダで起こった多数派フツ族による少数派ツチ族の大量虐殺とその後のフツ族難民の大量流出は、世界に大きな衝撃を与えた。ルワンダでは94年の春から初夏に至る100日間に国民の10人に1人、少なくとも80万人が虐殺された。この死者は、比率からすればホロコーストにおけるユダヤ人の犠牲者のほぼ3倍となる。国連監視団は虐殺以前に情報を入手し、国連本部に緊急ファックスを送っていたが、結局国連は何もしなかった。現代でも、これほどの規模のジェノサイドが起きたことに、あらためて身震いする思いだ。
ツチ族とフツ族はもともと言語が同じで、遊牧民族と農耕民族の違いが、あるだけ。フツ族でも豊かになって牛を手に入れればツチ族とみなされた。しかし植民地支配者は、ツチ族は北のエチオピアからやって来た黒いアーリア人であり、ヨーロッパ人に近い高貴な民族であるのに対し、 フツ族は下等な野蛮人とみなした。差別を利用した分断支配の手法だ。ルワンダは独立に至るまでにドイツ、ベルギーの統治下で、この神話は強化された。 ツチ族は権力をほしいままにした。独立をめぐってツチ族の支配者たちはベルギーと距離を置いて権力を維持しようとしたのに対し、ベルギーはフツ族支援にまわり、フツ族によるツチ族の大量虐殺が行われた。ルワンダ国内では、大統領を取り巻く北部のフツ族エリートたちが利権を独占したために、貧しいフツ族農民が多数存在していた。 政府は貧しさをツチ族のせいにし、彼らの不満がツチ族に向かうように仕向けた。アフリカにおけるフランス語圏を守ろうとするフランスは、このフツ族政権を支援していた。
1993年、ハビャリマナ大統領は、亡命ツチ族からなるルワンダ愛国戦線の軍事的な圧力と民主化を求める国際的な世論に抵抗できなくなり、和平協定に調印した。しかし利権を独占してきたフツ族支配層が反発。大統領が何者かに暗殺され、ツチ族の大量虐殺が始まる。ラジオのDJは「ツチ族の連中はゴキブリだから皆殺しにしろ」と扇動する。和平ムードが、血なまぐさい大量虐殺へと変化していくドキュメンタリーのような臨場感がすごい。
フツ族のホテル支配人が、ツチ族をホテルにかくまって1200人以上の命を救ったという実話の映画化。妻がツチ族で、家族を守りたいという動機が結果として多くの人を助けることになる。けっして、英雄ではない。そして武器は使わず、柔軟な対応や機知で困難な場面を切り抜けていく。その支配人をドン・チードルが、見事に演じている。ルワンダの悲劇を的確に伝えつつ、緊密なストーリー展開で観る者を離さない。映画的にも素晴らしい出来だ。
危険をおかして虐殺の場面を撮影したカメラマンに、支配人が「放送されたら助けが来る」と話す印象的な場面がある。これに対しカメラマンは「世界の人々は映像を見ても、恐いねと言うだけでディナーを続ける」と自嘲気味に語る。ぐさりと刺さる言葉だ。それでも、彼は報道のために映像を撮り続けるだろう。言葉とは裏腹の希望を胸に秘めながら。ジャーナリストとしての冷静さと気骨を感じさせる場面だ。
映画を見続けながら、自分ならどうした、何ができたと問い続けた。あの時、外国人としてルワンダにいたら、出国を拒否してとどまることくらいしかできなかっただろう。映画を観終わっても、自問は続いている。そうさせる力に満ちた映画だ。
| ブロークバック・マウンテン |  |
|---|
|
2005年作品。アメリカ映画。134 分。配給=ワイズポリシー。監督=アン・リー(Ang Lee)。製作=ダイアナ・オサナ(Diana Ossana)、ジェームズ・シェイマス(James Schamus)。製作総指揮=ラリー・マクマートリー(Larry McMurtry)、ウィリアム・ポーラッド(William Pohlad)、マイケル・コスティガン(Michael Costigan)、マイケル・ハウスマン(Michael Hausman)。原作=アニー・プルー(Annie Proulx)。脚本=ラリー・マクマートリー(Larry McMurtry)、ダイアナ・オサナ(Diana Ossana)。撮影=ロドリゴ・プリエト(Rodrigo Prieto)。プロダクションデザイン=ジュディ・ベッカー(Judy Becker)。衣装デザイン=マリット・アレン(Marit Allen)。編集=ジェラルディン・ペローニ(Geraldine Peroni)、ディラン・ティチェナー(Dylan Tichenor)。音楽=グスターボ・サンタオラヤ(Gustavo Santaolalla)。イニス・デル・マー=ヒース・レジャー(Heath Ledger)、ジャク・ツイスト=ジェイク・ギレンホール(Jake Gyllenhaal)、アルマ=ミシェル・ウィリアムズ(Michelle Williams)、ラリーン・ニューサム=アン・ハサウェイ(Anne Hathaway)、ジョー・アギーレ=ランディ・クエイド(Randy Quaid)、キャシー=リンダ・カーデリーニ(Linda Cardellini)、ラショーン・マローン=アンナ・ファリス(Anna Faris)、モンロー=スコット・マイケル・キャンベル(Scott Michael Campbell)、アルマ・Jr.=ケイト・マーラ(Kate Mara)
アン・リー監督は、ワイオミング州ブロークバック・マウンテンの雄大な自然を背景に、2人のカウボーイ、イニスとジャックの激しくも切ない愛情の物語を描き切った。大自然の中で時間を過ごすうちに、関係が深まる。少年時代に、同性愛者殺害シーンを父親に見せられたイニスが、同性愛に目覚めて激しく苦しむシーンが痛々しい。会話ではなく、眼で感情を表現する場面が多かった。そして会話には、ウイットと毒が潜んでいた。アクション大作「グリーン・デスティニー」とは別な形で、自然の美しさが生かされている。細部の仕掛けも見事。ラストでシャツがとても大きな感動を運んでくる。
「ブラザーズ・グリム」のヒース・レジャーと「デイ・アフター・トゥモロー」のジェイク・ギレンホール。ポイントを押さえながら、全体としては抑えた演技が、リアルさを醸し出している。イニスの妻アルマ役のミシェル・ウィリアムズは、「ランド・オブ・プレンティ」の清清しい演技とは対照的な重苦しい演技を見せる。「プリティ・プリンセス」シリーズのアン・ハザウェイが積極的なテキサス娘を演じていたのには驚かされた。それぞれの眼の演技が素晴らしかった。イニスの娘をはじめ、女性たちの演技が全体を支えていた。
| ナルニア国物語/第1章:ライオンと魔女 |  |
|---|
|
2005年作品。アメリカ映画。140分。配給=ブエナビスタ。監督=アンドリュー・アダムソン(Andrew Adamson)。製作=マーク・ジョンソン(Mark Johnson)。製作総指揮=アンドリュー・アダムソン(Andrew Adamson)ペリー・ムーア(Perry Moore)、フィリップ・ステュアー(Philip Steuer)。原作=C・S・ルイス(C.S. Lewis)。脚本=アンドリュー・アダムソン(Andrew Adamson)、クリストファー・マルクス(Christopher Markus)、スティーヴン・マクフィーリー(Stephen McFeely)、アン・ピーコック(Ann Peacock)。撮影=ドナルド・マカルパイン(Donald McAlpine)。クリーチャーデザイン=ハワード・バーガー。視覚効果スーパーバイザー=ディーン・ライト。特殊メイク=ハワード・バーガー。プロダクションデザイン=ロジャー・フォード。衣装デザイン=アイシス・マッセンデン。編集=シム・エヴァン=ジョーンズ、ジム・メイ。音楽=ハリー・グレッグソン=ウィリアムズ(Harry Gregson-Williams)。クリエイティブスーパーバイザー=リチャード・テイラー。ピーター・ペベンシー=ウィリアム・モーズリー(William Moseley)、スーザン・ペベンシー=アナ・ポップルウェル(Anna Popplewell)、エドマンド・ペベンシー=スキャンダー・ケインズ(Skandar Keynes)、ルーシー・ペベンシー=ジョージー・ヘンリー(Georgie Henley)、白い魔女=ティルダ・スウィントン(Tilda Swinton)、タムナスさん=ジェームズ・マカヴォイ(James McAvoy)、カーク教授=ジム・ブロードベント(Jim Broadbent)
「指輪物語」と並ぶC・S・ルイスの名作ファンタジー小説の映画化。第二次世界大戦のロンドンの空襲を逃れて疎開したペベンシー家の子どもたち、ピーター、スーザン、エドマンド、ルーシーの4人は、魔法の国ナルニアで、戦争に巻き込まれる。この辺の設定はなかなかユニークだ。しかし、その皮肉な運命に、子どもたちはあまり悩むことなく、身をゆだね参加していく。
後は、ずいぶんと単純で、善悪が鮮明で、都合の良い展開が続く。すべてが上滑りでドラマに欠けている。ストーリーが進んでも、子どもたちが魅力的にならない。子役のルーシー・ペベンシーは、確かにうまいが演技が心に響かない。お金をかけたはずのCGは、丁寧につくっていることは分かるが、躍動感に乏しい。「ロード・オブ・ザ・リング」はおろか、「ハリー・ポッター」シリーズのレベルにも達していない。先行したファンタジー映画の影響とディズニー的なお行儀の良さで、興行成績は上がるだろうが、映画としての力は弱い。
|
やむちゃ・バックナンバー
 バーのカウンター(HOME)へ バーのカウンター(HOME)へ
 Visitors Visitors since2006.3.12 since2006.3.12 |
| 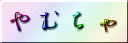
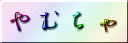
 キネマ霊園
キネマ霊園 キネマフォーラム
キネマフォーラム  掲示板
掲示板