
 |
オーナーが「おなか健康」を実践する切っ掛けとなり、20年以上も愛用している乳酸菌「ニブロン」は、左記の所で購入できます。 |

独断と偏見で選んだ「健康Webレポート集」です。 ご意見・感想 を、お待ちしています!【お願い】
著作権の関係で、オリジナル記事へのリンク設定を行っていません。併記してるURL情報を利用し、当該記事を検索して頂ければ幸いです。

ブログの方へ比重を移しています。→ ■ ブログ: 「おなか健康!不老の秘訣?」
http://health-info.asablo.jp/blog
先ごろ、日本抗加齢医学会の学術総会が横浜で開催された。
この学会は、アンチエイジングを研究・診療を行っている医師が年1回集まる大きな学会で、今回約4000人の医師が討論を行った。 この学会の特徴は、ほぼ全て診療分野の医師が集まっているということです。
■多くの仕事を細菌に「外注」している人間今回の学会での「キーワード」の一部を紹介すると、
■納豆やソラマメなどの豆類に多いポリアミン
- 腸内細菌
- 認知症の予防
- 運動のサイエンス
- 水素水
- サプリメント
- 機能性食品表示
- 男性ホルモン
- 女性医療
- 長寿遺伝子をどうやって動かすか
- 見た目のアンチエイジング
頭からつま先までのアンチエイジング・サイエンスに溢れていました。 中でも最大の関心を集めたのが「腸内細菌」でした。
人間は大量かつ多種多様の細菌と共存して、人間は多くの仕事を細菌に「外注」しています。 例えば、胃のピロリ菌は胃ガンの原因になるが、胃酸を薄めて胃の粘膜を守る作用を行っています。 でも、ピロリ菌を除菌すると胃潰瘍の薬を飲む必要性も生じてきます。
大腸にある「腸内細菌」は、住む場所や人種、食べ物といった、地球での人間の文化や生活と大きく関わっています。 腸内細菌は肥満に関係したり、ガンに関係することが判ってきましたし、「潰瘍性大腸炎」という難病も、他人の便を「移植」して腸内細菌を変化させると治ることもあることが判ってきました。「腸内細菌が認知機能を高める」という報告が、今回の学会でありました。
これは、アミノ酸の一種である「アルギニン」を、ある種の乳酸菌と一緒に摂取することで「ポリアミン」という物質が腸内で多く作られて「認知機能が高まる」という研究です。
ネズミでの実験で高齢ネズミの認知機能も良くなったというもので、超高齢社会最大の問題である認知症の予防に食べ物が有効であることが期待されます。 アミノ酸の効果を、ある種の乳酸菌が高めるということは興味深いです。
この「ポリアミン」は、もともと精液の栄養成分で発見され、アンチエイジングの重要なカギと言われています。
ポリアミンのアンチエイジング効果アルギニンを多く含む食べ物は、肉・魚介類、ゴマ、大豆、ナッツなどです。 また、ポリアミンが多いのは、納豆やソラマメなどの豆類。
- 動脈硬化を防ぐ
- 脂肪がつき難い
- 免疫力を高める
- 記憶力を保つ
ソラマメの季節、ビールとソラマメも良いですが、朝はソラマメとヨーグルトがアンチエイジングによさそうです!
「腸内細菌とおならの関係について」・・・・・・腸内細菌研究の第一人者で、1万人以上の腸内環境を調べてきた、理化学研究所の辨野義己(べんのよしみ)特別招聘研究員から取材したお話。
人間の一日の「おなら」の量は400~1200ml。この量はどのような物を食べているかで変動し、においも腸内細菌に深く関係しているという。
腸内細菌は、腸内に600兆~1千兆個も存在し、善玉菌・悪玉菌・日和見菌の3グループに分けられる。
その中の善玉菌は、乳酸菌やビフィズス菌や酪酸菌などからだに良いとされる菌。 この善玉菌は腸に届いた食物繊維などを分解して、短鎖脂肪酸やビタミンB群などの栄養素を作りだす、腸から吸収されてからだ全体に送られる。
一方、悪玉菌はウェルシュ菌や黄色ブドウ球菌などからだに悪影響を与える菌。 この菌は腸内の食べカスを腐敗させ、アンモニアやインドール、硫化水素などの有害物質を作りだし、臭いおならの原因となる。
つまり、無臭のおならが出る人は腸内で善玉菌が多く、臭いおならが頻繁に出るという人は腸の中で悪玉菌が増えている証拠なのです。
この腸内環境は食生活に気を付けるだけでガラッと変えることが出来る。 善玉菌を増やすために大切なのは食物繊維。 ごぼうやカボチャや海藻など比較的、食物繊維の多い野菜を中心へと食生活を改善し、1日350g以上の野菜をとることが目安。
また意外に勘違いしているのはヨーグルトの効果。
ヨーグルトを摂るだけで善玉菌が増えると思われるが、実際は増えない。 元々定住している善玉菌を活性化させる効果があるので、ヨーグルトを積極的に食べることで腸内環境が改善する。
腸内環境は、私たち人間にとって健康のバロメーター。 腸内環境を整えることで大腸ガンなど、様々な病気のリスクを下げることができるので、普段から意識して腸内環境に良い食習慣を心掛けることが大切だというお話でした。
※週刊朝日 2015年7月17日号
子どもへの使用を想定した動物実験で問題を指摘一般に使われている抗菌薬、いわゆる抗生物質の使用が子どもの発達に影響を与えかねないと報告されている。
体重や骨の成長に影響あり
子どもへの使用を想定した動物実験で、体重増加や腸内フローラへの変化が確認された。
米国のニューヨーク大学の研究グループが、有力科学誌ネイチャー誌の姉妹誌でオンライン科学誌であるネイチャー・コミュニケーションズ誌に6月30日に報告したもの。
研究グループは、抗生物質を人に置き換えたときに、平均的な子どもが最初の2年間に受けるのと同水準になるように調整して、メスのネズミに与えて、影響を調べた。
検証対象は、幅広い病原体に効果を示す抗生物質「アモキシシリン」、小児科で一般化しつつある抗生物質「マクロライド」の仲間である「タイロシン」。あるいは両方の薬の混合した薬。
結果は、「タイロシン」については多めの量で何度も使うと、体重を増やす影響があり、 「アモキシシリン」は、骨を成長させると分かった。
腸内フローラを変える
これら両方の抗生物質は、「腸内フローラ」を混乱させるという。 「腸内フローラ」は、腸内細菌叢やマイクロバイオームなどと言われ、叢は草むらの意味、フローラは花畑の意味で、さまざまな腸内細菌が集まっている状態を表していて、 細菌にとどまらない微生物の集まりとして微生物叢とも呼ばれる。
兼ねてより病気との関係が注目されており、最近でも糖尿病との関係が指摘されていた。 (腸内フローラの変化、1型糖尿病の成り易さと関連!)。 腸内細菌のバランスが崩れると、がん、肥満、精神などの問題と関係すると報告が続いていた。(遺伝子、食物繊維、腸内細菌の3つに意外な関係 https://www.mededge.jp/spcl/9889、
抗生物質を使うと、微生物の集まりの内訳が一変し、微生物の量、種類、共同体の状態などが大きく変化するという。
腸内フローラとは?デブ菌、人工甘味料、抗生物質の問題が関係 https://www.mededge.jp/b/tech/9196、
腸内細菌が「不安」「うつ病」「気分障害」の治療にも、「サイコバイオティクス」に動き https://www.mededge.jp/a/psyc/9977 を参照)。
特に「タイロシン」を使ったとき、「アモキシシリン」よりも大きな影響を与えており、抗生物質を使うたびに微生物叢の安定へのプロセスが邪魔されるという。
高脂肪食への対応ができず
この微生物叢の変化が肥満とも関係している可能性もあるという。 抗生物質に晒されて「腸内フローラ」が変わると、環境の変化への適応能力が落ちるという。
高脂肪食を食べると、微生物叢は本来適応して変化するところ、抗生物質を使っている場合には上手く適用できなくなるという。
抗生物質を使っていない場合には、新しい環境に1日で適応したのに対して、「アモキシシリン」で治療を受けたネズミでは「腸内フローラ」の一部は1日でシフトしたが、全体で見ると2週間を要して適応していた。
「タイロシン」で治療を受けていた場合には、全体が適応するのに1カ月も要した。
マクロライド系に「心配」
「タイロシン」の体重増加と「腸内フローラ」への強い影響、が特に心配であるとこの研究は指摘する。
日本でも子どもへのマクロライド系の抗生物質の処方が増えており、この研究は動物実験とはいえ、気になる。 無意味に長期に亘って薬を使うのは避けたいものだ。
2011/08/19協同乳業など、ビフィズス菌「LKM512」の摂取で寿命伸長効果を確認
協同乳業、理化学研究所(理研)、京都工芸繊維大学(工繊大)、及び京都大学(京大)が米国オンライン科学誌プロスワン「PLoS ONE」に発表した研究に依れば、ビフィズス菌「LKM512」の摂取により寿命が伸長する効果があるという。ヨーグルトを食べるのは健康に良いといわれてきたが、今回の研究成果はアンチエイジングにつながるという科学的な証明になりそうだ。
協同乳業の主任研究員の松本光晴氏らは、農業・食品産業技術総合研究機構・生物系特定産業技術研究支援センター「イノベーション創出基礎的研究推進事業」の平成21年度課題「健康寿命伸長のための腸内ポリアミン濃度コントロール食品の開発」の研究において、マウスにビフィズス菌LKM512を投与したところ、大腸内で増えたポリアミンの作用に起因する寿命伸長効果を試験により確認した。
ポリアミンは、DNA・RNA・タンパク質の合成および安定化や、細胞の増殖及び分化に関与している生理活性物質であり、全ての生物の細胞に普遍的に存在し、これまで、抗炎症作用、抗変異原作用、オートファジーの誘導、腸管バリア機能維持・促進等の作用が報告されており、濃度が高まることは生物にとってプラスになることが判っていた。
本研究は、「LKM512を投与することで腸内細菌にポリアミンを生成させ、老年病の原因である慢性炎症を抑えることが可能になる」という仮説を検証するものとして実施。大腸組織を健全化し、更に血中に移行したポリアミンが全身の細胞(特に免疫担当細胞)に供給され、老年病の原因である慢性炎症の抑制につながることを明らかにするというものである。
ヒトに換算して30~35歳に当たる10カ月齢のマウスのメスを3グループ(19~20匹)に分け、それぞれに対してLKM512、スペルミン(ポリアミンの一種で最も活性が強い)、生理食塩水(対照群)の3パターンに分けて、週に3回経口投与を行って比較した。その結果、LKM512を投与した場合は、大腸内のポリアミン濃度が上昇。大腸バリアの機能が維持され、抗炎症効果も得られ、それによって寿命を伸長させることが明らかとなった。実験期間40週目での生存率は80%以上。
二つ目のスペルミン群も、LKM512と比較すると弱いものの一定の寿命伸長効果を確認し、40週目で60~70%の生存率となった。但し、有意な効果とはいえないレベルであった。
対照群(生理食塩水)は、40週目では生存率 40%を切っており、大きな差が認められた。
逆に生存率が70%になる時点を比較すると、対照群に対してLKM512群は約6カ月の伸び。マウスの平均寿命が約2年なのに対し、その1/4に相当するという劇的な効果といえる。更に、LKM512の経口投与がマウスの外見・腫瘍および潰瘍発生に及ぼす影響も調査された。対照群は皮膚に腫瘍や潰瘍が多く見られたが、 LKM512を投与したマウスには投与期間中ほとんど観察されず、毛並みも非常によく、動きも活発であったことが報告されている。LKM512群は潰瘍が 5%ほどあったが、腫瘍は0%。対照群はどちらも20%あり、これまた大きな差がみられたという。
LKM512の経口投与におけるマウスの大腸内環境へ及ぼす影響も調べられ、投与したビフィズス菌(B.animalis subsp.lactis)やPrevotella属の16S rRNA遺伝子が強く発現し、腸内菌叢が変動していることが確認された。
またLKM512群の腸内ではポリアミン濃度の上昇が判明したが、スペルミン群では上昇は見らなかった。経口的に摂取したポリアミンは小腸で吸収されて大腸には到達されないことが確認された。また、一般的な腸内細菌の重要な代謝産物とされる酢酸や酪酸などの短鎖脂肪酸には、LKM512投与による影響は認められなかったという。また、炎症マーカー・尿中パプトグロビンへの影響においては、LKM512群は結腸組織の炎症関連遺伝子の発現が抑制され、炎症マーカーの減少も確認されたことにより、LKM512を投与することで腸内に継続的にポリアミンを作り出して炎症を抑制し、寿命が延伸した可能性があるという。
試験期間終了後に大腸を摘出した結果、対照群の半分は便が溜まり茶色く変色しているのに対し、LKM512群は全て若齢マウスと同じきれいな色をしていた。組織片の検査では、対照群の半数は組織が崩壊しつつあり、粘液を分泌する杯細胞の数も激しく減少していたが、LKM512群では十分な杯細胞も残っており、摘出手術直前まで粘液を分泌し続けていたと推定されることより、LKM512の投与により大腸のバリア機能の崩壊を抑制できたことを示している。
結腸の遺伝子発現パターンに対するマイクロアレイ法での調査において、LKM512群は若齢マウスに近いパターンを示すのに対し、対照群やスペルミン群はまったく逆のパターンとなったことより、大腸の老化に伴う遺伝子発現の変動をLKM512が防いでおり、更に、ポリアミンの経口摂取よりも大腸でポリアミンを作ることの方が、大腸組織の機能維持、さらには寿命伸長に効果的である可能性が高いこともわかったという。
≪その他の記事≫:
▼理化学研究所 > プレスリリース 2011.08.17 > ビフィズス菌「LKM512」摂取による寿命伸長効果を発見
2011/04/28細菌種とその比率で腸内細菌叢を3タイプに分類可能
http://health.nikkei.co.jp/hsn/article.aspx?id=MMHEb1001028042011&list=1
NikkeiNet いきいき健康 海外ニュース 2011/04/28ドイツ、ヨーロッパ分子生物学研究所(ハイデルベルグ)のManimozhiyan Arumugam氏らが、英科学誌「Nature(ネイチャー)」4月20日号に発表した研究によれば、ヒトの腸内細菌叢(bacterial flora)には3つの型があり、存在する細菌種とその比率によって区別できるという。例えば、タイプ1はバクテロイデス(Bacteroides)属の比率が高く、タイプ2はバクテロイデス属が比較的少なくプレボテラ(Prevotella)属の比率が高かった。タイプ3ではルミノコッカス(Ruminococcus)属が多いというもの。
ヒトの腸には500~1000種の細菌が生息しており、それぞれがミクロの生態系の中で互いに競合や協力しながら宿主である人体と共生的関係を持ちバランスを保っており、これらの微生物は単独ではなくコミュニティとして活動しており、宿主であるヒトの食べるものなどにも適応していることを示すもので、研究グループによれば、年齢・性別・体重等の特徴と腸内細菌叢の型に相関があるとの証拠は得られなかったが、検体を全て検討すると年齢・性別・体重と細菌の特定の遺伝子マーカーとの間に相関が見られ、いずれはこのような情報から、疾患や疾患になり易さを知る上で活用できる可能性があるという。
▼原文:Gut Bacteria Falls Into Three Major Types
2011/01/27ビフィズス菌が腸を細菌から守る仕組み解明
理化学研究所などのチームが、1月27日付の英科学誌ネイチャーに発表すした研究によれば、ヒトの腸内にすむビフィズス菌は、酢酸を作り出すことで細菌による病気の発症を防いでいることを、マウスを使った実験で確かめたという。研究は、無菌のマウスに特定のビフィズス菌を1週間経口投与した後に、病原性大腸菌O157を感染させて腸内を調べた結果、O157による血液中の毒素量が、ビフィズス菌を与えていないマウスに比べて1/5以下に抑えられていた。ビフィズス菌を与えていないマウスはこの毒素で死んだという。
ビフィズス菌の作る酢酸がO157感染を抑止することを発見
http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2011/110127/index.html
理化学研究所 > プレスリリース(2011) > 2011/01/27-善玉菌(プロバイオティクス)の作用機構の一端を解明-
≪抜粋≫:
理研免疫・アレルギー科学総合研究センターの免疫系構築研究チームと東京大学の研究グループは、腸管出血性大腸菌O157の感染を抑止する効果が知られているビフィズス菌が、酢酸を生産し、腸管上皮細胞を保護するため、抵抗性を強めることを、マウスを使った実験で世界で初めて明らかにした。通常では死に至る、1万個のO157菌を経口投与したマウス実験で、ある種のビフィズス菌(予防株)をあらかじめ経口投与しておくと感染死を防ぐことができた。しかし、予防できないビフィズス菌(非予防株)も存在し、ゲノミクス、トランスクリプトミクス、メタボロミクスを駆使した最新のマルチオーミクス手法で、予防株と非予防株の違いを詳しく調べた結果、予防株だけが腸管上皮に作用し間接的に感染死を防いでいた。▼リリース本文(詳細):http://www.riken.jp/r-world/info/release/press/2011/110127/detail.html
2010/10/19カゴメと近畿大学、ラブレ菌に過敏性腸症候群(IBS)の症状を改善する効果を確認
カゴメと近畿大学医学部堺病院の村上佳津美先生らが、3rd ASM Conference on Beneficial Microbes(第3回アメリカ微生物学会・有用微生物会議 10月25~29日、ハイアットリージェンシー・マイアミ[米国])で発表するところによれば、Lactobacillus brevis KB290(以下、ラブレ菌)の摂取によって、過敏性腸症候群(以下IBS)の症状が改善することを明らかにした。過敏性腸症候群(IBS)は、下痢や便秘を繰り返す腸の病気で、ストレスや環境、腸内菌叢の乱れが関係していると考えられており、ラブレ菌は便通改善効果と腸内菌叢改善効果があるプロバイオティクスであることが明らかになっているため、小児を含むIBS患者に対して、ラブレ菌の有効性を明らかにするヒト試験を行ったもの。
▼カゴメ > ニュースリリース(2010年) >「ラブレ菌に過敏性腸症候群(IBS)の症状を改善する効果が期待 ~カゴメ、近畿大学医学部堺病院の共同研究~」
2010/07/15バイオガイアジャパン、第11回国 国際統合医学会で抗菌作用を発表
バイオガイアジャパン(株)(広島県広島市)は、2010年7月17~18日に開催される第11回国際統合医学会学術集会において、ヒト由来のプロバイオティクスであるL.reuteri菌の病原性腸内細菌に対する抗菌作用を発表する。
L.reuteri菌は、ヒトの腸管内に棲息する嫌気性の腸内細菌の一種。同社は、4種のL.reuteri株より生産された「ロイテリン」について微生物学的活性を評価したところ、抗菌因子がL.reuteriにより産生され、様々な因子は「ロイテリン」と共に相互的に病原性腸内細菌を抑制する作用があることを確認したという。「ロイテリン(3-ヒドロキシプロピオンアルデヒド)」とは・・・・一部の乳酸菌などの微生物によってグリセロールの代謝産物として生産される物質
2010/07/03腸内細菌が関節リウマチを誘発
http://news.e-expo.net/world/2010/06/post-119.html
健康美容EXPO > 健康美容EXPOニュース > 海外ニュース:TOP > 徴候・症状 2010/06/17米ハーバード大学(ボストン)医学部病理学教授のDiane Mathis氏らが、医学誌「Immunity(免疫)」6月25日号に発表したところによれば、マウスを使った実験で、腸内細菌が関節リウマチ(RA)の原因となりうる免疫反応を誘発する可能性があるというが、今回の知見は自己免疫疾患の新たな見方につながり、新たな治療法や予防法をもたらす可能性があるという。今回の研究は、遺伝的に関節炎を発現しやすいマウスを無菌環境で飼育した。これらのマウスでは通常の環境で飼育したマウスに比べて関節炎を引き起こす抗体が少ないが、マウスを非無菌環境に置き、一般的な腸内細菌の分裂した糸状体を胃に送り込んだところ、直ちに抗体を作り始め、4日以内に関節炎が発現したというもの。Mathis氏によれば、「細菌感染を介して関節炎に“罹患する”のではなく、むしろ、遺伝的に感受性の高い状況で、細菌がプログラムの展開を誘発する。今回の場合、細菌はマウスに、ある種の白血球をより多く作らせ、これらの細胞が脅威をもたらす抗体であるとして免疫系が反応し、関節リウマチを引き起こした。」と説明している。
米マイアミ大学ミラー医学部内科教授のNancy Klimas博士は、反応性関節炎と呼ばれ、ライター症候群として知られる重症型の関節炎が遺伝的感受性により生じ、感染に誘発されることを指摘し、腸内細菌を変化させることで、これらの疾患の一部を予防または治療できる可能性があると述べている。(HealthDay News 6月17日)
2010/03/21在菌と付き合う2/乳酸菌摂取 下痢減らす
「プロバイオティクス」とは、「健康のために」を意味するギリシャ語に由来し、人間に利益をもたらす「善玉菌」を指し、その代表が、「乳酸菌」。ビフィズス菌やラクトバシラス等の細菌は、食物の残りカスを分解して乳酸を作るので乳酸菌と総称され、腸内細菌の10%を占める。
杏林大医学部感染症学教授の神谷茂さんによれば、激しい下痢を引き起こす腸管出血性大腸菌O-157等は中性の環境を好む。乳酸菌は腸内を酸性にすることで、侵入してくる病原菌を居辛くする働きをする。また、腸の収縮運動(蠕動運動)を活発にして便秘や下痢を防ぐなど、腸の働きを整えてくれるので、腸内に善玉菌を増やせば健康に役立つ筈という考えから、「乳酸菌入り」等の食品・飲み物が販売されている。善玉菌を摂取することの有効性を示す研究結果もある。
ロタウイルスが原因の下痢の症状が出た直後から乳酸菌を含む食物を食べたら、下痢が続いた期間は1.4日で、乳酸菌を摂らなかった人より1日早く治ったとか、開発途上国への旅行中、乳酸菌を含む食品や薬剤などを毎日服用した場合、何も取らないより、感染性下痢になる割合が減ったというもの。体外から摂取する細菌は腸内に棲み着かず、排泄されてしまうので、毎日、食べ続ける必要がある。
→・・・・このサイトに掲載されている解説図は、こちら!
2010/03/17在菌と付き合う1/腸内に400種類100兆個以上
人の顔、口、気道、胃、腸、尿路など、体のいたるところに細菌が棲み着いており、「常在菌」といわれる。 その中で腸には最も多くおり、400種類以上・100兆個以上とされ、大便の重量の1割は、腸内細菌の死骸と言われる。
杏林大医学部感染症学教授の神谷茂さんによれば、腸内にはバクテロイデス、ユウバクテリム、ラクトバシラスなど、さまざまな細菌が存在し、これらの多くは食物の残りカスを分解するなど腸内環境を整える働きがあり、人間に悪さをしない菌「善玉菌」が全体の8割ほどを占めるとされ、 残りは「悪玉菌」だ。大腸菌やウエルシュ菌などは、たんぱく質を分解して発がん物質を放出するとされるが、ほかの腸内細菌群が、この発がん物質を分解・無毒化している。
神谷さんによれば、大腸菌は単なる『悪玉菌』では無く、これらの悪玉菌も、
――などの良い働きをするが、悪玉菌が増えすぎて腸内細菌のバランスが崩れると体調不良につながる。
- 人間に必要なビタミンBなどを作る
- 腸に集まる免疫細胞を刺激して、細菌などの侵入を防ぐ免疫機能を高める
悪玉菌の増殖の原因は、
――ということなので、生活習慣を見直そう。
- 高たんぱく、高脂肪の食事を取り過ぎる
- 不規則な生活でストレスが多い
→・・・・このサイトに掲載されている解説図は、こちら!
2010/03/08腸内細菌が肥満を手助けか/米研究
http://www.afpbb.com/article/life-culture/health/2706844/5459516
AFP BB News > ライフ・カルチャー >ヘルス 2010/03/08米エモリー大学(Emory University)医学部のアンドリュー・ゲワーツ(Andrew Gewirtz)氏らが、3月4日の米科学誌サイエンス(Science)に発表した研究によれば、細胞が細菌の存在を感知する手助けをするタンパク質であるトール様受容体5(TLR5)が免疫システム中で欠乏するよう遺伝操作したマウスを使った実験によって、食べ物の消化を手助けする腸内細菌が正常に働かない場合に、かえって肥満の原因となってしまうことがあることを突き止めたという。この実験でのマウスの免疫システムは、TLR5の欠乏した状態でも細菌を制御し続けたが、正常な場合と比べて弱く、細菌構成が変化したほか、低レベルの炎症が起こり、インスリン受容体の感受性が弱まった。この結果、TLR5欠乏マウスは、食べる餌の量が正常なマウスより約10%増え、体重も約20%増加、メタボリックシンドロームとなったという。
これは、腸内細菌叢の中で不適当な種類の細菌が勢力を強めると、低レベルの炎症が起き、前糖尿病状態となって食欲が増進されるからだという。何かと座りっぱなしの生活スタイルや栄養過多な食事が肥満の原因だと云われるが、過剰なカロリー摂取の背景には無規律な食習慣のほかに、食欲や代謝に関与する腸内細菌が関わっている可能性を示すもので、少なくとも一部の肥満については、インスリン抵抗性が原因で起きている可能性があると分析している。
2010/02/14「NikkeiNet」>「いきいき健康」のページに、「健康サイト紹介」というコーナーが有ります。 結構古くからやっていたようです。 更新頻度が少なく、Link切れもある点がちょっと残念ですが、気になるサイトの紹介をされていると思いますので、ご紹介を致します。当サイトの紹介がされていないのは、残念ではありますが、広告費を払えないということから対象外かもしれませんね(笑)
2009/07/17http://www.kyoukaikenpo.or.jp/7,528,20,93.html
全国健康保険協会 > 保健サービス > 生活習慣病とその予防 > 気になる病気 > 「耳」> メニエール病健康について、情報を発信し、健康に気をつけていたつもりの本人が、今回情けなくも「突発性難聴」を再発したと報告いたしましたが、症状から「メニエール病」を発症していたということが判りましたので、訂正させていただきます。5年前に「突発性難聴」を発症し、ステロイドによる治療を行った経験では、治療直後は耳鳴りの症状は改善して、聴覚の周波数特性の低域側がのみが劣化していましたが、5年後の人間ドックでの検診時には回復していたのです。しかし、その人間ドック半年後の今回、突然の眩暈と嘔吐のあと、左耳の感度が周波数の全域において35dBほど劣化し、且つ耳鳴りの症状を呈している状況から、医師に確認したところ、「突発性難聴」は再発することはなく、眩暈を伴っていることより、「メニエール病」を発症しているという診断でした。
今回の発症直前の生活を思い起こすと、会社生活での「ストレス」に長期間晒されていたことや、それに加え慢性的な「疲労」というか寝不足状態だったことが思い起こされます。
仕事でのストレスが相当あったのでしょうが、それに加えて累積していた眼精疲労や、ストレスや更年期からくる決まった時間に目が覚めてしまうことによる慢性的な睡眠不足等々、更年期を上手く処理できなかったことからの発病と思われます。若しも不幸にも、突然の眩暈や嘔吐に見舞われた後、片方の耳に異常がでた場合は、自己判断をせずに、下記のサイト上の情報を参考にされて、一刻も早く大きな病院に駆け込んで治療を受けて下さい。
▼「全国健康保険協会」>「生活習慣病とその予防」上の、「メニエール病」の原因・症状について:
1.どんな病気?
「メニエール病」とは、耳の内耳の中には、音を感じる蝸牛や回転運動を感知する三半規管、直線加速度や位置感を感じる耳石など、さまざまな器官があり、それぞれがリンパ液でつながっています。
2.どうしてなるの?
この内リンパ液の調整が何らかの原因で過剰になると、内リンパ水腫をつくり、これが神経を圧迫し、めまい、耳鳴り、難聴などのさまざまな症状が現れるのが、この病気です。
突然、激しいめまいに襲われ、吐き気や嘔吐を伴うこともあり、初期は、めまいの発作時に耳の閉塞感や圧迫感など、耳が詰まったような感じを受け、めまいを繰り返すうちに耳鳴りや難聴を伴うようになり、次第に発作時以外にも症状が残るようになる。この病気は、30~50歳代の働き盛りの人が罹り易く、男性に多い傾向がある。多くの人に共通するのは、仕事や人間関係などで人一倍緊張感が続いていたり、責任感が強く、働き過ぎの傾向にあり、強いストレスの中で生活をしている人です。 また、季節の変わり目や気候の変化、特に低気圧の時に発作を起こし易くなるので、このような時には特に過労を避け、ストレスを溜め込まないようにする必要がある。
3.生活習慣改善アドバイス4.早期発見が鍵です!
- 心身ともにリフレッシュし、ストレスを解消する
- リズム感のある規則正しい生活を送る
- 睡眠時間を充分にとる
- 忙しくなる期間の前後にはできるだけ休養をとる
- ゆとりのある生活を心がける
- 休日には趣味やスポーツを楽しむ
メニエール病は、症状が悪化すると治療が困難になるので、初期のうちに正確な診断、適切な治療を受けることが大事。
聴力検査にて難聴かどうを調べ、平衡機能検査や、更に必要に応じて、頭部のCT検査やMRI、耳のX線検査なども行う。
2009/06/12(この記事の訂正版を2009/07/17「「メニエール病」について」にて行いました。)健康について、情報を発信し、健康に気をつけていたつもりの本人が、今回情けなくも突発性難聴を再発いたしました。
反省の意味を込めて、突発性難聴についての、情報を探ってみました。 その中でも、自分に施された治療とその後の経過等の体験を通しての判断を交えて、『ウィキペディア(Wikipedia)』の情報がお勧めです。
若しも不幸にも、片方の耳に異常がでた場合は、自己判断をせずに、下記のサイトの上の、原因・症状を参考にされて、一刻も早く大きな病院に駆け込んで治療を受けてください。
▼『ウィキペディア(Wikipedia)』上の、原因・症状:
原因 :
内耳などに障害が生じる感音性難聴の一種と考えられているが、現在のところ原因は不明である。
症状 :
毛細血管の血流が妨げられ内耳に血液が十分届かずに機能不全を引き起こすという内耳循環障害説、ステロイド(感染症に対して抗炎症作用を持つ)が効果を発揮することからウィルス感染を原因とする説などがある。 患者調査の傾向からストレスを原因の一つとする意見もある。耳以外の神経症状(四肢の麻痺など)は見られない。遺伝の要素は見つかっていない。分野としてはあまり研究が進んでいないのが現状である。軽~重度の難聴(低音型・水平型・高音型など)と耳鳴りなどが中心であり、それに加えて音が「異常に響く」「割れる」「二重に聞こえる」「音程が狂う」など、その副症状も人によって様々である。めまいや吐き気を訴える事もある(この場合はメニエール病も疑われる)。ほとんどの場合片側のみに発症するが、稀に両側性となる場合もある。
治療:誤解されがちな点であるが、突然の失聴が患者に与える精神的負担は極めて大きい。外見的に障害が見られず周囲の理解が得られにくい事に加え、健康体からの突然の発症からくるショックや、耳の異常を常時自覚せざるを得ないため、深刻なストレスと精神的苦痛を常に強いられる。特に大人になってからの中途失聴は障害認識が難しく、それまで言語コミュニケーションにより築いてきた友人関係・家族関係・社会的地位などを危うくする場合もある。
適切な早期治療と安静が極めて重要である。症状を自覚した場合は速やかに設備の整った病院(大学病院など)で耳鼻咽喉科の専門医の診断を受けることが肝要。判断と治療の困難さから小病院・一般医では知識や設備が不足している場合が多く、誤診による手遅れ・認識間違い等に注意が必要である(実際に聴力低下が見られても、ある程度会話が聞き取れれば正常とみなされ異常と診断されないこともある)。
なお治療方法は前述の仮説を想定したものが中心となる。一般的には発症から約2週間以内が治療開始限度と言われており、これを過ぎると治癒の確率は大幅に低下する。治療開始が早いほど、その後の症状に大きな差異が出るとの考えもある。重度であれば入院での加療が望ましい。
* ウイルス性内耳障害改善を目的とする、ステロイド剤投与(比較的効果が高い)。
* 内耳循環障害改善を目的とする、血流改善剤(アデホスコーワ等)、代謝促進剤(メチコバール等)、高気圧酸素療法、星状神経節ブロック注射等。
* 内リンパ水腫改善を目的とする、利尿剤(イソバイド、メニレット等)投与。
2007/09/17http://www.headache-g.com/
頭痛の悩み.com頭痛を治療するための情報を紹介しているHPです。頭痛について初歩的な疑問を持っている人のために、症状を引き起こしている主な原因、片頭痛(偏頭痛)や脳腫瘍、脳梗塞などの原因や治療法、普段の生活で実行できるおススメの予防法、薬の正しい飲み方、病院選びに失敗しないポイント、病院やクリニックの紹介などを行っています。
当サイトも、「リンク集」に、相互リンクされています。
2006/10/21免疫力高める乳酸菌発見
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20061015ik06.htm
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/10/15熊本県立大と大塚製薬の共同研究グループが、14日札幌市で開かれた日本消化器関連学会で発表した ところによれば、ウイルスや細菌などの病原体が、口や鼻から感染するのを防ぐ機能を高める新しい乳酸菌を発見したという。
乳酸菌の摂取で、人の唾液中の免疫たんぱく質の増加が確認されたのは初めてで、かぜやインフルエンザなどの予防対策に利用が期待される。小腸守る免疫 仕組みを解明…阪大グループ
大阪大の審良(あきら)静男教授らのグループが、10日の米科学誌ネイチャー・イムノロジー電子版に発表したところによれば、小腸から組織内に侵入しようとする細菌を免疫系が見つけて攻撃する仕組みをマウスの実験で突き止めたという。腸内には様々な常在菌や病原菌がいる。小腸は食物を分解して栄養分を腸壁の粘膜から吸収しており、何を手がかりに粘膜から入り込む病原菌を見分けるのかは謎だったが、審良教授らは、細菌が持つべん毛のたんぱく質をとらえるセンサー「TLR5」に着目。
病原菌は小腸の上皮を突き破る際にべん毛を使っており、樹状細胞が細菌の侵入を監視しているらしく、ビフィズス菌などの「善玉菌」にもべん毛はあるが、通常は腸内だけで活動、組織に侵入することはないため、このセンサーが働かないという。http://www.lc1.jp/general/index.asp
乳酸菌応用研究会乳酸菌応用研究会とは、乳酸菌研究の助成及びネスレジャパングループとの共同研究を推進して、健康に寄与する食生活を通じて生活の質の向上に貢献するところだそうです。その乳酸菌応用研究会が解説する「乳酸菌と健康」についての役立つページを紹介します。
リンクを設定していますので、記事メニューにカーソルを合わせて、リンク先の情報を参照してください。
- 乳酸菌は善玉菌
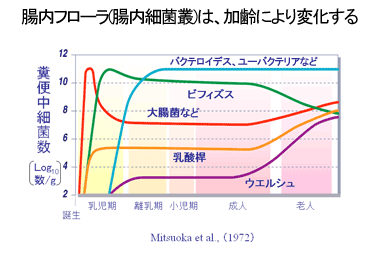
- プロバイオティクス
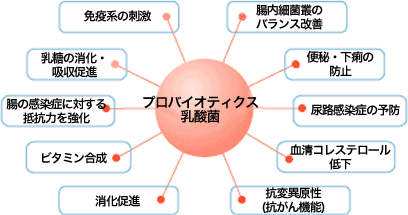
- 「プロバイオティクス」とは?
「プロバイオティクス」とは、口から摂取され、生きたまま腸に到達し、カラダの健康に役立つ微生物のこと。- 乳酸菌はプロバイオティクスの代表です
- 乳酸菌のプロバイオティクス機能
- 21世紀はプロバイオティクスの時代
- 乳酸菌と免疫
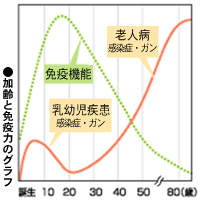
- 自然の防御力、それが免疫力
- 免疫系のふたつのしくみ
- 免疫と年齢、疾患の関係
- 免疫のポイントそれは腸
- 乳酸菌と免疫
- LC1乳酸菌の研究成果
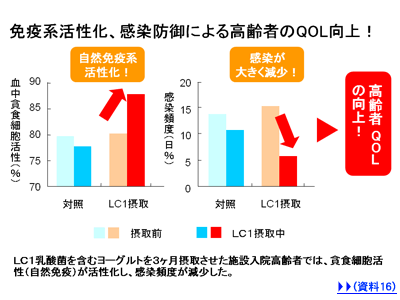
- プロバイオティクス「LC1乳酸菌」
- 「負けないカラダ」づくりをサポート、LC1乳酸菌のトリプル効果
- 腸壁に接着して、バリアをつくる
- 抗菌作用で有害菌の撃退
- 免疫系を活性化
- 腸内環境の改善
- 有害菌の抑制:食中毒菌
- 有害菌の抑制:ピロリ菌
- 高齢者のQOL改善
- 女性のカラダの悩み解決!
- アレルギーへの影響
- 安全であること
- Q&A おしえて乳酸菌
- あなたの腸は大丈夫?(今日の健康をチェック)
- 乳酸菌と健康関連用語集
- LC1乳酸菌学術資料集
http://community.dinos.co.jp/special/20021002/s04.html
http://community.dinos.co.jp/special/20021002/s03.html
Ricco リッコ ~キレイと元気を作る情報サイト > 特集 >Vol. 3 ヨーグルトで便秘知らず▼ヨーグルトを効果的に食べるコツ
一般的に200g/日。食事と一緒に摂る。ビタミン、食物繊維の豊富な抹茶や、オリゴ糖を含むきな粉、カルシウムが豊富なゴマなどは、ヨーグルトとも組み合わせ易く、手軽に効果があるのでおすすめ。
ヨーグルトの整腸効果は、毎日続けなければ意味がありません。 3日に一度は、違った種類の菌を含むものを摂った方が良いと、「日経ヘルス」2003/6月号の「ヨーグルトでキレイに!」に書いてあった。▼腸内環境を改善するヨーグルト選び
最近では各メーカーがプロバイオティクスの名のもと、独自の乳酸菌を含んだ機能性ヨーグルトを発売している。そのパッケージには、さまざまな乳酸菌の名前があり、いずれも健康への効用を持っているので、自分の目的に合わせて賢く選ぼう。
プロバイオティクス(BB536)に加え、母乳に含まれる健康成分ラクトフェリンを加え、パワーアップしたヨーグルト。胃の中で消化されると、直接悪玉菌を減少させる働きを持ち、整腸効果がある。 ラクトフェリンヨーグルト/森永乳業
120円(希望小売価格)/120g入り雪印が独自で開発した善玉菌の「ガセリSP株」と「ビフィズス菌SP株」を組みあわせたヨーグルト。SPは、、「Snow Probiotics(スノー・プロバイオティクス)」の略だそう。2つの菌の効果で整腸作用がさらにアップ。
200g入り130円(希望小売価格)の商品も。雪印ナチュレPRO-GB/雪印乳業
240円(希望小売価格)/500g入りビフィズス菌・BE80種には、腸に働きかけ、食物が腸内をスムーズに通過するようにする効果が。なめらかな食感もポイント。 ダノンビオ BIO/カルピス味の素ダノン
120円(希望小売価格)/110g入りLG21には胃と腸の調子を整える効果があり。胃かいようの原因のひとつとされるピロリ菌を減少させたり、感染を防ぐ食品として特許も取得している。
胃の粘膜の荒れを整える効果もあり。明治プロビオヨーグルトLG21/明治乳業
120円(希望小売価格)/120gヨーロッパでも高い評価を得ているプロバイオティクスLC1を使用。こちらも胃かいようや胃炎の原因とされるピロリ菌を減少させる効果があり、特許も取得。腸内環境を整え、免疫力も強化。 LC1ヨーグルトプレーン/ネスレ・スノー
120円(希望小売価格)/120gGG株には、腸内でウェルシュ菌やアンモニアの量を抑える働きが。
おなかの中の老廃物をきれいにクリーニングすることで、美肌効果もあり。ヨーグルトおなかへGG!/タカナシ乳業
80円(希望小売価格)/100g
テレビや雑誌で注目されている「カスピ海ヨーグルト」は、店頭販売はせず、クチコミだけで広まったヨーグルト。もともとは、京都大学名誉教授・家森幸男教授がコーカサス地方のグルジアから20年ほど前に持ち帰ったヨーグルトがはじまりのよう。
そのくせのない味わいと家庭でも簡単に増やせる気軽さから全国に広まり、「便秘が治った」「肌がきれいになった」など、各地で評判に。ほかのヨーグルトにはない、特徴ある粘り気はクレモリス菌によるもので、腫瘍を抑制したり、免疫力を高める効果があるのだそう。
最近ではネット販売などによる、入手方法もあるようですが、生モノだけに知りあいのツテなどで顔見知りの人から手に入れるほうが安全のようです。このとろみが特徴。きな粉や抹茶などと組みあわせると効果がさらにパワーアップ。
http://knorkator.hp.infoseek.co.jp/joghurt/joghurt.html
Brilliant Success Institute■腸内フローラとは?
■乳酸菌+オリゴ糖の摂取
■動脈硬化と腸内細菌
▼動脈硬化とは?
■がんに克つ!
▼脳で動脈硬化が起こると
▼心臓で動脈硬化が起こると
▼コレステロールと動脈硬化
▼がん細胞の発生と分裂
■アトピー性皮膚炎克服の鍵
▼がん細胞と戦う免疫機能
▼免疫機能の異常と腸内環境
▼がん予防・がん免疫治療
▼なぜアトピーが増えたのか
■肥満は万病のもと!
▼それでもステロイド剤を使用しますか?
▼アトピー克服の鍵
▼赤ちゃんをアレルギー体質にしないために
▼あなたの肥満度をチェック!
▼脂肪の取りすぎを阻止する腸内細菌
▼砂糖を吸収させない腸内細菌
http://knorkator.hp.infoseek.co.jp/joghurt/joghurt.html
NARUE's Home Page▼紹介されているヨーグルト
- チチヤス プロバイオティックロイテリ菌ヨーグルト
- morinaga ラクトフェリ
- morinaga おなかに配達ヨーグルト 宅配専用
- ネスレ ヨーグルト<プレーン>LC1
- 明治 プロビオヨーグルト LG21
- ダノン BIO スーパークリーミーヨーグルト
- 福島乳業 福ちゃん たべるデンマークヨーグルト
- 全国農協直販 ヨープレイト ビフィーナヨーグルト
- 横浜乳業 ビフィズスヨーグルト
- 蒜山酪農農業協同組合 HIRU RAKU 蒜山ジャージーヨーグルト
- タカナシ プレーンヨーグルト
- タカナシ プレーンヨーグルト + LGG
- ホウライの那須千本松牧場 ヨーグルト
- coop 生乳のヨーグルト
- 建部ヨーグルト 生乳
- 高原安瀬平乳業 自然の恵みをそのままパック ヨーグルト
- ヤスダヨーグルト あさごはんヨーグルト
- オハヨー乳業 おなかシアワセヨーグルト
- ホリ乳業 腸内活性 ヨーグルメイト
- 協同乳業 いつものヨーグルト生活
2006/09/03スダチの搾りかすに血糖値抑制効果、徳島大教授ら発表
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060830ik07.htm
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/08/30スダチの皮などの搾りかすに、血糖値の上昇を抑える効果のあることが、徳島市農協と共同研究した徳島大薬学部の高石喜久教授(生薬学)、土屋浩一郎助教授(薬理学)らのラットを使った研究でわかった。
スダチ特有の「スダチチン」など19種類の有機化合物の中に、血糖値を下げるインシュリンの働きを助けるものがあるとみられ、徳島大は同農協とその効能についての特許を出願したという。健康志向食材、商品化へ農水省が力 老化防止トマトなど
健康へのプラス効果が期待される食材や素材の開発に、農水省が来年度から本腰を入れ、同省の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構などで開発した食材、素材の商品化を本格的にスタートさせる。
期待されるのは、抗酸化作用があるリコピンを多く含む「高リコピントマト」や血圧上昇を抑えるギャバが豊富な胚芽を大きくした「巨大胚芽米」など。既に商品化されものもあり、花粉症緩和に効果があるメチル化カテキンを普通の緑茶の数十倍も含むお茶「べにふうき」は、飲料メーカーのアサヒ飲料が今年から一部で販売している。内臓脂肪症候群:ハンドブック出版、メカニズム紹介
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/08/20060828ddm013100040000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/08/28過食や運動不足のライフスタイルから心筋梗塞や脳卒中などの血管病を発症するまでの、メタボリックシンドロームの病態をわかりやすく解説され、平成20年度からの健診・保健指導義務化に備えた、医療従事者向けハンドブック「メタボリックシンドローム実践ハンドブック」(松澤佑次監修、メディカルトリビューン発行:A4判118ページ、3150円)が出版された。
本書は、職員に対する保健指導で生活習慣病予防に効果を上げた兵庫県尼崎市の取り組みに基づく、実践的な内容になっている。出版社コメント
1)尼崎市市役所職員の心筋梗塞・脳卒中を0にした保健指導の現場から生まれたものです。
2)保健師をはじめとする全国の健診・保健指導に従事している方々向けの実践書。
3)切り離してすぐ使える保健指導用チャートが付いています。
腸内細菌ドットコム <腸内細菌から始める病気予防>
http://www.chonaisaikin.com/index.html
サンユーコーポレーション腸内細菌に関する情報が、わかり易く、図入りで下記のメニューの内容で掲載されております。 でも、(株)サンユーコーポレーションさんの商品しか購入できませんが、腸内細菌の基礎知識を身に付けるには一読する価値はあるとおもいます。■ページ構成:
- 腸内細菌って何?
- 腸内細菌の役割
- 腸内細菌の働きとは
- 株って何?
- 善玉菌と悪玉菌?
- 乳酸菌と腸内乳酸菌?
- 腸内細菌 栄養学
- 予防医学って?
- ビタミンとは?
- 抗酸化って?
- 便秘と腸内細菌
2006/08/23コエンザイムQ10、業界団体が安全性情報収集
老化防止に効果があるといわれている健康食品「コエンザイムQ10」について、内閣府食品安全委員会が健康に与える影響を評価していたが、データ不足のために摂取量の上限を決めるのは困難としていたが、業界団体の日本健康・栄養食品協会は、1日当たりの摂取目安量が30mgを超える商品を対象に安全性情報を収集することを明らかにした。[探健くらぶ]コエンザイムQ10…老化防止 効果は「?」
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060821ik07.htm
YOMIURI ONLINE > 医療と介護 > ニュース 2006/08/20エネルギー作り助ける 重大な副作用報告なし
コエンザイムQ10は、体の中にあるごく普通の物質。“エンザイム”は酵素、“コ”は補う、という意味。細胞内でエネルギーを生みだす時に、酵素を助けて働く、なくてはならない存在。老化に係わる活性酸素を消す抗酸化作用もあり、年齢とともに減ってくるという。
国立健康・栄養研究所の健康食品情報収集を担当する薬学博士の梅垣敬三さんによれば、「ビタミンや鉄、カルシウムなどと違い、そもそも体に必要な量は現時点でははっきりしていません」とのことです。また梅垣さんたちは、コエンザイムQ10に関する世界中の医学的な研究論文を集め、信頼性の高い臨床試験の一覧をインターネット上に公開しているが、現時点では寿命や老化防止の効果を調べた臨床試験が無いという。
コエンザイムQ10は、レバー・イワシなどに多く含まれ、血液中の約4割は食べ物で摂った分と見られているが、体内でも作られので必ず外から補わなければならないというものでもない。もともと日本では心不全の薬として1973年から使われており、1日に飲む量は30mg。それより多く含まれる商品も流通している。既に90年代から広く錠剤やカプセルが売られている米国を含めても、これまでに世界中で命にかかわる重大な副作用は報告されていない。からだづくり:太りやすくなったのはなぜかな~
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/08/20060823org00m100011000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/08/23「最近、なんだか太りやすくなった」「運動をしても、思うように脂肪が落ちない」「毎年、少しずつ太ってきている。」という方、必見の情報です。なぜ太り易くなっているのか、日常生活の中の体に悪い習慣がチェックできます。さて、あなたは、いくつあてはまりますか?
【質問】
常に睡眠不足である(睡眠時間は5~6時間)/熟睡できない/週に4回以上菓子を食べる/子供の頃(幼少期~15歳位まで)に肥満になった経験がある /朝食を食べない/常にエアコンがきいている部屋にいる/両親共(又は兄弟が)肥満である/昼は13:00頃までに食べ終わり、残業などで、夕飯は21:00以降の日が多い/35才以上である/ストレスを感じると沢山食べてしまう/週に3回以上、つまみを食べながらお酒を飲む/近所のコンビニも車で移動する/車通勤である/早食いである/1日の内で、夕食を一番「がっちり」食べる
【答え】
上記の質問に対して当てはまる数が、ひとつ以上だと、要注意。3つ以上では、かなり危険。5つ以上は、大変です!
とろろ昆布、中性脂肪の上昇を抑制
フジッコ(神戸市)と東京海洋大大学院の矢澤一良教授との共同研究によれば、昆布を薄く削った「とろろ昆布」に血中の中性脂肪値の上昇を抑える作用があり、29日に開催される日本食品科学工学会で発表する。
昆布を薄く削ることで細胞が細かく切断されて、中性脂肪値の上昇を抑える水溶性食物繊維が体内に取り入れ易い状態になるためだという。▽フジッコ > プレスリリース 2006.8.18 > とろろ昆布が血中の中性脂肪の上昇を抑えることを証明
2006/08/20たばこは美容の敵 若い女性に国が禁煙キャンペーン
厚生労働省が来年度から 「たばこは美容の敵」を合言葉に、20~30歳代の女性向けに新たな禁煙キャンペーンに乗り出す。
04年の厚労省の調査では、成人全体の喫煙率26.4%(男性43.3%、女性12.0%)で、男性は前年より3.5ポイント下がっているが、女性は0.7ポイント上昇し、対策の必要性が指摘されていた背景が有る。
化粧品会社の調査では、喫煙者は非喫煙者よりシミやくすみの原因となる色素「メラニン」が約5歳分早く増えることが報告されており、また、歯が黄色っぽくなったり歯茎が黒ずんだりするといわれ、こうしたデータを盛り込み喫煙が美容の大敵であることを訴え禁煙意識を高める。知りたい:「牛乳有害」って本当? 栄養学的には少数派
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/08/20060818dde001040013000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/08/18「健康飲料」の代表格の牛乳を「有害」とする説が書籍やネット上で取り上げられ、波紋を広げているという話題について。
端緒となったのは、米国在住の胃腸内視鏡外科医・新谷弘実氏著となる「病気にならない生き方」(サンマーク出版)だが、著者の長年の臨床経験から導き出した食生活の改善法をまとめたもので、牛乳に関する記述が特に注目され、更に、環境ホルモンの観点からの有害説も登場しすそ野が広がったもの。
牛乳に含まれるカルシウムの摂取源として牛乳は有益でないとする根拠の一つが、骨粗しょう症との関係。
- 卵巣がんリスク上昇
- 子牛用飲むの不自然
- 工業化飼育法に問題
牛乳摂取量が多い欧米の高齢者の大腿骨頸部の骨折率は、日本より高いために「牛乳は防止策にならない」とする説に対し、体型の差だとする説もある。子牛の成長を促す牛乳には、硫酸エストロン等の女性ホルモンが含まれており、佐藤章夫・山梨医科大名誉教授によれば、「硫酸エストロンはビスフェノールAなどの環境ホルモンよりも強い」という。これに対し、山口大農学部の中尾敏彦教授(獣医学)は「牛乳からホルモンを摂取しても、女性の体内のホルモンの量に比べれば微々たるもの」と疑問を呈す意見もある。
有害の一つとして、「牛乳は子牛が飲むもので、人が他の哺乳動物の乳を飲むのは不自然」との考え方がある。
酪農学園大大学院の中野益男教授(環境生化学)によれば、最近の牛の飼育法が工業化され、牛の生理に合わなくなっている問題があるという。ザクロジュースが前立腺癌の進行を抑制
投与中8割超える患者でPSA倍加時間が延長、米UCLA大の研究http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200608/501195.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/08/18米カリフォルニア大学ロサンゼルス校(UCLA)のAllan J. Pantuck氏らが、Clinical Cancer Research誌2006年7月1日号に発表したところによれば、前立腺癌患者に毎日約240mLのザクロジュースを摂取させて、前立腺特異抗原(PSA)に与える影響を調べたところ83%の患者でPSA倍加時間の有意な延長が確認された。患者血清を用いたin vitro実験でも、抗酸化活性の上昇や、前立腺癌細胞株に対する増殖抑制と細胞死誘導作用が確認されたという。強い抗酸化作用をもつザクロ由来のフィトケミカルが、in vitroで前立腺癌細胞株の増殖を抑制することは既に知られていたが、植物に含まれるフィトケミカル(植物化学物質)には、抗酸化作用などによって癌予防に役立つ可能性を示すことが確認されたもの。
「メタボリック症候群減らせ!」健診時の指導強化
厚生労働省は18日、内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)の広がりを防ぐため、健康診断の際に実施される保健指導のあり方を見直す方針を固めた。
保健師が健診結果を踏まえ、具体的な目標を面接やメールで積極的に提供し、その後も継続的にチェックすることで、「相談型指導」から「介入型指導」への転換を図る。08年度から実施させる。
新しい保健指導は、メタボリック・シンドロームの指標となるウエスト周囲径や血圧、血糖値などの数値の改善を目標とする。
健診結果を見て、状況に応じて下記等を実施する。
〈1〉腹囲や血圧などに問題が多く、改善が不可欠な場合の「積極的支援」
〈2〉一部に問題はあるが現状維持でもいい場合の「動機付け支援」
ポリ容器から溶出物質 / 環境ホルモン作用確認
カップめんや弁当のポリスチレン製容器から溶け出すと報告されているスチレントリマーが、生体内でホルモンに似た作用をする環境ホルモンであるということを、ラットを使った実験結果を、東京都健康安全研究センターの大山謙一主任研究員らのグループが16日までにまとめた。妊娠中のラットにスチレントリマーを7日間投与し、生まれた雄ラットを調べたところ、1日体重キロ当たり10μgで、生後約100日後の脳や精巣の重量が、投与しない場合に比べて目立って減少していたほか、肛門と生殖器の間の距離が短くなったり、血中の精腺刺激ホルモンの量が減ったりするなど、ホルモンバランスに影響を与えたことを示す結果が得られたという。
トウガラシに食後の高血糖予防効果あり / 太っている人ほど効く!
このほど発表されたオーストラリアでの研究(Am.J.Clin.Nutr.;84,63- 69,2006)によれば、トウガラシに含まれる辛み成分「カプサイシン」は、食べた物を体内で熱に変える作用を持っており、肥満や糖尿病の原因となる食後の高血糖を抑える作用を持つことがわかったという。その効果は、肥満気味の人ほど高かった。
この研究では、チリソースが使われており、1日に食べた量は生のトウガラシ16.5g分とかなりの量。乾燥トウガラシの粉末で換算するとティースプーン4~5杯分になる。早食いは肥満のもと 名大グループ調査
名古屋大の玉腰浩司・助教授(公衆衛生学)、大学院生の大塚礼さんらが、愛知県内に住む35~69歳の男性3737人、女性1005人の身長・体重・食事内容・運動習慣のデータを分析した結果、早食いをすることで肥満を招き易くなることが判ったという。早食いそのものが、肥満を招く理由はまだよくわかっていないが、早食いだと、エネルギーの取り込みを促進するホルモン、インスリンが過剰に分泌される可能性などが考えられるという。
スイカの栄養価高めるには常温保存が一番
米農務省(USDA)サウスセントラル農業研究所(オクラホマ州)のPenelope Perkins-Veazie氏が「Journal of Agriculture and Food Chemistry」8月9日号に発表したところによれば、スイカは常温(室温)で保存する方が高い栄養価が期待できるという。
スイカの果肉の赤い色は、トマトと同じカロチノイド色素リコピンによるもので、量は少ないものの、βカロチンが含まれ、このような抗酸化物質には、細胞を傷つけ癌の原因となるフリーラジカルを無害化するはたらきがある。
常温で保存した2週間後のスイカは、カロチノイド含有量が品種により11~40%増大した。低温では酵素の活性が低下するために果実の成熟が止まるのではないかと推測される。
2006/08/03癒しんぼ:ドロドロ? サラサラ? あなたの血液はどっち?
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/08/20060802org00m100047000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/08/02生活習慣を見直すきっかけになるということで、美容と健康にうるさい女性たちの間で密かなブームとなっているTVの健康情報番組などでおなじみのバイタルチェックについてのレポート記事。大阪市北区にある女性専用の健康サロン「Rest Space マツノ」では、¥1000/回のチェック料金で、血液中の赤血球などの成分の状態をリアルタイムで見ることができる。
ドロドロ血液をモニターで見ると、赤血球同士が重なり合うようにくっついており、血中の粘度が高くなっているのが判る。脂っこいもの、甘いものを食べ過ぎると、いわゆる血液が「ドロドロ」になる。
ドロドロ血液の赤血球は、真ん中が白っぽく見える。それに対し、サラサラ血液の赤血球は、色が均一。ビタミンやミネラルが十分に足りて、中身がギュッとつまった状態なのだそうだ。
血液をサラサラに保つには、食生活+適度な運動(30分のウォーキング/日)+十分な水分(1.5L/日)を摂ること。
血液をサラサラにする食べ物は、ニンジンやゴボウ、タマネギといった根菜が良いそうです。内臓脂肪、ウエスト同じでも日本男性は米より「多め」
日本人は米国人ほど極端に太らず、少し太っただけでも糖尿病などの生活習慣病に罹り易いといわれているが、その理由は分かっておらず、メタボリック症候群をめぐって、滋賀医科大と米ピッツバーグ大が、草津市と米ペンシルベニア州で40~49歳の男性それぞれ239人、177人の住民のウエストサイズを測り、CTで腹部の内臓脂肪などの断面積を調べた結果、日本人男性は腰回りのサイズが同じでも、米国の白人男性より内臓脂肪多いことが判ったという。例えば、ウエストが88.9~96.8cmの層を比べてみると、皮下脂肪の断面積は白人の方が日本人より7平方cm上回ったが、逆に内臓脂肪は日本人が101.7平方cmと、白人の85.5平方cmを上回った。この傾向は体格にかかわらず見られたという。
生活習慣病予防の運動指標は「エクササイズ」
厚労省の検討会がが簡便な指針作成http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200607/501065.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/07/31厚生労働省の「運動所要量・運動指針の策定検討会」は、生活習慣病予防を目的に「健康づくりのための運動指針2006」を作成し、7月25日の第23回厚生科学審議会地域保健健康増進栄養部会に報告した。この指針は、身体活動全般を速歩やジョギングなどの「運動」、日常の掃除や買い物などの「生活活動」に分け、「エクササイズ(Ex)」という身体活動量の単位を設定し、どの活動をどれ程度行えば必要な運動量が達成できるかを示したのが特徴で、運動習慣のない人でも、日常生活の中で活動量を増やして生活習慣病予防に取り組めるよう工夫している。
●1エクササイズに相当する運動の例における活動内容 時間(分) ボウリング、バレーボール、フリスビー、ウエートトレーニング(軽・中強度) 20 速歩、体操(ラジオ体操など)、ゴルフ(カートを使って)、卓球、バドミントン、
エアロビクス、対極拳15 軽いジョギング、ウエートトレーニング(高強度)、ジャズダンス、エアロビクス、
スケットボール、水泳(ゆっくり)、サッカー、テニス、スキー、スケート10 ランニング、水泳、柔道、空手 7~8 ●1エクササイズに相当する生活活動の例における活動内容 時間(分) 普通歩行、床掃除、荷物の積み下ろし、子供の世話、洗車 20 速歩、自転車、介護、庭仕事、子供と遊ぶ(歩く/走る、中強度) 15 芝刈り(電動芝刈り機を使って、歩きながら)、家具の移動、
階段の上り下り、雪かき10 重い荷物を運ぶ 7~8
ヘルシーリポート:健康インフォメーション 中性脂肪に黒烏龍茶
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060729ddm010100213000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/07/29サントリーが5月から発売した「黒烏龍茶」が食後の中性脂肪の上昇を抑えるということで、特定保健用食品(トクホ)に認められた。
臨床試験は中性脂肪がやや高めの成人男女20人で実施し、食事と同時に黒烏龍茶を飲んで、他の飲料に比べ、食後の血清中性脂肪の濃度が約20%低くなった。
また、男女12人・10日間、食事時に黒烏龍茶を飲んで、便に含まれる脂肪量を調べたら、飲まない時に比べ、脂肪の排せつ量が約2倍も多くなった。
この効果は、茶葉の半発酵の過程でできる「ウーロン茶重合ポリフェノール」の作用によるという。▼サントリー>ニュースリリース No.9410 (2006.4.4)
サントリー「黒烏龍茶」(特定保健用食品)新発売 ― 脂肪の吸収を抑え、食後の中性脂肪の上昇を抑制する ―
日本人の平均寿命 右肩上がり、何歳まで?
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060728dde001040002000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/07/28インフルエンザの流行で05年の日本人の平均寿命が6年ぶりに前年を下回ったとはいえ、女性は21年連続の1位(85.49歳)、男性も世界4位(78.53歳)と長寿。 では、日本人はどこまで長生きできるようになるのだろうか?。
◇2300年国連予測、男女とも100歳超
国立社会保障・人口問題研究所が、国勢調査のデータなどを基にして’02年に出した、2050年の日本人の平均寿命は、男性 80.95歳、女性は89.22歳。
国連が04年に発表したリポートでは、1950年~2050年までの人口リポートを基に寿命が延び続けるとして、はじき出した2300年の日本人の平均寿命は、女性108歳、男性104歳。
国立長寿医療センター研究所(愛知県)によると、寿命の限界は120歳ほどだというが、実際の限界は分からない。衰えた器官などを再生することが出来るようになれば、平均寿命はさらに延びるかもしれない。
◇「予防医療重視に転換を」
女子栄養大(埼玉県坂戸市)の香川靖雄副学長によれば、現在の日本人の長寿は、高額な医療費に支えられているもので、財政破たんで医療制度が維持不能になれば下がるという。食生活の欧米化で肥満や糖尿病の生活習慣病により、平均寿命を押し下げる要因になりかねていると指摘している。
長生きをしても、寝たきりで意味がないので、いかに老化を抑えるかが重要であり、男性79.0歳=世界1位、女性84.7歳=同2位の香港では病気予防に主眼を置いているという。
パソコンやiPodでエクササイズに革命
米国人の過半数は、政府が推奨する「中等度の運動を1日30分以上」の運動量を満たしていないという。そういった状況の中、PCやiPodのような携帯情報端末があれば、バーチャル個人トレーナーやポッドキャスト、動画配信などの最新の技術を利用してフィットネスを米穀では始めることができるという。「PumpPod」は、iPodなどで利用できるトレーニングプログラムで、ヨガ、エアロビクスなど43種類の中から選び、インターネットからダウンロードできる。
費用の面においても個人トレーナーの35~100$/時に比べ、バーチャルトレーナーなら、10$/月ですませることもできるメリットがある。ローヤルゼリーが骨粗しょう症予防に有望
山田養蜂場は、静岡県立大学、福岡医療短期大学と共同で、国際学術誌「eCAM」に発表したところによれば、ローヤルゼリーが骨密度の減少を抑え、骨中のカルシウム量を増やすことをラットの試験で確認したという。ローヤルゼリーは疲労回復や抗老化を目的に、古くから服用されているミツバチの分泌物で、海外の論文誌への論文掲載は国内外で初めてという。
山田養蜂場によれば、更年期症状を持つ女性において、一日700mg~1200mgのローヤルゼリーが更年期症状などの改善効果を持つことも確認しているという。
2006/07/23睡眠が記憶を強化する
米ハーバード大学(マサチューセッツ州)医学部睡眠認知センターJeffrey M. Ellenbogen博士らが、生物学誌「CurrentBiology」7月11日号に発表したところによれば、少し前に学習した事実や出来事を思い出す「陳述記憶(言葉で表現できる記憶)」に睡眠が不可欠であるという。「how to記憶」とも呼ばれる「非陳述記憶(言葉で表現できない記憶)」に睡眠が有効であることは過去に示されていたが、陳述記憶にも睡眠が及ぼす影響については判っていなかった。
記憶の強化をはじめ、脳は睡眠中にもさまざまなことを行っており、記憶力を最大限にするためには定期的に睡眠を取ることが必要だという。食物繊維少ないと大腸がん発症の危険性
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/ext/200607/500999.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/07/20厚生労働省研究班が20日発表したところによれば、食物繊維は、10g/日を超えて取っても大腸がんの予防効果に差は出ないが、摂取量が少ないと発症の危険性は、2.3倍に高まるという。
同様の結果は欧米でも出ており、適度な摂取が健康維持に大切。厚労省は、生活習慣病予防の観点から大人で15~20g/日の摂取目標を掲げている。肥満予防・対策、「飲み物に注意」は少数 花王が調査
食事や運動に比べ、肥満予防・対策で飲み物に気をつける人は少ないという調査結果を花王がまとめた。
1日にとる飲み物の量は平均1486mLで必要量は満たしていたが、中身への意識は低いようだ。▼花王 > ニュースリリース(2006.05.30)
「サラリーマン・OL800人調査 「飲みものと肥満」の関係」
「調査によると、肥満予防・対策としての「飲みもの」への意識は「食事」「運動」に比べて低く、「何を飲むか」という中身についても、男性サラリーマンの意識が低くなりがち。メタボリックシンドロームが社会問題化する中で、「どれ位飲むか」だけでなく「何を飲むべきか」についても、意識を高く持つことが重要になってきている。」と結論付けています。
加齢臭:本人気付かず周囲困惑 においの元、40過ぎから増えストレスで加速
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060715ddm013100114000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/07/15脂臭いような青臭いような加齢臭特有のにおいの元は「ノネナール」という物質、1999年、資生堂と高砂香料工業が共同研究で発見したものだが、男女問わずノネナールは40歳過ぎから増えるが「加齢臭=おじさん臭」と言われがちなのは、男性は皮脂の分泌が多く、においの元の量も多いからだ。◇予防の基本は食事
自宅で作れる殺菌・消臭・制汗剤もある。
硬度が高いミネラルウオーター2L に、粉末ミョウバン50gを溶かした「ミネラルミョウバン水」を、スプレーで体に吹きかける。
加齢臭予防の基本は食事であり、肉類を控え、和食を中心に抗酸化物を多く含む緑茶やごま、納豆や豆腐などを食べると効果的という。
臭いは、健康のバロメーター。加齢臭の強い人は大概、高血圧や動脈硬化の危険性が高いメタボリックシンドロームの予備軍。この記事には、具体的には表現されていないが、加齢と共に善玉菌が少なくなって、悪玉菌が多くなった腸内環境の影響があることを、意識する必要ありです。
たばこの毒、細胞内ではダイオキシン並み 山梨大研究
山梨大医学工学総合研究部の北村正敬教授(分子情報伝達学)らが、米学術誌「キャンサー・リサーチ」15日号に発表したところによれば、たばこを吸うと、猛毒ダイオキシンが大量に体内に入った時と同じ反応が細胞内で起こるという。ダイオキシンが体内に入ると細胞にある受容体(カギ穴)にカギが入るように結びつき細胞を活性化させて毒性を発揮する。
国が定めているダイオキシンの1日の許容量は、体重1kg当たり4pgだが、市販されているたばこ1本分の煙を溶かした液体を使い、マウスを使い反応を調べたところ、国の基準の164~656倍のダイオキシンが受容体に結びついた状態に当たる活性がみられ、タール量が多いと活性も高くなる傾向が出たという。血液検査でアルツハイマー病を早期発見
オランダ、エラスムスErasmusメディカルセンター(ロッテルダム)神経疫学教授 Monique M. B. Breteler氏らが、医学誌「The Lancet Neurology」オンライン版7月6日号に発表したところによれば、アルツハイマー病を血液検査により早期発見できる可能性があるという。
Monique M. B. Breteler氏らの研究によると、アルツハイマー病患者の脳にみられる異常分子であるアミロイド-β蛋白(Aβ)のうち、 Aβ1-40の血中濃度が高く、Aβ1-42濃度が低い場合に、アルツハイマー病のリスクが高いという。(40、42は、Aβを形成するアミノ酸の数を示す。)生活習慣病防ぐには… 厚労省が運動量の目安まとめる
厚生労働省の運動指針小委員会が、生活習慣病の予防に必要な1週間の運動量の目安を示した指針「エクササイズガイド2006」を、15日までにまとめた、19日に開かれる同省検討会に報告する。
スポーツだけでなく、日常生活での活動も対象にして、内容ごとに具体的な時間をあげて、運動習慣のない人でも活用できるのが特徴。メタボリック症候群の人向けに、目安とされる腹囲(男性85cm以上、女性90cm以上)を1cm細くするのに必要なエネルギー消費量を「7000kcal」と設定。自分の腹囲を基準値以下にするために、1日にどれだけエネルギーを消費すればいいか分かるように示した。
活性酸素で加齢黄斑変性
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/ext/200607/500917.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/07/11慶応大の坪田一男教授(眼科学)らが11日、米科学アカデミー紀要(電子版)に発表したところによれば、失明の主因とされる加齢黄斑変性の原因は活性酸素とするマウスでの実験で裏付けた。
2006/07/09体細胞を“若返り”
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/ext/200607/500868.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/07/06京都大再生医科学研究所は、4日、人間の体細胞を、胚性幹細胞(ES細胞)と融合させることで、若返らせ、分化する能力を持たせる研究の実施を、文部科学省の専門委員会に申請した。定年うつ:会社人間ほど危険です 心の準備し、社会的な役割みつけよう
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060706ddm013100146000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/07/06仕事以外に楽しみの少ない「会社人間」だった人が定年退職をきっかけになり易く、最悪の場合、自殺に至ることもある「定年うつ」が注目されている。
最近の傾向として、定年退職だけでなく、役職を離れる「役職定年」や、退職後の転職先に適応できないことをきっかけにした「うつ」が増えているという。◇見分け方
(1)何をしていても楽しそうでない
以上のような症状が2週間続けば、うつ病の恐れがある。
例:熱烈な阪神ファンだったが、TVの野球中継さえ見なくなった。
(2)睡眠障害がある
例:「昼間に何もしていないのだから、夜寝られないのは当たり前」と家族も見過ごしがちになる。
早朝に目が覚めて疲れが取れていなかったり、夜間何度も目が覚めるのは要注意。
(3)焦燥感やイライラ感が強い
例:「こんな生活では駄目だ」と思い、家族にあたったり、怒りっぽく、不機嫌になる。アルコールの量が増えたりする。◇予防法
▽定年前から一度、定年後の自分の生活を想像し、心の準備をする
▽仕事以外の世界を見つけて人間関係を作る
▽ボランティアなど自分が存在する社会的な役割を持つ--など「愛のホルモン」で夫婦間ストレスが減少
米エモリー大学(ジョージア州)精神学行動科学のBeate Ditzen氏らが、ピッツバーグで開催された国際神経内分泌学会で報告したところによれば、「love hormone(愛のホルモン)」と呼ばれるオキシトシンに、夫婦げんかを鎮める効果があるという。オキシトシンは、脳で産生され下垂体から分泌されるホルモンで、人を信じる能力や互いをいたわる能力に関わりがあるとされているが、緊迫した状況でのストレスを軽減させるはたらきもあることが示された。
しわの多い喫煙者は肺疾患のリスク大
英王立 Devon & Exeter病院のBipen Patel博士が、医学誌「Thorax」オンライン版6月14日号に発表した研究によると、顔にしわの多い中高年喫煙者は、しわの少ない喫煙者に比べ、慢性閉塞性肺疾患(COPD)にかかる可能性が5倍であるという。
2006/07/02ヘルシーリポート:健康インフォメーション 植物性乳酸菌でアレルギー緩和
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060702ddm010100142000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/07/02植物成分を栄養源にした植物性乳酸菌の健康効果が注目されている
今年5月、日本アレルギー学会春季臨床大会で発表された、日本赤十字社和歌山医療センターの榎本雅夫・耳鼻咽喉科部長らとキッコーマンの共同研究によれば、植物性乳酸菌のひとつである「しょうゆ乳酸菌」が通年性アレルギー性鼻炎の症状を緩和するという。
研究は、中等度以上の症状を示す通年性アレルギー性鼻炎の大人45人を対象に、しょうゆ乳酸菌の錠剤(20mg/日と60mg/日の2群)を8週間飲んでもらった結果、60mg/日のしょうゆ乳酸菌を飲んだグループは、特にくしゃみ、鼻づまりが改善されたという。ヘルシーリポート:注目!ラクトフェリン 腸内細菌バランス、免疫力を調節
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060702ddm010100144000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/07/02人の母乳や牛乳などに含まれるラクトフェリンというたんぱく質に腸内細菌のバランスを改善させたり、免疫力を上げるなどさまざまな働きがあり、C型慢性肝炎の症状の改善にも効果があると期待されている。
◆乳児に不可欠
母乳に含まれるラクトフェリンや免疫物質などのおかげで、乳児は免疫力を高めている。
◆がん予防
ラクトフェリンは、がん細胞を攻撃する免疫細胞のNK(ナチュラルキラー)細胞などを活性化する働きを持っている。国立がんセンター研究所でも、ラットを使った実験では大腸やぼうこうなどのがんを防ぐ働きを把握しており、国立がんセンター中央病院(東京)では、大腸に5mm以下のポリープをもった患者にラクトフェリンのサプリメントを飲んでもらう臨床試験を行っており、秋にも結果がまとまるという。(津田洋幸・名古屋市立大学医学部教授 談)
◆C型肝炎
C型肝炎に対して、インターフェロンや抗ウイルス薬とラクトフェリンとの併用補助療法について、横浜市立大学市民総合医療センターや三重大学などの試験報告ではラクトフェリンの錠剤を3~6カ月服用すると血液中のウイルスが減ったなどの結果も出ている。
◆痛みの軽減
鳥取大学の原田悦守名誉教授と竹内崇助教授(獣医臨床検査学)らは、マウスを使った実験でラクトフェリンに鎮痛作用があるのを発見した。末期がん患者への有効性を確認するのが今後の課題だという。
◆骨粗しょう症
ラットを使った実験報告によると、ラクトフェリンには骨を作る骨芽細胞を増やし、骨を溶かす破骨細胞を減らして骨の成長を促す働きがあるという。ヘルシーリポート:健康インフォメーション ダイエットにかつお節
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/07/20060702ddm010100145000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/07/02カツオ節にはアミノ酸の一種のヒスチジンが含まれ、これが脳の満腹中枢を刺激して食べ過ぎを防ぐ働きがあるという。
人を対象にした研究で、ヒスチジンの摂取量が多いほど肥満度を表す体格指数(BMI)が低くなったという報告がある。20g/日程度のカツオ節を取れば、肥満予防の働きが得られるといわれる。
カツオ節にはアンセリンというアミノ酸も含まれ、アンセリンを取ってから運動をすると、疲労の指標となる血液中の乳酸が低いという試験研究もあり、運動後の疲労感を軽くする働きがある。クルミ:食べて健康に/メラトニンで抗加齢(その1・2)
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060628ddm013100002000c.html
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060628ddm013100125000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/06/28クルミは、そのまま食べることはあまりないが、最近動脈硬化など生活習慣病の予防効果が科学的な研究で分かり、注目されている。
◇「頭、よくなる油」豊富
他のナッツ類に比べて、α(アルファ)-リノレン酸という不飽和脂肪酸が豊富
◇血液サラサラ
クルミには動脈硬化を防いだり、悪玉コレステロールを減らす効果のあることが分かってきた。現代人の食生活で不足しがちなn-3系油の補充にクルミが役立つ。
◇コレステロール低下
米国FDA(食品医薬品局)は、2年前、「42g/日(殻付きで7~8個分)のクルミの摂取で心臓疾患のリスクを減らす」との健康強調表示を認ている。◇ペーストあれば便利--「ユリス麻布十番」総料理長・多田鐸介さんに聞く
クルミにはホルモンの一種で抗酸化作用をもつメラトニンも含まれる。
家庭料理でクルミを使う場合は、ペーストを作っておくと便利。
「クルミのペーストは介護食にも向く。専門展「サプリ&機能性食品2006」で名古屋大学大学院教授の大澤俊彦氏が講演
植物由来の抗酸化・解毒成分のエビデンスを紹介http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426830
----日経ヘルス サプリ&機能性食品 2006/06/24「サプリ&機能性食品2006」の専門フォーラムで名古屋大学大学院生命農学研究科教授の大澤俊彦氏が「植物素材による解毒と抗酸化」と題した講演を行った。重金属の排出を促すような解毒ルートだけでなく、肝臓のグルタチオンSトランスフェラーゼ(GST)などの解毒酵素による“毒を消す”解毒ルートが体内で重要だと述べた。
この解毒酵素を強く誘導するポリフェノールの配糖体などの植物性成分として、「ゴマ由来のセサミノール配糖体」、「ウコン由来のクルクミン」、「アブラナ科野菜抽出物」、「パパイヤ、アボガド、かんきつ類、リンゴなどの果実」などによるGST活性化データを示した。
同じカロリーで「肉や乳製品中心の食事」から、「野菜・果物中心の食事」へと食事内容を変えた場合に、尿中に排出される遺伝子酸化分解物8-OHdGが1/3に減った例を示した。
老化、生活習慣病、炎症などを防ぐために、活性酸素やフリーラジカルを消去する体内のレドックス系を維持することが重要。
抗酸化物質、抗酸化ビタミンなどを、複数摂取してレドックス系を維持することが重要で、そのためには、解毒・抗酸化ともに、野菜や果実などの植物性成分が注目されるようだ。【臨床講座】中高年女性を診る・連載第11回「女性に多い“健康オタク”」
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/series/tanaka/200606/500721.html
日経メディカル オンライン・連載 2006/06/19特に、みのもんた氏がゲスト医師と健康法を伝授するお昼の番組は人気があり、女性に多い“健康オタク”への影響力が大きい。
コレステロール値による食事療法は女性には不向き
この4月に出版されたこの番組本にも紹介されている「コレステロールの多い食材を健康食に変える食べ方」で、「最近の研究で、卵を1日1~2個食べるとコレステロール値の上昇が抑えられ、動脈硬化、高脂血症、脂肪肝の予防になる。」と書かれている。
一方で、臨床の現場行われている「卵はコレステロールを多く含むので、値が高めの人は、朝、卵を1個食べたら、その後は卵や内臓を含む食品(ししゃも、うに、しらすなど)などのコレステロールの多い食品は極力避けるように」という食事指導は、本当に有益なのだろうか?コレステロール値を目安にした食事療法は、女性には不向きであるという。その理由は、女性の高コレステロール血症の多くが、急激なエストロゲンの低下によるものだから。
食事指導で心筋梗塞の発症が増える?
高コレステロール血症について約5000人を6年間追跡調査した結果、調査開始時に食事指導をしていた群が、しなかった群に比べて2.87倍も心筋梗塞の発症が増えたことがあった.。その理由は、バターをやめてマーガリンにすることを勧めたため、リノール酸やトランス酸摂取が増えたことや、強力なコレステロール制限により卵を食べた人は魚を食べなかったことという事実があり、このような事例から、コレステロール制限の食事指導は、EPAやDHAの豊富な魚の摂取を減らすことになるため、逆効果になる可能性があることを示している。中高年女性には“健康オタク”が多いことを念頭に置き、血液検査などで大きな変化が見られた時は、特に食材の過剰や行き過ぎた制限について、問診すると共に、バランスのよい食生活の重要性を繰り返し伝える必要があるが、そのためには、医師自身も正しい食生活の知識をもっていなければならないと結んでいる。
ビールに前立腺がん予防効果 1日17本飲めば 米大学
米オレゴン州立大学の研究チームは、ビール原料のホップに含まれる化学物質「キサントフモール」に、前立腺がんの予防効果があるとの研究成果を発表した。
ただ、研究チームのエミリー・ホー助教授によれば、実験で効果があったのと同量のキサントフモールを摂取するには、1日17本以上のビールを飲む必要があり、ビールによる摂取は非現実的だが、キサントフモールを抽出した錠剤や効果を強化したビールが開発される可能性はあるという。
2006/06/25専門展「サプリ&機能性食品2006」で国立健康・栄養研究所理事長の渡邊昌氏が基調講演
「サプリは薬ではない、頼りすぎず、食事に注意を/進むファイトケミカル研究、症状と成分の相関も徐々に解明」http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426829
----日経ヘルス サプリ&機能性食品 2006/06/24「サプリ&機能性食品2006」で国立健康・栄養研究所理事長の渡邊昌氏が基調講演食を行い、「食」についての正しい知識をもつことの重要性を訴えた。食物が体に与える影響として、ファイトケミカル(ポリフェノールやカロチノイドなど、生活習慣病やガン予防に役立つとされている植物性成分)についての最新情報を紹介。
野菜や果物に含まれるカロチンやイソフラボン、含硫化合物など約50種類の成分の摂取量と、肥満、糖尿病、高血圧、うつ病といった病気との相関を調べた。相関例:
・カロチン類は、とるほど肥満のリスクを高めるが、カテキンは減らす方に働く。
・ケルセチンは、うつ病のリスクを減らす傾向がある。
・ファイトケミカルといえど全てて“効く”わけではなく、どんな疾病に対してもリスク軽減に有効だったのは、イソフラボンだけだったという。一人一人がこうした情報を知って、食生活に生かして、「100歳まで元気で生きて、コロっといく」ことを目指そうと呼びかけた。
BSE:ヤコブ病、潜伏期間50年超も--ロンドン大研究
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060624dde041100019000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/06/24英ロンドン大などのチームが、24日付の英医学誌ランセットに発表したところによれば、牛海綿状脳症(BSE)の牛を食べて発病するとされる変異型クロイツフェルト・ヤコブ病は、感染から発病までの潜伏期間が、長い人で50年を超す可能性があるという。
変異型ヤコブ病の患者に共通する遺伝的特徴があり、現在の変異型患者は潜伏期間が特に短い人である。牛から人へ種をこえた感染の影響を考えると、潜伏期間は個人の遺伝的特徴に左右されるため、50年よりさらに長い期間を経て患者が増える可能性があるという。リスク調整しても癌生存率に大きな格差
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/200606/500759.html
日経メディカル オンライン・Report 2006/06/23肺癌5年生存率に43.5~18.3%と2倍の開き厚生労働省の研究班がこのほどまとめた調査結果によれば、全国がん(成人病)センター協議会加盟施設における4種類の癌(胃癌、肺癌、乳癌、結腸癌)の5年生存率によると、3つの要素によってリスク調整を行っても、その成績に大きな格差があることが分かったという。
【調査対象施設一覧】(30施設)
国立病院機構北海道がんセンター/青森県立中央病院/岩手県立中央病院/宮城県立がんセンター/山形県立がん・生活習慣病センター/栃木県立がんセンター/茨城県立中央病院/群馬県立がんセンター/埼玉県立がんセンター/国立がんセンター東病院/千葉県がんセンター/神奈川県立がんセンター/国立がんセンター中央病院/癌研究会有明病院/東京都立駒込病院/新潟県立がんセンター新潟病院/静岡県立静岡がんセンター/愛知県がんセンター/国立病院機構名古屋医療センター/福井県立病院/滋賀県立成人病センター/大阪府立成人病センター/国立病院機構大阪医療センター/兵庫県立成人病センター/国立病院機構呉医療センター/国立病院機構四国がんセンター/国立病院機構九州がんセンター/富山県立中央病院/山口県立総合医療センター/佐賀県立病院好生館コーヒーが肝硬変リスクを軽減
米国の非営利医療保険組織Kaiser Permanenteの研究グループが、米医学誌「Archives of Internal Medicine」6月12日号に発表したところによれば、コーヒーを飲むことで、飲酒による肝疾患を予防できる可能性があるという。
1978~1985年の検査時に肝疾患が無く、アルコール、茶、コーヒーの消費量に関する情報が得られた125,000人余りのデータを分析したところ、1杯/日 コーヒーを飲んでいた集団は、アルコールによる肝硬変の発症率が22%少なかったというものだが、研究を率いたKlatsky博士は、肝疾患は大量飲酒に起因する多数の問題の一つにすぎないので、あくまでも飲酒は控えるべきだと述べている。コクランレビューの日本語訳が閲覧可能に
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200606/500746.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/06/22診療ガイドラインのデータベース・Mindsのウェブサイト(http://minds.jcqhc.or.jp/)で、6月19日よりコクラン・レビューの抄録の日本語訳が見られるようになった。
医学文献のシステマティック・レビューを行う国際的な団体であるコクラン共同計画が作成しているコクラン・レビューは、質の高いシステマティック・レビューとして定評がある。このデータベースであるコクランライブラリーは年4回改訂されるが、今回掲載されたのは2005年第4 版の日本語訳。尚、閲覧にはユーザー登録(無料)が必要。▽ 財団法人日本医療機能評価機構の医療情報サービス・Minds
http://minds.jcqhc.or.jp/アレルギー反応引き金引く細胞、理研チーム突き止める
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060621ik01.htm
Yomiuri-Online・・ 医療と介護・ 医療ニュース 2006/06/21理化学研究所免疫・アレルギー科学総合研究センターの久保允人(まさと)氏らの研究グループが、21日発行の米科学誌「イミュニティ」6月号に発表したところによれば、アレルギー反応の引き金を引く役割を果たしている細胞の存在をマウスを使った実験で突き止めた。
その細胞とは、血液中に存在するものの、その機能がはっきりしなかった「記憶型T細胞」で、この記憶型T細胞は体内に入ってきた異物の刺激により、免疫グロブリンE(IgE)を作るよう指示を出す役目のたんぱく質(インターロイキン4)を産生し、アレルギー反応の引き金を引いているとしている。男性更年期外来が自由診療に向いているワケ
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/report/200606/500598.html
日経メディカル オンライン・Report 2006/06/06最近、新聞や雑誌でも頻繁に取り上げられる「男性更年期」は、大学病院でも男性更年期外来を開設する動きがあるなど、医療関係者の関心も高い。 1950年代後半から男性医学の研究に積極的に取り組んできた札幌医大名誉教授の熊本悦明氏へのインタービュー記事
男性更年期に見られる症状は、性機能低下だけではなく、うつ症状や不眠といった精神・神経症状や、ほてり、動悸、手足のしびれ、肩こりといった、自律神経系の乱れによる様々な身体症状が同時に見られることが多く、これらの症状は個人差が大きいため、じっくり患者の話を聞くことが診療方針決定のために欠かせないという。(筆者・同感)男性更年期は、人生の折り返し地点にある“車検”のようなものだから、患者には1日でも早くきちんと治療して、早めに自信を回復して欲しいと結んでいる。
2006/06/18
今回は、非常に興味ある話題が報じられています。
「ファイトケミカル:「第7の栄養素」 がん予防、アレルギー改善の力秘め」 という毎日新聞の 2006/06/15付けの記事です。
健康で長生きするためには、免疫力を高めて、がん予防を行うにも、やはり野菜・果物を沢山食べることは有効だったのですね。 このような情報は健康雑誌には頻繁に取り上げられているのですが、このように新聞の記事として発表されることは、大いに有効だと思います。
是非一読し、これからの食生活を改善して、病気をしない体に改造していっていただければ、このようなサイトを立ち上げた甲斐があるというものです。
知識があるだけでは、健康にはなりません。良いと思うことを先ず実行することから始まります。
[解説]がん対策基本法が成立
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060617ik01.htm
Yomiuri-Online・・ 医療と介護・ 医療ニュース 2006/06/17▽患者情報の共有推進 医療格差解消に期待
日本のどこでも、高度ながん治療を受けられる体制の実現を目指す「がん対策基本法」が16日に成立した。新法は、国が患者や家族、有識者の意見を聞いたうえで、がんに関する基本計画を策定するよう義務付けた。 「情報の収集提供体制の整備」も規定された。生存率など基本的なデータを集めるために、患者の氏名や生年月日とともに治療経過を一元的に記録する「がん登録」の推進を事実上、定めたものだ。
新法は、患者の心身の痛みを取り除く「緩和ケア」についても、「患者の状況に応じて早期から適切に行われるようにする」と定めている。
法律は出来たが、どれだけ実効性のある対策が実現されるのかは、行政や医療現場の取り組みにかかっている。▽医療現場も「構造改革」を 「肺」など欧米型がん急増
新法は、専門医の育成もうたうが、実力ある医師を短期間で増やすのは困難だ。効果的な研修制度を整えると同時に、現場の意識改革も求められる。ファイトケミカル:「第7の栄養素」 がん予防、アレルギー改善の力秘め
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060615ddm013100164000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/06/15野菜や果物に含まれる植物性化学物質「ファイトケミカル」は、最近の研究からがん予防やアレルギーの改善にも役立つことが確認されており、「第7の栄養素」と言われるている。 そのファイトケミカルのパワーと食生活への上手な取り入れ方についての解説記事。◇淡色野菜や果物に約1万種
従来、栄養素といえばタンパク質、炭水化物、脂質、ビタミン、ミネラルの五つを指したが、食物繊維に続く7番目の栄養素として「ファイトケミカル」が浮上している。
キャベツ、タマネギ、ダイコンなどの淡色野菜やバナナ、パイナップルなどの果物に多く含まれ、代表的なものはアントシアニン、カテキン、大豆イソフラボンなどで、約1万種類あるといわれ、病気そのものを予防したり改善する力が有ることが判ってきている。◇白血球を増やし活性化
白血球は、体内に侵入した異物やがん細胞、ウイルスなどを殺したり弱める働きがある。植物の中には、この白血球の動きを高める成分が含まれていることが判ってきた。
野菜としては、ニンニクやシソ、タマネギ、ショウガ、キャベツ、長ネギ、果物としては、リンゴ、キウイ、パイナップル、レモンなどが白血球数を増やす。
キャベツやナス、ダイコン、ホウレンソウなどの野菜は、白血球に含まれるTNF(腫瘍壊死因子)を増やし、その濃度は抗がん剤やインターフェロンよりも高くなることが判明した。
果物もバナナ、スイカ、パイナップル、ブドウなどが白血球を活性化する力がある。
要は、野菜・果物を沢山食べることで、白血球を活性化して「がん」は勿論、高脂血症や動脈硬化、糖尿病等の生活習慣病や肝臓病、アレルギー疾患にも効果が期待できるということのようだ。
◇摂取に便利な常備菜を
ファイトケミカルを十分に摂るには、淡色野菜をゆでたり炒めたりして食べ易くし、摂取量を増やすことが大切。また量だけでなく食べる種類を増やすことも重要だ。
上記の記事にも紹介されている「ファイトケミカル」を、毎日確実に沢山摂るための秘訣が紹介されています。
果物は切っても保存しても栄養価値は意外と長持ち
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/426768
----日経ヘルス Topics 2006/06/12雑誌「農業と食品化学」(Journal of Agriculture and Food Chemistry )2006年6月14日号に発表された、カリフォルニア大学デービス校のアデル・カデール教授らの研究によれば、新鮮なパイナップル、マンゴ、カンタロープ(マスクメロンの一種)、スイカ、イチゴ、キウイを使った実験で、いずれの果物も、摂氏5度の冷蔵庫に9日間保存した場合、切ったり、袋に入れておいた場合でも、ビタミンCやその他の抗酸化作用のある物質は失われておらず、栄養価値に変化はなかったという。健やかに老いる:広がるアンチエイジング/下
カギは適度な運動 食事バランスよくhttp://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060612ddm013100051000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/06/11◇高齢者対象の筋トレ、医療費上昇率を抑制
「健康で長寿」のカギの一つが適度な運動だ。
筑波大の久野譜也助教授(スポーツ医学)らの研究グループによれば、高齢者約150人を対象に継続的なトレーニング(ウオーキングや、筋力トレーニングを2回/週、約1時間/日のペース)を続けてもらい、筋トレを 2回/週 続けたグループ(平均年齢65.2歳)は、腰の筋肉(大腰筋)量が平均で9.5%増加した。
その結果、年間医療費の上昇率において、トレーニングをしなかった村民(平均年齢68.4歳)は63%も上昇したが、トレーニングを続けたグループ(平均年齢65.2歳)の上昇率は、97年から2年間で17%だったという。◇動物性脂肪取り過ぎ、血管老化加速の恐れ
『人は血管とともに老いる』という言葉があり、健康長寿には、血管をしなやかに若く保つことが不可欠だが、食生活も重要。ある食品が良いと聞くとそれだけ食べ続けるなど、情報に踊らされている人が多いので、動物性脂肪を摂り過ぎないようにバランスよい食事を心がける必要がある。◇暮らしぶり変わり、揺らぐ長寿県・沖縄
「全国一の長寿県」の沖縄県の地位が揺らいでいる。02年発表の都道府県別の平均寿命の順位で男性は26位となり、全国平均からも下回った原因は、若い世代において料理の手間を嫌い、外食に頼り、油の使用量も増え、ゴーヤが嫌いな子どもが多くなった。またかつては農作業が良い運動になったが、都市化で、仕事で体を動かすことが減った。地域の人々が互いの健康を気遣う風習も薄れてしまったという。中高年もフィットネス
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/kaigo_news/20060611ik04.htm
Yomiuri-Online・・ 医療と介護・ 医療ニュース 2006/06/11かつて若者が主流だったフィットネスクラブの利用者は、最近は60歳以上の会員が増加しており中高年向けに変身中という話題。
「セントラルウェルネスクラブ東十条」(東京)でも、長く体を動かしていない熟年でも楽しめるような、体への負担が少ない「オリエンタル系」のプログラムを開発したとのこと。
介護予防や生活習慣病予防に取り組むフィットネスクラブも多くなっており、 「東急スポーツオアシス」(東京)では、介護予防プログラムを早稲田大学と共同開発した。初心者向けの「いきいき太極拳」と、椅子に座りながらの運動を中心にした「らくらく体操」の2種類で、介護予防に取り組む。
「コナミスポーツ&ライフ」(東京)でも、生活習慣病予防プログラム「シックスウィークス」を提供している。寄生虫を駆除してもアトピーは増えない
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200606/500716.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/06/16回虫、鞭虫、鉤虫といった腸内寄生虫の感染者が多い国ではアレルギー性疾患の有病率が低いことから、寄生虫感染とアレルギーは逆相関関係にあるといわれていたが、Lancet誌2006年5月13日号に報告されたエクアドルのPedro Vicente Maldonado病院のPhilip J Cooper氏らの研究によれば、エクアドルの小学生を対象に、駆虫を実施したうえでアトピーとアレルギーの有病率を調べたところ、実験開始前と差がみられないことが判ったという。アトピー:1歳までにネコ、ウサギ室内飼いでリスク増?--国立成育医療センター調査
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060611ddm041100035000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/06/11アレルギー性疾患の発症は、子どもが生まれて早い時期における家庭でのペット飼育と関係が有るとされているが、国立成育医療センター研究所の 松本健治・アレルギー研究室長らが、昨年1月 広島市内の小学校137校の2年生11,173人の保護者にアンケートを依頼し、1歳になるまでのペット飼育歴やアレルギーの有無などについて、9974人から回答を得た結果を分析したところ、1歳になるまでにネコやウサギを飼っていた家庭の子どもは、アトピー性皮膚炎になるリスクの高いことが分かったという。
松本健治・アレルギー研究室長によれば、「アレルギー性疾患の発症を促すのは、ペットの抜け毛で増殖するダニだけではなく、ペットの種類に関係する別の原因がありそうだ」とのこと。
2006/06/10ニンジン煮て美肌、ベータカロチン摂取が「生」の1.6倍
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060609ik09.htm
Yomiuri-Online・・ 医療と介護・ 医療ニュース 2006/06/09ニンジンは、ゆでて食べると、色素「ベータカロチン」の体内への吸収率において、生の場合に比べ摂取後6時間で平均1.4倍、8時間で1.6倍に高まることが、伊藤園中央研究所などの研究で判った。
にんじんに含まれるベータカロチンは、紫外線から肌を守る効果があるとされており、ゆでたニンジンを基に作った野菜果汁を飲んで、肌の状態を調べた別の実験では、摂取後8週間で シミの面積が減少すしたという。ゆでたニンジンのβカロチンの高吸収率を確認
/ ジュースのほうが生よりも効率良く摂取できると発表http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426765
----日経ヘルス サプリ&機能性食品 2006/06/09伊藤園中央研究所は、ニンジンに含まれるβカロチンは、ゆでたほうが生のまま摂取するよりも体内に吸収され易いことを確認し、5月27日に京都府立大学で開催された第444回日本農芸化学学会関西支部例会で発表した。
βカロチンは、ニンジンやブロッコリーなどの緑黄色野菜に多く含まれる色素で、消化吸収されたあと、ビタミンAに変わる。また、抗酸化作用があり、動脈硬化などを防ぐ効果もあるとされている。▼伊藤園 > [ニュースリリース]2006.5.19 >
βカロテンは生よりもゆでたにんじんからの方が体内への吸収率が高いことを確認乳酸菌で歯周病を予防するタブレット、ライオンとフレンテが共同開発
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426766
----日経ヘルス サプリ&機能性食品 2006/06/09ライオンとフレンテ・インターナショナルは、乳酸菌LS1を配合したタブレット「DENTシステマ・オーラルヘルスタブレット」を7月3日に発売する。
乳酸菌株LS1は、歯周病菌を殺菌する効果を持ち、他の乳酸菌と違って、同時に酸を作り過ぎないため、虫歯の原因菌も増やし難いという。白インゲン:加熱しても、ダイエット効果なし
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060609ddm013100135000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/06/09TVの健康情報番組で紹介されて注目を浴びた白インゲン豆のダイエット法において、加熱不足で下痢などを起こした人が多く出たが、十分に加熱しても、ダイエット効果はあるのかを探った記事。インゲン豆を生か加熱不足のまま食べれば、下痢などを起こすことは年配の人なら常識で、若い世代に受け継がれていないことが問題であるが、豆を水に浸したあと、軟らかくなるまで十分に煮れば、レクチンの毒性は無くなる。
消化酵素を阻害するたんぱく質(インヒビター)は、1Kgのインゲン豆に2g前後しか含まれていないので、インゲン豆の粉を、ごはんに振りかける位で減量効果を期待することは無理と、食品問題に詳しい高橋久仁子・群馬大学教授は指摘する。
肥満の男女12人でファセオラミンの効果を試験した浅野・浅野生活習慣病予防研究所長(内科認定医)によっても、副作用の心配はないが、2ヶ月間の服用で平均体重が81Kgから78Kgに減るというもので、劇的なものではないという。睡眠不足が体重増加と関連
米ケースウエスタンリザーブ大学(オハイオ州)医学部助教授Sanjay Patel博士らが、サンディエゴで開催された米国胸部学会(ATS)国際会議で報告したところによれば、夜きちんと睡眠をとることで、十分な休息が得られるばかりでなく、加齢に伴う体重増加を抑えることができるらしいという。 睡眠時間が5時間の女性は、7時間の女性に比べ、約15Kg以上の大幅な体重増加の認められた率が32%高く、肥満になった率は15%高かった。また、睡眠時間が6時間の女性は、 7時間睡眠の女性よりも大幅な体重増加が12%多く、肥満は6%多かったという。ビタミンとストレスの関係を知ることが出来る、中身の濃いページです。小山さんの自己紹介文:
様々な「ストレス」に対し、「ビタミン」の力を用いて対抗し、克服していく方法をご紹介しています。
ビタミンの事を書いてある色々なHPはあるとは思いますが、このサイトではよりわかりやすく説明しているつもりです。
2006/06/03黒豆由来のアントシアニンが脂肪蓄積を抑える 高脂肪食ラット1カ月の試験で、脂肪増加を抑制
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426736
----日経ヘルス サプリ&機能性食品 2006/06/02フジッコと静岡県立大学の共同研究で、このほど開催された第60回日本・栄養食糧学会大会で報告されたところによれば、黒豆の皮に含まれる黒いポリフェノール、アントシアニンにお腹まわりの脂肪の蓄積を抑える効果があることが、ラットを使った実験で判ったという。
実験では、肝臓に蓄積される脂肪の量にも大きな差が出た、また血液中のコレステロール値も下がり、中性脂肪値も減る傾向になったという。ホヤにアルツハイマー予防効果
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060601ik0d.htm
Yomiuri-Online・・ 医療と介護・ 医療ニュース 2006/06/01海に生息するホヤなどに含まれる脂質「プラズマローゲン」がアルツハイマー病を防ぐ効果を持つことことを、東北大大学院農学研究科の宮沢陽夫教授(食品学)らが、ラットを使った動物実験で突き止めた。来年にも錠剤の健康食品として発売されるという。
アルツハイマー病患者の脳内ではプラズマローゲンが通常より3割程度減少していることがわかっていた。宮沢教授らは、細胞の培養実験の結果、プラズマローゲンに神経細胞死を防ぐ効果があることを突き止めたもの。メタボリックシンドローム:減らせ!内臓脂肪 予備軍回避の食事は
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/06/20060601ddm013100055000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/06/01肥満がもとで、高脂血症や糖尿病、高血圧症など複数の生活習慣病になる危険性を抱え、動脈硬化を引き起こしやすい状態がメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)だが、5月の厚生労働省が発表では40~74歳で男性の1/2、女性は1/5がその該当者と予備軍だった。
メタボリックシンドローム予防のための食事は? ヒントとなるレシピや食生活の工夫をまとめている。◇低カロリーでも工夫で満足感--注目食材はアーモンド、酢
メタボリックシンドロームの原因は「内臓脂肪」。予備軍の人は、内臓脂肪を減らす、低カロリーの食事を心掛けることが必要。
◇プロの栄養士が作った糖尿病治療食の宅配食を利用
調理の工夫:
▽肉や魚は少量にして野菜でボリュームを出す
▽皿数を多くして見た目を豪華にする
▽だしをきちんと取った季節の汁物を加える
▽新鮮な食材を使う--など
▽調味料のなかで唯一制限なく使っていいのが酢。
注目の食材がアーモンド
悪玉コレステロールを減らすオレイン酸が豊富で、抗酸化物質のビタミンEや食物繊維も多く含む。
仕事と家庭を両立させている女性は健康
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/426720
----日経ヘルス Topics 2006/05/31英国のユニバーシティ・カレッジ・ロンドンの「疫学・公衆衛生学科」のアンネ・マクマン博士らが、1646年生まれの女性1171人について、20歳代の時から10年ごとに、健康・仕事・結婚・育児について情報を集め、54歳になった時点に健康状態をまとめた結果、母親、妻、勤務をこなした女性が、他の道を歩んだ女性よりも、もっとも健康だったという調査結果を、雑誌「疫学と地域医療」(Journal of Epidemiology and Community Health)2006年6月号に発表した。“メタボ”の診断基準、女性腹囲は80cm程度が妥当か
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200605/500554.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/05/305月25日~27日に開催された第49回日本糖尿病学会年次学術集会で、札幌医大第二内科教授の島本和明氏が発表したところによれば、メタボリックシンドロームの診断基準の中で、女性の腹囲の基準値を現行よりも引き下げた方がよいのではないかとの見解が示された。札幌医大に入院中の患者(男性235人、女性185人)を対象に、CTによる内臓脂肪面積と腹囲を測り、ROC曲線を描き、腹囲のカットオフ値を算出した結果より、高血圧や糖尿病、動脈硬化性疾患の合併を考慮すると、男性で83.7cm(内臓脂肪面積97.5cm2に相当)、女性で80.0cm(内臓脂肪面積74.6cm2)が導かれたことより、昨年発表されたわが国の診断基準「腹囲は男性85cm以上、女性90cm以上」の見直しの検討の必要性を示すもの。
たばこ肺疾患、チェックシートで早期診断
肺に炎症が起き、酸素と二酸化炭素を交換する肺胞が壊れたり、気管支が細くなったりする病気で、咳や痰、息切れなどが主な症状で、静かに進行し、やがては呼吸不全になる、慢性閉塞性肺疾患(COPD)は、たばこでリスクが高まる。
この「COPD」の早期診断チェックシートを相澤久道・久留米大教授(呼吸器・神経内科)らが作った。
このチェックシートは世界家庭医学会が認定したものを、相澤教授らが訳したもので、対象は40歳以上の喫煙者(過去喫煙者も含む)で、年齢やたばこの本数、体重を身長の2乗で割った肥満度指数(BMI)など8項目38点満点となり、17点以上だとCOPDの可能性が高い。昭和30年代生まれのバリバリのおっさんである「toku」さんが、友人の死をきっかけに禁煙。 それから一念発起。禁煙とダイエットに挑戦し、このような情報サイトを立ち上げたとのことで、禁煙に挑戦したいと思っている方、必見のサイトです。自己紹介文:
禁煙宣言では、管理人の禁煙体験や禁煙とたばこに関する様々な情報をご紹介しております。
禁煙に悩む皆様!一緒に禁煙宣言いたしましょう! どうぞよろしくお願いいたします!(^^)
ストレスの多い職種でも血圧は異常にはならない
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/426695
----日経ヘルス Topics 2006/05/25医師、教師、警察官、消防士、パイロットなどは、片時も気を許せないのでストレスの多い職業だが、この「ストレスの多い職業の人は高血圧になる」ということは実際には非常に少なく、高血圧の原因となっているのは、毎日働く「職場の人間関係にある」とする論文を、米コーネル大学医学部教授のサミュエル・マン博士らが、過去50年間に発表された、仕事のストレスと血圧との関連を調べた48件の研究を再検討した結果として、雑誌「現代の高血圧」(Current Hypertension Reviews)2006年5月号に発表した。やっぱり地中海食はいい! 地中海食を徹底するとアルツハイマー病が少なくなる
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/medwave/a027/426647
----日経ヘルス サプリ&機能性食品 2006/05/12米コロンビア大学助教授のニコラス・スカーミーズ博士らの研究グループが、「神経科学紀要」(Annals of Neurology)2006年4月号に発表したところによれば、ニューヨークのマンハッタンに住む2258人を対象に、健康状態と食事の内容を調べ、認知症にかかっていないかを確認した結果、オリーブ油、ナッツなどからオレイン酸などの不飽和脂肪酸を多く摂り、肉や乳製品は控え目で飽和脂肪酸を少なく摂り、豆、穀類、魚、そして果実や野菜をたっぷり食べるという地中海スタイルの食事を徹底している人は、心臓病に加え、アルツハイマー病の発症も少ないことが判ったという。
2006/05/27歩行テストで寿命を予測
米フロリダ大学加齢研究所のMarcoPahor氏らが、米国医師会誌「JAMA」5月3日号に発表したところによれば、高齢者の歩行能力が、将来の健康状態および寿命まで予測する重要な指標となることが判ったという。
今回の研究は米国の複数機関によるもので、健康な70~79歳の約3,000人に対し、6カ月毎に歩行テストを実施し、5年未満の平均を定期的に算定した結果、歩行速度上位25%のGrに比べ、最下位のGrでは死亡リスクが3倍高かったほか、心疾患、運動制限および障害を生じるリスクも高かったという。
約400mを短時間で歩き切ることができる人は、長生きする確率が高く、心血管疾患および身体障害を来す確率が大幅に低いという。「和食はヘルシー」実証 東北大、ネズミで実験
東北大の宮澤陽夫教授(食品学)らがネズミを使った実験で、健康に良いのは洋食より日本食という通説を科学的に立証した。
日米の国民栄養調査を基に、最近の両国の代表的な1週間のメニュー各21食分(日本食はさしみや雑炊、オムライスなどで、米国食はハンバーガーやフライドチキンなど)を選び、凍結乾燥し粉末にして3週間食べさせた。
ネズミの肝臓で計1万種類の遺伝子の働きを比べたところ、日本食のネズミではコレステロールや脂肪を分解する複数の遺伝子が、米国食の1.5倍以上に活性化し、肝臓内にたまったコレステロール量は、米国食の方が1割以上多かった。チーズが内臓脂肪の蓄積を抑える
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/426690
----日経ヘルス Topics 2006/05/24雪印によると、国産のゴーダチーズを配合した餌をラットに与え、チーズ以外の餌を食べたラットと比較した研究によれば、血液中の中性脂肪と総コレステロールの濃度が、チーズ以外の餌を食べたラットに比べて低下し、腸管の間に蓄積する内臓脂肪の量も減少したという。
内臓脂肪型肥満で問題になる血液中の、脂肪細胞が分泌するたんぱく質「アディポネクチン」の濃度もチーズを食べていると保たれることがわかった。▼雪印 > Press Release > 【2006.05.12】 チーズが内臓脂肪の蓄積を抑えることを検証しました
見直そう、お酢の力 メタボリックシンドロームにも効果
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/05/20060524ddm010100125000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/05/24お酢は身近な食材だが、意外にその効用が知られていない。肉を軟らかくしたり魚の臭みを減らすなど、隠し味としての調味料にもなるが、最近は高血圧や高血糖、高脂血症などの予防・改善、疲労回復など、さまざまな効果が科学的に分かってきた。■高血圧
高血圧の成人が15ml、30mlのリンゴ酢を含むドリンクを毎日、8週間飲んだところ、酢を飲まないGrに比べ、血圧が下がった。
■糖尿病
食事時に酢を一緒に取ると食後の血糖値の上昇が抑えられるという。
■内臓脂肪症候群
メタボリックシンドロームの予防・改善策として、運動はもちろんだが、食べ過ぎを戒め、減塩に努めることが大事。
できるだけ野菜を多く取り、油の少ないさっぱりした食事がよい。
ここで威力を発揮するのが酢で、塩やしょうゆの代役になり、食塩の摂取を減らせられる。
■カルシウム補給
シジミやアサリのスープに穀物酢を少々加えると、貝からミネラルが溶け出し、カルシウムの摂取量は数倍に増える。
■防腐効果も
細菌の増殖を抑える作用のある酢は食中毒の防止にも役立つ。抗加齢ドック:あなたの老化度、調べます 東海大学医学部付属東京病院に来月開業
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/05/20060523ddm013100129000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/05/23高齢社会を迎え、年齢を重ねても病気や衰えを極力少なくして元気に暮らすための「抗加齢医学(アンチエイジング)」が注目されているなか、大学病院としては全国初に、東海大学医学部は血管の老化度などを検査し、生活習慣の改善や食事などについてアドバイスする「抗加齢ドック」を医学部付属東京病院(東京都渋谷区、桑平一郎院長)に6月20日開業するという。内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム) 診断基準は妥当?
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060522ik05.htm
Yomiuri-Online・・ 医療と介護・ 医療ニュース 2006/05/22おなかに脂肪がたまる内臓脂肪症候群(メタボリック・シンドローム)の中高年が、予備軍も合わせ約2000万人に及ぶと厚生労働省が発表し、心筋梗塞や脳卒中を招くとされ、厚労省が対策に乗り出したが、診断基準の妥当性や治療のあり方を巡る課題も浮上しているという話題について。▼中高年男性の半数“危険水域” 定まらない医学的評価
内臓脂肪症候群が注目されるのは、
第一に、内臓脂肪が糖尿病、高血圧、高脂血症を引き起こすことが判ってきたためだ。
第二に、肥満と高血圧、高血糖、高脂血症の4項目の組合せが、心臓病や脳卒中と密接に関わっている点。▼ウエストサイズ、米は102cm超
ウエストサイズは、米国では男性で102cm超となっているのに対し、日本人男性は85cm以上と、かなり厳しく設定されている反面、女性の基準が、日本人は90cm以上と米国人(88cm超)より緩やかなのと対照的なことに対して、大櫛陽一・東海大医学部教授は下記の指摘をしている。〈1〉調査対象が数百人で少なすぎる
▼製薬業界高い関心 薬の過剰使用懸念
〈2〉危険因子を一つ持つ場合の内臓脂肪面積を算出しており、複数の危険因子を併せ持つこの症候群の診断基準データとして不適切
血圧、血糖、脂質値が高くなるこの症候群では、降圧薬、血糖降下薬、高脂血症治療薬などを同時に使うこともできることや、通り一遍の生活習慣指導では、血圧などは容易には下がらないため、安易に薬を出す場合もあるため、薬の過剰使用につながる懸念もある。▼減らない脂肪
いくら薬を飲んでも、肝心の内臓脂肪は減らない。おなか回りが気になる人は、軽い運動から始めてみてはどうだろうか。▼心臓病、脳卒中…医療費抑制へ予防に力点 厚労省
厚労省が内臓脂肪症候群の対策に力を入れる背景は、膨張すると予測される医療費の抑制だ。老人保健法を改正し、2008年度から40歳以上の健診を大幅に見直されて、新しい健診は、同症候群の発見を重視する方向だ。
予備軍の段階での保健指導を強化し、薬が必要になる前に、受診者の生活習慣を変えるよう促すが、保健指導だけで生活習慣を変えるのは簡単ではない。同症候群は国際的には診断基準が異なるなど、医学的な評価が定まっていない面もあり、保健指導により心筋梗塞などを予防できるかどうかのデータも少なく、今後の検証が求められる。老人の骨折防止に、男性でも女性ホルモンが必要
http://medwave2.nikkeibp.co.jp/wcs/leaf?CID=onair/nh/nh_news/426678
----日経ヘルス Topics 2006/05/22ボストン大学などの研究者らが、研究開始時に平均年齢が71歳だった男性老人793人を、約20年間追跡調査した 結果、男性のお年寄りで女性ホルモンが少ない人は、骨折し易いことがわかった、という。知りたい:内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム) ぽっこりおなか、ご用心
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/05/20060522dde001100005000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/05/22厚生労働省は、初の全国調査で、40~74歳の男性の1/2、女性の1・5が「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」とその予備軍だったと発表した。
メタボリックシンドロームは、内臓に脂肪がたまり、高血圧や高血糖、高脂血症などの症状が一度に複数出ることを指す、新しい病気の概念だ。「おなかがぽっこり出ていて、健康診断の数値のいくつかが正常値より少し高め」という人が該当する。その国内の診断基準は、日本内科学会など8学会が昨年4月に定めた診断基準は、下記のようになる。▼メタボリックシンドローム診断基準:
①に加え、②が二つ以上該当する場合で、②が1つが該当する場合は予備軍①ウェスト 男性 85cm以上、女性 90cm以上
②血圧 最高血圧 130以上 又は 最低血圧 85以上
血糖値 空腹時に 110mg/dl 以上
脂質 中性脂肪 150mg/dl 以上、又は HDLコレステロール 40mg/dl 未満がん細胞が免疫系の攻撃をかわす仕組みを解明
「Nature」オンライン版5月10日号に掲載されたSchering-Plough Research Institute(カリフォルニア州)のMartin Oft博士およびRobert Kastelein氏らによる研究によれば、がん細胞が免疫システムから逃れる鍵となる機序が明らかにされたという。
免疫細胞の攻撃を妨げるような環境を作るのは、インターロイキン-23(IL-23)と呼ばれる物質だという。
今回の研究では、IL-12またはIL-23のいずれかを欠損したマウスで癌誘発を試みた結果、IL-23をもたないマウスでは腫瘍が誘発されなかった。正常なマウスには予測された比率で癌が発生し、IL-12欠損マウスには予測より高い比率で癌が発生した。この結果は、以前は癌の元凶と考えられていたIL-12が、実はIL-23と相殺して癌を防いでいる可能性を示すものであるという。グレープフルーツジュースに含まれる薬物相互作用をもたらす原因物質を特定
グレープフルーツジュースには、薬剤が血中に取り込まれる効率を上げるため、用量および効果が増大し、時に危険な副作用が生じることがあるが、米ノースカロライナ大学(UCN)チャペルヒル校総合臨床研究センターのPaul Watkins博士らが、この原因となる物質が特定し、医学誌「American Journal of Clinical Nutrition」5月号に発表した。かつてはグレープフルーツの苦味成分であるフラボノイド類がこの薬物相互作用の原因であると考えられていたが、無調整のグレープフルーツジュース、フラノクマリン類(furanocoumarins)と呼ばれる物質を除去したグレープフルーツジュース、オレンジジュースを比較した結果、フラノクマリンを除去すると、フラボノイド類を全て残していても薬物相互作用が生じなかったという。
▼原文
:Researchers Discover Why Grapefruit Juice Interacts With DrugsMRSAに効く新抗生物質を発見
http://www.yomiuri.co.jp/iryou/news/iryou_news/20060518ik0a.htm
Yomiuri-Online・・ 医療と介護・ 医療ニュース 2006/05/18米製薬大手メルクの研究チームが、18日付の英科学誌ネイチャーに発表したところによれば、院内感染の原因となる細菌の中でも最も恐れられているメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)やバンコマイシン耐性腸球菌(VRE)などを殺す強力な抗生物質を発見したという。
MRSAに感染したマウスで試され、効果が確認でき、副作用もなく、VRE、肺炎球菌などに対しても強い殺菌作用を示した。 「プラテシマイシン」と名づけられた。
2006/05/14食品安全委:大豆イソフラボンは30ミリグラム--食事外摂取の上限値決定
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/05/20060512ddm041100029000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/05/12食品安全委員会(寺田雅昭委員長)は、食事以外に特定保健用食品として「大豆イソフラボン」を摂取する場合、上限値を 30mg/日 とすることを11日に正式に決めた。妊婦と15歳未満の子どもは、胎児や生殖機能などへの影響が懸念されるため、食事以外の摂取は推奨できないとした。イタリアでは、食事を含めた上限摂取量を 70~75mg/日を目安としており、日本人については国民健康栄養調査から平均的な摂取量を 16~22mg/日 と推計。上乗せ摂取が 30mg/日 以下ならば、1日の上限値を下回ると結論づけた。
豆ダイエット被害の原因はレクチンか
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200605/500398.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/05/10番組紹介の白インゲンダイエット被害は数百件に、TBSがホームページで告知・謝罪問題のダイエット法は、5月6日放送の番組「ぴーかんバディ」で紹介した「白いんげん豆ダイエット法」。番組を見て実践した人が、激しい嘔吐や下痢などの食中毒症状を訴えていたもの。
ダイエットに効果があるとされる成分はシロインゲンマメに含まれるファセオラミンと呼ばれる物質。 詳しい原因はいまだ不明だが、生豆に含まれる「レクチン」と呼ばれる蛋白質などの成分が加熱不十分な状態で残り、これが胃腸の粘膜に炎症を起こし、嘔吐や下痢の症状を引き起こした可能性が高いという。▼TBS>番組「ぴーかんバディ」>「白いんげん豆ダイエットへのご注意」
メラトニンの催眠効果は昼間に飲んでこそ効く
ボストンにある「ブリガム女性病院」(Brigham and Womens's Hospital )のチャールズ・ツァイスラー博士らが、雑誌「睡眠」(Sleep )2006年5月1日号に発表したところによれば、メラトニンの催眠効果は、昼間に飲ませた場合に有効であることがわかったという。内臓脂肪症候群、40歳超男性の半数危険 脳梗塞の原因
厚生労働省が国民健康・栄養調査の一環として’04年11月、無作為に選んだ20歳以上の男性1549人、女性2383人を対象に身体計測や血液検査などを実施した調査結果を発表した。
その結果によれば、心筋梗塞や脳卒中など生活習慣病の引き金となる「メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)」の疑いが強いか、その予備軍となる人が40歳を過ぎると急増し、40~74歳の男性の約半数に上るという。メタボリック症候群の判定は、内臓脂肪の蓄積を示す目安としてウエストが男性で85cm以上、女性で90cm以上を必須条件として、更に血中脂質、血圧、血糖の2項目以上で基準値を超えると「疑いの強い人(有病者)」、1項目で基準値を超える人を「予備群」としている。
コレステロールや中性脂肪、納豆が効果的 佐賀県有田町住民を調査
国立循環器病センターの北風政史・臨床研究開発部長らと、佐賀県有田町などが共同で住民を対象に実施した調査結果によれば、血中のコレステロールや中性脂肪が多い人には納豆が効果的なことが判った。血圧、脂質、血糖、肥満のいずれかの指標が高い47~81歳の男女52人に約1カ月間、朝食に30gの納豆を日常的に食べてもらった結果、高コレステロール群では平均7.7%、高中性脂肪群では平均12.9%、血中濃度が低下した。
学校でジュース販売禁止へ 子供の肥満防止に豪の州政府
豪州では10代の子供の3人に1人がジュース 2缶/日 以上飲んでおり、20~25%が肥満状態のため、 オーストラリア南東部のビクトリア州政府は、公立の小・中・高校にある売店や自販機でのジュースの販売を今年中に禁止するという。前立腺癌を予測するツール
医学誌「Journal of theNational Cancer Institute」4月18日号によれば、米テキサス大学保健科学センター泌尿器科教授のIan M. Thompson博士らが、前立腺特異抗原(PSA)の検査結果より正確に前立腺癌の発症リスクが予測できるという「リスク計算ツール」を開発したという。このツールは、PSA値のほか、年齢、人種、家族歴、過去の生検所見、直腸指診(DRE)所見からリスクを評価するもので、オンラインで利用できる。
▼前立腺癌リスク計算ツール(英文) (※日本人の場合は、人種の項目で「Others」を選択)
:http://www.compass.fhcrc.org/edrnnci/bin/calculator/main.asp生活習慣病と予防
http://www.oyappy.com/index.html
ミツカ ユウスケさんが運営するボランティア的な生活習慣病の解説ページ≪自己紹介文≫
★このホームページにきてくれた方に生活習慣病の怖さなどをレポートや体験をまとめ、
対策などをみて予防などに取り込んでくれれば幸いです。という、自称 40歳?のユウスケさんが運営する生活習慣病を解説し、関連サイトの紹介をしているボランティア的なページです。
2006/04/23緑茶・コーヒーに糖尿病予防効果 全国1万7千人調査
40~65歳の日本人男女で、糖尿病やがん、心臓病になっていなかった17,413人を調べた文部科学省の研究費による大規模調査の結果、大阪大の磯博康教授(公衆衛生学)らが、18日付の米国内科学会の専門誌に発表したところによれば、 緑茶を6杯/日以上飲む人は、1杯/週未満の人に比べて糖尿病の発症リスクが33%少なく、コーヒーを3杯/日以上飲む人も、1杯/週未満の人に比べ42%少ないという。
コーヒーの糖尿病予防効果は欧米などの研究で指摘されていたが、今回、緑茶の効果も明らかになった。朝鮮ニンジンが乳ガン患者に好影響
雑誌「米疫学ジャ-ナル」(American Journal of Epidemioloy )の2006年4月1日号に掲載されたジンセン(朝鮮ニンジン)と乳ガンとの関係を調べた研究報告によれば、1455人の乳ガン患者のデータを分析したところ、いずれの患者も、通常のガン治療(術、化学療法、放射線)を受けており、サプリメントのジンセンをなんらかの形で使っており、その割合は、以前よりジンセンを飲んでいた人が27%、診断後ジンセンを使用した人は63%だった。その後の5年間の経過を調べると、診断前からジンセンを使用していた人では再発やガン死の割合が30%低いという。癒やし効果を確認できた森林10カ所 林野庁が公表
林野庁は18日、森林が心身を癒やす効果が科学的な実験で確認できたという全国の10カ所を公表した。
森林浴の「癒やし効果」には、血圧や脈拍数が下がることなどがあり、6/10カ所は森林全域で効果が期待できる「森林セラピー基地」として、長野県の上松町、飯山市、信濃町と、山形県小国町、山口市、宮崎県日之影町を認定した。
4/10カ所は、森林の中を通る歩道に癒やし効果が確認できたため、「セラピーロード」として、岩手県岩泉町、長野県の南箕輪村と佐久市、高知県津野町を認定した。米ぬかに血圧、脂質、血糖値下げる成分
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200604/500226.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/04/17東北大学農学研究科食品機能健康科学講座のArdiansyah氏らが、J. Agricultural and Food Chemistry誌電子版に2006年1月27日に報告したところによれば、米ぬかには多様な抗酸化物質が含まれており、米ぬか由来の成分を添加した飼料により、脳卒中易発症高血圧自然発症ラット(SHRSP)の血圧を下げることに初めて成功した。血圧だけでなく、血中脂質量、血糖値も下がったほか、酸化ストレスの減少も見られたという。朝食:実力、再認識を!!
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/04/20060417ddm013100098000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/04/17◇日中活動のエネルギー源--抜くと知力減退朝食は血糖値や体温を上げて活動能力を高めると共に、体を太りにくくする働きを持つ。
◇しっかり、バランス良く--ご飯、卵、野菜も
朝食は、脳の働きとも密接に関係している。1日3食を「しっかり(朝)つないで(昼)グルメする(夜)」と説明する。
◇増え続ける欠食率--20~30代で顕著
但し、朝の「しっかり」は量ではなく質で、午前中の活動を支えるブドウ糖の供給源の炭水化物や卵、チーズといったたんぱく質などだ。ビタミンやミネラル類も必要。
英語の朝食(breakfast)には、「断食(fast)を破る(break)」という意味がある。朝食を抜くと食事回数が減り、その分、1回の食事で摂取するカロリーが増え、急激な血糖値の上昇を招き、肥満や糖尿病など生活習慣病の原因にもなる。
受動喫煙で糖尿病リスクが増大
米アラバマ大学医学部助教授でバーミンガム退役軍人局医療センター研究員のThomas Houston博士らが、英医師会誌「British Medical Journal」の4月8日号に発表したところによれば、米国人男女4,500人を対象に15年の追跡研究を行った結果、受動喫煙が糖尿病リスクを増大させる可能性もあることが示された。1日1箱以上の喫煙でEDリスクは4割増
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/int/200604/500185.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/04/12オーストラリアのシドニー西南地域ヘルスサービスのChris Millett氏らが、Tobacco Control誌2006年4月号に報告したところによれば、平均年齢37歳のオーストラリア人男性約8000人を対象とした大規模調査の結果、喫煙本数が1日20本を超える男性の勃起不全(ED)リスクは非喫煙者の1.39倍になるという。日本たばこ(JT)の2005年の調査によると、日本人男性の喫煙率は45.8%、うち「毎日吸う」と回答した人の平均喫煙本数は22.3本/日であり、他国に比べ潜在的なED患者が多いことを示唆するという。
▼論文の原題:「Smoking and erectile dysfunction: findings from a representative sample of Australian men」
2006/04/12喫煙者の心筋梗塞は3倍 厚労省研究班の調査
磯博康・大阪大教授(公衆衛生学)らの厚生労働省の研究班(主任研究者=津金昌一郎・国立がんセンター予防研究部長)が纏めた4万人規模の11年間の追跡調査によれば、喫煙者は吸わない人に比べて、男性で3.6倍、女性で2.9倍ほど心筋梗塞(こうそく)になり易いという。
禁煙すると2年以内に病気のリスクが下がっており、禁煙の効果は大きいという。コエンザイムQ10:安全性評価先送り
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/04/20060407ddm041040170000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/04/04老化防止に効果があるとされる健康食品の「コエンザイムQ10」について、政府の食品安全委員会(寺田雅昭委員長)は、データ不足などを理由に具体的な議論を見送っていたが、安全性評価を求めている厚生労働省に質問状を出し、回答を待って再検討することを決めた。日本、また長寿国世界一
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/ext/200604/500149.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/04/07世界保健機関(WHO)が、06年版の「世界保健報告」を発表した。その報告によると04年の平均寿命が世界で一番長いのは日本・モナコ・サンマリノの82歳で、日本は「長寿世界一」の座を維持した。
男女別で、日本女性が86歳で最長寿。 男性は日本、アイスランド、サンマリノが79歳で最長寿国。マグネシウムでメタボリックシンドロームのリスク低下
米医学誌「Circulation」3月28日号に掲載された、米国人約4,600人を対象として1985年に開始された研究報告によると、糖尿病や冠動脈疾患につながるメタボリックシンドロームの罹患率低下に、マグネシウムの豊富な食品が役立つことが判明した。
今回の研究の特色は、開始時点で20歳代という若年者を主に対象としている点で、マグネシウム摂取量の多い人は、その後の15年間のメタボリックシンドローム発症リスクが31%低くなることより、若い人も健康的な食生活に関心をもつことが必要のようだ。ビタミンCが老化を抑制
http://medical.nikkeibp.co.jp/leaf/mem/pub/hotnews/ext/200604/500091.html
日経メディカル オンライン・Hot News 2006/04/04東京医科歯科大や東京都老人総合研究所が、米科学アカデミー紀要(電子版)に4日発表したところによれば、ビタミンCに、生物の老化の進行を抑える可能性があることを確認したという。ビタミンCが加齢に関係することを科学的に証明したのは初めてだと発表。ビタミンC:老化防ぐ? 不足のマウス、老い4倍加速--東京医歯大など研究チーム
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/04/20060404ddm041100092000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/04/04東京医科歯科大と東京都老人総合研究所などの研究チームが、4日付の米科学アカデミー紀要の電子版に発表したところによれば、ビタミンCが不足したマウスは通常のマウスに比べ、4倍以上老化が速く進むという。アガリクス:あるのか?抗がん効果 副作用の疑い例も
http://www.mainichi-msn.co.jp/kurashi/kenko/archive/news/2006/04/20060403ddm013100071000c.html
毎日新聞・ 暮らし ・ 健康 2006/04/03厚生労働省は、2月にキリンウェルフーズ社が発売する「アガリクス」製品のうち1商品が発がんを促進したとの動物実験結果を発表し、発売元のキリンウェルフーズ社は回収に踏み切った。この話題について・・・・。
◆「顆粒」から発見、発がん促進作用
≪参考≫
問題の製品は、アガリクスを乾燥させて粉末化し、顆粒状にした「キリン細胞壁破砕アガリクス顆粒」。国立医薬品食品研究所が実験を担当し、発がん物質を投与したラットに「顆粒」を食べさせたところ、食べさせなかったラットに比べ、がんになる割合が高くなった。他の2社の製品でも同じ実験をしたが、異常は出なかった。
◆安全性検証には高額費用が必要調査は、流通している3社の3製品を抽出して実施しただけで、アガリクス製品に発がん促進作用があるのか、「顆粒」だけなのかは不明のまま。
◆副作用の疑い例も
医師グループのキャンサーネット・ジャパンが、各種の健康食品について医学論文を総ざらいし、「抗がんサプリメントの効果と副作用徹底検証!」(三省堂)という本にまとめたが、アガリクスについて効果を示した論文はなかった。
大阪府立成人病センターの佐々木洋・消化器外科部長らが、'05年の日本肝臓学会で発表したところによれば、肝臓がん患者に対しての再発予防効果も副作用も無かったという。
副作用の疑い例として、国立がんセンターの医師らが01年の日本癌治療学会にて、アガリクスを食べて劇症肝炎を起こした乳がん患者など3人のケースを発表している。
国立健康・栄養研究所は、ホームページ(http://www.nih.go.jp/eiken/)の「健康食品安全情報」で、アガリクスに対し「ヒトでの有効性と安全性について信頼できる調査結果が見当たらない」との見解を示している。
▼アガリクス(カワリハラタケ)を含む3製品の安全性について(厚生労働省 報道発表資料)
▼国立健康・栄養研究所の健康食品安全情報 での「アガリクスについて」メロドラマやトークショーは高齢者の脳を鈍らせる
米ニューヨーク市立大学ブルックリンカレッジ行動科学助教授のJoshua Fogel博士が、「Southern Medical Journal」3月号に発表したところによると、昼間、メロドラマやトークショーをよく見る高齢女性は認知障害を生じやすいという。
高齢者が頭を使わないようなテレビの見方をすると、認知力の低下につながることが窺える。間接喫煙の子どもは病原菌に感染しやすい
イスラエルのベングリオン大学のデービッド・グリーンバーグ博士(小児科学)らが、雑誌「臨床感染病」の2006年4月1日号に発表したところによれば、5歳以下の子ども200人を対象にした調査結果において、間接喫煙をしている子どもは、病原菌に感染し易いとことがわかったという。ビタミンC不足で老化促進 都の研究員ら解明
東京都老人総合研究所の石神昭人・主任研究員と東京医科歯科大大学院の下門顕太郎教授らの研究グループがマウスを使った実験で、ビタミンCが不足すると老化が進みやすくなることを明らかにし、米科学アカデミー紀要(電子版)に4日発表した。
2006/04/02玄米や全粒粉は心臓を守り、糖尿病や肥満にもなりにくくする
米臨床栄養学雑誌(Am. J. Clin. Nutr.)に報告された米国の研究によれば、玄米や、全粒粉のパンにパスタらを主食にしていれば、心臓病にも糖尿病にもなり難いという。
食物繊維、ビタミンやミネラルも豊富な未精製の穀物を食卓にもっと取り入れた方がよさそうだ。ダークチョコレート10g分のカカオを摂り続けると、心血管死とあらゆる原因による死亡リスクが半減する
オランダ国立公衆衛生環境研究所のBrian Buijsse氏らが、Archives of Internal Medicine誌2006年2月27日号に発表したところによれば、15年にわたり高齢者のカカオを含む製品の習慣的な摂取と、血圧と心血管死の関係を調べた結果、カカオ製品の摂取が血圧を下げ、心血管死と、あらゆる原因による死のリスクを半減させることが判った。血圧、心血管死、あらゆる原因による死とカカオ摂取が逆相関関係にあることを示した疫学的な研究はこれが初めてだという。▼論文の原題:「Cocoa Intake, Blood Pressure, and Cardiovascular Mortality」
MRSAの市中感染が増えている! 外来患者から分離した黄色ブドウ球菌は72%が耐性化――米研究で明らかに
米Beacon ClinicのMark D. King氏らがAnnals of Internal Medicine誌2006年3月7日号に報告したところによれば、米国ジョージア州アトランタで外来を訪れた黄色ブドウ球菌(S. aureus)による皮膚・軟部組織感染患者を対象に、市中感染の状況を調べたところ、感染部位から分離された黄色ブドウ球菌の、実に72%がMRSAであり、その87%が市中感染型のMRSAクローンであることが判明した。
この報告は、これまでは主に病院内で感染していたメチシリン耐性黄色ブドウ球菌(MRSA)が、医療とは無縁の人々にもMRSA感染が広がっていることを物語っている。5剤以上に耐性のある結核が世界的に増加中、CDCとWHOが発表
米国疾病対策センター(CDC)と世界保健機関(WHO)が、3月24日、発表したところによれば、2000年~2004年にかけて、6大陸の25の結核研究所施設を調べたところ、発生した結核の1/50件の割合で、結核の治療に使われる通常の治療薬(第1選択の抗生物質群)だけでなく、その他の治療薬(第2選択の抗生物質群)に対しても、耐性のある結核「XDR (extensively drug-resistant)TB」が、世界中で増加傾向にあるという。▼CDCのMMWR誌に掲載された報告の原題:「Emergence of Mycobacterium tuberculosis with Extensive Resistance to Second-Line Drugs --- Worldwide, 2000--2004」
カシス果汁の多糖類に強い抗腫瘍効果、メルシャンが確認
メルシャン商品開発研究所が日本農芸化学会大会で3月26日に発表したところによれば、カシスに含まれる多糖類(CAPS:カシスポリサッカライド)に強い抗腫瘍作用があることを動物実験で確認したという。▼メルシャンのプレスリリース(2006/3/22)> 「カシス」に強い「抗腫瘍効果」が存在することを確認」
一人でのランニングは効果半減?
米プリンストン大学(ニュージャージー州)心理学教授Elizabeth Gould氏が、医学誌「Nature Neuroscience」オンライン版3月12日号に発表したところによれば、ラットを用いた最新の研究では、社会的に孤立した状態で走ることにはあまり利点がなく、むしろ健康によくないという。
ただし、この結果が一人暮らしの人間にとっても意味をもつとはいい難く、社会的交流が健康的なものであり、ストレスの悪影響を緩和することがわかるとGould氏は述べている。運動の効果は高齢者ほど著しい--細胞レベルで解明
ワシントン大学のスージー・ウー博士らが「米心臓病学会誌」で発表したところによれば、エクササイズを行う前と後で、細胞レベルでの酸素の効率を調べた結果、その変化の割合は、お年寄りの方が、若い人よりはるかに大きく、お年寄りの方が運動により機能が向上することがわかったという。リンゴ成分、中性脂肪を抑制 アサヒビールが商品化検討
アサヒビールが25日から京都女子大学(京都市)などで開かれた日本農芸化学会大会で発表したところによれば、リンゴの抽出成分「リンゴポリフェノール」が、血液中の中性脂肪が増えるのを抑える効果があることを、人への臨床試験で初めて確認した。これまでは動物実験でしか確認されていなかった。▼アサヒビール > 研究レポート
・リンゴのポリフェノールによる筋力アップ効果と脂肪蓄積抑制効果を動物実験で確認
・リンゴ・ポリフェノールの脂肪蓄積抑制作用を動物実験で確認ビタミンDとカルシウムでお年寄りの転倒防止
米内科学雑誌」2006年2月27日号に掲載された研究によれば、サプリメントで年寄りの転倒を防ぐことはできないかを調べた3年間の研究で、ビタミンDとカルシウムを飲んだ女性では、転倒率が46%も少なかったという。胃がん手術後の生存期間はピロリ菌陽性者の方が3.4年も長い
独Ludwig Maximilians University of MunichのGeorgios Meimarakis氏らが、Lancet Oncology誌2006年3月号に発表したところによれば、胃がん手術を受けた患者の予後を追跡調査した結果、ピロリ菌陽性者の方が陰性者よりも、全生存期間で61.9カ月対19.2カ月と、大幅に生存期間が長いという常識的な予想を裏切る結果が報告された。赤ワインに歯周病予防効果の可能性
Laval大学(ケベック)のFatiah Chandad博士らが、オーランドで開催された米国歯科研究学会(AADR)の年次集会で報告したところによれば、マウス細胞を使った実験から、赤ワインに含まれる抗酸化物質ポリフェノールには、フリーラジカル生成の鍵となる蛋白を阻害し、フリーラジカル生成を遅らせる働きがあることが明らかになった。
このことから、赤ワインの抗酸化作用は、歯周病に対しても有用な武器となると考えられるというもの。
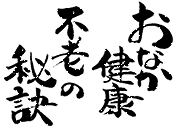
「とし坊 の読んで得する健康情報 バックナンバー」
57, 56, 55, 54, 53, 52, 51,
50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41,
40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31,
30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21,

「徐福」長寿伝説 Information ニブロンって? 読売新聞「医療ルネッサンス」のページへ 新着・更新 Home