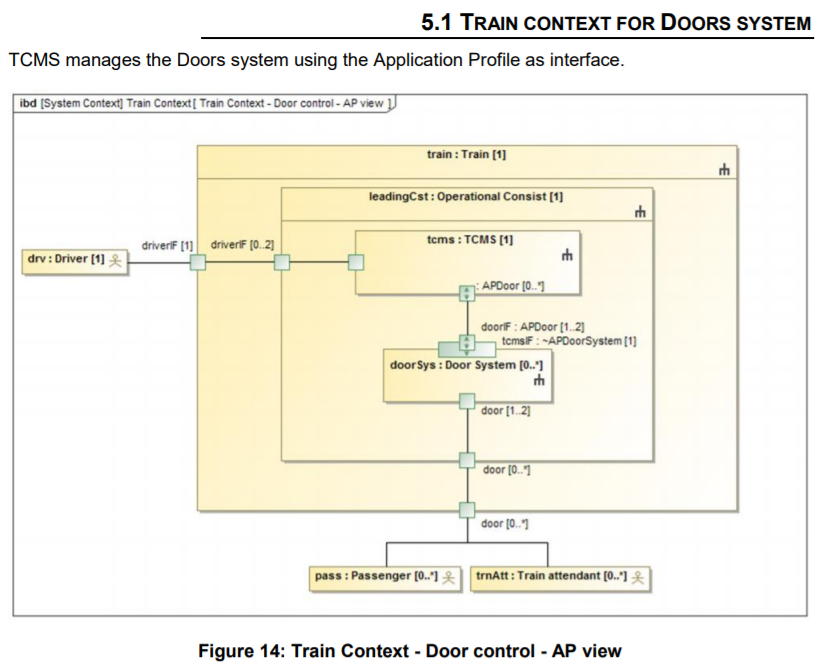次に進む
1つ戻る
- 1.パンタグラフ
- 2.車両の外寸
- 3.鉄道車両の軸重と材質
- 4.車体外側の標示
- 5.ETCS(列車運行システム)
- 6.オーバーラップと信号の変化
- 7.連結装置
- 8.脱出窓
- 9.レールの接地/非接地
- 10.ATCの速度照査パターンの引き方
- 11.電磁吸着ブレーキ
- 12.分岐器の鎖錠
- 13.デジタルモデリング・UICリーフレット
- 14.軌道構造
- 15.軌道構造・人材育成
- 16.接着・溶接認証
- 17.「速度信号」「予告信号」が必要な理由
- 18.速度超過検出
- 19.異相区分切替セクション
- 20.波動伝搬速度[架線の張力]
- 21.サードレールの活用
- 22.車両材料による火災対策
- 23.鉄道運転免許
- 24.プラットホームの高さ・ドア高さとドアの大きさ
- 25.車両のドア構造
- 26.5G対応無線式信号(FRMCS)
- 27.高速鉄道線のトンネルの断面積
- 28.列車の分類
- 29.民営化された国鉄路線(工事中)
- 30.行路表の配布者
- 31.オープンアクセスは強制開放
- 32.客室の座席配置
- 33.列車位置把握(工事中)
- 34.高速鉄道の在来線線路走行
- 35.メンテナンス
- 36.車両の堅牢さ
- .まとめてみました
目次
デジタルモデリング
digital modeling
日本のJRさん各社も加盟する世界鉄道連合(UIC)では、「RailSystemModel」「OntoRail」という2つの鉄道システムをデジタルデータ化していくためのプロジェクトを進行中です(2021年)。
これらのプロジェクトの中では鉄道のデータを図面をデジタルデータにすることによって、設計の合理化や、通信分野等の鉄道を取り巻く周辺技術分野との親和性が高まり、シナジー効果が出すことの研究が行われております。この技術は、単に便利になるだけの話ではなく、オンラインでリアルタイムでの車両や装置の保守データの収集を行うような、IoT技術の応用技術、「FRMCS」(Future Railway Mobile Communication System)のような無線通信を用いた次世代の信号システム(ETCSの後継)の実現のためにも有効なことから、積極的に技術開発が進められています。
それ相応のコストはかかりますが、鉄道の仕事のディジタル化が急速に進むと思われますので、鉄道技術分野全体にとって、大きな変革が訪れるものと思います。
土木分野の標準化
UICの「RailSystemModel」等は、全技術分野にわたる話ですが、これまで各国の法令や気候風土の違いから国際標準化の面では手つかずでした。しかし、そんな土木分野についても着々と標準化が進んでいます。
国際土木委員会(ISO 16739:2013)によるBIM
これは、BMIとも呼ばれています。道路、港湾等の国の公共工事で作成するデジタルデータを他社・役所と交換する際の3Dデータのフォーマットの標準(BIM)が国際的に検討されているものです。このモデルに、鉄道の高架橋等の3Dモデルの標準が含まれており、欧州の鉄道事業者さんが参画してフォーラム標準化が進められています。
一方日本国内では、鉄道線路データ等は大手会社さんがGISを自社のために開発し作成しており、電力や土木分野の「設備台帳」のように重宝されておられますが、どちらかというと社内向けのデータ共有システムのようです。
自社以外との3Dデータの交換については、現状の日本では道路との交差部分のようなクリティカルな部分では作成されている程度です(コストがかかりますから)。
しかし、今後、BIMにおいて「標準モデル」が国際標準化されてしまうと、海外プロジェクトのような国際入札を行う場合には、国際標準に整合させて作成することが必要となり、コスト面で懸念があります。デジタル化が進んでいる会社さんにおかれてはフォーマットの置き換え等の手間が、これから取り組む会社さんでは、動向注視が必要ではないかと思います。
すでに、BIMデータの提供を売りにされている例が見られます。こちら(シーメンスさん「台湾の鉄道信号の近代化案件」について(2021/6/2公開)にリンクを貼らせていただきます。
またJR東日本さんの土木部門についてもリンクにてご紹介させていただきます。
UICリーフレット(UIC IRS)の発行の活発化
世界鉄道連合規格
世界鉄道連合(UIC)も、鉄道分野の規格「UIC IRS」(UIC リーフレット)を作成・発行しています。
これには長年の歴史があり、750件ほど発行されています(UICリーフレットカタログに飛びます)。欧州の鉄道技術基準TSIからも多くのUICリーフレットが引用されていますし、UICリーフレットをEN規格化したものも含めると多く引用されています。
以下に紹介する「UICレール」もこの一つです。
UICリーフレットは鉄道事業者の視点から作られる規格ですから、メーカーの立場から作成される国際規格(ISO、IEC規格)とはまた違ったテーマでの規格なのですが、2018年からIRS(International Railway Solutions)という呼び名となり、運転間隔(ヘディング)等、鉄道事業者の関心が高い事項や、従来は一つに決めることが出来ないために標準化が難しかった、土木分野の規格、それに高速鉄道線に特化したUIC IRSも続々と発行されております。
鉄道事業者さんは発注元としてメーカーに強い影響力がありますので、高速鉄道関係の内容の規格ではともするとISO/IECを上回る強い影響が生じる可能性があり、注視が必要になっています。
現状では、欧州で歴史的に使われているUICタイプの連結器、ブレーキ、運転席デザインが多く使われていますが、その他のものは鉄道事業者さんの中だけで使われるものが多いです。運転士に視力、列車運行ダイヤ作成方法、等です。
このUICリーフレット(UIC IRS)は、TSIや国際規格からは多数引用されていますが、ブレーキ装置を除くと発注仕様書に書かれることはまずありませんでしたので、メーカーは特に気にしていませんでしたが、だいぶ状況が変わってきています。
またIRSは、UICのWGで審議されるものです。そのため、審議委員はメーカーではなくUICに加盟している鉄道事業者(日本ではJR各社さん)が対応するしかない状況ですので、JRさんの関心が薄いテーマについては、気づいたときにはIRSになっている可能性もあります。
【最近発行のUIC IRS(UICリーフレット)】
- IRS No.60662 高速鉄道-高速鉄道線のメンテナンス(2019年3月)
- IRS No.60673 実行-高速鉄道線の設計(2019年3月)
- IRS No.70779 鉄道トンネルの安全(2021年1月)
- IRS No.60681 高速鉄道線の信号と通信設備の設計(2021年11月)
- IRS No.60682 高速鉄道線の架線設備の設計(2022年6月)
- IRS No.60680 高速鉄道線の設計標準(2022年5月)
- IRS No.70719-1 バラスト軌道(2022年8月)
これらには例えば、高速鉄道線(200km/h以上の営業運行線)の予算計画や、図面の作成手順のようなことが書かれています。
国際規格であるIEC・ISOと、UIC IRSの違いとしては、国際規格では、同じことを実現するためにいくつもの異なる方式を併記するカタログのような形は極力避ける(=標準を決めることにならないため)のですが、UIC IRSでは積極的にさまざまな方式を紹介する形になっている点が大きな違いです。
カタログのような列記方式であれば、標準の座をめぐって各国の利害衝突・・・ということが起きにくいため、多数決にめっぽう弱い日本や中国には向いている形式です。上で紹介しているUIC IRSについても中国国鉄さんが主査又は共同主査を務めるケースが多く(※)、中国の標準的な概念を多数盛り込んでいます。最近発行されたIRS No.60682(高速鉄道線の架線設備の設計)の場合は、中国国鉄さんとスペイン国鉄さんの委員のお二人が共同主査をつとめ、JRさんらが各国の委員が審議に参加しています。
※そもそも中国規格TB10621-2014に基づくIRS作成提案ですので、提案国の中国が主査を務めるのは当然ですし、日本と中国とは携わる人数も、予算も、標準化人材に対する社内評価も違います。
なおIRS No60681「高速鉄道線の信号・通信設備の設計」については、日本の新幹線の信号システムである「ディジタルATC」も名前だけは書かれています。日本のJRさんは当初は規格審議WGに参加していなかったはずですが、意見は出していたようです。
また、UIC leafretに基づく認証も行われています。認証の種類や認証された機関はここ(UICホームページ)から検索できます。
日本では「UICレール」くらいしかなじみがないUIC規格ですが、ユニットブレーキ構造(UIC 541-4)やブレーキの試験を行う装置の認証が、やはりUICによって認証されているエキスパートによって行われており、欧州の鉄道運行事業者からこのUICリーフレットに対する認証が要求されることがあります。
UIC558(ジャンパー連結器)は欧州の技術基準TSIからも引用されていますので、これら、長らくUICタイプ、として使われてきたものについては広汎に利用されています。
鉄道事業者から要求されるものでは、他には溶接についてドイツ規格(DIN)に基づく認証が要求されることもあり、認められるための条件(どこの認証機関でなければだめ、等)欧州独特の運用が行われていると聞いております。
UIC IRSに基づく認証も利用されるようになっていますが、高速鉄道線に特化しているUIC IRSについてはそのような認証は無いようです(2022年時点)。
鉄道運行に関するこれまで規格化が進んでいない分野の規格化が進んでいるため、今後もし運行関係のIRSにも認証が広がると影響が大きいです。欧州域外での適用状況の情報を集めたいと思っております。
次世代の製品開発のためのモデリング
欧州規格EN 15380(鉄道車両システムの分類)では、鉄道(特に車両)に用いる部品について、使用される部位や部品の種類、部品同士の親子関係(この階層分けを、levelと呼びます)から、部品を特定するための部品の命名規則を規格化しています。
この規格は、電子図面等、使われる範囲が広いので知っておいて損はありません。RQMS(製品品質):ISO DIS 22163:2022のような鉄道技術と関係の薄いものからも参照されています。
- EN15380-1鉄道車両用の指定制度− 一般原則
- EN15380-2鉄道車両用の指定制度− 製品グループ
- EN15380-3鉄道車両用の指定制度− 設置場所
- EN15380-4鉄道車両用の分類システム− 機能グループ
- EN15380-5鉄道車両用の分類システム− システムブレークダウンストラクチャー
【備考】EN15380は以下のように、さまざまな観点から分類が行われます。
例えば、EN15380-2(製品グループ)では、車両部品の種類ごとにMPGとSPGをつなげた2桁の記号を定めております。これに部位情報をつけることで、どこに使うどのような部品を示すことができる記号を定めています。
- 部品種類別(MPG:Main Product Group)
- M・・・モニタリング&安全装置
- G・・・列車制御装置
- MPGの細分(SPG:Sub Product Group)
- MA・・・運転補助装置
- GC・・・ブレーキの制御
上記のEN15380のほかにも、各社さんが独自に定めた独自の部品番号体系も存在しております。ですが、各社間で取引される場合には、EN15380に基づく番号を使って流通させています。
一方日本では、同じ部品でも鉄道事業者さんごとに呼び名が異なりますので、メーカーさんでは同じ部品であっても、異なる名称で流通させる場合もよくあります。各社で共用できるような特定の決まりもない状態です。日本の場合にはそれが当たり前の状態で、システムも組まれていることから「特に支障はない」とのご意見が多いのですが、国際的に販売しようとする場合には逐一読み替える必要が生じます。
・・・以上のことだけなら、「共通番号がある」というだけなのですが、ところが欧州では、考えることが壮大です。鉄道の安全性を高めるために、この共通番号を基盤として、鉄道部品の機能のディジタル化を研究が進められています。
もともと欧州では、鉄道車両メーカーさんの組み立てに必要な図面は電子化されています(RAMSのトレーサビリティに関連してお示ししています)ので、部品メーカーさんのデジタル化対応も必然的に進んでおり、日本のメーカーさんのうち欧州の車両メーカーさんに納入している会社さんもやはりディジタル化が進んでいます。欧州では、これを基盤として、車両の安全にかかわる製品の開発段階から、その部品同士の物理的・機能的なつながり(プロファイル)を、コンピュータ上でモデリングすることが研究されています。
このようなデータを構築するための初期投資は膨大だと思いますが、一度できてしまうと、設計変更の際のさまざまな関連図面の修正の自動化や、オーバールッキング(見逃し、更新漏れ)が防げることから、次世代の製品開発の協力なツールとなると考えられます。
このような、産業を支える基盤づくりに取り組むにはコストや、将来展望が必要ですので、日本で同じことができるかというと厳しいのですが、何も、日本独自で同じようなことを行う必要もないため、システム更新時等にうまく取り入れられることが大切ではないかと思います。
日本の得意なモノづくりは、スケジュールギリギリまでお客さんの要望を極力反映していくカスタムメイドが強味ですから、こういう基盤システムがサプライチェーン内で共有されると有用なのではないかと思っています。