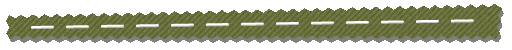
�F��Ƃ̗R��
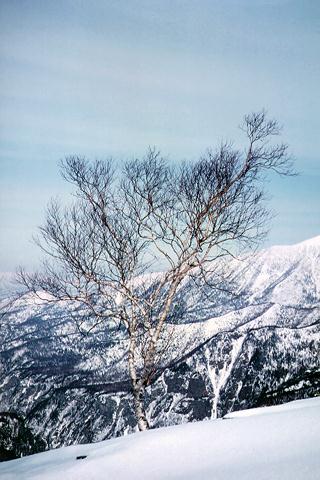
���̂��肢
�@��Ƃ̗R���A�ƌn�A�Ɩ䓙�ɂ��Ă̏��������������B����~�ς��邱�Ƃɂ��A���m���ȉ��������Ă邱�Ƃ��ł��܂��B���萔�����������܂����A�ǂ�����낵�������͂̂قǂ��肢�\���グ�܂��B �@�����āA�S���e�n������������������F�l�A���u�F��Ƃ̃z�[���y�[�W�v�́A�F�l���̂��͓Y�������������A�������o�邲�Ƃɓ��e�L���Ȃ��̂ƂȂ��Ă܂���܂����B���ꂷ�ׂĊF�l���̂������A�ƐS���犴�ӂ������Ă���܂��B �@�d������������������������ �@�c�u���Ƃ͑z���͂Ǝ��v�́w���挶�z�x�i���c�N�v�j�̒��̌��t�B���邽�߂ɂ́A���Ȃ���҂����łȂ��A�����g��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B��[���������Ă���̂ł����c�c�B �@���ԓI�E���_�I�E�o�ϓI�]�T���ł�����A�S���s�r�ɂł��������v���܂��B����܂ł̊ԁA���e�̕s���͂��������������B �@�܂��A�u��c���ǂ����Ƃ��A���[�c���ǂ����Ƃ������̂́A�K���Љ�̈������╨���B���f�����Ƃ��A���܂�炿���Ƃ������ӎ��́A���ʎv�z�̍����ƂȂ�B���݂��A�����Ė����𐳂����A�y���������邱�Ƃ���Ȃ̂ł����āA�ߋ��̖S����v������A�a���肷��悤�Ȃ̂͑匙�����v�i�w�e�r�`���E�l�����x���c�N�v�j�Ƃ������l���̕��������邱�Ƃ��A�t�L���Ă����܂��B �F��̋����i �y�F�䐩����́z �F�䐩�̗R�� �@���c�����́w�����ƌn�厫�T�i��j�x�́u�F��v�̍��ɂ́A�i�P�j�����̌F��i�Q�j�M�Z�̌F��i�R�j�L�O�̌F�䂪�������Ă��܂��B�F�䐩����ԑ������͒��쌧�łQ�T�R�ˁA��Ԗڂ���ʌ��̂Q�S�X�˂ŁA�O�Ԗڂɕ������̂P�S�T�˂ł�����A�قڐ����ƌn�厫�T�̋L�ڂ���Ă��邱�Ƃƕ������Ă��܂��B �@ �@�������A����łȂ�قǂƔ[�����Ă��܂����Ȃ�A�O���̌F�䐩�����ꂼ��ʌ̏ꏊ�ř�X�̐������������ƂɂȂ��Ă��܂��܂��B �@ �@�{���ɂ����Ȃ̂ł��傤���B �u�F�䐩���z�}�v�Ɓu�������̒m�s���v�Ƃ̕s�v�c�Ȉ�v �s�������F�䐩���z�ꗗ�i�Y�쐳���������j �i����Ƃ͕ʂɁA�S���̌F�䂳��̏Z���Ɠd�b�ԍ���}���قŒ����ς݂ł��B�������A�l���ی�@�ɒ�G���܂��̂ŁA���\�͍����T���܂��B�F�䐩�̕��z�́A�Y�쎁�����Ƃقڈ�v�j �F�䐩�W���n�� �F��Ƃ̉Ɩ� �@�F�䐩�̊F�l�A��Ƃ̉Ɩ�E���c���̒n������������ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ 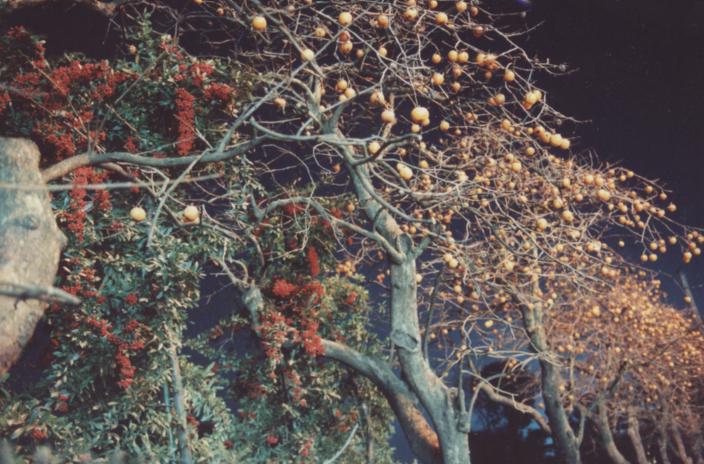 �S���̌F�䂳��E�F��Ƃ����n�� �@�C���^�[�l�b�g�̒��ɂ͂���Ȃɂ�������̌F�䂳���܂����B �@�n�������J������܂����B�c�c�u�l���ی�@�v���{�s����܂������A���̃y�[�W�̋L�ڂ͂��ׂāA�C���^�[�l�b�g(�o�ŕ����܂ށj�Ō��J����Ă�����Ɋ�Â��Ă���܂��B�f�ڂ�]�܂Ȃ����́A���A������������A�����ɍ폜�������܂��B �u�F��ꑰ�v�Ƃ��������{�ɂ��Ă̊��z �y�F�䐩�����̎�|����z �u�؉z�Ƃ̃z�[���y�[�W�v �@���[�c�����̎Q�l�ɂ����Ă��������܂����B �u�{��̃z�[���y�[�W�v �@�����̃����L���O�������ł��܂��B �@�F��͂P�V�W�X���тŁA�Q�O�W�O�ʂł����B �@ ���̕c���͂ǂ̓s���{���ɑ����� �@����s�ɂ��Z�܂��̓Y�쐳�������A�F�l�̕c���̕��z��L���i�u���ʕ��z�����v�̎萔���͈�̕c���R�O�O�~�A�u�s�����ʒ����v�萔���͈�̕c���T�O�O�~�j�Œ������Ă��������܂��B �@ �@���ʂƎs�����ʂ�����A���ꂼ��A�ꗗ�\�ƒn�}�����Ă��܂��B �@�u�Y�쎁�z�[���y�[�W�v�A�h���X http://www5a.biglobe.ne.jp/~myouji/welcome.htm �@�@�@�@�@�@�@�@�@  �y���������������z �S���e�n�ɂ��Z�܂��̌F��l ��ʌ����e�n�ɂ��Z�܂��̌F��l ���������e�n�ɂ��Z�܂��̌F��l �����ɂ����͂����������F��l�ւ̂��ւ� �F��p���l����̂��ւ� �N���}�O���̗{�B�ɐ������ꂽ �F��p������ �@���ւ����łȂ��A���d�b�܂ł��������܂����B�搶�̗D����������������܂��ɂ́A�������������������ł����B ��m�J�J�z�t�����̐}�i�F��p�������j �@���䌧�̏��R�ɌF�䐩�̂������A�Ȃ̎��Ƃ����锒�R�s�i���ߗ����j�ł͌Â�����l�`�ŋ��u�F�䑾�Y�v���������Ă��܂��B�ǂ����ĂȂ̂��낤���A�ƑO�X����^��Ɏv���Ă��܂����B �@�@�搶�ɂ����������������w�T�ԋ`�o�`���I�s�x�̑�Q�T���u�`�o�ƕ����v�ŁA�u���R�n�R���O�̋��͂��Ȃ���ƂĂ������ɉ��B�܂ł��ǂ蒅������̂ł͂Ȃ������v�A�Ɠǂ݁A�����������������̂��A�Ɩڂ��J�����v�������܂����B�@ �@���������A��������Y���Ƃ���ł����B�w�T�ԋ`�o�`���I�s�x�ɂ͖����ъG���f�ڂ���Ă��āA�u��m�J�J�z�t�����̐}�v�̑��ɂ��܂���R�u�F�䑾�Y���i�Ɓj��i���j���i�S�j�O���v�̐���p�H�����邱�Ƃ��ł��܂���B ��X�w�ҌF���l�i�j���[���[�N�ݏZ�j ���ѐM��l �u�]�˂̓s�s�s���v�������e�[�}�̂ЂƂƂ��ĂƂ肭��ł����鏬�ѐM��搶����A�]�˂̖����F�䗝���q���Ɋւ���������������܂����B �@�c�c�u�V�ۉ��v�̍ۂɌ�������c���g�p�������ꂽ����Ƃ��āA�����`�����N�Ԃ̑�̌F�䗝���q��̖��O�����́A�ꕔ�̌����҂ɒm���Ă��܂������A���̋Ɛтɂ��ẮA�܂������������i��ł��܂���ł����B �@�����ŌF�䗝���q�傪�֗^�������܂��܂Ȏd���̎j�����W�߂��Ƃ���A�ނ́A�V�ۉ��v����������N�Ԃɂ����Ă̍]�˂̓s�s�s���ɂ����āA�����قǏd�v�Ȗ������ʂ����Ă������Ƃ��킩���Ă��܂����B �@�ނ����[�_�[�ƂȂ��č��グ������g�D�̎��͂́A�]�˒���s���̌��Ђ�������������̂������ƍl���Ă��܂��B���̂悤�Ȕނ̋Ɛт́A������A�L���m����悤�ɂȂ�Ǝv���܂��v ���ѐM��l�������ꂽ�F�䗝���q��Ɋւ���_�� �w�]�˂̖��O���E�Ƌߑ㉻�x(�R��o�ŎЁA2002�N) ��V�́u�V�ۉ��v�ƍ]�˂̖���v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �F��}�ِ̊��i��ʌ����S���R���������j ���R���F��̕��i�i�u���̏t�v�B�e�O�D�h�ꎁ�@�f�ڒ����V����ʔŁj �F�䑾�Y����ِ̊��i���l�s���a�����@���j �F�䑾�Y����Ɋւ��鎑�� �����w�u��̗�v�L�� �@���ʂ̌Òn�}�i�Ă��t���^�C���j�Ɂu�F�䒬�v ��Ώ�i�������c��S�Y�c���j �@�F��z����v�d�����ł����B �Љ����܉E�q�� �@�ԕ�`�m�Љ����܉E�q��͔�������Ɣˎm�F��Ɓi�����ƉƐb�j�̐��܂�ł����B�Љ��ƂƂ����A�w���ƕ���x�ɑ��u�O�������v�A�`�o�ɏ]���l�X�̂Ȃ��ɌF�䑾�Y�ƂȂ��ŕЉ����Y�o�t�i��錧�����_�{�{�i�̎q���j�����܂��B �@�ԕ���Ƃ͊}�ԁi��錧�j����ڕ����ꂽ�̂ł����A�F��ƂƕЉ��ƂƂ̊Ԃɂ͌����̍�����̐[���������������̂ł��傤���B �g�c�����q�� �@�F��ƂƊւ��̂���ԕ�Q�m��������l���܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@  �y�}���ُ��z ���������y���ҁ��F��z�Ō������Ă݂������}���ق̑����ژ^ �F�{��w�}���فE�i���ɁE�א�ƌÕ����ژ^�E �@�F�{�̊W�u�Q�Q�O�ˎm���ցv�Ɂu�F��O�Y�E�q��a���͂��v������܂����B �@ �@�F�{���F�y�s�ɂ͌F�䐩���W�����Ă��܂��B�݂Ȃ���́A���̌F��O�Y�E�q�����̌�q������Ȃ̂ł��傤���B �u�F��ƕ����ɂ����v �@���{���}���ّ����w���{�j�w�N�ʘ_���W�x �@�����ٖ��@���V���}���� �@���݁@�@�@�@���ɂQ�|�Q �@�����ԍ��@�Q�P�O�E�O�S�^�U�T�m �@�����ԍ��@�P�S�P�O�S�P�P�S�W�O �@�F�䐩�W���n��̂ЂƂł���啪���������S���X�n�����̌F��ƂɊւ�镶���ł��B�����̎����͕����P�Q�N�A�k��B�s�̓c���q�q��������ꂽ���̂ŁA�҂ł���c�����͎�ꑺ�̌F��Ƃ̏o�g�Ƃ����B �@�@�������A�Y�t�u�F��ƕ����ژ^�v������ƁA���̕������c�����ے����v�g�̐����u�F��v�g�v�E�u�G��v�g�v�̓�ʂ�ɏ�����Ă��܂��B �u�F��ƕ����ɂ��āv���܂Ƃ߂�ꂽ�N�䐬�����́u�T���@�P�F��ƕ����̐����v�ɂ����āA�u�אڂ���Α��̏����G�䌣��Y����ꑺ�̑������Ƃ��Ă����v�i�w���������x�i�����ƕ����j�j�Ƃ���܂��̂ŁA�Ђ���Ƃ���ƁA���̎��̌F��Ƃ́A���Ƃ��Ƃ́u�F��v�ł͂Ȃ��u�G��v�������̂����m��܂���B �@�����F�䐩�𖼂̂��Ă��Ă��A�u�F��v�E�u�G��v�̓�̗��ꂪ����A�������u�G��v���͑啪���ƕ������ɑ����A�S���Q�P�Q���т̂����łR�R�����啪���A�����ĂQ�P�����������ɏW�����Ă��܂��B���̕��z�͋�B�n��ɂ�����u�F��v���̕��z�Ƃ��قڕ������Ă��܂��B �@���Q�l�܂łɁu�G��v���𖼂̂����l�Ɂu���͌��鎁�v�ꑰ�̒������������܂��B�퍑����A���̔��͌��鎁�́A���Ƃ����ɒB�ƉƐb�A�{�Ƃ͍��|���Ɛb�ƂȂ�܂����B�����������������z�O���������o�Ă��āA���̐}�߂Ă���ƂȂ��F�䐩�̕��z�Ƃ��d�Ȃ��Ă���悤�ȁB��R�A�ʔ����W�J�ɂȂ��Ă܂���܂����B �Q�l�����i�C���^�[�l�b�g�����j �w�啪���j���T�x�i�啪�̗��j�Ǝ��R�j �@���ڂT�O���ڎ��u��v���u���`���v�Ɂu�F��Z�Y���q��v�i���q�����j �@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�u�݁v���u�{�����v�Ɂu�F�䕺�q�сv�i���q����j�@ �w���c�ƉƐb�c�l���t�@�C���x���������튯�u�F�䑷�l�Y�v �u�G�䎁�v�Ɋ֘A����Q�l���� �@�C���^�[�l�b�g�����A�u�G�䎁�v�Ɋ֘A���鎖�����A�����ɓ�O�Y�t���܂��B �u���v�̂��c�� ���͌��鎁�ꑰ�E�Ɛb �o�l���Ǔ��Z�̑c �@�@�@ �i�剪�A���v�X�W�]��������̖k�A���v�X�̒��߁F�F���E���j �@�@ �@�@�@  �y���쌧�֘A�����z �@����e�n�̌F�䐩�̉ƁX�ɂ́A�F��闎��ƂƂ��ɓ���A�A�_�����Ƃ����`�����c���Ă��܂��B���K�s����k�シ��͐�ɓޗLj��Ɠc�삪����܂��B �@���̓�̉͐�́A���{�s�X���߂���������Ŕ���E�����H��ƍ������čҐ�ƂȂ�܂��B���̍Ґ�ɏ㍂�n�������Ƃ��鈲��ƁA���Ȓ��Ŗk���痬�ꉺ���Ă��������삪���ꍞ�݂܂��B �@�Ґ�͒���s�����Ő�Ȑ�ƍ������A�₪�ĐM�Z��Ɩ��������܂����A�s�v�c�Ȃ��Ƃɒ��쌧���̌F�䐩�̂���̕��z�́A�قƂ�ǂ����̍Ґ쐅�n�Ɛ�Ȑ쐅�n�̒��ɏW�����Ă��܂��i�Q�T�R���т̂����Q�Q�O���сj�c�F��P�������������ɂȂ��Ă��܂��B �������쐅�n�c���쑺�i�P�O�j�E�䍂���i�P�S�j�E���Ȓ��i�P�S�j ���ޗLj��E�c�쐅�n�c���K�s�i�Q�V�j�E���J�s�i�W�j ���Ґ쐅�n�c���{�s�i�Q�O�j�E�L�Ȓ��i�P�X�j�E�剪���i�P�Q�j�E����s�i�T�O�j ����Ȑ쐅�n�c��c�s�i�P�P�j�E�X���s�i�V�j�E�{��s�i�P�P�j�E�R�m�����i�V�j�E���瑺�i�P�O�j �@�Ґ�̎x���̂ЂƂc�삪�A���K�s�Ћu�F���k�サ�Ă��邱�Ƃ���A���K�F���{��Ƃ���F��ꑰ�ɉ��炩�̑厖�����N���������ʁA���ɂȂ��Đ쉈���ɓ���A���ꂼ��̒n�ɗ������тĂ������A�Ƃg�o�Ǘ��҂͐������܂��B �@����ł́A���̑厖���Ƃ͂Ȃ�ł��傤�B��͂�`���̒ʂ�A�V���P�S�N�i�P�T�S�T�j�U���P�S���F��闎�邾�����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B �F�䋽�i���K�s�Ћu�j �@���쌧�n���厫�T�i�p�쏑�X�j�E���{���j�n����n���쌧�i���}�Ёj����̔��� �M�Z���̌S�Ƌ��E���i�ޗǎ���E���������j �w�`��������x�E�w��ȋ��x����̔��� �k�F��z�K���i���쌧���K�s�Ћu�k�F��j �S���̐z�K�� �F����P�i���쌧���K�s�Ћu�k�F��j �F����Q�i���쌧���K�s�Ћu�k�F��j �F����R�i���쌧���K�s�Ћu�k�F��j �@�u�F��̗��j������v��ԉH�Ď����́A�F��闎���A���c�R�̒Nj���A�������𖼂̂����F��ꑰ�̗��������ł��܂��B �@�F�䐩�̎����Ƃ��āA����s�ɂ��Z�܂��̋��y�j�ƁA�F��P�����̋����[���������A�w���싽�y�j������@�֎��x��X�V���i�P�X�W�P�N�T���@�����łQ�O�O�Q�N�R���j �R��E�ٓ��W�� �i�T�O�O�~�j�Ɍf�ڂ���Ă��܂��B����ǂ��������B �@���싽�y�j������z�[���y�[�W�A�h���X http://www.janis.or.jp/users/kyodoshi/somokuji-2.htm �n���j�����G���f�[�^�x�[�X �F��P�������炢�����������������̏�����������Ə��������Ă݂܂����B �@�����ɏd�v�ȎQ�l���� �u�F��v�Ɋւ��ċL�q�̂���A���쌧���}���قɂ����ĉ{���ł��鑠���ژ^ �u�ҋ��@��Q�X���i�����W�N�P�Q���P�T���j�v�i�ҋ����y�j������j �@�F��y��Y���̌�\�c���F��ɉE�q���i�剪������F��Ƒ�Q�W��j�M�ʂ̍O����n�k�����u�k�^�Ӂv���f�ځB�y��Y���́u�k�^�Ӂv�����͒��쌧���}���ّ����̒��ɂ���܂��B ���q����̐��b�W�w���ΏW�x�ɏo�Ă���u�F��̒n���v�Ƃ� �@���싽�y�j������@�֎��w����x��P�P�R���u�M�Z�j�K�g�v�Ɍf�ڂ���Ă��镽�������̐M�Z�̑����P�P�ł�����ƁA�}���S�F�䋽�̒n���͐z�K���ЂƂȂ��Ă��܂��B�u�F��̒n���v�́u�z�K���Ёv�ŁA���̑�j�i�����ق�j�͋��h���ł����B���h�����Ĉ�̂ǂ�Ȉꑰ�������̂ł��傤���B �i�F��̉��c�F�����P�j ���i��C�@�i���Q�i�P�O�S�V�j�`�ۈ����N�i�P�P�Q�O�j �@�w�������x�i���쌧���}���ّ����j�ɑ剪������̂����ꌬ�̌F��Ɛ�c�́A��a���������e�i�E�B�L�y�f�B�A�t���[�S�Ȏ��T�Ō����ł��܂��j�̖����A�Ƃ���܂����B�����e�́w���ڕ����x�ɂ��Ɖi���Q�N�i�P�O�S�V�j�ɑO�M�Z��Ƃ��Ė����f�ڂ���A��a�E���h�E�W�H���̍��i����C���Ă��܂��B �@�C�����I�����O�C���i�̎q��͂��̂܂ܔC���ɓy�����ĉ�❁�Ƃ������ɂ̊��l�ƂȂ�A�×�����ݒn�Ɋ�Ղ����y�������Ƃ��������ŁA�s���炭���̍��i�i��j�̂��ƂŎ����������Ă��܂�������B���K�F�䏯���J���̂́A���̗��e�Ɖ��̌q���銯�l���������m��܂���B �i�F��̉��c�F�����Q�j �M�Z�������w����Ƃ͂ǂ�Ȑl �@���i��C�Ȃ�тɐM�Z�j�����ɏ�ɍڂ���w���̈ꑰ���A��ˌ@�̓y�؋Z�p����g���đ����F�䋽���J���C�����ĂȂ�Ȃ��̂ł��B �i�F��̉��c�F�����R�j �@�����N�W���̋��y�������̂f�� �w�����L�x�i�F����̋L�q���c���j������䎁�Ƃ͒N�H �u�剪�̌F����������ɕ�����Ă��āA���݂��ɉƌn�������Ƃ����b�������Ă��܂���v�ɂ��� �F��Ƃ̗R����T���⏕���Ƃ��āi�ێR�Ƃɂ��Ă̍l�@�j �F��Ƃ̗R����T���⏕���Ƃ��āi�����Ƃɂ��Ă̍l�@�j �w�b�M�����Ӂ@��P�ҏ㉺�x �i���r���c�^�ҁ@�o�Ŏҁ@�b�M�����Ӕ��s���@�P�W�X�U�N�o�Łj �w�������i�т߂������݁j�x �i���r���c�^�ҁ@�o�Ŏҁ@���r�A���Y�@�P�X�O�R�N�o�Łj �@������̏����ɂ��剪������F��Ƃ̐����n���Ɋւ���L�q������܂��B�]��f���i���̏]��j�̌F�䑝�G�����剪������̂����ꌬ�ʂ̌F�䐩�̂���Łw�������x�������Ă��������A�{�̑��݂��n�߂Ēm��܂����B �w�b�M�����Ӂx�E�w�������x�Ƃ����쌧���}���قɏ����i�ݏo�s�j�B�n�}�t���r���c�̎�ɂ����̂ŁA���Q�l�܂łɏЉ�Ă����܂����B�c�c�Ȃ��w�������x�͓����s�������}���فE��������}���ق̗��}���قŁA�w�b�M�����Ӂx�͍�������}���قł����邱�Ƃ��ł��܂� �w�������x�u�F��a�Y�N�v�̍��@ �O���F��Ƃ̂��� �G�b�Z�C�u�R��w�����v �@�䂪�Ƃ̉��c���̒n���悤�₭������܂����B �����؉Ƃ̂��� |