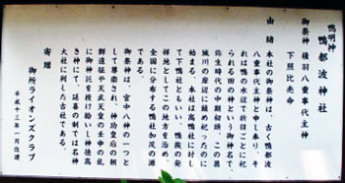やっと春らしい雰囲気になってきたので、KLEを桜や桃の下で撮影したくなった。2週間ほどカバーをかぶったままのKLEを、外に連れ出した。龍門山の麓一帯が、桜と桃が満開になっていてきれいであった。 KLEをきちんと撮るのは久しぶりである。 桃は今日が最後だろう。摘果がはじまると花が一気に少なくなり写真になりにくい。桃山の「桃源郷祭り」もこの日であった。 雲一つない絶好の天気。ローアングルのKLEも決まっている。 名前も知らない神社の桜。ヒヨドリを待っていたのだがあまり来なかった。かわりにメジロがたくさん飛んできて桜の蜜を吸っていた。 というわけで、やっと春がきた。
21日は、朝からいい天気だったが、昼からすこし鬱陶しくなってきた。買い物も兼ねてすこし走った。
 いままで山の中の写真が多かったが、久しぶりの都市の香りのするショットである。 いままで山の中の写真が多かったが、久しぶりの都市の香りのするショットである。 ちょうど、政府が仕分け作業をやっているが、いろいろ我々が知らなかったことが表に出てている。 それはそれでいいことだが、これからはさらに突っ込んで、こうすれば国民にとっていいことだ、というところまで落とし込んでほしいと思う。宝くじの収益金等は、これまでは天下り官僚に高い給料を払ったり、高い家賃で事務所を借りてるなど、不明瞭な点が多いが、収益金などは、今以上に福祉等に充当するとか言ったところまで切り込み約束させ、それをきちんとしなければペナルティを与えるようにすればいい。そういえば気になったことで、仕分け人の議員が、「白砂青松」を「しろすなあおまつ」と言っていたことである。これからこうした訳のわからない議員が増えてくるだろう。 バイクの話からすっ飛んだけれど、田尻漁港はいかにも魚が釣れそうな雰囲気であった。時間のあるときは竿を持ってこなくてはいけない。
少し暇をもてあましていると、新聞記事で奈良国立博物館で開かれている大遣唐使展の会期終了が迫ってきでいるとのことだったでひとっ走りいってきた。 行くときは京奈和を走ったが、奈良方面行きの車が多く、悪いことに前をパトカーが走っていたので、路側を走り抜けることが出来ず、時間がかかった。  それに昼食や昼寝をしたために、4時間ほどかかり、朝11時頃出たのに奈良に着いたときは3時であった。 昼食休憩は野口神社でやった。大和のいくつもある神社でも面白い神社みたいである。 この神社は以前室生寺へいった折りも立ち寄った。ベンチがあり、国道の騒音もそれほど聞こえてこないのでいい。 野口神社から裏道を走ると、鴨都波神社があった。小休止することにした。高鴨神社の高鴨社に対して下鴨社といい、全国の鴨、加茂社の発祥地であるという。弥生時代からの人々の、心のよりどころだったのだろう。 鴨都波神社を出て街中を行くと、懐かしい町並みがある。御所駅も木造で親しみが持てる。 少しゆっくり走りながら、後世の裏道、というよりこちらが本道であったと思うが、懐かしさの残る道を走ったあと、京奈和道路で奈良に向かった。 展覧会はかなりの展示物があり、内容も面白かったので、かなり見応えがあった。特に吉備真備の絵巻物の前は人だかりで、なかなか順番が回ってこなかった。 思っていたより人出は少なく、遅く入った割にはスムーズに見ることが出来てよかった。 平城京の頃、かなりダイナミックに、そしてすばらしい人材を唐に派遣していたのだと、改めて感じた。 同時に、遣唐使船は大阪から出たのだから、平城京1300年のイベントとあわせ、大阪も何か一緒にやればよかったのにと思った。大阪と奈良は仲が悪いからね。 いずれにしろ、これを一人400円で見ることが出来たことに大満足。(一応学割がきいてるため) 展示会を見終わったあとはひたすら帰りモードで走った。途中食事や少しの休憩を挟み、家に着いたのは9時を少し過ぎていた。ちょうど180km走っていた。日帰りの距離としてはこのくらいがいいかな。
 古来よりの桜の名所・吉野山に、役小角(えんのおづぬ)を開祖とする修験道の根本道場、吉野は金峯山寺。これまで何度か訪れたが、いついっても新しい発見があり、楽しめるところである。 古来よりの桜の名所・吉野山に、役小角(えんのおづぬ)を開祖とする修験道の根本道場、吉野は金峯山寺。これまで何度か訪れたが、いついっても新しい発見があり、楽しめるところである。 室町時代の、木造古建築としては東大寺大仏殿に次ぐ大きさを誇る蔵王堂は何度見てもすばらしい。 今回は、過去・現在・未来を現す三尊の金剛蔵王権現像が平城遷都1300年にあわせて特別開帳されるということで、KLEと一緒に走った。 悪魔を振り払う怒りの形相と、慈悲の心を表す青黒色の、7メートルを超す国内最大級の秘仏である。一見の価値はある。 まず仁王門が迎えてくれる。仁王の表情もいい。西洋の彫刻も精緻でいいが、日本の彫刻もまけてはいない。独特のパワーがある。 門をくぐるとすぐに楓の木があるが、葉はまだ青く、「また秋に来なさいよ」と言っている感じであった。 目指す金剛蔵王権現像は蔵王堂の中にある。拝観料1000円を払うと、お守りとお札が一緒になった木片をくれた。 パキッと折ると上の部分がお守りに、下が願い事を書くお札になっている。堂内に入ると「靴入れです」といって黒いバッグをくれた。このバッグはいわゆるイベントグッズのようにちゃちではなく、結構しっかりと作られており、使える、という感じのものであった。これだけいただけると、何となく得した!という感じになる。ほかのお寺も見習ってほしいね。 蔵王権現像は、すごい迫力であった。  7mもの彩色された巨大な仏像はほとんどない。それが3体あるのだから迫力満点である。 像の前の両側に障子で囲われたコーナーがあり、そこに座って対峙できるようになっていた権現像の声が聞こえるのだろう。 参拝者が交代でそこに座っていた。 残念だったのは写真が撮れないことで、やむを得ず街角のポスターを撮って記念にした。 権現様だから仕方ないし、やはり仏像はこちらもおいそれと撮れないような、そんな気になる。これは街角に張ってあったポスターである。 ビニールでカバーされているため光が写りこんでいる。 境内には、稲荷神社がある。ここの鐘のひもには鈴がいっぱいついている。いい音がした。本堂に向かって左の階段を下りると吉野朝宮の跡がある。 「ここにても 雲井の桜 咲きにけり ただ かりそめの 宿と思うに」 後醍醐天皇 後醍醐天皇は悲運の生涯をここで閉じたが、その後、南朝3代の歴史が続いたという。徳川時代に、家康が、吉野修験の強大な勢力を恐れ弾圧を行い、寺号を没収し、寺名をもとの実城寺に戻して、幕府の支配下においた。明治時代になり廃仏毀釈により廃寺になってしまったという。いま建っているのは南朝妙法殿で、周辺は皇居跡公園として整備されており、後醍醐天皇以下、南朝4帝の歌碑が建っている。 そこをさらに下っていくと、役の行者の銅像がある。酒の瓶らしき壺を持った従者を2人足下に従えている。 像の周辺には様々な顔をした不動明王が立ち並んでいる。ここには今回初めて来た。 再び蔵王堂の境内に戻り、仁王門から参道を歩いた。参道の店屋で草餅を買ったがおいしかった。以前別の店で買った草餅は着色料を入れたまがい物の草餅であったが、今回のは純粋なよもぎ餅であった。やはり本物は香りが違う。 仁王門からの坂を少し下ると、銅の鳥居(重文)がある。高さ約7.5m、柱の周囲約3.3m、すべて銅製である。 1348(正平3)年に高師直の兵火で焼失したあと、室町時代に再建されたものという。正しくは発心門というが、そういえば熊野古道に本宮にも発心門がある。ここ吉野では、山上ヶ岳までの間に発心・修行・等覚・妙覚の四門があり、これが最初の門となる。行者たちの気持ちとして、まさに発心し、ここから先を冥土と見たてたのである。ここから山上ヶ岳までひとつ門をくぐるごとに俗界を離れて修験の道に浸っていくのである。 時間が迫ってきたので、同じ道を引き返し、KLEのところに戻った。  ナビをセットした。このナビ少しバグがあって、動いていないときでも、女性の声で「運転中は操作しないでください」という。これは私のだけではなく、買った人がほとんどこのことを書いている。ただしタッチキーを長押しすると、普通に入力できるようになる。便利なことは変わらず、きっちりガイドしてくれる。ただ地図ソフトが古いので、京奈和道路が道なき道をガイドするので空中を走っている感じである。 KLEで走り出し、帰りは久しぶりに吉野神宮に立ちよることにした。 吉野神宮は、明治天皇が後醍醐天皇を偲んで明治22年に創立を命じたと言うことである。明治25年に行われた御鎮座祭に勅使を使わし霊代を奉納し、後村上天皇が作ったと伝えられ、それまで吉水神社(明治7年までは吉水院・南朝の行宮)におかれていた後醍醐天皇の尊像も吉野神宮の本殿に奉還したという。 後醍醐天皇はここで神様になっているのである。 吉野神宮を出て、県道39号線を走って戻った。途中彼岸花がたくさん咲いているところに来た。道標があり、みると山の上に古墳があることを示していた。早速見に行くことにした。道は結構急斜面で、息が切れかかったとき「もう一息です」との表示。なかなかいい。古墳内部は盗掘され何もないが、構造がよくわかりおもしろい。これをみられたことで、ちょい乗りも得した感じになった 帰りはちょうど夕日が美しい時間であった。道の駅で食事休憩したが、ちょうど満月。うまくKLEと一緒に写ってくれた。 帰ってメーターを読むとトータル125km走っていた。チョイ乗りとしてはちょうどいい距離だった。
大和下市に行きたかった。ずっと昔、写真仲間と行ったきりである。その当時はフォトジェニックな景色がたくさんあって、撮影も楽しかった。その楽しさを味わいたかったのと、割り箸の里として今どうなっているかを見てみたかったのである。 出発前、オドメーターを見ると46353km、気温は24度。 少し暑いが、天気がいいので楽しめそうであった。ライダージャケットの背中にカマキリがくっついたまま走った。 10時40分であった。 最初に吉野川の休憩所で昼食を兼ねて休憩した。11時40分に着いた。46kmを一時間。こんなものかな。 川ではカヌーが次々とやってきた。上手なのもいればそうでないものもいる。それらを眺めながら昼食を食べた。 休憩所から10kmほどで下市である。1時に着いたが、割り箸の里が分からず、ぐるぐると町をまわり、とりあえず駐輪しようとNTTの近くにおけるところを探し、そこから町を歩くことにした。 町は、以前来た時より建物がほとんど新しくなっていた。記憶の中の下市は、こうでなかったのである。これはどの町でもそうであるが、少し寂しい気もした。町が変わっているので、写真を撮った記憶と全く一致せず、全く新しいところに来たような気がした。 ここに来たのは1975年頃である。写真も一番盛んにとっていた頃で、5,6人と車ではるばる新宮から来た。まだ道も整備されていず、かなり時間がかかった気がする。当時は、どの家の軒下にも割り箸の半製品をうまく傘状にして並べていた。それがすごく風情があったのを覚えている。それがどの辺だったかさっぱり思い出せないでいた。 KLEを駐輪して、街中に歩き出した時に、真っ先に目についたのが赤い建物である。料亭か宿屋の気もするが、通りがかりの人もなく、確認できないままに道を進んだ。川縁には、人の住まない危なっかしい家が何軒かあった。 川筋から少し中に入ったところに願行寺がある。小振りだがきりっとした感じの寺である。 ここは伊勢路も近く、昔は栄えたのではなかろうか。案内板にもあるように600年近くの歴史がある。 下市の町の中心を川が流れている。覗くとアヒルとサギ、そして鵜が群れていた。 川縁に昔ながらの銭湯がある。これも趣があっていい。一度入ってみたいと思った。そういえば銭湯へは長いこといってない。 町は、新しくなったとはいえ、30年代にタイムスリップしたような景色がまだ残っている。歩いていても何となく心地よい。デジタルハイテクの時代とはいえ、人が本来求めている風景はこんな所にあるのではないだろうか。その証拠に、古い町並みの残る観光地はよく人が訪れている。 街中を行く時、割り箸の里がどこにあるか聞いた。それによると、歩いてきたところよりもう少し  川の上流の方にあるという。しかし、「今日は休みだから皆閉めているよ」という答えと共に「あなたが昔見たという頃よりずいぶん減ってしまっているし、割り箸の乾燥も機械でするから、もうほとんど軒下には干していない」という返事であった。工場が減っているといおうことは、幾分予想していたことだが、会社が休みということは想定外であった。残念。 川の上流の方にあるという。しかし、「今日は休みだから皆閉めているよ」という答えと共に「あなたが昔見たという頃よりずいぶん減ってしまっているし、割り箸の乾燥も機械でするから、もうほとんど軒下には干していない」という返事であった。工場が減っているといおうことは、幾分予想していたことだが、会社が休みということは想定外であった。残念。KLEに乗ろうと、駐輪しているNTTの横にくると、近くの人が声をかけてくれた。「このバイク大きいなー。何CC?」「いやー、ボディは大きくても400CCです」「そうか、ワシも若い頃バイクに乗りたくて免許を取ったけれどとうとう乗る機会がないままにこれまで来てしまった」 それは残念。いろいろ割り箸の話などして、帰り際に、 「ワシの所はそこだからお茶でも飲んでいかないか?」と誘ってくれた。 時間がないので丁重に辞退したが、行って話をお聞きすればよかったかなと、KLEで走り出してから思った。  やはりその土地土地のいろんな人から話を聞きながら、歩いたり走ったりがその旅にプラスアルファが得られる。そういうふれあいのある旅をしなくてはいけない。 やはりその土地土地のいろんな人から話を聞きながら、歩いたり走ったりがその旅にプラスアルファが得られる。そういうふれあいのある旅をしなくてはいけない。帰りは天川村のゴロゴロ水でコーヒーでもと思って、本伊勢道の309号を南下した。走り出したのは3時20分を過ぎていた。 下市の町を出て、元来た道を行くのもいやなので、国道309号線を南西に下った。12km足らず走ったところに、格式のありそうな神社があった。 丹生川上神社下社である。KLEを駐め境内を行くと、これがなかなかいい。手入れも行き届いており、きれいであった。 その格式にふさわしい雰囲気を漂わせている。 神社で教えてもらったとおりの道を走った。道は川に沿ってくねくねと続いた。途中かなり立派な廃校があった。  見た感じまだ十分活用できそうな感じである。往事には、この校舎にも子供があふれていたのだろう。少し寂しい気がする。 見た感じまだ十分活用できそうな感じである。往事には、この校舎にも子供があふれていたのだろう。少し寂しい気がする。道は、看板で、奈良県道赤滝五条線と分かった。 道はかなり整備されており、途中の真新しいトンネルは「恋風トンネル」といった。なかなか粋な名前である。その県道を12kmほど走ると、国道168号線にでる。 4時50分であった。 西吉野温泉郷で旅館がたくさんあった。またここは、かの有名な五新線の現在の終着点である。負の遺産は、新宮方面のトンネルにバリケードが張られていた。今度は168号線を北上し、一路貴志川まで53kmを走った。 途中葛城の道の駅で休憩したので、家に着いたのは7時を過ぎていた。 総行程約150kmのちょい乗りであった。 (2010年9月26日)
和歌山のススキの名所生石高原。近いためにいつでもいけるだろうと思っているが、なかなか行けていない。余りに近いとつい後回しになってしまう。近いといっても道も山道で狭くけっこう時間がかかる。今年こそ見ようと走った。 途中田があり、マネキンの頭部を使った案山子があった。極めてリアルで今にも語りかけてきそうであった。 生石高原はたくさんの人が来ていた。その昔ペルセウス流星群が見えるとき一家でここにテントを張って一晩中空を眺めた。ただし、和歌山市と海南市の明かりのせいで流星はあまりきれいでなかったのを覚えている。 観光スポットとして手軽でここはいい。はじめてラジコングライダーを見たが面白そうである。 山頂へ行き、その周辺を散策して帰る頃は、もう陽も完全に落ちていた。
▲ページトップへ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||