
 |
第21章 1988-95年技術部門トップを補佐して |
バイオケミカルテクノロジー・プロジェクト部長を2年勤めたころ、組織改革があるといううわさが聞こえてきた。そのころ 技術部隊の面倒をみていた 木町さんが
「研究所には上町という元気のいいのがいるが、お前もそろそろ研究所の面倒をみてほしいのだが手伝ってくれぬか」
という。上町さんは創業者社長の命令で長らく東北大学で助手として研究していた人とのこと。
若いときから研究所にはあいそをつかして設計部門にいながら、顧客の潜在ニーズにあう新設計をリスクをおかしてやってき た身にとっては新技術はどのようにして開発されるのかということは分かっているつもりであった。
バイオケミカルテクノロジーは大いに知的好奇心をみたすものをもっていたが、エンジニアリング企業にとってはプロジェク ト規模が小さくものたりない。そろそろ前線で銃を持って戦うことは年貢の納め時かもしてないと考え引き受けた。
世の進歩の裏には常に技術の進歩があるのは論を待たない。欧米の化学会社はカロザースのナイロン合成研究の成功に触発さ れて中央研究所を持っていた。しか1980年代後半になると投資効果がみられない反省から欧米のメジャーでは中央研究所は縮小傾向にあった。 私は1980年代後半、中央研究所時代は終焉したという世界的な認識の潮流を共感していた。しかし残念ながら、日本全体の技術開発に関する固定観念が新技 術は研究所が開発するものだという単純なものある以上、それを社内で理解させるのは至難の技と思われた。声高に言ってもわかってはもらえないだろう、実績 で示すしかないと決意した。
木町さんも同じ考えであったかどうか、独自技術開発に成功してきた私に目をつけ、研究開発の予算配分のお目付け役にした らうまくゆくのではないかと考えたのだろうから同じだったのかもしれない。しかし確認ははばかられた。でもある覚悟をもって木町さんのくどきに乗ってバイ オプロジェクト部長から技術本部の方に引き抜かれることに同意した。
実際の組織が発表となってみると、私は木町さんの補佐役で研究所長は上町さんである。直接指揮を得意とする私にとっては 隔靴掻痒である。研究費の配分くらいにしか影響力を駆使できない。それなら自分の価値観にしたがって研究費の配分をきめさせてもらうのみと決意した。でき ればいままでのような研究所は縮小解散でもよいとひそかに思った。むろん口に出すわけにはゆかない。ひそかにそうするのだ。そうして自分でも研究所の外で してきたように顧客⇔潜在需要を感じ取る営業⇔設計部門⇔試作・試用で新技術に取り組むこれからの方向を目指せばよいと密かに思った。
そもそも欧米でも工事に主力を置くエンジニアリング企業は中央研究所を持たなくなって久しい。戦前に開発された石油精製 プロセスを多数開発し、ライセンスするUOP社ですら戦後は新規プロセスの開発に成功しておらず、研究部門は切り離して売り飛ばしてしまって、ライセンス 事業で細々とその生存をしているだけになっていた。だからといって技術進歩が滞ったわけではない。新しい技術は研究所ではなく、顧客⇔潜在需要を感じ取る 営業⇔設計部門⇔試作・試用の連携のなかで生み出される時代になっていたのだ。 時代を画する大発明はどこで生じるか分からない。それが大学か企業の研究所か、設計部門かは分からない。管理できないものに金をかけても無駄だというのが 1世紀かかって分かったことだ。
化学工学会の理事をしているとき、ICI取締役フィルムディビジョン事業本部長リチャードサイクス氏と 一晩飲み明かしてこの感を深くした。この方は英国生まれながらイェール大を卒業した 。ICIのスカウトマンにくどかれて新卒として入社した経歴をもつ。 彼はICIもかって中央研究所を持っていたが、廃止して受託試験所に改組したと説明してくれた。会社は12の事業本部に分割され、それぞれの事業本部長が 自分の商品の品質改良、製造工程の近代化、品質管理などの研究テーマを確定し予算をつけて受託研究所に委託することにしたのだという。では世界をひっくり 返すような大技術はどうやって開発するのか問うとたとえば12事業部のうちもっとも利益率が高いのは医薬品事業部だが、この利益の源泉は英国のとある大学 が開発した薬で、その工業化をICIが分担 したのだという。大学の研究費はむろんICIが支払っているのである。若くて優秀な頭脳を少い金で使えるというメリットを享受したわけである。頭脳を囲い 込むことなく、自由に羽ばたかせ、その経済的成果はいただくというオープンな社会システムがあってはじめて可能なことで 、日本の国立大学ではまだ無理だな、しかしいずれそうならなっければ日本もおしまいだなと思ったものだ。
ちなみにサイクス氏は教師をしている奥さんを英国に残したまま日本に単身赴任している。
「なぜロンドンのピカデリー街に面するあの堂々たる本社に常駐しないのか」
と問うたところ、
「フィルムビジネスのセンターは日本だからだ」
という。 フィルムビジネスとは日本のビデオテープメーカにポリエステルフィルムを供給するビジネスである。ICIジャパンの社長とあなたとどちらがえらいのかとき くと
「それはむろん私である。ICIジャパン社長はICIの受託試験所の日本支部のキャンプマネジャーみたいな地位である」
とのことで参列者は日本との価値観の違いにびっくりした。
顧客が一番大切と思う心は当然のことだが、ジュニアが打ち出した”営業主導”には疑問を持っていた。あるとき役員会の資 料をとりまとめている事務局を手伝わされた。このとき思い切って役員会事務局の立川さんに”営業主導”は弊害がある。当事者能力のない連中にリーダーシッ プを握られたらとんでもないことになる。取り下げるようにできないかと提言してみた。彼はグラッとしたようであったが検討しようといった。
この提言が原因か、軽井沢の役員保養施設で開催された次期経営方針策定役員会議に事務方補助の肩書きで出席させられるは めになった。全役員のまえで、ジュニアに
「君は”営業主導”には反対のようだがそうやすやすと取り下げるわけには行かない」
と笑顔を浮かべて言われた。その後 、どういう風の吹き回しか、立川さんに呼ばれて
「君は取締役候補になったので奥さんとも相談してうけるかどうか返事せよ」
と申しつかった。木町さんは
「何用で本社に呼び出されたのか 」
と聞く。事情をはなすと
「フーン」
と多少驚いたような顔をした。これで木町さんの推薦ではないことがわかる。”営業主導”に批判的なので取り込まれたかな などいろいろ考えたが、使用人待遇の平取りとはいえ、まず役員にならなければ影響力は発揮でいないと受けることにした。しかし以後、言動にはますます慎重 に ならざるをえない。周りからは元気がないねといわれるようになった。我ながらなさけない。
大学の恩師、前田前学長(故 人)を囲む会に出席したとき、先生から関西なまりで
「おい、なんでお前が取締役になれたのか」
と聞かれた。もっともな疑問である。やむをえない、
「社長の前でちらちらするのが目障りなので取り込んで黙らせたのでしょう」
というとさもありなんという顔をして
「ムム」
と言ったきりであった。
このとき、役員に登用されたのは岳下さん、頭島さん、同期入社の川畠、段葛、土連他であった。 人事部から
「恒例として新任の取締役は創業家に挨拶に出向くことになっている。その時、ジュニアの奥様におみやげをもっていくことになっている。彼女が希望している ものをあらかじめ聞いておいた。それはxxxです」
ということが下達された。xxxがなにであったかは覚えていないが 、川畠が幹事となって用意したように記憶している。われわれが自発的にするなら別だが、人事部が介入するのは妙なものだとおもった。ジュニアの奥様とは創 業社長の形見のお嬢様である。はじめてお会いしたとき、若い頃はさぞかし美人だったろうなと思われる人だった。ジュニアが夢中になったのはうなずけた。彼 女がギョロ目で我々一人一人を眺めまわしたとき、私はその目のうしろに 創業社長を見つけて懐かしくもぎょっとしたものである。これはDNA鑑定するまでもなく、親子だと思ったものだ。 会社は創業家のものだということを新任役員に印象付ける儀式としてこれは有効であったと認めざるをえない。
慣例で思い出したが、新任役員は夫婦同伴で忘年会に出席せよという。そうして、全ての新任は夫婦それぞれ壇上に立ち、挨拶することを強要された。私はなに を話したか覚えていないが、わが妻は
「夫が毎日、会社がどうの、会社が・・・と言っているのを聞いていて、一体会社というものはどんなものだろうかと想像していたが、今日はじめて会社とは何 かわかった。それは皆様方である」
とやってしまった。ジュニアは、
「そうだ、おれたちが会社だ」
と大いによろこんでいた。
後日、木町常務から、「君が取締役に選ばれたのは君のネアカな性格が会社には必要だとジュニアが考えたからからだよ」と言われた。なるほどそういうものか と合点がいったものだ。
2年の任期が終わる頃、木町さんから次の役員候補としてお前が推薦する人物は居るかときかれた、すぐ頭に浮かんだ名前は後崎君であった。彼の能力と考え方 は大いに評価していたためである。なんといってもプロセス設計ツールとしてのCAPESの開発が最大の貢献であろう。今となっては同じような機能のソフト は市販されているが、まだそのようなものがないころは大変役に立ったものである。それに新技術開発には威力を発揮する。いつでも新しい物性や単位操作を開 発して組み込めるからである。そして木町さんがどう動いたかは知らないが、後崎は取締役に任命された。
取締役会で審議事項が少ない時など、技術テーマにつき報告をさせられることがあった。充分準備してあとは簡潔に早口で一気呵成にしゃべるのだ。木町さんが
「お前は説明がうまいな、感心したよ」
とおっしゃる。普段の会話では困難を感じていたからその落差に感心したのではと疑っている。どうも私は不用意にはなすと、自分では話したつもりが、目的語 などが抜けてしまい分かりにくいらしいのだ。LNG冷熱 利用発電装置開発で 発生する技術的問題の解決策を持って顧客のTガスに出向いて、一気呵成の説明すると顧客は納得してくれたことを思い出す。しかし彼らが社内で議事録を照合 すると結構くい違いが出てきていったいおれ達は何を聞いていたのかと反省したものだと聞いたことを思い出す。なにも言葉巧みにごまかしているわけではな く、その技術対策を実施すれば問題は解決できるのだから、真実を語っているのだ。その自信が説得力をもつのだろう。
さて顧客⇔潜在需要を感じ取る営業⇔設計部門⇔試作・試用で新技術開発に取り組む方向を目指すといっても、このリンクの なかで切れているところが営業であった。 ピーター・ドッラッカーが 「できないことではなくできることに注目せよ」というが、何ができるかはやはり技術系でなくては判断できない。 創業社長時代には 前葛さん(故人)、善畠さん、常畠さん、平などの技術系の営業がいて、顧客とは親密な関係を築き、信頼されてまだアイディアの段階から一緒に新技術を育て ることができた。しかし ジュニア時代には希望の星、前葛さんは過労でくも膜下出欠で倒れ、それに続く少数派の技術系営業担当者は文系営業の職域を侵されたくないという防衛本能の 執拗な攻撃を受けて、ささやかな成功はゆるされても営業のメジャーになることは許されず、死に体になっていた。 文系でも眼力をもっていた人間も居ないではないが、その他は日本流の商社くずれの宴会営業上がりで 、客の技術的要請を芽のうちに敏感に感じ取り、適切な技術部門に伝えることができる人材は少ない。ジュニアの”営業主導”で舞い上がって紅衛兵のようにや けに元気なだけだ。国内ならこれでも技術部門が直接接触できる裏リンクがあるが、海外となっては裏リンクをつくることは物理的に不可能で顧客⇔潜在需要を 感じ取る営業⇔設計部門⇔試作・試用の体制はついに作れなかった。そもそも顧客の組織は技術系で固められている組織である。ここに 文系の営業が出かけたところで、話もできなければ友情を育てるこもできない。ましてやまだ雲をつかむような未来計画を話してもらえるような雰囲気はつくれ ない。彼らに出来きることといえば、購買部に出向き、設計の完成した建設予定の競争引き合い書をもらい、現地商社や現場工事にあやかりたいとむずむずして いる現地工事業者と当たりをつけることくらいである。残りは価格と納期の過当競争をくりひろげるという不毛な戦いに突入するだけということになる。
「研究は、詩と同じく、万人が受け入れるようには定義できない」
という言葉がある。まさにそのとおりだと思う。会社を去るとき、おなじく退任して会社を去る翁川さんが近寄ってきて
「新技術の開発に失敗したからこうなったんだよな」
という。この言葉に反論する余地はない。しかし、
「この人は技術をどうあつかったらよいか分かっているのか疑わしい」
と声には出さないが思った。通産省から天下った京戸という役員も研究は重要だとの言葉を呪文のように繰り返していた。といって研究所に金を投じただけでは 成果が出るのもでもないのだ。 創業社長時代の研究所が身をもって証明しているではないか。この人々は19世紀後半から20世紀前半の企業の中央研究所が大成果をあげたことの記憶を語っ ているに過ぎない。 遅れて来た知識の虜になっているのだ。
トルーマン時代に米国の科学技術政策をリードしたヴァネバー・ブッシュの 研究⇒開発⇒生産⇒マーケットという一方流れのリニアモデルは米国の戦後の国家と企業の技術戦略の中心的思想であった。日本の学会も役所もむろん米国をみ ているのでこの思想の奴隷であった。通産省とその傘下のNEDOは大真面目で石油・電力税という目的税のカウンターとして、民間企業の研究費の一部を補助 する制度を作ってくれている。しかし、完全自由研究には補助金は出さない。通産省が国家目的にかなうと判断したテーマに限るのである。ここからが問題なの だが、潜在需要を発見する能力のない通産省の文官が大切だと思うものがテーマになる。たとえば、時の新聞をにぎわしている都市排水のバイオ処理技術開発と か分散型燃料電池発電といったものである。
企業の中央研究所の研究者は会社の研究費が先細りなので、こういう研究テーマに飛びつく。私が研究予算の配分を見始めた とき、すでにこのようなテーマが進行中だった。後に社長になる前研究所長の桃平さんが補助金研究を奨励したということだった。しかし都市排水のバイオ処理 は建設省の傘下に全国の地方自治体の施設の設計を排他的に担当する組織があって、市場は開放されていないのだ。50%の予算を自腹を切って担当して報告書 を書いてそれでチョン。縦割り行政だから通産省は手も足もだせない。要するに潜在的需要はゼロだった。分散型燃料電池発電開発組合もそう。確かに燃料電池 発電は気になるテーマではある。大型のスチームリフォーミングプラントの最大手としての わが社にとっては無関心ではいられない。むずむずして参画したが、結局これを買ってくれるマーケットは無かったのである。企業内で失業状態にある研究者の 救済事業みたいで、まったく後ろ向きの研究開発となる。以後、上町さんと連携して、段階的撤退をはかったものである。通産省から天下った京戸氏が「研究は 重要」と連呼する声は雑音と聞き流した。ホンダ技研、ソニー、インテルの成功とゼロックスの失敗を目撃した米国ではリニアモデルを信仰を信じる人は 1990年以降いないのではないか。燃料電池技術がいい例だ。その後、有機膜を使う新型の燃料電池がカナダのベンチャーからひょっと出てきたではないか。
役員になると大学教授になっている後輩から、
「どうです、論文ドクターをとりませんか」
と声がかかった。研究所のボスになっていた上町さんからは木町さんや頭島さんのドクター号取得を手伝った若手を手伝わせるからとの声もかかった。しかし、 研究所の連中が会社に貢献する技術開発より、論文ドクター取得に夢中になるのを苦々しく思っていたから断った。 東頭さんは私が途中で会社に嫌気を出して大学に去るのではないかと危惧を抱いていたようだが、その心配はなかったのである。いまだに日本の大学という存在 は日本を駄目にしているという思いが頭を去らない。
「科学者は解ける問題を解く。技術者は解かなければならない問題を解く」
と言っている。日本の大学の工学部は科学者気取りの人で埋まってしまっているのだ。
アルンLNGプロジェクトで大型回転機械担当エンジニアだった短畠君が自ら希望して営業に出たいという申し出があった。 利益に責任を持たなくてよしとされた文系主体の営業部門に移籍したいというのである。大勢の技術系先輩が文系の妨害にあって辞めていったを話してきかせた が、自分は大丈夫と言って技術本部を去った。
「先輩のようになるなよ」というはなむけの言葉を与えた。
その言葉よろしく免疫力をつけていたのか、ヒューストン事務所勤務で鍛えられたためか、彼は先輩の文系の妨害をうまくさ ける能力を持っているようだった。その彼が
「岳下さんを連れてプリンストンに出向きM社のナンバー2にカタールLNGプラントの工事引き合いをよろしくと挨拶にゆ くが、岳下さんは長口舌をするだけで客への説得力がないからついてきてくれ」
という。M社は合併前のでプリンストンにあった。いいかげん管理業務 に嫌気がさしていたので渡りに船と出かけることにした。
長年苦楽を共にしたプロセス設計部の善山吉次がこれを聞きつてやってきて、
「天然ガスに含有される有機硫黄が脱水装置で吸着され、脱水装置を燃料ガスで再生するときに脱着され、燃料ガス中の有機 硫黄含有量が間歇的に高濃度になる。そうするとガスタービンのウッォベ数が急変し、燃焼が不安定になる。かつブレードの腐食を生じさせるという問題が発覚 し、顧客が困っている。設計を請け負ったK社は燃料ガスの再処理工程を追加することで解決しようとしている。しかし燃料ガスの再処理をせずに、有機硫黄も 硫化水素と同時に吸収してくれるスルフィノールプロセスを採用すれば、きれいに解決できる。しかしこの場合、 同時に吸収される炭化水素が硫黄回収プラントで不完全燃焼し、硫黄を黒変させるのだが、サルファープラントの権威である戸下君が試運転時にライセンサーに も内緒で隠れた実験をしてススをださない運転法を見つけている 」
という。その詳細はここでは明らかにできないが、理論的に納得できる話だった。無論公式にはライセンサーであるコンプリ モは性能保証してくれないが、ライセンサーが性能保証してくれなくても結構。コントラクターとして自ら責任をとればよいのだ。失敗するはずがないとすぐ判 断した。いままで何回も冒険したが、化学や物理の原理にかなえば自然は裏切らないという確信を得ている。契約はあくまで弱い人間が保身のためにすることで 当面無視してよいと10分位の会話で合点した。
なにせカタール沖にあるドーム・ガス田はソ連の北極圏にあるヤマルガス田に匹敵する世界最大のガス田だ。モービル社のビーツ氏もインドネシアの北スマトラ のガス田が枯渇したら、カタール沖のガス田開発に社運をかけることになるだろうと予測していた案件である。これを受注するか失注するかは後日に分岐点だっ たと思われるのではないかとの予感があった。
というわけで久しぶりのニューヨークからエキステンデッド・ボデーのキャディラックでプリンストンに乗り込んだ。短畠君 の予想通り、岳下さんの30分の長口舌をがまんして聞いていたM社のナンバー ・ツー氏が立ち上がりかけたとき、岳下さんが私の方を振り向いて
「なにか言うこと無いか」
と声をかけてくれた。そこで一言、
「だいぶガスタービンのウォッベ数ではお困りのようであるが、これはスルフィノールプロセスを採用すれば解決できる。し かし副生硫黄が黒くなって売れなくなる問題も発生する。しかし当社はこの問題の解決法を知っている」
と一言 、一気に述べた。立ちかけていたナンバー・ツー氏がホホーという顔をして座り直し、
「それは耳よりな話だ、明日部長共をあつめるから一つ説明してやってくれないか」
と言ってくれた。これぞまさに 顧客⇔潜在需要を感じ取る営業⇔設計部門⇔試作・試用で新技術に取り組む理想の仕組みのトリガーが外れた瞬間だった。短畠君が営業を担当していなかったら こうはならなかっただろう。 約2時間、自分より若いモービルの部長連中に懇切丁寧に包み隠さず説明した。彼らの姿勢で感心したのはこれはライセンサーも知らない千代田だけのノウハウ だといってもビビらなかったことである。理屈にあうものは万一の失敗があったときどうしようと腰が引けない積極性というものを感じた。
結局、K社の基本設計は参考にして、自由な新設計をも認める工事引き合いが来ることになった。 メジャーが出す工事の競争入札で前例の無いやりかたである。これもこちらが良い技術を持っているからである。積算を担当した岩屋プロジェクトマネジャーが 適切な見積もりをしてくれたおかげで受注でき、世界最大のガス田の上に鎮座するLNGプラントのグラスルーツの建設工事を受注できた。 受注後、ライセンサーの設計担当者は戸下君の説明で納得したが会社としては保証できないと言ってきた。千代田としてはもう受注してしまっているので、間に 立った課長の善山は苦労したようだが千代田の責任で押し通すしかなく、結果オーライであった。
再生千代田が2004年暮れにこの拡張工事を受注できたのも
短畠営業の思い付きのおかげだと思っている。あの傲慢な朝日新聞ですら2004年12月17日にこの受注を報じた。2005年にも7系列目まで継続し
て受注したという。すべて短畠営業と、岩屋を次いだ大樹プロジェ
クトマネジャーのコンビが顧客の信頼を維持できている証拠だ。大樹はアルンLNGのオフプロットエリア担当チーフエンジニアとして初めてLNGプロジェク
トに参画して以来ズットLNG1本できた男だ。おかげで一時低迷した株価は
底値の50倍の高値に舞い上がり、人々を驚かせている。2005年春技師長を一旦首になった善山も再任されたという。むべなるかな。残念なことに、その後
の千代田は依然文系営業が続き、業績もぱっとしない。
逆の例として、技術を表面的にしか理解できない文系営業が長い歴史のなかでは淘汰させるような技術に飛びつく弊害をいくつか経験し、無駄な出費を強いられ たので紹介する。プラスチックを油化させる技術である。プラスチックのベストな使い方は①リユース、②直接素材としてリサイクル、③油化して燃料、 ④RDFにして発電所で燃す、⑤直接燃して発電という5つの方法がある。技術的にはいずれも可能である。物の持っている価値から考えれば、この番号順に好 ましいだろう。しかしコストを考えれば③と④は疑わしい。しかし技術に無知な文系中心の地方自治体の役人はこういう話に飛びつき、予算をつけてしまう。文 系営業の耕平も③の案件を嬉々として予算不足を承知で無理に受注してしまうのである。 受注した以上、ちゃんと稼動するものに仕上げたが、大きな赤字を抱えたままでおわった。リピートオーダーも無かった。他社は④を受注し、旨く稼動せず、訴 訟問題にまでなったり、自然発火事故を起こして新聞をにぎわした。
バイオエンジニアリング企業スターン・キャタリティックの営業マンは技術系だ。ベクテルにトレードされた平も機械出身のプロジェクト エンジニアだ。少なくともこれが米国のエンジニアリング企業の実態なのである。
そもそも文系営業が営業を聖域化し、技術屋を排除しようとするのは創業社長時代にきめた人事採用枠の固定と終身雇用制に 起因すると感じていた。 文系の採用枠が多すぎ、文系の花形職場である営業の少ないポジションを巡っての社内競争が激しすぎるからこうなるのだ。 技術系も営業は文系の聖域を考えるので営業のセンスをみがかず、技術バカになる人も出る。文/技の採用比は常務会で毎年きめるのだが、誰もこれを変えよう とした常務は居ないという。やむをえない、取締役になって人事部の採用面接会議に出席したおり、枠を変える時期がきたのではないかと発言してみた。常務の 反塚さんが
「優秀な技術屋を営業のようなヤクザな仕事に使うわけにはいかない」
という反論を軽いノリでした。むろん彼の言うことにも一理ある。特に日本の顧客は習慣として文系の営業を前提としている ので文系の方がよいといえるであろう。しかし海外マーケットは違うのだ!私の発言は国内営業のボス的人物だった経歴を持ち、当時購買の元締めをしていた 反塚さんの理解の外だったのだ。その後も、採用人事枠が変えられることはなかったようにおもう。
1992年8月、クアラルンプール市開 催第10回世界LNG会議(LNG10)にパネリストとして参加し た。米国のJ・C・カーターというLNGポンプメーカーの技術者と名乗る男が「最近、LNGエキスパンダーを採用するとのことだが、あんなもので動力を回 収したところでたかが知れている。経済性がないのではないか」という質問をした。壇上にいた私は外のパネリストが一瞬どう回答するか天井を見あげている間 に手をあげて回答を買ってでた。「あなたの質問は もっともだが、事の本質を見ていない」といいたかったのだが、上手い英語がでてこない。とっさに「あなたは誤解している」とやってしまった。すこしキツ かったかなと反省しつつ、「たしかに動力回収を目的とするならあなたの言うとおりです。しかし動力回収などが目的ではないのです。LNGエキスパンダーに 空気ブロワーを直結して回収動力を空気に捨ててしまっても、得られる利益は大きいのです。60気圧の圧力下で冷却されて液体なってもこれをジュールトムソ ン弁で大気圧まで減圧すれば、等エンタルピー膨張により一部がガス化してしまう。しかしLNGエキスパンダーで等エントロピー的に減圧すればガスの発生を 少なくまたは全くゼロにできるのです。結果として液化に必要な動力を大きく節約できるのです」と説明した。
あとでJ・C・カーターを辞職してエバラが買収した競争会社の営業になっていた男がやってきて「あのバカが愚かな質問をしたことにたいしてのあなたの返事 は胸のすくよう で、気分良かった」というではないか。たまたま会場にいた桃平副社長は私のキツイ言葉使いが気になったようだが、満足している風情だった。
元J・C・カーターの営業は1986年ロスアンゼルスで開催されたLNG8の時、ネバダ州、レノにある工場に案内してくれて以来の知り合いだった。ちなみに LNGの国際会議は3年毎に開催されていて、1989年のLNG9はニース、1995年のLNG11はバーミンガム、1998年のLNG12はパースで あった。会議後、サラワク州ビンツルのシェル社のLNGプラントとフィシャー・トロピッシ合成プラントを見学した。
いまにして思えばやはり文系中心の営業に「営業主導」というリーダーシップを与えたことが千代田化工をだめにしたと思
う。「お客様は神様」と営業主導は似て非なるものだ。
フェアチャイルドをスピンアウトしてインテル設立をしたロバート・ノイス、ゴードン・ムーアに資金提供したベンチャーキャピタリストのアーサー・ロックが
AMDの設立を口説きに来たフェアチャイルドの販売マーケティング・マネジャーのジェリー・サンダースにいった、投資できない理由が
「
わたしはずいぶんいろいろな企業に投資してきましたが、失敗だったのは、すべてマーケティング専門家がトップに立った会社でした」であったと
後で知り、むべなるかなと思ったものである。
創業社長は九州大学工学部の応用科学科を卒業後、三菱合資会社に入り、旧M石油の立ち上げに参画した。 東北大の徳久教授もその仲間だった。創業社長は太平洋戦争中は陸軍の軍属として日本軍占領下にあるスマトラ島パレンバンの製油所の復興の指揮をとった。オ ランダが撤退の前に破壊していたのである。戦後マッカーサーの製油所操業の禁止令でメシが食えなくなり、25人の仲間と わが社を創業した。戦後復興と高度成長の波に乗り、 創業社長指揮下、日本のトップのプラントメーカーに育った。国内プラントマーケットが成熟して、需要が縮小に転ずるや、彼は市場を海外に求め、1963年:流動床式脱水素パイロット・プラントの試運転で ふれたように研究開発能力を武器にサウジ市場開拓に成功した。オイルショック後は豊かになった中近東のプラントマーケットを席巻し、東南アジアの勃興とと もにそのプラントマーケットに参入した。そして彼は 東南アジアのマーケットが巨大に成長するのを待たずに急死するのである。
ジュニアがトップマネジメントに登場したのは中近東のプラントマーケットが一巡してアジアマーケットが旺盛な投資熱に沸く前の端境期であった。不幸な登板 であった。 創業以来、長年創業社長を支えた森所さんが社長にならずに引退したのはバーンアウトしたこともあろうが、前途多難さが分かっていたからであろうか。ジュニ アがしたことは1985-87年:バイオケミカルテクノ ロジー・プロジェクト部長拝命で記したように余剰人員の有効活用としての多角化であった。こうして多角化した分野の新技術開発も視野に入れなけれ ばならないことになった。
創業社長の頭の中にあった技術に関するイメージは新技術は研究所でおこない、既存の技術で設計するプロセス設計部以下、 各ファンクショナル部が間違いなく仕事をするようにマニュアルを整備して粛々と設計業務をこなすことだということであった。いわゆるリニアモデルの呪縛に かかっているのだ。常畠さんと私が組む独立愚連隊のやることはある時点でとっ捕まえてマニュアルを書かせる必要があると考えたのだろう、M商事の神戸基地 の受注時に自ら乗り出してマニュアル化を直接指導た ことでも分かる。プロセス設計部の連中はマニュアル通りしっかりやればいいのだという風にしつけられてしまった。けっして前例のないことはしないという癖 が 身についたのである。特に石油精製グループにこれが徹底していた。このような組織は既製の技術を展開する上ではそれで問題ないのだが、進歩に寄与するなど ということはみじんも考えない。したがってプロセス設計部の石油グループに新技術開発を期待するわけにはゆかないのも道理であった。
大学でひも付きでない自由な研究という理想を植えつけられ、シーズを生み出すべく、純粋科学を追及すべきという思想に感化されたボット出の研究者は秀才ほ ど目の前にある潜在需要には興味を示さず、 シーズを発見しなければと力むのだった。化学工学会の理事になって学会誌の編集長を務めていた時、編集員の一人があの人は東大でも秀才で貴社にはすごい人 が行ったものだと思ったといわれた 深沼君とはシーズかニーズかで論争したことがある。かれは頑としてシーズ派でゆずらなかった。後年、彼は結局大学教授に転出するのだが、わが社に在籍して いた間、シーズは沢山作ったが、会社に利益をもたらすものを独自に発見することはなかった。無駄飯を食ったことになる。
深沼君などまだいいほうで、その他はいかにかっこいい論文を書いて博士号を取得するかしか考えていない。このようなとこ ろから売れる新技術がでてきるはずもないのだ。試験所になれというものなら、おれ達を土方のようにさげすむのかと反発で顔をゆがめて嫌悪する。
創業社長はUOP型の研究所を夢見ていた。重油中に濃縮する硫黄による大気汚染が深刻になったとき、米国のGオイルとい う中規模の石油会社が重油を構成する分子に組み込まれている 有機硫黄を水素添加して分解し、硫化水素として分離する技術を開発した。わが社はこの1号機の詳細設計と建設を担当し、完成したプラントは非常にうまく動 いた。創業社長はここに未来のマーケットを感じたのだろうか、はたまた独自技術を持たなくては欧米が技術ライセンスしてくれなるとメシの食い上げになると 危惧したのか 桃平さんを研究所長に任命してこれと類似の技術開発の大号令をかけた。この技術はよい触媒を開発することにつきるのだが、かろうじて自社開発したという触 媒がようやく一つしかないのに、Gオイルが持っていたようなベンチスケールのテストスタンドを子安に土地を買い求め、数十台建設してしまった。しかし、こ れでテストする触媒は1種しかないのだ。そもそも 、自社開発した触媒といえども文献を参考にして造ったので短期の活性は高いものの、実用化したらどうなるかわからないものであった。 それに触媒製造プラントは持っていないので製造は外注しなければならない。問題山積だった。とどめは顧客からやってきた。GオイルはS社に吸収合併される のだが、このS社が競合技術を開発するなら、ノウハウ保護のためにプラント建設は任せられないと言いだした。ここで創業社長の夢は砕け散ってしまい。膨大 なテスト装置は子安の地で立ち枯れてゆくことになる。
こうして高い代償を払ってエンジニアリング企業がプロセス開発する時、顧客と競合する技術には手をつけてはいけないこと を学んだ。
ところで、S社からライセンスした重油脱硫装置をA社に納入していたのだが、10年以上操業したある日、定期点検を終えて再スタート中の高圧熱交換器の蓋 が飛んで、大勢の作業員が犠牲となる事故が発生した。第一報が入ったとき、社長室に呼ばれて担当者部長からの報告を聞いた私は、その原因をライセンサーの 仕様書にあるネジ山の高さ不足と判断して、その旨発言したところ、事故対策担当者としては不適任と判断されて、もう一人いた杉戸技術副本部長が担当となっ た。私はほっとしたのだが、杉戸技術副本部長は針のムシロのような時間を過ごしたと思う。ライセンサーのS社は巨額の損害賠償金を押し付けられるのではと 恐れていたようだが、ライセンサー責任はウヤムヤになって事件は落着した。メジャーオイルとは事を構えたくないという関係者の配慮も働いたのだと思う。A 社は準国策会社で社長は元大物通産官僚であったため原因究明委員会を仕切った大学教授は苦労して理解不能な理屈を展開していた。大学と会社の先輩でA社に 請われて移籍していた梅外も寿命が縮まるような時期だったと、後日述懐していた。
さて後崎、上町と私の3名は、総額だけ与えられてその配分を任された。いざ研究費を配分する仕事を担当してみると大蔵省 の主計官もこれで悩むのであろうと思った。
大体予算配分などという不合理なものはない。 国の場合は各省庁、地方自治体がいかに予算を多くとるかであらゆる術策を弄してくる。そのどれも、もっともらしい御託をならべて差がつかない。いきおい総花的予算配分に落ち着 く のではないかと勘ぐっている。そうすれば皆がしょうがないなという顔で引き下がるだろう。この構図とまったくおなじことが少ない研究予算の争奪合戦で繰り 広げられるのだ。 2005年に金融庁を退職した大串博志氏も主計局キャリアだった経験から国家予算策定過程は「共倒れのプロセス」になっていると指摘している。経済学用語 で「合成の誤謬」とほぼ同じ意味と受け取ってもらっていいという。(Paradox Serial No.14)
そのようなことにならないように予算要求を出してくる研究グループの言い分を聞き、その人間の力量を見極め、世のなかで の位置を見極めて自分の偏見と独断できめてみる。そうするとその予算を要求した多角化した各部門の本部長が会長にかけこみ、隠然たる圧力をかけてくる。や はりICIのように事業本部を独立採算制とし、自分の研究開発費は自分で利益の中から出すという仕組みにしないと研究費のあらかたは無駄使いになると感じ た。
旧通産省から天下った京戸常務から主計官には4種類のタイプがあるとうかがったことがある。 それは
「Aクラスは予算をつけるのを断って、尊敬される。Bクラスは断って、恨まれる。Cクラスは予算をつけて、感謝される。 Dクラスは予算をつけて、ばかにされる」
というものであった。私は社内でいったいどのタイプとされたのであろうか。 ところで主計官のつれあいが女友達だったので主計官殿に会ったこともあるが、ただの人だという印象だった。
予算要求のなかで割合簡単に却下できるものがあった。これは研究所長の上町とも意見が一致したので即実施した。それは研究所の前所長の桃平氏が不要な研究 者の救済事業として始めた通産省の補助金をもらって国の研究の下請けをすることである。無論収入は減るが、残りの50%は自己資金だ。これを節約できるの も利点だがモラルハザードを防止できるのがないよりだった。
当時の通産省がNEDO経由で支援している研究はほとんど民間企業が利益を狙って自らの身銭を切ってするべきことだっ た。政府が金をばら撒くので日本の企業の研究はその金に群がって無能な研究者の救済資金とする誘惑に勝てない。そういう救済的な研究資金を総て返上すべき と主張し実施できたのは幸いであった。多分無能な研究者からは恨まれたことであろう。いやしくも国家が支援すべき研究は企業と競合する研究ではなく、どの ような応用分野があるか分からない段階の基礎研究とそれをすることにより有能な研究者を育てることであろう。
1980年代にジュニアは若手文系営業の上峰など若手将校群が葛戸さんなどを担 いで提唱した ストラテジック・ビジネス・ユニット(SBU) という名の下に本業のエンジニアリング以外に多角化する案を採択した。以後紅衛兵の跋扈に 会社は苦しむことになる。そして海外プロジェクトは前葛さん、国内プロジェクトは桃平さん、そして多角化した新規分野は露平さんが管掌ということになっ た。SBUとはかっこいいが、米国の経営雑誌を表面的に読んだ生半可なもので名 前は勇ましいが、独立採算制は採用しなかったのである。これはご本家のSBUとは似て非なるものであった。独立採算制は各部門の本部長達がよってたかって 反対してつぶしてしまうのである。歴代の社長も会長もいずれも非力で、リーダーシップを発揮して独立採算制に成功した人は結局だれもいなかった。結果とし て各事業部は研究開発はいうに及ばず、実業でも赤字経営をたれ流してもおとがめなしということになった。新技術開発に失敗したと指摘した、翁川さんが関連 した事業のなかにはグアム島のリゾート開発向け土地購入、北海道の富良野町のゴルフ場用土地購入、S工業などの口車にのって多量の売れ残りを発生させたカ ナダや湯沢のリゾートマンション開発などがある。なぜか私は投資すべ きかどうかの事前審査委員に任命されていたが、
「自分が自腹を切っても買いたいとおもうような物件でなければ売れないのではないでしょうか」
などと意見を言うものだからその都度つぶれてしまう 。結局、委員はお役御免になってしまった。そもそも委員会ほど無責任なものはない。うるさい委員はお引取りねがって、なんでもごもっともという人を任命す れば、任命者の意のままになる。結果は私の発言通りのありさまになったのである。ある日、ジュニアが通りがかりに廊下で
「おまえが遠慮しているうちに皆でよってたかって会社をくいものにしてしまう ぞ、もっと積極的に動いたらどうかね」
と言われた。現状を気にはしていうのだなということはわかったが、
「社長それはあなたの仕事ではないですか」
という言葉を飲み込んだ。 自分はいい子になって私を憎まれ役にしようという軽い気持ちなのか。軽い気持ちで会社経営などできないではないか。
いまにして思えば、ジュニアが遅まきながら不安を感じたバブルの最後の観光事業開発の失敗の元凶、翁川などは、参謀でありながら司令官を無視して勝手な命 令を出して日本を戦争に引き込んでいった辻政信、東条英機とダブって見える。このようなことが生じるのは小室直樹、日下公人の「太平洋戦争、こうすれば勝てた」 によると日本の組織が下位代行を奨励しているためという。アメリカは絶対に下位代行をさせない。「上の者が自分でやれ」という制度である。それは上でなけ れば考えつかないことや言い出せないことがあるからである。通産省から天下りした京戸常務が日本の役所では下克上が奨励されているということをおっしゃっ たが 、日本の中央官庁も同じ組織文化を持っているようだ。
多くの研究開発テーマのなかで放射性廃棄物の開発は中断すべきと判断し、紅衛兵的営業に背後からさされないように電力系 顧客には隠然たる影響力をもっていたジュニアを真っ先に説得してから営業を説得し、動燃に断りを入れてもらったことがある。以後出入り禁止になるのは覚悟 の上だ。予想通りの展開となったが、いまでもこの判断には誇りを持っている。 競争相手のN社が後日動燃の放射性廃棄物処理でホゾを噛む思いをすることになるのだ。
わが社の研究開発の歴史の中で成功したものが二つある。一つは創業社長のころ、東北大の村上研究室の研究成果をヒントに 開発した石膏法排煙脱硫技術である。これも入町さん以下、楢沼さん、川末さん 、東平さんなどプロセス設計部の人々が主体となって装置を工夫し、研究所でテストをしたというケースである。これは大成功で、日本の石炭焚きボイラー発電 装置のシェアの1/3を占めるまでになった。もう一つはCDやDVDの基盤として需要拡大傾向にあったポリカーボネート樹脂の原料、ビスフェノールAの製 造技術開発である。 いずれも研究所から生まれたアイディアではない。いずれも研究所は試験というサービスを提供するという役割を担っただけである。
大学発のシーズを工業化するのは欧米のメーンルートである。しかるに我が国の場合は事情が異なる。とある化学会社がとある大学教授の論文が気に入ってこれ を一緒に工業化しようと持ち込んできた。細菌の生態は多様で中にはメタンガスなどを還元して水素を生成する菌もある。この菌を培養して乾燥させ固定しても 菌体のなかにある還元酵素が活性を維持するのでメタンから水素を製造するプラントができるのではないかというものである。通常はスチームりフォーミングと いう触媒を使って高温でメタンを水蒸気と反応させる高価な方法を採用せざるをえないので我々も耳寄りな話ととびついた。早速研究所で確認試験をすると、た しかに水素生成菌は水溶液のなかでは活性を維持すて水素ガスを発生させるがこれを乾燥させれば酵素の活性は乾燥度に反比例して低下してゆき完全な乾燥状態 では活性はゼロになるという報告が上がってきた。そもそも酵素の活性は原理的にいって水溶液中で発揮されるものだ。はじめから疑わしい話だったのだ。先生 に確認するとそうですか?変んだなというばかりで要領をえない。大学での実験ノートも見せてもらえない。我々はでっち上げの論文であるか、実験した学生が 嘘の報告をしたのいずれかに違いないと結論せざるをえなかった。
2006年に韓国で黄教授のES細胞細胞論文捏造事件が生じ、東大の某教授の論文も再現性がないと話題になったが、大学発のシーズにはこのようにあやしげ なものもあるということを学んだ。その他のシーズはどうかというと大部分は博士号製造目的のたたき台で経済性のないものであるというのが実業に携わるもの の感覚であった。
ある日、NHKの記者から電話がかかってきて「貴社が石油生成菌を使って原油を製造する方法を開発した」と某教授から聞いたので取材させてほしいという。 社内でそんな話は聞いたこともないのでなにかの誤解ではないですかと切った。すぐ研究所に問い合わせてわかったことはある研究者がこの某教授と石油生成能 力を持っている藻類の勉強会をしていただけというものであった。ではその某教授はどうしてそのような話をNHKの記者にしたのか疑念が生じたものである。 株価操作が一つの回答ではあった。もしそうなら犯罪ものだ。大学教授も地に落ちたものだと思ったものだ。
1984年、インドにあったユニオン・カーバイド社(UCC) の農薬工場でイシシアン酸メチル(Methyl-isocyanate, MIC)が漏れ、周辺の住民3,000人が死亡し、UCCは600億円の保証金をインド政府に支払った。UCCはこの保証金の支払いのため、売れるものは 何でも売り払う方針をとり、ビスフェノールAの製造技術もその中にはいっていた。彼らがこれを売ることにした判断基準は製品純度をあげることができず、ポ リカーボネート樹脂には使えない。せいぜいエポキシ樹脂にしか使えないだろうというものであった。 引葛さんが精製工程を改善すれば、ポリカーボネート樹脂にも使える可能性がある。価格も適正であるので買おうと提言してきた。木町さんも賛成して買い取る ことになった。それから研究所で精製工程の改良試験をすることになったが、プロセス設計部の後崎君が
「やぶからぼうにパイロットなどつくっても銭を失うだけである。不純物を含む循環系のシミュレーションモデルを造り、ど こにその不純物が濃縮するかを見定め、その部分だけの試験をすれば安く、早く改良研究ができる 」
と提案した。研究所は設計グループに主導権をにぎられるのが不満であったが、このスキームは私が夢に描いてきた研究開発 のやりかたである。おおいにこの方式をサポートし、研究所長の上町さんも了承した。 後崎君は手兵を引き連れて研究所に乗り込み研究所の連中と一緒になって実験に加わった。結局これは成功し、新日鉄化学が第一号プラントを買ってくれた。採 用の決断をしてくれたのは前田研究室の1年先輩のH氏(当時常務)であった。いまでもその決断に感謝している。 その後いくつも売れた。成功する技術開発のモデルといっても良いものをすべて備えていたから成功すべくして成功したのだと思う。キッカケを作った功績者の 引葛さんはしかしと関係していたバングラデシュにBOT(ビルド・ オペレート・トランスファー)で建設後操業中の肥料プラントの採算性が悪化していた矢先に、第三者のセメント輸送船が出荷桟橋に衝突して沈み、セメントが 固化して長期にわたりプラント停止に追い込まれた責任を負わされてか、率直な物言いをする人だったためトップの不興を買 ったのか役員を首になり、早々に会社を去ってM物産の関連会社に転職した。
競争激化のおり、志望して研究所に入った冶金出身の外畠君が、工事の合理化のために溶接に代えて摩擦圧接を採用すべきと 喧伝していた。フランジのボルト穴位置も所定の場所で止められる機械を開発できたという。たしかに摩擦圧接そのものは瞬時に溶接が完了するので大変生産性 が高い。しかし電気溶接器のような安価な投資ではなく、高価な圧接機械に投資しなければならない。稼働率さえ維持できれば有望な技術であるが、機械を現場 で持ちまわるにしても稼働率維持はむずかしい。そこで日本全土の溶接を一箇所に集中すれば稼働率を維持できるのでないかと九州のS運輸の倉庫で工業化する 案がもちあがってきた。太畠も投入して採算性を検討してもらったが、あまりよい採算性はみられなかった。内心は中断する決意で最終判断を先送りしていた矢 先、私がどこか海外出張している間に木町さんとジュニアで事業化のゴーをきめてしまった。そのうちにどうも外畠君のいう成功の歩留まりが低い、内バリ取り がうまくゆかない、薄肉がむずかしい、どうも大本営発表をしていたようなのである。特にフランジ穴を定位置にするということは絶望的らしかった。事実そう だと判明したのだが、もう車は走り出している。太畠を投入してなんとか改良の余地がないかサードパーティー メンバーとしてみてもらったが、これは駄目というのが彼の最終結論だった。それから溶接工法ではないので新技術には慎重な通産大臣の特認が必要というのも 足かせとなった。溶接の品質管理責任者も今後の品質管理に責任をもてないという。工事技術開発にかける上層部の期待も大きく、木町専務はこの期待の空気の 中でミスジャッジをしてしまったのだろう。 木町さんも最大のミスジャッジだったと自ら認められた。S運輸にも迷惑をかけているので、大変苦しい撤収作戦であった。
エンジニアリング会社は売れるプロセス技術を用意しておかなければ、単なるタタキ大工に成り下がり低コスト競争で疲弊する。あまり売れる技術ではなかった が、ポリマー技術ではBASF社とポロプロピレンのライセンス契約を結んでいた。あまり売れないので、表敬訪問してつなぐ必要にせまられルード ウィヒシャーフェンのBASF社を訪問した。アニリン合成成功にはじまる近代化学工業発祥の地たる老舗の伝統に感銘をうけたものである。 特に化学産業に従事している者にとってアンモニア合成反応の第一号反応塔は感銘深いものがあった。
ルードウィヒシャーフェン市はライン河の上流岸にあるが、この支流沿いにアルトハイデルベルグがあるというので出かけた。半壊した古城を持つ美しい町であ る。

アルトハイデルベルグ
創業社長時代から水素製造用スチーム・リフォーマーのライセンサーであったデンマークのトプソ社のメタノール製造プロセスは売れていなかった。そこで引葛 さんのリードでICI社のメタノール技術を提携した。トプソ社がイタリアのエンジニアリング会社、スナムの傘下に入ったこと、トプソ氏自身もご高齢になっ ていたことも気がかりでICIとの提携で保険をかけたつもりでもあった。ICI社は当然トプソ社のメタノール技術の放棄を求めた。デンマークのトプソ社は わが社が水素製造用スチームリフォーマーを日本の石油精製会社に沢山売ったので感謝していたのだが、少し気まずくなった。1991年、関係 修復のために 木町さんが出かけることになり、私はカバン持ちとして随行した。このとき、ICIの本社に立ち寄った。ビクトリア朝の古風なビルの外壁だけ残して内部を近 代的高層ビルにした、ボストンに多くあるような本社をはじめて訪問した。
トプソ社は1977年頃、コントラクターになりたくて海上フローティングガスプラントに手をだしたとき、要請されて私は積算の応援に駆け つけたことがある 。懐かしかった。80才を越えてまだかくしゃくたる、 トプソ博士自ら運転するベンツの助手席に乗せられて会食予定のレストランに向かった。高齢のドライバーがたそがれのモヤのなかの高速道路を高速で飛ばすの だ。思わず無事を祈ったものである。 コージーなレストランで奥様も交え、創業社長や森所さんとのなつかしい思い出話にひと時を忘れた。 夫妻はトプソ社が倒産の瀬戸際にあったとき、森所さんが飛んできたことを大変感謝しているとなつかしそうに語った。わが社が支援していたらスナムの傘下に 入らなかっただろうにという無言の言葉を聞いたような気がした。

フュン島のイーエス コー城
オレフィン・プロセスに関するライセンスも一言ふれておかねばなるまい。ストーン・アンド・ウェブスターとルマスに関わ る話はすでに第2章で ふれた。残るはCFブローンとケッログ社があった。CFブローンのプラントはサウジで経験済み、しかし、知的所有権問題をかかえていた。ケッログのプロセ スはナイジェリアで建設中であった。ある日ケッログが韓国と米国で建設したプラントが旨く稼動せず、訴訟問題に発展しているとの新聞報道を入手した。しか しその内容は簡単に解決できそうなものである。後崎君がケッログ社のミリセコンド炉のプロトタイプ炉の実験に深く関与したI石油化学の友人の思い出話を思 い出し、そこで考えた解決策をケッログ社に提示すると、即賛同が得られた。その対策を講じるとナイジェリアのプラントは技術的な問題もなく立ち上がった。 これで自信を深め、後崎君と一緒に
「オレフィン・プロセスは特定のライセンサーと心中せず、コントラクターに徹する」
という方針を頑固に主張する桃平副社長を説得し、ケロッグ・プロセスにコミットすることをシブシブ合意してもらった。この事件は二つの教訓を教えてくれ る。すなわちライセンサーのケッログ社ですら、キーパーソンを失うと肝心のノーハウが消失し、 まともに動くプラントを設計できなくなる。マニュアルは万能ではない。なぜそうしたかはマニュアルには書かれないからだ。そしてその書かれなかったノーハ ウは人が簡単に移動しない日本で、とある個人の頭の中で維持されていたということである。法的にはケッログ社にライセンス権利があるが、技術はモヌケの空 だったということである。 とはいえ”のれん”は大切である。まともに動くプラントの設計技術をもち、ライセンス権のあるケロッグを看板に掲げればよいのだ。 コンプリモのサルファープラントと同じ扱いにしたわけである。サブライセンス無しの”たたき大工”としてのコントラクターに徹すればプロジェクト参入チャ ンスは増えるが、価格競争の消耗戦を戦わねばならない。しかし、サブライセンサーとしての立場なら、不毛な価格競争を回避できるということである。ベクテ ルもLNGに関してはフィリップスのカスケード・サイクルにコミットして成功している。さて技術とは関係ないが、顧客のナイジェリアは産油国でありながら 破産国である。プラント代金回収には苦労した。
水素製造用リフォーマーはトプソ社、メタノールはICIという棲み分け、オレフィンはケロッグにコミットするというライ センスポリシーは結局正しかったかどうかはその後のわが社の受注成果を見れば明白だ。
サルファープラントのサブライセンスも似たようなもので、コンプリモというライセンサーの中心的エンジニアが高齢で引退すると残された人々はこの技術の本 質を理解しなくなる。むしろコントラクターのエンジニアの方が改良技術をもつようになる。この改良技術が原料ガス中に有機硫黄の多いカタールLNGプラン トの受注のキーとなる秘密兵器だったのだ。
もう一つ忘れられないことは自社開発の石膏法排煙脱硫技術を米国のベクテル社にライセンス供与する案件があった。ベクテル社は米国最大のコントラクターで 火力発電プラントは数え切れない程手がけている。もしこの契約ができていれば、計り知れない成果が上がったと思われるのだが、 当方がフレキシブルな思考ができなかったため、破談となった。わが社はライセンスと基本設計だけ、ベクテルが詳細設計以降の全てを担当して米国の火力発電 所のオーナーに石炭火力の排煙脱硫を売り込もうという企てである。基本設計料はプラントコストの数%である。しかし米国での商習慣では火力発電所のオー ナーは設計の瑕疵によって性能が出ないときはプラントの支払い金額の30%を免責の最大値として性能が出るまで補修する義務を課すことになっているとい う。貴社がこの条件を飲んでくれというものであった。ところが、石油や化学の商習慣では免責の最大値はライセンスフィーの50%であった。これを楯に頑固 一徹な法務部の低楢氏はノーといい、桃平副社長、木町技術本部長もノー、そして私もライセンス課長の耕平も皆、ノーであった。しかし今思えば、 わが社は性能保証で出なかったことは無いのだ。特に排煙脱硫技術は確立していて危なげなかった、仮にこれをのんでも実質は無害だったのである。教条主義に に陥っていて思考停止していたと今ははっきり分かる。そうして巨大な米国市場を失しなった。歴史にイフはないが、もし法務部にフレキシブルな思考のできる 段森法務大臣が残っていたら異なった展開になったかどうか?現在でも本件をベクテル側から仲介した元社員で、ダス島LNGプロジェクトで苦楽を共にした平 からは
「あなたを含め、千代田はどうしようもない思考停止の人間だらけだった」
と批判され続けている。その後、千代田はE社に排煙脱硫技術をライセンスし、巨大な中国マーケットに進出しているし、米国市場にもようやく再進出できたと 聞こえてきた。
このほかのライセンス技術管理、知的財産管理は殆ど契約事務や弁理士管理であるので耕平にまかせっきりで思い出すことも ない。発明保証システムの運営もしたが、大発明にめぐまれなかったので青色LEDのようなゴタゴタにも巻き込まれなかった。
木町さんの下では色々担当させられたが、IT担当もその一つである。俗にいうCIO(チーフ・インフォメーション・オフィサー)というやつである。米国で は都合悪くなると真っ先に首を切られる役回りとされていた。
わが社はIBMメーンフレームと端末の上で使うCADAM(CATIAの前身)というCAD開発のベーターテストサイトとなっていた。完成したCADAM は すぐれてはいたがコスト高で実用にならないことが判明しつつあった。丁度メーンフレームの限界が見えてきて時代である。エンジニアリングワークステーショ ン上で稼動する インターグラフというCADシステムが米国と中東で普及しはじめていた。これでは出遅れるとCADAMをすてて、インターグラフに乗り換えることにした。 この判断はその後の流れで正しかったのだが、トップダウンで決定したため、いままでCADAMを育ててきた社内の配管エンジニアには完全に背中を向けられ てしまった。 頭の中にある配管レイアウトをいきなりレイアウト図に描いてきた連中が新しいツールに遭遇してもその使い方は旧来の手順で使おうとするから生産性は上がっ ていなかった。むしろ面倒な道具でただきれいにアウトプットできると言うくらいの感覚であった。
このころ、配管設計の実務はもう社内では行っておらず、わが社の設計組合に加盟する中小の設計会社と台湾の設計会社に発注していた。まず台湾の設計会社は 配管設計だけの下請けはじたいすると申し入れしてきた。また設計組合のリーダー達は手描 で配管設計をしていた経験しかない。従ってそもそもCADには無関心だった。CADAMなどIBMのメンフレームすら見たこともない想像外の世界の出来事 だった。そこへエンジニアリングワークステーションを導入してインターグラフのCADを使えといってもまだ無理だった。そもそも米国で開発されたツールはプラスティックモデルで配管設計をしていた米国の設計 手法を三次元CAD(3D CAD)に置きかえたものである。日本では生産性の上がる使いかたに頭を切り替えさせることはかなり困難だと感じた。
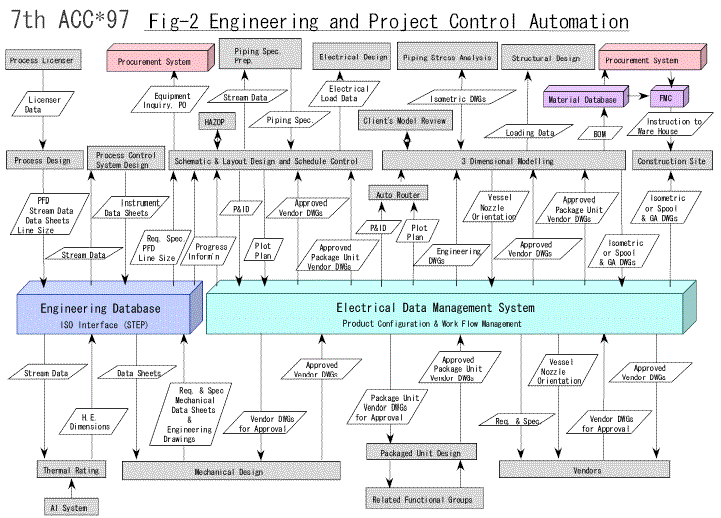
当時のエンジニアリングシステム
そうこうしているうちにパソコンで動く安い国産のCADも出てきて、彼らの興味はそちらに動いてしまった。もう設計ツールの共通化など無理となった。イン ターグラフは当面社内でP&IDのドラフティングに使うという情けない事態となった。CADAMに未練を残す配管のベテランエンジニアは依然イン ターグラフには背を向けて郷愁の世界に閉じこもったままである。ところがCADAMには思いいれのない若い世代の一人の配管エンジニアが配管設計にイン ターグラフの3D CADを使ってみて、意外に生産性のよいことを証明してくれた。こうして新体制はようやく動き出すが、1995年中ごろの安値受注殴りこみによるわが社の 歴史上最大の受注量をこなせるようになるには遅すぎた。
競争相手のN社がフィリピンに設計拠点をおき、T社がインドに設計拠点をおいて成功しているという話が伝わってきた。わが社も発展途上国に設計拠点をもつ べきではないかと直属の上司の木町技術本部長に提言した。しかし彼はネガティブであった。
それでも時の勢いには逆らいがたく、商社の紹介でフィリピンにフィリピンの設計会社と合弁の設計会社が設立されることになった。少し遅れてインドでデン マーク人のラーセンとターブロ氏が設立したエンジニアリング、機器製作企業であるラーセン・ターブロ社と合弁の設計会社を設立する ことになった。当然インターグラフを投入した。(現在はオートキャド社に吸収合併されている)
その開所式に出席するためにボンベイから社用機で1時間の距離にある設計事務所に出かけた 。若い社員達は明るい未来に期待して目が輝いていた。私は景気の良いときはよいとして逆境のとき彼らを養ってゆく義務もあるわけで、気分ははれなかった。 またホテルから1歩出ると貧しい子供達に取り巻かれるため、ホテルに軟禁状態であったなど不自由な経験をした。それになにより道路の真ん中に横になる牛達 をよけて車が通らねばならないことも憂鬱になる原因だった。しかしこのインドでの設計拠点の業務開始が正解で一時期競争力低下で苦しんだ千代田を救うこと になる。日本国内での設計は最早高い人件費で不可能になり、近代的ツールをつかいこなせない老齢化した名人芸的設計職人を排除せざるをえないということを 意味した。
東大の工学部での講演を頼まれていていたとき、リファイナリープロジェクトを追って数日の出張をしたことがある。講演に間に合うようにエアインディアの ジャンボ機に乗り込んだのだが客が少ないとしてフライトがキャンセルされてしまい往生した。講演会に招待してくれた先生に迷惑をかけてしまった。
こうして国内の設計組合がCADに背を向けたままでいるのにフィリピンとインドの設計会社遅まきながら動きだすのである。現地の若いエンジニアは3D CADに何の違和感もなく素直に使ってくれる。教えるほうも、職人芸を教える必要はない。設計ルールはプログラムにビルトインされている。機械の操作法を 教えればそれ以上に手取り、足取り指導しなくとも3D CADが描くモデルを見れば一目瞭然なので自然に設計能力が身につくということが判明した。
だがこの海外設計拠点も桃平社長のもとでの1995年ごろの無謀な低コストでの受注しまくりの結果としての空前の受注量を処理出来るようになるまでに育て るには少し時間不足であったのは後に非常に慙愧に思うことになるのである。
IBM/富士通メーンフレームー端末から1人パソコン1台のパソコン時代への移行期間をリードするに当たり、当時の DOSはまだエンジニアリングの生産性の向上には貢献しないと思った。デスクトップメタファーの概念の導入に成功したマッキントッシュに興味を持ち、個人 でこの高価なマシンうを買うために自家用車を断念し、70万円を支払って買い求め、使ってみてこれならいけると確信した。しかし私には社費で全員に買い与 える予算を新に確保する説得材料もなかった。そこで社員が納得して要求の声を出すようにしようと考えた。 木町さんもパソコンを一人一台づつ使う生産性向上をするには全社員がキーボード・アレルギーを払拭しなければだめだとの認識を持っていた。兎に角、皆に 使ってもらい、その効用を知ってもらうためには個人に 機種選択の自由度を与えようという私の提案に異議はなかった。そこで閉鎖的なNECを除く、IBM AT系のDOSマシンはメーカーにかかわらず、これにマッキントッシュを加えて個人購入パソコンを会社に持ち込んで使ってかまわないことにした。同じ考え をもつ多数の個人がDOSマシンよリ高価なマッキントッシュを会社に持ち込み、その有効性を皆に伝えた。買えない若年層にはIBMメーンフレーム/端末系 の予算を浮かせた枠内で順次会社DOSとマッキントッシュを買い与えることができた。こうして一時は2機種が混在する環境となった。そうこうしているうち に、DOSが進化してウインドウズ95となり、マッキントッシュと同じ使い勝手となった。以後会社が導入する機種はウインドウズ系に統一 できた。毎年減り続ける予算内でこれを達成したことに満足している。
木町さんが指揮する技術本部は営業が受注目標をするプロジェクトが幸運にも受注できたらヒューマンリソースをどう確保するか予想する必要に迫られていた。 そこで1980年代のエンジニアリングの生産性を売上高と消費エンジニアリングマンアワーから逆算し、プロジェクト横断的に一定の値であることを確認し た。これは使えると考え、 営業の受注量予想にこの生産性を適用して必要マンアワーを予測することにした。すると技術本部所属のエンジアでは足りないという結果がでてしまう。それも 1980年代よりプラントの建設単価が下がっているにもかかわらずにである。メーンフレームに毎月蓄積される実使用マンアワーのヒストグラム (時系列に並べた棒グラフ)を前月までについて作り、これに今月からの予想マンアワーのヒストグラムをつなげると段差が出来てしまう。このまま社内に配布 すれば、折角1980年代より生産性を高めて競争力を出そうという運動に水をさすことになる。 木町さんにどうするか判断を仰いだ。目標生産性(どのような名前にしたかは記憶がない)とでもいうファクターを作り、このファクターで予想値を割り、不連 続をなくしたヒストグラムを作って社内に配布しようということになった。自動的に作図するプログラムも簡単に開発できた。無論目標生産性はそのヒストグラ ム上に数値として表示した。
しかし社内の人々は目標生産性として月々表示される地味な数値には注目せず、多色で印刷されたヒストグラムの形にのみ注目した。 一番喜んだのは桃平社長であった。本業不振で異分野に展開した営業本部は目の色を変えて受注予想の多さを競うようになった。営業が受注目標とするプロジェ クトはヒストグラム上では将来到来する波のピークとして表現されるが。そのようなピークは失注によって消え去り、ピークは常に沖に向かって崩れ、津波のよ うに襲ってくることはなかった。 桃平社長はこれを楯に毎月営業の尻をたたきはじめた。営業としてはこれが不満で、翁川さんなどはこんなものの配布はやめてしまえと、怒鳴り込んでくるしま つであった。木町さんは継続しろという。 利益率はそれぞれのプロジェクトが苦しさを隠して楽観的な予想をあげるので本当の利益率はプロジェクトが完成しないとでてこない。完成まで3年のタイムラ グがあるのだ。社長みずから採算度外視して受注に狂奔する姿をみることになる。今になって思えば、このヒストグラムほどミスリーディングな経営情報システ ムはなかったと自戒している。なぜならこのヒストグラムには設計品質が反映されていないからである。 可視化はインパクトが大きい。しかし中途半端な導入は弊害あって一利もなかったと反省している。人間組織は柔軟なもので、オーバーロードになる位に仕事を 与えられたエンジアは出来ないといったら身の破滅と思っているから、出来ないとは言わず、サブコントラクターに無理に押し込んでしまう。サブコントラクタ は仕事を失いないたくないから断らない。結果として設計品質は低下し、現場での手直し、材料の過不足となって後日、顕在化するのだ。このように設計品質の計測に もタイムラグがあるのだ。迅速を旨とする経営情報システムに取り込むにはもう一工夫必要であったのである。これに気がつくにはまだ時間がかかっ た。
千代田は制御システムを含むプロセスプラントを設計建設する企業である。日本のF電機が光ファイバーをつかったフィールドバスを情報伝達系とする制御系を 共同で販売したいという提案でつくった販売子会社が思ったように売れないので、どうしたものか相談を受けた。聞いてみると、情報系は光で問題ないのだが、 フィールド計器に電力を送る手段がなく、当時はバッテリー容量も小さく、 顧客には2年に一度のバッテリー交換が煩雑と受け取られたようだ。私は各ノードの接続、分岐を100%光系でやろうとしたところにフレキシビリティーが欠 ける問題があると判断した。光によるエネルギー逆搬送も提案したが、F電機にはそのような技術開発の意欲はないようであった。コスト低下には量産が必要だ が、2社だけの閉鎖系で商売をしようとしたため、量を確保できなかったのも敗因と判断して、販売会社解散もやむをえないと判断した。その後、バッテリーの 能力も向上し、F電機はこの技術で細々と営業しているとのことである。
会社の蔵書はかなりのもので大変役に立ったものである。私は入社以来、マニュアルのない新しいことに挑戦してきたため、必然的にもっともお世話になった一 人と思う。しかし間接費の重みを減らさなければ国際的な価格競争力がつかない。不要な雑誌と余剰人員を削減することになった。図書館長の造川さんは大学の 先輩でダス島のLNGプラント建設現場の図書の選 定の仕方をみれば教養あふれる文人という風情だし、サムエル・ウルマンの”青春の詩”などを翻訳して角川文庫から出版していた人で あった。しかし図書館の重要性を主張して頑として抵抗する。言われなくとも分かっているのだ。しかたなく 図書館長を降りてもらった。”泣 いて馬謖を斬る”という言葉があるがやむをえない。しばらくして彼は 会社を去った。彼の逗子の自宅の壁は造りつけの書棚になっていて天井まで本で一杯だと聞いた。
その後のインターネットや電子情報化により紙の情報伝達量は急激に落ちている。この痛みを伴った改革は多分正しかったのであろう。 その後、本人と再会して逗子のお宅の造りつけの書棚の話になったが、ほとんど整理してしまったとのことであった。
社会的要請にこたえるべく企業は環境への配慮を示す必要にせまられた。経済団体が編成する環境委員会に参画を求められ、環境担当という役目をおおせつかっ て、1991年10月より2年間 経団連環境部会国際環境タスクフォース委員、1992年8月より経団連環境部会環境基本問題検討ワーキング・グループ委員、1992年11月(財)日中経 済協会環境委員、1992年12月より3年間(社)日機連環境委員会副委員長などを勤めた。
1992年、ブラジルで環境サミットが開催された。私が環境担当だからと経済団体のミッションに加わる要請がきた。しかしお祭り騒ぎにフィーバーするのは むなしいと上町さんに代理参加を頼んだ。彼はアマゾン中流域にある町、マナウスへのツァーに参加してインディオ達と環境問題を語りあったらしい。
まだ木町さんの副官をしているとき、ヨーロッパ発の品質保証システムのISO9000シリーズの品質保証の認証取得の指揮を途中からとることになった。上 町氏が指導し、全社を動かして作成した膨大なマニュアルを引き継ぎ、審査官の審査を受けた。イギリス人の審査官はこのマニュアルを読むと、
「貴社はまとまった一社のようには見えず、各部門は独立した企業のように定義されている。このままでは認証はそれぞれの独立組織体毎に行うことになるが、 それでよろしいか」
とのお言葉である。それはまずい、書き直すので数ヶ月後に再審査をお願いすることになるのである。審査官は続けて
「貴社のマニュアルは詳細すぎる。このようなマニュアルではニッチモサッチもならなくなるよ。もっと簡潔にしなさい」
という。
このような事態になったのは上町氏のミスリードだったのだがやむをえない。今回はしっかりと指導させてもらい、数ヶ月遅れで初取得できた。
リクルート活動
その他
わが社は海外でプロジェクトが主流となっていたために動乱にまきこまれる経験をしている。古くはイランのホメイニ革命で、完成させたばかりの巨大化学コン ビナートを棄てて国外脱出するときにバスが銃撃される経験をしている。
父ブッシュのイラク侵攻の時はサウジで完成させたばかりの空港が米軍の出撃基地になった。日本の企業が逃げ出すなか、元請のベクテル社から安全は保証する との約束でそこにとどまり、通過パスポートをもらって米軍基地と化した空港の燃料設備と電気システムの維持に携わった。帰国した電気技師から司令部の管制 センターの最新式設備や垂直に離陸する英軍のハリヤー戦闘機の飛行の模様など興味深く聞いたものである。日本の新聞は脱出してしまっていて、このようなこ とは知るよしもないので報道もされなかったが、外務省は大変感謝して大使みずから陣中見舞いをしてくれた。
このような縁でか、外務省で情報担当だった、元岡崎大使が退官後、わが社の顧問に就任され、定期的に国際関係を解説してくださった。氏が繰り返し、述べら れたのは日英同盟を破棄したのが最大の失敗で、そこから太平洋戦争への道をたどるようになったという点である。今の外務省はこの教えを守って米国ー英国ー 日本の同盟関係を重視してうごいているようにみえるが、子ブッシュの愚かさのおかげで、岡崎大使の教えに陰りがでているのは残念なことだ。
元朝日新聞記者だった飯沼和正氏が書き下ろしの戦後の日本の技術史に渡末君の作成した企業年表を加えて創立50周記念の 小冊子を出版したこともあった。 女子ゴルフコンペのスポンサーになるより、適切な企画だったと自負している。2006年になり、森永氏やキリスト者という縁で飯沼和正氏と知り合った元会 社同僚や朝日新聞で同じ釜のメシを食った高校の同期生から飯沼和正氏のことを聞き及び、世の中は狭いと感じたものだ。
February 27, 2005
Rev.September 11, 2016