| 橋本康男のトップページへ | 参考フレーズ集 | 駄文抄 | 遊びのページ | English Page | 広島大学での4年3か月 |
|---|
2014年12月28日
一昨日昨日と,ふるさと枠(県からの奨学金を受ける医学生)や自治医大の学生等を対象とした地域医療合宿セミナーを実施しましたので,今日から年末年始休暇です。県庁を退職して念願だった地域医療の仕事を得て2年目,成果評価は別として充実した1年だったと思います。
個人的な活動としての研修講師も,自治体職員研修や保健医療圏の研修に加えて復興途上国などの外国政府職員研修が増えていますし,最近は地域づくりの話も依頼されています。日赤広島看護大学の社会人大学院生への非常勤講師としての講義も少しずつ増えていて,新たな経験をさせていただいています。
こんな経験を通じて,改めて社会人対象の実践的な人材育成への取組みの広がりの必要性を感じています。高等教育機関としては大学がありますが,基本的には二十歳前後の学生たちを対象とした教育経験が主であり,社会人教育に体系的・継続的に取り組んでいる訳ではありません。広島大学に転職していた時にも,学内では,「二十歳前後の学生を対象にキャンパス内で教育しているだけではなく,現役社会人も重視したキャンパス外にも広がる継続教育に広げていくべき」と主張していました。
自分自身,両方の教育に関わってみて,二十歳前後の学生を対象とした知識教育と,社会人を対象とした実践教育との違いを感じています。それには,知識研究と実践経験との違いもあります。
一言で言えば,「こうすればいいのだ」と「どのようにすればそれが実現できるのか」との違いのようにも思えます。実践現場では,「こうすればいいと言うこと」と「それを実際に実現すること」との間には子どもと大人ほどの違いがあります。「自分の気が済むこと」ではなく,「社会の課題が少しでも改善していくこと」を行動基準においていける人材育成が求められているように感じています。
この一年間,この「ひとり言」をお読みいただいたみなさま(というほど多くはありませんが)に感謝申し上げます。限られた人数とはいえ,お読みいただいている方がいらっしゃることに元気をいただいています。ブログにして双方向の動きを生み出すというのもSNSの時代にはあると思いますが,「交流」から離れて静かに考えてみる時間も大切なようにも感じています。ということで,もうしばらくはこのスタイルで自らのつぶやきを書き留めていきたいと思います。
この1年間お付き合いいただきありがとうございました。みなさま方にとって,来年が良い年でありますように。
2014年12月21日
先週からずっと,1月に頼まれているフィリピン・ミンダナオとスーダン・ダルフールの行政職員研修の資料づくりに悩んでいます。とはいっても,本業の方でも,かなり思い入れのあるプロジェクトの立ち上げの大事な局面ですので帰宅後の夜と早朝の話ですが。,
いつもは以前作ったものをざっと見直して気付いた部分を少しずつ修正する程度なのですが,今回は依頼側の担当者と2
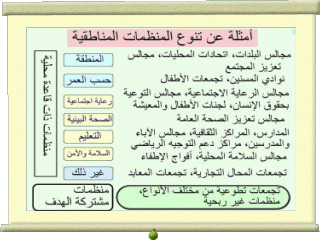 時間ほど議論をして何が必要かをまとめたものに従って全体の見直しをしていますので,思いのほか時間がかかっています。結局,パワーポイントの画面でほぼ100枚ほどになってしまいました。この英文にネイティブチェックをかけてもらうことになります。
時間ほど議論をして何が必要かをまとめたものに従って全体の見直しをしていますので,思いのほか時間がかかっています。結局,パワーポイントの画面でほぼ100枚ほどになってしまいました。この英文にネイティブチェックをかけてもらうことになります。先週のイエメン政府職員研修は,受講者がアラビア語とのことで久々に通訳を介しての講義でした。8年前に初めて外国政府職員研修を頼まれたのがカンボジア政府職員でその時も通訳付きだったのですが,なぜかその後の30回ほどは全て英語でしたので,久々の通訳付きというのでちょっと緊張しました。もちろん日本語で話す方が楽に決まっているのですが,相手に思いを伝えるという点では直接に語りかける方が手応えがあります。
とはいえ,今回は通訳の方が素晴らしく,また,私も少しは通訳を介しての対話に慣れてきた?こともあり,手応えのある時間でした。単なる知識や技術だけではなく,行政職員としての思いやめざすもの,姿勢なども交えてお話しさせていただいたのですが,質疑応答の時間に,わざわざ手を挙げて「実務経験に根ざした話だったのでとても良かったと。」言っていただきました。
また,質疑の中には「自分は30年間○○省で働いているが職場の中にはなかなか前向きに話を聞いてくれない人もいるが,どうすればいいのか?」といったようなものもあり,いつもながらお役所仕事は世界共通と苦笑したところです。
話の種に,アラビア語に翻訳していただいたパワーポイントの画面をご紹介します。
2014年12月13日
ガバナンスの原稿の校正が済みほっと一息ついたところで,来週から1月末にかけて4本頼まれている外国政府職員研修の準備に悩んでいます。ここ何年にもわたり30本ほど経験はしているのですが,折角の機会なので帰国後の取組みの役に立つものを提供できればと思うと簡単ではありません。
何でもあるのが当たり前という今の日本の行政の状況と,混乱の中から自分たちの国を作り上げようとしている人たちの状況は大きく異なります。規則はこう要綱はこうなどと決まり事を振り回し自分は間違いのないことをやっていると役人風を吹かせているだけでは何も生まれません。ルール自体を生み出していくことから始めなければならないし,何よりも,汚職やコネなどが蔓延しがちな環境の中で,未来の自分たちの国のために今自分たちがなすべきことは何かというある面青臭い理想を大真面目に掲げて力強く前に進もうとする人たちがいなければ,未来は生まれません。
これは,実際には日本の社会や組織でも同じなのだと思います。決まったことをきちんとやる人はもちろん必要ですが,それだけでは未来は生まれません。なぜ何のために何をめざして今何をしなければならないのかを考え行動する人が必要です。しかしながら,往々にして,そんなことは考えず目の前の箸の上げ下ろしにばかりこだわる行動様式の方が一見安定してもっともらしく立派に見えてしまうこともあります。
そんな中で,いじけずふてくされもせず,弱気になりそうな自分を精一杯励まして,孤独に耐えて変化を生み出していくことのできる人が求められています。そんな人たちの励まし合いの仲間も必要です。
楽ではないけれど楽しい仕事,というのは,当たり前のことをしたり顔してもったいぶってやるよりも,不安におびえながらも道のない方向に踏み出していくスリルと緊張感のある仕事のように思えます。自分が周りの人や組織の力をつないで何か新たなものを生み出すことにささやかでも貢献できたかどうかが,自分の仕事の納得につながっていくのだと思います。汚職や守旧派が少なくない厳しい状況の中で社会の未来のために戦わざるを得ない人たちに,少しでも前に進む力になれたらと思っています。その難しさと厳しさは,どこの国であっても同じなのですから。
2014年12月6日
あっという間に12月です。
先週も書いたように,今回初めて自治体職員向けの雑誌に「組織間連携とコーディネート力」という私の関心領域のど真ん中のテーマで原稿を書かせていただく機会を得て(これまで「対話力」や「組織内連携」などは書かせていただきましたが),また本業でも,無から新しい組織間連携のシステムづくりに取り組んでいることもあり,このあたりのことを考える機会が増えています。
その中で感じるのは,新たなことを生み出そうとする時に,軸というか,軸と言うよりもむしろ軸受けの役割の大切さです。いろんな回転や動きが生まれそれらが一つの目的に向かった動きに収れんしていくためには,その回転軸を定めていく軸受のようなものが(主役ではありませんが)大切になります。
そんな軸受けには,どんなことがあっても揺らがずブレないことが大切になります。自分の気分によってぶれたりせず,周囲の環境や事態の展開に一喜一憂したりせず,じっと軸受けの役割を担う存在がなければ,しっかりとした事業は育たないように思います。
新たな取り組みはうまくいくこともいかないこともあります。そんな時に,軸受けが自分の気分によって揺らいでしまえば,全体の動きが一つにまとまっていきません。晴れの時も曇りの時も雨の時も,じっと軸受けの役割を担っていける存在があって初めて,様々な力が一つになれるのだと感じています。
私は,「雨も天気のうち」という言葉を思いついて,うまくいかない時の慰めにしています。晴れの日ばかりじゃないし晴れの日ばかりでは困ります。雨の日だって必要なのだから,そんな日とうまく付き合っていくことも大切です。雨の日は雨の日なりに,折り合いを付けて楽しんでいきたいものです。
続いていくことが大切なのだし,明日を思う心が持ち続けられることが何より大切なのだと思っています。
2014年11月29日
本業の方の動きがあわただしい上に,個人的な頼まれごともいろいろあって,気ぜわしい師走です。
トップページでも紹介させていただいていますように,地方自治体職員向けの雑誌『ガバナンス』にこれまで「対話力」「組織内連携」「新任課長へのメッセージ」を書いていますが,来年1月号に「組織間連携とコーディネート」を書かせてていただけることになりここ何日か原稿作成に没頭していました。私にとってはもっとも関心のあるテーマであり,長年意識的に取り組んできたことでもあるので集中しました。
このような原稿作りの機会は,編集者の方とのやり取りで気付くことも多く面白いものです。今回は,私が「組織間連携とコーディネート」は新しいものを生み出すためのもの,という思い込みでいたことに気付きました。実際,私自身そう思ってやってきましたが,冷静に考えてみたら,組織間連携は何も新しいものを生み出すためだけのものではなく,今の仕事をよりよくよりスムーズに進めていくためのものでもあるのだと思い至りました。
そういうことは,(実際には無意識にはやってきたにしても)これまでまったく考えたこともなかったので,とても新鮮でした。つまり,普段の仕事をスムーズに動かす組織間連携は,わざわざ意識しなくても当然にすることであり,私は,社会課題を解決するために新たなものを生み出そうとする時にのみ「組織間連携」に意識的を集中して取り組んできたということだと思います。
草稿を書き終えた後のやり取りでそれに気が付いたため,今回は「新たな組織間連携を生み出すコーディネート力」という限定を付けさせていただくことにしました。別に,新たなことでも既存のことでもやることにさほど変わりはないのですが,今回は新たなものを生み出す難しさとそれを突破し実現するための留意点に力を入れて書いたので。
実はこれは今朝の通勤電車の中で気が付いたのですが,こんなところにも思い込みがあるのだという意外感と,「組織間連携」といえば新規の取組みと思い込んでいた自分がおかしくて一人(心の中で)笑ってしまいました。
2014年11月22日
何かと気ぜわしい日々が続いています。本業の方がドタバタしているのに加えて,今日午前中は日赤広島看護大で大学院の医療福祉行政論を2コマ,12月には障害のある人たちの就労支援をされている方々を対象とした講演会とJICAのイエメン政府職員研修もあり,1月には,フィリピン・ミンダナオ自治政府職員研修にスーダン政府職員研修,熊本県自殺対策企画研修と続くので,なんとなく落ち着かない気分です。
今日の日赤看護大の授業は,実務経験のある社会人大学院生ばかりなので,話が通じやすくて楽しくやらせていただきました。現場で苦労している人たちと,現場の問題をどのように解決していくのかを話していくのは手応えがあり楽しいものです。このような社会人対象の継続教育の機会がもっと増えればいいと考えていますし,私自身もこれまでの経験を生かしてそれに参加できたらと願っています。もちろん,現役として実際の事業活動に参加しながらですが。
また,先週は自治体職員向けの雑誌への「組織間連携とコーディネート力」をテーマに原稿依頼をいただきました。これまでも「対話力」や「組織内連携」などについて書かせていただいたことはあるのですが,今回は私自身の中心的な関心分野ですので,ちょっと力が入っています。まあ力が入れば良いものが書ける訳ではないので,ほどのよい力の入れ方が必要ですが。
明日は本業の方での勉強会があり,気ぜわしい週末です。
2014年11月16日
昨日は,朝5時過ぎから友人の船で久々の釣りに出て昼過ぎに寄港後もなんとなくドタバタで終わってしまいました。
最近,本業の方が何かと業務が詰まっているのでいい気分転換でした。いろんな仕事をしてきて,仕事にも満ち潮引き潮の時期があるように思います。この満ち潮の時に大事な仕事が動くことが多いので,それを逃さずに対応できるように準備しておくことが大切だと感じています。
普段,無駄な動きを減らしておいて,大切な時に集中して継続的にエネルギーを投入できるかどうかが長い目で見た成果を決めるように思います。
比較的暇な時には,無駄な仕事に手を出さないようにして,将来に備えた必要な準備をしておく,というのは理屈ではあっても実際にはなかなかできないものです。そんな一つひとつのことが実践できるかどうかが,仕事の結果を決めていくように感じています。
とりあえず,これまでの準備の積み重ねが実際の変化という成果につながっていくように,集中して取り組んでいきたいと思います。
2014年11月8日
4日間の週ということもあり,あっという間に過ぎました。というより,本業の方でいろいろ動かさなければいけない時期に来たということでもあります。いろんな仕事をしてきてみて,仕事の呼吸というか緩急をうまくコントロールしていく必要性を感じています。
地道に足固めをするべき時にジタバタ焦っても仕方ないし,動くべき時にそれを見過ごして漫然と時間を過ごしてもいけません。そのあたりの呼吸をつかむのは簡単ではないと感じています。もちろん何が正しいかを考えていても仕方なく,動くべきだと感じた時に動くしかないのだと思います。
このほかに,外国政府職員研修が4本と日赤広島大学大学院の授業が2コマ,年明けには熊本県での自殺対策企画研修の2回目があります。特に,大学院の授業については,理論研究と実践経験をどう組み合わせていくのかという年来の課題に関わるものですので,真剣に取り組まなければと思っているのですが,なかなか前進しません。実践経験だからといって体験談だけ話せば良いという訳もなく,どう受講者一人ひとりの実践の役にたつ講義をしていくのかは難しい課題です。
研究者としての講義であれば,「間違っていないこと」「理論として一般に認知されていること」を知識として伝えれば最低限の責任を果たしたことにはなります。(もちろん,講義にはピンキリがあります。)
研究による知見と実践による知見の相乗効果を生み出す社会人教育とは何なのかを考えていきたいと思っています。
2014年11月3日
金曜日夜から上京して,自治医大の地域社会振興財団主催の「健康福祉プランナー養成塾アドバンストコース」の開講オリエンテーションと講師をしてきましたので,定例の?土曜日に書けませんでした。この「健康福祉プランナー養成塾」は今年で開講以来16年連続で講師をさせていただいています。
地域の保健・医療・福祉の連携を進めるコーディネーターを養成しようとこの養成塾を企画されたのは自治医科大学の坂本敦司教授であり,その先見の明と実現にまで持ち込まれたご努力に敬服しています。その後16年にわたってこの養成塾が続いているのも坂本先生の熱意の故だと思っています。私は,17年前にこの財団主催の三重・奈良・和歌山三県のへき地医療フォーラムにお招きいただいてお話しさせていただいたのがこの坂本先生との出会いなのですが,このようなご縁をいただいた幸運を感謝しています。
シンガポールとの学生交流は22年続けているのですが,講師を16年続けるというのはまた別の重みがあります。毎年講義をすることは,毎年何か新たなものを加え工夫していくチャンスをいただくことにもなります。
今回も坂本先生とお話しする中で,健康福祉プランナー養成塾は講師も養成していると申し上げたのですが,私自身については実感です。まさに養成塾に育てていただいていると感じています。
毎年,全国各地から集まってこられる熱心な方々に触れさせていただくことで,自分自身も襟を正し真剣に取り組まなければと思いを新たにさせていただきます。自分がめざしたいものがあることそしてその中で自分ができる可能性を追求していくこと,が何より大切ですし,幸せなことだと思います。他人の愚痴を言い批判をしていても,何も生まれません。前に向かおうとしている仲間と出会い,思いを共有することが何よりの幸せだと感じています。
2014年10月25日
新しいノートパソコンを買いました。広大時代からずっとパナソニックのレッツノートを愛用していて,代々その中でももっとも小さくて軽いものを選んでいたのですが,ここ数年,一番軽い1kg未満のタイプが無くなってしまっていたので,ここ数か月ほど旧ソニーのVAIOなど他社製に切り替えようかどうしようかと悩んでいました。レッツノートのホームページを時々眺めていたのですか新製品情報もなく,諦めかけていたところに,たまたま新製品の発表日にそれを見つけてすぐに予約しました。
先週末に届いて設定とファイルの移動も終えて,来週末にある自治医大の地域社会振興財団主催の「健康福祉プランナー養成塾」で実戦デビューです。使ってみて,我慢できずに他社製を買ってしまわなくてよかったとしみじみ思っています。
研修講師稼業が多い私としては,本とパソコンには結構投資をしています。その中でも,ノートパソコンは,(実際にはどれでも大差はないとはいうものの)やはりこだわりの対象です。自分が満足できる道具を使えているかどうかは,気分に関わります。厳しい局面や緊張する局面では特にそうです。県の国際部長時代に知事の随行で緊張感の高い海外出張に出ていた時にも,手元の小さなノートパソコンが気持ちを支えてくれたような気もします。ということで,満足できる製品が出るまで待って本当によかった。待つこと,というのも大切ですね。
2014年10月18日
今年は,5月と6月にフィリピン・ミンダナオ自治政府立ち上げの職員研修に声をかけていただき,6月はしばらく休止されていた立命館大学のインドネシア政府職員・大学教員研修が4年ぶりに復活し,7月には3年目となるJICAの紛争影響国政府職員研修があり,国際から離れても声をかけていただけるものだと喜んでいましたら,9月にはJICAから12月のイエメン政府職員研修の依頼をいただき,昨日は同じくJICAから来年1月のスーダンの地方行政職員研修に声をかけていただきました。一番最初にこのような復興途上国の政府職員研修の声をかけていただいたのは,平成20年のJICAのカンボジア政府職員研修でした。それまで,日本に招へいした研修員に対して日本の地方自治についていろんな講義をしてもどうも地方自治自体の理念が伝わっていなければ知識だけではダメなのではないかとの反省がありその部分を担当してほしいとのご依頼でした。
以来,7年間で累計30回になります。このような機会をいただいて感じるのは,やはり原点を大切にして真摯に正面から向き合うことの大事さです。アフリカ,南アジア,南アメリカなどの厳しい状況におかれた国々の政府職員の人々に対して,豊かになって飢えの怖れや汚職の誘惑もなく「普通に過ごせる」という恵まれている日本の行政職員の感覚で知識や現状を説明しても,それだけでは彼らにとって手の届かない別世界の話で終わってしまいます。
どんな開発段階の社会においても,そこに住む人々がより幸せに暮らせる社会を築いていくためには,それぞれに困難や悩みがあり,それに一つひとつ立ち向かっていき現実の変化や改善を生み出していくためには,行政職員の一人ひとりの覚悟と努力が必要なのだ,ということを共有していくことがなにより大切だと感じています。
そのような話をさせていただくことは,何より自分自身への自省の機会でもあります。今日の食べ物や明日の命の心配をせずに,今の職を維持するために賄賂を贈る必要もなく汚職への誘惑と戦う必要もなく,ただ自分の仕事をすればいいという恵まれた状況の中で,その恵まれた状況にふさわしいだけの努力を日々積み重ねているかどうか。どんな社会も,今よりもよりよい社会のために努力をしたいと思う行政職員や住民の力がなければ,崩れていくのだと思います。
"To Have or To Be" 何を持っているかではなくどう生きているのか,を問いかける言葉です。いつも外国政府職員研修の最後のまとめに使っています。
2014年10月11日
相変わらずドタバタしています。その中で,仕事の成果について考えることが増えています。目の前のことにエネルギッシュに取り組む,というのももちろん大切なのですが,それだけでなく将来を見据えて本当に責任のある仕事をしているのかということを考えていくことも大切です。今のことだけ考えて走り回ってしまっていて,将来起きる問題を考え「今」の時点から打つべき手を打つという対応をしていなければ,将来その仕事を担当する人々に対して無責任ということになってしまいます。
こう書いてしまえば当たり前のことなのですが,長年組織で仕事をしてきてみて,これが意外にできない,難しいことだと感じています。常に意識していなければ,目の前のドタバタに振り回されて視点を変えることができないものだと感じています。
10年近く前に三次市の行革審議委員会の会長として基本理念を議論していた時に,当初「透明,参加,効率」が基本だろうと委員の皆さんと話していました。その頃に,駐日シンガポール大使と一等書記官と3人で夕食をとる機会があり,この話をしたところ,「効率」よりも「優先度(Priority)」が大切ではないかと言われました。効率を上げても優先度が間違っていては仕方ないということです。この話はこれまでも何度も書いてきましたが,本当に考えさせられた良い経験でした。シンガポールの通産省と外務省の事務次官を務められた大使ならではのご助言だと感謝したところです。結局,三次市の行革の基本理念は,「透明,参加,選択」ということになりました。何を優先すべきかの選択を大切にしようというものです。
エンジンを回しているだけではなく,ハンドルも大切ということですね。年度の折り返し点に立ち,チームのみんなが安心してそれぞれの担当の仕事に集中できるように方向性と優先度を間違わないようにしなければと考えているところです。
どれだけやったか,よりも,何をやったか,を意識しながら取り組んでいきたいと思っています。
2014年10月4日
あっと言う間に10月です。年度の半分が過ぎてしまったので,今年度の成果について考えざるを得ません。目の前のことだけ見てドタバタと忙しい気分になっていても本質的な成果が挙がる訳ではなく,長期的な戦略を考えている気分になっているだけでも現実の行動が伴わなければ仕方ないし,難しいものです。とりあえず最低限必要なことはチームのムードを維持し高めていくことだと思いますが,それだけで十分な訳でもありません。
今までとは違うことをどうやって生み出していくのか,現実のものとして実現していくのかが問われているし勝負なのだと思います。そういえば現実をひっくり返すことが実現なのですね。
私の場合,理数系を得意としながら,高校の文化祭の事務局長をやった経験などから,いろんな人たちと一緒に社会に関わる仕事をやりたいと思って行政を選んで,結果的には恵まれたキャリアをたどることができたと思っています。でも,それは,あえて言えば過去をそれまでの蓄積と実績を捨てて勝負することができたからだとも思います。そうするためには,ある面での乱暴さも必要になります。また,そもそも自分がめざしたいものがなければ,そんな乱暴な選択と行動も生まれてきません。
そういう乱暴な選択と行動を重ねてこれたのも,多くの人たちの支えがあったからこそだと,心の底からしみじみと感じています。
役所の中には,口ではもっともらしいことを言いながら,変化を生み出していくためには必要な乱暴さを持てずリスクを取って勝負できない人が多いだけに,これからの激動の社会に必要な変革を生み出す力をどう現実のものにしていくのかが問われているのだと思っています。
2014年9月27日
信州松本で息子の転職祝いをした後に,学生時代によく登っていた北アルプスに行ってきました。といっても今回はロープウェイでです。
山麓の駐車場からほんの10分ほどで北アルプス南端の西穂高岳の尾根の標高2100メートル地点に到達できます。北には槍ヶ岳から穂高連峰が,正面には笠ヶ岳が堂々とした姿を見せています。笠ヶ岳は,学生時代に山登りの同好会の仲間と北アルプス北部の立山・室堂からテントと1週間分の食料で20数kgのザックを担いで1週間の縦走でやっとたどり着いた思い出の山です。
山登りで学んだのは,浮かれずひたすらリズムを守り続けることと,楽観を捨てて現実を見ることの大切さです。
前者については,山登りの最初ではついどんどん歩いてしまうものですがそれでは重い荷物を担いで1日13時間を1週間歩き続けられません。はやる気持ちをひたすら押さえて安定した一定のリズムで歩き続けることが大切です。
後者については,大きな山を登っていると山頂がなかなか見えないものなので苦しい中でつい目の前に見えているところが山頂だと思い込んてしまっては落胆することを繰り返してしまいます。自分に都合よく安易に楽観せず歩くことに集中することを自分に言い聞かせていました。
当時は,北アルプスと八ヶ岳,そして南アルプス北部を登っていたのですが,どの山に登っていても同じ思いでした。40年を経て思い出の山と対面して,そんなことを思い出しました。
槍ヶ岳と笠ガ岳の写真を添付しますが,私は雨男なのでこんな好天気にはほとんど恵まれず,「雨も天気のうち」と自分で自分を慰めながら黙々と登っていました。
帰路に立ち寄った岐阜県の山深いところにある温泉では,一風呂浴びた後に周囲を散歩しているとほんの数メートルの距離で野生の鹿に出会いました。しばらく向き合っていたのですが,そのうち静かに立ち去って行きました。



(左端が槍ヶ岳) (笠ヶ岳と新穂高ロープウェイ) (美濃の山中で出会った鹿)
2014年9月20日
飛び石の休みの間の月曜日に休みを取って,信州松本で暮らしている息子夫婦のところに行ってきます。シンガポール時代の私の友人(日本人)のランドスケープアーキテクト(景観設計)にあこがれて同じ道を歩いています。今回,転職が決まったのでそのお祝いを兼ねて。
いろんな仕事がありいろんな転機がありますが,やはりそれぞれにめざすものという軸が必要なように思います。時々はブレたり不安になったりはしても,自分がめざしたいものを持っていれば,背筋が伸びた取り組み姿勢になると思います。そうでなければ目の前の損得,うまい立ち回りを考えてしまいます。人との付き合いにも表れてしまいます。
今からの人口減少時代,特に労働人口比率の極端な低下の時代がどのような社会になるのかは分かりませんが,少しでも良い社会になるために,自分の役割を少しでも多く果たしてほしいと願っています。
2014年9月15日
土曜日から東京で開催された自治医大主催の地域医療フォーラムに行ってましたので,遅くなってしまいました。
先週ひょんなことから,昨年度全国6ブロックで担当した「自殺対策連携コーディネート研修」の概要が今年の内閣府発行の自殺対策白書に掲載されているのを見つけました。その参加者の評価アンケートも内閣府のウェブサイト(ホームページ)に。情報公開の時代だなあと思った次第です。まあ,9割近くの参加者が「とてもよかった」「よかった」と評価していただけたのでほっとしています。
やはり,社会の現場で苦労されておられる方に評価していただくことほどうれしいことはありません。理屈の正しさで評価されることも大切ですが,社会の現場で苦労されている方にいくらかでも元気になるヒントが得られたと思っていただけることが私としてはやりがいになります。
肩書きや地位など「持っている物」で評価されるのではなく,何かを感じ共感していただけることこそ,最大の評価なのだと思います。学生時代に傾倒していた社会心理学者のエーリッヒ・フロムの"To Have or To Be"(何を持っているのかではなくどのような存在であるのか)という言葉が頭から離れません。
歳をとるにつれて,「持っている肩書や実績」に頼らないことの難しさを感じるが故に,このフロムの言葉を大切にしていきたいと思っています。
2014年9月6日
あっという間に9月です。事業系の仕事をやっていて感じるのは,変化を生み出す努力の面白さと難しさです。こうしたらいい,というのは簡単ですが実際に形にしていくのは簡単ではありません。
最近,研修講師をする時には常に,最初に「あなた自身が自分から言い出して何か変化を生み出したことがどれだけあるか」を振り返っていただいています。
自分だけが考えて自分がやるというのではなく,周囲の人に働きかけて一緒に変化を起こすというところがポイントです。それを立場や権力に頼ってするのではなく,めざすものへの共感と行動提案への納得を得て具体的な行動に結び付けていくことは簡単なことではありません。
自分一人だけでできることは限られていますし,継続的に拡大していくものにはなりにくいものです。それを周囲の共感と納得を得ていろんな人が参加した取り組みにしていくことが,一人の個人としての成果を超えたものを社会に生み出していくことだと思います。
自分だけが優秀で有能だと満足するのではなく,自分だけでは到底できないことが,自分が調整側に立つことによって生まれてくることの面白さと楽しさを感じることが,社会の中で組織の中で働くことの面白さだと感じています。
そんな仕事をする機会がしょっちゅうある訳ではないので,普段はこつこつと目の前の仕事の整理をして,資料の整理ややり方の整理をする中で新たなことに取り組む余力を生み出しておいて,その時期が来た時に少しずつ足を踏み出していく,そんな感覚が大切なように思っています。
手荒に扱うと割れてしまう風船を,少しずつ膨らませていくような慎重さと根気も必要なような気がします。
2014年8月31日
昨日は,自宅から徒歩8分の日赤広島看護大学での非常勤講師3コマ4時間半の授業でした。昨年は,南米チリの国際フォーラムでのスピーチへの出発前日でしたので準備も十分ではなくしかも翌週の3コマを前倒しして1日で6コマ9時間やったので大変でした。
授業は「看護政策論」で,政策立案実行の部分については実際の経験に事欠かない分野なので比較的楽しくやらせていただきました。普段は研修会の講師が多いので,テーマに関わらず1時間10分程度で話をまとめて,その後グループワークなどをして2時間または4時間をまとめるのですが,昨日は久々にじっくり語ることができました。
受講生の方はみなさん社会人であり実践経験をそれぞれお持ちですので,話も通じやすく楽しくやらせていただきました。
社会に出て一定の経験を積んだ方を対象に実務に役立つ議論をしていく機会がもっと必要だと思っています。それは必ずしも学位と結びついていなくてもいいとは思うのですが,それだと少なくない受講料を支払ってかなりの時間を費やすことに踏み切りにくいようにも思いますので,いろいろと工夫が必要なように感じています。また,教える側にも,学位に必要な単位認定という権力によらず社会人から受講する意義を評価してもらう必要が出てきますので,これはこれで大学のあり方をかなり変えていく必要が出てくるように思います。
広島大学に転職していた際にも,これからの大学は,20歳前後の子どもを対象に大学キャンパスの中だけで教育をするだけでなく,社会人も対象にキャンパス外でも教育を考えるべきだと言っていましたが,これには,大学教員を理論側と実践側の2本立てにするなど,新しい姿を模索していく必要があるように思っています。
2014年8月23日
広島市の土砂災害について,海外からも含め友人のみなさまからお見舞いのメールをいただきました。お心遣いに感謝です。幸い我が家のある廿日市市は広島市の西部に位置しており被害はありませんでした。とはいえ,仕事でお世話になった方のご自宅も被害に遭われており,他人事ではありません。亡くなられた方々に心からのご冥福をお祈りするとともに,被害にあわれた方々にお見舞いを申し上げます。
一瞬前までは何の変哲もない日常だったものが,突如として暗転してしまう。そんな危うさの中で私たちは生きているのに,そんなことは忘れて過ごしてしまっています。日常の仕事でもそうです。一つの世界で長く過ごしていると,その組織での仕事のやり方が当たり前の常識ように思うようになり何の疑問も持たずに過ごすようになりがちです。
一寸先が見えない経験をする中で,怖れを知り謙虚さが生まれ素直な問いかけが始まるのだと思います。
いまここで,精一杯手を伸ばして生きていられる幸せを感じ,少々の苦しいことがあっても楽しいと声を出して言える前向きな姿勢を持って,その幸せを大切にしながら生きていきたいと思います。
今あるものが当然なのではなく,すべてが無くなっても不思議ではないという思いの中から,今あることの大切さを大事にしながらも,あえてそれを超えた未来へと踏み出していけるのだと思います。どんな環境の中でも,目の前の一つひとつを受入れ大切にして過ごしていきたいと思っています。
2014年8月17日
校長先生方への講演も無事?に済みほっと一息です。大学もそうですが,「先生」と呼ばれる職種は基本的には個人が自立して活動しているので,組織としてそれをまとめていくというのは特有の難しさがあるように思います。事務職であれば,ひら社員から主任,係長,課長,部長と段階的に職責が重くなりマネジメントの経験を積んでいきますが,専門職の世界はそうではない部分があります。また,事務職の場合,毎年の人事異動によって継続的に評価と処遇の機会がありますが,専門職の場合はそうでないことも多いです。
そんな中で,学校という組織をまとめ運営していくのは大変だと思いながら,校長先生が個人として孤立せずに内部と外部のいろんな力をうまく引き出し集めて活用して成果を出していくための参考となるようなお手伝いができればと思ってお話しさせていただきました。
何でもそうですが,メンバーの一員として参加するというのと,リーダーになるというのは重みと責任が違います。もちろん,リーダーになって急に責任を考え出してできる訳ではなく,メンバーの時期にも自分の仕事の責任を明確に意識して取り組んでいてこそ,リーダーが務まるようになるのだと思いますが。
普段とは異なるタイプの組織の方々にお話しする機会をいただき,いろいろと考えることがあり新鮮でした。
これが済んだために,やっと月末からの日赤広島看護大での看護政策論の準備に入っています。昨年は,南米チリで開かれた大規模災害と復興力の国際フォーラムでのスピーチの準備に追われてあまり考える時間がなかったので,今年はまじめ?に取り組んでいます。今まで「政策」は普段の仕事の中にあったのでことさら考えることなく取り組んでいたのですが,それを大学院の社会人学生に説明しようとすると,改めて考えるべきことがいろいろあります。普段の生活の中でやってきた動作や思考過程を体系的に言葉にしていくというのは簡単ではありません。これもいい機会になっています。産学官財団海外で産業振興や地域医療,国際協力,平和と復興などいろんな分野を経験させていただけたことを,少しでも社会にお返ししたいと思っています。
2014年8月10日
月曜日に,地元の小中学校の校長先生30人近くにお話をさせていただく機会をいただいたのでその準備をしています。教育関係の方々にお話しさせていただくのは久しぶりです。10年ほど前に,ある教育事務所主催の中学校の進路指導の先生方への講演を頼まれたり,別に高校生1・2年生800人や高校の新入生150人への講演なども頼まれたことはありますが,校長先生方というのは初めてです。
今年も,4月以降,中学生へのシンガポールの話やフィリピンミンダナオやインドネシア,復興途上国の政府職員研修,沖縄や熊本での保健医療連携関係の研修,三原市や香川県の職員研修,日赤看護大学での授業,三次市の行財政改革推進審議委員会関係などなどいろんな分野に関わらせていただいていますが,共通するものもあるように感じています。
それは一言でいえば,めざすものを持って目の前の課題にまじめに取り組むことだと思います。自分の損得や周囲や社会からの評価といった相対的なものではなく,自分がめざしたいもの,手応えややりがいを感じるもの,面白いと思えて楽しいもの,といった主観的なものを大切にしていくことが,周囲や運不運に振り回されずに,自分なりの道をブレたり一喜一憂したりせずに進んでいけることにつながるのだと思います。
広大時代に,世界でも高いレベルの研究者の方と子どもの科学教育のプロジェクトを一緒にやっていた時に,大切なことはめざすもののために泥臭く模索を続けることであり回り道をやり続けることにこそ意味があるという話で盛り上がったことがありました。結果だけを気にすると回り道は「ムダ」かもしれませんが,めざしていくことのプロセスからすれば,それは必要なものですし,むしろ本質とでも言えるものかもしれません。
結果はどうでもよくてプロセスが大切と言う訳ではなく,結果は偶然や運不運に振り回されることもあるし長い道のりの中における一つひとつの通過点でしかないので,めざす方向を掲げ続けて回り道を厭わぬ忍耐強い取り組みこそが大切だと思うのです。
2014年8月2日
これまでこのひとり言は日曜日に書いていましたが。出かける都合でたまたま先々週の土曜日に書いてみたら,土曜日の朝の方が書く気分になる感じなのでしばらくこれで行こうかと思っています。長年の習慣というのはこういったものだと思っています。なんとなく続けていることでも,変えてしまえばそれが定着していきます。
「変えること」にかなり意識的に取り組んできたつもりですが,改めて思い込みを感じています。
昨日は本業の方で30分程度のプレゼンをしました。不思議なもので,今後の仕事に影響すると思うとちょっと緊張してしまいます。普段の個人的な研修講師が緊張しないという訳ではないのですが,仕事という場合との違いはあります。とはいえ,個人的にも興味関心分野の地域医療をテーマにしたものですので,業務の一環として十分時間を取って準備できたという点で,改めて今の仕事に感謝しています。
また,聞いていただくのが主にはドクターなので,毛色の変わった話として好意的に受け入れていただけるというのも恵まれていると思います。「違い」を価値にしていくことの大切さを感じています。それぞれにめざしているものがあり取り組んでいることがあるのですから,そういった力が有効に組み合わさっていくように努力していく必要があると感じています。
今の恵まれた環境を生かして,責任を果たしていきたいと改めて考えています。
2014年7月26日
木曜日に,今年で8年目となる香川県庁のグループリーダー研修が終わり,ちょっとほっとしています。5月から本業の合間を縫って,外国政府職員研修4件のほか保健医療系と行政職員系の研修などが続き,京都,沖縄,熊本,栃木,香川と出かけていましたので,ちょっと一息です。
このような機会に恵まれて感じるのは,社会の実践者を対象とした人材育成について,知識伝達型ではない行動につながる研修等の工夫がもっと必要なのではという思いです。「現場研究」「人材育成」「現場支援」が継続的なサイクルとして結びついた実践者の支援システムの必要性を6〜7年前から主張していますが,最近改めてその必要性を感じています。
もちろん,誰がそれを担えるのかというのは課題です。大学の研究者でも誰でもができる訳ではないですし向き不向きもあると思います。また現場実践者についても同様です。とはいえ,現場実践者の実践感覚に沿った納得性の高い研修で,普段の仕事のやり方取り組み方を考え直していく機会は大切だと思います。
研究者とは違う実践者による相互刺激といったようなものも実現できればと思っています。結局は,現場での成果に責任を負う立場の者にとって実際に役に立つものがもっと提供できればと思うのです。
理屈や正しいことだけでなく,道を切り開いていく原動力となるパワー,社会の課題を認識する問題発見力と良質な怒り,人と組織をつなぐコーディネート力,それに必要な好奇心や度胸と腕力と感性。現場でいい仕事をしたいと頑張っている人の応援がもっとあればと思っています。
2014年7月19日
今日午後から明後日にかけて,16年前の立ち上げ以来ずっと講師をしている自治医大の財団主催の健康福祉プランナー養成塾に行ってきますので,このひとり言も一日早く。別に日曜日と決めている訳ではないものの,習慣ですね。いろんなことを抱えていると,考えたり悩んだりしなくていいことは習慣にしておくことが限られた力をうまく生かす方法のような気がしています。なお,養成塾は,講師としての出番は秋コースなのですが,今回は運営委員としての開講式等への参加です。
最近,本業副業共に忙しく(本業の方については「当たり前」と言われそうですが…。相対的にです。),気ぜわしい日々を過ごしています。
今週は,月曜日に日赤広島看護大の授業を1コマお手伝いと,木曜日に7年目となる三原市の職員グループのシリーズ研修でした。学生と社会人との違いを改めて感じたところです。
個人的には,社会の現場で苦労したり悩んだりしておられる社会人向けの研修の方が好きなのですが,今週の学生は熱心に聞いていただく人が多かったせいか一定の手応えがあり,学生向けも悪くないなと思った次第です。
とはいえ,社会の現場に出る前の未知数の学生に向けて,今後の成長へのエールを送るのと,実際に日々苦労されている方々に問題解決への糸口やヒントにつながることをお伝えしようとするのとでは手応えが違います。こうしたことからすると,大学のみならず,先生方にも組織を中心とした社会人経験も身に付けていただく工夫も必要なのではと思ったりもします。もちろん,どの仕事でもそれぞれの苦労は大きいのですが,教える側と教えられる側という関係だけでなく組織の中での役割責任だとかコーディネート力なども有益なような気がしています。
来週はJICAのアフリカや南アジアの政府職員研修と8年目となる香川県庁の管理職登用研修で,これが終わると研修講師業の方は一息つきます。昨年は秋が忙しかったのですが,今年は5月から7月に集中しました。不思議なものですね。よい週末をお過ごしください。
2014年7月13日
新しいパソコンが届いて1週間。ウィンドウズ8は初めてなので,スタート画面の違いに戸惑いながらもなんとか動かせるようになりました。ついでに机周りも少し整理して,ちょっと気分が新しくなったところです。時々はこうした変化が大切だとも思います。
LAN経由で外付けハードディスクにデータをバックアップしていたので,助かりました。このような対策の大切さを改めて感じました。最悪の事態を想定して対策を講じておくことはどんな仕事にも大切なことですが,なかなかできないことです。私自身,やらないといけないなと思いつつ,先延ばしにしていて痛い目にあったことが何度もあります。そうした経験を通じて初めて,体が動くようになるのだと思います。最近の研修で,受講者の方から比較的好意的な評価を頂けているのも,そうした実践経験の話に共感をしていただいているのではないかと思っています。
正しいことを研究しまとめる人も必要ですが,それをどうやって実際に実現していくのかを語る者も必要だと感じています。理屈通りに無駄なく一直線に実現への道を進む,なんてことはよほどのことがなければありません。「うまくいかないのが当たり前」「めざせば叶う訳ではないがめざさなければ何も始まらない」という単純なことを,とにかく嫌になるほど言い続けることが大切だと思います。
実践というのは,スマートに格好良く効率的に進むものではありません。どんなささやかな変化も,理屈通りにいかない現実にへこたれずに投げ出さずに進み続ける根気と忍耐力・持久力から生まれます。
毎日使っている自宅のパソコンの突然のダウンという唖然とするような出来事に直面してみて,久しぶりにこんなことを思い起こしました。
2014年7月9日
先週の日曜日の夜に沖縄での研修講師から帰ってきたら,デスクトップパソコンがハードディスクを認識しなくなって立ち上がらず。いろいろ調べてもどうも無理らしいので,唖然としながらもすぐに新しいパソコンを選んで注文。週末に大阪で開催された臨床研修病院の合同PR イベントで一日中立ちっぱなしで客引きをして帰ってから必死になって?セットアップ。初めてのウィンドウズ8に四苦八苦しながら3日目でやっとなんとかほぼ復旧しました。
なんてこった,という感じですが,これまでずっといろんな新しいことに手を出してきた中で,このような思いもよらないアクシデントにも随分遭遇してきましたので,いくらかは耐性がついてきたような気もしています。平たく言えば,ぐじぐじ不幸を嘆くのではなく,さっさとできる対応をしていくということです。ついでに,気分を変えるために何か変化を付け足す。今回は,モニターを4台までつけられるパソコンを選び,これまでの3台に加えて4台のモニターにしました。1台のモニターでウェブサイトの情報を表示し,後の2台でワードとパワーポイントの資料を作っていましたので,3台で十分なのですが,単に現状復旧だけでは元気が出ないので思い切って投資しました。
考えてみれば,今までも,新たなことにチャレンジして予想外のトラブルに悩みジタバタしながらプラスアルファを付け加えるという行動パターンが多かったような気がします。とにかく,ちょっとほっとしたところです。
2014年6月29日
木金と休みをいただいて,沖縄県北谷(ちゃたん)町に行ってきました。昨年秋の自治医大の健康福祉プランナー養成塾を受講された方に声をかけていただいて実現したものです。昨秋の講義の終了後に声をかけていただいた時は,そうは言っても役所の壁を超えるのは簡単ではないので多分無理だろうと思っていたのですが,その方の熱意で実現したものです。自分が関わった話で言うのもどうかと思いますが,思いが実現することの意味を感じました。と同時に,責任感もですが。参加者の皆さんにも好意的に受け止めていただいたようでほっとしました。
20数年ぶりの沖縄本島は,依然として基地の街ではありましたが,米軍の接収地域の返還が少しずつ進んでいるようで,地域開発につながっているようです。
こうした変化の中にある自治体の職員の方々には,未来への可能性を感じる熱意があるように思いました。若さでもあるのかもしれません。
今この時点でも,70年近く接収されていた土地が返還されて新たなまちづくりが進んでいる地域があることに,驚きを感じるとともに,そのような地域が日本全体にもたらす活力の可能性を感じた旅でした。
とてもいい時間を過ごして帰って来たら,自宅のデスクトップパソコンのハードディスクが壊れてしまったようで困っています。好事魔多しですね
2014年6月22日
なんだか最近のひとり言を眺めると,研修講師の話ばかりで,本業をちゃんと腰を入れてやっていないんじゃないかと突っ込まれそうですが,頑張ってます。ただ,仕事としてやっていることについてはここでは書きにくいので書いていないだけです。(言い訳っぽいですね。)
週末は来週の沖縄県北谷町,再来週の熊本県,翌週の日赤広島看護大,翌々週のJICA紛争復興国政府職員研修と香川県職員研修の準備をしていました。このうち,JICAの研修にはコートジボアール(日本サッカー残念でしたね)の政府職員2名も参加されます。21世紀に入ってからも内戦があり国としては復興途上の厳しい状況ですが,それだけにサッカーによって国民の一体感が高まり元気になっていただきたいものです。ちなみに面積は日本の9割で人口は2千万人とか。
内戦の歴史など多くの課題を抱えながらも,それぞれの国の未来を信じて頑張っている人たちがいます。
日本も,自殺に至らずに済む地域の人のつながりづくりや,国の支出の半分は後世への借金という財政破たんへの対策,人口の急速な減少への対策など,過去の蓄積の成果を漫然と食い潰しながら今の豊かで平和な状況にあぐらをかいているのではなく,真剣に破壊的創造に取り組んでいく必要があると思います。
そのためには,もっと社会の不条理に目を向け理解し,「良質な怒り」に裏打ちされた「静かな迫力」で,目の前の変化を少しずつでも起こしていくことが必要だと感じています。
2014年6月15日
先々週のフィリピン・ミンダナオ自治政府職員研修4時間に続いて,先週は京都の立命館大学でのインドネシア政府職員・大学教員研修4時間を担当してきました。
何といっても,33歳の時に生まれて初めてハウアーユーから始めた英語で,今では年に数回しか使うことがないので,英語で話していても自分でももどかしく情けない思いもあります。
でも,先週も書きましたが,実務の現場で壁にぶつかり悩みながらもがいてきたことについては,不思議に共感していただけます。先週のインドネシアからの30数人は海外の大学で学んだ人も多くインドネシアの中でも超エリートに属する人たちだと思いますが,事業を実際にやる中で直面する悩みや葛藤は世界中同じようで,一つひとつの言葉に素直に反応していただけます。
2週連続でいい時間を過ごさせていただきました。来月は,アフガニスタン,コートジボアール(今日は残念でした),リベリア,ネパール,パキスタン,南スーダン,スーダン,イエメンという紛争からの復興国の政府職員方々の研修です。長い内戦の間に子ども達まで行き渡ってしまった武器を回収するのが最大の懸案というような国もあります。
恵まれている日本の私たちが,恵まれていることを無駄に浪費せずに,恵まれていることとの責任を感じ幸せに暮らせる社会づくりに真剣に向き合わなければならないと,心から思える時間です。
失って初めて分かるというのではなく,失う前にそれを大切にしなければと思います。恵まれていることが悪いことではなく,恵まれていることを最大限に活かそうとしていないことこそが悪いことなのだと感じています。
2014年6月8日
新年度が始まって3か月目に入りいろんな新規事業等が立ち上がりつつあってドタバタしている上に,個人的にもなんともいろんな話を持ち込んでいただくので,かなりあたふたしてきました。とはいえ,いろんな地域医療,国際,行政など色んなバリエーションがあるので,適度に気分転換ができるような気もしています。(忙しいのには変わりはありませんが)
ただ,悩みは休暇日数です。県外での頼まれごとが多いので,どうしても休暇を取る日数が増えてしまいます。今年は少し余裕があると楽観していたのですが,予想以上に頼まれごとが増えていくので,ちょっと不安になってきているところです。もちろん,本業はライフワーク分野ですので,今まで以上に真剣にやっています。
先週,2回目のフィリピン・ミンダナオ自治政府職員研修は,グループワークを中心として4時間みっちりやりました。何といっても英語力が乏しいので話していても適切な言葉が出てこなくて情けなくなったり,受講生の英語が聞き取れずに落ち込んだりすることも多いのですが,地方自治の理想や使命などの中身の話については共感していただくことも多く,手応えを感じる楽しい時間でした。このあたりが,研究者と実践者の違いだと思っています。正しいことを理路整然とは話せなくても,仕事にかける思いや,壁にぶつかった時の対応,問題を解決するための取組み方などは世界共通なので,実践者同士の連帯感といったようなものが生まれてきます。正しい答えを考え続けるのではなく,めざすものとめざす方向さえはっきりしてきたらまず行動を起こして,その中で考えていく中で成果が出てくることもあります。
成功は偶然の産物かも知れないがその偶然を生み出したのは努力の産物,と私が言うのはそんな経験からです。めざせば叶う訳ではないがめざさなければ何も始まらない,助走の無いジャンプはない,なども同じ流れの話です。40年以上の内戦にやっと終止符を打ち自分たちの自治政府の建設に向かって夢を持って熱く語る方々と向き合ってみて,これからの成功を心から祈る思いです。
来週は,京都の立命館大でインドネシア政府職員・大学教員対象の汚職防止研修4時間です。今の目先のことだけでなく,どんな社会を後に続く世代に残していくのかを一緒に考えていきたいと思っています。
2014年6月1日
早いものでもう6月です。本業の方は,少しずつ歯車が噛み合ってきているように思いますので,気を抜かずにしっかり成果を出していきたいと思っています,20年近く前に県の地域医療係長をやっていた時にも感じたことですが,日々の医療に真剣に携わっている医師の方々の中には,患者さんにより良い医療を提供できるような社会の仕組みづくりが大切だと感じておられる先生方が少なからずおられます。このような先生方に対して,社会課題への取組みを本業として来ている者として向き合い,自分の知識と経験を生かしていくというのはとてもやりがいのある仕事だと感じます。
また,個人的な活動の方でも,6,7月は,フィリピン・ミンダナオ自治政府職員研修,立命館大のインドネシア政府職員・大学教員への計画倫理研修,JICAの紛争影響国研修研修,沖縄県北谷町の保健福祉計画研修,熊本県の自殺対策連携コーディネーター研修,日赤広島看護大学での1コマだけの講義(8月には大学院の集中講義もありますが),香川県の管理職登用研修などバラエティに富んだものをお引き受けしているので,いつものことながら準備はドタバタです。
ただ,本業の方にしても個人的な活動の方にしても,「なぜ何のために何をめざして」取り組むのかという原点を考え,そして「成果は何か,何をもって成果と言えるのか」を問いかけていくことが大切だという原点はすべてに共通だと考えています。
恵まれている時は恵まれているなりに,そうでない時はそうでないなりに,必死に一生懸命に頑張ることが必要でと思います。恵まれていることが悪いことではなく,恵まれていることを生かさずに無駄に食い潰していることが問題なのだと思います。恵まれている時にもそれを生かしていい仕事をしようとしていれば,そうでない時にも,ただ不運を嘆くのだけではなく,その置かれた環境の中での最善を尽くそうとすることができるのではないかと感じています。
これまで,産学官・海外と様々な環境の中でそれなりに真剣にジタバタしてきて良かったと思えるのは,置かれた環境についてあれこれ考えるのではなく,今ここで自分のできることを精一杯やろうとすることが大切なことだと思えるようになったことだと感じています。
2014年5月25日
新しい年度が始まって本業の方の仕事が拡大している中で,個人的な活動の各種研修講師の準備も増えて,早起きが続いています。
復興・開発途上国の政府職員等研修や地域医療系の研修が中心です。いずれの研修についても,未来の社会のありたい姿を描いて,そのために必要な取組みを考え,個々の事業について「なぜ何のために何をめざして」を常に意識しながら取り組むこと,が基本となります。
方向性としてはこんなところですが,「うまくいかないのが当たり前」でも「めざせば叶う訳ではないがめざさなければ何も始まらない」ことを改めて認識して取り組んでいただくことの大切さをお伝えしたいと思っています。
理屈と方法論の正しさだけでなく,それを実際に具体化する力が求められるところが,研究者ではなく実務者の世界の面白いところだと思います。極論すれば,まぐれ当たりでも当たりは当たりです。ただし,何も考えずに何の練習もせずにバットを振ったからといっていつもまぐれ当たりが続く訳ではないので,それなりの努力が必要です。「成功は偶然の産物かも知れないが,その偶然を生み出したのは努力の産物」と私が言うのはそんなところをお伝えしたいからです。
間違っていないことを言ってるだけでは何も始まりません。
10点20点レベルでもまずはやってみることがすべてのスタートです。最近,新しい分野の仕事を頼まれた時に改めてそう思います。ある分野においていろいろと出来るようになった人の中には,知らない分野でもがくことをしたくない人もいるでしょうが,そんなもがきの中から少しずつ形が生み出せていけるのは,他の分野での一定レベルの仕事の経験がある故であり,だからこそ実践の世界は面白いのだと改めて感じているところです。
2014年5月18日
13日にも少し紹介させていただきましたが,5月12日(月)にフィリピン・ミンダナオの自治政府設立準備の一環としての研修のお手伝いをさせていただきました。フィリピンでは少数派のイスラム教徒地域が40年余にわたる内戦を経て自治政府を樹立することになったというものです。
今回は,今後の研修の進め方を検討するためのお試し?ということで8名の方が参加されました。内戦地域からということで一定の先入観があったのですが,皆さん物静かで知的で誠実で熱心でびっくりしました。思い込み,先入観で考えてはいけないと改めて反省したところです。やり取りをしていても,これから自分たちの地域の未来を切り開いていく責任を自分たちが担っていくのだという責任感が強く伝わってきて,清々しい印象を持ちました。来月初めの研修終了時には4時間の振り返りを一緒にさせていただく予定です。
このような開発途上国の人たちと交流していると,恵まれている日本の行政職員の責任を感じます。恵まれていることに安住することなく,常に置かれた環境を最大限生かしてよりよい社会のためのチャレンジを続けていくことが求められています。
昨日は,19年目となる三原市の中学生のシンガポール交流のお手伝いに行ってきました。19年前にこの交流への手伝いを頼まれた時に,単なる税金を使って子どもを海外旅行させるというものにならないために,事前に約3か月間ほぼ毎週集まって交流の準備をすることを提案し,これまで18年間実践していただいています。昨日は,「学校生活」「家庭生活」「三原の文化など」の3つの区分で,シンガポールとの違いを考えた上で,何をテーマとして取り上げてどう紹介するかを考えてもらいました。三原市には,三原国際外語学院と広島シンガポール協会の共同事業としてシンガポール国立大学日本研究学科から毎年1人留学してもらっており,今年で7人目となる学生が来てくれています。昨日は,この学生にも参加いただいて,日本とシンガポールの違いの話に参加してもらいました。
この研修については,言葉の問題もあってこれまで18年間私が交流先との連絡の間に入っていたのですが,今年から直接やっていただくようにお願いし了解いただきました。その方が,より実感を持っていただけるのではないかと期待しています。
2014年5月13日
昨日のフィリピン・ミンダナオの自治政府職員研修がNHKニュースで取り上げていただいたので。(掲載期間は限られていると思いますが←1週間でした。掲載終了しています。)
2014年5月11日
なんだか,どたばたと過ごしています。
明日12日は,フィリピンのミンダナオで内戦をしていた人たちが主体となって自治政府を作るための研修のお手伝いです。そんな厳しい状況にある人たちに何らかの意味のあるものを持って帰っていただこうとすると,行政の原点や本当に大切なこと,をしっかりと自分自身で考えていただく機会を提供しなければと責任を感じます。
誰しも当初はいろんな夢を持って取り組み始めても,役所仕事に陥ったり汚職の風土が広がってしまったり。内戦等の間にめざしていた理想の姿が色あせてしまうことも,歴史では見受けられます。みんなの夢が,歯車が噛み合って前に向かってつながっていくようにしたいものです。
同時に,平和で豊かな日本で暮らしている私たちが,それをただ食い潰していくのではなく,恵まれている者の責任として,よりよい社会をめざしていくことの責任も感じています。いつも言うのですが,100kgの荷物を持つことのできる人が,10kgの荷物しか持てない人が11kgを持ち上げようと頑張っているのを見て笑うのではなく,110kgを持ち上げようと努力することで初めて対等に向き合える関係が生まれるのだと思っています。
宗教や民族や政治的な対立などにより日々の命が脅かされている人々が少なくない中で,恵まれていることを無駄にすることなく,人々の前向きの思いが形にしていけるような平和な社会づくりに向かって必死になって汗をかいている姿を見ていただけるようになりたいものです。
2014年5月4日
年度初めにバタバタしているうちにもう5月です。連休中も早起きをして仕事関連のレポートづくりにこつこつ取り組んでいます。とはいっても,個人的な関心分野なので,仕事を持ち帰っているやらされ感はなく,楽しく悩んでいます。一気にはまとまったものにはならないので,少しずつ作り上げています。
一気に書こうとすると,今書けることしか書かなくなってしまうような気がしています。つまり既に頭の中にあるものを並べるだけに終わってしまうような気がします。これに対して,最初から完成形をめざさずに,大きな骨格と問題意識を大切にして,問題の背景や変化,課題となっているもの,めざすべきものとその方向性を意識しながら,抜けている部分も仕方ないとして,書けるところだけ書いていくと,少しずつ抜けた部分や新たに書き加えるべき部分に気がついたりしていきます。そんな積み上げ型の作業を楽しんでいます。
先週書いた外国政府職員研修以外にも,6月は沖縄の北谷町,7月は熊本県に保健医療系の研修に声をかけていただいていますし,7月の香川県の職員研修は8年目になります。こうして声をかけていただくのは,知識や理論だけではなく,実践場面において直面する問題にどう向かっていくのか,どう気力を維持していくのかといった現場実践力といったものの大切さも評価していただいているからかなとうれしく思っています。
自分自身が,常に新しいことをに手を出して(別に新しいことをやりたかった訳ではなく必要だと思うことがそれまでなされていなかったから結果的に新しいことになっただけ)壁にぶつかって悩んできた中で身に付けたことが,少しでも前に向かった取組みをしたいと思っている方々のお役に立てればと思っています。
昨日は久しぶりにカレーを作りました。大量の玉ねぎを1時間程度かけて根気よく炒めるのがポイントです。その決め手は缶ビール。とはいってもカレーに入れるのではなくて飲むのですが。カレーを炒める根気のためにはビールが必要と昼間っからおおっぴらに飲める幸せを感じながら作っています。こんな楽しみを仕掛けることも仕事を長続きさせるコツかなと。(自分に都合のいい酔っ払いのたわ言です。)
2014年4月27日
週末は,連休明けに頼まれているフィリピン・ミンダナオのパンサモロ自治政府職員研修の準備などをしています。長年の内戦状態から今年平和合意が成立し自治政府の建設が始まっています。
平和な社会に暮らしていると,それが当然のことだとおもっしまいますし,「社会とは」といったことも考えずに過ごしてしまいます。ところが,現在のシリアなどの状況を見ても,今日の食べ物と命の心配をすることなく静かに日々を生きることそれ自体が夢のまた夢といった状況に置かれた人々か数多くいます。そんな国から来た政府職員の人たちにただ日本の制度の説明だけをしても,きれいに飾られたショーウィンドウの中を眺めてもらっただけになります。社会って何のためにあって,行政職員の使命は何かを一緒に考えていただくことが大切だと感じています。
そのような真剣な議論をしていると,私自身も,日々の目の前の仕事に追われて過ごしている中で忘れてしまっていることを考えるきっかけとなります。
6月には立命館大学のインドネシア政府職員と大学教員研修,7月にはJICAの紛争影響国研修と続きます。自分自身と足元を見直す良い機会だと感謝しています。
2014年4月20日
年度当初からずっとドタバタしています。本業は2年目に入り,実際の変化・成果を生み出すためにより加速して取り組まなければならないと気を引き締めています。副業の方も,三次市の行革推進審議委員会や三原市の中学生のシンガポール交流などの定例的なものに加えて,外国政府職員や国内自治体職員研修,保健医療分野コーディネート研修などを声をかけていただいています。
研修講師については,過去に担当したものに参加された方やご覧になった方からのものがほとんどなので,声をかけていただけるというのは一定の評価をしていただいたという感じでうれしいものです。
とはいえ,まずは,本業副業を含めて,自分が関わる仕事において具体的な成果を出していくことが肝心です。このあたりが現場で仕事をすることの面白さだと思っています。いくら正しいことを言っても,周囲の人や組織に働きかけて何か新たなものを生み出していくことができなければ面白さは出てきません。理屈に合わないこと,不意の問題発生,理不尽な対応などトラブルは常にあります。手を出さなけりゃ良かった,始めなきゃよかったと思うこともしょっちゅうです。それらに一喜一憂していても仕方ないので,とにかくめざすものに向かってこつこつと努力を積み重ねていくことが大切になります。一番大切なことは,まず30点でもいいから実際に初めて見ること,そして,できるまで止めないことだと思います。
できるまで止めなきゃいいので,焦り過ぎる必要もありません。時には,機が熟すのを待つ忍耐力も必要です。
60歳になっても,相変わらずドタバタもがいている自分を見て,いろいろと頭の痛いことはありますが,まあ幸せかなと思っています。
2014年4月13日
新年度早々,本業の方で急に新たな事業提案書をまとめる必要があり,5人ほどの方々とのメールでのやり取りを元に取りまとめ作業をしました。期限が切られていたので,久々に集中した感じです。昨夏,南米チリでの大規模災害と復興力についての国際フォーラムでのスピーチを1か月前に頼まれて,1か月間毎朝3時に起きて準備した時ほどではないですが,それなりに没頭しました。
やはり,こういった何かに全力で集中し没頭する時間というのは大切だと思います。
日々過ごしている時間は均一ではなく,濃密な時間もあればゆったりとした時間もあります。
どちらが価値があるということではなく。大切なのは,同じ時間の長さであっても,中身には大きな違いがあることを知っておき,いざという時には本気で集中力を切らさずに頑張る準備をしておくことだと思っています。
それが,晴れの日は晴れの日なりに,雨の日は雨の日なりに楽しんでいくことにもつながるのではないかと思っています。
これは,嵐の日々を経験しているから平穏な日々の大切さありがたさを感じることができるということにもつながると思います。波乱があり過ぎるのも考えものですが,平穏な日々が続き過ぎて,そのありがたさを忘れてしまうのも困りものです。難しいものですね。
2014年4月6日
新年度が始まりました。桜の花の下での新たな年度の始まりです。
ちょうど20年前の3月31日にシンガポールから広島に帰ってきた時のことを思い出しています。3年近く1年中気温32度湿度96%という世界で過ごしていて,帰ってきた広島は桜の花が咲き,水道の蛇口をひねれば冷たい水がほとばしり夜には布団をかけて寝ることのできる場所でした。仕事としてはもう少しシンガポールで続けたかったのですが,帰ってきてほっとしたのも事実でした。
とはいえ,慣れた場所とは180度異なる環境で仕事をさせていただく経験を積めたことは,とても価値のあることだったとしみじみと思っています。それは,伊藤忠での1年,広島大学での4年3か月も同じことが言えます。一つの世界に長くいれば,どうしてもその世界の常識に従って生きていくようになりかねません。それ自体は悪いことではないのですが,今とは違う考え方や常識や基準があり得るということを忘れがちになってしまうと変化を生み出す力が弱くなるのではないかとも思います。昨日と同じ今日,今日と同じ明日だけではない明日があると思って今の自分の可能性と一つひとつの選択を大切にしていくことによって,結果として明日何が起きても,それを素直に受け入れて正面から向き合っていくことができるのではないかと思います。
「相手の反応は自分の心の鏡」というのがシンガポールで仕事をしていて感じた最も大きな教訓の一つです。先入観や思い込みではなく自分の心を空にして,相手と向き合うことは,いろんな可能性を大切にしていくことにもつながります。
この新しい年度も,一日一日を大切に過ごしていきたいと思っています。引き続きよろしくお願いします。
2014年3月30日
県庁を退職し転職して1年が経とうとしています。いろんな点で恵まれた1年間だったと思います。15年ぶりに地域医療の仕事を本業として向き合ってきてみて,改めてやりがいがあり面白い仕事だと感じています。その理由としては,社会から切実に必要とされている分野であること,医師など専門家によって構成されている分野であるため,新たな課題解決やシステムづくりなど行政において培ってきた経験や力を(非専門家として)役立てることができること,そして何より,社会サービス分野の連携のコーディネートという私の継続的なテーマが生かされる分野であることです。
とはいえ,この1年間は,15年間のブランクを埋め,最近の環境変化や政策・課題変化に追いつくとともに,担当分野の事業整理や体系化などに追われて,十分に新たな取組みを進めることができたとは言い難い状況でした。
明後日からの新たな年度においては,より攻めの姿勢で,積極的に仕事に取り組んでいきたいと思っています。
新たな年度が始まる前夜,これまでを心静かに振り返り,新たな一年への気力を高めていく大切な時間にしていきたいと思います。
みなさまのこの1年が平穏に終わり,新たな年度が,前向きの一年でありますことをお祈りしています。
2014年3月23日
先日,以前いた職場の人と会う機会があり話していたら,私が残した遺産として,毎朝の挨拶と毎週水曜日終業前の全員での掃除,和やかな雰囲気を言ってくれてとてもうれしく感じました。
もちろん,仕事の中身が大切なのですが,チームとしていい仕事ができる環境づくりが基本的に大切だと思っています。行政職員は,「社会のためにフルタイムで働く住民」であり「専門家を活かす専門職」だと思ってますので,自分だけが優秀というのではなく,社会の人や資源を活かすための裏方役を務めることが大切であり,そのためには,行政組織の中でもメンバーがそれぞれの力を生かせる環境づくりが大切だと感じています。
とはいえ,一方ではほかの人から,「人の話を聞かない」とか「聞きたい話しか聞かない」と言われたこともあり,実際にはなかなか思うようにできていないものだと思っています。耳の痛いことを言われると,瞬間的には,誰しも欠点はあるとか,いい人ばかりではいられないなどとつい反発してしまうものですが,そうはいっても反省しなければと思うところです。
日々の仕事と生活の中で,少しずつ見直していきたいと思います。
2014年3月16日
この一年間,県を退職して新しい仕事をいろいろとやる中で,これまでの経験を通じて得たものの中で最も大切なものの一つは,できないことに耐える力ではないかと感じています。昔は,「ある山の頂上からより高い山に登ろうとすれば,必ず一旦山を降りないといけない。見晴らしの良いところから,見通しのきかない藪の中を地道に歩くことも必要になる。そうやって初めて前よりも高い山に登ることができるのだ。それが嫌で今いる山頂から降りれない人は『お山の大将』で終わってしまう。」と言っていました。この歳になって,改めてそのことを思っています。
自分の知らない分野の仕事をしたりするときは,分からないことが多いだけに,悩んでしまいますし,分からないことに不安を感じて臆してしまいがちです。でも,100点満点の10点程度の出来でもいいから,とにかく一つでも二つでも資料をまとめてみる,人に会ってみる,といった行動を(不安の中で)続けていくことが本当に大切です。そんな出来の悪い資料を作ったって仕方がないと言っていても何にも始まりません。できないながらもがいていくことが,極めて大きな違いを生み出していくのだと改めて感じています。
そんな仕事は,膨大な無駄や回り道が続く割にはなかなか成果が見えてきません。やりなれた仕事に比べれば,あきれるほどに効率の悪いものです。でも,普段の仕事と違って,効率など度外視でひたすら先の見えない作業に膨大な努力を延々と続けていって,無駄な作業で終わることも良くありながらももがき続けることができるかどうかが,大きな違いを生み出すと思います。
できない言い訳をいくらしても,あるいはできないことを他人のせいにしても,一時の気休めにはなっても問題は実際には何も解決しませんし前進もしません。
最近,同じようなことを何度も書いているようにも思いますが,例え今は出来なくても不様でももがいていれば何かが変わることもあるのにと思うことが続いたせいかもしれません。
もうすぐ県庁退職丸1年です。つくづく恵まれていると思いますしありがたいと感じています。
2014年3月9日
あっという間に,月日が経って行っています。昨年の今ごろは,県庁退職目前でどたばたしていました。そう思えば,この1年は恵まれていたと思います。
金土と島根県に仕事で行ってきたのですが,金曜日に訪問させていただいた中国山地の病院では院長さんとスタッフの方々が安心と安らぎを感じさせる病院づくりをしておられましたし,土曜日に参加した中四国の地域医療フォーラムでは,各県それぞれの取組みを学ばせていただきました。そんな中で改めて感じるのは,専門職の中において,異なる角度からの視点を提供することの意味です。専門職の専門家としての見識・知見に敬意を表しつつ,継続・発展できる社会システムづくりにつないでいくための視点や,専門職が真摯に努力を積み重ねておられることの社会的な意義を分かりやすく説明していくことなどの大切さを改めて感じています。
これが,20年近く前に,県庁の地域医療係長として初めてこの分野に関わる機会を得た時に感じたことであり,それは今も変わっていません。「専門家を活かす専門職」という言葉もそのようにして思いついたものです。
雑多な経験をしてきたからこそできることを意識して,多くの方々の力がより生きるように頑張っていきたいと思っています。
ところで,職場環境が変わることで,学ぶことは多々あります。この1年,いろいろと自分が意識できていなかった課題や足らないことを学ぶ機会もありました。環境の変化は必要だと思っています。
2014年3月3日
週末は,本業の仕事で,福岡で開催された医師確保のための初期臨床研修医誘致のための研修病院合同説明会に行ってきました。県内の研修病院さんの支援の一環です。福岡のほかにもいくつかの都市で開催されているのですが,私の勤め先では,あと東京と大阪に参加します。
福岡での開催なのに,北海道から沖縄まで全国から参加される大きなイベントです。全国の医師確保のための熱い思いを感じました。
ばたばたしているうちにもう3月です。新職場での最初の1年の締めくくりとして,大切に過ごしていきたいと思っています。
2014年2月23日
還暦を迎えてしまった…とはいえ,気分はその半分以下のつもりで過ごしていますが,自分よりも若い世代を見てて,生きることへの余裕の違いを感じるのはやはり歳のせいだと思います。すなわち,テレビも車も無く外食もあり得なかった世界で過ごした世代は,生きることそれ自体が最優先課題でした。とにかく階段を踏み外さないように頑張っていくことが生きていくことの第一条件でした。それが良いかどうかなどではなく,それ以外に生きる道などないと思っていたように思います。すなわち,迷う余地などない(と思ってた)時代でした。
そんな何にもない時代に育ったが故に,何にもない時代に戻ってしまう恐怖感(というよりも,ありうる可能性)を感じてしまうのです。迷う余地もなくひたすら前を向いていたことが良かったかどうかは別として,それ以外の生き方が考えられなかった時代だったように感じます。
最近,研修講師をしていて,「実際に楽しいかどうかではなく,『楽しい』と口に出して言えるかどうかが大切だ」と言っている自分の言葉に,選んだり迷ったりすることの考えられなかった自分の若い頃の時代を思い起こしています。
今の自分がどうであるかを考えていても仕方なく,今,自分がやるべきことを実際にどれくらいやれているのかを考えることが大切だと思います。
真面目に悩んでいれば今の自分に満足できることなどあり得なくて,いつも後悔と反省の中で暮らしてしまうことになりますが,いくら後悔し反省しても,それだけでは未来は開けませんし,何も変わりません。後悔と反省が,具体的な行動に表れなくては意味ないのだと思います。
内向きな反省はもちろん大切ですが,外向きの行動変容こそが大切です。
2014年2月16日
最近,「なぜ何のために何をめざして」を考えることの大切さを感じる機会が多くあります。自分がなぜ何のために何をめざして頑張っているのかを意識していないと,その達成のための努力への集中力が続かないと感じます。本当にやらなければならないと自分が思える仕事であれば,自分にそれができるかできないかを考えるのではなく,たとえささやかではあってもそのために自分ができることは何なのかを考えるようになります。自分ができることを少しでもやり切ろうとする思いが出てきますし,たとえささやかであっても自分の責任を少しでも果たそうと思うようになります。できるかできないかからスタートするのではなく,できないながらも自分が努力できることは何なのかを考えることが大切だと思います。
このように考えるようになったのは,行政というある面安定した組織をベースとしながらも,自分が提案した商社派遣制度で出向し,自分から手を上げてシンガポール広島事務所の立ち上げを行い,自分で決めて広大に転籍する中で,できるできないではなく,やらなければ生き残れないという環境変化を何度も経験したことが大きかったと今更に思います。
人は困難に直面した時には,いろんなできない理由を考えます。私もそうです。仕事の困難さ,恵まれない環境,色んな障害,時期の悪さ,人材の量や質,場合によっては自分の能力や学歴などあれこれ足らないものを数えだします。それらはどれもそうかもしれませんが,できない理由を並べたからといって,何かが変わる訳でもありません。自分がすべてを解決できることがそんなにある訳ではなく,みんながそれぞれのできることをほんの少しずつでも実際にやっていくことによって,それらの積み重ねの結果として少しずつ変化は生まれてくるのだと思います。ゼロよりはまし,が基本なのだと思います。また,みんなの力を集めることが大切であり,自分がそれに参加することに意義があるのだと思います。
自分は(どんなにささやかではあっても)歴史の歯車を前に動かそうとしているのか,止めているのか,後ろに動かしているのか,を考えることが大切だと思います。自分が100点取れそうにないからやらない,あきらめるというのではなく,全体の中でたとえ3点でも5点でも,自分のできることをやろうとすることに価値があるのだと思います。
100kgの荷物を持てる人がそれに満足して自慢するよりも,10kgしか持てなくても11kgが持てるようになるために努力をする方が価値があるように思いますし好きです。
できない言い訳を100個考えて落ち込むよりも,一つでも二つでもできることに取り組みもがいていたいと思っています。
とんでもなく厳しい環境の中に置かれても,それに不満を言う余裕もなく必死になってひたすらに真剣にもがいている人たちも数多くいらっしゃる訳ですから。
2014年2月9日
先週金曜日は,午後休暇を取って,ここ6年お手伝いしている三原市職員の組織風土改革研究会の市長発表会に行ってきました。1チーム5人が3チームで,毎年,生活,産業,インフラの各分野に分かれてテーマを決めて議論しています。普通であれば「企画力研修」とでも言いそうなものなのですが,これが組織風土改革研究会と名付けられているのは,新たな発想で課題を分析し提案していくためには気楽でまじめな議論が必要であり,それを中堅クラスの職員に体験してもらうことで,組織風土改革の意義と効果,必要性を組織に根付かせていきたいという発想だったようです。最初に考え方悩み方についてお話しし,その後1〜2か月に1度計3回ほど(悩み方の)アドバイスをしています。
これまでの参加チームはもちろんそれぞれに頑張ってくれたのですが,今年は特にチームとしての完成度が上がっていてびっくりしました。もちろんメンバーの努力が素晴らしかったのですが,このような取組みを続けることの意義も感じたところです。代々の先輩チームの努力が蓄積となって有形無形に積み上がっていくこともあるのではないかと思います。またお手伝いさせていただいている私自身も,毎年学ばせていただいており,アドバイスの仕方もいくらかは改善しているかもしれません。
新たな取組みは,すぐに成果が見えないことも多いのですが,底の見えない沼に石を投げ込んでいるように,水面上に変化は見えなくても水面下では少しずつ石が積み上がっているものだと思います。
成果の保証のあるものしかやらないという考え方もあるかもしれませんが,何かをめざして仮説を立てて地道に継続的に取組んでいくことも大切だし必要なのだと思います。続けていくことによってその効果や成果が水面上に見えてくる,そんなこともあるのだと思います。
全体像をつかんだ上で論理的で体系的な課題の掘り下げ方をし地域社会の未来のために取組むべきことを考える,そんな作業を一握りの「優秀な」者だけではなくみんなで知恵を出し合える関係性をつくり出していくこと,その大切さを改めて感じました。
知識の量や経験の長さだけでは十分ではなく,それらにこだわり過ぎることなく,柔らかで自由な発想を持って,互いの力と可能性を認め,相互作用の効果を生み出していくために努力をしていく,そんな組織づくりが求められているように思います。
私自身,産学官・財団・海外と,それまでの知識や経験が全く役に立たない経験を何度もする中で,周囲のいろんな人との連携の大切さを体験を通じて学ばせていただいたと思います。そんな経験を,少しでも社会のためにお返ししたいと思っています。
2014年2月2日
最近,還暦なるものを迎えてしまいました。自分ではまだその半分くらい?のつもりでいるのでいささか心外ですが,こればかりは否定しても仕方ありません。その直後に聞きに行った講演会のアンケートの年代別の質問で60代に丸をするのにいささか抵抗がありました。
とはいえ,そんなことは忘れて,引き続き活きがいい状態で頑張っていきたいと思います。本業の地域医療の仕事も,とりあえず最初の9か月で少しは足場が固まってきつつあるようにも思いますし,いろんな課題が見えてくる中で,同時にいろんな可能性も感じるようになってきました。15年ほど前に地域医療に関わっていた時に感じた「専門家を活かす専門職」の可能性を改めて感じています。
いろんな現場で,それぞれに強い思いを持って必死に頑張っておられる方々がいらっしゃいます。そんな方々の力がつながり引き出され生かされる環境づくりをする力を持った人材の必要性を感じています。
このあたりが,産学官財団国際と様々な経験をする機会に恵まれ多くの人々の助けのおかげでここまでこれた自分として,その経験を生かして頑張る分野だと改めて感じています。
今しかできないこと,今だからできること,を大切にしながら一日一日を過ごしていきたいと思っています。
2014年1月27日
先週は,三次市行財政改革推進審議委員会の会長として,市長さんに行革メッセージを提出してきました。12人の委員で半年間議論した結果です。キーワードは「共感,決断,行動」で,行政組織を人の体に見立てて,「心」市民との共感力,「頭」変化への決断力,「体」機敏な行動力としています。「市民と共感できない,決めれない,実行できない」行政が多いようにも思いますので。
三次市に行く機会に,発達支援センターにお伺いして話を聞かせていただきました。久々に,社会のために全力でいい仕事をされている現場の話をお伺いした感じです。私の好きな言葉である「静かな迫力」を感じました。こういう仕事をされている方々にお会いすると,うれしくなりますし,自分も頑張らなければと思います。
最初から恵まれた環境だった訳ではなかったと思いますが,10年近くをかけて,今の姿に作り上げておられます。
人の力が付くということは,結局こういうことではないかなと思います。苦しい時には,何で自分がやらないといけないのか,何で自分だけが苦労するのか,といった思いも出る中で,歯を食いしばって必死になって頑張るから,力が付くのだと思います。給料同じなのになんで自分だけが人一倍苦労しないといけないのか,などと考えだすと仕事は出来なくなると思います。
十分ではない環境で理想を掲げて頑張る中で徐々に成果は見えてきますし,同時に,短時間にあれこれ始末をする集中力や,手戻りがないように先を見ながら対応していく先見力なども身に付いてくるのだと思います。やらなくてもいいけど,やるべきだと思うからやる。そんな人々の思いが,社会を良くしていくのだと思います。
世の中には,自分では選べない状況の中で必死になって頑張っている人もいます。安定した公務員が,一皮むけた実力を身に付けていくには,いろんな理不尽さに対する怒りを抱えて努力していくことも大切なように思います。負荷がかかった中で人は育ちます。自分からめざした環境で頑張り続けることが,いろんな環境下で頑張る力を生み出すのだと思います。
沢山の頑張っておられる方々に負けないように,今年も努力を続けていきたいと思っています。
2014年1月19日
先週,来週と2つの市の行政職員研修のお手伝いが続き,自宅で準備をしています。といっても,課題研究の発表の整理の仕方のお手伝いをしているだけですが。どちらも,市長さんの前での発表の準備なので,みなさん熱意を持って取り組んでいただいていますし,着眼点もいいので,お手伝いしていても充実感があります。
ここ何年もこのようなお手伝いをしていて感じるのは,問題提起,現状と課題・論点の体系的整理,実現方策の検討と行動提案,その効果評価と着手点などについての整理の仕方,進め方などを実践的に体験し学ぶ機会が少ないことです。
もちろん,実際の仕事の中では無意識にやっていることですが,通常は目の前の課題からスタートすることが多く,全体の把握から始めることは意外に少ないのではないかと思います。何年もやってきて,やっと最近,そのあたりの進め方の説明と手伝いが,以前よりは少しうまくできるようになってきたのではないかと思っています。自己満足かもしれませんが。
いずれにしても,実際の現場で仕事をしている職員さんたちとこんな作業を一緒にすることは,学生相手よりも面白いと感じています。このような社会人教育というか,現場の実践者のスキルアップの支援の重要性が高まっているように感じています。
このあたりも,これまで雑多な分野で雑多な経験をさせていただいたからだと思いますし,その恩返しを少しでもしたいと思っています。
2014年1月12日
年末年始の休み明けに5日間働いた上に,土日に行事があり2日間とも終日仕事に出ていたので,なんだかずいぶん働いた感じです。
まあ,そうは言っても,年明けから仕事があるというのはありがたいことであり,感謝しています。
年明け早々からも,いくつか個人的な活動の話をいただいており,いい感じです。
振り返ってみれば,一つの型に収まらないできたことが,何らかの意味を生み出しているのではないかと感じています。安定的に頼ることのできる資格や肩書やポジションがないまま,その時々の取組みや成果の積み重ねに集中してこれたことは,結果としては恵まれてきたことだと思っています。
大学に転職した時に,そのままいれば定年までまだ何年もあったのですが,辞めたことで,結果的には,新たな経験ができて良かったと感じています。このように,常に不安定な自転車操業を続けてきた感じですが,それだけにこだわるものなく,自由にもがいてこれたのだと感じています。
着実に実績と能力を積み上げていかれる方を尊敬しますが,私なりの道もあると思っています。常に新たな環境の中で緊張感を持って無から手探りで勝負してきたが故に,できることもあるのではないかと思っています。
新たな年の仕事を始め出して,改めてそんなことを考えています。今年も,地域医療,国際,行政の3つのバランスよく,元気にジタバタしていきたいものだと思っています。
2014年1月5日
普段よりも2日長かった年末年始の休暇も,今日でおしまいです。昨年の年末年始は13連休を取りましたが,南イタリアのレンタカー旅行で10日使いましたので,今年の方がゆっくり過ごした感じです。
特に,昨年末は,12月下旬に新潟での研修講師の後の佐渡ヶ島旅行,年末休暇の最初に尾道の老母と義父を連れての島根の温泉旅行と行事を予定していたために,大掃除を12月中旬に済ませたため,いつもの年末の気忙しさがなく,気分的にゆっくり過ごせました。
気になることは早めに片付けておくものだと感じた次第です。
今年は,県庁退職後の2年目を迎える年です。昨年は,退職時のドタバタがあり,新たな仕事に就いての立ち上げ,三次市の行革審議委員会会長就任や日赤広島看護大学の非常勤講師や南米チリでの国際フォーラムでのスピーチ,内閣府の自殺対策連携コーディネート研修の全国6都市ツアーなど新たな展開が続いて,いつもながら目の前のことに追われた日々でしたので,今年は少しじっくりとこれからを考えたまとまった仕事をしていきたいと思っています。
特に,内閣府の研修で全国を回ってみて,社会サービス分野での連携とコーディネートについて,学問的な理屈ではなく,実践を通じての体験から得た知見を共有する機会が少なく,かつ,それを求めている方々が多くいることを感じましたので,このあたりの部分をもう少し掘り下げていければと考えています。
幸い,県庁を辞めて血圧が15も下がった健康状態は維持できていますし,新しい仕事の足場も少しずつ踏み固めつつありますので,これまでの38年間の社会人経験の実践の中で得る機会に恵まれた経験をできるだけ共有させていただき,また多くの人々との交流の中で新たな発見を加えながら,発展させていきたいと思っています。
今年も既に,地域医療,国際,行政の各分野で研修講師等の声をかけていただいていますので,一つの分野の中で深めていくのではなく,実際に雑多な分野でもがき続けることのできた実体験を一つの価値として,その経験を少しでも,現場で頑張っている方々に役立てていただければと思っています。
この一年が,皆さまにとっても充実した一年になりますように。
2014年1月1日
あけましておめでとうございます。
昨年は,波乱の年でもありましたが,新たな展開の年でもありました。
今年は,さらに前に歩みを進めていきたいと思っています。
多くの魅力的な方々とのご縁をいただいていることに感謝をしつつ新たな年を迎えています。
様々なご縁に恵まれていることの幸せを,社会のためにも少しでも生かしていきたいと願っています。
本年もよろしくお願いいたします。
今年が,みなさまにとって良い年でありますように。
| 橋本康男のひとり言2014年 | '01 | '02 | '03 | '04 | '15 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | 今年 |
|---|
| 橋本康男のトップページへ | 参考フレーズ集 | 駄文抄 | 遊びのページ | English Page | 広島大学での4年3か月 |
|---|
Since 13 Feb. ' 05