| ���{�N�j�̃g�b�v�y�[�W�� | �Q�l�t���[�Y�W | �ʕ��� | �V�т̃y�[�W | English Page | �L����w�ł̂S�N�R���� |
|---|
�Q�O�O�W�N�P�Q���Q�V��
�@����ŁC���N��(�{�Ƃ̕���)�d���[�߂ł����B�P�`�R���́C������ے��Ƃ��āC�l�Â���r�W�����̎��܂Ƃ߂�C���y�`���v��̒����n���v�������Ƃł̂T�������ȂǁC���\�艞���̂���d���ł������C�S�`�P�Q�������ۉے��Ƃ��āC���Ȃ���ʉۑ�ɑS�͂Ō����������X�ł����B���������肪���̂���d���ł������C�l�I�ɂ́C���Ɖۂ̎d���̕����C���X�_�C�i�~�b�N�ɕω��ƃX����������C�����̊W�҂̕��X�Ƃ̋�̓I�Ȃ���肪�����āC�l�I�ɂ͌����Ă���悤�ȋC�����܂��B���p���ۑ��V�K�ۑ�Ȃǂ��낢�날��܂������C�Q�O�l�Ƃ������ǂ��K�͂̑g�D�ł�����C�X�^�b�t�݂̂�Ȃƈꏏ�ɑO�����Ɏ��g�߂��Ǝv���܂��B�i���������Ă̎������̑�|�����Q�����j
�@�{�Ƃ̎d���̓��e�ɂ��Ă͂����ł͐G��܂��C���N�����낢�날�钆�ŁC�l�Ƃ��Ă߂������̂������Ƃ̑�������߂Ċ����܂����B�����łȂ��ƁC�`���⌨�����E�̖ʂɖ��Ӗ��ɂ������悤�ɂȂ�܂��B�����ł͂Ȃ��āC�߂������̂��������l�̐Â��Ȕ��͂����߂��鎞��ɂȂ��Ă��Ă���̂��Ǝv���܂��B�ȑO�����������Ǝv���܂����C�w������ɓǂ�ł����Љ�S���w�҂̃G�[���b�q�E�t�����̖{��"To be or To have"�Ƃ����̂�����܂��B�i�����܂ŏ����Ă��āC�O�̂��߂ɏ��I�Ŋm�F������"To have or To be"�i���{���́w������Ƃ������Ɓx�I�ɍ������X�j�ŏ��Ԃ��t�ł����B�����Ǝv���Ⴂ�����Ă��܂����B�j�u�v�́C�������⎑�i����Y��ߋ��̎��тȂǂ��ǂꂾ�������Ă���̂��ł͂Ȃ��āC���C�����������߂����Ăǂ̂悤�ɐ����Ă���̂�����肾�B�v�ƁC���͉��߂��Ă��܂��B���̓_������C�{���̏��Ԃ̕����K���ł��ˁB
�@�ߋ������ɓ���̂ƁC�����Ȃ������Ɍ������Ė͍����Ă����̂Ƃł́C�X�����Ə[�������Ⴂ�܂��B
�@�C������Ȃ��Ƃ͂��낢��Ƃ���܂����C�܂��Ȃ�Ƃ�"������"�d���[�߂̓����}���邱�Ƃ��ł��C�E��̃`�[���̃����o�[��W�҂̕��X�Ɋ��ӂł��B
�@�Ƃ������ƂŁC���������B�ւR���Ԃ̃~�j���s�ł��B
�Q�O�O�W�N�P�Q���Q�P��
�@���N�̎c��̓��X�����Ȃ��Ȃ��Ă������ŁC���Ԃ͒����ɉ߂��Ă����܂��B���j���́C�ߑO���ɁC���N�V�����猎�P����x�̃y�[�X�ł���`�����Ă���O���s�̐E�����C�ɍs�������œ����ł̍������_�ی��������̌�����ɁB�����v�����Ƃł����C�G���Ȃ��Ƃɐߑ����Ȃ����˂�����ł��邱�Ƃ̈Ӗ��̈�́C���l�ȕ���ł����d�������Ă�������X�ɂ���ł��邱�Ƃł��B
�@���_��Q�̂�����̏Z���m�ۂ̂��߂ɐ^���Ɏ��g��ł�������X�Ƃ́C�ӌ������̏�ɎQ�������Ă��������Ă��邱�Ƃɂ��w���Ă��������Ă��邱�Ƃ̑傫�������߂Ċ����܂����B
�@�����w�߂��ł̌�����̌�ɁC�T�l�قǂň��݂ɏo���Ƃ���C�N���̋��j���Ƃ������ƂŁC�\�������ȂŒf���āC����Ɠ���܂����B�F�{���痈���Ă���搶���C�u�F�{�ł͖��Ȃ̓X��������̂��������̂Ɂv�ƌ����Ă����̂ɋ������܂����B���ꂾ�����X�Ɍ��݂����r���ɐl������C�d��������Ƃ����̂��M�����Ȃ������ł��B
�Q�O�O�W�N�P�Q���P�S��
�@�����������雷�H�Ђ��̓��X�ł��B���T���������薄�܂��Ă��܂��B���i�C�����I�ɂ͂قƂ�Lj��݂ɏo�Ȃ��̂ŁC�����̓��X�ł��B
�@���N�́C��N�N���ɒǂ����ݎ��������鍑�����_�ی��������̉Ȍ��̌������|�[�g���Ȃ��̂ŁC�v�X�ɂ̂�т菬���s�����悤�Ɨ��s�v��𗧂ĂĂ��āC�u�p�b�N�c�A�[�nj�Q�v(�g�b�v�y�[�W�Q��)�̕ʂ̖ʂ������܂����B�ŏ��ɂ��̌��t���v���������ɂ́C�c�A�[�q���g���u���͉��ł��Y����◷�s��Ђ̂����ɂ��ĕ��������(��������ȍR�c�������̂ł��傤����)�Ƃ����b���āC��g�ł��ĉ�������Ƒ��l�̂����ɂ���Ƃ����s���l����\���Ӗ��Ŏg���o���܂����B
�@�������Ȃ���C����C���ȁI�Ƃ̋�B�ւ̂Q���R���Ƃ��������s�̌v��Â�������Ă݂āC��̌v�����邽�߂ɂ͐��������̏��Ǝ��s���낪�K�v�ɂȂ�Ƃ���������O�̌o�������܂����B���ꂾ���C�ŋ߂́C���X�ڂ̑O�̂��Ƃɒǂ��Ă���Ƃ������Ƃ�������܂���B���ꂱ���C���s��Ђ��p�ӂ����p�b�N�c�A�[�ɎQ�����邩������Q�l�ɂ���ΊȒP�Ȃ̂ł��傤����ǁC����ł́u�W���I�Ȃ��́v��Ǒ̌����邾���ŏI����Ă��܂��܂��B
�@���x���s���Ă�����x�͒m���Ă����̋�B�ł��C�����R�����̓������l���悤�Ƃ���ƁC�����̌o�H�����ł��������H����ʓ����C�t�F���[�͎g�����ǂ����ȂǁC���ꂼ��̏��v���Ԃ◿���ȂǂׂĔ�r���Ă݂�K�v������܂����C���̓r���Œʂ��Ă݂����ꏊ�̑I��ɂ���Ă����_�͕ς���Ă��܂��B�h�ɂ��Ă��C�R�X�g�d���������₩���ґ���߂����̂��C���̐܂荇���̒��Ŗ����ݏo�����߂ɉ��ɏd�_��u���đI�Ԃׂ����ȂǁC���ꂱ���K�v�ɂȂ�܂��B����ɂ͐�����蓹�̍�Ƃ�����܂����C�܊p�W�߂Ă����ʂɂȂ���R����܂��B���i�̏T���̍u�t���̏����ɔ�ׂĂ����������������ł������C�l���Ă݂�ΐV�������Ƃ����鎞�͂�������Ȃ��̂ł��B
�@�ł��C����Ȏ��s����̒��ł́u���ʁv�̒~�ς��C�Ӗ��������Ƃ�����܂��B�ړI�n�ɍs�������Ȃ�p�b�N�c�A�[�ɎQ�����āC���邢�͂��̍s�����Q�l�ɂ��Đ^��������ł��傤���C���̗��s���̂��������y�������Ƃ���C�����ߒ��ł́u���ʂȁv�u�]�v�ȁv��Ƃɂ��Ӗ����o�Ă���̂��Ǝv���܂��B����P�{�̓������m��Ȃ��̂ł͂Ȃ��C���s����̌��ʂƂ��đ����̓���m������ł����̓���I�ԂƂ����̂́C���Ɛ[�݂��Ⴄ�悤�Ɏv���̂ł��B�����o���̐��̍��ɂ��Ȃ���悤�Ɏv���܂��B
�@�Ȃ�āC���������s�̌v��ɂ����Ƃ��炵���u�߂�����Ă����傤���Ȃ��̂ł����C�����Ȏ��Ԃ����������Ƃւ̎������g�ւ̌�����ł��B
�Q�O�O�W�N�P�Q���V��
�@�����P�Q���ł��B����c�̐E���Z�~�i�[���Ȃ�Ƃ��I���C�v�X�̖�s��Ԃ����߂������ɋA���Ă��āC���Ƃ͂����Ȃ���̃h�^�o�^�Ƃ����P�T�Ԃł����B�Ƃ��������C���Ӊ���H�Ђ��̔�ꂪ���܂����P�T�Ԃ������Ƃ����������������ł��B
�@�u�t���ɂ��Ă͂Ƃ肠�����ڂ̑O�̏h�肪�Ȃ��Ȃ����Ǝv���Ă�����C�P���Q���ɂ��ꂼ��p��o�[�W�����̂��̂��T���Ă���C�Ȃ�ƂȂ��C������ɂȂ��Ă��܂��B�������͑�������ł��ˁB
�@�Ƃ͂����C���N�̔N���͌������|�[�g�̏h�肪�Ȃ��̂ŁC�v�X�ɂ�����肵�悤�ƃ~�j���s�̌v�撆�ł��B
�@���N�P�N��U��Ԃ�̂͂܂������ł����C�N���h�^�o�^���Ă��邱�Ƃ̃����b�g�̈�́C���낢��Ȗ��͓I�ȕ��X�ɂ���ł��邱�Ƃł��B����́C���͓I�ȕ��X�Ƃ̐ړ_�����������ɁC����ɋC�������Ƃ̂ł���\���������Ȃ�Ƃ��������������邩������܂���B��������̂Ȃ��b�����Ă��邤���͋C�����Ȃ������̂ɁC������Ɠ��ݍ���Řb�����Ă݂悤�Ƃ����v���ɂȂ�C����������łĂ����������Ԃ��Ă��Ďv�킸�b������ł��܂��Ƃ������Ƃ����X����܂��B�������C��U�������̂ł����C�������Ԃ��߂������o�����ςݏd�Ȃ�ƁC��U��ɑς��₷���Ȃ�悤�ɂ��v���܂��B
�@���N�������܂ŗ��ꂽ���ƂɊ��ӂ��āC�c����ɉ߂��������Ǝv���܂��B
�Q�O�O�W�N�P�P���R�O��
�@���N�O�Ɉ˗�����Ă��炸���ƋC�����肾�������S�E���S�Ȃ܂��Â�������k�斯���i�L���s�j�ł̍u���u�n����J����Ă�Θb�͂ƃR�[�f�B�l�[�g�́v���Ȃ�Ƃ��ς�ŁC�ق��Ƃ��Ă��܂��B�̂̎d���̂Ȃ�䂫�ň������T���̍L�����x�̒n�楐E��h�Ɛ��i�����C��Łu�l�Ɛl���Ȃ��Θb�͂ƃR�[�f�B�l�[�g�́v���ꂵ����ɂ�����̂��_�@�ň�����H�ڂɂȂ����̂ł����C�n��h�Ƃ̑f�l���������Ȃ������ƌ�����ǂ����ł����B�斯���T�O�O�l�ł̍u���Ƃ����̂͏��߂āC�Ƃ��������̗��R�ň������̂ł����C����͏����D����������܂����B
�@�����C�����̏o���͕ʂƂ��āC�Ȃ�ł��������傱���傢�ň����邱�Ƃ́C�������Ƃ���ł͂���܂���B�����ɕ�����₷���`���邩��^���ɍl�����������ʁC�V���Ȕ���������܂����B�������钆�ɃA�C�f�A���v�����C��������p���[�|�C���g�̏C����Ƃ����Ă��܂����B
�@��͂�C�����ɂȂ��Ă��C�����Ŏ������ǂ��l�߂����������Ă������Ƃ́C�������Ƃ���ł͂Ȃ��Ɗ����Ă���Ƃ���ł��B
�@���N�́C���Ƃ͖�����̑���c��w�̐E���Z�~�i�[�����I�Ǝv���Ă܂�����C���j����ɋ��m�̈�t��̐搶����d�����h����˗�����āc�B�����Ȃ���C�Ȃ�ł���Ȃɂ��܂����v������悤�Ɏ��̎d��������̂��낤�ƕs�v�c�Ɏv���܂��B�����́C����ŐU��ꂻ���ł��B
�@�{�Ƃ��i������O�ł����j���Ȃ�Z�������ŁC�ǂ��������̂��ƔY�݂C�Y��ł��d�����Ȃ��ƊJ�������Ă���Ƃ���ł��B
�Q�O�O�W�N�P�P���Q�R��
�@�����́C�V���̂W�X�̒a�����j���ɔ����ցB�j���V�����ƕ��炰�錒�V�Ԃ�Ɋ��S����̂݁B
�@����ȊO�́C���ς�炸�̍u�t���̏����łR�A�x���I��肻���ł��B�T�����͌����L����w�̂P�N���Ώۂ̎��ƁC���̓��j���������k����S�E���S�Ȃ܂��Â�������k�斯����ł̍u���B���̎��̏T�����́C����c��w�̐E���Z�~�i�[�̍u�t�ŁC����Ŗ{�N�̗\��I���ł��B
�@����c�͂P�����ċA����肾�����̂ɁC�����ɋc��̈ψ���̗\�肪���������߂ɁC��s�Q��ʼn��R�܂ŋA���ĐV�����ɏ��p���ŐE��ɂ͒莞�o����H�ڂɁB�v���Ԃ�̖�s��Ԃł��B
�@����Ȃ��Ƃ����Ă��邤���ɁC���N����ꂻ���ł��B�ʂɌ��C�u�t�ȂǂłP�N���߂����Ă����ł͂Ȃ��̂ł����C�{�Ƃ̂��Ƃ͂����ł͏����ɂ����̂ť���B����ꂽ���E�Ő����Ă��銴���ł��B
�@�Ƃ͂����C����͏T���P��̓������̃N�A�n�E�X�ʂ��̉��H�ɁC���߂Ēʂ�R���Ƀg���C�B�Ό��Ԃ������瓖���o�b�N���ė����ꏊ��T���Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ȓ����h�L�h�L���Ȃ���o���čs���܂����B�����R�n�̉��₩�Ő[�݂̂���g�t�����\���܂����B
�Q�O�O�W�N�P�P���P�U��
�@��T�ؗj���́C�I���x�ɂ�����āC�P�A�}�l�E�X�L���A�b�v���C�̎��ጤ���̍u�t���H�i����`���j������Ă��܂����B���Ɋւ�鎖�ጟ���̒��ŁC�l�̓w�͂Ƒg�D�I�E�Љ�I�x���̂������Ƒ��̎p�Ȃǂ��l��������ꂽ�Ƃ���ł��B
�@�j�Ƒ������i�ނƂƂ��ɁC�a�@�╟���{�݂ōŊ����}���邱�Ƃ����������Ƃɂ��C�l���̍Ō�̎����ɐڂ���@��ɒ[�ɏ��Ȃ��Ȃ��Ă��Ă���悤�Ɋ����܂��B���̎����ɂ́C����܂ł̐l���̗l�X�ȗl��������Ă��邱�Ƃ��w�т܂����B�D�����łȂ��Ă����̂ŁC�����Ȃ�Ƀo�����X���Ƃ�[�����Ȃ��琶���Ă������Ƃ�����Ɖ��߂Ċ����܂����B
�@����ō��N�͂��ƂR�{�̗\��ł��B���T�������̏����łقڏI����Ă��܂��܂����B����Ȃɖ��T���T�ڂ̑O�̏����ɒǂ�ꑱ���Ă��āC��̉����c��̂��낤���Ǝv���܂����C�l���Ă��Ă��n�܂�܂��C����Ȃ�Ɋy����ł��镔��������܂��̂ŁC�܂��������Ǝv���Ă��܂��B
�@�{�Ƃ̕����C�i������O�ł����j���낢�날��C�ْ���������X���߂����Ă��܂��B����Ȃ��肬��̐����𑱂��Ă�����̂��E��̓����̂������Ɗ��ӊ��ӂł��B
�@���������C����͖����߂鏬�w�Z�̉��y�ՂɁB�ŋ߂́C�l�ނ͈�Ă���̂ł͂Ȃ�������҂�I��������̂��C�Ƃ����_��������܂����C�����ł͂Ȃ�����̗͂����߂ċ��������܂����B����͎��ɂ�������l�����ď��߂Ď���������̂��Ƃ������܂����B���ɂ�����낤�Ƃ���l�̓w�͂ɐ�����������������l�͏�ɂ��āC����ɑς��Ď��ɂ������w�͂��������قnjǗ����ɂ����Ȃ܂��Ƃ����ꂵ���ɑς��Č��ʂ��o���l�̑�����������Ƃ���ł��B�Ƃ͂����C�����������ł͂Ȃ��C�������Ȃ���撣�鑤�ɗ��ĂĂ�������K���ł͂Ȃ����Ƃ��v���܂��B
�Q�O�O�W�N�P�P���P�O��
�@�T���ɖ{�Ƃ���݂̎d�����������̂ŁC����������̂����O���Ă��܂����B�ʂɖ��T�����K�v���Ȃ��C�܂��C�`���Ɋ�����̂�����Ńu���O�ɂ��Ă��Ȃ��̂ł����C��͂艽�������Ȃ��ƂP�T�Ԃ̋�肪���Ȃ��悤�ȋC�����܂��B
�@����́C�w������̂ƂȂ��ĉ^�c���Ă��鍑�ۃC���^�[���V�b�v�̔��\��ɂS���ԏo�Ȃ��܂����B�O���[�v�ł̊w���Ƃ̈ӌ������ɂ��Q�������̂ł����C�u���ۍv������肽���v�Ƃ����w������ɑ��āC�u����I�ɉ��������Ă�����Ƃ����v���ł͂Ȃ��������w�ѕω����Ă����Ƃ����p�����K�v���v�Ƃ��u�w�ł��邱�ƁC��肽�����Ɓx�Ɓw���ׂ����Ɓx�͈Ⴄ���C���ׂ����Ƃ��l���Ă��Ȃ��ƒ��������Ȃ��v�ȂǂƁC���������ɂȂ��Ă��܂��Ă��鎩���ɁC�������Ă��܂��܂����B
�@�ł��C���ꂾ���̎��Ƃ�����Ă���w�������ɁC�u�����̎Ⴂ����v�ւ̔F����ς����@��ł����B�Ƃ͂����C���͂�͂�Љ�l����̎d���̕����C���ɍ����Ă���悤�Ɏv���܂��B
�Q�O�O�W�N�P�P���R��
�@��T�́C�J���{�W�A���{�E���ւ́u�Ȃ��s�����Z���ɑ��ăT�[�r�X����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�Ƃ����e�[�}�ł̂Q���Ԕ����C�́C���҈ȏ�ɔ������悭�C�[���������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B�i���Ȗ�����������܂�����j��������Ă��C�S�������Ă������������̖ڂ̐F�₤�Ȃ������͓����悤�Ɏv���܂��B����e�[�}�Ȃ̂ŁC��������ŏ������n�߂Č�������̂ł����C���ʂƂ��Ă͂�点�Ă��������ėǂ������Ƃ�����ۂł��B�V���Ȃ��Ƃ𗊂܂ꂽ���ɁC�u���Ŏ��������Ȃ�������Ȃ��̂��v�Ƃ����������͂��肤��Ƃ͎v���܂����C�Ƃ肠���������Ă݂Ă���Y�ނƂ����̂��C�i��ςł͂���܂����j�����Ȃ��Ǝv���Ă��܂��B
�@���̂R�A�x�́C�n��Љ�U�����c�̌��N�����v�����i�[�{���m�̂P�O���N�L�O�t�H���[�A�b�v���C�ŁC���l�̃z�e���̌��C���ɂR���Ԋʋl�ł����B�e����Ŋ���Ă���u�t�̕��X�ɁC���̒��ɂ͂����d�������Ă�������X��������������̂��Ɖ��߂Ċ��S����ƂƂ��ɁC�������������Ă��������܂����B���́C�Q���ڌߌ�ƂR���ڌߑO�̃O���[�v���[�N�̂���`���������̂ł����C�S���e�n����W�܂�ꂽ���X�̔M�S�Ȃ��b�ɁC����܂��������^���ɂ��Ȃ���ƍl��������ꂽ�Ƃ���ł��B
�@���X�̐����ɂ́C�^�s�^���g��������܂����C�����炸�������C�u���ꂽ���̒��Ŏ����ɂł����̓I�ȍs����ςݏd�˂Ă����Ȃ���C���̂悤�Ɋe�n�Ŋ撣���Ă�����X�ɂ���������ɒp���������Ȃ��Ă��܂��ƁC����܂����߂Ċ���������ł��B
�@�{���m�̋c�_�ł́C�n���̌���ł̎�g����ɂȂ��Ă��鎞��ɁC���̂悤�Ȍ���̒m�b��S���ŏW�ċ��L���邽�߂̃Z���^�[�Â�����ǂ����Ă����̂�����̃e�[�}�ł����B�����g�̓A���`�����ł����C�n���̌���̎��H���瓾��ꂽ�m�b�̏W�ςƋ��L�̎d�g�݂͕K�v���Ɗ����Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�P�O���Q�U��
�@��T�́C�ŋ߂����̂ł����^��w�̌�����ŋx�ɂ�����ď㋞�B�F�X�Ǝh�����邱�Ƃ��ł���̂͂��肪�����̂ł����C���N���̋x�ɂ��c�菭�Ȃ��Ȃ��Ă��܂����B
�@���T�����C�N���܂łɈ����Ă���u�t���̏����ŏI����Ă��܂��܂����B�i�Ƃ͂����C�͂Ȃ͂��W���͂̏オ��Ȃ��C������Ȏ��Ԃ��߂��Ă��܂��܂������B����Ȏ��́C�ڂ��ڂ�����Ă��������Ȃ��Ǝv���Ă܂��B�j
�@�v���������Ȃ��悤�ȎG���ȕ���̈˗����_�{�n�[�ň����Ă��邤���ɁC�F��Ȋp�x���猩�������ł���̂��ʔ����Ƃ���ł��B�����́C�i�h�b�`�̌��C�ŃJ���{�W�A���{����h�����ꂽ�E���̕������ɁC�u�Ȃ��s�����Z���ɑ��ăT�[�r�X����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v���Q���Ԕ��Ō��Ƃ��������ł��B������N���[����ť���B�������ʖ���C���O�ɍ쐬�����������N���[����ɖ|�Ă��������Ă���̂ł����C�|�ꂽ���̂����������ǂ߂Ȃ��̂ŁC�ǂ��Ȃ邱�Ƃ��Ƃ����Ƃ���ł��B�m�l���痊�܂�āC�����l�����Ɉ����܂������C�o����m�����傫���قȂ�l�����ɍl������`���悤�Ƃ���ƁC�v�����ă|�C���g���i��K�v������C�{�����l����悢�@��ɂȂ�܂����B�i�����̐��ʂ��o��O�̂Ƃ肠�����̎��Ȗ����ł��B�j
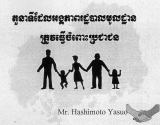
�Q�O�O�W�N�P�O���P�X��
�@�y���Ƃ��������璋�܂ŁC���܂��Ă��錤�C���̍u�t���̏����ɖv�����Ă����̂ŁC�ߌォ��A�ꍇ���Ɛ������R�n�̃h���C�u�ɁB��T�͏㉺���C���T�͉��v���ƁC�ǂ�����Â�����̒���K��܂����B�̂���݂�Ȃ��ꏏ�ɕ�炵�Ă����Ƃ�������c��X�ł����C�Ⴂ�l�����Ȃ��Ȃ����Ƃ����_�ł͓����ł��B
�@�ŋ߂ł́C�n���݂̂Ȃ炸�����܂ł������Ȃ��āC���������Ă��Ȃ�������Ղ̐Ǝコ�������܂����C����ł́C�l�X�����̂悤�Ȃ�����݂̂Ȃ������K���Ɗ����Ă��鑤�ʂ��ے�ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B���������Ă��Ȃ��܂܂ɌǗ������ĕY���������l�X�ɂ��\������関���̎Љ�̎p�́C�����Ă��̐l��������炷�X�̎p�͂ǂ̂悤�ɂȂ��Ă����̂ł��傤���B��s�s�ł͌��i�Ǘ��j�����i�݁C��K�͏Z��c�n�ł͈�č�����i�݁C���R�Ԓn��ł͋����i�ށB����Ȓ��ŁC�N���Љ�̖������l���Đ^���Ɏ��g��ł����̂��C�l����������Ƃ���ł��B
�@�l�X�����ѕt���鉽�炩�̐V�����J�����߂��Ă���̂ł��傤���ǁC�����L���ŗD�������̂ɂ��Ă����H�v�����߂��Ă���悤�Ɋ����܂��B
�Q�O�O�W�N�P�O���P�Q��
�@���̂P�����قǂЂ�����Ƃ̓��O�̕ЂÂ������Ă��āC�قڍ��T���ň�i���ł��B��Ɖߒ��ŏo���_���{�[���Ȃǂ��������݂ɏo�����̂ŁC��͗��T�̑�^���݂̓��ɁC�v��Ȃ��Ȃ������[�Ƌ���o���C�قڏI���ł��B
�@�����͋v���Ԃ�ɂS�����N���Ō��e�����C�P�O���߂�����P��̔����̘V�e�̂��@���f���ŎO��_���ƊD�˃_���߂���B�D�˃_���ł́C�ȑO�m�l�ɘA��čs���Ă�������C�_�����v�ɂ��W�c�ړ]�n�̂����~�����B�҂��������̂悤�Ȍ����Q�ɕ��G�ȐS���ł����B"To be or to have"�����߂čl��������ł��B
�Q�O�O�W�N�P�O���S��
�@���T�����Ƃ̕Еt���ɐ��o���Ă��܂��B�����₩�Ȓ�̏����ȃX�y�[�X�ɂ��傤�Ǔ��镨�u���l�b�g�V���b�v�Ō����āC�����t����ƂƂ��ɁC���ꂱ��Еt�������Ă��܂����B�����������Ȃ��Ă����̂ɁC�������߂��Ă��āC�����ۂ��ۂ��������Ԃł����B
�@���̂Ƃ��뉽�N���C�T���͂قƂ�ljƂŕ����ɕ��������āC�]�Z�̍u���⌤�C�u�t�̏����ɖv�����Ă��܂����̂ŁC�{�i�I�ȕЕt���ɂ͎肪�o�����ɂ��܂����B�ʔ������̂ŁC���肾���Ƃ�����������肽���Ȃ��Ă��܂��B�u�ʔ����Ȃ�v�Ƃ������Ƃ��Ǝv���܂��B���ɁC�Ƃ̓��O�̍�Ƃ́C���ʂ������ɖڂɌ����܂����C�֗��ʼn��K�ɂȂ�̂ŁC���C���o�܂��B���̖{�Ƃ̎d���Ȃǂ̏ꍇ�́C�Ȃ��Ȃ������͂����܂���B��̌����Ȃ����ɂ����Ɛ𓊂����ݑ����Ă���悤�Ȃ��̂ŁC��̑O�Ɍ����Ă���̂��ǂ�������s���ɂȂ��Ă��܂��B
�@����ȕs�����ɑς��Đ𓊂����ݑ����Ă����ӎu�ƔE�ϗ͂����߂��܂��B�~�߂��ɑ����Ă���ƁC�ςݏd�Ȃ��������̐��ʂɓ����o���悤�ɐ��ʂ������Ă��邱�Ƃ�����܂��B�����łȂ����Ƃ��C���X�ɂ��Ă���܂����B
�@������ɂ��Ă��C���������₩�Ȃ��Ƃł���̓I�ɍs�����N�����Ă������ƁC�����āC���̒��Ŋy���݂����o���Ă������Ƃ���Ȃ悤�Ɋ����Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�X���Q�W��
�@��T���ɑ����āC�Ƃ̓��O�̕Еt���ɐ����o�����T���ł����B���N�Ԃ肩�Ƃ�����|����ȍ�Ƃł��B�����ɂ�炸�C�V���Ȃ��Ƃ��n�߂�Ɨ\�z�O�̂��Ƃ��o�Ă��ċ�J����̂��C�����y���݂Ȃ���h�^�o�^���Ă��܂����B�L���̕ǖʗp�ɓV��܂ł̍����̑g�ݗ��Ď��̎��[���E�F�u�T�C�g�ōw�����Đݒu�����ۂɂ́C�g�ݗ��ď����ԈႦ�Ă�蒼������(����͒P�ɒ��ӗ͕s���ł�)�C�҂��������\�肪�V��̉��̏���V���ז��ɂȂ��ē���Ȃ����߂Ɉꕔ�����͂߂ɂȂ�����C����̕ǖʂ��V�������[�̔��F�̔��ł��ꂢ�ɂȂ������߂ɁC���̖ʂ̕ǎ��̉��ꂪ�ڗ��悤�ɂȂ��Ă��܂��ǎ��̒��ւ��܂ō�Ƃ��L�����Ă��܂�����B�ǎ���\��̂��C�ŏ��͗v�̂�������Ȃ����߁C���s�����ł����B�܂��C��̕����C�R�u�قǂ̍L���Ƀ����K��~���l�߂�̂ɁC�ȑO�C�蔲���ŒP�Ƀ����K����ׂĂ��̂ł����C���ǂ���ł͂��܂��������C�y���@��Ԃ��č�����~������~������Ń����K����ג����܂����B��͂�C��{�ɒ����Ɏ�����Ɋ�b������Ȃ���������肵�����̂ɂ͂Ȃ�܂���B
�@�d���ł������ł����C�����V�������Ƃ���肾���ƁC�\�z�O�̖�肪�N������̂ł����C�V���ȗ]�v�ȍ�Ƃ����X�ɍL�����Ă������̂ł��B�܂��C���̏ꂵ�̂��̎蔲���d���͌��ǂ͊�b�����蒼�����ƂɂȂ�܂��B�ŏ��͂��܂����������s���J��Ԃ��C�䖝���Ă���Ă邤���ɁC����Ɨv�̂��悭�Ȃ��Ă��āC�Ȃ�Ƃ��i�D�ɂȂ��Ă��܂��B���̉ߒ����y�����̂����m��܂���B�u�y�v������Ƃ����̂ƁC�u�y���ށv�Ƃ����͈̂Ⴂ�܂��B���ɂ����Ȃ���Ύ��s�����܂��C�����ݏo���y�������o���ł��܂���B
�@������ʔ����Ɗ������̂́C�V���Ȃ��ƂɎ��g��ł���ƁC�����̂Ă���悤�ɂȂ邱�Ƃł��B���i�������Ă��Ȃ����ɂ́C�����g��Ȃ����̂ł��Ȃ��Ȃ��̂Ă��Ȃ����̂ł����C�V�������Ƃ�����Ă��鎞�ɂ́C���肫�肪�ł���悤�ɂȂ�̂�������܂���B�������������������Ă����Ă�C�O�ɐi�߂Ȃ����炩���B
�@�Ȃ��C���P�b�������Ȃ��Ă��܂��܂������C�̂����č�Ƃ����邱�Ƃ̖ʔ��������߂Ċ������T���ł����B�i�ł��C�������ō��͒ɂ����C�F�≊�Œʉ@���Ă���Ђ����ɂ�������B�j
�Q�O�O�W�N�X���Q�S��
�@���������C��r�I�Â��ȓ��X���߂����Ă��܂��B
�@�������C���������������Ďd�������Ă����ł�����C�����Ƃ�����ɂ͂����܂���B
�@����Ȓ��ʼn��߂Ċ�����̂́C�������g����Ɂu�]�v�Ȃ��Ɓv�����������u�v��Ɓv���������Ă����Ƃ����v���ł��B�u�펯�v��u���V�v�Ɏ�����������Ȃǂ܂������Ȃ��Ă��C�u�ǂ���v�Ǝv���Ă��t���C���O�����Ă��܂����Ƃ̘A���������Ǝv���܂��B
�@�u�v��Ɓv������ƌ���ꑱ���Ȃ�����C����ł����̍s���l�����ς��Ȃ��̂́C����ɂ���Ď����ł������Ƃ̕����u�g�D�̏펯�v�ɏ]�����������傫�������̂ł͂Ȃ����Ƃ����v���ł��B�u�����͋��R�̎Y����������Ȃ������̋��R�ݏo���͓̂w�͂̎Y���v���Ɗ����Ă��܂��B���R�̂��肪�����͏[�������Ă��܂����C����ł��w�͂̎Y�����ƌ��������̂́C�u�v��Ɓv�����Ă��Ȃ���ΐ��܂�Ȃ��������Ƃ������Ƒ̌����犴���Ă��邩��ł��B
�@�s�V�ǂ��D�����ʼn߂����Ă��邾���ł́C�ω��͐��܂�Ȃ��̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B�u�v��Ɓv���������āC���s��p���������v���ɑς������邱�Ƃɂ���Đ��܂����̂�����̂��Ǝv���Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�X���Q�Q��
�@���j���̒��o������C�������͋x�݁I�Ǝv����K���B�����́C�������ł����B
�@�W�����̑������n�r���e�[�V�����������I����āC�v���Ԃ�ɖڂ̑O�̂��̂��ɒǂ��܂����Ȃ����X���߂����Ă��܂��B�i�{�Ƃ̃h�^�o�^�ƁC�N���ɂ��ƂX�{�u�t�������Ă��܂��Ă���]�Z�̏����͒u���Ƃ��āB�j
�@�ǂ��܂����Ă���ƁC�K�v�Ȗ{�����ǂ܂Ȃ��Ȃ�܂��B�W���͂Ђ����烊�n�r���e�[�V�����W�̖{��ǂ�ł��܂����B�Ƃ����Ă��C�ƂŊ��Ɍ������Ă��鎞�͎��������ň�t��t�Ȃ̂ŁC�ʋ̉����Ȃǂ̈ړ����Ԃ𗘗p���Ăł����B
�@���ꂪ�C�ӂ��Ǝ��Ԃ��ł������ɁC�������̂����{�ɏo����Ƃ��ł��܂����B���o�r�W�l�X�Œm�����_�J�G�����́u�j���[���[�N���������T�l�̑傫�ȉ�Ёv�i���I���[�j��C�����̏��]�œǂ�ؕq�v���́u�d�����y�@�X�^�W�I�W�u���̌���v�i��g�V���j�Ȃǂł��B
�@�v�X�Ɋ��Ɍ������Ė{��ǂގ��Ԃ��ł��C�{�̓��e�ɂ��G������āC�������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B��̂���l�́C����̏���l�������Ⴄ�Ǝv���܂����C���ʂ��Ă�����̂́C�߂������̂ւ̂������̂悤�ȋC�����܂��B�߂������̂ɎЉ����Ր�������p���������Ȃ������ł��邩�炱���C�ꐶ�����ɂȂ葱������̂��Ɖ��߂Ċ����܂����B�s���ɓ����Ă݂āC�u�ꐶ�������p���������Ȃ����Â���v�Ƃ������Ƃ��v�������Ă��܂����B�Љ�ƌl�̉\��������������Ƃ����߂������̂�����C����̐l���������قǂ̂�����肪�Ȃ���C�ꐶ�����ł��葱���邱�Ƃ͂ł��Ȃ��悤�Ɏv���܂��B�ڂ̑O�̑����ł͂Ȃ��C����������ňÂ��C�ɒ���ł������ɒp�����ɂ����邩�ǂ����C���ꂪ�s���K�͂ɂȂ�̂ł͂Ȃ����Ǝv���Ă��܂����B
�@���̂���l�ɋ��ʂ��Ă���̂́C�ߋ��́u���сv��ے�E�̂ċ���V���Ȃ��̂ݏo�����Ƃ��ł�����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�ߋ��̒~�ς̏�́u���̐��E�v�̒������Ő�����̂ł͂Ȃ��C�����Ɍ����Ď����𓊂��o���Ă��������̋�̓I�ȍs�����ł��邱�Ƃ��C�l�݂̂��݂��������ݏo���悤�Ɏv���܂����C���܂������ۏ̂Ȃ����Ƃɒ��킷��s�������������ݏo���̂��Ǝv���܂��B�w������ɌX�|�����Љ�S���w�҂̃G�[���b�q�E�t�����̒���ɁuTo be or To have�v�Ƃ����̂�����܂��B(�ߋ��̐��ʁC���i�C�������Ȃ�)���������Ă��邩�ł͂Ȃ��C���C�Ȃɂ��߂����Ă���̂��Ƃ����u���݁v��₤���̌��t�́C�����V�����Ǝv���܂��B
�@�������͋x�݁I�Ƃ����K���������B
�Q�O�O�W�N�X���Q�P��
�@�l�ɂ͂��ꂼ��W���N�X�Ƃ����������̂悤�Ȃ��̂�����Ǝv���܂����C���̏ꍇ�C�V�C�������Ȃ肩����Ɩ��ӎ��ɉ����̂��������Ȃ�Ȃ�悤�ł��B�w������ɎR�ɓo���Ă������ɂ�������イ�J�ɍ~���Ă����̂͊W�Ȃ��ɂ��Ă��C����Ă���̂ŎԂ������胏�b�N�X���������肵���Ƃ���ɉJ�ɍ~����Ƃ������Ƃ��C���R�Ƃ͂����Ȃ��p�x�ő����܂����B�ǂ����C�V�C�����ꂩ����Ɓi�C���������肩����ƁH�j�����̂��������Ȃ�悤�ł��B
�@����̓y�j�����C�i������ƈꑧ���Ă��邱�Ƃ�����j�Ƃ̒��̖͗l�ւ����������Ȃ�C���ʏ��̎��[�̉��P��L���ɕ��ׂĂ���{���̈ړ��ȂǂɊ��������Ă���ƁC��ɂ͂�������J���~��܂����B�܂��C�J���Ƃ̒����璭�߂Ă��镪�ɂ́C��������Č��\�ł����B
�@���T���ɂR�Okm�̃h���C�u�Œʂ��Ă��鉷��v�[���t���̃X�|�[�c�W���ւ̉����̔_�����i���C������ďH�F�ɂȂ��Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�X���P�R��
�@��T�́C�����ƘA�x�ɂ��Ă�����蓇���ւ̂P���Q���̗��s���y���ޗ\��ł������C���j���̒��̐V���L�������������ɏI���h�^�o�^���Ă��܂��܂����B��̑O�Ȃ痷�s�𒆎~���ĐE��ɏo��Ƃ���ł������C�g�ѓd�b�̑��݂Ƃ����ɐE��ɏo�đΉ����Ă���邵������҂̃X�^�b�t�Ɍb�܂�Ă��邨�����ŁC�Ȃ�Ƃ����邱�Ƃ��ł��܂����B���ӊ��ӁI�ł��C���킵���x�ɂł����B
�@����́C�O���Ő��܂�ĂU�܂ʼnƒ�����܂߂ĉp����ň���āw�A���x���ꂽ���̂��b�����Ă��������@�����܂����B���{�ꂪ�܂������ł��Ȃ��ŋA�������U�̎q�ǂ������ʂ����u�ٕ����̌��v�Ɓu�ِ��l�̌��v�ł��B�������Љ��C�ώ����̌��z�Ɏx�z���ꂽ���{�́i�q�ǂ��j�Љ�Ɂu�߂��āH�v�݂āC���{�ꂪ�ł��Ȃ��Ȣf���l�q���炩�炩���钆�ŁC�F�B���~�����Ċ撣�����Ƃ����b�ɁC�����炵���������܂����B
�@����Ȏv�����������ŁC�u���݂̌ċz�v�Ƃ������{�l���m�̊W�́C�{���ɑ���̂��Ƃ𗝉����Ă���̂��^�₾�Ɩ₢�����܂��B����̂��Ƃ�������Ȃ��ē��R�Ƃ����Љ�ł́C����ɑ���̂��Ƃ����t�Ƃ��Ă����ˁC��������ꂽ��ʼn�b���i��ł����̂ɑ��āC���{�̎Љ�ł͎����̂��Ƃ����������Ȃ�����������������Ȃ��Ƃ����̌������܂��B�������ٖM�l�ł��邱�Ƃ�������@��i�قƂ�ǁj�Ȃ����{�̎Љ�ŁC�����̗����Ă��鑫�ꂪ�Ⴄ�Ƃ������o���������q�ǂ����C���̎v���ɐ܂荇�������悤�Ɠw�͂��C���{�̎Љ�̒��Ɏ����̗����ʒu�����o�����Ƃ��ė������̂�̌������������܂����B
�@���̈Ⴂ�����ꑸ�d���邱�Ƃ���X�^�[�g����Љ�ƁC�Q��Љ���ێ����邽�߂Ɍ`���������{�Љ�B���̓��{�Љ�̌`�����u�����v���O��Ă��܂��āC�������u�c�v������Ă��Ȃ��܂܂�������ǂ��Ȃ��Ă����̂��Ƃ����Ƃ���܂ŁC�b�͍L����܂����B
�@�َ��ȑ��݂�������{�Љ�C�ٕ�����w�i�Ƃ���l�X�̋����̌��̂قƂ�ǂȂ����{�Љ�C�C�O����̐l�ނ�����邱�Ƃɂ��Ẳۑ�ȂǁC�����Ԃ��̂��Ƃ��l����������@��ł����B
�Q�O�O�W�N�X���U��
�@�傫�Ȍ��Ď������������Еt�����Ǝv������C���̌��ɉB��Ă������Ď������\�ɏo�Ă����肷��ȂǁC�Ȃ��Ȃ���������Ƃ�����ɂ͂����܂���B
�@�Ƃ͂����C�傫�Ȍ��Ă̐����͖ڏ������������̂ŁC�U�߂ɓ]���悤�Ƃ��Ă���Ƃ���ł��B
�@�Ƃ������ƂŁC���̑O�ɓ����ƘA�x�ɂ��āC�������ցB���~�����ɎR�����ɍs�����̂ŁC�����n���߂���̑�Q�e�ł��B�l�I�Ɍ��C�u�t���������߂��Ă��邽�߂ɁC�x�ɂ̎擾�����ł̓g�b�v�N���X�ł����C�܂��C�����ȋx�ɂ��K�v�Ƃ������ƂŁB
�@���Â��C�E��̓����ɏ����Ă��������Ă���Ɗ����܂��B�i�ے����C�ŗ��炪�����H�j
�@�����ɓ����ĂR�N�ڂ̏��a�T�R�N�i������R�O�N�O�ł��I�j�ɁC�����������߂悤�Ǝv���āC�R�o��̂��߂ɂV�A�x�����o�����̂��C�����ȈӖ��œ]�@�������Ǝv���܂��B���̌�C��i��d���Ɍb�܂�Ďd�������߂�̂��~�߂����Ƃ��ǂ��������ǂ����͉��Ƃ������܂��C�T�N�ڂ���͉Ƒ��ł̐V�������������ł̂V���̃L�����v�����̂��߂ɂP�O�A�x����葱�������Ƃ́C�������Ƃ��Ă̐����Ɉ��̃����n���ݏo�����悤�Ɏv���܂��B
�@���L���Γ͂��̂ɁC�F�X�Ȏv�����݂�u�펯�v�ɔ����āC���L���Ȃ����Ƃ͐���������悤�Ɏv���܂��B�����ɁC��������L�ׂ����̂ɁC���s�����Ēp���������v�������邱�Ƃ��C���l�ɁC�������������Ƃ����̂����̑̌��ł��B
�@�ł��C�����Ȃ�C���L���Ȃ���C�߂����Ă��������Ƃ����̂��C���̑f���ȐS���ł��B
�Q�O�O�W�N�W���R�O��
�@���̂U�����قǁC�����ƋC������ɂȂ��Ă����������n�r���e�[�V��������(�S��)�������Q���Ԃ̓������I�����܂����B
�@���n�r���e�[�V�����̖�O���ł��鎄���C�T�̕��ȉ�̂����̈�́u�g�D�A�g�ƃR�[�f�B�l�[�g�v�d�ɂ������Ă��܂����̂́C�o����̎��̂̂悤�Ȃ��̂ł����B��w�Ζ�����ɁC��Q�̂�����̍�Ə��̎x���������˗����Ă���ꂽ���̂��Љ�ŁC�L�����ۑ�w��萐搶�ɂ�������̂͂ق�̋��R�������̂ł����C���ꎞ�Ԃقǂ̎G�k���I��������ɂ́C�u���ȉ�̃R�[�f�B�l�[�^�[��낵���ˁB�v�Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��Ă��܂����B
�@����̂悤�ɁC�{���ɖ�O���ł���u���n�r���e�[�V�����v�̃V���|�W�E���𗊂܂�Ă݂āC���߂čD��S�����������邱�Ƃ̑���������܂����B���ꂪ�Ȃ���C����̘b�����������邱�Ƃ͂Ȃ������Ǝv���܂����C�i���ꂾ���y�͂ł�����������܂��j���ꂾ���̂��Ƃ��w�Ԃ��Ƃ��Ȃ������Ǝv���܂��B
�@�F�X�Ȍo���������Ă����������ŁC�V���Ȃ��Ƃ��w�ԋ@��̂��肪�����������Ă��܂��B����ȋ@��Ȃ�Ă��ł�����Ǝv��ꂪ���ł����C�l�̏o��́u�����v�Ɓu���肪�����v�������邪�̂ɁC�M���ł���u�l�̓����v�ɑ��鎩���̚k�o�ւ̐M�������ɂ���̂��Ǝv���܂��B
�@����̃V���|�W�E���ł̎��̐��ʂ̈�́C�u�g�D�A�g�̈Ӌ`�v�̈�́C�l�̔M�̂����g�݂��l�̏���Ȏ�g�݂Ƃ����̂ł͂Ȃ��g�D�̎�g�݂ɂ��邱�Ƃɂ���āC����I�E�p���I�Ȏ�g�݂ɂ��Ă����Ƃ������ƁC�����āC�l���ٓ����Ă��C�g�D�̎�g�݂ɂ��Ă������Ƃɂ���āC�Œ���̒�x���ɂȂ�Ƃ������Ƃł��B
�@�u����̉ۑ��g�D�̉ۑ�ɂ����ĎЉ�̉ۑ�Ɂv�Ƃ����l�����Ƃ��Ȃ�����̂�����悤�Ɋ����܂����B
�Q�O�O�W�N�W���Q�S��
�@��T�ؗj���ɂ́C���쌧�̉ے��⍲���C���C�łS�V�l��ɂS���ԂƂ������C�������Ă��������܂����B���Ԃ��]���Ă��܂��̂ł͂ƐS�z���Ă��܂������C�݂Ȃ���̂��b�����������Ă���Ƃ����Ƃ����ԂɎ��Ԃ������Ă��܂��܂����B�o�����O�ɁC�{�Ƃ̕��̂m�o�s�i�j�s�g�U���j�֘A�Ńh�^�o�^���Ă��܂��܂������C���Ƃ������ɍς�łق��Ƃ��Ă��܂��B
�@���T���́C�P�T�Ԍ�ɔ������������n�r���e�[�V�����������̏����ɖv�����Ă��܂����B�_�{�n�[�I�ɂ��ꂱ������Ă��܂����Ƃ̂��낢��ƌ��߂͂���܂����C�����ă����b�g�̕����l����C�o����O��̂Ȃ��s�����̒��Ɏ�����u�����Ƃ��Ǝv���܂��B�u���Ƃ��Ȃ�v�Ƃ����ۏ̂Ȃ��s���ȂƂ���Ɏ�����u�����炱���C�ꐶ�����ɂ��Ȃ��̂��Ǝv���܂����C�����ɂ��Ȃ��̂��Ǝv���܂��B
�@�y�j���ɂ́C���̍L����w�Ζ�����ɁC�}�c�_���c�Ƃ̃^�C�A�b�v���Ƃ́u�Ȋw�킭�킭�v���W�F�N�g�v�̑����Ƃ��āC�����Ă��̒��S���Ƃł���Ȋw�m�i���Z���Ώہj�ƃW���j�A�Ȋw�m�i���w���Ώہj�̏m���Ƃ��āC�{���ɂ����b�ɂȂ����L����w�̑吙�搶�ɂ�����܂����B�S���ԘA���Œ�����[���܂ł��ꂼ�ꒆ������ɁC�^���ɋ����Ă��������Ă������i�����������v���o����܂��B���ɁC���w���Ώۂ̃W���j�A�Ȋw�m�ł́C�����̍��h���ɁC��x���܂Œ��w����Ɏԍ��ɂȂ��āC�M������Ă���ꂽ�吙�搶�̎p�ɂ́C���������������̂�����܂����B�{���̖{���̂��������C�u�n���v�ł��F�m���ĕ]�����ĉ���������Â��肪����Ɗ����Ă��܂��B���ꂪ�C�u��s�v��ɏW���̂Ђ��݂𐳂��āC�n���̉\���������o���Ă��������Ɗ����Ă��܂��B
�@�吙�搶�́C���N�U���ɂm�`�r�`���ł��グ���K���}���V�̉q���f�k�`�r�s�����{�����o�[�̑�\�҂�����Ă����܂��B�m�`�r�`�̃z�[���y�[�W�ł��f�k�`�r�s�̃����o�[�Ƃ��ďЉ��Ă��܂��B
�@�n���ł����̂悤�Ȋ������ł���Ƃ������Ƃ��C�����ƃA�s�[�����Ă����������̂��Ƌ��������Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�W���P�V��
�@�W���Ɏc���Ă��邠�ƂR��̌��C�u�t��V���|�W�E���R�[�f�B�l�[�^�[�̔z�t�������e�̎��O���t���ς܂��āC�ꑧ�����̂��悢���ƂɁC�A�ꍇ���F�s�Ő�����C�݂̃h���C�u���Ă�U�R����֍s���Ă��܂����B�h�͂Q���O�ɒT�����̂ł����C���̎��_�ł��~����̓y�j���ɏh���\�ȏh���ȒP�Ɍ����ł���Ƃ́C�C���^�[�l�b�g�̈З͂��������Ƃ���ł��B�i�P�P�N�O�ɃX�^�[�g�����S���ŏ��߂ăC���^�[�l�b�g�𗘗p�����L�����~�}��Ï��l�b�g���[�N���C�y���ɐf�Ă��炦���Ë@�ւ�f�ÉȂƒn��Ō����ł���悤�ɂ������Ƃ������_��������܂������C���ꂪ���ʂɂȂ�������������܂����B�j
�@�U�R����͏��߂Ă������̂ł����C�R�Ԃ̂ЂȂт�����n�ŁC�O���i�����̓��j�𒆐S�Ƃ������{�̉���n�̌��_�̕��������Ă���C�h���璬�̓��܂ŗ��ߊ|���ʼn���X���Ԃ�Ԃ�����Ă����̂��Ȃ��Ȃ��̕���ł����B���悭�C���������h���q�������Ă������̂ɂƂ��������ł����B
�@�C���^�[�l�b�g�́u���A���^�C���ł̏�M�@�\�v���C�n��̐����c���ɂ����Ɛ������Ȃ����̂��Ɗ���������ł��B
�@���ł́C�u���q�݂��U�L�O�فv�ցB��O�͂��ׂČR����`�̎��ゾ�����Ɛ�̂ĂĂ��܂������ł����C���ꂼ��̐l�X�����ꂼ��̎v���������Đ����Ă������Ƃ������܂��B�������C�Љ�̂�������Ȃǂ̒��ʼn����Ԃ���Ă��܂����l�X�͏��Ȃ��Ȃ��C�����ĎЉ�S�̂Ƃ��āC�R����`�̖\�����~�߂��Ȃ��������Ƃ��C���̐���ɂ��`���Ă����K�v�������܂��B
�@�A�H�̍����́C�������H�����ߖ�̂��߂ɂ����ƈ�ʓ��ŁC���ɒ����R�n�̋����ߓ��̎R�z���͌������C�Ȃ�Ƃ�����ƉƂ܂ł��ǂ蒅�����Ƃ���ł��B
�Q�O�O�W�N�W���P�O��
�@��T���E�̂Q���ԁC���m���̐E�����C�łQ�T�O�l�ΏۂɂQ���ԂƂ����̂��Q���A���ł��C�V�C�W���Ɉ������P�O�{�̂����V�{�܂ōς�ŁC�ꑧ���Ă��܂��B���̂P�����قǂ́C�����ƍu�t�����Ŏ��]�ԑ��Ə�Ԃ������悤�ȋC�����܂��B�S���ȗ������ƖZ�E����Ă����{�Ƃ̕����Z���Ղ���ŁC�E��݂̂�Ȃɏ����Ă��������Ă̂��Ƃł����B�Ƃ͂����C�܂��������n�r���e�[�V�����������Ȃǂ�����܂��B���ɁC�V���|�W�E���̃R�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ����̂́C�����̓s�������ł͂����Ȃ��̂ŁC�����ɓ��������܂����C�����ɁC����ł������H������Ă������X�̂��b��a���Ƃ����y���݂�����܂��B���҂ƕs���Ƃ������Ƃ���ł��B������ɂ��Ă��C���̂悤�Ȗڂ̑O�̂��Ƃ���l���ĉ߂����Ă��Ă������̂��ǂ����C�Y��ł��܂��܂��B
�@����́C�F�l�̑D�Œނ�ɏo�āC�^�R���R�o�C�ނ�܂����B���˂̗[�i�Ɂi�ʃr�[���t���Łj�����Ă��܂����B�s��ł͂Ȃ�����Ȋ��ŕ�炵�C��肪���̂���d���Ɍb�܂�邱�Ƃ��K�����Ǝv���܂��B
�@���É��ł́C���Ԃ𗘗p���āC�g���^���Y�ƋZ�p�L�O�����������ۋ�`�����w���Ă��܂����B�g���^�̗͂�������ƂƂ��ɁC�����ȊO�ł��̂悤�Ȋ��͂��������邱�ƂɌ��C�t�����܂����B
�@�n��ɍ��������O���[�o�����Ɗ��͂��߂����Ă����������̂ł��B
�Q�O�O�W�N�W���R��
�@��T�C��ւ������Q�̍u�t���������H�I���C���T���́C�W�����́u�������n�r���e�[�V�����������in�L���v�̏����ƁC�P�O�����ɗ��܂�Ă���^�J���r�㍑�̐��{�E������̌��C���������Ă��܂����B�i���̍��̌���ɖ|�邽�߂ɁC�W���P�T���I�܂łɎ������o����悤�Ɍ����āj
�@��u�҂͍s�����Z���ɃT�[�r�X������Ƃ����T�O�������ł��Ȃ��̂ŁC�u�Ȃ��s�����Z���ɑ��ăT�[�r�X����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��v�Ƃ�����{�I�ȍl�������K�������ė~�����C�Ƃ̃��N�G�X�g�ł��B�l���Ă݂�ƁC������������̂́C���\������̂�����܂��B
�@�����ɑR���Ďs�������̎��R�ƌ�������������Ă��������j�̂���Љ�ł͂Ȃ��C�܂��C�������{���肫�̎Љ�ł́C�����̊T�O��C�J��n�ł̎��q�E�����̂��߂Ɍx�@�C���h�C��ÁC����Ȃǂɋ����Ŏ��g���_�͗������ɂ�����������܂���B�u�V�т̃y�[�W�v�̃^�X�}�j�A�̎ʐ^�W�Ɍf�ڂ��Ă�����h�Ԃ́C�����ȑ��ʼn߂������N���X�}�X�ɁC���̏��h�����Ԃɏ��h�c������荞��ŃN���X�}�X�\���O��炵�Ȃ���ҁX������Ȃ��爹�𓊂��Ĕz���Ă�����i�ł��B
�@���{���Ɍ����C�u���h�Ԃ�����Ȃ��ƂɎg���Ƃ́I�v�ƂȂ邩������܂��C���Ƃ��Ǝ����������������o�������Ď��q�̂��߂ɗp�ӂ������h�c�Ə��h�Ԃ��Ǝv���C���R�ɒ��߂��܂��B�u�����v�̌��_�������悤�ȋC�����܂����B���{���C�^�����{�E�������Ȃ���������܂���B
�@���ƁC�P��̃~�j�h�b�N���܂����B�̏d���s�[�N����Tkg�قǗ��Ƃ��Ă����̂ŁC�Ђ����Ɏ��M�������ėՂ̂ł����C�A���R�[���̈��݉߂��H�œ������b������C�Ƃ��B�撣��˂B
�Q�O�O�W�N�V���Q�V��
�@��T���j������C�Q�T�Ԃ̊ԂɂT�{�Ƃ������C�u�t���̏W�����ɓ���C�������]�ԑ��Ə�Ԃł��B��Ȃ��牽�����Ă�Ǝv���܂��B�Ƃ͂����C���ꂼ��ɑΏێ҂��e�[�}���Ⴄ���e�Ȃ̂ŁC�ْ���������C�w�Ԃ��Ƃ�����悤�Ɏv���܂��B���������Ă��������ƁC�܂���������Ƃ̂Ȃ��Ώێ҂�e�[�}���Ɓi���M���Ȃ��Ă��j�������Ă��܂��C�ォ���⊾�����Ȃ��珀��������Ƃ����̂͂Ȃ����낤�Ƃ����v���̂ł����C���������Ƃ���Ɏ�����ǂ����ނ��Ƃɂ���āC���߂Čo���̕����L����悤�ɂ��v���āC�J�������Ă��܂��B
�@��������āC�I��D�݂������ɎG���Ȃ��ƂɎ���o���Ă����Ƃ����̂́C�u���Ɓv�ɂ͂ł��Ȃ����Ƃ��Ǝv���܂����C��������ĎG���Ȍo����ς�ŁC���ꂼ��ɂ���Ȃ�Ɉꐶ�����ɏ��������钆�ŁC���낢��ȋC�t�����o�Ă��܂��B������ƁC�����ɂ��݂̂悤�ȋC�����܂����C�l���Ă��d���Ȃ��̂ŁC�Ƃ肠�����́C���]�ԑ��Ƃ𑱂��悤���Ɓc�B
�@�ŋ߁C����̒}�g��w�̑�w�E���Z�~�i�[�ȂǁC��w�E���̖����Ɋւ���b�������Ă��܂��B��w���\������̂́C�����ƐE���ł���C����܂ł͋������S�̈ӎv����E�^�c�X�^�C���ŁC��w�E���͂��̎w�����Ď������s���Ƃ����C���[�W������܂��B�Ƃ��낪�C��w�ƎЉ�̊W���L�����Ă���ƂƂ��ɁC�������`�[���Ŋ��������ʂ������C�Љ��̑g�D�I�Ȏx���̐��ݏo���Ȃ���Α傫�Ȍ����Ɏ��g�߂Ȃ���ʂ������Ă��钆�ŁC�����Ƒ�w�E���Ƃ̐V���ȊW�̖͍����n�܂��Ă��܂��B
�@�Ƃ͂����C�����ς���Ƃ����̂͗e�ՂȂ��Ƃł͂Ȃ��C������n�߂�ׂ��Ȃ̂����ۑ�ł��B���Ƃ��ẮC�Ƃ肠�����́C�ڂ̑O�̎����d���͊m���ɏ������鍂�������\�͂ƂƂ��ɁC�u���̂��߂Ɂv�Ƃ��u�Љ�ɂƂ��Ă̈Ӗ��́v�Ƃ��u���j�̗���̕����̒��ł̒n�ʕt���́v�Ƃ��������_����������͂�C�����\���̕]���\�́C���l�ȉۑ�̑̌n���\�́C�\�z�O�̉ۑ�ւ̑Ή��͂Ȃǂ̊��́C�����đΘb�͂�R�[�f�B�l�[�g�͂Ȃǂ��������āC��͌ʂ̎��H�̒��ŁC���������Ǝ��т�ςݏd�˂Ă����K�v������̂ł͂Ǝv���Ă��܂��B
�@�s���E���ɂ��ʂ���b�̂悤�ȋC�����Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�V���Q�O��
�@���j���̌ߌォ��x�ɂ�����āC���N��������̃R�[�f�B�l�[�^�[�{�����C�̑ł����킹�ɓȖ܂ōs���Ă��܂����B�������N������Ŏ��g��ł������̂ł����C���N�̌��C�̉��ŋc�_�����Ă���ƁC����܂ł̋c�_�Ŕ��������Ă��܂��Ă����_�������������Ă��āC����ŗՏꊴ����c�_�����邱�Ƃ̑�������Â������܂����B
�@�y�j���̖�x���A�L���C�A�x�̐^�̓��j�����Ƃ����̂ɁC�����͏I�������ɂ������āC����̋c�_�̂܂Ƃ߂��쐬������C���T�P�{�C�ė��T�Q�{�C���̎��̏T�ɂ��Q�{�ƈ����Ă��܂��Ă��錤�C�u�t���̏����ɖv���i�Ƃ����قǏW���ł����ɂ��������Ɓj���Ă��܂����B���ꂼ�ꕪ�삪�Ⴄ���̓��e�Ȃ̂ŁC�������Ă��Ă��x���ŗ�ŁC��̎����͉�������Ă���낤�ƁC�����������Ȍ����Ɋׂ��Ă��܂��Ă��܂��B
�@���߂Ẵe�[�}�ɂ��Ă͂ł��邾��������悤�ɂ��Ă���̂Ŏd���Ȃ��̂ł����C����ɂ��Ă������������Y�I�Ȃ����͂Ȃ����̂��Ǝv���Ă����܂��B�A�g�ƃR�[�f�B�l�[�g�Ƃ������ʍ��͂���̂ł����C����ɂ���ď������ׂ����Ƃ͂��ŏ��Պ����Y���Ă��܂��܂��B
�@�Ƃ͂����C�����̐��E�̎d���ł͓����悤�Ȏd���͂قƂ�ǂȂ��C�d�����I�ׂȂ����̂Ȃ̂ŁC�����������H�̒��̃e�[�}��ǂ������Ă���ȏ�d���Ȃ����ƁC�J������I�ɔ[���������Ă�����Ƃ���ł��B
�@���������܂�ς��f���̂��Ȃ����ɂȂ肻���ł��B
�Q�O�O�W�N�V���P�S��
�@�܊p�������ԂɋA����̂ɁC�������������߂����u�t�ҋƂ��R�ς��߂��Ď��|����C�ɂ��Ȃꂸ�C���܂��܂����d����Еt���Ă��܂��B���܂ɂ́C����Ȏ��Ԃ��d���Ȃ����ƊJ�������Ă���Ƃ���ł��B
�@����Ȓ��ŁC��T���j���̃V���|�W�E���̌�̑ł��グ�œ��Ȃ������V�A����̓��{��̊��\�ȗ��w���Ƃ̂������v���o���܂����B�ƂĂ��ǖقȐl���Ȃ̂ŁC�����b���Ă��炨���ƁC�ނ��߂����Ă�����̂Ȃǂɂ��ĕ����Ă܂�����C�ˑR���{��Łu���������������̎u��m����v�ƌ����Ă��܂��܂����B
�@���X�ڂ̑O�̎�����ɒǂ��Ă��鎩����p������������������ł��B
�Q�O�O�W�N�V���P�R��
�@��T�Ηj���̖�́C�}�g��w�̑�w�����Z���^�[��Â���w�}�l�W�����g�Z�~�i�[�Łu��w�E���Ɋ��҂����R�[�f�B�l�[�g���v�Ƃ����e�[�}�łQ���ԂقǍu�t�������Ă��܂����B�Ηj���̖�U��������Q���ԂƂ����ݒ�ɂ�������炸�C��s���̑��l�ȑ�w�����P�O�O�����̑�w�E���̕��X���Q�����ꂽ���Ƃɋ����܂����B���ꂾ���̐l���W�ς�����C���ꂾ���̔M�ӂ����������X�����̐l���K�͂ŏW�܂�̂��ƁC�����̗͂��������Ƃ���ł��B
�@���j���ɂ͍L����w���w���Z���^�[��ẪV���|�W�E���ɌĂ�ł��������b�������Ă����������̂ł����C�n�����C�l�̏W�ρu�ʁv�ɗ��邱�ƂȂ��C���ꌴ�_�̍s���͂ŋْ����̂��鎿�̂����d�������Ă������Ƃ̑�����������Ƃ���ł��B
�@�y�j���ɂ́C�W�����ɕ��ȉ�R�[�f�B�l�[�^�[�𗊂܂�Ă���u�������n�r���e�[�V�����������in�L���v�̎��O�ł����킹�ŁC�����p�l���X�g�Ƃ��Ă��Q�����������C���Ő��_��Q�҂̏A�J�x���m�o�n�̗�����������Ă����鐸�_�Ȉ�̐搶�����K�˂��Ă��܂����B���̂m�o�n�̊W�҂̕��X�ɂ���������Ă����������̂ł����C���Ɠ������T�O��ȏ�̕������S�ŁC���̕��X�̖��邢�Ί炪��ۓI�ł����B
�@�܊p�Ȃ�C���̂悤�ȕ��X�Ɠ����Ί�����L���������̂łƊ���������ł��B�}�g��w�̃Z�~�i�[�ŗ͂����Ă��b�������Ƃ̈�́C�u����d���͓��������Ă��Ă͂ł��Ȃ��B�Ȃ��Ȃ�C�i����d���Ɏ��g�ނ��߂ɂ͑����̎��̂�����K�v�ł���j�K�v�ȏ���L�������I�ɏW�܂邽�߂ɂ͖��邭�y�������͋C���K�v������B�v�Ƃ������Ƃł��B�u�]�v�Ȃ��Ƃ�������Ȃ�����ǁC���̏���������Ƌ����Ă����Ă�낤���B�v�Ǝv���Ă����������Ƃ�����Ɗ����Ă��܂��B
�@���ʂ��o���Ȃ��Ă�����Ȃ����Ȃ�C���������Ԃ����̂����ȑԓx������Ƃ��炵�����������Ă��Ă��d���͂ł��邩������܂��C�V�������Ƃ��J�悤�Ƃ������d���̏ꍇ�͂����͂����܂���B����ȑ̌���ςݏd�˂Ă����l�X�̉��l�������Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�V���U��
�@�����C�V���ł��B�S�������C�ɉ߂��Ă��܂��������ł��B����Ȓ��q�œ��X���߂����Ă��܂��Ă����̂��Ǝv���Ȃ�����C���ْ̋������y����ł��܂��B
�@�Ƃ͂����C�ڂ̑O�̉ۑ�̉��������ɖv�����Ă���̂����Y�I�ł͂Ȃ��̂ŁC�{�Ƃ̕��ł͒n��̐����c��헪�̋c�_���J�n���܂����B�v��Ƃ������ɁC�W���n�ł��K���Ƃ����l����������ł��傤���C���̐���ւ̐ӔC���ʂ����K�v�͂���Ǝv���܂��B
�@�ʋΓr���ɃN�����g���哝�̂̉������Ă��܂����C�u���̂��̐��E�́C�����������̐��ォ��a�����Ă�����̂��B�v�Ƃ��u�S�N��̐���ɁC�����������̎��������̂��Ƃ�����l���Ă����̂ł͂Ȃ������̎Љ�̂��Ƃ��^���ɍl���Ă����ƌ���ꂽ�����̂��B�v�Ƃ����t���[�Y�Ɋ������Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�U���Q�X��
�@��T���j���Ɋt�c���肳�ꂽ���N�́u�����̕��j�v�ŁC���߂č��x(����)�l�ނ̎���g�傪�ł��o����܂����B���������Ƃł���C���E������l�ނ��W�߂Ĕ��W�𑱂��Ă���V���K�|�[���ɂR�N���݂����o������C���ۓI�Ȑl�ނ̊��p�̑���͒Ɋ����Ă��܂��B
�@�Ƃ͂����C���̂悤�Șb�́C�L�����ł��l�������݂̂Q�W�X���l���炱���R�O�N�ԂŖ�T�O���l��������Ɛ��v����Ă��邱�ƂȂǂ��w�i�ƂȂ��Ă���Ǝv���C�l�������邩��O���l�������Ƃ����Z���I�ȃ��W�b�N�ɂȂ��Ă��Ȃ����Ƃ������O�͂���܂��B�݂��ɈقȂ�������╶����@���E�����K���������Ȃ�����܂荇���ċ��ʍ��ݏo���Ȃ��狤�����Ă����Ƃ����E�ϋ�����g�݂Ɋ���Ă��Ȃ����{�l�ɁC���̂悤�Ȏ���ꂪ�ł���̂��Ƃ����s��������܂��B������g�債�č�������̂ƁC���ꂸ�ɃW���n�ɂȂ��Ă����̂ƁC�ǂ��炪�K���Ȃ̂��낤���ƍl���Ă��܂��܂��B�������C��R�̑I�������������Ă����w�͂��K�v���Ǝv���܂����B
�@�����Ƃ��C�V�e�F�s�Ńh���C�u�ɍs�������D���̂��钬�Ő������̊O���l�̎p�����钆�ŁC��������Ȗ₢�������������̕����������i��ł���Ƃ͊����܂����B
�Q�O�O�W�N�U���Q�W��
�@�V���ƂW���ŁC���C�u�t�����ौ��O�e�S��ƃV���|�W�E���̃R�[�f�B�l�[�^�[�Ɣ��\�����P�����Ă��܂��Ă���C�{�Ƃ��X�������_�Ȃ̂ɉ����āC�l�I�ɂ��X�������_�ł��B����ȂɈ����Ȃ��Ă��Ǝv���̂ł����C���������Ă����������肪�����ɁC�������Ă��܂��܂��B��ÁC���ہC�s���ƁC����͂܂��܂��Ȃ̂ł����C�ӊO�ɑ��݂Ɋ֘A���Ă���悤�Ɋ����܂��B
�@���ʍ��́C�u�Ȃ��Ŋ������v�ł��傤���B���ꂼ��撣���Ă�������X�ɂ��āC���q���Ƃ��ĂȂ��ł������������Ă����l�����邱�ƂŐV���ȉ\�����L����悤�Ɋ����܂��B�܂����܂肤�܂������ł���i�K�ł͂Ȃ��̂ł����B
�@���̂ق��C���ꊴ�o�╨�������������̑���������Ă��܂��B�����������܂łɂ́C�������̎��s������܂��B�����͂���̂��Ƃ����Ă��܂��Ă�����ȂǁC��R�̖��ʂ����Ă��܂��܂��B�ł��C����Ȗ��ʂ��蓹�ɂ���āC���ꂪ�ł܂��Ă����悤�ȋC�����܂��B��̌����Ȃ����̒��ɍ��C�悭�𓊂�����ł���ƁC�������ʂɓ����o���Ă���Ƃ��������ł��傤���B�����Ɨv�̂悭�C�K�v�ȂƂ���Ƀs���|�C���g�ő����g��ł��܂��Ƃ�������������Ǝv���܂����C�𓊂�����łł����́C���ʂȍL���肪���邾���ɁC�|�C���g���ω��������̑Ή��ɂ�艞�p�͂�����悤�ȋC�����Ă��܂��B�v�̂̈��������ɂ��݂�������܂��B
�@�i���̕������̉����̉��ł́j�������̖��ʂ��蓹���C���ǂ͕������������߂̋ߓ��ł���悤�ɂ������܂��B
�@�܂��C��������Ƃ̂��邱�Ƃ��������Ă���ƁC�ǂ����Ă��ו��ɖڂ������Ă��܂��悤�ȋC�����܂��B���߂Ă̂��Ƃ������������������Ēǂ��l�߂��邱�ƂŁC�{���ɑ�Ȃ��Ƃ͉��Ȃ̂����l������Ȃ��Ȃ饥��C�Ȃ�Č���������Ȃ���C�h�^�o�^�̖������߂����Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�U���Q�R��
�@���̂ЂƂ茾�̍����́u�N�v�������ƂQ�O�O�V�N�ɂȂ��Ă���Ƃ��t������̂���l���炲�w�E���������܂����B���N�̃X�^�[�g�ɐV�����y�[�W����������̒����Y��ł����C���̂悤�ɂ����Ȏ��s�ɋC�t�����ɓ��X�߂����Ă�����낤�ƁC���߂Ď�����������ł��B�����̂��t�����܂Ɋ��ӂł��B
�Q�O�O�W�N�U���Q�P��
�@�����Ȏd�������钆�ŁC�X�̎d���̔\�͂Ƃ��������C�u�g�����i���̂��߂ɁC�����߂����̂��j�v�Ɓu�ӔC���i�����̖��������Ȃ����߂̊撣��j�v�̑���������܂��B
�@����ƁC�u���ꊴ�o�v�ł��傤���B�u�����ȃt�H�[���v�Ȃ�z�[���������łĂ��ł��Ȃ��C���ۂɂ́C�u�o�������v��u���R�v����������܂��B�ł��C�u�����͋��R�̎Y����������Ȃ������̋��R�ݏo�����͓̂w�͂̎Y���ł���v�Ƃ����̂��܂��������Ǝv���܂��B
�@������ɂ��Ă��C�������k���������ł́C�����̕����̓��������߂��Ȃ��Ƃ������Ƃ͌����Ɏ����K�v������Ǝv���܂��B���x�����p���Ă��܂����C���Y�S�[���В��́u���͎��H�I�Ȑl�Ԃ��B�����������s���Ă����������Ȃ����Ƃ�m���Ă���B������C�����������Ɍ������B�ǂ�Ȋ�ƂɂƂ��Ă��C�ł��傫�Ȋ댯�̈�͘��������Ǝv���B�v�i2002.5 ���o�r�W�l�X�C���^�r���[�j�Ƃ������t�ɂ́C�d�݂�����Ɗ����Ă��܂��B
�@����ɕt��������Ƃ���C�u�p���I�ȓw�́v�ł��B�u�Z�������͔|�v�ł͂Ȃ��C�u�~�߂Ȃ����Ɓv�������ւ̗B��̋ߓ����Ɗ����Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�U���P�T��
�@�Ȃ�Ƃ������C�����l�߂ē��X�ڂ̑O�̉ۑ�Ɍ������Ă��閳�_�f�^����Ԃ̓��X�ł��B�Ƃ͂����C����ƍ����́C��r�I������肵�܂����B
�@��T�́C���x�{������̎d���ŁC�n����S���i�w�����E�E����S���i�A�������C��Ȃ���̂Łu�l�Ɛl���Ȃ��Θb�͂ƃR�[�f�B�l�[�g�́v�Ƃ����e�[�}�ł̍u�t�������Q�����ł���Ă��܂����B�n��ƐE��Ƃ����܂������w�i���قȂ�Q���҂����݂��Ă��钆�ł��b������Ƃ����̂͐����s���ŁC���������Ƃ�������Ȃ��珀�����܂������C�Ȃ�Ƃ������ς݂܂����B���Ƃ��Ă��������ɁC�ł��邱�Ƃ���������Ă������Ƃ������Ȃ�悤�ȋC�����܂����C�K���s�K���C���ɈӊO�ȂƂ��납��F��Ȉ˗��������������Ƃ���C�h���Ƌْ����ɂ͎������܂���B
�@�o���̂Ȃ����ƁC�����̕ۏ̂Ȃ����ƂɃ`�������W���Ă��Ȃ��ƁC�s������Y��Ă��܂��悤�ȋC�����܂��B���Y�����Ԃ̃S�[���В����C�u���͎��H�I�Ȑl�Ԃ��B�����������s���Ă����������Ȃ����Ƃ�m���Ă���B������C�����������Ɍ������B�ǂ�Ȋ�ƂɂƂ��Ă��C�ł��傫�Ȋ댯�̈�͘��������Ǝv���B�v�i2002.5 ���o�r�W�l�X�C���^�r���[�j�ƌ����Ă����܂����C���̌��t���ɂ��Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�@���T�͋x�ɂ��Ƃ��āC�����v���W�F�N�g�̑ł����킹�ɓȖ̎������܂ōs���Ă��܂��B�{�Ƃ̕��͂ƂĂ��x�ɂ��Ƃ��悤�ȏł͂Ȃ��̂ł����C�E��̃����o�[���݂�Ȋ撣���Ă���Ă���̂ŁC���ӂ�����������Ă��������Ă܂��B
�@���́C�����̒ʋΎ��Ԃ��قڗB��̓Ǐ����Ԃł��B�i�q�ƃo�X�̎Ԓ��ł̉����Ōv�P���Ԃقǂ������ǂ߂鎞�Ԃł����C������ς���Υ���ŁC���\�ǂ߂���̂ł��B��T�́C����̊��J�搶�ق��́w�l�������Z�p�@����ƎЉ��N�w����x��ǂݏI���܂����B���J�搶�ɂ́C�ȑO�C�L�����l�Â���r�W�����̊W�ł��b�����f�������Ă������������Ƃ�����܂����C���芴�̂��閣�͓I�Ȑ搶�ł����B�Љ�̈�P�ʂƂ��Ắu�l�v�Ǝ����Ƃ����u���ȁi���j�v�Ƃ��āC�Љ�̈���Ƃ��Ắu�l�v��b���`�����Ă����Ƃ����T�O�́C�l�Â���r�W�����ł��c�_���ꂽ�_�Ȃ̂ŋ������o���܂����B
�Q�O�O�W�N�U���V��
�@�{���́C�ߌ�ɎO���s�̒��w���Ƃ̂P�R�N�ڂ̌𗬎��Ƃŗ��L���̃V���K�|�[���̃o���X�e�B�A�q�����w�̐搶���Ƃ̃f�B�X�J�b�V�����C��͂P�V�N�ڂ̌𗬎��Ƃŗ��L���̃V���K�|�[���|���e�N�j�b�N�i��������j�̊w�Ȓ��Ƃ̗[�H���k��ƁC�V���K�|�[���f�B�ł����B�i�����́C�I�[�X�g�����A�̗��L�Ή��ł��B�j
�@���i�p����g���@��قƂ�ǂȂ��̂ŁC��Ȃ����������̂ł����C�V���K�|�[���̕��X�Ƃ̓����b�N�X���Ęb����̂��s�v�c�ł��B�������Љ�Œb����ꂽ�ނ�̃z�X�s�^���e�B�̂ł��傤���B
�@�ǂ����Ȃ�C�ނ�̂悤�ɖ��邭�g�����t�����h���[�ɂ����������̂ł��B
�Q�O�O�W�N�U���P��
�@��T�́C�Ηj���ɏo���œ����֓��A�肵�C���j���ɂ͏T���̌ߌ�T������V���܂ŁI�Ƃ����ݒ�̐��_�ی��W�̌����J���Ȍ��̌�����ɏo�Ȃ��邽�߂ɋx�ɂ��Ƃ��ē����֍s���Ă��܂����B�����珊�v���Ԃ��Z�k���ꂽ�Ƃ����Ă��C�T�Q��̐V���������͔��܂��B
�@���_�ی��̐��Ƃł��Ȃ����������U�N�����̂悤�Ȍ�����ɐ��������Ă��������̂́C���Ƃ��������R�[�f�B�l�[�g�͂̕������Ǝv���܂����C�������L�����x�̒n�楐E��h�Ɛ��i�����C��Łu�l�Ɛl���Ȃ��Θb�͂ƃR�[�f�B�l�[�g�́v�Ƃ����^�C�g���Řb�𗊂܂�C�������}�g��w�̑�w�����Z���^�[��Â���w�}�l�W�����g�Z�~�i�[�Łu��w�E���Ɋ��҂����R�[�f�B�l�[�g�́v�Ƃ����e�[�}�Řb������悤�ɗ��܂��̂����l���Ǝv���̂ł����C���ꂪ�{�Ƃɂ͂Ȃ�Ȃ��Ƃ��낪�C���H�����ĂȂ�ڂ̘b�Ȃ̂œ�����O�Ƃ����Γ�����O�Ȃ̂ł����C�Y�܂����Ƃ���ł��B
�@��T�C�h�������ӂɂ��Ă��������Ă��鑁��c��w�̕����w��w�́u�v���W�F�N�g�v�ł���Ȃɕς��x�i���m�o�ϐV��Ёj�Ƃ����{���o����܂����B���̒��ɂ́C�v���W�F�N�g�R�[�f�B�l�[�g�̋M�d�ȑ̌��k��m�b���l�܂��Ă���̂ł����C���̂悤�Ȏ��H�̘͂b���A�J�f�~�b�N�Ȑ��E�ɂȂ��炸��������̒��Ŋ�������ɂ������Ƃ��ۑ�ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B
�@���������C���̂悤�ȃR�[�f�B�l�[�g�͎͂��H�̒��Ō��ɂ����̂ŁC�u�����v��u����v�ɂ͓���܂Ȃ��Ƃ����l��������Ƃ͎v���̂ł����C�L���b�`�A�b�v�^�̎��ォ��t�����g�����i�[�̎���Ɉڂ钆�ŁC���[�_�[������I�Ɉ�������̂ł͂Ȃ��C�����̐��Ƃ̗͂����܂������o���g�ݍ��킹�Ă������Ƃɂ��Ă̌����⋳�����ɂȂ��Ă���̂ł͂Ȃ����Ɗ����Ă܂��B��N�x�C�Љ�l�w���Ƃ��ďC�m�_���������Ă��钆�ł��낢��Ɛ�s������T���Ă݂��̂ł����C���߂Č����~�ς̏��Ȃ��������܂����B
�@���̂悤�Ȏ��H�Ɋւ��̌��C�m�E�n�E�C�m�b�̒~�ςƓ`�B�̂��߂̎d�g�݂Â�����l���Ă��������Ǝv���Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�T���Q�T��
�@��T�̉Ηj���ɂ́C���m���̐V�C�Ǘ��E���C�̍u�t�Ƃ��ČĂ�ł��������܂����B���N����̍��쌧�ɑ����ĂQ���ڂł����C���Â����オ�ς�����Ɗ����Ă��܂��B���m���ł́C�Q�O�O�l�̕���ΏۂɂQ���ԁC�u�Â��ɍl���Â��Ɍ��Â��ɒ����v�Ƃ����O���[�v���[�N�������Ă�点�Ă��������܂����B���̎�@���Q�O�O�����̐l���ōs���̂͏��߂Ăł������C�l�I�ɂ͗ǂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B�i�Ƃ�悪��̎��Ȗ�����������܂�����B�j
�@���̓y���́C�������̑g�D���y���v�̌𗬉��ɕ��ȉ�̉^�c�ψ��Ƃ��ĎQ�����Ă��܂����B�Q���ɂ킽�镪�ȉ�ł̈ӌ������̒��ł́C�u�X�|�[�c�v����̐���ɂȂ����悤�Ɏv���܂��B
�@���݂̖ڕW�������Ď��g��ł��邤���́C�`�[���̃����o�[�ɋْ��������邵�C�炢���K�ɂ��ς��ēw�͂�ςݏd�˂Ă������Ƃ��ł���B�����āC���̓w�͂̐��ʂƂ��ď��Ă����ɂ́C���������悤�ȒB��������������B�������Ȃ���C�`�[���͂������āC�g�b�v�N���X���߂����Ƃ����ڕW���Ȃ����Ă��܂�����C�ْ������ɂ�ł��܂��݂��̃~�X�ɖڂ��ނ荇���Â����ɂȂ��Ă��܂��B�Ƃ����b����ۓI�ł����B
�@�������߂����ĐV���Ȃ��ƂɎ��g��ł������ł́C�s�����⋰�|��������܂��B����Ȏv���ɑς��Ă������ŁC�v���̒ʂ��������Ԃ��~�����Ȃ�̂��Ǝv���܂��B�t�ɁC�ߋ��̉����́u�ԈႢ�̂Ȃ��v���Ƃ������Ă���ƁC����Ȏv���������Ƃ��Ȃ��C�߂����Ă��܂��܂��B���Y�̃S�[���В��̌��t�ōł��D���Ȃ̂́C�u�����͎��H�I�Ȑl�Ԃ��B�����������s���Ă����������Ȃ��Ƃ������Ƃ�m���Ă���B����������������Ɍ������B�v�Ƃ������̂ł��B�R�Q�N�]�O�Ɍ����ɓ���C�����P�O�N�Ԃ��o����߂����肵�Ȃ��猧���ȊO�̎d�����o�����Ă�������������C�����̈ꕔ�̐l�́u�����������v�Ƃ����̂��C����Ȏv�����������ɉ߂������Ƃ��痈��̂ł͂Ȃ����Ƃ��v���Ă��܂��B
�@��������������Ƃ́C�l���̒��ő傫�ȕ������߂����d���̏�ŁC�ْ����̂���d�������邱�Ƃ́C��l�̐l�ԂƂ��ăv���C�x�[�g�̕����ɂ��C��̂Ƃ��ĂȂ����Ă���Ƃ������Ƃł��B�Ђ�ސS���������āC���������C������}���āC�������Ă��������Ǝv���܂����B
�@��������������������������o�[�ʼn߂����������̐��E�ł́C�ᔻ�E��]�E���Ȏ咣�ł͕����オ���Ă��܂��Ă͂����o����Ă��܂��܂��B������炵�ĕ]�_�ƕ��Ɂu�R�����g�v�������̂ł͂Ȃ��C�������g�������̓����҂Ƃ��ĎQ�����C�v���b�V���[�╗���ɑς��Ă����������ł��O�ɐi��ł������Ƃ�����Ɖ��߂Ċ����܂����B
�Q�O�O�W�N�T���P�W��
�@��T�́C�A�W�A�̉�ŁC�u�C�ɒ��ލ��H�c�o���v�̘b�����������܂����B�@�u�C�ɒ��ލ��v�̌�́u�H�v���~�\�ŁC�}�X�R�~�́C�Z���ԁE�v�������߂�����ςɂ��_��������ނɂ��C�s�u�ɂ����ꂽ�u�c�o�����v����C�b�͎n�܂�܂����B����̎����ɓ���̏ꏊ�����Ɍ�����ے��I�ȉf�����B��C�n���̐l�X�Ɂu���߂���i���҂����j�����v�̂��߂̃C���^�r���[�B�ŋ߁C���k�́u���E�W���v��ނɊւ��āC��������̃}�X�R�~��ނɊւ��āC�܂����������b�����x�������@������������ɁC�l���������܂����B�����āC�n���̐l�X���C���̂悤�ȊC�O���痈���}�X�R�~����C���̂悤�Ȏ�ނ������邱�Ƃɂ��C�u��芵��āv����������̌��t�Ƃ��Č��悤�ɂȂ�ƁE�E�E�B
�@�u�c�o�����v�̖ʐς́C�Q�Uk�u�B�L�����̑��㓇�����S�Rk�u�C�{�����R�Ok�u�ł�����C�{���������������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B�l���́C�X�C�U�O�O�l�I�B�Ȃ��l���P���l�ȉ��ŋ{�����������ȓ������ێЉ�̒��Ő����Ă�����̂��C�Ƃ����^��͏����܂���B�����̎{�݁E�ݔ��E�o��͊O������̉����i���{�����ł������P�V�N�x�ɂ͂P�O���~�m�l����l������P�O���~�I�n�̖����������́j�ł܂��Ȃ��Ă��܂��B�I�[�X�g�����A��j���[�W�[�����h�͂��̐��{�̉��������Ă��܂��B���̂悤�ȁu���v���u���v�ƌĂׂ�̂��C���̂悤�ȍ��𑶗������Ă��錻�݂̍��ێЉ���ǂ��l���邩�ȂǁC�c�_�͂��肻���ł��B
�Q�O�O�W�N�T���P�P��
�@�����́C�ߑO������O���s�̒��w���̃V���K�|�[���𗬂̎�`���ɁB�P�R�N�ڂł����C���ς�炸�V�N�ł��B�V���K�|�[���̒��w���ɁC�O���i���{�j�́C�w�Z������ƒ됶���C�Љ凌����C�n��̓��F�Ȃǂ�������Ă������ڑI�т����Ă��܂����B�ŋ߂́C���w������V�O�Α�܂ŕ��L���N��w�̕���ɂ����Ă��������@��Ɍb�܂�āC���ꂼ��Ɋw�Ԃ��Ƃ�����܂��B
�@�����́C�ė��T�̖^���̊Ǘ��E���C�Ɩ{���ł̒n�楐E��h�Ɛ��i�����C�̏����ɖv�����Ă��܂����B����ȂɎx���ŗ�łǂ��Ȃ�Ƃ��v���܂����C�܂��C�ʔ������Ăł��Ă��邤���͑����悤���Ǝv���Ă��܂��B�ʔ������̂ŁC���ŖZ�����̂͑ς����܂��C���̂悤�ɏ�ɂ������̎d���ɒǂ��܂����Ă���ƁC�ǂꂩ�ōs���l���Ă����̎d���ŋC���]�����ł��āi�X�̌��ʕ]���͕ʂɂ��āj���ꂼ�ꂪ�ς�ł����̂��s�v�c�ł��B�s���s����ᔻ���s�������Ă��Ă��d�����Ȃ��̂ŁC�Ƃ肠�����́C�ڂ̑O�̎d����ǂ������Ă��������ƍl���Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�T���T��
�@�A�x�𗘗p���āC�Ƒ��ō��m�̖q��A�����ɍs���Ă��܂����B�V���K�|�[�����ォ��̗F�l�̈�c���ꎁ�������h�X�P�[�v�i�i�ϐv�j���肪���Ă�����̂ŁC����C�A�����̂T�O���N�L�O���ƂƂ��đ傫�ȉ��C���Ȃ��ꂽ�̂ŁC��������ɍs���܂����B�@�������ꂽ�i�ϐv�����o���S�n�悢��ԂɂT���ԋ߂��Z���Ă��܂����B�@��c����́C�V���K�|�[�����{�Ƀ����h�X�P�[�v�̐��ƂƂ��ď�����āC�P�O�N�Ԃɂ킽���ăV���K�|�[�����{�Ŋ���C�㔼�̂T�N�Ԃ͍����������c�̕����̗v�E�߂Ă����܂����B�@�˔\����҂𐢊E������W�߂Ďd����C����V���K�|�[�����̐����Ⴞ�Ǝv���܂��B���{�Ŋ������Ǝ��E���ē��{�ɋA������c������C���Ɏ���܂ʼn��x���V���K�|�[���ɌĂ�Ŏd����C���Ă���Ƃ����x�ʂ̍L�����V���K�|�[�����Ǝv���܂��B
�@�b�͕ς��܂����C�s���g�D�ɂ��čl����@�����܂����B
�@�n��Â���̋c�_�ɂ����ẮC������̂悤�Ȓn���Ռ^�̑g�D�ƁC�{�����e�B�A�O���[�v�̂悤�Ȍl��P�ʂƂ����ړI���L�^�̑g�D�Ƃ̘A�g���ۑ�ɂȂ�܂��B�ړI���L�^�̑g�D�́C�T�[�N�������̂悤�Ȃ��̂ōD���Ȑl���D���Ȏ������W�܂��Ď������������Ă����܂����C�n���Ռ^�̑g�D�́C�����͂����܂���B�@�����g�́C�s���g�D�ɂ́C���̂����̒n���Ռ^�̑g�D�Ɏ����Ƃ��낪����悤�Ɋ����Ă��܂��B��{�I�ɂ����Ƃ��̒��ɂ����ł�����C�����̎v���悤�ɂȂ�Ȃ����Ƃ������C���Ƃ����Ď��߂Ĕ�яo���đ��̑g�D�Ɉڂ邱�Ƃ��ȒP�ł͂���܂���B�@�ł�����C�����ł��C���ꂼ��̍\�����̎v�����Ȃ���C�l�����������悤�Ɂu�g�D���y�v��E�ϋ����ς��čs�����Ƃ��K�v�ɂȂ�̂��Ǝv���܂��B
�@����́C����̌l���h��ɗ��������������Ŏ���������̂ł͂Ȃ��C��������ƌ݂��̘b�Ɏ����X�������āC�����������Ă�����ӎ������������̂��̂ł͂Ȃ��C���̐l�Ƌ��L�ł�����̂��Ƃ������Ƃ����������C�l�̒��ł̔[���ݏo���~�M�����Ă������Ƃ̂ł���g�D���y�Â��肩�琶�܂����̂��Ɗ����Ă��܂��B�@�s���g�D�̒��ł́C���������ł͑����Ȃ����C������E�����̎p���Ŏ��g�ޕK�v������܂��B�@�g�D�̈����������Ă��C����́C�������������Ƃ��Ă̎g�����ʂ������Ƃ��Ȃ�������ɂ͂Ȃ�܂���B���̂��߁C�������Ƃ��āC�����ڂ��Ȃ��g�D�̒��ŁC�O�����̎d������葱���Ă������߂ɂ́C����Ȏ�g�݂������ł��݂��ɗ����������āC���Ԃ����ݍ�����悤�ȁu�g�D���v�ݏo���K�v������ƍl���Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�S���Q�X��
�@�����́C�O���s�̒��w���̃V���K�|�[���𗬂́C�h�����k�̑I�l��ɍs���Ă��܂����B�ŏ��Ɏ����T�O���قǃV���K�|�[���̊T�v�ƌ𗬂̈Ӌ`�ɂ��Ęb�����āC���̌�C���k�ɍ앶�������Ă��炤�ƂƂ��ɁC�����̖ʐڃ`�[�������艞��ґS�����Ⴄ�ʐڃ`�[�����Q��ʐڂ����Č��߂�Ƃ����C������������̂ł��B
�@���N�łP�R�N�ڂȂ̂ł����C�ŏ��̔N����C�V���K�|�[���ɖK�₷��O�ɂR�����߂����T�y�j���ɂS���Ԓ��x���Ԃ�����ď�������������Ƃ����C�{�C�ł̎��g�݂ł��B�m��N���u������K�����ȂǂŖZ�������w���ɂƂ��ẮC��ςȕ��S�Ȃ̂ł����C�ŋ߂́C�Q�����鉿�l�̂���v���O�������Ƃ����]�������R�~�Ŋg����C�����傫�����鉞��҂�����ƂƂ��ɁC�{���Ɋ��S����悤�Ȏq�ǂ����������債�Ă��܂��B�v���O�����̕]����Ƃ������Ƃ̑���������Ă��܂��B
�@�ŏ�����C�P�Ȃ�C�O���s�ł͂Ȃ��C�o���ɂƂ��ĈӋ`�̂��鎞�Ԃɂ��邽�߂ɏ[���ȏ���������Ƃ������j���C�����ǂł���O���s������������ƈێ����Ă��������Ă��邩��̂��Ƃł��B�������ŁC�V���K�|�[���̒��w�Z����������]���Ă��āC�K��R�N�ڂ���̓z�[���X�e�C������̒�ĂŎn�܂�C�U�N�ڂ���͐��������O����K�₷��悤�ɂȂ�C�o�����̌𗬂ɂȂ��Ă��܂��B
�@���N����́C�V���K�|�[��������w����̂P�N�Ԃ̓��{�ꗯ�w�̊w�����C���N�O���ɗ��邱�ƂɂȂ�܂����̂ŁC����Ȃ锭�W�����҂���܂��B
�@���t�̖�肪����̂�,����̊w�Z�̐搶�Ƃ̘A���͎������p���Ă���C���Ԃ̂Ȃ����ɂ͕��S�ɂȂ�Ȃ����Ƃ��Ȃ��̂ł����C���̂悤�ȃv���O�����͒N�������O���f��������K�v������̂ŁC���̖���肩�Ɣ[�����Ă��܂��B��ߐ��C�������C�v�����̃C�x���g�ł͂Ȃ��C���C�������������ĐM�p�ƌo����~�ς��Ă������Ƃ̑���������Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�S���Q�V��
�@����̓y�j���́C�Ȗ���̂Q�l�ɁC�L����������͋�����a���C�����a���C������G���C�O���s�C�����s�s����C��t�C�ی��t�C��Ã\�[�V�������[�J�[�C�Ћ��C���c�C�s���ȂǑ��l�Ȑl�X���W�܂��ĂS���ԃm���X�g�b�v�Ō���������Ă܂����B
�@�e�[�}�́C�n��ł̕ی��E��ÁE�����̘A�g�Ɋւ��邱�Ƃł������C�w����܂ł̎d������낤�Ƃ���u����̂��߂̎d���v�ƁC�V���Ȗ����������悤�Ƃ���u�����̂��߂̎d���v�����悤�Ƃ���l�����̊ԂŁC�����Ɨ���͂͑傫���قȂ�x�Ƃ��C�w�u���ɗ����Ă���v�u���Ăɂ���Ă���v�u��������Ă���v�Ǝv���āC�C�������O�Ɍ������Ă����悤�Ȏd�|�����̍H�v����x�Ƃ��C���ꂼ����H�o���̖L�x�ȕ���������C�[���x�̍������t���R�������Ă��������܂����B
�@�L�����Ƃ�����̌�����t�������̂ł���P�ʂł̐l�̃l�b�g���[�N���S���g�D�ƂȂ����ĐV���Ȗ͍������Ă����\�����������Ƃ���ł��B
�@�����͑������炻�̋��c�L�^�쐬�ɖv�����C�ߌ�͖{���ɋv���Ԃ�ɍL���s�̒��S�X�ւ̃V���b�s���O�̂����i���^�]�茓���z�j�ɏo�Ă��܂����B���̒��̏���͎Ⴂ���������[�h���Ă���Ƃ������Ƃ�̌������Ă��������������ł����B
�Q�O�O�W�N�S���Q�O��
�@�y�j��������j���̌ߑO���܂ŁC�ǂ����e���V�����̂�����Ȃ��T���ł������C���j���̌ߌ�ɁC�P�T�Ԍ�ɍT����������̎��O�ł����킹�����Ă��烌�|�[�g�쐬�܂ł͔�r�I�W���ł��܂����B�ǂ����ǂ��l�߂��Ȃ��Ƃ��߂ł��B
�@�{�Ƃ̕��ł��ۑ�R�ςł����C�����������ĉ����ł�����̂ł��Ȃ��C�C�͂�������̂̔�r�I�X���[�e���|�ʼn߂��Ă��܂��B�i�ڂ̑O�̂��Ƃɂ͒ǂ���Ă��܂�������j
�@���t�́C�v���Ԃ�̊w�������ɋْ����Ă��āC�{�Ƃ��h�^�o�^�ł����B���̒ʋΎ��ɁC�Ԃƒ��̐����y���߂�]�T���Ȃ�Ƃ����邾���������Ǝv���Ă��܂��B���j���̒��́C�R�ɂ�������܂Ō���܂����B���������̂��C�K���Ȃ̂�������܂���B
�Q�O�O�W�N�S���P�R��
�@����̓y�j���́C���T������F�l�̑D�ŏt�̐��˓��C�ɋ��ނ�ɏo�܂����B�������J�̓��X���C���璭�߂Ȃ���C�n���ɕ�炷�K���ɐ����Ă��܂����B�i�������C�����ς炩��ʃr�[�������т��ш��ݑ����Ă��������ł�����܂����B�j
�@�ŁC�����͂�͂蒩�T������C�����ɂ������āC���N���痊�܂ꂽ�^���̌��C�u�t�̏����ƁC�n��̈�Õی������A�g�̐l�ވ琬�V�X�e���i���ꌤ���C�l�ވ琬�C����x���j�����v���W�F�N�g�̃��|�[�g�쐬���I������Ă��܂����B��N���痊�܂�Ă��鍁�쌧�̐E�����C�������ł����C�����̂��Ƃ������Ƃł��Ă��Ȃ��̂ɁC�����̌��C�̂���`���������Ă��������Ƃ����͉̂����s�v�c�Ȋ��������܂��B
�@��T�́C�{���̐V�K�̗p�E���̌��C�u�t�����܂����B�u���ꂩ��v�Ƃ����������ɂ��b������̂͐ӔC�������܂����C�V�N�ȔM�C�������ċC�����̂悢�ْ����ł����B���낢�남�b�����̂ł����C�u�������́C�ڐ�̗��Q�ł͂Ȃ��C�Љ�̂��߂Ƀt���^�C���œ�����d���v�u����̉ۑ��g�D�̉ۑ�ɁC�����ĎЉ�̉ۑ�Ɂv�u�߂���������Ƃ����Ċ�����ł͂Ȃ����C�߂����Ȃ���Ή����n�܂�Ȃ��v�u�Љ�̕s�𗝂ւ̗ǎ��ȓ{��v�u�����͐V���ɉ��ݏo������ς����̂����l����v�Ƃ������_�����ɗ͂̓������Ƃ���ł��B
�@��̑g�D�ɒ��������Ă���ƁC���̐摗��������茩�Č��ʐU��������肷��P�[�X������܂��B�g�D�̊O�̐l�X�Ɛ��ʂ�����������đΘb���邱�Ƃ����ɂȂ����܂����Ƃ�����悤�ɂ������܂��B�g�D�̒��̏펯�����Ԃ̏펯�Ƃ���Ă���̂́C�ǂ̑g�D�ɂƂ��Ă��傫�Ȗ�肾�Ǝv���܂��B�����̑g�D�̒������ʼn��K�ɉ߂����ă`�������W�����Ȃ��Ȃ�Ɛl�͎��s��Y��Ę����ɂȂ�C�Ɠ��Y�̃S�[���В��������Ă����܂��B�u���S��Y�ꂸ�v�^���Ɏ��g��ł����������̂ł��B
�@���X�ł����C�C�m�_�����u�ʕ����v�ɃA�b�v���܂����B
�Q�O�O�W�N�S���U��
�@�l���ٓ��̃h�^�o�^�̂P�T�Ԃ��߂��܂����B�ŋ߂͎��ߌ�t���Ȃ��C�W�X�ƐV�N�x���n�܂�܂��B
�@�Ƃ͂����C�E������ς��̂ɂ͈Ⴂ�Ȃ��C�V�̐��̗����グ�ْ̋����͂���܂��B�܂��͕����̑�|���Ə��ނ̑啝�팸�C�͗l�ւ����݂�Ȃł����̂����ʂł����B�ۑ肪�傫����Α傫���قǁC�g�̉��̐��������Đg�y�ɂȂ邱�Ƃ̑���������Ă��܂��B
�@�{�Ɗ֘A�̎d���͂��܂�Ƃɂ͎����A��Ȃ��̂ł����C�������ɍ���͂������������C��������Ă܂����B
�@�Ƃ���ŁC�ȑO�C���ۊW�̎d��������Ă������ɁC�C�O������{�̎����̂ɏ��ق���Ă��鍑�ی𗬈��̉p�����[�����O���X�g�ŁC���{�̐l���ٓ��ɂ��Ă̋^��̈ӌ�����������Ă����̂��v���o���܂����B�H���C�Ȃ��{�l�̊�]�ɂ�����炸�l���ٓ�������̂��Ƃ��C���N�ǂ�Ȏd�������邩������Ȃ����Ōv��I�Ɏ����̔\�͂����߂�w�͂͏o���Ȃ��ł͂Ȃ����Ƃ��C�Ђ��Ă͉��Ŗ��\�Ȑl�������N���ے��߂Ă���̂��Ƃ��C�܊p�D�G�œK�C�̉ے������C���Ă��Ȃ��P�N�œ������Ă��܂��̂��Ƃ��B�B�����c�_�ɎQ�����܂������C���̎��ɐ��������̂́C�r���̒��̃����[�S�[�����h�Ƃ������t�ł����B�e�K�Ƀ����[�S�[�����h������Ă���C�ŏ�K�̃����[�S�[�����h����ސE�Ől��������ƈ���̊K����l���[���Ȃ��炻�ꂼ��̊K�̃����[�S�[�����h������Ă���Ƃ����V�X�e���Ȃ̂ŁC����̐l�����̃|�X�g�ɌŒ肷��Ƃ��̃����[�S�[�����h�S�̂��~�܂��Ă��܂��̂��Ƃ��������ł��B
�@�����҂ɂ͓��R�Ǝv���邱�Ƃł��C���O�҂̈ӌ��ɐG��邱�ƂŁC�����Ȕ��������܂����̂ł��B
�@�����́C�V�C���ǂ������̂ŁC�����ƈႤ��������Đ��˂̊C�����Ƀh���C�u�����Ȃ�������ցB���˂̔������C�ݐ��̃h���C�u���y���݂Ȃ���C�Ȃ����̂悤�ȏꏊ�ŕ�炵�Ȃ���C�`�������W���O�Ŏh���I�Ȏd���������ɂ����̂��ƍl���Ă��܂��܂����B������ɏW������������悤�Ɏv���钆�ŁC���������������Ă鐶�����̒��ł�肪���̂���d�����ł�����Â��肪�K�v���Ɗ����܂����B���{�ȊO�ł́C���Ƃ̖{�Ђ���s�ɏW�����Ă����͂��܂�Ȃ��悤�Ɏv����̂ɥ���B
�@���̂��߂ɂ́C�n���ɂ����Ă��C���̂Ȃ��ԈႢ�̂Ȃ������Ƃ��炵���d���ł͂Ȃ��C�V���ȕω��̑n����]������g�D�Â��肪�K�v�Ȃ悤�ɂ��v���܂��B�n��������ێ��̎p���ɗ��܂�C�����Ƃ̍��͂܂��܂��g�債�Ă��܂��܂��B����ɁC�����Ȕ���̐��E�̒��Ŏ��M�����Ղ�Ɍv�Z�͈͓̔��̎d������������̂ł͂Ȃ��C��̌����Ȃ����E�Ŗ͍����钆�ŏ�Ȃ����s�̌J��Ԃ������Ȃ�����O�ɐi�����Ƃ�������C��قǐl�Ԃ炵���Ɗ����܂��B
�@���J�̍����݂Ȃ���̕Ď������V�e�A��̃h���C�u�ŁC���ꂱ��v�������т܂����B
�Q�O�O�W�N�R���R�O��
�@�N�x���Ō�̏T�����C�i�s���̌������|�[�g�쐬�̂��߂ɕ����ɕ��������ĉ߂����Ă��܂��B�����������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃɒǂ�ꑱ���Ă���Ƃ����̂́C����ʋْ����������Ĉ����͂Ȃ��̂ł����C�ڂ̑O�̉ۑ���������邱�Ƃ����œ��X���߂��Ă����Ă���悤�ȋC�����܂��B
�@�Ƃ͂����C��T���㔼�̂R��͈ȑO�̎d���ł���������������̃v���W�F�N�g�̊W�̃����o�[�Ƃ��ꂼ��M�k��Ɉ����Ă���C���̂悤�Ȏ��Ԃ����L�ł��邠�肪���݂������Ă���Ƃ���ł��B�R��Ƃ��ʁX�̃v���W�F�N�g�ŁC������������O�̒��Ԃł��B�ǂ����q�������̂����������ɁC���܂Ōo���Ă��C����̍��̔M�C����݂�����܂��B���������o�����ςݏd�Ȃ�ƁC����Ă͂����Ȃ��Ǝv���悤�ɂȂ�C�܂��܂������̎���i�߂Ă��܂��Ƃ����\�}�ł��B
�@��T���C�v���������Ȃ���������̍u�t�˗�������C���Lj������̂ł����C���܂ł�����Ȓ��q�ň����Ă�����j�]�������ł��B�����ȕ���Ɏ��˂����܂��Ă��������Ă��邱�Ƃ��瑽�l�Ȍo���������Ă����������Ƃ��ł��C���ꂪ�{�Ƃ̕��ɂ��v���X�ɂȂ��Ă���Ƃ͎v���̂ł����C���̂悤�ɗ������Ă��������邩�ǂ����ɂ��Ăͥ���B
�@�ł��܂��C��̉�邤���́C�ڂ��ڂ�����Ă������Ǝv���܂��B
�Q�O�O�W�N�R���Q�R��
�@���Ǝ��i�w�ʎ��^���j���������݂܂����B�ŋߏ����������Ȃ������F�l���炨�j�����Ă��������C�K���C���ł��B
�@�Ƃ͂����C�T�����畗�ׂŁC����͂قڏI���Q����ł��܂����B�s�v�c�Ȃ��̂ŁC�Q����ł�����Ȃ��ɂȂ�ƕ��ׂ������悤�ȋC�����܂��B
�@�����͋x�ɂ�����ēȖ̎������Œ�����V���������v���W�F�N�g�̑ł����킹�ł��̂ŁC�����ߌォ��ړ��ł��B�̒������悤����Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�R���Q�O��
�@�l���ٓ��̔��\������܂����B
�@�L�����ł́C�V�N�قǑO�ɂ���܂ł́u�����ہ��W�v���C�u�����ǁi���������j�������O���[�v�v�ɂ��܂����B���́C���́u���v�v�̎����ɂ͌����𗣂�Ă����̂ł悭������Ȃ��̂ł����C���ꂪ�u�t���b�g���v�Ȃ̂��Ƃ̂��Ƃł����B���ꂪ�C���̂S������u�ǁ������ہ��O���[�v�v�ɂȂ�Ƃ��B�����͋ǒ��ɁC�ǒ��͕����ɥ���B�����C���̑̑��̐��E�ł��B�ŁC���́C�S������u�����ǔ鏑�L���ۉے��v�Ƃ̂��ƁB������Ă���|�X�g�̐E���́u�����敔��撲���NJ��āi������S���j�v����u���U���ǐ����敔������ے��v�ɕς��̂������Ȃ̂ŁC�E���͎�Z���Ȃ�܂��B
�@��T���ɂ́C�����L����w�ی������w���i�O���L�����p�X�j�ŁC���������������Ă���搶�ɗ��܂�āC��w�@�̎��Ƃ̂���`�������Ă��܂����B�����Ȃ���w��ł���l�������C���̔M�ӂɐӔC�������Ȃ���b�����Ă����Ƃ���ł��B
�@���́C�ȑO�C��w�ɂ������ɃR�[�f�B�l�[�g���������C���x�Ƒ�w�Ƃ̌��炻���ƍ߂̋��������̊W�҂̓�����ŒɈ����Ă��܂����B�߂����ׂ����̂����L���āC���l�ȕ���̎҂�������Ƃ�����Ƃ����ʔ����ƈӋ`�ɘb���e�Ƃ���ł��B���ƁC���݂����܂����B
�@�ŁC�����́C�l�w���ŗ��܂ꂽ�V�K�̗p�E�������̍u�t�̏��������Ă��܂����B���������Č����ɓ����Ă��Ă����Ⴂ�l�����ɁC�������������������`�������ƁC�ǂ����l�ߍ��݂����̊�������܂��B�ڐ�̗��Q�ł͂Ȃ��Љ�̂��߂Ƀt���^�C���œ�����d���Ƃ��Ă̍s���̖ʔ����C�߂���������Ƃ����Ċ�����ł͂Ȃ����߂����Ȃ���Ή����n�܂�Ȃ����ƁC�Љ�̕s�𗝂ւ̗ǎ��ȓ{��̑���C�����͐V���ɉ��ݏo������ς����̂����l���Ȃ���d�������Ăق������ƁC�Ȃǂ����`���ł���Ǝv���Ă��܂��B
�@�����͑�w�@�̏C�����ł��B
�Q�O�O�W�N�R���P�U��
�@�����Ƃ������Ă��邤���ɁC���X�͒����ɉ߂��Ă����܂��B
�@��T�́C�A�W�A�̉�ŁC��w�@���x�w���āC�i�h�b�`�̃{�����e�B�A�Ƃ��ĂQ�N�ԃ��L�V�R�ɍs���Ă������̂��b�������f�����܂����B
�@�R�����u�X�����݂̃h�~�j�J���u�����v���Ĉȗ��C���̒n�̂قƂ�ǂ̌��Z�����E�Q�������ƁC���L�V�R�ɂ��Ă��C�X���߂��l�X���E���ꂽ�Ƃ̂��ƁC���̂悤�Ȏ��̋��|�����Ɋ�������Ȃ������ɂ����āC�[���̂��Ղ肪���܂�C����ꂱ���ׂ̌`�������`���R���[�g��p����H�ׂāC���ւ̋��|�ɑ��ċ��������H�̂ł͂Ƃ��B�X�y�C���l�́C���L�V�R�e�n�ɁC�X�y�C���̊���̓s�s���C���H�⌚���܂ł������肻�̂܂܃R�s�[�����s�s������āC�����s�s���������Ƃ����b������܂����B
�@�X�g���[�g�`���h��������������C���̎x���ɂ��������ꂽ�o������C�j�̎q������ΏۂɎЉ�A�x�������Ă���g�D�̊����C���̂悤�Ȑ��������Ă���q�ǂ������������Ă�����́i�W���͂�䖝����S�C�v�����S�j��C���̎q�����ɁC�u���Ă���Ă���l������̂���v�Ƃ������b�Z�[�W��`���邱�Ƃ̈Ӌ`�C�Ȃǂɂ��b���y�т܂����B���̂悤�Ȏx���҂̕�����C�u�D��S�v�ݏo�����߂ɂ͈��̕����H���x�����K�v�Ƃ̎w�E���������Ƃ̂��Ƃ��C�����[�����������܂����B
�@���L�V�R�Љ�́C�悻�҂̎�e�x�̍����C���{�܂łP�Q���ԂȂ̂ŁC����̓��{�l�E���n�l�ɂ́C���{�ɋA���Ď��ɂ����Ƃ����l�͂��܂�Ȃ��C���X���{�ɋA�邱�Ƃ͂����Ă��C���L�V�R�ł̐������y����ł���Ƃ����_����ۓI�ł����B�W�c�ږ��^�ł͂Ȃ��������߂ɁC���n�l���U�݂��ĕ�炵�Ă����Ƃ����̂��C���L�V�R�Љ�ւ̗n�����ݓx�����߂Ă����Ƃ̂��ƁB
�@�s�v�c�Ɏv���̂́C���̂悤�ɊC�O�ɏo�ĐL�т₩�Ɋ�������Ă�����ɂ͏����̕��������悤�ȋC�����邱�Ƃł��B�j���́C������E�ɒ����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ƃ����ӎ�����������ł��傤���B������ɂ��Ă��C���̂悤�ȋM�d�Ȍo�����Љ�Ő�����������K�v���Ɗ����Ă܂��B
�Q�O�O�W�N�R���W��
�@�V���K�|�[������̂P�N�Ԃ̗��w���Ƃ��̎w�������ꂽ�搶�Ƃ̂R�l�ł̑Βk�^�̍u������������܂����B���߂Ă̌o���ŁC��������x�ȒP�Ƀ��n�[�T�������������ł����̂ŐS�z�ł������C���w���Ɛ搶�̂��炵�����b�̂������ŁC�v�����ȏ�ɏ[���������̂ɂȂ�܂����B
�@���ł��C�p�ꌗ�̃V���K�|�[�����痈�����w���́C������͘b���Ă����퐶���ł͊������g�����Ƃ��܂������Ȃ��̂ŁC�����Q�O�O�O���Ƃ������{�̍��Z���x�̍������x����v���������{��\�͎����P���̏����ɂ͑�����J�����悤�ŁC�u�������痈�����̗��w����肢�������x��Ă����̂ŁC�����͂����Q���������Ă���̂�����ƒ��߂����Ȃ����肵������ǁC����܂ł߂����Ă������̂��Ƃ��l���āC�w�������ނȁC����������Ɗ撣��x�Ǝ����Ŏ������܂��āC�Ō�܂ŕK���Ɋ撣��܂����B�v�u�i�w�͂̍b�゠���ĂP���ɍ��i�ł��āj�����ăV���K�|�[���ɋA���čs�������ł��B�v�ȂǂƘb���Ă���C�Ō�ɂ́C�u�w�����Ɍ����C������Ȃ��悤�ɁC�����炵���������������x�Ƃ����̂������̃��b�g�[�Ȃ̂ŁC���ꂩ�������Ȃӂ��Ɋ撣���Ă��������B�v�ƌ����Ă��ꂽ���ɂ́C���̎v�����`����Ă��āC�R�[�f�B�l�[�^�[�����Ă����ɂ�������炸�����l�܂��Ă��܂��܂����B
�@���̂ق��ɂ��C��ۓI�Șb����R����܂����B�V���K�|�[���̍�������𑲋Ƃ��ē����o������C����ɃX�e�b�v�A�b�v���悤�ƁC�V���K�|�[���ŊJ�u���Ă���A�����J�̑�w�Ɏd�����ς�̖�ɒʂ��Ė������Ƃ����Ƃ��C�R�N�ԓ��n��Ƃœ����Ă��Ă��Ȃ�d�����C���Ă�����Ă������ǁC���w���̘b���Đ\������ō��i�����̂ʼn�Ђ����߂ă`�������W�����Ƃ��C�Ȃ�Ƃ�����₩�ŗ��������b�ł����B�i�ޏ������Ƃ����C�V���K�|�[���ŊJ�u���Ă���Ƃ������̑�w�́C�Ȃ�ƁC�I�N���z�}�s����w�Ƃ����A�����J�̒n���s�s�̌�����w�ŁC�V���K�|�[�������łȂ��C�}���[�V�A�C���`�ȂǃA�W�A�e���̂ق��J�i�_��p���ɂ�������h�����ĊJ�u���Ă���̂��Ƃ��B�j
�@����ɁC���{�l�����Ζʂ̐l�ɂȂ��Ȃ��S���J�����Ƃ��Ȃ����Ƃ��Ƃ��C���{�l���m�̊W������������̂ł͂Ȃ����ȂǁC���̒ɂ��w�E������܂����B
�@�V���K�|�[�����痈�Ă������P�N�̂Q�T�̗��w�����C�z�e���̑�z�[���łR�O�O�l�߂����O��O�ɓ��X�Ǝ��R�Ɍ�肩����p�ƁC���̓��e�̂������肵�Ă��邱�ƂɊ��S���C���̓��{�ł��̂悤�Ȏ�҂̎p���ǂꂾ�����邱�Ƃ��ł���̂��낤���ƍl���Ă��܂��܂����B
�@�C�m�_�����ς�ł��ق��Ƃ���܂��Ȃ��C�{�Ƃƕ��Ɨ����ŃX�����̂�����X�������C������Ə��ՋC���ł������C�������������v���ɂ����Ă��������܂����B
�Q�O�O�W�N�R���Q��
�@�����́C�R���U���ɍL���̃��[�K���C�����z�e���ŊJ�Â���L���V���K�|�[������̑Βk�`���̍u����̑ł����킹�ɎO���ɍs���Ă��܂����B�{�N�x����C�L���V���K�|�[������C�O�����ۊO��w�@�C�L���M�p���ɂ̂R�҂̋������ƂƂ��ĊJ�n�����C�P�N�Ԃ̓��{�ꗯ�w�����w�����x�̑�P���Ƃ��č�N�S���ɃV���K�|�[������O���ɗ��āC�����C���{��\�͎����P���ɍ��i�������w���Ƃ��̎w���ɓ�����ꂽ�搶�Ǝ��̂R�l�ł̑Βk�`���̍u����ł��B
�@�V���K�|�[���̍�������𑲋ƌ�C���n��Ƃœ����Ȃ���C�V���K�|�[���ɕ��Z���J���Ă���A�����J�̂���s�s�́u�s����w�v�i�s����w���O���ɋ������J���I�j�v�ɕғ����ĂQ�N�ԕ����đ��Ƃ��C��蒧�������������ƁC���̏��w���v���O�����ɉ��債���V���K�|�[���l�����ł����C�ł����킹�����Ă��邤���ɁC���̈ӗ~�ƃo�C�^���e�B�ɉ��߂Ċ��S���Ă��܂��܂����B�V���K�|�[���ɒ��݂��Ċ������̂́C�����ւ̖��ƈӗ~�������ċ�̓I�ɍs�����C�撣���Ă���l�����́u�w�̐L�сv�ł��B�u���v�ɖ������āC�ڂ̑O�ׁ̍X�������Ƃɂ�������Ĉ�t��t�ʼn߂����Ă���l�ɂ͂Ȃ��C�������������������Ă��܂��B
�@�w���ɓ�����ꂽ�搶�́C�O���s�̒��w���̃V���K�|�[���𗬂łP�Q�N���̂��t�������ł����C���{�̒n���s�s�ŁC�C�O������{�Ɋw�тɗ��Ă���ӗ~�����҂ɑΉ�����Ă��钆�Ŋ������Ă��邱�Ƃ̑傫�����C���O�Ɋ��������Ă��������܂����B
�@�Q�O�N�]�O�ɏ��Ђɏo���������ɁC�u����ێ������ޖ�v�Ƌ������܂������C���̓��{�́C���߂Ă��̌��t���v���N�����K�v������悤�ɂ������܂��B
�@�C�_���ς݁C���������̌������|�[�g���ς݁C�ꑧ���Ă���͂��Ȃ̂ɁC���ς�炸�h�^�o�^���Ă��܂��B�܂��C���ꂪ�K���Ȃ̂��Ǝv���Ă���Ƃ���ł��B
�Q�O�O�W�N�Q���Q�S��
�@�p�[�������s������^��̈ɐ��ւƁC�P���ȗ��R�ōs���Ă��܂����B�C�ɖʂ����g�����n�Ƃ�����ۂŏo�������̂ł����C���������ɗ����������Ԓ��C���ɐ��Q������Ă��܂����B���́C���H�̉��ɂ��铚�u���Ƃ����W�O�O���тقǂ̓��̏h�ɔ��܂����̂ł����C�o���������Ȃ��C�̂�т�Ɨ[�������ނ̂��Q���Ԃقǒ��߂Ă��܂����B���傤�Ǔ��̍Ղ�̓��ł��ׂĂ̋��D�����͏��ŁC�H�n�ɂ͐_�l�ւ̂��������̂��~�������������X���s�������Ƃ����C������Ԃł����B���ꂼ��̒n��̎��������������Ƃ���ł��B
�@�n��n��̃v���C�h���x���镶���̌p���̑���������܂����B�Ƃ͂����C�A�H�C���łQ���Ԃقǎ��Ԃ��߂������ŁC�s��̎��u�ʁv�̗͂������C�������ē˂����炸�C���R�ɒn��̗ǂ����y���߂邽�߂ɂ́C�ǂ���������̂��ƍl���������܂����B
�Q�O�O�W�N�Q���Q�O��
�@���T�C�p�[�����i�R�O�N�j�̏j�������܂����B���Ԃ�C�݂��Ɏ������䖝�������炱�̓����}����ꂽ�̂��Ǝv���Ȃ��祥��B���T���́C�p�[�������s�ł��B���Ȃ݂ɁC�R�O�N�O�́C�}�C�i�X�P�W�x�̑��R�����x�ł̃X�L�[�Ɩԑ��̗��X�ł����B
�Q�O�O�W�N�Q���P�U��
�@�����H�C�_�̔��\��I�����܂����B�C�_�̃e�[�}�́u�Љ�T�[�r�X��C�m�x�[�V�����̂��߂̑g�D�A�g�ƃR�[�f�B�l�[�g�@�\�̌����@�`���N���������ΏۂƂ��ā`�v�ł��B�P�T���Ԃ̔��\�̌�ɂT���Ԃ̂p���`�Ȃ̂ł����C���̎��ɁC�u�R�[�f�B�l�[�^�[���ɂ͕��L���m����o�����K�v���낤����C��N��̐l�������Ă���̂��v�ƕ�����āC�v�킸�u�Љ�T�[�r�X��C�m�x�[�V�����̂��߂̃R�[�f�B�l�[�^�[�Ƃ����̂́C�Љ�̕s�𗝂𐳂��Ă��肽���Љ���߂������߂ɁC�߂��������ɂ��ĊW�҂̎v������ɂ��Ă������߂̓����������d�v�Ȗ����Ȃ̂ł���C�m����o���̗ʂŌ��܂�悤�Ȃ��̂ł͂Ȃ��C���悢�Љ�ւ̎v������Ȃ̂��Ǝv���B�v�ƔM������Ă��܂��܂����B������̎���ɁC�u�Љ�T�[�r�X��C�m�x�[�V�����̌��������Ƃ��āC�w�y�K�ȉ����@�z�����ł͏\���ł͂Ȃ��C�g�D����Ƃ����т����含�̑g�����Ǝ��Ԏ��ł̉����Ɋ�Â����s�Ɖ��P�̌p�����K�v�ł���C����𐄐i����R�[�f�B�l�[�g�@�\���d�v�x�C�ƒ�N���Ă��邪�C���̉����͌����ꂽ�̂��H�v�Ƃ������̂�����C����ɂ��Ă��C�u���̉����S�̂����ł����Ƃ͎v��Ȃ����B�w������������̂Ɂx�ƌ��������ł͑ʖڂȂ̂��I�Ƃ������Ƃ��C���̌�����ǂ�ł������������̑����������Ă���������C�Ӗ�������Ǝv���B�v�Ƃ��������܂����B
�@�܂��C���܂�A�J�f�~�b�N�Ȍ����ł͂Ȃ��������߂Ɏ��₳���搶������J���ꂽ�Ǝv���܂��B���낢�날��܂������C�����g�Ƃ��ẮC����Ă悩�����Ǝv���Ă��܂��B�Ȃɂ��C�v�������Ɓi����܂Ŏ������g�����g��ł����Љ�ۑ�ւ̎�g�݂̃R�[�f�B�l�[�^�[���ɂ��āC��x�܂Ƃ߂Ă݂����Ƃ����v���j�����ۂɍs���Ɉڂ����Ƃ������ƂɁC�����₩�ɖ������Ă��܂��B���ł��ł����C���ۂɂ���Ă݂�����Ȃ��Ƃ�����܂��B��N�x�قǂ͖Z�����Ȃ����낤�Ǝv���Ă����̂��C�g�D�ύX������P�D�T�{���炢�Z�����Ȃ��Ă��܂������ƁC��N�x�܂łT���P�T�����I�Ǝ����������̂����N�x����T�����I�ƂɂȂ������߂ɗ[�H���r�X�P�b�g�Ȃǂōς܂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ������Ɓi�������łSkg�₹�܂����B�����߂�܂������B�j�ȂǂȂǁC�z��O�̂��Ƃ͂����������܂��B�ł��C�����V�������Ƃɓ��ݏo�������Ɋ����邱�Ƃł����C����Ă݂Ȃ��ƕ�����Ȃ����ƁC�o���ł��Ȃ����Ƃ���R�����āC���ꂪ�ʔ����Ɗ����Ă��܂��B����܂ŁC���ȗ��ɏ����Ă����������|�[�g���C�����ȏC�m�_���ƂȂ�Ƃ����Ȗ�������܂��B�ʓ|���ȂƎv�����Ƃ�����܂����C�S�̂Ƃ��ẮC�m��Ȃ��������Ƃ�m��ʔ����̕��������Ă����悤�Ɏv���܂��B�u��肽���Ǝv���Ă��v�Ƃ����̂Ɓu����Ă݂��v�Ƃ����Ԃɂ́C�傫�ȈႢ������Ǝv���܂��B
�@�Ƃ肠�����C���Ƃ��C�_���i�R�����ʂ͂܂��ł����j�ꉞ�I���܂����B�u���Ԃ��ł��邾�낤�v�ƌ�����̂ł����C�ǂ��������̂ŁC�i�{�ƈȊO�Ɂj���������Ȏd������������ł��Ă��܂��B���N�P�N�ԁC�j�n��ł������C���N�x�����܂�ς�肻���ɂ͂���܂���B�ƁC�܂����肵�Ă���悤�ȗ]�T�͂Ȃ��C���N�x�ɂ܂����c���Ă���d�����������ɎR�ς��Ă���C���T������������撣��˂Υ���B
�@�����ɐR����ʂ�����C�C�_���u�ʕ����v�ɃA�b�v�������Ǝv���Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�Q���P�P��
�@�����́C��������ɘU�������ŁC�C�_�̎d�グ�ƏC�_���\��̏����i�{�p�[�������s�̌v��Â���j�B����͒ނ�ŁC�����̓N�A�n�E�X�B��T�́C���j���̌ߌォ��ؗj���ɂ����ċx�ɂ�����ēȖցB�Z�����̂��̂�т肵�Ă���̂�������Ȃ����X�ł��B
�@��T���j���̖�́C�ւ��̂��錧���̎s���猧�ɏo�����Ă���Q�l�ƒɈ��B����ς�C�u�̂�т�v�ł��B
�@�n�����x�[�X�ɁC��肪���̂���d�����ł�����̑���������Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�Q���R��
�@����a�������}���C�l�̌ܓ����肬��̍ɂȂ�܂����B����ȏ���Ώ�Ȃ̂ɁC��X�����݂��݂������Љ�̂��߂ɔM�ӈ����g�݂�����Ă����y������������Ⴂ�܂��̂ŁC�Ȃ�Ƃ�����ȕ��ɂȂ肽�����̂��Ǝv���Ă��܂��B
�@��T�́C�{�Ƃ̕��łQ�N������Ŏ��g��ł����̑傫�Ȏd�����C�i�܂��܂���͒������̂́j�ǂ������̎R����Ȃ�Ƃ��z���邱�Ƃ��ł��C�����₩�ɂق��Ƃ��Ă��܂��B����������āC���j���ɂ́C�o���ōs���������Ŏd�����ς܂�����ɁC�������胊���b�N�X���ē��n�̗F�l�����Ƃ������Ԃ��߂������Ƃ��ł��܂����B
�@�Ƃ͂����C�C�_�̒�o���ߐ�Ɣ��\����ԋ߂ɍT���C�{�Ƃ̕����܂��܂����낢��Ƃ���C�C�������܂���B����Ȓ��ł��C���T�͋x�ɂ�����ēȖ܂ŐV���������v���W�F�N�g�̑ł����킹�ɁB
�@�����́C�����̘V�e����āC�N�c�̂͂�݂�����p�قɍs���Ă��܂����B�G�����炵�������̂ł����C�V���Ђ̘_����W�ōŗD�G�܂ɂȂ������͂ɍl���������܂����B���a�R�N���܂�Ƃ���������̒��ŁC��Q�������Ȃ��琶���Ă����������ƐS�̗h��B���̌b�܂ꂽ���Ɋ���Â��Ă��܂��āC�S�g�S��������ĕK���ɂȂ��Ď��g�ނ��Ƃ�Y��Ă͂Ȃ�Ȃ��Ɖ��߂Ċ���������ł��B
�@�ƁC�����܂ŏ����Ă��āC���X�̖ڂ̑O�̂��Ƃ��������ĂȂ����ƂɋC�t���܂����B����C���郁�[�����O���X�g�ŁC�u�q�i������j�v���b��ɂȂ�܂����B�́C�����̏������犴�������̃C���[�W�́C�u��Ȑl���Ȃ�������ɁC�����̒��ŐÂ��ɓ��ݍl�����ݍ��܂��鎞���v�Ƃ������̂ł����C����Ȑ�捂Ȏ��ԂƂ������̂ɉ������߂����Ă��܂��B
�Q�O�O�W�N�P���Q�U��
�@�ς��f���̂��Ȃ����X���߂����Ă��܂��B����́C�{�Ƃ̎d���ŏ��]�ɍs���āC���\�X�����̂�������ς܂��C�����͏I�������ɘU���ďC�_�̍�Ƃ����Ă��܂����B�d�����������Ƃ͊���Ă���͂��ł����C�P�O�O�y�[�W�߂����̂��蒼�����Ă����Ƃ����̂́C�����ɃG�l���M�[��v�����Ƃ��Ƃ������ƂɋC�����܂����B�����������Ƃł����Ȃ���C�����Ȃ�ɏ��������̂Ŏ��ł��Ă����Ǝv���܂����C�w�������ɂȂ��Ă����������搶�Ȃǂɂ��낢��Ƃ��w�E�������������ŁC�ۉ��Ȃ������C����Ƃ����Ă��܂��B
�@�����̎v�������ōς܂��Ă��܂��Ȃ����ɐg��u�����Ƃ̑�����ĔF�����Ă��܂��B�Ƃ͂����C���������W���͂��r�����C�ǂ��܂Ŋ����x�����߂�����̂��Ɗ뜜���Ă���Ƃ���ł��B
�Q�O�O�W�N�P���Q�O��
�@���ς�炸�̗��̒��ł��B�{�Ƃ̕����i������O�ł����j���Ƃ����낢��Ƃ���C�P�T�Ԃ��I���Ƃ����Ƃ��������ł��B�ŁC����̓y�j���́C�l�I�Ȋ����̕��Ō����̒��R�Ԓn��ɂ���f�Ï��ɏ�������ւ̃C���^�r���[�ɍs���Ă��܂����B�n���Â𒆐S�Ƃ����A�g�̐��i�̂��߂̐l�ވ琬�⌤�C�C�x���̐��̘b�ł��B��w����������Ă��錻��o���̖L�x�ȕی��t�ƈ�Ã\�[�V�������[�J�[�̐搶�Ƃ̋�����Ƃł��B�n��̎������q���݂��Ɋ����������d�g�݂Â���₻�̂��߂̃R�~���j�P�[�V�����\�͂ȂǂȂlj��ׂU���Ԕ��ɂ킽�萷��オ��܂����B����͌l�I�Ȋ����ł����C���̂悤�Ȓn��̐��Ƃ̕��X�̘b�����������C�ۑ�����ĕ��������l���C�s���̂��߂̃R���Z���T�X�Â�������Ă����Ƃ����̂́C�s���ɓ��������E�̖{���߂����ׂ���肪���̂���d���ł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B�ƒ�̉��͂̕���ȂǁC�n��ŋN�����邱�Ƃ��������������Ƃ��āC�n��̉ۑ���s���g�D�̉ۑ�ɂ��āC������Љ�̉ۑ�ɂ��Ă������Ƃ����߂��Ă���悤�Ɋ����Ă��܂��B
�@���j���́C��w�Ζ�����Ɍg������C�n��Ƃ̋��������v���W�F�N�g�̓�����B��w�̂S�̕���̐搶���ƒn��̍s���g�D�̋��������ŁC�ŏ��͊F�ڕ������̌�����������T���ԂŐh�����������グ�����̂��C�Ȃ�Ƃ����̕]�������������Ƃ��܂ł�������ꂽ���̂ł��B��̌����Ȃ����ŁC�s���Ƃ�����������Ȃ�����C�����Ƃ��Ă̕������Ǝ����̊����ɂ��Ȃ���ْ������ێ����đO�ɐi�߂Ă������Ƃ́C����ȂɊȒP�Șb�ł͂Ȃ��C�ߋ��̌o���̗��ł����Ȃ�����܂��Ă��܂��̂ł͂Ȃ����Ɗ����܂��B
�@�n��Ŏd�������邱�Ƃ̖ʔ����́C���l�ȕ���̊W�҂��C���ӎ������L���Ă����ߒ��ő��̍������`�[�������܂�Ă��āC�݂��̐M���W�̒��ʼn����Ɋ�Â����s������̊��o�������Ȃ���i�߂Ă����邱�Ƃł͂Ȃ����Ɗ����Ă��܂��B
�@���[�́C�s���W�̗F�l�̎d������݂̂��j���̉�B�n��̐l�����ƈꏏ�ɑO�����Ɏd��������ʔ����̘b�ȂǂŐ���オ�������ŁC�l���]���̘b�ɂȂ�C�ׂ����]����ŕ]����������́C�ߋ��P�N�ԂɎ������H�v�����ƂƂ��̌��ʂ������Ă��炤���Ƃ̕����]���L�v�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ƙb�������܂����B�ǂ�ȐV���Ȃ��ƂɎ��g��łǂ�Ȑ��ʂ��o���̂��C���ʂ��o�Ȃ������̂Ȃ炻�ꂩ��ǂ�Ȕ��Ȃ����ǂ�Ȃ��Ƃ��w�̂��C�������Ă��炤�B�����́C�ʂɐV���Ȃ��Ƃւ̎�g�݂łȂ��Ă��C���X�̎d���ɂ��āC�ԈႢ�����炵�C�����ʓI������I�ɐi�߂Ă������߂ɂǂ�ȍH�v�����āC�ǂ�Ȑ��ʂ��o���̂����C���ʂ��o�Ȃ������̂Ȃ炻�ꂩ��ǂ�Ȕ��Ȃ����ǂ�Ȃ��Ƃ��w�̂��C�������Ă��炤�B����ȑO�����̐l���]���������̂ł͂Ȃ����Ƃ����b�ł����B
�Q�O�O�W�N�P���P�S��
�@�܊p�̂R�A�x�ł������C�N�A�n�E�X�Ɉ�x�s���������ŁC�Ђ�����C�m�_���ɖv�����Ă��܂����B���܂ł͗ʂ������グ��̂Ɉꐶ�����ł������C�S�̂�ʂ��ă`�F�b�N���Ă݂�ƁC�܂��Ȃ�Ƃ����_����ŁC�蒼���ɒǂ��Ă��܂����B�Ƃ͂����C�����͓V�C���ǂ������̂Ōߌ�͉Ƃ̊O���̕Еt����͗l�ւ������Ă��āC���ɂł��B
�@�C�_�ł́C�������g���ւ�����n���ÊW�̘A�g�̎��ጤ�������������グ�Ă���̂ł����C������ǂݕԂ��Ă���ƁC���R���ւ̌������Ƃ����L�[���[�h�����߂ĕ�����ł��܂��B�u�����͋��R�̎Y���ł��邪�C���̋��R�ݏo�����͓̂w�͂̎Y���ł���B�v�Ƃ������t���ȑO�v�����āC�C�ɓ����Ďg���Ă��܂��B�V�������Ƃɒ��킷�����قǁC��̌����Ȃ��s���̒��ŁC�K���ɖ͍��𑱂��邱�ƂɂȂ�܂��B���̖͂�������₽���ځC���_�o�Ȍ��t�ɗ������݂Ȃ���C�����~�߂���Ƃ����������g�̂����₫�ɍR���Ȃ���C�������������钆�ŁC���ʓI�ɓ]�@�ƂȂ���R�ɉ��x���������Ă��܂����B
�@�ŋ߁C�i���Ƃ����������j�����Ȃ��Ǝv���̂́C�����ł͐V���Ȃ��Ƃ͉������������Ă��Ȃ��̂ɁC�u�������v������U��Ĕᔻ�Ɣ�]�����邨��l�ł��B���̋��ʍ��́C�u���R���ւ̌������v�Ƃ͑ɂɂ���Ƃ������Ƃł��B�����Ȑl�ɏ������C�����ȋ��R�ɏ������邱�Ƃɂ���āC�l�͌����ɂȂ�̂��Ǝv���܂���(�������g�̂��Ƃ͒I�グ���Ă�����)�C����ȕs������m�炸�ɂ����Ƃ��炵�����������˂���ƁC�j�R�j�R���Ȃ�������S�{�苶���Ă��܂��܂��B
�@��T���j���ɁC�ȑO���疡�̂���l���Ǝv���Ă����^���̊��ے��ƌl�I�Ɉ��ދ@�����C���̎v����V���ɂ��܂����B�ނ́C�V���ɂ����X���グ���鐏���������S�����Ă���̂ł����C�����j�R�j�R���Ă��܂��B������Ώ�ŁC���Č��̂��߂ɉ��x���O���]�V�Ȃ�����Ă��錵�����Ȃ̂ł����C�j�R�j�R���Ȃ���u��ς���`�B�v�ƌ�����p������ƁC�������ꂾ���őS���̐M����u���Ă��܂��܂��B������Ƃɓ��������Ď��g��ł���C���肪�h�����đ�ȏ�����Ă��܂���B����Ȃ��Ƃ������炸�ɁC���������Ėܑ̂��������Ԃ�Řb������l�ɂ́C���֍ہC�߂Â������Ȃ��Ȃ�܂��B���������Ă��Ă��ł���悤�Ȃ��Ƃ������Ă��Ȃ������̂ł͂Ȃ����ƁC���������Ȃ��Ă��܂��܂��B
�@��T�ؗj���ɂ́C�A�W�A�̉�ŁC�p�v�A�j���[�M�j�A�ɂ��̂T�N�Ԃʼn��ׂP�N�����s���C�P��̖K��łQ�`�W�����������ȏW���ŊԎ�����Ȃ��璲���𑱂��Ă��镶���l�ފw��(�̗�)�̂��b�����Ƃ��ł��܂����B�p�v�A�j���[�M�j�A�̂��b�͈�ЂƂ��V�������͓I�������̂ł����C����ȏ�ɁC����ނ̒n�̒��Ɏh����Ăڂ��ڂ��ɂ���Ȃ�����C���炪�߂��������̂��߂�(�Ӓn�ɂȂ���)�撣��Ƃ����^���Ȏp���Ɋ������܂����B����Șb�ɔ�ׂ�C����������������������l�Ȃ�āC�����ǂ��ł�������Ǝv���܂��B
�Q�O�O�W�N�P���U��
�@�����́C������I���C�����ł̌��E�W���Ɋւ��錤����ցB��w�@�̎��Ƃ̏o�Ȋ��Z�Ƃ������Ƃōs���Ă����̂ł����C���낢��ƍl����������Ƃ��낪����܂����B
�@��́C���̓��{�̒��R�Ԓn��܂Ắu�c�Ɂv�̒u����Ă���́C���{���̂��u����Ă���̏k�}�ł͂Ȃ��̂��Ƃ������Ƃł��B���܂ł̗��j�̒��ŁC����ʉ��K�Ȍp�����̒��ŁC�]���҂����ꂸ�ɂ���܂łƓ����������ێ����Ȃ���C�V���ȓW�]���J�����ɋꗶ���Ă�����̂́C���͂���Ȃ�ɉ��K�ł���Ƃ����ł͂Ȃ����Ǝv���܂��B
�@�^�̊�䥂ł̋t�̃`���h�Ⓚ�̓r�Ɍ������Ă���̂�������܂���B���̂悤�Ȏ������C�e��̐��Ƃ̐����ÂɌq�����킹�āC�n��̎���ɍ�������g�݂��C�Â��Ȑ��Ō���Ă����l�����߂��Ă���悤�Ɋ������Ƃ���ł��B
�Q�O�O�W�N�P���R��
�@�N���N�n�̋x�ɂ������ōŌ�B�C�_��{�ƈȊO�̌������|�[�g�C��|���ɉƂ̓��O�̑�Еt���ƁC��������[���܂Ńh�^�o�^�̓��X�ł����B�����͔��������{�Ƃ̎d�������傱���ƁB
�@�N�n�ɁC���̂ЂƂ茾�̐V�����N�ւ̍X�V�����Ă��āC����������o���Ă�������U�N�����Ƌ����܂����B�Q�P���I�̏����t���ő�w�Ɉڂ����N�ɏ����o�����̂ł����C�����̌o�̂͑������̂ł��B
�@��A���ɂ������܂������C����܂ł���Ă��āC���肪�����Ǝv���̂́C�������g�̑I���̒��ŁC���ۂɂ��ꂼ��̑̌������Ă��ꂽ���Ƃ��Ǝv���܂��B��ЂƂ̕]���͕ʂƂ��āC�ǂ��������������̒��Ɏ����Ƃ��Ďc���Ă��܂��B��������ǂ��Ǝv���Ȃ�����C�����̑I��������Ǝv���Ȃ������Ă��ꂽ���Ƃ́C�K���������Ǝv���܂��B����ɂ́C�w������̎R�o��̌o�����傫���Ƃ������Ă��܂��B��������ł��낢�댾���Ă��S�Ŋ���Ă��C���ۂɈ����������Ȃ��ƌ����ĖړI�n�ɂ͒����Ȃ��Ƃ������Ƃ�̂Ŋo�������Ă�������悤�Ɏv���܂��B
�@���N�������Ȃ��Ƃ����肻���ł��B�����ȕ��Ƃ̏o��Ƃ������ɁC�u�����v�̂�����X���߂����Ă����������̂��Ǝv���Ă��܂��B
| �@�Q�O�O�W�N�P���P�� �@�����܂��Ă��߂łƂ��������܂��B �@���N���F�l�ɂƂ��Ă悢�N�ł���܂��悤�ɁB �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i����߂����i�̊C�j |
 |
|---|
| ���{�N�j�̂ЂƂ茾�Q�O�O�V�N | '01 | '02 | '03 | '04 | '15 | '06 | '07 | '08 | '09 | '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | ���N |
|---|
| ���{�N�j�̃g�b�v�y�[�W�� | �Q�l�t���[�Y�W | �ʕ��� | �V�т̃y�[�W | English Page | �L����w�ł̂S�N�R���� |
|---|
Since 13 Feb. ' 05