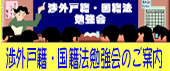|退令訴状|国籍訴状|退令答弁書|国籍答弁書|国籍原告準備書面1|退令原告準備書面2|国籍被告準備書面1|
|原告準備書面3|被告準備書面2|原告準備書面4|原告求釈明書|原告準備書面5|被告準備書面4|被告準備書面5|




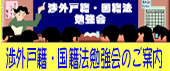
平成5年(行ウ)第5、6号
退去強制命令等取消、国籍存在確認請求事件
被告 準 備 書 面 (4)
任意認知に受理が必要とされる根拠について、以下のとおり主張を追加する。
1 既に被告準備書面3で述べたとおり、民法781条が、「認知は届け出ることによってこれをする」として、右身分行為の成立要件を届出を必要とする要式行為と定めたことから、受理が要件として必要となると解されるものであるが、同条が「戸籍法の定めるところにより」と規定して、右届出の方式や手続等を戸籍法に委ねているところ、この届出に関する1戸籍法の規定の解釈からも、任意認知の成立要件に受理が必要と解されるところである。
2 すなわち、戸籍法は、同法25条から22条にかけて、第4章「届出」とし、うち同法25条から48条にかけ、届出に関する通則規定を、49条以下に各種届出に関する規定を定め、認知については、第3節「認知」として、同法60条から65条にかけて規定を置いている(なお、同法28条以下は、第6章「雑則」とされている。)。
3 これらのうち、同法34条2項が、「市町村長は、特に重要であると認める事項を記載しない届書を受理することはできない」と定めていること、並びに、同法48条1項、28条及び29条から、各種戸籍の届出が戸籍事務管掌者に受理されない場合、届出人は、不受理の証明書を受けられるとともに、家庭裁判所に対し、不受理処分の不服申立てをすることができ、右申立てに対しては、家庭裁判所は戸籍事務管掌者に対し届出の受理を命じる旨の形成的裁判ができる(特別家事審判規則15、17条)ことになるが、このような救済手続を設けたこと自体が、正しく受理処分がなければ届出は効力が生じないことを前提にしたものと言わざるを得ないものであることのほか、同法42条が在外公館で受理した書類の送付について、同法45条が届出を受理した場合の追完について、同法46条が期間経過後の届出の受理について、同法47条が死亡前に郵送した届書の受理にっいて、同法131条が市町村長の届出の不受理についての過料について、戸籍法施行規則20、21条が届出の受理処分したときの手続について、それぞれ受理に関連して個別的な規定を定めていることも合わせ考えると、戸籍法上の届出は受理をその要件と解していることは動かし難いところである。
4 そして、右各規定が、それぞれ戸籍法第4章届出の通則規定及び同法第6章雑則に置かれていることからすると、戸籍法は、届出1般について、要件として受理を必要としているものと解されるから、届出についての各則に当たる任意認知の届出についても、これらの規定が当然に及ぶものと解される。
5 他方、同法60条以下には、「受理」の文言はみられないが、任意認知に係わる同法60、61条も同法29条と同じく届書の記載事項にっいて定めるものであって、任意認知の届出に関する重要事項を定める規定にほかならず、その形式的な内容からすると、受理の際の形式的審査事項の1つを定めるものと解される。そうすると、同法60、61条は、受理が要件として必要とされる根拠になるものであって、これに受理の文言
がないことをもって、届出の成立要件に受理を排斥する積極的な根拠にはならないことは言うまでもないところである。
2 胎児認知の成立
(1)前項で述べたとおり、Aは、遅くとも平成3年9月12日に胎児認知届書及び母の同意書を、胎児認知届をする意思で戸籍管掌者である広島市西区役所職員の宮下康に提出し、宮下も少なくともAが胎児認知届をする意思で区役所に赴いてきたことは認識していた。
そうだとすると本件では、 国籍法2条1号の解釈を云々するまでもなく、単に戸籍事務取扱い上の原則から、9月12日に胎児認知の受付がなされ、同月30日に母の国籍を証する書面が追加提出され、胎児認知の届出が受理されたことにより、受付日である9月12日に遡って胎児認知の効力が発生したと解するべきである。
以下、その理由を述べる。
(2)本件胎児認知において必要な要件について
[1]日本人父が外国人母の懐胎した子を胎児認知するという場合、日本人男性は日本法によって胎児認知することができるが(法例18条2項)、日本法では胎児認知には母の承諾が必要である(民法783条)。また、子の本国法が本人または第3者の承諾または同意を要件としている場合にはこれらの要件も充たす必要がある(法例18条2項。尚、同項における「子の本国法」は胎児認知の場合には「母の本国法」と読み替えて処理する。法例の1部を改正する法律の施行に伴う戸籍事務の取扱いについて通達平成元・10・2民第3900号)。
[2]本件では子の本国法(読み替えにより母の本国法)はフィリピン法であるが、フィリピン法にはそもそも認知に関する規定がないため、本件胎児認知は日本法の要件のみを充たせばよいことになる。しかし、この結論は、母の本国法がフィリピン法であることを前提としているから、母の国籍がフィリピンであることの証明が必要となる。
[3]以上により、本件胎児認知では、日本人父たるAの胎児認知届の他に外国人母のFの承諾及び国籍証明が必要となるのである。
(3)戸籍に於ける受付と受理の関係について
[1]戸籍による届出は、受付・審査・受理・戸籍記載という順序で処理される。
すなわち、戸籍の届け出が市区町村の戸籍係の窓口になされると、戸籍事務担当者はその届出を受領するが、この事実行為たる受領を受付という。戸籍事務担当者は受付後、届出が法定の要件を具備しているかどうかを審査し、具備していれば即日受理をするが、添付書類の提出がない場合や戸籍担当者が判断しかねる問題があった場合など即日受理決定できない場合にはその旨を戸籍発収簿に記載する(戸籍事務取扱準則33条、34条)。そして、受理が決定された場合には、受付帳に記載した後、届出に基づく戸籍の記載が行われる。受理の後、届書に不備があることが発見され、戸籍の記載ができない場合には、届出人に追完届を行わせ、不備を是正した後、戸籍記載が行われる(戸籍法45条)。これに対して、不受理が決定された場合には、その旨を戸籍発収簿に記載した後、届出人に届書が返戻される(以上、甲第50号証8頁)。
[2]そして、後日受理決定がなされれば、その効力は受付の時点にさかのぼる。なぜならば、市町村長の審査する期間の長短によって当事者の身分関係の形成される時点に差異が生ずることは妥当でないばかりか、受理の時点で効力が生ずるとすれば、日時の経過に伴い、当事者の死亡または能力喪失という事態が発生することもあり、ひいては身分関係を形成することの当否の問題にまで拡張し、法律関係が混乱する
からである(加藤冷造ー岡垣学「全訂・戸籍法逐条解説227頁)。
[3]この受付の段階では、届出が受理されるために必要な要件を証明する書類をすべて具備している必要はない。本件胎児認知について言えば、受理のためには、前述のように、母の承諾及び母の国籍証明が必要であるが、受付の段階でこれらが揃っている必要はないのである。
なぜならば、まず、母の承諾は、母の意思人格の尊重と認知の真実性の保証のために必要とされるものであることからすると(注釈民法(22)の1、219頁)、受理の時点までに承諾があれば十分であるし、また、母の国籍証明は、日本法適用の前提として必要とされるものに過ぎないのであるから、やはり受理の時点までにその証明があれば事足りるのである。
そもそも胎児認知は、本来、父が子の出生前に死亡しそうなときなど子の出生後の任意認知が不可能となるおそれがあるような場合になされることを予定された制度である(右同頁)。このような緊急時を想定して設けられた胎児認知について、受付時点で母の承諾や国籍証明などの要件がすべて具備されていなければならないというのであれば胎児認知の制度趣旨を没却するものとなりかねない。
[4]以上により、本件では原告Fの懐胎中に胎児認知の受付が行われたのであれば、原告ダイちゃん出生後の1991年(平成3年)9月30日に受理決定がなされたのであっても胎児認知は成立していることになる。
従って、本件では胎児認知の受付がいつなされたかが問題となるのである。
(4)本件胎児認知の受付日について
[1]前項(1本件胎児認知届の経緯)で述べたとおり、Aは遅くとも平成3年9月12日胎児認知届書及び母親であるFの承諾書を宮下に提出し、これに対応した宮下はAが単なる相談ではなく、胎児認知届をなすために赴いてきたことを十分に認識した上で、Aの持参した右各書類の手交を受け、1旦は受領したが、届出書に添付書類が添付されていないことを理由に届出書をAに返還したというのが事実の経緯であ
り、大筋のところにおいて原・被告間に争いはない。
[2]そこで、問題は、胎児認知届書を宮下がAに返還した行為をいかに評価するかである。
被告らは準備書面5において、「宮下としては、父の本国法である日本民法を準拠法としても、母の承諾書の添付がない上、子の保護要件についての審査をすることができず、また、胎児の母の本国法を準拠法として胎児認知届の適法性を審査しようとしても、母の国籍証明書の添付がないので、右審査をすることができないから、結局、日本民法によるも母の本国法によるも不受理処分をせざるを得なかったものである。そこで、宮下が、Aに対し、添付書類なしでは受理し得ない旨説明したところ、Aが了解して持参した届書を持ち帰ったというのが事実である。したがって、仮にAが持参した届書をいったん窓口に提出したとしても、同人はその届書の提出を任意に取下げないし撤回したものであり、右提出をもって届出があったという余地はない。」と主張する。
しかし、受付の段階で添付書類が備わっている必要がないことは前述のとおりで、西区区長自身、「とりあえず受領し、必要書類の提出(提示)を求め、提出(提示)があれば、審査のうえ受理、不受理の認定をする。」と回答している(甲第41号証)。(なお、宮下は母の同意書も添付していなかった旨証言するが、そのようなことは証拠上もありえないこと、仮に添付していなかったとしても国籍証明書同様後日に提出すれば済むものであることいずれも前述したとおりである。)
したがって、宮下としては戸籍実務上、届書を一旦受領して受付るべきところ、真に重大な誤りを犯してこれを怠ったものである。
宮下自身、「今現在考えた場合には、それは発収簿で取る事案だったかなと思っています。」(同人の証人調書・261項)と述べ、受付をすべき事案だったことを認めている。
かように本件の本質は国民からの届出を適正に受付けるべき職務を国民から負託されている区役所職員がその任務懈怠したことにあるのであって、「届書の提出を任意に取下げまたは撤回した」と届け出た国民の側に責任を押しつける被告らの主張は何をかいわんやである。
Aとしては、胎児認知届として当面為すべきことは為しているのであって、適正な手続を保障する見地から9月12日に受付があったとみることは当然である。
[3]以上のことは、大正9年2月10日の民事第3663号民事局長回答からも言える。
右回答は、当事者より郵送を受けた縁組、離縁、婚姻などの届書に戸籍と符号しない点があり、これを訂正させるために、その届書を養親または夫あてに返送したところ、養子または妻は、その届書が到達する前または到達後に死亡していたが、その後、養親または夫より、誤りを訂正した届書が再び送られてきた場合には、これを受理する、というものである。
この回答は、戸籍と符号しない届書が最初に郵送された時点を受付日とし、届出の効力は、この受付日にさかのぼることを前提としている。なぜなら、その後、当事者の一方が死亡しているのであるから、このように解さない限り、届出は受理できないはずだからである。
そこで、仮に本件においても、訴外Aは、胎児認知届を持参するのではなく、郵送したとする。しかし、母の国籍証明書がないと受理できないから、区役所の職員は、これを添付させるために、届書を返送するか、または添付書類が必要であることだけを通知するであろう。そして、原告ダイちゃんが生まれた後に、母の国籍証明書を添付した届書が再び送られてきた場合、この届書は、胎児認知届として受理されることになる。なぜなら、届出の効力は、最初に郵送された(添付書類のない)届出が到達した時点にさかのぼるからである。
このように届出が郵送された場合と、本件のように、自ら区役所に赴いたばかりに、届出の受領が拒否された場合を比較すると、前者では、受付があり、後者では、受付がないとするのは、極めて不合理である。そこで、この不合理な結果を回避するためには、本件では、宮下が届出を認識して応対した日を、受付日とすべきである(以上、甲第50号証10頁)。
[4]さらに、昭和31年12月25日の民事甲第2878号民事局長回答(甲53号)では、届出が休祭日または退庁後に行われ、宿直職員が戸籍事務の処理能力を有しないため、当該届出を審査することができず、後日に審査した結果、適法な届出として受理された場合にはその受付日は届出があった日、すなわち宿直職員が届書を事実上受け取った日であるとしているが、このように届出が休祭日または退庁後に行われたために機械的に届出書が受領された場合には受付があったとされるのであれば、平日在庁時に戸籍事務の処理能力を有する職員に対し、届出がなされた本件のような場合には、受付があったとされて当然であり、職員の判断ミスで届出書が受領されなかったとして受付がなかったとされるのは不合理極まりないというべきである。
[5]結論
以上のように、本件では遅くとも1991年(平成3年)9月12日には胎児認知の受付がなされ、同年9月30日に受理が決定されたことにより、その効力は同年9月12日にさかのぼり、9月18日に出生した原告ダイちゃんは日本国籍を取得しているのである。
3 国籍法2条1号に関する現行の行政解釈・運用の違憲、違法性
(1)日本人父から生まれた非嫡出子差別
[1]被告らは、国籍法2条1号の「出生の時に父又は母が日本国民であるとき」の解釈につき、<1>「父又は母」とは法律上の父又は母をいい、かつ、<2>右父子又は母子関係は子の出生の時点で既に成立していることが必要で認知の遡及効は国籍法上は認められない、と主張する。
[2]そうすると、日本人と外国人の間に生まれた子において、一人父が日本人の場合の婚外子のみ日本国籍が取得できないということになる。
つまり、法律上の母子関係は、認知を待たずに出生との事実をもって成立するものと解されているから、母が日本国籍の場合、その子は常に「出生の時に母が日本国民であるとき」にあたり、日本国籍を取得する。これに対し、父が日本国籍の場合は、出生の時に父母が婚姻しているか、又は父が子を胎児認知しているかでないと出生の時に法律上の父子関係があるとは言えず、胎児認知のなされていない非嫡出子については、例え生後認知がなされたとしても、準正による国籍取得(国籍法3条)をしない限り、日本国籍の取得ができないということになるのである。これは、嫡出子(準正子を含む)に対する非嫡出子の差別であり、非嫡出子のうちでも胎児認知が行われた子に対する生後認知が行われた子に対する差別である。
[3]他方、日本国籍を取得できない非嫡出子の不利益は、悲しいかな内外人平等の原則が貫徹していない現状においては甚大である。
外国人であれば、選挙権や被選挙権も与えられないし、公務員になることも大幅に制限される。その他の職業及び事業活動の制限、財産権の制限もある。
しかし、もっとも重要な問題は、我が国への入国及び在留の制限である。これらは、現状においては基本的に国の裁量の問題と考えられているため、本件のように子が国外への退去を強制され、子が父と同じ国に居住できないという事態も生じうるのである。
かような父子の分離は、未成年の子にとってその精神的成長を大きく阻害するのが一般であろうし、法律的に見ても、子が父に扶養義務の履行を求めることが極めて困難な状況に陥られ、子の被る不利益は計り知れないものとなる(なお、子どもの権利条約9条において親子の分離を禁止しているが、日本政府は退去強制の場合においては同条に違反するものではない、との解釈宣言を行っていることに留意すべきである)。
(2)非嫡出子差別は、憲法14条1項の「社会的身分」による差別に該当嫡出子か嫡出子でないかは、本人を懐胎した母が、本人の父と法律上の婚姻をしているかどうかによって決定される事柄で、本人の全く関与できないものであるから、子の立場から見れば、まさに出生によって決定される社会的地位又は身分ということができ、非嫡出に対する差別は憲法14条にいう「社会的身分」による差別にあたる。
そうすると、非嫡出子を差別的に取り扱うにつき、合理的な理由がない限りその取扱は違憲となる。
そして、「社会的身分」を理由とする差別的取扱は、前述のように、個人の意思や努力によっては如何ともしがたいものであること、また、国籍を取得できないことにより被る不利益がその子の一生を左右しかねない重大なものであることに鑑みると、合理性の有無は、差別的取扱をする目的の重要性及びその目的と用いられた手段との間の実質的な関連性の存否という点から判断されるべきである(東京高裁平成5年6月23日決定)。
(3)国籍法の変遷
父が日本国籍である場合の非嫡出子のみ日本国籍の取得を認めないとの取扱は、国籍法の変遷にもかかわるので、まずそれを概観する。
[1]旧国籍法
旧国籍法は、1条で「子ハ出生ノ時其父カ日本人ナルトキハ之ヲ日本人トス」と規定し、父系血統主義による生来的国籍取得を原則とするとともに、5条にて「外国人ハ左ノ場合ニ於テ日本ノ国籍ヲ取得ス
1 日本人ノ妻ト為リタルトキ
2 日本人ノ入夫ト為リタル卜キ
3 日本人タル父又ハ母ニ依リテ認知セラレタルトキ
4 日本人ノ養子ト為リタルトキ
5 帰化ヲ為シタルトキ」
と規定し、婚姻・縁組・認知という身分行為による伝来的国籍取得も認めていた。
しかし、この婚姻、認知(生後認知)などによる国籍取得は、身分行為による伝来的な国籍取得(すなわち、認知などの時から国籍を取得する)と制度上されていたため、生来的国籍取得である旧国籍法1条の「出生ノ時其父」というのは法律上の父子関係にある父でなければならないと解されていた(単に生理上の父子関係で足りるとするなら認知による伝来的国籍取得を認める意味はなくなる)。
[2]戦後の改正
しかし、敗戦により新憲法が制定され、家族制度も戸主制度から個人の尊厳を重視したものへと大きく変換したことにともない、1950年(昭和25年)に旧国籍法が大幅に改正されて、身分行為に基づく国籍取得をすべて廃止し、婚姻・認知などによる国籍取得は認められなくなった。
つまり、立法者は、婚姻・認知などで妻や子が日本国籍を取得するというのは、妻は夫の国籍に従う、子は父または母の国籍にしたがうという前近代的な制度そのものであって(家族国籍同一主義)、国籍の取得については妻や子に独立の地位を認めることこそが新憲法の精神に合致すると考えたのである(家族国籍独立主義)。
もっとも、父系血統主義については、旧国籍法をそのまま引き継ぎ、母のみが日本国籍を有するにすぎない時は原則として国籍取得を認めなかった。また、法律上の父子関係が出生の時に必要だとの解釈もそのまま維持された。
[3]父母両系血統主義への改正
しかしその後、この父系血統主義は女性に対する差別だとの議論が起き、日本政府が女子差別撤廃条約を批准するのにともない、1984年(昭和59年)に国籍法が改正され、現行の父母両系血統主義に改められた。
その結果、前述したように母が日本人である場合には、婚外子であっても分娩との事実で出生の時から法律上の母子関係の存在が認められるから、常に国籍取得が認められるようになったが、そのような関係にない、すなわち、認知という身分行為を介在させることなしに、法律上の父子関係の成立が認められない日本人の父から生まれた非嫡出子の場合のみ国籍取得が認められない事態となったのである。
しかし、準正が行われた時まで出生の時法律上の父が存在しなかったとして国籍取得を認めないとするのなら、あまりにも不合理な結論となるので、1984年(昭和59年)の改正に際し、準正嫡出子についてのみ、届出により国籍取得を認めるとの3条の規定が新設された。
(4)合理性の有無
[1]「正常な家族関係」の有無
<1>かように国籍法の変遷の結果、現状においては父が日本人の場合の非嫡出子のみ国籍取得が認められない、ということになったのであるが、その合理性については被告らは次のように主張する。
まず、血統という単なる動物的要素を絶対視せず、親子関係により我が国との真実の結合が生ずる場合に国籍を付与する、というのが現行国籍法の基本的な考え方だとした上で、「親子関係により我が国との結合関係が生ずるのは、子が日本国民の家族に包含されることによって日本社会の構成員となることによるから、日本国民の嫡出子については、当該日本国民が父であるか母であるかを問わず日本国籍を取得させることが適当である。しかし、非嫡出子については、正常でない家族関係における子であって、あらゆる場合に、嫡出子と同様親子関係の実質的結合関係が生じるとは言い難く、通常、母子関係に比し、生理上の父との間で実質上の結合関係すなわち生活の同一性が極めて希薄である。このことから、原則として、日本国民父の非嫡出子は出生により日本国籍を取得せず、日本国民母の非嫡出子は日本国籍を取得するとの現行国籍法2条1号の結果は合理的な差別といえるものである。」
<2>しかし、この理論は明らかにおかしい。
胎児認知をした場合は、生来的な国籍取得が認められるが、この場合は、父子間に国籍を認めるに足る「正常な家族関係」が存するというのであろうか。なぜ胎児認知という制度があるかといえば、父が子の出生前に死亡しそうな時、死亡の危険の多いところに赴く時、父母が内縁関係を解消する時など、子の出生後に認知が不可能となるおそれがある場合などに備えてである。それゆえ、胎児認知がなされた場合の父子関係の実際は、子が父の家族に包合されるどころか父子関係そのものがなくなることさえも予想されるものなのである。
つまり、胎児認知による生来的な国籍を認める以上、国籍取得を認める場合と認めない場合を、「正常な家族関係」の有無ということでは説明しえないのである。
<3>さらに、現実の家庭生活を考えると、婚姻(法律婚)=生活の一体化というように必然的に結びつかない。
たとえば、法律上婚姻している夫とは事実上離婚状態にある下で、子どもが他の男性との事実婚(同棲)の結果誕生した場合、生活の一体化は事実婚の側にある。
また、嫡出子であることの推定は、婚姻解消から300日以内に生まれた子にも及び(民法772条2項)、この子も日本国籍を取得することになるが、父との関係をみれば、父が養育をしていない限り「生活の一体化」はない。
さらに、ライフスタイルが多様化した現在、婚姻届を出さず、事実婚を統ける夫婦も急増している。しかし、このような場合、確実に「生活の一体化」があるのに、子は日本国籍を取得できない事態となる。
そもそも、父母による子の養育は、必ずしも父母双方と同居するということには限定されない。やむなく父母が離婚し、母が子と生活をするが、父が子に経済的・精神的な援助を与え、父母双方の責任において子を養育していくことは、よくあることである。
女性の経済的自立が進んだ今日、女性は家庭から解放され、家族関係も従来の家を中心とした関係では捉えきれなくなっている。このような現代社会において、家族関係を「正常なもの」と「正常でないもの」に区別すること自体、まったくナンセンスなものとしかいいようがなく、非嫡出子の父子関係は、母子関係に比べ、生活の同一性が極めて希薄であることを根拠にすることに、正当性・合理性は全く見いだせないのである。
[2]子の意思の尊重
<1>次に被告らは、1950年(昭和25年)の国籍法の改正に際し、「憲法24条の精神を受けて、国籍自由の原則を採用して、出生後の身分行為に基づく国籍の移動を認めないとした」のであるから、生後認知による国籍取得は認められないとする。
確かに改正の経緯は被告らの主張するとおりであり、子の意思の尊重という目的は正当なものとも思える。
しかし、婚姻や養子縁組と同様に認知があった場合の国籍取得についてまでも旧民法の家制度に由来するもので憲法24条の精神に反するのか否かは大いに疑問である。
すなわち、婚姻や縁組における国籍取得は、日本人と全く血のつながりのない者に、日本人の「家」に入ったということで国籍を付与するものであるのに対し、認知はそもそも日本人と血統関係がある者に認知という法的親子関係の成立を機に国籍を付与しようというものであって、両者は全く異なり、認知による国籍取得は「家制度」と全く無関係だと考えられるのである。
したがって、認知による国籍取得を否定した立法事実自体、合理性がないものと言わざるを得ないのである。
そしてそもそも、嫡出子については子の意思にかかわらず例外なく日本の国籍を取得するシステムとなっている。これは国籍法が血統主義を採用しているが故の必然的な帰結である。
したがって、非嫡出子のみ、子の意思を云々することは全く不合理であり、差別的取扱いを認める目的において重要性はない。
<2>しかも、本件の如く、子が未成年の場合において、その法定代理人である母も日本国籍の取得を希望している場合にまで当然に国籍取得を認めないのは、目的を達成する手段として社会的許容性を欠いているものといわざるを得ない。
[3]国籍の安定性
さらに被告らは、「認知に遡及効を認めて、出生後に父の意思によって国籍の変更が認められるとの解釈を採るならば、出生による国籍の取得は出生時点において確定されるべきであるとする出生時点主義に反する結果となり、妥当ではない。」と主張する。
しかし、1984年(昭和59年)の改正では、準正による国籍取得を認めるに至っており、その他国籍留保届をしなかった者が後に届出を行った場合(国籍法17条)や帰化等、生後に国籍取得が認めれる場合は多々ある。
逆に嫡出子として日本国籍を生来的に取得した者であっても、嫡出否認の訴えなどが確定すると、出生の時に日本人父との法律上の親子関係が成立していなかったとして出生の時点までさかのぼって日本国籍は喪失してしまう。
そうすると、国籍の安定性といっても何も絶対的な要請ではないということである。 認知による生来的国籍取得を認めた場合、仮に第三者の権利を侵害する事態が発生するとしても、民法784条但書の適用または類推適用により第3者の権利を害することはできないと解されるから、これによる不都合が生じることもあり得ないのである。
したがって、国籍の安定性ということも生後認知による国籍取得を一律に否定する根拠とはならず、とりわけ出生後相当期間内になされた認知による国籍取得まで否定するのは、目的と手段との間の相当性を著しく欠くものと言わざるを得ない。
[4]二重国籍の防止
また被告らは、生後認知による国籍取得を認めれば「二重国籍を取得することになり国籍の積極的抵触という極めて不都合な事態を招来する結果となる」という。
しかし、1984年(昭和59年)の国籍法改正により、父母両系統血統主義が採用されたのであって、この場合、一方の親が外国人である場合当然に父母双方の国籍を取得することがあり得ることを前提としている。したがって、父が日本人の場合の非嫡出子のみ二重国籍の防止を云々することはまったく理由とはならない。
なお、二重国籍の取得が問題とするならば、国籍選択制度によって事後的に解消すれば済む話である。
(5)以上のとおり、生後認知をしても国籍取得を認めないとの現行の取扱は、とりわけ出生後相当期間内に認知がなされた場合において、差別的取扱をする目的の重要性及びその目的と用いられた手段との間の実質的な関連性は存せず、憲法14条に反するものと断ぜざるを得ない。
(6)国際条約違反
[1]非嫡出子差別の撤廃
<1>我が国が既に批准した「市民的及び政治的権利に関する国際規約」(国際人権B規約)24条1項および「子どもの権利条約」11条1項は、出生による子の差別を禁じている。
然るに、多々の非嫡出子差別が残存する我が国の現状に対し、国際人権規約委員会は、1993年11月5日日本政府に対し、「委員会は、非嫡出子に関する日本の法律から差別的な規定が除外され、規約の2、24、26条の条項に一致するように改正することを勧告する。規約の2、3と26条に一致するように未だ日本に残る差別的な法律や慣習は廃止されるべきである。日本政府は、このことについて世論に影響を及ぼすように
努力すべきである」との勧告をしている(甲第39号証の114頁)。
したがって、日本政府は、あらゆる形態の差別から非嫡出子が保護されるよう、あらゆる措置を講ずる義務を負っているというべきである。
<2>右勧告も受け、1995年3月1日からは、嫡出子について「長男」「長女」、非嫡出子について「子」と表記されていた住民票もすべて「子」と表記するよう改められたのをはじめ、法定相続分差別の見直し等、立法・行政の対応も非嫡出子差別を撤廃する方向で確実にすすんでいる。
[2]国籍取得の権利
また、子どもの権利条約7条は、子どもは出生の時から国籍を取得する権利を有するものと定める。
この規定の趣旨は、無国籍の防止との点にあるが、国籍は国から恩恵的に与えられるものとの従来の考え方をまったく転換し、子どもが個人として尊重され、生きていくための必要不可欠な人権として国籍取得の権利を位置づけているところに画期的な意義がある。
したがって国が正常な家族関係にある子か否かということを決めつけ、それに基づき国家の構成員としてふさわしいか否かとの判断のもとに、国が子に国籍を与えるという発想は否定されるのである。
そして、同条約がさらに子どもはできる限りその父母によって養育される権利を有すると規定し(7条1項)、子どもがその父母の意志に反してその父母から分離されないことを確保するよう締約国に義務づけている(9条)ことを考えると、その子が生まれ、生活を続けることを希望する国の国籍を取得する権利をも保障したものと考えるべきである。(二宮教授意見書、甲第55号証 36頁)。
[3]以上のとおり、国籍に関する非嫡出子差別は、国際人権B規約24条1項および子どもの権利条約2条1項に、さらに滞在国における国籍取得の権利を認めようとする子どもの権利条約7条1項に反することになる。
(7)諸外国の立法例
認知による国籍取得を認めるのは、我が国と同じく血統主義を採用する諸国の立法の主流である。
たとえば、フランス、イタリア、ベルギーなどの諸国では、一貫して認知による国籍取得を認めてきている。
また、かつては認知だけによる国籍取得を認めず、準正を要求していたドイツにおいても、1993年の国籍法改正によって子が23歳に達するまでの間は認知による国籍取得を認めるに至っている(奥田教授意見書、甲第50号証 43頁、甲第51号証)。
(8)総括
以上のとおり、日本人を父にもつ非嫡出子のみ、例え生後に認知をしても国籍取得を認めないという現行の行政解釈・運用は、憲法14条1項、国際人権B規約24条1項、子どもの権利条約2条1項、同7条1項に違反する違憲、違法なものであるし、また国際的な立法の動向に反するものである。そうだとすれば、国籍法2条2号の解釈としても認知の遡及効を認め、原告ダイちゃんの本件請求を認容すべきである。
仮にそれが困難だとしても、後述するように国籍法2条1号の「出生の時を柔軟に解し、出生後相当期間内に認知届をした本件の場合、原告ダイちゃんに国籍取得を認めるべきである。
4 国籍法2条1号の「出生の時」の解釈
(1)国籍法2条1号の「出生の時」の意義
被告らの主張は、国籍法2条1号の「出生の時」を文字通り分娩の時であることを前提にするものである。しかしながら、右のような解釈を本件のような場合にも貫こうとすると、まさに子の人権を保障しようとした憲法や条約等の趣旨を没却する結果となる。そうであれば、右「出生の時」を戸籍法や国籍法等の他の条項と整合性を保ちつつ、かつ、憲法や条約等が要求する趣旨に適合するように、次に述べるように解釈すべきである。
(2)戸籍法104条の趣旨を導入した解釈
まず、戸籍法104条の趣旨を国籍法3条1号の「出生の時」の解釈に取り入れ、認知届が戸籍法49条の期間内(国内出生は14日以内、国外出生は3か月以内)に行われた場合は、右「出生の時」に認知届があったものと解すべきである。
戸籍法104条1項、2項は、国籍法12条に規定する国籍留保の意思表示は、出生の日から3か月以内に出生届と同時に国籍留保の届出によって行うとしている。戸籍法104条がこのように規定した趣旨は、出生前に国籍留保の届出を行わせて、あくまでも「出生の時」に国籍を確定させることは実際上無理であることから、出生届を行うべき期間(戸籍法49条に規定する期間)内に留保の届出を行えば、日本国籍を確定させることができるとした点にある。つまり、出生により外国の国籍を取得した日本国民で国外で生まれた者が、日本国籍を確定的に取得しようと思えば、国籍留保の届出をしなければならないが、国外で出生したなどの事情を考慮し、出生と同時に右留保の届出をしなくとも、出生届の際に併せて留保の届出をすれば、日本国籍を確定的に取得できるとしたのである。
このように国籍留保届は、これを行わなければ「日本の国籍を失う」という文言で規定されているが、実質上は、国籍留保届を行うことによって、初めて国籍取得が確定されるのであるから、「国籍取得届」の機能を営んでいる。ところで認知届も、通常は、非嫡出父子関係を成立させるだけであるが、日本人父と外国人母から生まれた子にとっては、国籍法2条1号の要件を充たすために必要であり、やはり「国籍取得届」の機能を営んでいる。そうすると、戸籍法104条の趣旨を、国籍法2条1号の「出生の時」という文言の解釈に取り入れることは可能であり、しかも、現に居住している国の国籍を取得しているかどうかは、その子の居住の権利等に重大な影響を及ぼすのであるから、出生後に認知届があった場合にも前記「出生の時」に認知届があったものとみなすことは、まさに子の人権を保障した憲法や国際人権B規約、子どもの人権条約等が要求していることと言わなければならない。
ただ、出生後相当期間経過後の生後認知による国籍取得を認めると国籍の安定を害することになることは否定できない。そこで、戸籍法104条が規定するように、出生届を出す期間、すなわち国内出生の場合は出生の時から14日以内、国外出生の場合は出生の時から3か月以内(戸籍法49条)に認知届が出された場合に、なお国籍法2条1号の「出生の時」に認知届があったものとみなすべきである。また右のように解する
限り、認知届が合理的期間内(14日以内、または3か月以内)に行われなかった場合には、なお国籍法3条の存在意義が残っている。さらに、右解釈は、戸籍実務上もなんら問題を生じない(甲第50号証28頁)。したがって、右のような解釈は、戸籍法や国籍法の他の条項とも充分に整合するのである。
以上から、本件での認知が仮に1991年(平成3年)9月30日であったとしても、出生の日である9月18日から14日以内の認知届であるから、国籍法2条1号の「出生の時」に認知届があり、したがって、その時点で原告ダイちゃんと訴外Aとは非嫡出父子関係が成立していたというべきである。したがって、原告ダイちゃんは日本国籍を取得したというべきである。
(3)本件の具体的事情を考慮した例外的解釈
次に、本件の認知が仮に生後認知であっても、本件の具体的事情を考慮するならば、例外的に国籍法2条1号の要件を充足しいていると解すべきである。
国籍法2条1号の「出生の時」の意義を字義どおりに解するならば、出生の時に非嫡出父子関係が成立していることが国籍取得の絶対要件となる。そして父が出生後に認知した場合、その効力は「出生の時」にさかのぼらないと解されている。したがって出生後の認知で非嫡出父子関係が成立したとしても、 子は日本国籍を取得できないこととなる。つまり、国籍法は、出生による国籍取得は「出生の時」に確定する、という原則を採用していると言われている。しかし、この原則は既に述べた国籍留保の場合にすでに破られている(戸籍法104条1項、2項)。
しかも、天災などの不可抗力によって、期間内に届出ができない場合には、届出ができるようになった時から、14日以内に届け出ればよいとされている(戸籍法104条3項)。
すなわち戸籍法・国籍法は、出生の時にではなく、出生後右期間内に国籍留保の届出を行った時点で国籍を確定させる場合を認めているのである。このような例外を認めた趣旨は、既に述べたとおり、出生と同時に国籍を確定させる手続をとることが実際上無理であるとの配慮に基づく。とするならば、国籍留保の場合だけでなく、認知によって国籍を取得しようとする場合にも右のような配慮がされてしかるべきである。この点で、1995年(平成7年)2月29日の東京高裁判決で示された考え方が参照されるべきである。
この事件では、韓国人母の婚姻中に懐胎した子は、母の夫(日本人)の嫡出子と推定されるため、実父が夫以外の日本人であるにもかかわらず、出生前には、嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えによって、この推定を排除することができず、また実父による胎児認知届も受理されないから、胎児認知による国籍取得が全く不可能な状態であった。子の出生後、親子関係不存在確認の審判が確定し、その後に出生届と実父による認知届が出された。第1審(1994年(平成6年)9月28日東京地裁判決)は、認知に遡及効を認めると、子の国籍は父の認知があるまでは不確定とならざるを得ない、との原則論により、子の国籍取得を認めなかった。
これに対し、東京高裁は、右のような具体的事情のもとでは、原則論を貫くと、本来なら日本国籍を取得し得るはずの子が日本国籍を取得できないこととなって不合理である、嫡出が否定された時に接着した時に新たな出生届と認知届出があった場合に限って、国籍法2条1号の要件を満たすものと解してよい、とした。
そもそも、胎児認知の場合に国籍取得を認め、生後認知の場合に国籍取得を認めないことは、全く恣意的な区別である(甲第52号証・11頁上段3行目以下)。右判決は、「嫡出が否定された時に接着した時(嫡出子であることが確定した裁判によって否定された時から、本来の出生届の期間内)に新たな出生届と認知届出があった場合」に限って国籍取得を認めるのであるから、国籍の安定性を害することはないし、国籍法3条とも矛盾することはない。したがって、右判決を、出生の時に国籍が確定するという原則に対する例外的適用のケースを一般的に示したものとしてとらえるべきである。そして、本件は、まさにその例外的適用の場面にほかならない。
本件においては、訴外Aが、胎児認知によって原告ダイちゃんに日本国籍を取得させようと、何度も役所に足を運んだ。そして、認知届のためには、原告Fの出生証明書の添付が必要と知るに至って、同女の本国に連絡をして、出生証明書の送付を依頼した。しかるに、フィリピンにおける火山の爆発などによって到着が遅れた。訴外A及び原告Fが促しても結局、出生証明書の到着は、原告ダイちゃんの出生後となった。訴外Aは到着後直ちに翻訳し、原告Fの出生証明書を区役所の戸籍事務担当者に提出した。それが1991年(平成3年)9月30日であった。また、既に述べたとおり、訴外Aは、原告ダイちゃんの出生前の9月12日に、胎児認知届の意思を戸籍事務担当者に表明しているのであるから、原告Fの出生証明書がなくても、受付はなされるべきであった。しかるに、右担当者の誤った判断により、受付さえ拒まれたのである。結局、認知は出生後の9月30日になったのであるが、それは、出生後14日以内であった。本件では、このような特別な事情があったのであるから、まさに前記判決が示した例外的適用のケースというべきである。
よって、本件では、原告ダイちゃんの出生後である9月30日の認知によって、例外的に国籍法2条1号を適用し、原告ダイちゃんに国籍取得を認めるべきである。
第2
1 本件各退去強制命令等の違憲、違法性
出入国管理及び難民認定法第24条7号の不該当
前述の如く原告ダイちゃんは、日本国籍を有する者であって「外国人」ではないから出入国管理及び難民認定法24条7号には該当せず、本件退去強制処分は違法である。従って、原告Fについても、本件処分の基磯となった事実に誤認があることになり、その処分は違法となる。仮に原告ダイちゃんの日本国籍取得が認められないとしても、原告らに対する各退去強制処分等は以下のとおり違憲、違法である。
2 本件各処分の違憲、違法性
(1)ダイちゃんに対する退去強制は、憲法22条及び26条並びに市民的及び政治的権利に関する国際規約(以下「B規約」という。)24条1項に違反する。
[1]ダイちゃんは、日本で生れ、現在4歳9ヵ月となった子どもであり、今後、基本的人権を基調とする社会の一員として、自己の個性と能力を発揮できる人格に成長していく地位を有するものである。そして、ダイちゃんが右のような人格に成長していくには、本件の具体的事情からして、扶養の意思と能力のある父親Aのごく近くにあって、養育ないし教育を受けることがもっとも適切である。
子どもが親から受ける右のような利益について、憲法13条及び26条は、幸福追求権及び教育を受ける権利の1内容として保障する。また、1979年8月4日、条約第7号として批准されたB規約24条1項は、「すべての児童は、…出生によるいかなる差別もなしに、未成年者としての地位に必要とされる保護の措置であって、家族、社会及び国による措置についての権利を有する」としている。
ダイちゃんに対する退去強制は、Aのダイちゃんに対する養育及び教育を実質的に不可能ならしめ、かつダイちゃんの養育ないし教育を受ける権利を侵害するものであって右各条項に違反するものというべきである。
[2]これに対し、被告らは、ダイちゃんがフィリピン国籍であることを前提として、フィリピンで教育を受ければよいこと、原告Fの親族がフィリピンにおり、生活の本拠となり得るから、原告らがフィリピンに退去強制させられても、前記各法条に反することはないと主張している。
しかし、既にダイちゃんは、生れてから4年9ヵ月もの間、日本から国外に出たことはなく、同人は日本語を母国語とする社会の中で生活してきているもので、現在、日本語を話すことはできるが、フィリピンの言葉はほとんど話すことはできない状況にある(11回F本人234、235、240項)。ダイちゃん及びFの生活の本拠は日本にあることは明白であって、ダイちゃんがこれまで成長することができたのは、Aの扶養と教育があったからこそ可能となってきたのである。被告らは、Fに対する尋問の中で、日本とフィリピンの生活費の格差のことを問題にして、フィリピンに仕送りしてもらって生活すればよいと受け取れる質問をしていた(11回F本人314項ないし319項)。被告らの考え方は、扶養を単なる金銭的支出の問題とする理解を前提にしているようである。しかし、これは、養育や教育というものが人格的接触の中で営まれていくものであるという極く当然の事実から目を背けるものであって、全く不当である。
被告らのような考え方に対して、Aは、「私の考えは、そういう距離的、時間的に離れることはできない。身近において初めて養育できるのであって、親としての最低の義務と言いましょうか、それが達せられるという信念がありました。」と述べ、親としての責任を果たす気持ちを明確にしている(7回A185項)。このようなAの心情を実現できるよう保護することが、前記各法条に合致することになるのである。
(2)原告らに対する退去強制は、憲法24条及び98条2項並びにB規約23条1項及び離散家族の発生を許さない国際慣習法に違反する。
[1]ダイちゃんは、FとAとの間の子である。この親子が一個の家族を構成することは否定できない事実である。
ところで、家族が社会の自然かつ基礎的な単位であることについては特に異論のないところであるが、B規約23条1項は、これを法的に承認し、「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位であり、社会及び国による保護を受ける権利を有する」とする。その趣旨は、基本的人権の保障を十全ならしめるため、個人の人権のほか、その個人が属する家族を全体として保護する点にある。また、かかる理念は、これまで憲法24条も承認してきたところである。
ところが、原告らが退去強制されると、原告らとAはフィリピンと日本とに遠く離れて、生活せざるを得なくなり、家族間の精神的、物質的な助け合いも思うように出来なくなる。かかる事態は、まさに右各法条に違反するものである。
[2]また、右各法条が家族を一個の単位として保護すべきとしていることの中には、当然家族離散となる措置をしてはならないとする趣旨を包含していると解される。家族離散と退去強制については、すでに、1938年の国際連盟「困窮外国人扶助に関するモデル条約第3条」においても、「送還が家族員をその意に反して離散せしめる結果となる場合」には送還を行ってはならない旨を規定しており、その趣旨は今や国際慣習法となっている。
[3]本件各処分は、原告らとAを離散させるものであって、これらB規約、国際慣習法に明らかに反する。さらに、日本が締結した条約及び確立された国際法規の誠実な遵守を義務づけた憲法98条2項にも違反するというべきである。
[4]この点について、被告らは、原告らとAの関係について、「社会の自然かつ基本的単位となる家族関係を形成した事実はなく、今後もその形成は困難な状況にある」として、原告らとAとの間の家族関係を否定しようとしている。被告らは、Aが既婚者であって、法律上の妻と離婚する意思がなく、Aが原告らと同居できないことを根拠としている。しかし、この考え方は、法律上の婚姻関係から出生していない婚外子=「非嫡出子」に対する差別的取扱いを真正面から肯定しようとするものであって、全く不当である。家族を形成しているかどうかは、血縁関係、家族としての具体的な接触状況に即して考えられるべきものである。
本件ではAとダイちゃんに血縁関係が存在することは問題がない。また、具体的な生活状況において、Aと原告らが日常的に同居していないとしても、同居に準ずるような家族としての具体的な接触状況があるかどうかを検討するべきである。よって、この点については、被告らの強調する同居の有無をあまり重視するべきではない。
[5]そこで、原告らとAの家族としての具体的な接触状況を検討する。まず、Aがダイちゃんが生れたころにどのような生活を送っていたかを見ると、「ダイちゃんが生れてからも、朝会社に行く前と終ってから、ずっと病院に通っていた。その後ダイちゃんが退院してからも、当時A住んでいたBからCのFのところに、朝直行して、ダイちゃんのおむつを替えて、病気がないという確認をして、そこに置いてある自転車で会社に行く。会社が終ってからは、ダイちゃんを風呂に入れて、寝たころに帰るという生活を続けていた」(7回A166項ないし289項、11回F本人220ないし222項)。
その後、1993年の本件を提訴後に、Aは、原告らを大阪に呼び寄せたが、AはFのところに毎日電話して、週に1、2回はダイちゃんの保育園への送り迎えをし、父母の面談の際にも必ず行っており、保育園の連絡ノートにも目を通して、いろいろ記入してきていた。また、大体決まって土曜日の夕方には、親子3人で食事をしたりしてきている(7回A186項、192項ないし197項、201項、11回F本人236項)。
以上のような事実関係からすると、原告らとAが固い絆で結ばれた1つの家族を構成していることは明らかである。
(3)原告らに対する退去強制は、憲法22条の個人の尊重及び幸福追求権を侵害し、B規約7条により許されていない「非人道的な取り扱い」に該当する。
原告らは、現在、Fがクリーニング店で得た収入とAの援助により生活を維持している(11回F本人224ないし227項)。Aは、ダイちゃんについて、法律上の妻との間の子どもと「差別することなく、私の子どもとして同等と言いますか、養育する義務を果たそうと最後まで果たそうと思っています。」(7回A212項)と述べている。このようにAはダイちゃんについて、「成人までは正真正銘の日本人として全責任をもつ」ことを固く決意している。
Fも、Aにたいし、「ダイちゃんに日本の教育を受けさせ、誇り高い日本人として育てる。私は命がけである。どんな苦労もするつもりである」と強く訴えてきており、日本でダイちゃんを育てていく覚悟をしている(11回F本人110ないし114項)。
かかる固い絆で結ばれた家族が、相互に励まし合い、助け合っていくためには、完全に同居することはできないとしても、往来の容易な近接した場所で暮らすことを保障するのが、まさに憲法13条の幸福追求権の内容となるのである。さらに、B規約7条は国家権力による非人道的取り扱いを禁止しているが、原告らに対する退去強制は、この非人道的取扱いに該当する。したがって本件退去強制は、憲法13条のほかB規約7条にも反するものといわなければならない。
(4)原告らに対する退去強制は、憲法31条及びB規約7条にも反するものといわなければならない。
憲法31条の「法律の定める手続」及びB規約7条の「法律に基づいて」とは、単に形式的名目的に法律に従うことを意味するものではなく、その法律の内容が適正であることをも要求する趣旨であると解すべきである。したがって、本件において、退去強制の処分をなすことは、法定の手続に従っているだけでなく、そのことが真にやむを得ない場合に初めて許容されるというべきである。
原告ら及びAが固い絆で結ばれた家族であることは前述したとおりである。したがって、日本人であり日本に住居を有するAとともに、原告らの生活の本拠もまた日本に存するのである。かかる原告らに対し退去強制することは到底やむを得ない場合にあたるとはいえない。Fに不法入国という事由があるにせよ、右のような家族の実情を考慮するならば退去強制もやむなしと云うにはあたらないというべきである。
さらに、ダイちゃんに対する退去強制は、国際連合が採択し、日本も1994年4月22日に批准し、同年5月22日に発効している「子どもの権利に関する条約」に、明らかに抵触する。同条約9条は、「子どもが親の意思に反して親から分離されないこと」と、同一8条は「親双方が子供の養育及び発達に対する共通の責任を有するという原則の承認を確保するために最善の努力を払う」と、そして同27条は、すべての子どもに対して、身体的・心理的・精神的・道徳的及び社会的発達のために十分な生活水準を受ける権利を規定しているのである。これらの規定はすべて、子どもが次代を担う一員として処遇されるべき権利を有するとの理念に基づいている。かかる理念は、当然、適正手続条項の「法律」の内容適正の解釈においても考慮されなければならない。 したがって、子どもの権利に関する条約の右各条に抵触するダイちゃんに対する退去強制は、やはり憲法31条及びB規約13条に反するというべきである。
3 裁量権の逸脱ないし濫用
(1)原告らに対する各本件退去強制令書発布処分は、出入国管理及び難民認定法24条によるものである。
ところで、法24条は、「次の各号の1に該当する外国人については、次章に規定する手続により、本邦からの退去を強制することができる」と定めているが、その法意は、出入国の問題は歴史的事情等が複雑に絡んでおりかつ人道上の問題とも深いつながりを持つので、形式的に退去事由を定め形式的にこれを執行すると種々の不都合が生じることになるから、退去強制するかしないかについて裁量の余地を設けたものである。
法50条1項3号もこれを受けて、仮に法24条各号に該当する者であっても「法務大臣が特別に在留を許可すべき事情があると認めるとき」はその者の在留を許可することができると定めている。
(2)そして右裁量にあたっては、前述した事情のほか次のような事情が考慮されなければならない。
[1]ダイちゃんは、婚外子といえどもダイちゃん自身にはなんらの責任はなく当然のことながら両親に監護、扶養、教育をされ、尊厳ある個人として成長する権利を有するものであるし、逆に両親も互いに協力してダイちゃんをそのような個人として成長させる義務と権利を有するものである。仮に婚外子であり、胎児認知があったと認定されないが故に、その子どもに両親双方からの養育を受ける権利がない、また一方の親には養育する義務及び権利がないとするならば、それは、「嫡出子」と比べて、婚外子を不当に差別するばかりではなく、尊厳ある個人としての成長を全く阻害するものとして憲法の基本原理である平等原則そのものを否定することになる。
近時、婚外子差別の問題に関して、婚外子に対する相続分を2分の1とする民法900条4号但書について、1995年7月6日、最高裁判所大法廷において、10対5の多数意見で右規定を合憲とする判決をしたものの、右規定を合憲と判断した10人の裁判官のうち4人が補足意見において、立法府による法改正を求めるか、法改正の必要性を示唆する内容を述べている。このような最高裁の判断は判決の結論はともかく、法律上婚外子を「嫡出子」と別異に取扱うことについて、生れてきた婚外子には全く責任がないもので、「生れによる」差別であって、撤廃すべきであるという認識が一般化してきた状況を反映したものと見るべきである。
[2]本件の場合、Aは、法律上の妻との離婚ができない状況にある。このため、AはFと婚姻する方法によって、ダイちゃんに日本国籍を取得させることはできない。しかし、Aは、ダイちゃんを自らの近く、において養育し、その成長を見届けることを切望し、現実にもそのようにしてきている。1993年4月にAは広島から大阪に転勤することになった。その結果、原告らとAは、一時、同じ日本国内とは言え、家
族が離散した状態となってしまったが、原告らは入国管理局の許可を得て、Aが原告らを大阪に呼び寄せて、大阪で生活できるようにして現在に至っている。
原告らとAの間には、強い親子の絆があるもので、ダイちゃんが現在の行政解釈の中で日本国籍を取得できないのは、もっばら、ダイちゃん自身にはなんらの責任もない、父母が法律婚をしていないという事情にのみよるものである。
そして、本件のようにAが自分の責任を果たすためにダイちゃんを側に置いておきたいというケースですら、原告らの退去強制を認めることになれば、いわゆるJFC(ジャパニーズ・フィリピーノ・チルドレン、日本人男性とフィリピン人女性との間に生れ、日本人男性から遺棄されている子ども)を日本人の父親が一方的に遺棄しても、なんら咎められることがないという状況を作り出すことにつながりかねないものである。このような日本人男性の無責任な態度を助長しかねない結論に至ることは厳に避けるべきものである。
したがって、原告らを退去強制処分とするのは、この親子の絆を国家が切り離すことであって、それは著しく人道に反し、甚だしく正義に反するものと断ぜざるえない。
(3)以上のとおり、原告らに対する本件各処分は、著しく非人道的、かつ、正義に反するものであって、法務大臣が原告らに特別在留許可を与えなかったことは、裁量権を逸脱濫用するものであり、本件各退去強制処分は違法である。
第3 おわりに
1 本件のように、日本人男性とフィリピン人女性が性的交渉をもち、子を産むというケースは今日激増している。
フィリピン人女性の多くは、原告Fのようにエンターテイナーとして出稼ぎに来た人たちである。年間5、6万人のフィリピン人女性が日本にやって来るといわれている。
その彼女達が店の客である日本人男性と知り合い、子を産んでいくわけである。
出会うきっかけは、正に貧困故にである。彼女達は貧しさ故に日本に出稼ぎに来、貧しさ故に日本人男性に近づき、少しでも貧しさから脱却しようとする。
これに対し、日本人男性側はどうか。
その多くが彼女達を人間として扱わない。性の対象としか見ず、生まれた子を含めぼろくずのように捨てていく。
彼女達が在留を続けることができず帰国することになれば、知らぬ存ぜぬを決め込む。
いま、フィリピンにはこのようにして父親に捨てられた日比混血児(ジャパニーズ・フィリピーノ・チルドレン)が1万人はいるといわれる。
その多くが極貧の生活を送りながらも父親に抱きしめられることを望んでいる。
しかし国境の壁もあり、父に抱いてもらうことさえ実現できない子がほとんどである。
他方、Aのように、原告Fと直ちには結婚できないが、子は自分の目の届く所で自分が責任をもって育てようとする日本人男性もいる。
にもかかわらず、被告らは、原告ダイちゃんは外国人である、日本に在留させるか否かは国の裁量の問題である、「不法」入国した外国人女性から生まれた子をたとえ日本人男性の婚外子だとしても日本に留め置くことはできない、との理論でこの父子を切り離そうとするのである。
子が「外国人」であるが故に父子を切り離しても当然だとする被告らの姿勢は、無責任な日本人男性を助長するもの以外何ものでもない。
現状において国境を越えて子が父の援助を受けられる可能性はいかほどあるというのか。仮に経済的援助は受け得ても、子が父に抱きしめられることはない。本来、子は、親との様々な交わりのなかで高度な精神作用を行い、一個の人格として成長していくにもかかわらずである。
世界において国境が存する現状下では、国籍は子が親とつながり、尊厳ある人として成長していく、ための基盤である。
そういう意味で、子と親とが生活の基盤を置いている国の国籍を子が取得するということは、子にとっては最も根本的な権利であるはずである。
2 しかも、本件において、Aは原告ダイちゃんを胎児認知し日本国籍を取得させようと、本人としてなし得るすべての手続を行った。
しかし、西区役所の大谷市民課長ら市民課職員らは、本来胎児認知の受付をしなければならないのに、それを怠った失態を糊塗しようとして、当初ダイちゃん出生前にAが胎児認知に赴いた事実自体をことさら隠蔽し、被告らもAらの真撃な訴えを一蹴し、何ら具体的調査もせず、頭から無批判的に大谷らの報告を受入れ、本件各処分に至る失態を犯した。
ある意味では勇気あるとも思える宮下証言がなければ、子のために自分のできるだけのことはしようとした父親が逆にうそつき呼ばわりされて終わりかねない事案であった。
3 行政の非嫡出子に対する差別的取扱い及び自らの失態を国民に転嫁しようとする対応に対し、国民の権利を救済しうるのは、司法のみである。
裁判所におかれては、国際婚外子にとって国籍のもつ意味を十分に理解され、Aがダィスケを抱きしめていたい、ダイちゃんもAに抱きしめられていたい、という人間として当たり前の願いを確固なものとして実現されるよう望むものである。