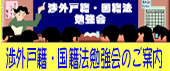|退令訴状|国籍訴状|退令答弁書|国籍答弁書|国籍原告準備書面1|退令原告準備書面2|国籍被告準備書面1|
|原告準備書面3|原告準備書面4|原告求釈明書|原告準備書面5|被告準備書面4|原告準備書面6|被告準備書面|




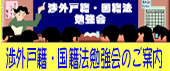
平成5年(行ウ)第5、6号
退去強制命令等取消、国籍存在確認請求事件
被告 準 備 書 面 (2)
第1 受理の存否について
1 原告らは、1991年(平成3年)9月12日に広島市西区長に対し口頭による胎児認知届出をしたとして、その受理は問題とせず、右届出だけでもって原告ダイちゃん(以下「ダイちゃん」という。)が日本国籍を取得したものと主張するようである。しかし、身分法上、胎児認知届の受理なければ、認知行為の効力が発生しないことはいうまでもないところである。したがって受理の主張を欠く以上、胎児認知の要件の欠缺は明らかであり、もちろん、胎児認知に関わる国籍取得の要件も満たし得ないから、原告ダイちゃんの国籍存在確認の請求は主張自体失当となるというべきである。
2 訴外A(以下「A」という。)による胎児認知届がなく、もちろんその受理がなかったことは既に述べてきたところであり、右受理の不存在については、直接の当事者であるA自身が、不受理を理由に広島家庭裁判所に対し審判を申立てるという行動に出ていることからも明らかというべきであるが、さらに、右胎児認知届の受理の当否の争いに関し、既に右広島家庭裁判所及び広島高等裁判所において家事審判がなされ、いずれも同届を受理せよとの申立ては排斥されていることから、右受理の不存在は客観的に明らかになったものといえるから、もはや本件行政訴訟においては右受理の存否については争えないものと解すべきである。
すなわち、戸籍法28条は、戸籍事件に関して不服あるものは、家庭裁判所に不服申立てができると規定するが、同条は、行政事件訴訟法1条にいう特別の定めがある場合に該当するものである。また、戸籍法119条の2は、同事件について、行政不服審査法による不服申立てを許さないと定める。これらの規定から考えると、戸籍法においては、戸籍事件につき、一般の行政訴訟や行政不服審査による救済よりも戸籍事件に常時関与している家庭裁判所の審判によるそれに委ねるのが妥当と考え、右のような管轄に関する定めを設けたものと解される。
したがって、家庭裁判所の専権的審判事項とされた認知届の受理の当否について既に家庭裁判所での審判を経ている以上、もはや国籍存在確認請求といった一般の行政訴訟において、それを争うことはできないものと言うべきである。したがって、以上の点から、受理がなかったことは明らかであると共に、この受理を不存在の事実に反する一切の主張は認められるべきではないから、仮に受理の存在について何らかの事実を主張したとしても、それは理由がないというべきである。
3 以上によれば、本件において原告らは口頭による胎児認知の届出行為があった旨主張し、それを基礎づけるために種々の事実を主張しているが、本件国籍存在確認請求の判断において、受理の不存在が明らかである以上、そもそも届出の如何をめぐって審理することは全く無意味と言えるから、事実審理は不要であるので、裁判所におかれましては、速やかに以下の法律上の争点について判断の上、早期結審を図られたい。
第2 国籍法2条1号の解釈について
原告らは、A認知が生後認知の場合でも、原告ダイちゃんの日本国籍取得が認められるべきであるとして、国籍法〔昭和25年法律第147号(以下「現行国籍法」という。)〕2条1号にいう「父」は、法律上の父に限定して解釈すべきでなく、特段の事情がある場合は事実上の父と解して差し支えない旨主張する。
しかし、同号の「出生の時に父が日本人であるとき」とは、子の出生の時において、その子の父が法律上の父であることを意味すると解するものであることは、既に被告提出の平成5年10月7日付け準備書面1で述べたとおりであり、これに加えて自然的血縁関係があるだけの生理上の父(または事実上の父)も含まれると解するする余地は全く存在しない。この点について、今回さらに詳述すれば以下のとおりである。
1 すなわち、日本国憲法は、同法31条2項で国籍離脱の自由を保障するほかは、同法10条において「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」とするのみで、国籍の得喪の要件を立法府の裁量に委ねている。したがって、憲法は、出生に係る国籍の取得に関し特定の原則を採用すべしと要請するものではなく、いわゆる血統主義または生地主義のいずれを原則とするかについては立法裁量事項として法律の定めによって決定すべきものと解されている。
そこで、現行国籍法の規定をみるに、同法は血統主義を採用しているものの(現行国籍法2条1・2号参照)、それを絶対視せず、同法3、12、17条1項等において出生地の如何による地縁の有無、本人の意思等の血統以外の要素を考慮して国籍の要件を定めていることから考えると、血統主義を原則としつつ、なおそれを徹底するものではないことは明らかであるから、血統主義を理由に直ちに生理上の父をもって同法2条1号にいう父を意味すると解することはできないところである。
そもそも、血統とは、血脈による愛着性を基礎とするものではあるが、それ自体は単に生物としての人間の生物的出自を示すものにすぎず、国籍が、個々の国民の関心、利害のみならず国家的利害の関わることから、国籍付与の基準としては、血統を絶対視することは適当ではない。また、ここでいう血統主義とは、自国民と血統関係にあることにより自国との結合関係の存在するものに国籍を付与するという政策を説明するための概念にすぎず、それが合理性を有するゆえんは、自国民の子について、通常自国民の家族に包摂されることによって実質上自国民の社会構成員となることから、自国の構成員とするのに適当であると価値評価できることに基づくものである。
したがって、国籍の得喪に関し、このような説明概念にすぎない血統主義の「血統」の文言からのみ解釈するのは妥当でなく、右立法の合理的理由からみて血統を重視しながらも、他方、法の規定に現れている他の要請も考慮し、我が国と真実の結合関係のある者に対して日本国籍を付与できるような解釈をすることが、法の趣旨にかなうものというべきである。
2 したがって、国籍の付与が前述の自国民とするのに適切かどうかの価値評価に基づくとの考え方からすれば、同法2条1号の「父」を法律上(親族法)の父と解するのが妥当であることは、疑いのないところである。けだし、法律上の父子関係が認められる者には日本国民たる父の家族に包含されることで日本国民の社会構成員となることから、右の考え方の帰結と言えるからである。
3 加えて、現行国籍法所定の「父」をめぐり、そして、法律上の父をこえて、それを生理上の父まで拡張すべきでないと解されるのは、以下の理由によるものである。
(1)第1に、生理上の父子関係は、母子関係が分娩という事実により明白に認識されるのと異なり、第3者から客観的に判定することが困難な性質のものであることから、その困難性を緩和する必要があること、及び、父子関係の存否は相続等にみられるように第3者にも大きな影響を及ぼすものであるため、第三者にも明白であるように公示することが要求されることから、生理上の父子関係をそのまま基準とせず、より明確な基準として法律上の父子関係に限定して解するのが妥当と言えるからである。このことは、国籍は国家の構成員を決定する重要な事項であって、生来的国籍取得はその中心的問題であり、しかも、実際問題としてはそれはできる限り、出生と同時に国家に判明しやすいものとして確定的に決定されることが望まれるのであって、出生子の数が膨大な数に上ることからしても当然の要請と言えるのである。
(2)次に、出生による国籍の取得といった生来国籍取得を操作する危険性の回避の必要があることを挙げることができる。すなわち、生理上の父子関係を基準にした場合、当事者をして生父判定の困難性に乗じ、その恣意によって出生子の生来的国籍取得の有無を左右させるといった危険性があることから、この基準を排斥して、法律上の父子関係とすることでこの危険性を未然に防止することが可能となると言えるからである。
(3)第3に、現行国籍法2条は、旧国籍法(明治32年法律第66号)1条、3条及び4条と同旨の規定であり、現行国籍法自体が同法の血統主義の建前を引き継いだとされる沿革的理由から、現行国籍法2条について旧国籍法と同様に解するのが妥当といえることによる。
すなわち、旧国籍法1条にいう「出生の時に父が日本人であるとき」の「父」の意義については、法律上の父と解されていた。このように解された理由の1つは、条文上、旧国籍法において、出生後に日本人父に認知された子はその認知により日本国籍を取得し(旧国籍法5条3号)、逆に出生後に外国人父に認知されて外国国籍を取得した日本人たるその子は日本国籍を失うものとされていたが(旧国籍法32条)、もし旧国籍法上の「父」を事実上の父と解するのであれば、そもそも、出生後の認知を問題とする余地がなく、このような規定を設ける必要は全くないといえるからである。
そうすると、旧国籍法上の「父」は法律上の父を指していたことは明らかであり、現行国籍法もその建前を否定することなく引き継いだものと解されることは争いがないことから、現行国籍法上の「父」も当然に法律上の父を指すものと解するのが相当ということになる。
(4)さらに、出生時における法律上の親子関係の有無等により国籍取得の要件が異なることは不均衡であり、憲法14条に定める平等原則に反するとの主張があるが、これについては、血統という単なる動物的要素を絶対視せず、親子関係により我が国との真実の結合が生ずる場合に国籍を付与するという現行国籍法の基本的な考え方によるもので、血統主義の原則に反するものではないことは当然、平等原則に反するも
のとも言えないことは明らかである。
すなわち、親子関係により我が国との結合関係が生ずるのは、子が日本国民の家族に包含されることによって日本社会の構成員となることによるから、日本国民の嫡出子については、当該日本国民が父であるか母であるかを問わず日本国籍を取得させることが適当である。しかし、非嫡出子については、正常でない家族関係における子であって、あらゆる場合に、嫡出子と同様親子関係の実質的結合関係が生じるとは言い難く、通常、母子関係に比し、生理上の父との間で実質上の結合関係すなわち生活の同一性が極めて希薄である。また、現在の外国の諸法制をみると、婚姻していない日本人父と外国人母との間の子は、母から外国国籍を承継することが可能であるが、婚姻していない日本人母と外国人父のとの間の子については、父の外国国籍を取得する可能性がほとんどなく、後者の子に対しては出生により日本国籍を付与しないと無国籍となる可能性が極めて大となる。このことから、原則として、日本国民父の非嫡出子は出生により日本国籍を取得せず、日本国民母の非嫡出子は日本国籍を取得するとの現行国籍法2条1号の適用の結果は合理的な差別と言えるものである。
なお、最近父母両系主義を採用した諸外国において、自国民母の子には、嫡出子たると非嫡出子たるとを問わず出生により自国籍を付与するが、自国民父の子については、嫡出子であるときに限り出生により国籍を付与するするものとする法制が多いのも、右理由と同旨の考虜に基づくものと考えられる。
(5)本件事案をみても、Aと原告Fとの関係は重婚的内縁関係であり、原告ダイちゃんとAの生活の同一性がないから、実質上の結合関係があるものではない。さらに、父が日本人(なお、真実は不明)、母がフィリピン人であって、原告ダイちゃん自身は日本人の血統率が50パーセントの者である。このような原告ダイちゃんに対し、血統による生来国籍を取得させるとした場合、日本人父、フィリピン人母のいずれの国籍を付与したとても血統の原則には反しない。のみならず、母子関係により原告ダィスケに付与された確定的生来フィリピン国籍(フィリピン憲法は、父母両系血統主義を採用している。)が付与されているほかに、わざわざ生後の認知によって日本国籍を後発的に付与しなければならない合理的理由は存在しないばかりか、そのことにより、原告は二重に国籍を取得することになり国籍の積極的抵触という極めて不都合な事態を招来する結果となるだけである。
そうすると、本件においてもやはり子の国籍は生来国籍を出生時点で確定的なものとし、浮動性を防止できるよう、現行国籍法にいう「父」の意義を法律上の父に限定して解釈するのが相当ということになる。
4 ところで、現行国籍法2条1号の解釈においても、認知の遡及効を認めて生来的国籍取得を認めるべきとの見解もあり、これに依拠して生理上の父も含まれるとの解釈もあり得るが、これも妥当でないというべきである。
(1)すなわち、第1に、認知と国籍取得との関係については、旧国籍法は・同法5条3号、6条3号。4号において、出生後に発生する事由のうち、認知という身分行為に基づいて伝来的に国籍の取得を認めていたところ、現行国籍法は、すでにこれらの規定を削除して、認知等の身分行為による国籍の変動を認めない建前を採用しているのである。
このことは、昭和25年国籍法改正の際の法律案提案理由で、次のように説明されていることから明らかである。
(前略)第3に、現行国籍法は国籍の取得についても、又、喪失についても、「妻は夫の国籍に従う」という原則及び「子は父又は母の国籍に従う」という原則を採用しており、婚姻、離婚、養子縁組、離縁、認知等の身分行為に伴い、或いは、夫又は父母の国籍の得喪に伴って、当然に、妻又は子の意思に基づかないで、その国籍の変更を生ずることになっているのでありますが、これまた憲法第24条の精神に合致しませんので、この法案におきましては、近時における各国立法の例に倣い、国籍の取得及び喪失に関しては、妻に夫からの地位の独立を認めてその意思を尊重することとし、又、子についても、出生によって日本国籍を取得する場合を除いて、子に父母からの地位の独立を認めることとしました。(後略)
右立法趣旨からも分かるように、旧国籍法が旧民法における家制度に対応する国籍法を制定していたため、出生後の身分行為(婚姻・離婚・縁組・離縁・認知)により国籍の移動が生じる各規定を設けていたのに対し、新憲法の制定、それに基づく民法の部分的改正等に対応するため、昭和25年に旧国籍法が全面的に改められたものであるが、その際、憲法24条の精神を受けて、国籍自由の原則を採用して、出生後の身分行為に基づく国籍の移動を認めないとしたのが、改正の経緯である。
したがって、現行国籍法の下では、子の出生後に日本国民である父が認知した場合に、子の日本国籍の伝来取得はあり得ず、これについて、例外は認められていないのである。
(2)次に、旧国籍法の解釈においても認知の遡及効により日本国籍の生来取得を認める建前をとっておらず、文言どおり、認知のときから日本国籍の取得が認められただけで、子の出生時まで遡及するものではなかったのである。
(3)第3に、もし、認知に遡及効を認めて、出生後に父の意思によって国籍の変更が認められるとの解釈を採るならば、出生による国籍の取得は、出生時点において確定されるべきであるとする出生時点主義に反する結果となり、妥当でない。けだし、右出生時点主義とは、国籍の浮動性の防止という国籍法の理想を受けて、国籍の早期確定のはかろうとする原則であるところ、国籍の生来取得が出生後の事情で容易に変動するような解釈は、それに真っ向から対立するものであって、到底認め難いものと言えるからである。
(4)以上のとおり、現行国籍法が、これらの出生後の身分行為による伝来国籍の得喪を認めない建前を採るに至ったこと、認知に関する国籍法解釈の沿革、及び出生時点主義等から考えると、特に認知の場合にのみ、その遡及効を認めて生来国籍の取得を認めることは、法解釈としての一貫性を欠くとともに、実際上も妥当性ある解釈とは言い難く、認知に遡及効を認めるような解釈は、現行国籍法の解釈としては、採用し得ないというべきである。
5 最後に、原告は、大阪高裁昭和62年2月6日決定(以下「昭和62年決定」という。)の旧国籍法1条の解釈をめぐる判示部分を引用の上、現行国籍法2条1号にいう「父」についても、旧国籍法1条と同様に解釈して、特段の事情のあるときには事実上の父も含まれると解すべき旨主張するが、これも妥当でないというべきである。
けだし、旧国籍法1条にいう「父」には自然的血縁関係のみの事実上の父を含まないと解されていたことは、従前から述べているとおりであって、実務の運用、多数の裁判例をみても、この点について昭和62年決定のような例外を認めるものはほとんど存在しないこのように、右決定自体、極めて異例のものと言うべきであるから、これを根拠とすることには、相当な理由がなく、この点をしばらく置くとしても、昭和62年決定は、そもそも就籍許可請求事件であって、国籍確認請求事件と訴訟物を異にし、国籍取得についての判断は、単なる理由中の1部の法律判断にすぎないだけでなく、その結論にとって不可欠な理由とも言い難いからである。すなわち、右決定は、就籍許可の前提として、抗告人の国籍取得原因として、「旧国籍法1条、または同法3条に準じて日本人となり、日本国籍を取得するものというべきである。」と判示するも、右1条と3条は選択的な規定であって、右判示では、抗告人の国籍取得原因を真に明らかにしているものとは言い難い。仮に、昭和62年決定のように就籍許可するとの結論を妥当と解した場合、同決定が抗告人の母は日本人であると認定していることから、抗告人は旧国籍法3条により日本国籍を取得したとの解釈も可能であって、たまたま旧国籍法1条についての解釈を詳細に展開してはいるが、果たしてそこでの例外的解釈までする必要があったかについてはなはだ疑問が残る事案であったと言わざるを得ない。
したがって、昭和62年決定の具体的事案を基礎に考えれば、このような例外を認める拡張解釈の先例性は低いものとみるべきであり、さらに理論構成としても、立法趣旨を十分に検討しておらず、例外的場合を限定できるように十分練られた解釈とは言い難いことから、右判旨を安易に一般化できるものではない。以上により、本件について、昭和62年決定の理由を援用すること自体、相当でないというべきである。
6 以上詳述したところにより、現行国籍法2条1号所定の「父」について、生理上の父が含まれるとする解釈を採るは全く存在しないから、原告等の主張に理由がないことは明らかと言うべきである。
よって、本件請求を速やかに棄却されたい。