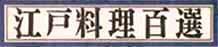 |
落語にみる
江戸の食生活
* 第4 回 * 豆腐
第 4 回 落語『酢豆腐[上方版:ちりとてちん]』へ飛びます。 豆腐料理も一口に言ってもいろいろな種類がございますが、冬は湯豆腐。そして夏場は、なんといっても冷蔵庫から出した冷た〜い「冷奴(ひややっこ)」が頭に浮かびます(真っ白い姿が涼しそ〜)。奴の上にさらに様々な工夫を凝らして洋風・中華風にトッピングされるものもございます。お豆腐は江戸時代の昔もいろいろな料理法で食卓にのぼり、当時の落語にも豆腐のことが沢山でてきます。毎度の食事に欠かせない、大変に忙しい売れっ子だったのでございます。今回は『酢豆腐』をご紹介するのですが、この噺、お豆腐好きの方にはゾッとさせてご免なさい。だからってお豆腐を嫌いにならないでくださいよ。 冷蔵庫のない、情報もない時代ならではのあわれな噺じゃ〜ございませんか。
豆腐の歴史
『庭訓往来』---精進料理の文献として最古のものの一つであり、生活百科として長いこと多くの人々に読まれた。
「文安元年(1444年)刊の『下学集』飲食部にも"豆腐"のことが書いてある。
うどん豆腐 --- 豆腐をうどんのように細く切って湯煮し、醤油にサンショウ、コショウなどを入れて食べる。
落語の祖といわれる策伝和尚が、江戸初期に編んだ咄本『醒睡笑』に豆腐の笑話がのっている。・・・江戸の初期に辺鄙な村里にまで豆腐の行商人が入りこみ、どうやら商売になっているらしいことである。
上方と江戸の豆腐
「上方きらいの馬琴は、豆腐は江戸の方がうまく、上方は「店構えが凝っているだけ」とけなしつけている。」(『図説江戸時代食生活事典』日本風俗史学会編・雄山閣出版 篠田統著)
江戸時代、料理本の紹介
『 豆腐百珍』
『 豆腐百珍続編』 『豆腐百珍続編 』の中には東海道の石部と草津の間の、目川村の田楽屋の絵が描かれている。『江戸料理百選』の装丁箱は、その挿絵を使用した。 この菜飯田楽は多くの紀行文に出てくる。江戸、浅草雷門前広小路にあった菜飯料理の店『目川』は目川村の菜飯を模しているとして有名である。
※『江戸料理百選』より。
『江戸料理百選』の『豆腐料理いろいろ』をご参照ください! ← クリック
豆腐で有名な江戸の料理屋
◆上方
※参考文献:『図説江戸時代食生活事典』篠田統編 日本風俗史学会編・雄山閣出版
|
■ HOME ■