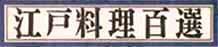 |
落語にみる
江戸の食生活
* 第3 回 * そば
第 3 回 落語『そば清[上方版:蛇含草(じゃがんそう)]』へ飛びます。江戸はこの頃、大食い競争といわれるものが庶民の間に大変流行っておりました。 現代でもテレビで、大食いチャンピオンなどという番組が賞金付で数多く放送されています。古今東西、人のやることはどうやら同じようです。大食いをするかたは何をいくつ食べたのなどと必ずあちこちで自慢話を吹聴しています。そこにいくと食い道楽のかたは、不思議に人前ではあまり自慢をされないようです。実に食い物の恨みはおそろしい。それでお話しにならないのかと、私食いしん坊なものですから、つい思ってしまいます。 ここに登場する清兵衛という男。そばならば、いくらでも食べるという大のお蕎麦好き。それも、もりにかぎっているようです。ほんとうにそばの好きなかたは、「もりそばの味が一番!」といわれるかたが多いのではないでしょうか。
このお話は真夏の出来事。黒の絽の夏羽織を着こんだ清兵衛さん、そばの大食い競争に三両をかけて挑みました。清兵衛さん、秘密に用意した裏細工で自信満々。勝つはずだったのですが、あらーびっくり、可哀想に。
そばのルーツ
江戸のそば
落語家の桂南喬さんが『江戸の食文化』(河出書房新書)で落語での蕎麦の食べ方を「べろを細めにすぼめて上顎へかるく付け、細かくそれを振動させてツルツルッと音を出して、口中に入れたらわりとこきざみに噛むのがこつです・・・左手にどんぶり(の縁と底)を持ち、食べるまえに箸(扇子)で麺をまぜながら、ふうふう吹くことをしなくてはいけません。」と書かれておられます。
また『そば物語』(植原路郎著)には「・・・パッと肩でのれんをはねのけてとび込む。割り箸を前歯でパチンと二つに開いて『もり』でも『かけ』でもスルスルとかっ込むと見るまに、銭をそこへ放り出し、さっと姿を消す。」と描かれていて、江戸っ子の威勢よさ、悪く言えば大変にせっかちな性格が伺えます。
江戸の初めの頃はうどんも蕎麦も菓子屋でうっていました。次いでうどん屋が独立し、傍らで蕎麦切りもうっていました。最初のうちは、蕎麦屋もうどん屋とよんだらしいが、江戸も中頃をすぎるとこの傾向は逆転する。
1664 寛文四 江戸(吉原の仁左衛門)で、けんどん蕎麦切りが始まる。
そばのご紹介
年越蕎麦(三十日(みそか)蕎麦)---関東の三長者の一人増淵民部の家で毎年、除夜の鐘の鳴るころ雇人たちに蕎麦を振る舞ったことからはじまったといわれるがいろいろな説があるようです。
もりやかけ以外の「たねもの」
『江戸料理百選』の『霙蕎麦(みぞれそば)』をご紹介します! ← クリック
蕎麦を扱った江戸落語
蕎麦を詠んだ時世(文化期1806年頃)の句
西瓜と蕎麦は食べ合わせが悪いといわれた。
有名な蕎麦やさん
◆現在はないが江戸時代に有名だった蕎麦やさん
※参考文献:『たべもの江戸史』(永山久夫著 新人物往来社)
|
■ HOME ■