応保二年(1162)、藤原俊成(当時の名は顕広)四十九歳の時の子として生れる。母は藤原親忠女(美福門院加賀)。同母兄に成家、姉に八条院三条(俊成卿女の生母)・高松院新大納言(祗王御前)・八条院按察(朱雀尼上)・八条院中納言(建御前)・前斎院大納言(竜寿御前)がいる。初め藤原季能女と結婚するが、のち離婚し、建久五年(1194)頃、西園寺実宗女(西園寺公経の姉)と再婚した。子に因子(民部卿典侍)・為家ほかがいる。寂蓮は従兄。御子左家系図
仁安元年(1166)、叙爵し(五位)、高倉天皇の安元元年(1175)、十四歳で侍従に任ぜられ官吏の道を歩み始めた。治承三年(1179)三月、内昇殿。養和元年(1181)、二十歳の時、「初学百首」を詠む。翌年父に命ぜられて「堀河題百首」を詠み、両親は息子の歌才を確信して感涙したという。文治二年(1186)には西行勧進の「二見浦百首」、同三年には「殷富門院大輔百首」を詠むなど、争乱の世に背を向けるごとく創作に打ち込んだ。
文治二年(1186)、家司として九条家に仕え、やがて良経・慈円ら九条家の歌人グループと盛んに交流するようになる。良経が主催した建久元年(1190)の「花月百首」、同二年の「十題百首」、同四年の「六百番歌合」などに出詠。ところが建久七年(1196)、源通親の策謀により九条兼実が失脚すると、九条家歌壇も沈滞した。建久九年、守覚法親王主催の「仁和寺宮五十首」に出詠。同年、実宗女との間に嫡男為家が誕生した。
正治二年(1200)、後鳥羽院の院初度百首に詠進し、以後、院の愛顧を受けるようになる。後鳥羽院は活発に歌会や歌合を主催し、定家は院歌壇の中核的な歌人として「老若五十首歌合」「千五百番歌合」「水無瀬恋十五首歌合」などに詠進する。建仁元年(1201)、新古今和歌集の撰者に任命され、翌年には念願の左近衛権中将の官職を得た。承元四年(1210)には長年の猟官運動が奏効し、内蔵頭の地位を得る。建暦元年(1211)、五十歳で従三位に叙せられ、侍従となる。建保二年(1214)には参議に就任し、翌年伊予権守を兼任した。
この頃、順徳天皇の内裏歌壇でも重鎮として活躍し、建保三年(1215)十月には同天皇主催の「名所百首歌」に出詠した。同六年、民部卿。ところが承久二年(1220)、内裏歌会に提出した歌が後鳥羽院の怒りに触れ、勅勘を被って、公の出座・出詠を禁ぜられた。
翌年の承久三年(1221)五月、承久の乱が勃発し、後鳥羽院は隠岐に流され、定家は西園寺家・九条家の後援のもと、社会的・経済的な安定を得、歌壇の第一人者としての地位を不動のものとした。しかし、以後、作歌意欲は急速に減退する。安貞元年(1227)、正二位に叙され、貞永元年(1232)、七十一歳で権中納言に就任。同年六月、後堀河天皇より歌集撰進の命を受け、職を辞して選歌に専念。三年後の嘉禎元年、新勅撰和歌集として完成した。天福元年(1233)十月、出家。法名明静。嘉禎元年(1235)五月、宇都宮頼綱の求めにより嵯峨中院山荘の障子色紙形を書く(いわゆる「小倉色紙」)。これが小倉百人一首の原形となったと見られる。延応元年(1239)二月、後鳥羽院が隠岐で崩御し、その二年後の仁治二年八月二十日、八十歳で薨去した。
建保四年(1216)二月、自詠二百首から撰出した歌合形式の秀歌撰『定家卿百番自歌合』を編む(以下『百番自歌合』と略)。自撰家集『拾遺愚草』は天福元年(1233)頃最終的に完成したと見られ、その後さらに『拾遺愚草員外』が編まれた。編著に『定家八代抄(二四代集)』『近代秀歌』『詠歌大概』『八代集秀逸』『毎月抄』などがある。古典研究にも多大な足跡を残した。また五十六年に及ぶ記事が残されている日記『明月記』がある。千載集初出、勅撰入集四百六十七首。続後撰集・新後撰集では最多入集歌人。勅撰二十一代集を通じ、最も多くの歌を入集している歌人である。
*
「定家は、さうなき物なり。さしも殊勝なりし父の詠をだにもあさあさと思ひたりし上は、まして餘人の哥、沙汰にも及ばず。やさしくもみもみとあるやうに見ゆる姿、まことにありがたく見ゆ。道に達したるさまなど、殊勝なりき。哥見知りたるけしき、ゆゆしげなりき。ただし引汲の心になりぬれば、鹿をもて馬とせしがごとし。傍若無人、ことわりも過ぎたりき。他人の詞を聞くに及ばす。(中略)惣じて彼の卿が哥の姿、殊勝の物なれども、人のまねぶべきものにはあらず。心あるやうなるをば庶幾せず。ただ、詞姿の艶にやさしきを本躰とする間、その骨(こつ)すぐれざらん初心の者まねばば、正躰なき事になりぬべし。定家は生得の上手にてこそ、心何となけれども、うつくしくいひつづけたれば、殊勝の物にてあれ」(『後鳥羽院御口伝』)。
「風体義理を存して意深く詞妙なり。けどほきものから又面白く侍り。昔にはぢぬ歌人なるべし。造りある家の庭の面に玉を磨ける心ちするに、楽屋の内より陵王の舞ひ出でたらむとやいふべからむ」(『続歌仙落書』)。
「此道にて定家をなみせん輩は、冥加も有るべからず。罰をかうむるべき事也」「恋の哥は、定家の哥ほどなるは、昔より有るまじき也」(『正徹物語』)。
*
勅撰集入集歌と『拾遺愚草』を主として百首の歌を抄出した。出典を記していない歌は全て『拾遺愚草』から採ったものである。「員外」とあるのは『拾遺愚草員外』の略である。
注釈なしのテキストはこちら
春 21首 夏 10首 秋 17首 冬 9首
恋 26首 哀傷 1首 旅 5首 雑 11首 計100首
春
後京極摂政、左大将に侍りける時、家に六百番歌合し侍りけるに、余寒のこころをよめる
かすみあへず猶ふる雪に空とぢて春ものふかき埋み火のもと(風雅34)
【通釈】霞が立ち込めるまでに至らず、なお降る雪に空はふさがって――春を奧深く感じつつ過ごす、埋み火のもとよ。
【語釈】◇かすみあへず すっかり霞みきらず。立春になって霞が立ちそうな気配はあるが、実際はまだそこまで行かず、雪が降っているのである。◇ものふかき 奧深くにある、奧ゆかしい、趣が深いなど、さまざまなニュアンスで使われる語。源氏物語にしばしば見えるが、和歌では当詠が初出のようである。◇埋(うづ)み火 囲炉裏などの灰の中に埋めた炭火。
【補記】建久四年(1193)秋に披講・評定された『六百番歌合』出詠歌。定家三十二歳。題の「余寒」は立春を過ぎて残る寒さ。炉辺にあって雪降る空を眺め、埋み火の温もりに浅春の候の趣深さを感じている。
【他出】六百番歌合、夫木和歌抄、題林愚抄
【主な派生歌】
そことなき花の香りにかすまれて春ものふかき宿のあけぼの(伏見院)
霞みあへず猶ふる雪もけふよりの人の心の春はうづまず(小沢蘆庵)
守覚法親王家五十首歌に
大空は梅のにほひにかすみつつ曇りもはてぬ春の夜の月(新古40)
【通釈】広大な空は梅の香に満ちておぼろに霞みながら、すっかり曇りきることもない春の夜の月よ。
【補記】前歌と同じく建久九年(1198)夏の「御室五十首」。「にほひにかすみ」という嗅覚・視覚の境界を不分明にした共感覚的表現、「曇りもはてぬ」による更なる朧化、また源氏物語「花宴」朧月夜の一場面のほのめかしなど、石田吉貞氏の言う「縹渺美」(『妖艶 定家の美』)を極めた一首。
【他出】御室五十首、百番自歌合、拾遺愚草、愚問賢註、井蛙抄、耕雲口伝、東野州聞書
【本歌】大江千里「千里集」「新古今集」
照りもせず曇りもはてぬ春の夜のおぼろ月夜にしくものぞなき
【主な派生歌】
大空はそことも見えずかすみつつゆく方しらぬ有明の月(後鳥羽院)
百首歌たてまつりし時
梅の花にほひをうつす袖のうへに軒もる月のかげぞあらそふ(新古44)
【通釈】梅の花が匂いを移し染める袖の上に、軒を漏れてくる月影も涙に映って、香りと光が競い合っている。
【語釈】◇にほひをうつす 匂いを染みつける。「うつす」は「月のかげ」については「映す」意を兼ねる。◇軒もる月のかげ 伊勢物語の「あばらなる板敷に月のかたむくまで…」の一節を思わせる。
【補記】香(嗅覚)と光(視覚)という異種の感覚が「あらそふ」と見たところ、定家の特異な資質に根差す斬新さが感じられる。梅と月の取り合せや、「軒もる月」などから、当時の読者は伊勢物語第四段(「月やあらぬ…」の歌よりも物語の地の文)を想ったことだろう。著名な物語の余香を漂わせ、一首の情趣を複雑化するのは、父俊成より引き継いで深化させた、これも定家得意の詩法であった。正治二年(1200)秋、後鳥羽院が群臣に詠進せしめた百首歌「正治初度百首」。定家三十九歳。後鳥羽院に認められ、定家にとっては宮廷歌壇に足場を築くきっかけとなった百首歌であった。
【他出】正治初度百首、拾遺愚草
【参考】「伊勢物語」第四段(→資料編)
又の年のむ月に、むめの花ざかりに、
正治二年百首歌たてまつりける時
花の香のかすめる月にあくがれて夢もさだかに見えぬ頃かな(続後拾遺130)
【通釈】梅の花の香が霞むようにたちこめ、おぼろに霞んでいる月に心がさまよい出てしまって、夢もはっきりとは見えないこの頃であるよ。
【語釈】◇花の香のかすめる月 「かすめる」は前後に掛かり、香りが霞むように立ち込める意と、月がおぼろに見える意と、両義を兼ねる。
【補記】春の耽美的気分が、現実ばかりでなく夢にまで浸透している。前歌と同じく正治初度百首。
【他出】正治初度百首、百番自歌合、拾遺愚草
【参考歌】よみ人しらず「古今集」
涙川枕ながるるうき寝には夢もさだかに見えずぞありける
守覚法親王の五十首歌に
霜まよふ空にしをれし雁がねの帰るつばさに春雨ぞ降る(新古63)
【通釈】
【語釈】◇霜まよふ 安東次男『藤原定家』が指摘するとおり、張継「楓橋夜泊」の「霜満天」、またこの詩の影響を受けたかという伝家持の「かささぎの渡せる橋におく霜の白きを見れば夜ぞ更けにける」などとの関連が窺われ、霜気が空に漂う、さ迷うといったニュアンスで用いたものであろう。◇しをれし 窶れた。「し」と過去の助動詞を用いていること、また春の帰雁を詠む下句との対比から、秋に渡来した時の雁のさまを言うと思われる。長い旅路を経てこそ「しをれし」の語は活きよう。 ◇雁がね 元来は《雁が音》すなわち雁の啼き声を言うが、また雁そのものをも指す。ここは後者であるが、哀れな啼き声も聞こえる遣い方である。
【補記】建久九年(1198)夏、守覚法親王に召されて詠んだ五十首歌。《帰雁》《春雨》の二主題をからめた趣向の歌は定家以前にほとんど例を見ず、あっても引くに値しない凡作である。故郷へ帰る雁の翼にほんのり浸透する春雨と対比的に、渡来した時の秋空の霜気が呼び起こされる(雁の飛来が本格化するのは晩秋である)。冷気漂う空に飛んでいた
【他出】拾遺愚草、続歌仙落書、和歌口伝
【参考歌】よみ人しらず「古今集」
春霞かすみていにし雁がねは今ぞ啼くなる秋霧のうへに
藤原定家「皇后宮大輔百首」
秋霧を分けし雁がねたちかへり霞に消ゆる曙の空
【主な派生歌】
雁がねのかへる翅にかをるなり花をうらむる春の山風(源実朝)
雁がねの忘がたみの花の色やかへる翅にかかる白雲(宗良親王)
さえ暮るる嵐を寒み飛ぶ鳥の帰る翅に霰降るなり(武者小路実陰)
歌合百首 遊糸
くりかへし春のいとゆふいくよへて同じみどりの空に見ゆらん
【通釈】春の陽炎は、繰り返し、どれほど永い年にわたって、変らぬ
【語釈】◇くりかへし 糸の縁語、というより元来は糸を何度も手繰ることを言い、転じて同じことを反復する意に用いた。◇いとゆふ 陽炎。漢語「遊糸」に由来する語かという。漢字では「糸遊」と書き、「遊」の字音仮名遣は「いう」であるが、和語としては「いとゆふ」と書くのが慣い。◇いくよへて 「へて」は「
【補記】建久四年(1193)の六百番歌合、春中二十四番左勝。右は家隆の「のどかなる夕日の空をながむれば薄紅にそむるいとゆふ」。俊成の判は「『くりかへし』『いくよへて』などいへる、糸の事にかかれるやうにぞ侍れど、『おなじみどりの』などいへる末の句は、優に侍るにや。右は、夕日の空をながめて遊糸をそめたる心をかしき方は侍るを、暮天の赤気すこしさらでもと見え侍れば、みどりの空、勝にてや侍るべからん」。
【他出】六百番歌合、夫木和歌抄、題林愚抄
【参考歌】作者未詳「和漢朗詠集」
霞はれみどりの空ものどけくてあるかなきかにあそぶ糸遊
光明峰寺入道前摂政内大臣に侍りける時よませ侍りける百首歌に、尋花といふことを
鳥のこゑ霞の色をしるべにておもかげ匂ふ春の山ぶみ(玉葉180)
【通釈】鳥の囀りや霞の春めいた色に導かれ、桜を尋ねてゆくと、見る前から花の面影がほのぼのと目に浮かぶ、春の山歩きであるよ。
【語釈】◇鳥の声 一般的には「鶏の声」の意に用いられた語で、「小鳥の声」の意に用いるのは例外的であることを岩佐美代子『玉葉和歌集全注釈』は指摘している。◇面影にほふ 「面影」は眼前には存在せずありありと目に浮かぶもの。「にほふ」は気配が漂う、感じられる意。◇山踏み 山を踏んで歩くこと。
【補記】建保三年(1215)、内大臣藤原(九条)道家主催の歌会に詠進された百首歌「内大臣家百首」において「尋花」の題で詠んだ歌。「鳥の声」「霞の色」と対句的な構成でリズミカルに歌い出し、花を探し求める心を朗らかに、かつ幽艶に謳い上げている。「『花』ともなく、『たづぬる』ともなくて、花を尋る心十分なる事、上手のしわざ也」(拾遺愚草俟後抄)。
【他出】拾遺愚草、六華集
【参考歌】藤原俊成「続詞花集」「新勅撰集」
面影に花のすがたを先だてて幾重越えきぬ峰の白雲
【主な派生歌】
宿やこれ霞のうちの見し花のおも影にほふ色もかはらで(正徹)
後京極摂政家花五十首歌に
霞たつ峰の桜の朝ぼらけ
【通釈】ほんのりと朝が明ける頃、霞がたなびく峰々の桜の景色は、あたかも天の川の波を紅に
【語釈】◇紅くくる 紅に
【補記】峰々にたなびき、天へと続く霞。そのところどころに透ける桜の薄紅色を、天の川の白波を括り染めにしたと見た。山桜の花の色は普通白であるが、紅い若葉が出ると、遠目には薄紅色に見えるのである。「紅」にはまた朝焼の反映を見てもよいか。大胆な喩と叙法を用い、妖艶なばかりの春の叙景歌。建久元年(1190)秋、良経邸での「花月百首」。
【参考歌】在原業平「古今集」
ちはやぶる神代もきかず龍田河唐紅に水くくるとは
【主な派生歌】
春の池のみぎはの梅のさきしより紅くくるさざ波ぞたつ(九条良経)
神無月みむろの山の山おろしに紅くくる龍田川波(式子内親王[新千載])
秋はけふ紅くくる龍田河ゆくせの波も色かはるらん(飛鳥井雅経[新勅撰])
紅葉する峰の梯みわたせば紅くくる秋の山人(順徳院[続後拾遺])
龍田川くれなゐくくる秋の水色もながれも袖のほかかは(九条道家[新後撰])
大井川ゐせきに秋の色とめて紅くくる瀬々のいは波(亀山院[続拾遺])
木の葉のみちりしく比の山河に紅くくる鳰の通路(飛鳥井雅世[新続古今])
夕日影山は下てるもみぢ葉に紅くくる嶺の秋霧(正広)
高嶺よりまなく落ちくる紅葉葉の紅くくる滝つ岩浪(冷泉為村)
居所
やどごとに心ぞ見ゆる
【通釈】家ごとに、なごやかに打ち解ける心が見える。一家揃って円座する、花の都の如月・弥生の頃には。
【語釈】◇やど 語源は
【他出】夫木和歌抄、六華集
【補記】建久二年(1191)、九条良経家の十題百首。花の季節の《都》の家居の平和な風景を詠む。同百首の一つ前の歌は「秋津島をさむる門ののどけきにつたふる北の藤波のかげ」と摂関家を讃める歌を詠んでおり、掲出歌にも国を治定する摂関家に対する讃美の心が籠ることになる。
【参考歌】源経信「経信集」
すむ人の心ぞ見ゆる年ふれどみくさびすゑぬ宿の池水
【主な派生歌】
むめが枝はむつきのころの花にして桜はすゑのやよひきさらぎ(伏見院)
建保五年四月庚申に春夜
山のはの月まつ空のにほふより花にそむくる春のともし火(玉葉211)
【通釈】月の出を待つ山の端の空がほのかに明るむや否や、花に向けていた灯火を背後へ押しやる。(こうして、月と花がおぼろに融け合う春夜の情趣を味わう準備をする。)
【語釈】◇空のにほふより 山の端の空が(月の余光で)ほのぼのとした色に映えるとすぐに。「にほふ」は花に縁のある語。◇花にそむくる 桜の花に対して背ける。◇春のともし火 漢語「春燈」による語。春の夜のほのぼのとした感じのする燈火。
【補記】「花の匂ふ時分、月を待心」(六家集抜書抄)。灯火を「花にそむくる」理由につき岩佐美代子氏『玉葉和歌集全注釈』は「月光でこそ花を眺めたいため」と解するが、月を単なる花の照明役と見なすのであれば、《夜花》の趣意には適っても《春夜》の題には適うまい。また、わざわざ「空のにほふ」と遣った定家の意図、すなわち一首の縹渺たる余韻を見損なうことにもなろう。「花もひとつにかすみつつおぼろにみゆる春の夜の月」(新古今集)、「春の夜は月こそ花のにほひなりけれ」(新勅撰集)といった、花と月がほのぼのと融け合う春夜の風情を憐れむためにこそ、「ともし火」は邪魔とされたはずである。建保五年(1217)四月十四日、後鳥羽院の御所における庚申五首歌会出詠歌。定家五十六歳。同月十六日の『明月記』には大納言公経の言として当五首につき「今度の歌抜群の由、殊に叡感有り」と後鳥羽院の賞賛の言を伝えている。
【他出】続歌仙落書、拾遺愚草、秋風集、六華集、題林愚抄、六家抄
【参考】「白氏文集・春中与廬四周諒…」「和漢朗詠集・春夜」
背燭共憐深夜月 踏花同惜少年春
建保二年詩歌合侍りけるに、河上花を
花の色のをられぬ水にこす棹のしづくもにほふ宇治の河をさ(続古今116)
【通釈】花の色を映す、折ることの出来ない水に、宇治川の渡し守が棹をさし越してゆく――その棹から垂れる雫も匂いたつかのようである。
【語釈】◇をられぬ水 映じている花を折り取ることのできない水面。伊勢の本歌から取った語句。◇しづくもにほふ 雫も花の色を映して匂う。「にほふ」は美しい色や香が溢れるさま。◇河をさ 川長。川舟の船頭。
【補記】建保二年(1214)の内裏詩歌合。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、歌枕名寄
【本歌】伊勢「古今集」
春ごとにながるる河を花と見てをられぬ水に袖やぬれなむ
【参考歌】「源氏物語・橋姫」
さしかへる宇治の川長朝夕のしづくや袖をくたしはつらむ
橘広房「新勅撰集」
この里と言はねどしるき谷水のしづくもにほふ菊の下えだ
【主な派生歌】
さす棹のしづくも香にやにほふらむ堤の花の影うつるころ(村田春海)
秋日侍太上皇仙洞同詠百首応製 春
おのづからそこともしらぬ月は見つ暮れなばなげの花をたのみて
【通釈】おのずと、どことも知らぬ場所で月は見ることになった。「暮れなばなげの花かは」と詠まれたように、きっとあるはずの、恰好の花の蔭をあてにして、山中を尋ね歩いた果てに。
【語釈】◇おのづから 自然な結果として。◇月は見つ 「つ」は完了の助動詞。起こしてしまったことを後悔する気持を籠めることもあり、反対にやり遂げたことに満足する気持を籠めることもある。◇暮れなばなげの花 本歌に基づく詞。本歌では「かは」と反語があとに続くので、「無げ」ではない(すなわち有りそうな)「花(の蔭)」を意味する。
【補記】主題を言うなら《尋花》であろう。花に耽溺する心から、木蔭に宿るつもりで日暮らし山を尋ね歩いた挙句、見知らぬ場所で旅寝することとなり、花の蔭での月見となった。「そこともしらぬ月は見つ」には、過失の後悔よりも、予想外の満足感を読みたい。「おのづから」により、花蔭の月見までは期待していなかったことが窺われるからである。いずれも春の耽美的な願望を詠んだ素性の二首から詞を借り、その願望を成し遂げて春情を満喫する一日を歌い上げた。定家独得の屈折した詞遣いもここでは魅力的であり、興趣尽きない一首である。正治二年(1200)の正治初度百首。八月八日追給題、同二十五日詠進。作者三十九歳。
【本歌】素性法師「古今集」
いざけふは春の山べにまじりなむ暮れなばなげの花のかげかは
素性法師「古今集」
思ふどち春の山べにうちむれてそことも言はぬ旅寝してしか
花月百首 花
花の香はかをるばかりを行方とて風よりつらき夕やみの空
【通釈】花の
【語釈】◇花の香 桜の花の
【補記】建久元年(1190)秋、良経邸での「花月百首」。闇の中の香を詠むのは梅花詠の常套であり、この「花の香」を塚本邦雄は「梅の香と解すべきであらう」とする(『定家百首』)。が、風より夕闇が「つらき」と言うのは嗅覚よりも視覚の美を尊ぶゆえであって、むしろ梅花詠にはあるまじき歌である。この「花」はやはり桜以外ではあり得ない。可視と不可視のぎりぎりの境界をゆくような落花のイメージを詠んで、「縹渺美」の極限に至った一首。
【参考歌】藤原公通「新勅撰集」
月影にかをるばかりをしるしにて色はまがひぬ白菊の花
建暦二年の春、内裏に詩歌を合はせられ侍りけるに、山居春曙といへる心をよみ侍りける
名もしるし峰の嵐も雪とふる山桜戸のあけぼのの空(新勅撰94)
【通釈】「春は曙」と言うが、その誉れも紛れない。庵の山桜戸を開けて眺めれば、嶺に吹く嵐も雪とばかりに桜の花びらを降らせている、美しい曙の空よ。
【語釈】◇名もしるし 「名」は名誉・名声の意。「しるし」は紛れもなく顕れているさま。何の「名」を指すかについては、曙とする説、桜戸とする説、また嵐・嵐山説など、諸説あるが、掲出歌の題は《山居春曙》であり、一首の中心をなすのは花降りしきる曙の空の景であるので、曙を指すのは明らかであろう。もとより枕草子の「春は曙」も意識しての謂に違いない。補記参照。◇山桜戸 「雪と降る山桜」「山桜戸」と掛けて言う。山桜戸は山桜を材とする戸であり、また「桜の辺に有宿」(六家集抜書抄)の意でも遣われた語。◇あけぼの 「あけ」に「開け」の意が掛かり戸の縁語。
【補記】山居の人が起き抜けに庵の戸を開けた瞬間、曙の空いちめんに舞う花吹雪を見た感動である。建暦二年(1212)五月十一日の内裏詩歌合。定家五十一歳。語釈に書いたように「名もしるし」を巡って諸説あるが、題の《春曙》を指すことは紛れもない。後年の作であるが家隆が『九条前内大臣家百首』において「遠村秋夕」の題で詠んだ「名もしるし雲も一村かかりけり誰が夕暮の秋の山もと」(壬二集1582)が参考になろう。もとより家隆の歌の「名」は「秋夕(秋は夕暮)」の誉れであり、掲出歌の影響下にあることが窺える。なお、参考として「名」が何を指すかに関する諸説・諸訳を以下に挙げる。「あけぼのの事を云り。あくる時分はしろき物なれば、その上に桜も雪のごとく白妙にて、曙といふ名のしるきよし也」(抄出聞書)、「花の雪とふるをみてさくら戸の名もしるしと云心也」(六家集抜書抄)、「嵐山の心あるべからず。ただなるべし。あらいといふ名もしるきといふ心なるべし。むべ山かぜをあらしといふらむというたるたぐひなり」(耳底記)、「小倉の山荘に在て、嵐山の落花を見てよみ玉へる意にて、初句は、嵐山と云名もしるく見ゆと也」(美濃廼家苞折添)、「嵐山という名もしるく…」(訳注全歌集)、「山桜戸の名もしるく…」(岩波新古典大系・中世和歌集鎌倉篇)。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、両卿撰歌合、詠歌一体、正風体抄、井蛙抄、六華和歌集、歌林良材、六家抄
【参考歌】作者未詳「万葉集」
あしびきの山桜戸をあけおきて吾が待つ君を誰か留むる
千五百番歌合に
桜色の庭の春風あともなしとはばぞ人の雪とだに見む(新古134)
【通釈】桜の色に染まって吹いた庭の春風は、もはや跡形もない。今や花が地面に散り敷いているだけで、人が訪れたならば、せめて雪とでも見てくれようが。
【語釈】◇桜色の 桜の色をした。「春風」にかかる。「桜色」は衣の色について詠まれた例はあるが(「桜色に衣はふかくそめて着む…」)、風の色については前例を知らない。◇雪とだに見む 桜色の春風は見られなかったけれども、せめてその名残として、庭に散り敷いた花を雪と見てくれよう。
【補記】庭に花を吹き散らした「桜色の春風」を憶い、今は地面に散り敷くばかりの花は、客が訪れても雪と見るばかりであると寂しむ心であろう。遅れて訪れた客人が落花を「雪と」見るという趣向は業平の本歌から取ったものである。建仁元年(1201)七月に詠進し、翌年歌合に結番された千五百番歌合、二百三十五番、右持。俊成の判詞は「右歌は、『明日は雪とぞふりなまし』といへる歌の心を、とかくいひなして侍る、詞づかひをかしく侍るにや」。しかし心に残るのは、むしろ不在の「桜色の庭の春風」の鮮やかなイメージである。上句に山場がある秀逸の一例。
【他出】新古今集、定家八代抄、百番自歌合、六家抄
【本歌】在原業平「古今集」
今日来ずは明日は雪とぞ降りなまし消えずはありとも花と見ましや
建保二年内裏詩歌をあはせられけるに、河上花
名取川春の日数はあらはれて花にぞしづむ瀬々の埋れ木(続後撰135)
【通釈】名取川には桜の花が散って、春の日数の積もったことははっきりと知れる一方、瀬々の埋れ木はその花びらに埋れて沈んでいる。
【語釈】◇名取河 既出。◇春の日数 春になってから経った日数。◇瀬々のむもれ木 本歌から取った語。埋れ木は水中や土中に永く埋もれていて、変わり果ててしまった木。
【補記】名取川に言寄せた古今集の恋歌を、春歌に転じた本歌取り。本歌では恋の露顕の象徴とされた「埋れ木」を落花のうちに沈め、逆に顕れたのは「春の日数」であるとして、本歌の趣向を反転させた。建保二年(1214)二月三日の内裏詩歌合(散逸)で、《河上花》題を詠んだ歌。番われた漢詩も賞賛されたが、順徳天皇の判断で定家の勝となったことが当日の『明月記』に記され、定家は「存外面目」と喜んでいる。
【他出】明月記、百番自歌合、拾遺愚草、両卿撰歌合、万代和歌集、歌枕名寄、井蛙抄、六華和歌集、六家抄
【本歌】よみ人しらず「古今集」
名取川瀬々の埋れ木あらはればいかにせむとか逢ひ見そめけむ
一字百首 春
きのふまでかをりし花に雨すぎてけさはあらしのたまゆらの色(員外)
【通釈】昨日まで薫っていた桜は今どうなっているか。夜来、嵐の雨が降り過ぎて、今朝は残っていまい。玉ゆらのようにはかない花の色よ。
【語釈】◇あらし 「あらじ」「嵐」の掛詞。◇たまゆら ほんの一瞬。万葉集の「玉響」の旧訓「たまゆらに」に由来する語(現在の定訓は「たまかぎる」)。
【補記】建久元年(1190)六月二十五日、「あさかすみ」「むめのはな」など二十の語句を決めておいて、その一字一字を一首の歌の頭に置くという条件で詠んだ百首歌。掲出歌は「かきつはた」の「き」を最初の一字としている。この百首を定家は六時間のうちに詠了したという。二十九の歳であった。
守覚法親王、五十首歌よませ侍りけるに
春の夜の夢の浮橋とだえして峰にわかるる横雲の空(新古38)
【通釈】春の夜の、浮橋のように頼りない夢が、遂に中途で絶えてしまって、空を見遣れば、横に棚引く雲が峰から別れてゆく。
【語釈】◇夢の浮橋 定家以前に和歌に遣われた確実な前例のない語で、源氏物語五十四帖の最後の巻名であるが、源氏の本文にも見えない語である。「浮橋」とは、水面に筏や舟を並べ、その間に板を渡して橋の代りとしたもの。後撰集に「へだてける人の心の浮橋をあやふきまでもふみみつるかな」と、「憂き端」に掛け、人の心の危うさ・頼りなさの象徴として用いている。「夢の浮橋」は、夢を浮橋に喩えたもので、特に恋に関わらせて読めば、浮橋のようにはかない、夢の中の通い路ということか。但し本居宣長は「とだえをいはむために、夢を夢のうき橋とよみ玉へり」(美濃廼家苞)と言い、他にも単に夢の意とする説が多い。◇とだえして 途絶えて。◇峰にわかるる 峰から離れる。「別るるは、離れるのを、擬人に近い言ひ方にしたもの」(窪田空穂前掲書)。但し峰に当たって二つに別れるの意にも解せよう。◇横雲の空 横雲、すなわち横の方向にたなびく雲がある空。「横雲の風に別るるしののめに…」(山家集)など、横雲は明け方の雲として歌に詠まれることが多い。
【補記】建久九年(1198)夏、守覚法親王に召されて詠んだ五十首歌(御室五十首)。「春の夜の夢」「浮橋」「途絶え」「別る」、また後朝の空を想わせる「横雲の空」と、恋をほのめかす語が連続するのは、偶然ではあり得ない。安東次男『藤原定家』は、源氏物語の「呆気ない終り様」が作者の狙いにあったと見、また文選「高唐賦」の巫山の神女の故事も思い合わされているかと言う。余情妖艶体の代表作。
【他出】御室五十首、自讃歌、百番自歌合、拾遺愚草、新三十六人撰、竹園抄、耕雲口伝、冷泉家和歌秘々口伝、正徹物語、心敬私語、兼載雑談、雲玉集
【参考歌】壬生忠岑「古今集」
風ふけば峰にわかるる白雲のたえてつれなき君が心か
藤原家隆「六百番歌合」「新古今集」
霞たつ末の松山ほのぼのと波にはなるる横雲の空
【主な派生歌】
思ひ寝の夢の浮橋とだえしてさむる枕に消ゆる面影(俊成女)
明けわたる高嶺の花に風過ぎて春にわかるる横雲の空(飛鳥井雅親)
我が涙峰にわかるる横雲の袖はかすとも猶やあまらむ(正徹)
村もみぢ夜の間にそめて横雲の嶺にわかるる松の色かな(後水尾院)
浮橋のとだえ果てざる夢の跡にとどろき残るほととぎすかな(下河辺長流)
はるばると見送るも憂し横雲の峰にわかるる雁の一つら(冷泉為村)
重奉和早率百首 春
ふりにけりたれか
【通釈】庭は古び、花も盛りを過ぎてしまった。誰がわざわざ見ただろう、
【語釈】◇ふりにけり まずは杜若の花が新鮮でなくなった意であろうが、「みぎり」すなわち庭が寂れてしまった意や、春が
【補記】文治五年(1189)三月の重奉和早率百首、題は《杜若》。晩春、見捨てられた閑庭にただひとり深紫に咲く花に対し、呼びかける形で哀れみの情をつよく打ち出している。慈円の『早率百首』の同題詠「紫の色にぞにほふかきつばたゆかりの池もなつかしきまで」の懐古的な気分の反響が窺える。
【主な派生歌】
玉章をたれか砌の荻の葉にあまた結びてわたる雁金(正広)
洞院摂政家百首歌
にほふより春は暮れゆく山吹の花こそ花のなかにつらけれ(続古今167)
【通釈】美しく咲くや否や、春は暮れてゆく。山吹の花こそ、花の中でも人に辛い思いをさせる花である。
【補記】「つらし」は、仕打ちなどがひどく、耐え難い気持をあらわす。花自身が辛い思いをすると解することも無理ではないが、当時の「つらし」の用法としては異例となる。初出は貞永元年(1232)成立の『洞院摂政家百首』、題は「暮春」。
【参考】「狭衣物語」巻一
「花こそ花の」と、とりわきて山吹を取らせたまへる御手つきなどの、世に知らずうつくしきを、人目も知らず、我が身に引き添へまほしく思さるるぞ、いみじきや。
【他出】洞院摂政家百首、拾遺愚草、秋風集、題林愚抄
【参考歌】よみ人しらず「古今和歌六帖」「続後撰集」
にほふより心あだなる花故にのどけき春の風もうらめし
遊客漸辞庭有草、樵夫独往嶺無花
春はいぬ青葉の桜おそき日にとまるかたみの夕ぐれの花(員外)
【通釈】春は去った。青葉になった桜の枝に、暮れなずむ夕暮、花が形見のように咲き残っている。
【語釈】◇遅き日に 遅日に。日が暮れるのが遅い日に。
【補記】建保六年(1218)の韻字四季歌六十四首より。韻字「花」を末尾に詠み込んだ漢詩句と、同じ字を末句に詠み込んだ和歌を並べ詠むという趣向である。漢詩句を訓み下せば「遊客漸く辞す庭に草有り
夏
五月水鶏
槙の戸をたたく
【通釈】曙、槙の戸を叩く音がして、開けてみると人はなく、水鶏の声に騙されたのだが、やはり人が訪れたのかと怪しむばかりに、軒の菖蒲の移り香が濃く立ちこめている。
 |
| 水鶏(ヒクイナ) |
【語釈】◇槙の戸 杉や檜の板で作った粗末な戸。◇水鶏 水辺に棲む小鳥。ツル目クイナ科ヒクイナ。初夏の頃、戸をたたくような声で鳴く。◇あけぼの 曙。「(戸を)開け」る意を掛ける。◇あやめ 菖蒲に動詞「あやむ」(不審に思う)意を掛ける。人かと怪しむ。◇軒のうつり香 軒の菖蒲が戸の周囲に沁み込むように香っていた、ということであろう。
【参考歌】よみ人しらず「拾遺集」
たたくとて宿の妻戸をあけたれば人もこずゑの水鶏なりけり
紫式部「紫式部日記」「新勅撰集」
ただならじとばかりたたく水鶏ゆゑあけてはいかに悔しからまし
【補記】後仁和寺宮花鳥十二首。仲夏五月の鳥として《水鶏》を詠む。鳴き声が戸を叩くように聞こえることから、人が訪れたかと勘違いする趣向は古くからある(参考歌)。定家はこれに軒の菖蒲を結び付け、「うつり香」に恋の趣――明け方まで男を待ち続けた女の風情を香らせた。「一読なだらかに言い続けた歌のように見えながら、三十一文字のうちで聴・視・嗅覚のすべてを言取っている」(安東次男『藤原定家』)。
さみだれの心を
【通釈】あの人が通りすがりの人に託す伝言も絶えて久しい、長く降り続ける五月雨の空よ。
【語釈】◇玉鉾の 道の枕詞。◇道ゆき人 道をゆく人。◇ことづても 伝言も。本人からの直接の連絡が無いので「ことづても」と言う。◇程ふる 「ふる」は「経る」「降る」の掛詞。
【補記】文治五年(1189)春、慈円の『早率露胆百首』に和した百首歌『
【他出】定家八代抄、百番自歌合、拾遺愚草、六華集、題林愚抄
【本歌】柿本人麿「拾遺集」
恋ひ死なば恋ひも死ねとや玉桙(たまぼこ)の道ゆき人にことづてもなき
【主な派生歌】
あまのすむ里のしるべのけぶりだにたえてほどふる五月雨の空(嘉喜門院)
守覚法親王、五十首歌よませ侍りける時
夕暮はいづれの雲のなごりとて花橘に風の吹くらむ(新古247)
【通釈】夕暮れ時になると、庭の花橘に風が吹き、しきりと昔を偲ばせる。一体如何なる雲のなごりを運んで来たというので、これほど昔を懐かしませる香りがするのであろう。
【語釈】◇雲のなごり 雲となった故人を思い出させるもの。火葬の煙は空に昇って雲になるので、空に懐かしく匂う花橘の香を「いづれの雲のなごり」かと疑ったのである。◇花橘 橘の花。「橘」は柑子の類。初夏に白い花をつける。◇風の吹くらむ どの雲(どの故人)のなごりとして、花橘に風が吹き香るのだろうか。「らむ」は疑問詞「いづれ」を承けて用いた推量の助動詞。
【補記】建久九年(1198)夏、守覚法親王家五十首。「花橘」は古今集の歌(参考歌)により懐旧の情と結び付けられたが、橘の香から感じられる懐かしさを由来不明のものとして「いづれの雲のなごり」、すなわちどの故人の思い出のなごりかと不審がってみせたのである。花橘の香から因果を辿って「雲のなごり」を引き出して来たのは鬼気迫る詩魂と言うべきであろう。『常縁口伝和歌』と『美濃廼家苞』は文選「高唐賦」の巫山の神女の故事の心を取ったかと言う。亡き夕顔を夕空の雲に偲ぶ源氏の心情なども重ね合されているのであろうか。いずれにしても極めて隠微な余情の漂う歌で、定家の歌風の一極限を示している。
【他出】御室五十首、拾遺愚草、新三十六人撰、雲玉集
【参考歌】よみ人しらず「古今集」
五月待つ花橘の香をかげば昔の人の袖の香ぞする
「源氏物語・夕顔」
見し人のけぶりを雲とながむれば夕べの空もむつましきかな
「源氏物語・葵」
雨となりしぐるる空の浮雲をいづれの方とわきてながめむ
相模「後拾遺集」
五月雨の空なつかしく匂ふかな花橘に風や吹くらむ
皇后宮大輔百首 夏
あぢさえの下葉にすだく蛍をば四ひらの数の添ふかとぞ見る
【通釈】あじさいの下葉に集まって明滅している蛍の光――それを、ふと、四弁の花が数を増したかと見るのだ。
【語釈】◇あぢさえ あじさい。当時は「あじさゐ」「あじさえ」両様の呼び方があったらしい。◇四ひらの数 四弁の花びらの数。あじさいは四枚の装飾花が多数集まって花序をなす。
【補記】蛍の光をあじさいの花に取り違えるという、夏の黄昏時の一瞬の錯覚を詠む。両者の取り合せは、おそらく俊頼の歌(下記参考歌)のあじさいと月光の取り合せからヒントを得たものか。「…をば…とぞ見る」は古今集の時代からある見立ての常套的文体であるが(下の隆源の歌もその一例)、定家の歌はパターン化された趣向としての見立てではなく、鋭い感覚の集中が引き寄せた幻視といった趣がある。
【参考歌】源俊頼「散木奇歌集」
あぢさゐの花のよひらにもる月を影もさながら折る身ともがな
隆源「堀河百首」
ながれゆく河辺にすだく蛍をばいさごにまじる黄金とぞ見る
【他出】夫木和歌抄、三百六十首和歌、六華和歌集、雲玉集
【主な派生歌】衣笠家良「夫木和歌抄」
飛ぶほたる日かげみえゆく夕暮になほ色まさる庭のあぢさゐ
夏
さゆりばのしられぬ恋もあるものを身よりあまりてゆく蛍かな
【通釈】夏草の繁みにひっそり咲く小百合の花のように人に知られぬ恋もあるというのに、思いの火が身からあふれんばかりに飛んでゆく蛍であるよ。
【語釈】◇さゆり葉 小百合。「葉」は慣習的に付けたもので、この場合花の咲いた小百合を指す。◇こひ 恋。「ひ」に火の意が掛かる。
【補記】建保四年(1216)仙洞百首。「思ひ」「こひ」に火を掛けて、隠れも無き恋心の象徴とされた《蛍》を、万葉本歌の「姫百合の知られぬ恋」と対比した、興趣深い着想の歌。
【他出】万代和歌集
【本歌】大伴坂上郎女「万葉集」「古今和歌六帖」
夏の野の繁みに咲ける姫百合の知られぬ恋は苦しきものぞ
【参考歌】よみ人しらず「後撰集」
つつめども隠れぬものは夏虫の身よりあまれる思ひなりけり
和泉式部「後拾遺集」
物おもへば沢の蛍も我が身よりあくがれいづる魂かとぞみる
一句百首 夏
うつり香の身にしむばかり契るとて扇の風の行へたづねば(員外)
【通釈】移り香が身に沁みるばかりに言い交わすとしても、扇であおぐ風の行方を尋ねれば如何。移り香もやがて消え去るように、あの人の心は私を離れてゆくだろう
【語釈】◇身にしむばかり 身に沁み込むばかりに。情交をほのめかす表現。◇契る 情を交わす。また、固く言い交わす。◇扇 「逢ふ」意が響く。◇尋ねば 尋ねたなら。このあとに「いかならむ」などを略した気持。
【補記】建久元年(1190)六月、定家二十九歳。定められた句を定められた位置に置くというルールのもとで速詠した百首。掲出歌は「扇の風の」を第四句に置いて詠んだ。「扇の風のゆくへ」は扇であおいだ風の行方で、やがて尽きてしまう将来が暗示される。とすれば班婕妤の『怨歌行』の扇が想われずにはいない。なお同じ勒句で慈円が詠んだ「わぎもこと物がたりする夕暮はあふぎの風のうつり香にこそ」はあたかも定家の歌に前句付けした趣である。
【参考】班婕妤「怨詩一首」(→資料編)
新裂斉紈素 鮮潔如霜雪 裁為合歓扇 団団似明月 出入君懐袖 動揺微風発 常恐秋節至 涼風奪炎熱 棄捐篋笥中 恩情中道絶
【他出】夫木和歌抄
題しらず
夕立の雲まの日影はれそめて山のこなたをわたる白鷺(玉葉416)
【通釈】夕立を降らせた雲の切れ間から日が射し、空は晴れてきたところへ、濡れて青々とした山のこちら側を飛んで渡る白鷺よ。
【補記】建久二年(1191)冬、良経邸での「十題百首」の鳥十首。一見写生風の歌であるが、雨で青さを増した夏山と、その前を横切る白鷺の色彩の対比は、漢詩を思わせる構成の仕方である。『拾遺愚草俟後抄』に「かやうの景はいつもある事也」とするのも、漢詩にありふれた趣向として言うのだろう。継いで同書は「よくみたてたる歌也。風景たぐひなし」(傍線引用者)と、構成的な叙景歌として賞賛している。
【他出】拾遺愚草、夫木和歌抄
【参考】梁武帝「夏日臨江」(→資料編)
雲散遠山空 鷺飛林外白
【主な派生歌】
見わたせば秋の夕日のかげはれて色こき山をわたる白鷺(伏見院)
みどりこき日かげの山のはるばるとおのれまがはずわたる白鷺(*徽安門院[風雅])
夕立の雲とびわくる白鷺のつばさにかけてはるる日のかげ(*花園院[風雅])
題しらず
立ちのぼり南のはてに雲はあれど照る日くまなき頃の
【通釈】雲は南の果てに湧き起こっているけれども、太陽の光は隈なく照り渡る、今どきの季節の大空よ。
【語釈】◇たちのぼり 入道雲が湧き上がるさまであろう。◇照る日くまなき 大空のすみずみまで日が照っているさま。
【補記】建久七年(1196)九月十八日、韻歌百二十八首。韻字《
【他出】拾遺愚草、夫木和歌抄
【参考】「白氏文集・青龍寺早夏」(→資料編)
夏雲忽嵯峨
【主な派生歌】
ぬれつつもゆかましものをやすらひて照る日くまなき夕立の宿(肖柏)
閑居百首 夏
松風のひびきも色もひとつにてみどりに落つる谷川の水
【通釈】松風の響も色もひとつになって、碧の滝壺に落ちる谷川の水よ。
【補記】上句では松林を吹き渡ってくる風の音と色を一体として、すなわち聴覚・視覚が融合した共感覚で捉え、下句ではしかも松風の響・色が谷川の水の響・色にも渾然と一体化して「
泉河
泉川かは波きよくさす棹のうたかた夏をおのれ
【通釈】泉川の清らかな川波にさした棹から泡が生まれてははかなく消え、その都度泡自身が夏の暑さを消してゆくかのようだ。
【語釈】◇泉河 山城国の歌枕。木津川の古称。鈴鹿山脈に発し南山城を流れ、当時は巨椋池に注いでいた。◇きよく 泉の縁語。◇さす棹 「さす」は水に突き刺して舟を進める意。◇うたかた夏を 泡が夏を。「第四句の『うたかた』(水泡)の次に小休止を持たせながら、『うたかた夏』(はかない夏)という新語を作り出している」(安東次男『藤原定家』)。◇おのれけちつつ 自分自身で消しながら。
【補記】建永二年(1207)の最勝四天王院名所御障子歌、《泉河》題で季は夏、納涼詠である。「泉河」というその名も清らかな川のイメージを活かしつつ、さす棹によって生まれては消えてゆく水泡に感じる爽涼感を、人がそう感じるとは詠まず、「うたかた夏をおのれけちつつ」と泡自身を主として詠んだのは特異にして新鮮な表現である。合点あり、障子歌に撰入された。
秋
名所の歌たてまつりける時
秋とだに吹きあへぬ風に色かはる生田の杜の露の下草(続後撰248)
【通釈】今が秋だとさえ、はっきり分かる程は吹かない風であるが、生田の杜の下草は、その風に散った露に早くも色が変わり始めている。
【語釈】◇吹きあへぬ 吹きおおせない。「あへぬ」は動詞連用形について「すっかり…し切れない」といった意。◇生田 摂津国八部郡生田。今の神戸市中央区の生田神社あたり。◇露の下草 露に濡れる下草。露は草葉を色づかせるものとされた。
【他出】後鳥羽院御口伝、百番自歌合、拾遺愚草、両卿撰歌合、歌枕名寄
【補記】最勝四天王院名所御障子歌、《生田杜》題で季は秋。揉み揉みと曲折を尽くした定家調で、『百番自歌合』にも採った自信作であった。ところが後鳥羽院はこの歌を障子歌に撰入せず、それゆえに定家から誹謗を受けたらしい。『御口伝』で院は自らの撰を「失錯」と認めつつ、定家歌の本質に関わる厳しい批判を述べている。「まことに、『秋とだに』とうちはじめたるより、『吹きあへぬ風に色かはる』といへる詞つづき、『露の下草』とおける下の句、上下あひかねて優なる歌の本体と見ゆ。かの障子の生田の森の歌(引用者注:障子歌に撰ばれた慈円の『しら露のしばし袖にと思へども生田の杜に秋風ぞふく』を指す)には、まことにまさりてみゆらむ。しかはあれども、如此の失錯自他、いまもいまもあるべき事なり。さればとて、ながきとがになるべきにはあらず。この歌もよくよくみるべし。詞のやさくしくえんなる外は、心もおもかげもいたくはなきなり。森の下にすこしかれたる草のある外は、景気もことわりもなけれども、いひながしたることばつづきのいみじきにてこそあれ」。
【参考歌】清胤「詞花集」
君すまばとはましものを津の国の生田の杜の秋の初風
【主な派生歌】
さればこそ吹きあへぬ風に乱れけりかごとがましきしののをすすき(烏丸光広)
養和のころほひ、百首歌よみ侍りける秋歌
天の原おもへばかはる色もなし秋こそ月の光なりけれ(新勅撰256)
【通釈】思えば、大空にこれと言って変わった徴候もない。天上において、秋という季節の情趣は、ただ月の光がそう感じさせるものだったのだ。
【語釈】◇天の原 天空を原に喩える。高天原への連想もはたらく語。◇かはる色もなし 「色」は《様子、きざし》の意と《色彩》の意を兼ね、「変わった徴候は無い」の意に「変化する色彩は無い」の意を兼ねる。◇秋こそ月の光なりけれ 「月の光こそ秋なりけれ」を逆倒した叙法。漢詩に見られる倒装の技法に拠ったもの。
【補記】「名歌也。『おもへば』といふに心得あり。よくよくおもへば、あまの原にかはる色はなき也。秋は月の光と成りて人に心をつくさするかと也」(『拾遺愚草抄出聞書』)。紅葉によって鮮やかに色を変える地上の秋と、ただ月の光によってそれと知られる天上の秋。尖鋭な対比のうちに情趣の本質を追い詰めてゆく、初期定家に特徴的な詩法が鮮やかに成功した一例。後年、定家自ら新勅撰集に採った程で、相当の自信作であったろう。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、正風体抄、井蛙抄
【参考歌】源道済「道済集」
つねよりも今宵すぐれて見ゆるかな月こそ秋のすがたなりけれ
和泉式部「和泉式部続集」「新勅撰集」
いづれともわかれざりけり春の夜は月こそ花のにほひなりけれ
後京極摂政、左大将に侍りける時、月五十首歌よみ侍りけるによめる
明けばまた秋のなかばも過ぎぬべしかたぶく月の惜しきのみかは(新勅撰261)
【通釈】この夜が明ければ、今年もまた秋の半ばも過ぎてしまうことになる。沈みかけた月が惜しいだけだろうか、残り少なくなった秋もまた惜しいのだ。
【語釈】◇秋のなかば 秋の半分。陰暦八月の十五夜は秋の真中にあたるので、この夜を境に秋は後半に入る。
【補記】建久元年(1190)秋、良経邸での「花月百首」。中秋の名月を惜しむ心が、そのまま過ぎゆく秋を愛惜する心に重なる。「定家卿名歌のうち也」(抄出聞書)。有心優艶の風で、以後の中世歌人に庶幾された。定家自身、新勅撰集や百番自歌合に採り、自信作であったと知れる。藤原信実の『今物語』では藤原家隆が選んだ定家随一の秀逸としている。
【他出】三百六十番歌合、百番自歌合、拾遺愚草、今物語、十訓抄、新三十六人撰、和歌口伝抄、正風体抄、三百六十首歌合、井蛙抄、六華集、耕雲口伝、正徹物語、題林愚抄
月をよみ侍りける
こしかたはみな面影にうかびきぬ行末てらせ秋の夜の月(玉葉688)
【通釈】月を眺めれば、これまで歩んで来た過去の思い出は、皆ありありと目に浮かぶようだ。私がこれから進む道をも照らしておくれ、秋の夜の月よ。
【語釈】◇こし方 過ぎて来た時。「行く末」の対語。
【補記】定家三十四歳の建久六年(1195)秋、良経邸で末の句十句を書き出した上で詠むよう命じられて詠んだ、当座の十首。掲出歌は結句「秋の夜の月」を予め定めて詠んだ歌。月に昔を偲ぶ趣向の歌は多いが、未来の指針をも月に願うと詠んだのである。「行く末てらせ」には、前途への漠然とした不安と、明るい将来を願う心が籠められていよう。
【他出】拾遺愚草、六華集、題林愚抄
【参考歌】和泉式部「拾遺集」
暗きより暗き道にぞ入りぬべきはるかに照らせ山の端の月
元暦のころほひ、賀茂重保人々の歌すすめ侍りて、社頭歌合し侍りけるに、月をよめる
しのべとやしらぬ昔の秋をへておなじ形見にのこる月影(新勅撰1080)
【通釈】私の知らない昔の秋を幾つも経て、今も変わることなく古人の形見として残っている月影よ。そんな遠い昔まで私に偲べと言うのか。
【語釈】◇しのべとや 私に「しらぬ昔」を偲べというのか。月に対する疑問として言う。初句切れ。◇しらぬ昔 私が知らぬところの昔。◇秋をへて 幾秋を経て。主語は月。◇おなじ形見にのこる月影 変わることなく、古人の形見として残っている月。
【補記】「もろともに見し人いかがなりにけむ月は昔に変はらざりけり」(登蓮法師集)など、月に古人を偲ぶ習いがあったが、定家は月の経て来た悠久の時に、そしてまた月を見る人が積み重ねてきた永い心の歴史に思いを馳せて,スケールの大きな構想である。元暦元年(1184)九月、賀茂重保主催の賀茂社歌合に《月》の題で詠んだ歌。定家二十三歳、若年期の有心秀逸。
【他出】拾遺愚草、百番自歌合、井蛙抄、正風体抄
【主な派生歌】
梅の花あかぬ色かもむかしにておなじかたみの春の夜の月(*俊成卿女[新古今])
忍ぶべきことども哀れその時はしらぬ昔の涙そふらん(正徹)
生駒山
生駒山あらしも秋の色にふく手ぞめの糸のよるぞかなしき
【通釈】生駒山では、嵐も紅葉を混ぜて秋の色に吹いている。男に飽きられた河内女が無聊のよなべに
【語釈】◇生駒山 大和・河内国境、今で言えば奈良県と大阪府の境をなす山。◇あらしも 山に吹く強風も。木々の葉も手染めの糸も「秋の色(紅)」なので、「あらしも」と言う。◇秋の色 下句の「染め」との関連で紅の色すなわち紅葉の色が連想される。また男の「飽き」方になった心模様を暗示する。◇手染の糸
【本歌】作者未詳「万葉集」
河内女の手染の糸を繰り返し片糸にあれど絶えむと思へや
【本説】「伊勢物語」二十三段
君があたり見つつを居らん生駒山雲なかくしそ雨は降るとも
【他出】百番自歌合、両卿撰歌合、雲葉和歌集、歌枕名寄、夫木和歌抄、玉葉集、東野州聞書、心敬私語、歌林良材、六家抄
【補記】建保三年(1215)十月、順徳院の命によって詠進された百首歌、「建保名所百首」。題の「伊駒山」から伊勢物語の河内高安の里の女へ、さらに万葉集の「河内女の手染の糸」へと繋げた連想で、これを紅葉を吹き散らす生駒の山風にかかわらせて、男に飽きられた女の秋夜の悲しみを詠んだ。想の展開を仮に図式化すれば次のようになろう。
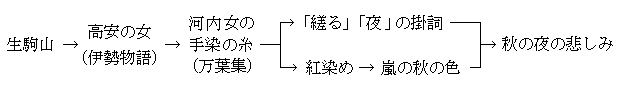
もとより実際の創作過程がこのように整然としていることはあり得ないが、定家の発想法の一例として参考に示すのみである。『名所百首哥之時与家隆卿内談事』には自らの手の内を次のように明かしている。「『手染の糸』は
【主な派生歌】
いこま山て染の糸の中たえてみじかき色にちる木の葉かな(正徹)
水無瀬殿にて秋歌よみ侍りけるに
夕づく日むかひの岡の薄紅葉まだきさびしき秋の色かな(玉葉769)
【通釈】夕日が射す向かいの岡の薄紅葉の色は、早くも寂しさを感じさせる秋の趣であるよ。
【語釈】◇夕づく日 夕日。万葉集巻七1294番歌の「
【補記】薄紅葉に夕日が射してひととき色を濃くし、一足早い深秋の寂しさを感じている。新しい景趣の発見がある。「夕の景気は、初秋より、暮秋などのごとくさびしきと也」(抄出聞書)。建保二年(1214)八月二十七日、水無瀬馬場殿で講ぜられた撰歌合(散逸)での秋十首歌、第六首。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、定家家隆両卿撰歌合、万代集、雲葉集、歌枕名寄
百首歌の中に
おのづから秋のあはれを身につけてかへる
【通釈】自然と秋の情趣を身につけて、山人が帰りがてら小坂で口吟む夕暮の歌よ。
【語釈】◇おのづから 意識せずして。無意識のうちに。◇秋のあはれ 秋の悲しげなおもむき。◇身につけて 習得して。◇小坂 山の坂道を意味する普通名詞か。『堀河百首』藤原公実詠「ますらをが小坂の道も跡たえて雪ふりにけり衣かせ山」によれば、鹿背山(山城の歌枕)の山道の名か。◇夕暮の歌 日暮れ時、仕事を終えての帰り道に口吟む歌。定家がのち関白左大臣家百首で「山人の歌ひて帰る夕べより錦をいそぐ峰のもみぢ葉」と詠んでいるとおり、歌い手は山人である。
【補記】建保六年(1218)の韻字四季歌百首、秋。『拾遺愚草員外』に「建保五年の事にや、内裏に此韻の字を人々たまはりて詩をつくると伝へ聞きて、つれづれなりしかば歌にもなりなむやと、試みにかきならべて見侍りしいたづらごとを、思ひいでて書きつく」と添書きがある。韻字を賜り、それによって漢詩句を作り、和歌を併せるという試みであった。掲出歌に添えた詩句は「寞閨砧杵向霜怨、酔客徒誇白綺歌」(寞閨(まくけい)砧杵(ちんしよ)霜に向つて怨む、酔客徒(いたづら)に誇る白綺(はくき)の歌)。霜夜、女が独り閨で怨むように砧をうつ一方、戸外では酒に酔った男が大声で白綺の歌をうたう、という景。掲出歌は詩句の「酔客」を山人に転じ、その歌声に意識せぬ秋の風雅を聴き取っている。海人や山人といった、当時下層と見られた人々の行状に「おのづから」の「あはれ」を見る態度は、新古今時代に好まれた風流であった。(この歌、諸注釈書・評釈書、解釈を誤っている。)
【他出】拾遺愚草員外、夫木和歌抄
【参考】李白「陪族叔刑部侍郎曄及中書賈舍人至游洞庭 其四」(→資料編)
洞庭湖西秋月輝 瀟湘江北早鴻飛 酔客満船歌白苧 不知霜露入秋衣(洞庭湖の西秋月輝き 瀟湘江の北早く鴻飛ぶ 酔客船に満ち白苧を歌ふ 知らず霜露の秋衣に入るを)
紀貫之「貫之集」
声たかくあそぶなるかな足曳の山人いまぞかへるべらなる
九条良経「秋篠月清集」(先後関係は不明)
おのづから治まれる世や聞こゆらむはかなくすさむ山人の歌
【主な派生歌】
山人のかへる小坂の道のべに折りやすげなる下わらびかな(藤原知家)
越えわぶる小坂の道の雪どけにかへるさ苦し小野の里人(衣笠家良)
山人のかへる小坂の春風もなほ身におはぬ梅が香ぞする(二条為明)
夜さへにつま木こるらしますらをが山ぢわけ入る夕ぐれの歌(花山院師兼)
帰るさを月待ちてとややすむらん小坂にうたふ山人のこゑ(中院通村)
西行法師すすめて、百首歌よませ侍りけるに
見渡せば花も紅葉もなかりけり浦の苫屋の秋の夕暮(新古363)
【通釈】あたりを見渡してみると、花も紅葉もないのだった。海辺の苫屋があるばかりの秋の夕暮よ。
【語釈】◇花も紅葉も 美しい色彩の代表として列挙する。◇苫屋(とまや) 菅や萱などの草で編んだ薦で葺いた小屋。ここは漁師小屋。
【補記】文治二年(1186)、西行勧進の「二見浦百首」。今ここには現前しないもの(花と紅葉)を言うことで、今ここにあるもの(浦の苫屋の秋の夕暮)の趣意を深めるといった作歌法はしばしば定家の試みたところで、同じ頃の作では「み吉野も花見し春のけしきかは時雨るる秋の夕暮の空」(閑居百首)などがある。新古今集秋に「秋の夕暮」の結句が共通する寂蓮の「さびしさはその色としも…」、西行の「心なき身にもあはれは…」と並べられ、合せて「三夕の歌」と称する。
【参考】「源氏物語・明石」
いとさしも聞こえぬ物の音だにをりからこそはまさるものなるを、はるばると物のとどこほりなき海づらなるに、なかなか、春秋の花紅葉の盛りなるよりは、ただそこはかとなう茂れる蔭どもなまめかしきに、水鶏のうちたたきたるは、誰が門さして、とあはれにおぼゆ。
【他出】拾遺愚草、三百六十番歌合、御裳濯集、六華集、新三十六人撰
【主な派生詩歌】
見わたせば心は色もなかりけり柳さくらのはるの曙(烏丸光弘)
ながめばや花も紅葉もわすれ草岸に生ふてふ住吉のうら(〃)
「
家に月五十首歌よませ侍りける時
さむしろや待つ夜の秋の風ふけて月をかたしく宇治の橋姫(新古420)
【通釈】冷たい莚――そこに臥して待つ夜の秋風は、更けるにつれて吹きつのり、月光を敷いて独り寝する宇治の橋姫よ。
【語釈】◇さむしろ 莚。寝る時に用いる敷物。「さ」は習慣的に付ける接頭語。「寒(さむ)」の意が響く。◇待つ夜の 男を待つ夜の。◇秋の風ふけて 「秋」には「飽き」の意が響く。「風ふけて」は「夜更け」と言うことからの造語。夜が更けるにつれて風が吹きつのることを言う。◇月をかたしく 月光が映る敷物に横たわる。「かたしく」とは、自分の衣だけを敷いて独り寝すること。共寝の際は、二人の衣を敷いて寝るという風習があった。◇宇治の橋姫 下記本歌から借りた語。宇治橋の守り神かという(『奥義抄』)。対岸の「離宮」という男神が橋姫のもとへ毎夜通ったなどの伝説があったが、定家は古歌に付会した後世の作り話として退けている(『顕註密勘抄』)。
【補記】建久元年(1190)秋、良経邸での「花月百首」。男の立場から自分を待つ「宇治の橋姫」を思い遣った古今集の本歌を、秋風と月光という季節の情趣の中に移し、眼前にするかのごときイメージとして描き出して見せた。
【他出】玄玉集、百番自歌合(前稿本)、拾遺愚草、時代不同歌合(初撰本)、歌枕名寄、六華和歌集、耕雲口伝、六家抄
(初句を「さむしろに」として載せる本もある。)
【本歌】よみ人しらず「古今集」
さむしろに衣かたしき今宵もや我を待つらむ宇治の橋姫
【主な派生歌】
ふけゆけば鹿に一夜の宿かりて月をかたしく小野の草ぶし(守覚法親王)
はれくもり時雨ふるやの板間あらみ月をかたしく夜はのさむしろ(後鳥羽院)
かり庵の月をかたしく袖のうへに稲葉が末の露ぞみだるる(順徳院)
秋をへて都のそらに思ひこし月をかたしくさよの中山(肖柏)
ふし待の昨日の名残そのままに月をかたしく床のさむしろ(細川幽斎)
百首歌たてまつりし時
ひとりぬる山鳥の尾のしだり尾に霜おきまよふ床の月影(新古487)
【通釈】独りで寝ている山鳥の尾、その垂れ下がった尾に、霜が置いているのかと迷うばかりに、しらじらと床に射す月影よ。
【語釈】◇山鳥 山に住む、雉によく似た鳥。雌雄は峰を隔てて寝ると信じられたため、独り寝の例に引かれて歌に詠まれた。雄は羽毛が赤銅色で美しく、横縞模様の入った長い尾羽を持つ。◇しだり尾 垂れ下がった尾。本歌から取った語。◇霜おきまよふ 霜が「おきまよふ」との表現は定家自身『韻歌百二十八首』および『正治二年院百首』に前例があり、いずれも「霜が迷うように置く」ほどの意で用いている。しかし月影との紛らわしさに主眼がある掲出歌では、「霜が置いたのかと見紛う」、すなわち霜が現実とも幻覚とも区別がつかないというニュアンスを帯びる。
【補記】恋から秋への本歌取り。本歌では序詞の中に喩として用いられているに過ぎない(圧倒的な存在感は放つが)「山鳥」、その「しだり尾」を、定家は言わば一首の主役に据え、晩秋の夜の霜と見紛う月光を浴びた幻像として描き出した。「床」はまずは鳥の寝床(巣)と読めるが、もとより人の寝る「床」を連想させずにはいず、独り寝する人の姿態と閨怨が余情として喚起される仕組みになっている。千五百番歌合、七百五十五番右負。当番は定家の自判で、「『山鳥のしだり尾』『とこの月かげ』など、霜夜のながきおもひ、詞たらぬところおほく、心もわかれがたく侍るめり」。もとより謙辞で、本歌の「ながながし夜を…」を思い合わせることにより「霜夜のながきおもひ」はひしひしと伝わるであろう。
【他出】千五百番歌合、定家八代抄、百番自歌合、拾遺愚草、時代不同歌合、六華集
【本歌】柿本人麿「拾遺集」
あしびきの山鳥の尾のしだり尾のながながし夜をひとりかも寝む
【参考】「白氏文集・秋夕」(→資料編)
葉声落如雨 月色白似霜 夜深方独臥 誰為払塵牀
内裏詩歌合
夕づく日うつる木の葉や時雨にしさざ浪そむる秋の浦風(百番自歌合)
【通釈】夕日が映って美しく照る木の葉は、時雨が降ったさざ波が染めているのだろうか。秋の入江を吹く風に、湖の水面にはさざ波が立つ。
【語釈】◇ ◇ ◇
【補記】建暦二年(1212)の内裏詩歌合。拾遺愚草にも同員外にも見えない。
【参考歌】
【主な派生歌】
建保五年四月庚申、秋朝
小倉山しぐるるころの朝な朝な昨日はうすき四方のもみぢ葉(続後撰418)
【通釈】小倉山に時雨が降る頃、周囲の紅葉は朝ごとに濃くなってゆき、昨日見た美しい色も、これに比べれば薄かったのだと気づく。
【語釈】◇昨日はうすき 今朝に比べれば、昨日の紅葉は色が薄い。
【補記】「昨日もいろこきもみぢなれ共、けふにあはすれば薄きと也」(抄出聞書)。昨日の美しかった色の記憶も、今朝見た紅葉によって薄れてしまうという驚きを婉曲に詠んだのであろう。さりげなくも優美な詞の運びに、紅葉の深まりに対する日々の密かな感動が沁み渡って感じられる。定家仮託書『愚見抄』は「遠白体」の秀歌例に挙げ、『耕雲口伝』は「春の夜の夢の浮橋…」等と共に「上手の風骨をみて幽意微詞おもしろし」としつつ、初心者が真似れば「邪路」に落ちる歌として引く。確かに「昨日はうすき」など、浅薄に真似れば嫌味な言回しを生むだけで、学ぶには怖い詞であろう。建保五年(1217)四月十四日、庚申待に際して後鳥羽院が催した庚申五首(既出)。定家五十六歳。
【他出】続歌仙落書、百番自歌合(前稿本)、時代不同歌合、両卿撰歌合、万代集、和歌口伝、歌枕名寄、愚見抄、三百六十首和歌、六華集、耕雲口伝
【参考歌】恵慶「拾遺集」
昨日よりけふはまされる紅葉ばのあすの色をば見でややみなむ
西行「山家集」「新勅撰集」
かぎりあればいかがは色のまさるべき飽かずしぐるる小倉山かな
【主な派生歌】
朝な朝な時雨るる頃の山風に木のは降りそふ神なびのもり(衣笠家良)
霧たちてしぐるるころの朝な朝な山のもみぢぞ色まさりゆく(伏見院)
後京極摂政太政大臣、左大将に侍りける時、家に百首歌合し侍りけるに、ははそをよみ侍りける
時わかぬ波さへ色にいづみ川ははその
【通釈】季節によって違いはないはずの波さえ、秋が色に顕れている泉川よ。上流の柞の森に嵐が吹いているらしい。
 |
【語釈】◇時わかぬ 季節を区別しない。◇いづみ川 木津川の古称。鈴鹿山脈に発し南山城を流れ、当時は巨椋池に注いでいた。「(色に)出づ」意を掛ける。◇ははそ コナラ・クヌギなど、里や丘陵によく見られる落葉高木の類の総称。晩秋、赤褐色や黄褐色、濃淡さまざまに色づく。
【補記】「浪の花にぞ秋なかりける」と詠んだ康秀の歌の、詞は採らずに唱和した体の本歌取りである。六百番歌合、秋下十二番左勝。判者の俊成は「『浪さへ色に』などいへるすがたは優に侍り」と賞しつつ、「はての句の『らし』や、上句にことに
【他出】新古今集、定家八代抄、百番自歌合、歌枕名寄、六華集
【本歌】文屋康秀「古今集」
草も木も色かはれどもわたつうみの浪の花にぞ秋なかりける
【主な派生歌】
打ちいづる浪さへ色にうつろひぬ井手の川瀬の山吹の比(永福門院)
眺望
吹きはらふ紅葉のうへの霧はれて峯たしかなる嵐山かな
【通釈】嵐が吹き払い、紅葉の上にかかっていた霧が晴れて、顕れた峰――その高嶺がくっきりと確かに望まれる嵐山であるよ。
【語釈】◇たしかなる しっかりと揺るぎない。◇嵐山 山城国の歌枕。渡月橋の西の山。桜・紅葉の名所。
【参考歌】宜秋門院丹後「新古今集」
吹きはらふ嵐ののちの高嶺より木の葉くもらで月や出づらむ
【補記】貞永元年(1232)四月、関白左大臣家百首。題「眺望」。『定家十体』に言うところの「長高様(丈高い体)」にして「見様(目に見えるような景気の体)」の歌だろう。一見客観的な詠みぶりであるが、「峰たしかなる」はむしろ主観をつよく出した把握であり、歌人の充実した心の張りが感じられる。「『吹きはらふ』と、大胆に初句切の気味に詠み起し、『峯たしかなる嵐山かな』と言据えたところは、やはりしたたかな表現だろう。存分に眺め抜いた景を以て、即ち、耐え抜いた心の表現としている。…これは、数ある定家の歌のなかでも、心にのこる佳い歌である」(安東次男『藤原定家』)。
【他出】夫木和歌抄
建暦三年九月十三夜内裏歌合、暮山松
秋はいぬ夕日かくれぬ峰の松四方の木の葉の後もあひ見む
【通釈】秋は去ってしまった。夕日は隠れてしまった。だが峰の松よ、四方の木の葉が散った後も、変わらずおまえに
【語釈】◇夕日かくれぬ 夕日が沈んでしまった。「夕日がくれの」とする本が多い(補記・校異参照)。◇木の葉ののち 木の葉が散ってしまったのち。
【補記】建暦三年(1213)九月十三夜、順徳天皇が仙洞御所で催した三題各五番合計一五番の歌合、十三番左(勝負付・判無し)。題《暮山松》は前例未見。定家は秋の最後の夕暮、峰の松に対して再会を契り、変わることのない松に対する慕情を詠ったのであろう。なお、第二句は【他出】に挙げた諸書、新編国歌大観で見る限り全て「夕日がくれの」としている。但し新編国歌大観『歌合建暦三年九月十三夜』では「夕日かくれぬ」。
【他出】百番自歌合、両卿撰歌合、雲葉和歌集、井蛙抄、六家抄
【本歌】作者未詳「万葉集」巻七
山高み夕日隠れぬ浅茅原後見むために標結はましを
二見浦百首 秋
ただいまの野原をおのがものと見て心づよくもかへる秋かな
【通釈】ただいま眼前の野原の景色を、自分がもたらしたものと見おさめて、心残りも見せずに去ってゆく秋であるよ。
【語釈】◇ただいま 「今」を強調した言い方。まさに今。ほかならぬ今。「今」とは秋の終末(九月尽)。◇おのがもの 自分がもたらしたもの。用例「桜花木のもとごとに吹きためておのが物とや風の見るらむ」(上西門院兵衛『久安百首』)。◇心づよくも 心の弱みも見せず。気丈にも。
【補記】「草の葉にはかなく消ゆる露をしも形見におきて秋のゆくらん」(源師俊『金葉集』)など、去りゆく秋を擬人化する趣向は古歌に少なくないが、「心づよくも」という捉え方は未曾有である。人に豊かな収穫をもたらし、明月に光を添え、美しい野の花や紅葉を見せてくれた秋も、最後はうら寂しく枯れた野末を去ってゆく。そんな《秋》という季節への、これは惜別の歌というよりも讃美の歌ではないだろうか。「ただいまの」「おのがものと」「心づよくも」といった力強い詞の繰り返しがそう思わせるのである。
【他出】百番自歌合、御裳濯和歌集、拾遺風体和歌集、夫木和歌抄
【参考歌】殷富門院大輔「殷富門院大輔集」(先後関係は不明)
うき世とは思ひながらにすむものを心づよくも帰る雁かな
冬
惟明親王家の十五首歌に
神無月暮れやすき日の色なれば霜の下葉に風もたまらず(続拾遺405)
【通釈】神無月となり、陽射は早々に暮れがちなおもむきなので、草木の下葉は霜枯れしてしまって、風が吹き留まることもない。
【語釈】◇神無月(かみなづき) 陰暦十月、初冬。この月、日本中の神々が出雲大社に結集して不在となるため「神無月」という――という語源説は平安後期の文献より見え始める説。定家の時代には信じられていたようである。◇暮れやすき日の色 冬の陽射しの暮れやすいおもむき。この「色」は色彩の意よりも、「おもむき」「気色」の意に近い。◇霜の下葉 霜枯れの下葉。朝、草木の下葉に付いた霜が、日の短さゆえなかなか融けず、葉を枯らしてしまう。◇風もたまらず 多くの葉が散ったため、下葉がもはや風を吹き留めない、ということ。
【補記】神が去ってしまった後の頼りないような、虚ろなような気分が、「暮れやすき日の色」、「風もたまらず」といった語句にまで染み渡っているように感じられる。『拾遺愚草』の詞書は「三宮十五首、冬歌」。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、題林愚抄
【参考歌】和泉式部「和泉式部集」
夏のせし蓬のかども霜枯れてむぐらの下は風もたまらず
藤原公実「堀河百首」
霜枯れの草の戸ざしのあだなれば賤の竹がき風もたまらず
【主な派生歌】
今日よりは冬たつ空とおもふにも暮れやすき日の惜しき老かな(正徹)
千五百番歌合に
花すすき草の袂も朽ちはてぬなれて別れし秋を恋ふとて(新続古今648)
【通釈】花薄の袂も朽ち果ててしまった。馴染んだあと別れた秋を恋い慕うというので。
【語釈】◇花すすき 穂の出た
【他出】千五百番歌合、百番自歌合、両卿撰歌合、六家抄
【補記】永い和歌の歴史において主流をなした詠法は、自然に寄せて人情を詠むというものであったが、定家は掲出歌においてこの態度を逆転し、人情(この場合恋)に寄せて自然の景を詠む趣向に挑んでいる。「こころなき花すすきを心あるやうにいひて、『なれて別し秋をこふとて』など、尤さもありつべくいひなしたる、奇妙の作為にや」(俟後抄)。この「奇妙」はすぐれて面白みのある趣を賞賛する語である。歌合九百十番、右持。判者季経は「『草の袂もくちはてぬ馴れて別れし秋を恋ふとて』といへる、又やさしく侍れば、いづれと思ひかね侍りぬ」。
【本歌】在原棟梁「古今集」
秋の野の草のたもとか花すすき穂に出でてまねく袖と見ゆらむ
南窓背灯坐、風霰暗紛紛
風のうへに星のひかりは冴えながらわざともふらぬ霰をぞ聞く(員外)
【通釈】風が吹く空の上に星の光は冴えながら、ことさら目に立つほどもなく霰が降っている――そのかすかな音に耳を傾ける。
【語釈】◇わざともふらぬ ことさら目に立つ程にも降らない。
【補記】建保六年(1218)、慈円に勧められて詠んだ、白居易(白楽天)の詩文集『
【他出】夫木和歌抄
冬雨をよめる
冴えくらす都は雪もまじらねど山の端しろき夕ぐれの雨(続古今639)
【通釈】冷え冷えとしたまま日が暮れた都では、雪も交えずに雨が降っているけれど、山では雪が積もったのであろう、稜線が白い。
【語釈】◇さえくらす 冴え暮らす。◇山の端 山の空との境目をなすあたり。稜線。
【補記】前大僧正御房四季題の百首歌。
【他出】拾遺愚草員外、三百六十首和歌、六華集、題林愚抄
【主な派生歌】
雲くらきかた空晴れて山ぎはの日影にしろき夕立の雨(正徹)
百首歌の中に
かきくらす軒端の空に数みえてながめもあへずおつるしら雪(玉葉979)
【通釈】にわかに掻き曇り、いちめん暗くなった軒先の空に、いくつと数えられるほど舞い散るが、じっと見守っていることもかなわず、たちまち地に落ちる白雪よ。
【語釈】◇ながめもあへず 眺めも敢へず。空に舞うさまを充分眺めることができないうちに雪が地上に落ちてしまう、ということ。「敢へず」は動詞連用形に付いて「…し切れない」「すっかり…できない」などの意。
【補記】舞い散る雪片の美しさを堪能しようとして叶わないもどかしさ。雪の降り始めのさまと、それに興を覚える視線のうごきを、みごとに捉えている。建久二年(1191)十二月、九条良経に詠進した十題百首の天部十首より。定家三十歳。
【参考歌】藤原俊成「千載集」
石ばしる水の白玉数見えて清滝川にすめる月影
百首歌たてまつりし時
駒とめて袖うちはらふかげもなし佐野のわたりの雪の夕暮(新古671)
【通釈】馬を停めて、袖に積もった雪を払う物陰もありはしない。佐野の渡し場の雪降る夕暮どきよ。
【語釈】◇佐野のわたり 万葉集に詠まれた「狭野」は紀伊国であるが、中世の歌学書などは「佐野」を大和国の歌枕とする。「わたり」は渡し場。「あたり」の意とする説もあるが、河原や海辺の茫漠とした感じが一首の感興には相応しかろう。◇雪の夕暮 雪降る夕暮。治承三年(1179)の『右大臣家歌合』(主催は九条兼実)で寂蓮が「ふりそむる今朝だに人の待たれつる深山の里の雪の夕暮」と詠んだ先例がある(新古今集に入集)。但し藤原為家の『詠歌一体』に「雪の夕暮」を「ぬしぬしある事なればよむべからず」として制の詞としたのは、定家の歌あってのことである。
【補記】正治初度百首。主観性を強く出して旅情を歌った本歌を、定家はより客観的に、一幅の画のようにしつらえてみせた。本歌の雨を雪に替えたことも本歌取りの技法として賞賛されて来たところである。「本歌の雨を雪にとりかへてよめり。いへのなきところなれば、たちよるべきかげだになきと、雪の夕暮をかなしぶ也」(抄出聞書)。安東次男『藤原定家』は、源氏物語「東屋」の巻に源氏が「佐野のわたりに家もあらなくに」と口ずさむ場面が定家の発想にあったと見、「『さののわたり』の旅人は、二人の男の愛に揺れる浮舟を雪中の宇治に尋ねる匂宮であり、同時にまた、仏弟子の本意を遂げた浮舟を諦めきれぬ薫の姿だろう」と言う。
【他出】自讃歌、定家八代抄、続歌仙落書、百番自歌合、拾遺愚草、別本和漢兼作集、和歌口伝、歌枕名寄、井蛙抄、六華集、了俊一子伝、了俊歌学書、落書露顕、歌林良材
【本歌】長奥麻呂「万葉集」
苦しくも降り来る雨かみわの崎狭野の渡りに家もあらなくに
【参考】「源氏物語・東屋」
佐野のわたりに家もあらなくに、など口ずさびて、里びたる簀子の端つ方にゐ給へり。
摂政太政大臣、大納言に侍りける時、山家雪といふことをよませ侍りけるに
待つ人の麓の道はたえぬらむ軒端の杉に雪おもるなり(新古672)
【通釈】待つ人が通って来る麓の道は行き止まりになってしまったのだろう。我が家の軒端の杉に雪が重みを増しているようだ。
【語釈】◇待つ人 私の待つ人。題「山家雪」からすると、山里に籠り住む人が友の来訪を待っている風情。◇おもるなり 重くなっているようだ。この「なり」はいわゆる伝聞推定の助動詞。ここでは、「軒端の杉」の枝が立てる音などから、雪の重みを感じ取って推量する気持。
【補記】詞書の「摂政太政大臣」は九条良経。『拾遺愚草』によれば文治五年(1189)十二月の作。
【他出】定家八代抄、百番自歌合、拾遺愚草、愚秘抄、落書露顕、題林愚抄
(第二句を「麓の道や」とする本もある。)
【参考歌】よみ人しらず「古今集」
わが庵は三輪の山もと恋しくはとぶらひ来ませ杉たてる門
九条良経「秋篠月清集」(掲出歌との先後関係は未詳)
野中なる葦のまろ屋に秋すぎてかたぶく軒に雪おもるなり
【主な派生歌】
朝夕に通ふ山人みちたえて峰のときは木雪おもるなり(道助親王)
友と聞く深山の嵐おともなし軒端の杉に雪つもる頃(花山院長親)
荻の葉に風も音せぬさ夜ふけて月に千草の露おもるなり(正徹)
つもりえぬ程はむもれてしだり行く軒端の杉に雪ぞこぼるる(姉小路基綱)
侵頭霜色白過半、憶子鶴声絃第三
白妙のいろはひとつに身に沁めど雪月花のをりふしは見つ
【通釈】
【語釈】◇ ◇ ◇
【補記】
【参考歌】
【主な派生歌】
歳暮時昏思往事、当初幽襟尚難堪
おもひいづる雪ふる年よ己のみ玉きはる世の憂きに堪へたる
【通釈】
【語釈】◇ ◇ ◇
【補記】
【参考歌】
【主な派生歌】
恋
初恋のこころをよめる
昨日けふ雲のはたてにながむとて見もせぬ人の思ひやは知る(風雅964)
【通釈】恋に落ちたここ数日は、日の沈んだ山の彼方、旗手のように棚引く雲を眺めては物思いに耽ってしまう――そんなことをしたところで、逢ったとも言えないような疎い人の胸の内が知れようか。そうは分かっていても…。
 |
| 「雲のはたて」(筋雲の先端) |
【語釈】◇雲のはたて 雲の、幡の先端のように風に靡く処。藤原定家著と伝わる『僻案抄』に「日のいりぬる山に、ひかりのすぢすぢたちのぼりたるやうに見ゆる雲の、はたの手にも似たるをいふ也」とあり、中世歌学では「雲の旗手」と解するのが普通だったようである。「旗手」は「長旗の末端の風になびきひるがえる所」(広辞苑第五版)。◇見もせぬ人 業平の本歌(下記参照)より、「見ずもあらず見もせぬ人」の意になる。
【補記】恋を自覚して間もない頃の心を詠む。夕暮れ時に眺める「雲の旗手」は乱れ靡く恋心の象徴でもあろう。建保四年(1216)院百首、恋十五首の第二首。『拾遺愚草』は第二句「雲のはたてを」。
【本歌】読人しらず「古今集」
夕暮は雲のはたてに物ぞ思ふ天つ空なる人を恋ふとて
在原業平「古今集」
見ずもあらず見もせぬ人の恋しくはあやなく今日やながめくらさむ
春のころ物申しそめける人の梅花を折りてさしおかせ侍りける、又の年おなじ所にてよみ侍りける
心からあくがれそめし花の香になほ物思ふ春の曙(続拾遺979)
【通釈】自分の心から惹かれ始めた花の香ではあるけれど、やはり物憂い思いに耽ってしまうのだ、春の曙にその匂いをかげば。
【補記】交際を始めたばかりの頃、恋人が梅の花を折って逢瀬の場所に飾っていた。翌年、それを思い出し、同じ所で詠んだという歌。言うまでもなく梅の花に恋人を暗示している。同じ時のもう一首は「我のみや後もしのばむ梅の花にほふ軒ばの春の夜の月」。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、万代集、和漢兼作集
【主な派生歌】
わすれずよあくがれそめし山里のその夜の雨の音のはげしさ(*宗尊親王)
建保百首歌たてまつりける時
初雁のとわたる風のたよりにもあらぬ思ひを誰につたへむ(続拾遺1004)
【通釈】初雁が天の
【語釈】◇とわたる 天の通り路を渡る。参考歌では天の川の
【補記】建保四年(1216)の院百首、定家五十五歳。題は不掲出であるが、「不被知人恋」、人に知られぬ恋の心であろう。見所はやはり本歌取りの手法にあり、古歌の懐かしい調べが情趣を深めている。
【他出】百番自歌合、続拾遺集
【本歌】在原元方「古今集」
たよりにもあらぬ思ひのあやしきは心を人につくるなりけり
【参考歌】藤原菅根「古今集」
秋風に声をほにあげて来る舟はあまのと渡る雁にぞありける
洞院摂政家百首歌に、忍恋
うへしげる垣根がくれの小笹原しられぬ恋はうきふしもなし(続後拾遺632)
【通釈】上の方に草葉が茂っている垣根に隠れて人目に触れない笹叢のように、人に知られぬ恋は辛そうなふしも見えないが、心の底は多くの憂さを隠している。
【語釈】◇を笹原 笹の一群。この「原」は何らかの植物の固まって生えている場所を指し、広がりのある空間を含意しない。◇うきふし 憂き節。「ふし」は笹の縁語。
【補記】貞永元年(1232)の洞院摂政家百首(関白左大臣家百首)、「忍恋」題五首の第三首。定家七十一歳。初句を「植ゑしげる」とする本もある。
【他出】百番自歌合、洞院摂政家百首、拾遺愚草、万代集、夫木和歌抄、題林愚抄
【参考歌】大伴坂上郎女「万葉集」「古今和歌六帖」
夏の野の繁みに咲ける姫百合の知られぬ恋は苦しきものぞ
和泉式部「和泉式部続集」
今はただそよそのことと思ひでて忘るばかりのうきふしもなし
家に百首歌合し侍りけるに、祈恋といへる心を
年もへぬ祈る契りははつせ山をのへの鐘のよその夕暮(新古1142)
【通釈】何年も経った。長谷観音に祈る恋の成就の願掛けは、これ以上続ける甲斐もない。折から山上の鐘が入相を告げるけれど、私にはもはや無縁な夕暮時であるよ。
 |
| 長谷寺 鐘楼 |
【語釈】◇年もへぬ 願掛けをして何年も経った。◇祈るちぎり 恋の成就の祈願。◇はつせ山 初瀬山。奈良県桜井市。長谷寺、特に本尊の十一面観音の換喩として山の名を言う。「はつせ」に「果つ」(限界に至る)意を掛ける。◇をのへの鐘 峰の上にある寺から響く、入相の鐘。◇よその夕暮 (入相を告げる鐘が)自分にとっては無縁な夕暮。夕暮は恋人たちが逢う時であり、「自分以外の他の人々は逢瀬を楽しむ夕暮時」といった意も匂わせる。余情多い表現。
【参考歌】源俊頼「千載集」
憂かりける人を初瀬の山おろしよはげしかれとは祈らぬものを
【補記】恋の成就に霊験があるとされた長谷観音を詠むに際し、「はつせ山」に掛けて願掛けも「果つ」とし、また長谷寺の名物であった「をのへの鐘」に寄せて、夕暮時の孤独に繋げたのであろう。絶望や怨恨、憎悪といった心情を一切秘め隠した結句「よその夕暮」に極まる凄艶は、定家の歌の中でも著しく妖しい魅力を放ち、多くの評家の賛辞を得てきた一首である。『六百番歌合』恋二、五番左勝。右は家隆の「朽ちはつる袖のためしとなりねとや人をうきたの杜のしめ縄」。俊成は判じて「両首共に風体はよろしく侍るを、左は心にこめて詞たしかならぬにや」と、余情を籠めようとしたあまり詞が不明瞭ではないかと難じたが、家隆の歌にも難があるとして、定家に勝を付けた。
【他出】六百番歌合、自讃歌、定家八代抄、百番自歌合、拾遺愚草、歌枕名寄、六華集、正徹物語、心敬私語、題林愚抄
【主な派生歌】
初瀬山谷吹きのぼる川風に鐘は雲ゐのよそのゆふぐれ(正広)
建保六年内裏歌合、恋歌
来ぬ人をまつほの浦の夕なぎに焼くや藻塩の身もこがれつつ(新勅撰849)〔百〕
【通釈】なかなか来ない人を待つ私は、松帆の浦の夕凪の頃に焼く藻塩ではないが、身も焦がれるような思いで過ごしている。
【語釈】◇まつほの浦 松帆の浦。下記万葉歌に由来する歌枕。淡路島北端。「まつ」に「待つ」「松」を掛ける。◇藻塩(もしほ) 海水を掛けた海草を焼いて作る塩。
【補記】詞書に「建保六年」とあるのは誤りで、建保四年(1216)が正しい。順徳天皇の内裏で開催された歌合に出詠された作。九十一番右勝。
【他出】建保四年内裏歌合、拾遺愚草、定家自歌合、定家家隆両卿撰歌合、百人一首、新三十六人撰、正風体抄
【本歌】笠金村「万葉集」巻六
名寸隅の 船瀬ゆ見ゆる 淡路島 松帆の浦に 朝凪に 玉藻刈りつつ 夕凪に 藻塩焼きつつ 海をとめ ありとは聞けど 見に行かむ 由のなければ ますらをの 心は無しに 手弱女の 思ひたわみて たもとほり 吾はそ恋ふる 船楫を無み
【主な派生歌】
須磨の蜑は心とくもる月ぞ見るやくやもしほのなびく煙に(作者不詳[菊葉集])
藻塩やくけぶりもすずし昨日までまつほの浦の秋の初風(松永貞徳)
逢ひみては願ひもみつの浦に焼く今ひとしほに身もこがれつつ(〃)
思ひとふ人のなさけの色に出でて焚きし紅葉の身もこがれつつ(藤原惺窩)
来ぬ人をまつの梢に月は入りて恋をせめくる風のおとかな(*蓮月)
西行法師、人々に百首歌よませ侍りけるに
あぢきなくつらき嵐の声も憂しなど夕暮に待ちならひけむ(新古1196)
【通釈】苦々しくも、激しい嵐の声さえ厭わしい。どうして夕暮に人を待つ習慣ができたのだろう。
【語釈】◇あぢきなく 「あぢきなし」は物事が自分の思うようにならず、どうしようもなくなって、苦々しく思ったり、愛想を尽かしたりする気持をあらわす。「あぢきなく」は古く下句に掛かるとする説がとなえられたが(拾遺愚草抄書・八代集抄など)、三句切れなので無理がある。「憂し」に掛かると見る方が自然であるが、気分的には下句にまで尾を引き、「など…待ちならひけむ。あぢきなくも…」と冒頭に戻るような心持であろう。円環的な構造を志向した歌は新古今時代珍しくない。◇つらき嵐 堪え難いほどに激しい嵐。「つらし」は仕打ちが耐え難いと感じる心。「嵐」は山から吹き下ろす風。朝と夕に吹くことが多い。◇声も憂し 声もまた憂鬱だ。「声も」というのは、《ただでさえ夕暮は切ない時間で、来ぬ人を待つのは辛いのに、そのうえ嵐の声までも…》という気持。◇など夕暮に待ちならひけむ なぜ夕暮に人を待つ習いができたのだろう。「など」は《よりによって、なぜ夕暮に…》との思い。
【補記】文治二年(1186)、西行の勧進に応じて作った二見浦百首。主題は「待恋」または「久待恋」で、男を待つ女の立場で詠んでいる。「あぢきなく」「つらき」「憂し」とネガティブな感情をあらわす類義の形容詞を畳みかけた、粘着力ある表現は作者の独擅場。
【他出】和歌一字抄(増補本)、自讃歌、定家八代抄、続歌仙落書、百番自歌合、拾遺愚草、新三十六人撰
【主な派生詩歌】
今来むとたのめてとはぬ夕暮にたがまことより待ちならひけむ(藤原為家)
夢に見しあだなる雲の跡をだになど夕暮にたのめざりけむ(四条隆親)
その道は銀の道 私らは行くであらう/ひとりはなれ……(ひとりはひとりを/夕ぐれになぜ待つことをおぼえたか)(立原道造)
歌合百首 待恋
風つらきもとあらの小萩袖に見てふけゆく夜はにおもる白露
【通釈】風がひどく吹き、もとあらの小萩を私の袖に落した――その花を見ながら、夜が更けるにつれ、白露は重みをましてゆく。
【語釈】◇風つらき 風がひどく吹く。本歌では「風」は男の比喩。「つらし」は相手の仕打ちの酷さを恨む気持で、訪れない男に対する恨みが籠る。◇もとあらの小萩 粗く(まばらに)生えている萩。◇おもる白露 涙が添わり、重くなる小萩の白露。
【補記】古今集の本歌の道具立てをほぼ引き継ぎつつ、庭の縁先などで男を待つ女の視線から一首を構成する。人の姿はほとんど消し去り、小萩と白露という微小な風物のイメージに読者の注意を集中させようとしている点、人臭い古今集読人不知の本歌とは極めて対照的である。正徹は「まことに心くるしく夜もすがら待ち居たるすがた艶にやさしきなり」と賞賛している(正徹物語)。六百番歌合恋二、十八番左持。右は隆信の「来ぬ人をなにに
【本歌】よみ人しらず「古今集」
宮木野のもとあらの小萩露をおもみ風を待つごと君をこそ待て
【他出】夫木和歌抄、正徹物語、題林愚抄、歌林良材、六家抄
恋歌とてよめる
帰るさのものとや人のながむらん待つ夜ながらの有明の月(新古1206)
【通釈】よそからの帰り道に眺めるものとして、あの人は今頃この有明の月を眺めているのだろう。私にとっては、あの人の来訪を待つ夜、ずっと眺め続けていた月を――。
【語釈】◇帰るさ 自分以外の恋人の家からの帰り道。◇待つ夜ながらの 待っている夜の間ずっと眺め続けていた。◇有明の月 明け方まで空に残っている月。
【補記】女の心になって詠んだ歌。物語の一場面を髣髴させる、新古今時代の恋歌の代表作の一つ。文治三年(1187)十一月、藤原家隆と共に詠んだ「閑居百首」。定家二十六歳。
【他出】自讃歌、無名抄、定家十体(有心様)、定家八代抄、続歌仙落書、百番自歌合、拾遺愚草、新三十六人撰、六華集
【主な派生歌】
こぬ人を待つよながらの軒の雨に月をよそにてわびつつや寝む(九条良経)
いつも聞くものとや人の思ふらむ来ぬ夕暮の秋風の声(*九条良経[新古])
太上皇仙洞同詠百首応製和歌 恋
久方の月ぞかはらで待たれける人には言ひし山の端の空
【通釈】月は相変わらず心に待たれてしまうのだった。以前は、人には月の出を待っているのだと言いつつ実は恋人を待ち焦がれて眺めた、山の端の空よ。
【語釈】◇月ぞかはらで… 「月ぞ」は人(恋人)に対して言う。月こそ変わらず待たれるが、人の心は変わってしまって、もう待つことはない。◇人にはいひし… この「人」は他人、第三者。人には「山の端の空」に月の出を待っていると言った。
【補記】本歌を言わば過去の事件として一首に取り込み、後日譚のようにして唱和した本歌取りである。「月ぞかはらで」によって、恋人は既に心変わりがしたことが暗示され、かつては期待を込めて眺めた「山の端の空」に、今はただ惰性で月の出が待たれるという。終わってしまった恋にまつわる心情を、きわめて婉曲に匂わせた、余情妖艶の歌。千五百番歌合、千三百四十六番右負。顕昭の判詞は「あしくも侍らぬに、すゑの『人にはいひし山のはの空』と侍る、すこしおろかなる心ゆかずや」。自分の愚かな心には下句がよく理解できないというのだが、本歌に気づかなければ理解しようのない歌である。
【他出】千五百番歌合、百番自歌合
【本歌】柿本人麻呂「拾遺集」
足引の山より出づる月待つと人には言ひて君をこそ待て
【主な派生歌】
月まつと人にはいひし偽のいまやまことの夕暮の空(藤原家隆)
ほととぎすまつ夜更行く山のはに人にはいひし月やいづらん(九条道家)
建保四年百首歌に
夜もすがら月にうれへてねをぞ泣く命にむかふ物思ふとて(続後撰733)
【通釈】一晩中、月に訴えて、声あげて泣くのだ。命に逆らう恋に悩んでいるといって。
【語釈】◇月にうれへて 月に向かって訴えて。「うれふ」は心中の不満や悩みを訴える意。◇命にむかふ 命を相手に戦う。命も失せるほど強く恋していることを言う。
【補記】建保四年(1216)院百首。『定家卿百番自歌合』六十八番左勝。「夜もすがら」「月にうれへて」「ねをぞなく」と強い語を畳み重ね、万葉から取った「命にむかふ」の烈しさへと盛り上げてゆく詞の運びがみごとである。因みに『六百番歌合』でこの語を用いた定家の歌につき、判者俊成は「『いのちにむかふ』や、万葉集などには侍るめれど、殊に庶幾すべからざるにや」と難じたことがあるが、定家は再びこの語を遣い切ることに挑んでみせたのである。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、定家家隆両卿撰歌合、万代集、井蛙抄、正徹物語
【参考歌】中臣女郎「万葉集」巻四
直に逢ひて見てばのみこそたまきはる命に向ふ我が恋やまめ
藤原定家「千五百番歌合」
いく秋を千々にくだけて過ぎぬらむ我が身ひとつを月にうれへて
【主な派生歌】
夜もすがら秋の思ひやなぐさむと月にうれへて鹿もなくなり(西園寺実材母)
摂政太政大臣家百首歌合に
忘れずは馴れし袖もや氷るらむ寝ぬ夜の床の霜のさむしろ(新古1291)
【通釈】私から心を移していないのなら、馴れ親しんだあの人の袖も、今頃氷りついているだろうか。眠れずに過ごす夜の寝床、そこに敷いた筵には、いちめんに涙の霜が置いている。
【語釈】◇忘れずは 恋歌における「忘る」は、主に「他に心を移す」意で用いられた。◇馴れし袖もや 馴れ親しんだ袖もまた…か。この「袖」は相手の袖。「も」と言うのは、話手自身の袖も、また狭筵も氷りついているから。◇こほるらん 氷っているだろう。恋人の置かれた今の状況を想像している。◇寝ぬ夜の床 眠れない夜の床。◇霜のさむしろ 霜が置いた筵。「涙は霜と結んで、衾全体を霜としてゐる」(窪田空穂『新古今和歌集評釈』)。
【補記】六百番歌合、恋九、三十番左勝。題は《
【参考歌】よみ人しらず「古今集」
さむしろに衣かたしき今宵もや我を待つらむ宇治の橋姫
【他出】六百番歌合、百番自歌合、拾遺愚草、定家家隆両卿撰歌合、題林愚抄
恋歌の中に
契りおきし末のはら野のもと柏それともしらじよその霜枯(続後撰936)
【通釈】末の原野の本柏は枯れても残っているが、別のところで霜枯れしているかどうか、それと知られまい。そのように、約束を交わした末に、当初の心は残っているとしても、別の所であの人の心は私から離れているかもしれない。
【語釈】◇末の原野 所在未詳。『歌枕名寄』なども未勘国とする。万葉集に「梓弓
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、歌枕名寄、井蛙抄
【補記】恋人の心変りを憂える心情を、古今集で初心の象徴とされた「もとがしは」に絡めて詠む。「末の原野」は万葉集で鷹狩の地として詠まれた歌枕であるが、定家はこれを「末」に掛け、「もとがしは」に繋げるためにのみ用いている。
【参考歌】よみ人しらず「古今集」
いそのかみふるから小野のもとがしは本の心はわすられなくに
千五百番歌合に
消えわびぬうつろふ人の秋の色に身をこがらしの杜の下露(新古1320)
【通釈】消えようにも消えきれず、苦しんでいたよ。私に飽きて心を移す人の、秋の木の葉の如く変わりゆく有様に、我が身を焦がし――まるで木枯しの森の下露のように。
【語釈】◇消えわびぬ 「わぶ」は「落胆する」「つらがって嘆く」といった意味であるが、動詞連用形に付いて「…する気力を失う」「…しようとしてし切れない」といった意にもなる。掲出歌では、「消え」が「露」の縁語になって死を暗示するため、「消えわび」で死に切れないことを苦しみ嘆くといった意に取れる。◇うつろふ人の秋の色 「うつろふ」は「人」に掛かって「心変わりする」意をあらわすとともに、「秋の色」に掛かって「木の葉が色を変えてゆく」意をも示す。◇身をこがらしの杜の下露 「身を焦がし」「木枯しの森」の掛詞。木枯しの森は駿河国の歌枕。静岡市羽鳥付近の藁科川の中洲にある森という。時雨と紅葉の名所。「杜の下露」は森の木々から落ちる露。言うまでもなく涙を暗示している。
【補記】建仁元年(1201)に詠進、翌年結番された千五百番歌合、恋一、千百九十一番、右勝。源師光の判詞は「心詞いひくだされてことに宜しくこそきこえ侍れ、仍可勝にや」。心と自然の景を重ね合わせ、一つ一つの詞にさまざまな味わいやイメージを重ね合わせ、かつ詞と詞のつなぎめを滲ますように暈しつつ、しかも流麗に「言ひ下されて」いる。複雑精妙この上ない、新古今歌風の一極限を示す一首。
【他出】千五百番歌合、自讃歌、百番自歌合、拾遺愚草、時代不同歌合、歌枕名寄、愚秘抄
【参考歌】作者未詳「古今和歌六帖」「新後拾遺集」
人しれぬ思ひするがの国にこそ身を木がらしの森はありけれ
被忘恋の心を
むせぶとも知らじな心かはら屋に我のみ消たぬ下の煙は(新古1324)
【通釈】私がいくら咽ぼうとも、あの人は知るまいな。瓦屋に消さずにある煙のように、心変わらず、ひそかに燃やす恋情は私ばかりが消さずにいることは。
【語釈】◇むせぶとも 恋に咽び泣くとも。「むせぶ」は本歌から取った語。煙の縁語。◇かはらや 瓦屋。瓦を焼く窯。「変はら(ず)」の意を掛ける。◇下のけぶり 心中ひそかに燃える恋心の暗喩。本歌の「下たくけぶり」による。
【補記】定家四十五歳の建永元年(1206)七月二十八日、和歌所で後鳥羽院より給題され、当座で詠んだ歌。題「被忘恋(忘らるる恋)」は前例未見。趣向はもっぱら実方の歌に負い、本歌の「むせびつつ」を「むせぶとも」と承けた、唱和に近い本歌取りである。しかし本歌の語彙・題材はより圧縮した形で取り込まれており、倒置・句割れ(しらじな/心)など文体を複雑化したところにも技巧を見せる。恋人に忘れられ、ただ独り思いを燃やし続ける者の心境に深く沈潜して詠んだ、有心体の恋歌である。
【本歌】藤原実方「後拾遺集」
忘れずよまた忘れずよかはら屋の下たくけぶり下むせびつつ
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、題林愚抄
歌合百首 暁恋
面影も別れにかはる鐘の
【通釈】今や別れを告げるものに変わる鐘の音に、恋人の面差しも憂わしく変わり、空がほの白むこの
【語釈】◇面影 顔つき・面差しの意で遣うか。同様の例に鴨長明の歌「右の手もその面影も変はりぬる我をば知るやみたらしの神」などがある(「面影」は面相の意に水影を含意)。◇別れにかはる鐘の音 別れを告げるものに変わる鐘の音。入相の鐘は出会いの時を、対して暁の鐘は別れの時を知らせる。「かはる」は「面影も」も承ける。◇ならひ 東雲に別れる人の世のならい。
【補記】六百番歌合恋四、五番左負。右はやはり暁鐘の音を詠む慈円の「暁の涙やせめてたぐふらん袖におちくる鐘の音かな」。右方人は定家の歌を「打ち聞きに心得がたし」(ちょっと聞いただけでは合点が行かない)と難じ、俊成は判じて、「彼の喜撰が歌をいふに、『
【他出】題林愚抄、六家抄
【参考歌】よみ人しらず「古今集」
しののめのほがらほがらと明けゆけばおのがきぬぎぬなるぞ悲しき
千五百番歌合に
思ひいでよ誰がきぬぎぬの暁もわがまたしのぶ月ぞ見ゆらむ(新後撰1066)
【通釈】それを見たら思い出しておくれ。誰との後朝の別れの暁にせよ、私がなお昔を偲んでいるのと同じ月が、あなたにも見えるだろう。
【語釈】◇きぬぎぬ 後朝。衣を重ねて共寝した男女が、翌朝、各々の衣を着て別れること。
【補記】千五百番歌合、千二百六十一番、右負。後朝の時刻にかつての恋人を思い遣った歌。物語の登場人物に成り切ったような詠み方で、若い頃から定家が好んだ風情であり、得意とした手法である。判者の顕昭は下記本歌を指摘した上で「秀逸には見え侍らぬうへに、月の字かさなりて侍り。あかつきと詠みならはしたれば、聞きよからずや」。「あかつき」と「月」の繰り返しを難じているのである。
【本歌】よみ人しらず「古今集」
しののめのほがらほがらと明けゆけばおのがきぬぎぬなるぞ悲しき
【主な派生歌】
見しままにわがまたしのぶ夕ぐれはおもひもしらじ心ならひに(藤原為家)
【他出】千五百番歌合、百番自歌合、拾遺愚草、六華集
水無瀬恋十五首歌合に
白妙の袖の別れに露おちて身にしむ色の秋風ぞ吹く(新古1336)
【通釈】差し交わしていた白い袖を引き離して別れる時となり、私の袖には露のようなしずくが落ちて――そこへ身に染みるような秋風が吹きつける。色などないはずなのに、こんなにもあわれ深く身に染みとおる風が。
【語釈】◇白妙の袖のわかれ 白い夜着の袖を差し交わして寝ていた、その袖を離れ離れにして別れる、ということ。後朝(きぬぎぬ)の別れと取るのが王朝和歌の常道であろう。が、それに限定して考える必要もない。万葉集巻十二に「白妙の袖の別れは惜しけれど思ひ乱れてゆるしつるかも」「白妙の袖の別れを難みして荒津の浜にやどりするかも」など、上代すでに定型句となっていたことが窺われる。定家はそれを復活させたのである。◇露 秋風の縁で涙を露という。紅涙と解釈し、白と紅の対照に着目する説は採らない。◇身にしむ色 この「色」は、趣・気色(けしき)、ほどの意だが、初句の「白」が響いて、色彩の意も帯びざるを得ない。本来風は無色透明であるはずだが、これほど「身にしむ」ということは、どんな色だというのか、との心がこもる。下記和泉式部の歌参照。
【補記】建仁二年(1202)九月十三日、後鳥羽院主催の水無瀬恋十五首歌合、題「寄風恋」、七十五番左負。右は雅経の「今はただこぬ夜あまたの小夜更けてまたじと思ふに松風の声」。元久二年(1205)、特に後鳥羽院の命が下り、新古今集巻十五(恋歌五)の巻頭に置かれることとなった。
【参考歌】作者不詳「古今和歌六帖」
吹きくれば身にもしみける秋風を色なき物と思ひけるかな
和泉式部「詞花集」
秋吹くはいかなる色の風なれば身にしむばかりあはれなるらむ
【他出】水無瀬恋十五首歌合、若宮撰歌合、水無瀬桜宮十五番歌合、定家八代抄、百番自歌合、拾遺愚草、井蛙抄
【主な派生歌】
吹く風の身にしむ色のあらはればうつるばかりぞ秋はみえまし(藤原為家)
夕ぐれは身にしむ色の松の風誰にうかれとあきをそふらん(心敬)
すゑつひに身にしむ色の初しほや衣手かろき今朝の秋風(後水尾院)
建暦二年十二月院よりめされし廿首 恋
なく涙やしほの衣それながら馴れずは何の色かしのばむ
【通釈】泣く涙、それによって濃い紅に染まった衣――それらは変わらないまま、あの人とは馴染む機会がない。このまま親しむことがなければ、私はこの恋に何の色を偲べばよいのか。ただ紅涙の色を堪え忍ぶだけなのだろうか。
【語釈】◇やしほの衣 八入の衣。幾度も染め直し濃く染めた衣。血涙に染まる衣を暗示。◇それながら それはそれで変わらないが。◇なれずは 睦み合わなければ。衣を着古すことを「
【補記】建暦二年(1212)十二月、後鳥羽院より召された二十首歌。暗示性に富み、その表現の婉曲さがまた妖艶を深めるという、定家の恋歌の特色がよく出ている。
【本歌】作者未詳「万葉集」
紅の八しほの衣朝な朝ななれはすれどもいやめづらしも
【他出】百番自歌合、両卿撰歌合
題しらず
かきやりしその黒髪のすぢごとにうち臥すほどは面影ぞたつ(新古1390)
【通釈】独り横になる折には、あの人の面影が鮮やかに立ち現われる。我が手で掻きやったその黒髪が、ひとすじごとにくっきり見えるかのように。
【語釈】◇かきやりし 我が手で(女の髪を)掻きやるように撫でた。本歌による。◇黒髪のすぢごとに 黒髪の一すじ一すじごとに。◇うちふすほどは 横になる折は。「うちふす」は「ふす」を強めた言い方で、ふっと横になる、ばったりと臥すなど、唐突さや勢いの強さといった感を伴う遣い方。本歌による語。
【補記】「黒髪」という当時最も尊ばれた女人の美の精彩を極めたかのような一首である。迫真的な官能性という点では、新古今時代の数多の秀歌にも一頭地を抜いていよう。しかし「かきやりし」「黒髪」「うちふす」という印象的な語は全て和泉式部の本歌にある語であって、しかも一首の要となる「髪のすぢごとに」さえ(意味合いは異なるものの)同じ和泉式部の歌に先蹤のある詞なのである。愛読した女流歌人の歌をばらばらの素材に一旦分解した上で再構成した(定家の天才はそれを無意識のうちに一瞬で成し遂げたかもしれないが)歌であり、本歌の妖艶に触発されてこその新たな妖艶美の造型であった。本歌取りの技法としては、本歌の「かきやりし人(男)」の身になって、女に返したとも読める作りである。『百番自歌合』に採られているので、建保四年(1216)二月以前の作。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、歌林良材
【本歌】和泉式部「後拾遺集」
黒髪のみだれもしらずうちふせばまづかきやりし人ぞ恋しき
【参考歌】和泉式部「和泉式部集」
かきなでておほしし髪のすぢごとになりはてぬるを見るぞ悲しき
千五百番歌合に
たづね見るつらき心の奥の海よ潮干のかたのいふかひもなし(新古1332)
【通釈】探って見る、つれない人の心の奧――それはあたかも遥かな
【語釈】◇心のおくの海 「心の奧」「奧の海」を言い掛ける。「奧の海」は中世の歌学書などに陸奥の海を指すとする。定家の歌との先後関係は明らかでないが、藤原家隆の歌にも「おくの海やえぞが岩屋の煙だに思へばなびく風や吹くらん」と陸奥の海として用いたと思われる例がある(壬二集)。◇いふかひもなし 「かひ」は「貝」「甲斐」の掛詞。これと言った貝もない。また、何を言う甲斐もない。
【補記】奥の海と恋人の内心と、「尋ね見る」二つの景情を絡み合わせるようにして詠み、粘着力のある表現は定家の独擅場であろう。千五百番歌合、千二百十九番右負。左は藤原公継の「ふぢばかま夢路はさこそ通ひけれ逢ふと見る夜のうつり香もがな」。定家の歌につき顕昭は源氏物語の本歌(下記参照)を正しく指摘し、「この歌の『伊勢島』をかへて『つらき心の奥の海』となされ、『潮干の潟にあさりてもいふかひなきは
【他出】千五百番歌合、定家卿百番自歌合、拾遺愚草、歌枕名寄、夫木和歌抄、井蛙抄
【本歌】『源氏物語』「須磨」
伊勢島や潮干の潟にあさりてもいふかひなきは我が身なりけり
【参考歌】「伊勢物語」十五段、在原業平「新勅撰集」
しのぶ山しのびてかよふ道もがな人の心の奥も見るべく
和泉式部「和泉式部集」「新古今集」
潮のまによもの浦々尋ぬれど今は我が身のいふかひもなし
恋不離身といふ心を
心をばつらきものとて別れにし世々のおもかげ何したふらむ
【通釈】恋に苦しむ心を堪え難いものとして別れてしまったが、あの人のその時々の面影が浮かんで我が身を離れない。どうして心は慕い続けるのであろう。
【語釈】◇世々の面影 過去の、その時その時の面影。「世々」には「夜々」の意が掛かろう。
【補記】意志ではどうにもならない恋心の不可思議に迫った、有心の恋歌。制作年等未詳。題「恋不離身」は前例未見であるが、別れた後も添うて離れない恋人の面影は、「忘れにし人はなごりもみえねども面影のみぞたちもはなれぬ」(久安百首、堀河)など、古歌にも見える恋の主題である。
【他出】百番自歌合、定家家隆両卿撰歌合
逢不遇恋
忘れぬやさは忘れける我が心夢になせとぞいひて別れし
【通釈】忘れてしまったのか。そうとは忘れていた私の心であったよ。「逢ったことは夢だと思おう」と言い合って別れたのに。今もあの人と現実に逢いたいと思い続けているとは。
【語釈】◇忘れぬや 初句切れ。「や」は終助詞と解するしかなく、疑問や詠嘆の意の終助詞「や」は終止形に接続するので、直前の「ぬ」は完了の助動詞「ぬ」の終止形と解するしかない。すなわち「忘れてしまったのか」と自問している心であろう。◇さは忘れける我が心 そうとは忘れていた我が心よ。「さは」の「さ」は「夢になせとぞ言ひて別れし」ことを指す。◇夢になせとぞ 二人の逢瀬を夢に見なせと。
【補記】『正徹物語』に定家の難解歌として挙げられた一首で、正徹は「か様に定家の歌はしみ入りて其の身に成りかへりて読み侍りしなり。定家に誰も及ぶまじきは恋の歌なり」と絶賛した。なお、参考に挙げた歌は定家の母が父俊成に贈った歌。
【校異】第二句を「さはわすれけり」とする本もある。『心敬私語』は第三句「逢ふことを」。
【他出】正徹物語、心敬私語
【参考歌】美福門院加賀「新古今集」
たのめおかむたださばかりを契りにて憂き世の中を夢になしてよ
建保三年内大臣家百首歌に、名所恋
芦の屋に蛍やまがふ海人やたく思ひも恋も夜はもえつつ(続後撰915)
【通釈】芦屋の里に見える火は、蛍の光を見紛うのか、海人の焚く漁火か。我が身にも、「思ひ」の火だの「こひ」の火だの、夜は燃え続けてやまない。
【語釈】◇葦の屋 題は「名所恋」であるから地名。摂津国の歌枕、芦屋。◇思ひもこひも 思ひ・こひ、いずれも「ひ」に「火」を掛ける。
【補記】建保三年(1215)九月十三日の内大臣家百首。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、定家家隆両卿撰歌合、歌枕名寄
【本歌】「伊勢物語」八十七段、在原業平「新古今集」
はるる夜の星か川辺の蛍かも我がすむかたに海人のたく火か
建保三年内大臣家百首歌に、名所恋
白玉の緒絶の橋の名もつらしくだけておつる袖の涙に(続後撰893)
【通釈】緒が絶えるという「緒絶の橋」の名を思い出すのも辛い。あの人との仲が絶えぬかと憂え、真珠の緒が絶ち切れたように砕け落ちる、私の袖の涙を見るにつけて。
【語釈】◇白玉の 万葉集巻十六に「
【補記】「緒絶の橋」と言えば後拾遺集の藤原道雅詠「みちのくの緒絶の橋やこれならむ…」が名高く、この歌を踏まえて「まどふ」心を詠むことが多いが、定家は道雅の名歌を全く無視するかの如く、万葉集の歌から橋の名に「白玉の」を冠し、「袖の涙」に繋げるというアクロバティックな詩想の展開を見せる。歌枕の名は口実に用いられているだけで、橋としての意味は全く剥奪されているのである。「『緒絶の橋の名』とうけたるばかりにて、上下に『橋』の縁なし。加様の事斯集におほし。後世凡歌の及べき所にあらずや」(拾遺愚草俟後抄)。
【他出】百番自歌合、拾遺愚草、万代和歌集、歌枕名寄、六華和歌集、六家抄
哀傷
母身まかりにける秋、野分しける日、もと住み侍りける所にまかりて
たまゆらの露も涙もとどまらず亡き人こふる宿の秋風(新古788)
【通釈】露も涙も、ほんの一瞬も留まることはない。亡き人を恋しく思い出す宿に吹きつける秋風のために。
【語釈】◇たまゆら 万葉集の「玉響」(現在の定訓は「たまかぎる」)の古訓に由来する語。「ほんの一瞬」といった意であるが、玉が揺れるイメージも添う。
【補記】庭の草に置いた露も、おのれの目から溢れる涙も、野分の風に吹かれて、一瞬も留まってはいない。無常迅速を歎きつつ母を失った悲しみを詠む。定家の母美福門院加賀の死去は建久四年(1193)二月十三日。父俊成の家集『長秋草』にも載り、詞書は「七月九日、秋風あらくふきあめそそきける日、左少将まうできてかへるとてかきおきける」とある。俊成は定家の歌に対し「秋になり風のすずしくかはるにも涙の露ぞしのにちりける」を始め三首の歌を返した。
【他出】長秋草、自讃歌、定家十体(幽玄様)、定家八代抄、続歌仙落書、百番自歌合、拾遺愚草、正徹物語、歌林良材
【参考】源為憲「新撰朗詠集」「本朝麗藻」(→資料編)
故郷有母秋風涙 旅館無人暮雨魂(故郷に母有り秋風の涙 旅館に人無し暮雨の魂)
【主な派生歌】
いまはとて消えなむ露の夕べこそ亡き人恋ふるかぎりなりけれ(木下長嘯子)
風になびく浅茅が末の露の世に亡き人恋ふる我もいつまで(〃)
旅
韻歌百二十八首 旅
面影のひかふるかたにかへりみる都は山の月繊くして
【通釈】しきりと面影が浮かび、旅立ちを引き留められるような気がする都の方をかえりみれば、山の端に
【語釈】◇ひかふる 「引き合ふる」の約。引き留める。袖などをひっぱり相手を引き留める動作を言う語。◇月繊くして 三日月などの細い月を言う。三日月は女性の眉に喩えられたので、「その人の眉を思わせて」(訳注全歌集)ということになる。
【参考】「源氏物語・須磨」
道すがら面影につとそひて、胸も塞がりながら、御舟に乗り給ひぬ。
【他出】愚問賢註、東野州聞書、六家抄
【補記】建久七年(1196)九月十八日、当時内大臣だった良経に命じられて詠んだ「韻歌百廿八首和歌」。韻字は《
守覚法親王家に、五十首歌よませ侍りける旅歌
こととへよ思ひおきつの浜千鳥なくなく出でし跡の月かげ(新古934)
【通釈】言葉をかけてくれよ。思いを残してやって来たこの興津の浜――ここで悲しげに鳴いている浜千鳥ではないが、私が泣く泣く出て行ったあとの都の空に残っていた月、あの時と同じ月の光よ――。
【語釈】◇こととへよ 呼びかけの対象は何か、千鳥か月か、あるいは都の家族か、判り難い(その曖昧さも計算の上であろう)。ここでは月への呼びかけと解した。◇思ひおきつ 「思ひ置き(つ)」と「興津」を言い掛ける。「思ひ置く」は心を残す意。「興津」は下記参考歌の詞書によれば和泉国の歌枕。但し駿河国にも同名の歌枕がある。後者と考えれば東国への長い旅路となり、旅愁はより深くなる。◇浜千鳥 旅先の海辺の情趣を釀し出すと共に、「思ひおき」と「なくなく」をつなぐ役割を担っている。◇なくなく出でし この「し」は過去回想の助動詞。◇月かげ 月の光。旅立ちは普通払暁を選んだから、明け方に見た有明の月であろう。それと同じ月を、今は旅先の夜空に眺めている。
【補記】都と東国を往還する旅人が興津の浜に宿をとった晩、都を出て来た時と同じさまの月に向かって「言問へよ」と呼びかけた歌であろう。都の家族もまた同じ月を見ていると思えば、「言問へよ」は家族への呼びかけともなり、ひとしお哀切である。建久九年(1198)夏、守覚法親王に召されて詠んだ五十首歌。
【他出】御室五十首、百番自歌合、拾遺愚草、歌枕名寄、井蛙抄、六華集
【参考歌】藤原忠房「古今集」
君を思ひおきつの浜になく鶴(たづ)の尋ねくればぞありとだに聞く
【鑑賞】「例によつて複雑で、又巧緻でもある。それを貫く調(しらべ)もあるが、その調が、単に詞の調子となつてしまつて、当然伴つて来るべき気分が足らず、その為に、全体の感じが散漫になつた趣のあるものといへよう。作者の長所と共に、弱所をも現してゐると見える歌である」(窪田空穂『新古今和歌集評釈』)
「どう解釈しても、歌の言わんとする気分の方は変りない。そこがいわゆるだるま歌の面白みである。情景は読者がそれぞれに思い設ければよい、というところに定家の安心した、むしろ意識的な狙があるのだろうと思う。俊成が六百番歌合の初瀬山の歌について、いみじくも指摘したように、風体よろしく、心にこめた詠みぶりではあるが、詞に不確かな典型的例の一つである」(安東次男『藤原定家』)。
【主な派生歌】
忘れめや鳥の初音に立ちわかれなくなく出でしふるさとの空(*宗尊親王)
夜をこめてなくなくいでし涙ゆゑゆふつけ鳥の声も露けし(三条西実隆)
みても猶あかず過ぎ行く名残をぞ思ひおきつのあとのしら波(中院通村)
後京極摂政家詩歌合、羈中眺望
秋の日のうすき衣に風たちて行く人待たぬをちの白雲(玉葉1162)
【通釈】秋の淡い光が射す中、薄い旅衣に風が吹き立つと、彼方に見える白雲は、旅人を待つことなく、さらに遠ざかってしまう。
【語釈】◇秋の日のうすき衣 「うすき」は「秋の日のうすき」「うすき衣」と前後にかかる。◇ゆく人またぬ 行人(旅人)を待ってくれない。雲を旅人の伴侶または道しるべと見なしての謂。
【参考】「白氏文集・長恨歌」(→資料編)
黄埃散漫風蕭索 雲棧縈廻登劍閣 峨嵋山下少行人 旌旗無光日色薄…
藤原定家「拾遺愚草員外」
行衣夕薄袖中秋
【他出】拾遺愚草、夫木和歌抄、心敬私語
【補記】建仁三年(1203)八月一日、良経邸での詩歌合。定家四十二歳。題《羇中眺望》は前例未見。
旅の歌とてよめる
旅人の袖ふきかへす秋風に夕日さびしき山の
【通釈】旅人の袖をひるがえして吹く秋風――あたかも故郷の方へ人を戻すように吹くその風と共に、夕日が寂しく照らす山の
【語釈】◇ふきかへす 裏返して吹く、翻して吹く。「吹き戻す」の意もある語なので、故郷の方へ旅人を帰すように吹くといった意が響く。◇秋風に 助詞「に」は添加あるいは並列の意。この「に」一語が一首の要。◇かけはし 山の急斜面に板などを棚のように架け渡して通れるようにした道。懸橋・桟・梯などと書く。
【補記】定家三十五歳になる建久七年(1196)九月十八日、良経邸で詠んだ「韻歌百二十八首」のうち秋の部。韻字は《
【他出】定家八代抄、続歌仙落書、百番自歌合、拾遺愚草、別本和漢兼作集、詠歌一体、六華集
【参考歌】志貴皇子「万葉集」巻八
采女の袖ふきかへす明日香風都を遠みいたづらに吹く
【鑑賞】「秋風、夕日、山のかけはし、おのおの異々(ことごと)にて、たがひに何のよせもなく、その上に三の句より下、旅人の縁もなし。かやうにただ物をあつめて、けしきをいひならべたるは、玉葉風雅のふりにちかし」(本居宣長『美濃廼家苞』)
「一首の意、旅人が山の桟(かけはし)を行く折から、秋風が袖を吹きかへし、さびしげに夕日のさしたるは、かなしかるべき事と也。人のうへを言ひたりとしてもよろしく、旅人をやがて我が身の事としてもよろし」(石原正明『尾張廼家苞』)
「さみしく、あはれな自然の中に、人間を小さく点じた心のもので、当時の詩情である。一つの状態として客観的に見たもので、自然の方に力点を置いて、人間に対しては感傷の一語をも出さず、それは余情としてゐる。生趣を持つた歌である」(窪田空穂『新古今和歌集評釈』)
「定家は表裏・明暗・遠近に心を配っていて、構成力のたしかさを窺わせる一首である」(安東次男『藤原定家』)
【主な派生歌】
鷺のとぶ河辺のほたでくれなゐにゆふ日さびしき秋の水かな(*衣笠家良)
かきくれし雪は名残もとどまらで夕日さびしき峰のときは木(肖柏)
落ちかかる夕日さびしき里川の堤の穂たで秋風の吹く(井上文雄)
詩を歌に合せ侍りしに、山路秋行といへることを
都にもいまや衣をうつの山夕霜はらふ蔦の下道(新古982)
【通釈】故郷の都でも、今頃妻が私を慕い、衣を
【語釈】◇都にも 「都」は話手の故郷。「にも」と言うのは、話手も旅路にあって妻を慕っているから。◇衣をうつ 砧の上で、木槌で衣を擣つ。旅先にある夫を慕いつつする女の仕事とされた。「うつ」は地名「宇津」に掛けて言う。宇津の山は駿河国の歌枕。今の静岡市宇津ノ谷あたり。東海道の難所として名高く、伊勢物語第九段によって歌枕となる。◇蔦の下道 蔦が繁る下を通る道。本説の伊勢物語を踏まえた定家の造語であろう。
【補記】元久二年(1205)六月十五日、後鳥羽院の五辻御所で催された『元久詩歌合』(既出)、二十七番右(勝負付・判無し)。題《山路秋行》は前例未見。定家は「うつ」の掛詞によって、擣衣に寄せる故郷思慕の情と、宇津の山を旅する心細さとを結びつけた。それによって、故郷で夫を思いつつ砧を擣つ妻と、旅の難路で故郷の妻を思う夫と、両者の面影・心情が交錯させたのである。結句で伊勢物語の蔦楓の描写が呼び起こされ、ひとしおの余情を添える。
【他出】拾遺愚草、百番自歌合(前稿本)、和歌口伝、歌枕名寄、六華和歌集
【本説】「伊勢物語」第九段
宇津の山にいたりて、わが入らむとする道は、いと暗う細きに、蔦、楓はしげり、もの心細く、すずろなるめを見ることと思ふに…
【主な派生歌】
うつの山夕霜はらふ松風に蔦のかれ葉は猶のこりけり(正徹)
雑
題しらず
忘るなよ宿るたもとはかはるともかたみにしぼる夜はの月影(新古891)
【通釈】忘れないでくれ。共に別れの涙を流し、濡れた袂に月の光を宿した――その袂は変わるとしても、その夜お互いに絞った月の光のことは。
【語釈】◇宿る袂 月の光が涙に映る袂。◇変はるとも たとえ袂は変わるとしても。「袂の変はるとは、月日ふるほどに、衣を
【補記】文治二年(1186)、西行勧進の二見浦百首、題は「別」。伊勢物語の本歌は、昔男が東国へ旅立つ際、友人たちに贈ったという惜別の歌。定家の歌は「かたみにしぼる」に恋情の趣が濃く、旅に出る男が女に贈った歌として読むのが妥当であろう。
【他出】百番自歌合,拾遺愚草
【本歌】「伊勢物語」第十一段、橘忠基「拾遺集」
忘るなよ程は雲居になりぬとも空行く月のめぐりあふまで
清原元輔「拾遺集」
ちぎりきなかたみに袖をしぼりつつ末の松山波こさじとは
於北野聖廟詠之
下もゆるなげきの煙空に見よ今も野山の秋の夕暮(百番自歌合)
【通釈】
【語釈】◇ ◇ ◇
【補記】『百番自歌合』八十一番右勝。『拾遺愚草』『員外』には見えない。
【参考歌】
【主な派生歌】
和歌所歌合に、海辺月といふ事を
藻塩くむ袖の月影おのづからよそに明かさぬ須磨の浦人(新古1557)
【通釈】藻塩のために海水を汲む袖はしとどに濡れ、その上に月の光が映じて、須磨の浦の海人はおのずと月をよそにすることなく一夜を明かす。
【語釈】◇藻塩くむ 藻塩を作るための海水を汲む。◇おのづから 自然と。意図せずに。◇よそに明かさぬ 月影を疎遠に明かしはしない。すなわち、月影に親しいまま夜を明かす。
【参考歌】宮内卿「新古今集」
心ある雄島のあまの袂かな月やどれとは濡れぬものから
【他出】卿相侍臣歌合、定家八代抄、百番自歌合、歌枕名寄
【解説】「海辺月」は平安末頃から好まれた歌題。定家は塩焼の名所である須磨の「海辺」を舞台に、海人の袖に映る「月」を詠んだ。山人や海人の生業に「おのづから」生ずる風流に興じた趣向は当時好まれたもので(参考に挙げた宮内卿の歌もその一例)、定家自身の作にも「山がつの身のためにうつ衣ゆゑ秋のあはれを手にまかすらん」(二見浦百首)、「おのづから秋のあはれを身につけてかへる
二見浦百首 述懐
見るも憂し思ふも苦し数ならでなど
【通釈】今のこの世は、見るのも厭だし、考えるのも苦しい。数にも入らない身で、どうして昔を懐かしく思い始めたのだろうか。
【補記】二見浦百首、述懐五首の一。懐旧の情を詠む。「現世を厭い過去を慕う」という心情は、古人にあまねく行き渡っていた態度であり、述懐歌に好まれた主題であった。定家もそうした一般的傾向に従ってこの主題を取り上げたのであろうが、初二句の現実嫌悪の烈しさは前例を見ないものである。次いで「数ならで」と言うのは、必ずしも卑下ではない。むしろ、自身の過去の栄光ゆえ昔を懐かしむのではない、すなわち古今集の「我も昔は男山」といった心情の否定、俗情としてのノスタルジーの否定であろう。戦乱の時代背景も思われる一首である。
粟田宮歌合
思ひかね我が夕暮の秋の日に三笠の山はさし離れにき(百番自歌合)
【通釈】
【語釈】◇ ◇ ◇
【補記】承元四年(1210)九月。題は「寄山暮」。『拾遺愚草』は結句「さしなはなれそ」。
【参考歌】
【主な派生歌】
行末も照すひかりの長月につげのをぐしはさしはなれにき(順徳院)
建暦二年十二月院よりめされし廿首 雑
思ふことむなしき夢の中空に絶ゆとも絶ゆなつらき玉の緒
【通釈】私の願いは虚しい夢の中途で絶えてしまうとしても、命を苦しく繋ぎ止めている玉の緒は絶えないでくれ。
【語釈】◇たゆともたゆな 「思ふこと」が絶えても、「玉の緒」は絶えるな。◇玉の緒 命を繋ぎ止めるもの、延いては命そのものを言う。
【他出】百番自歌合、両卿撰歌合
【補記】建暦二年(1212)、後鳥羽院に詠進した二十首。この歌の前の二首からの流れからすると、「思ふこと」は我が身の栄達、官位昇進についての願望であろう。前年秋定家は従三位に叙せられ公卿の身分を得たものの、誇りある左近衛中将の地位は息為家のために辞しており、また念願の蔵人頭の職も逃していて、相変わらず不遇感に苛まれていた。
【参考歌】式子内親王「新古今集」
玉の緒よ絶えなば絶えねながらへば忍ぶることのよわりもぞする
【主な派生歌】
夜はの夢たゆともたゆな大舟におろすばかりの縄のうらなみ(正徹)
最勝四天王院名所御障子歌 松浦山
たらちめや又もろこしに松浦舟今年も暮れぬ心づくしに
【通釈】母上よ、どうしていらっしゃいます。私はまだ唐土にあって、松浦舟の迎えを待っています。故国の筑紫に思いを馳せ、あれこれ気を揉むうちに、今年も暮れてしまいました。
【語釈】◇たらちめや 「異国の地で望郷の念を抱きながら、母に呼び掛けるという設定」(渡邉裕美子著『最勝四天王院障子和歌全釈』)。◇まつら舟 松浦舟。肥前国松浦で造られた舟。宝治二年(1248)の『宝治百首』の基家詠に「松浦潟もろこし船はいでぬ日も…」とあるように、松浦は外国往来船が発着する地であった。定家は「待つ」意を掛け、我が国と唐土を往来する船としてこの舟の名を用いている。◇心づくしに 心も尽きるほどに。あれこれと気を揉んで。「つくし」に筑紫(九州の古称)の意を掛ける。
【補記】建永二年(1207)の最勝四天王院障子和歌、「松浦山」題で季は冬。「唐の者が日本にゐるを、唐の母が待心也」(六家集抜書抄)とすれば、定家が愛誦したという源為憲の詩句「故郷に母有り
【他出】百番自歌合、正徹物語、歌林良材
関白左大臣家百首歌よみ侍りける眺望歌
ももしきのとのへを出づる宵々は待たぬに向かふ山のはの月(新勅撰1168)
【通釈】内裏の外郭の門を出る夜々にあっては、待つこともなく向かうことになる、山の端の月よ。
【語釈】◇ももしき 内裏。宮城。◇とのへ 宮城の外郭。◇いづる 月の縁語。
【補記】貞永元年(1232)に成立した「関白左大臣家百首」は、定家七十一歳の最後の百首歌である。題「眺望」。警衛などの勤務を終え、夜ごと城外に眺める月を詠む。有明の月は普通待たれて出ずるものであるが、夜番の身にとっては「待たぬに向かふ」ことになるというのである。定家自身、左近衛府の次官を長年勤めた身であった。《眺望》の景としては何ということもないが、生活詠ふうの詠みぶりにかえって新鮮なところがある。老いて自在な歌境が窺われる一首である。
【他出】百番自歌合、洞院摂政家百首、拾遺愚草、正風体抄、井蛙抄
おなじ時、外宮にてよみ侍りける
契りありてけふみや河のゆふかづら永き世までにかけてたのまむ(新古1872)
【通釈】前世からの因縁があって、今日伊勢の
【語釈】◇宮河 伊勢国の歌枕、宮川。伊勢神宮外宮の近くを流れるので、外宮の象徴とされた。「み」に「見」の意を掛ける。◇木綿鬘 既出。外宮で神事が行われたことを示し、かつ「かけて」を言い起こすはたらきをする。◇ながき世までも 永く続く将来の世までも。子孫の世々までも。◇かけて 「かけ」は木綿鬘の縁語。
【他出】拾遺愚草、百番自歌合、歌枕名寄
【補記】建久六年(1195)二月、伊勢勅使となった良経に従って伊勢に下り、外宮に参詣した時の作。伊勢参詣をめでたい巡り合せとし、その縁を力として神のご加護をつよく請い願う心である。掛詞・縁語を駆使した巧みな詞運びのうちに緊張感が漲っている。定家三十四歳。
道助法親王家五十首歌に閑中灯を
つくづくと明けゆく窓のともし火のありやとばかりとふ人もなし(玉葉2167)
【通釈】物思いに沈んで夜を過ごすうち、窓が明るくなって来て、灯火もあるかないかになる。そんな灯火のように頼りない思いでいる私を、無事かとばかり尋ねてくれる人もありはしない。
【語釈】◇つくづくと 一つの対象に見入ったり考え入ったりするさま。また、物思いに沈むさま。◇明けゆく 夜が明けてゆく。「あけ」には「開け」の意が掛かり、窓の縁語。◇窓のともし火 本説の「窓灯」に拠る。「ともし火」は今にも消えそうな思いでいる話手自身の暗喩でもある。◇ありやとばかり 健在かとだけでも。◇とふ 見舞う。慰問する。家を訪ねることにも、手紙で尋ねることにも言う。
【補記】つくねんと灯火に向かって明かす孤独な夜。「明けゆく窓のともし火」は話手の見ている対象物であると共に、話手自身の心の象徴であり、かつまた「ともし火の」から「ありや」を言い起こす序のはたらきをする。上句から下句への転が絶妙で、しみじみとした味わいを出している。題《閑中灯》は前例未見。
【他出】拾遺愚草、題林愚抄
【本説】「和漢朗詠集・暁」「白氏文集・禁中夜作書与元九」
五声宮漏初明後 一点窓灯欲滅時
従今便是家山月、試問清光知不知
しるや月やどしめそむる老いらくのわが山のはの影やいく夜と(員外)
【通釈】月よ知っているか。余生を過ごす庵に住み始めた老残の我が山――その山の端に射すおまえの光を、あと幾夜幾年見られるかと。
【語釈】◇知るや 句題の「知不知」による。◇やどしめそむる 新しい庵居に移ったばかりの。◇我が山の端の影 私が住む山の、その山の端の月影。句題の「家山月」による。◇幾世 幾年、幾夜。「世」には「夜」の意を掛けたのであろう。
【補記】建保六年(1218)の文集百首。句題は白氏文集巻六十六の「初入香山院対月」より。「今
更新日:平成19年04月26日
最終更新日:平成24年02月01日