インドの地勢とか気候とかは適当な資料で調べればよろしい。
問題は感覚的に理解できるかどうか。
ありがちな地図(1)を見ると、インドは暑いというけれど「シンガポールよりも北にあるじゃん」と気づく。デリー、コルカタあたりでも台湾と同程度。と、こちら側(東側)から見ると実感がつかみにくい。実態ではなく「実感」というのがミソである。
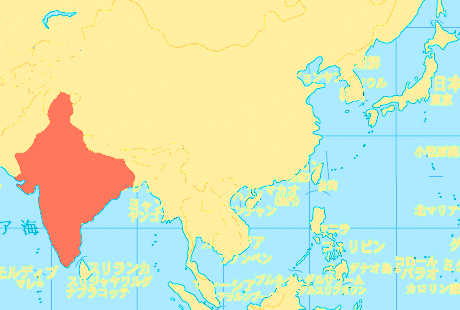
そこで、ズリズリとインドを西に移動してみる。(2)
デカン高原とサハラ砂漠の緯度がほぼ同じ。なるほど、これでは暑そうだ。気候の感覚はこんなもんである。
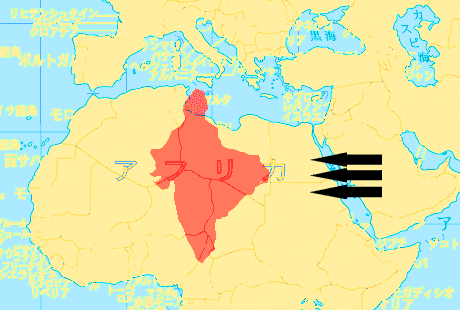
ついでにズリズリと北に移動。(3)
一国で西ヨーロッパをほぼカバーしてしまった。広さの感覚はこんなもんである。
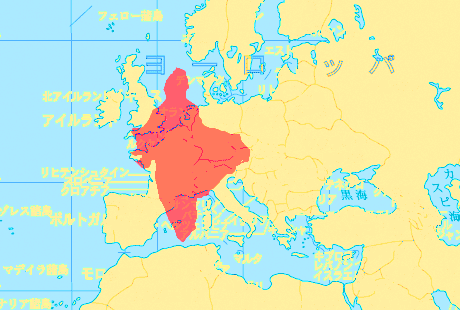
たとえばコルカタからデリーへの移動を東京から大阪へ行くように思っては間違い。東京から北海道の稚内、あるいは九州の鹿児島へ移動するぐらいの距離である。図(3)で考えるとイタリアからイギリスへの移動になるのだろうか。よくある『ヨーロッパ主要都市5日間/ロンドン・パリ・ローマ』的な短期カミカゼツアーを笑う個人旅行者でも、自分が同じことをしていると知る人は少ない。
ツアーを利用する人も移動にはそれなりの覚悟が必要。ガイドブックや地図では隣町へ移動する感覚でも、たとえばデリーからタージ・マハールのアーグラーへ行くには列車でも3、4時間かかる。東京観光の翌日に大阪観光をするようなものである。
横の次は縦。
同じヨーロッパでもポルトガルとデンマークが同じような国と思う人はいないだろう。インドでも南北の端では同じぐらい、いやそれ以上に異なる。人種が違う。言葉が違う。文字が違う。気質が違う。食べ物が違う。つまり、何でも違う。
まず、インドの州(西ベンガルやタミールやウッタル・プラデーシュなど)はヨーロッパでは国に相当すると考えるといい。国によって言葉が違うのは当たり前。インドでは州によって文字も異なることがほとんど。だから、インド国民にとってもコミュニケーションのための英語とアルファベット文字は重要になってくる。
『インド概略2』
約3億年前という昔々、世界は巨大な一つの大陸で、それが分裂・移動して今日の諸大陸になったという大陸移動説がある。巨大大陸の名はパンゲア。
妙に納得してしまうのは、現インド亜大陸のパンゲアにおける位置である。ユーラシア大陸は現在よりも北に位置している。南西に接して北アメリカがあり、その南東にアフリカ、さらに南東にインドが接している。大雑把に言えば、今のマダガスカルの辺りにあったインドがアフリカから分かれ、ドンブラコと漂った末に、迷惑にもアジアの南側にガツンとぶつかったのである。その時に隆起したのがヒマラヤ山脈というのは有名な話。
私は勝手に「インド人もインド亜大陸に乗ってやってきた」と思っている。だから納得しているのだが、歴史的にはウソである。3億年も昔の話で、多くの旅行者が接するアーリア系のインド人は(アーリア人がインド・ヨーロッパ語族とも呼ばれるように)西からやってきた人たちだ。
それでもアジアの東端(日本だな)から順番に国を訪ねていくと、インド亜大陸に入った途端、世界は劇的に変わる。
どう変わるのか。
それを確かめるのもインドの旅だ。多分、酔狂なインド人パンゲア起源説を信じたくなると思う。