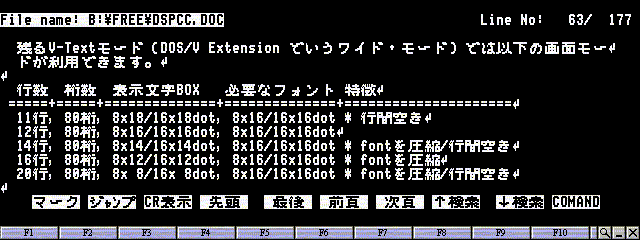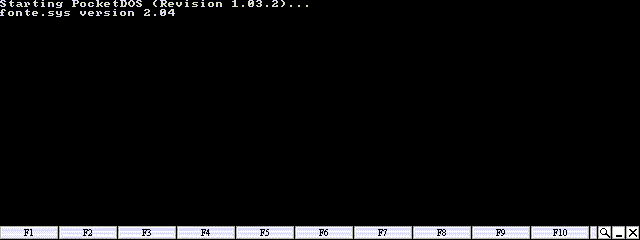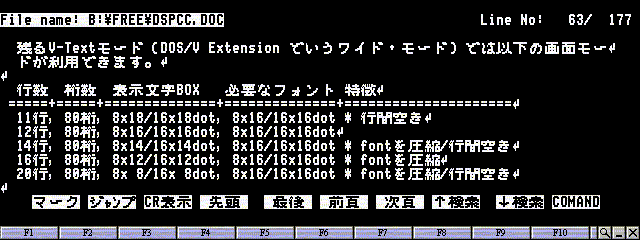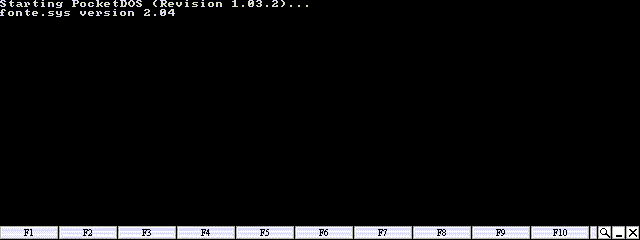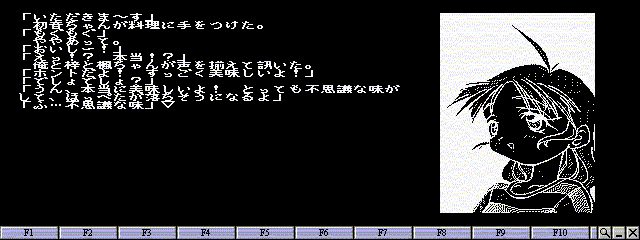HP200LX のフラッシュメモリカードを有効活用
Jornada720 DOS遺産継承作戦 4
作戦参号「切詰めて日本語」
PocketDOSの日本語DOS/C化
さて、お約束のとおり、PocketDOSでの日本語化についてです。本サイトの目的とするところとはちょっと離れてしまいますけど、
- 「PC Cardスロットに通信系カードを差してPATyでモバイル勝馬投票」など目的を限定して多くを望まない
- PC CardにもCFにも余裕がない
- あるいはそもそも外部ストレージがなく、内部メモリにインストール
などの場合は、総バイト数が少なく済むこちらのコースのほうが合目的的でしょう。ただし、やはりPocketDOSは謎の互換OSなので、コレを載せたCE機は文字通り謎パーと化します。何がおこるか判りません。
HP200LX日本語化キット(jkit)を使ってみる(失敗)
…玉砕しました。
HP100LX フリーDOS/C環境を適用してみる(頓挫)
…さすがは原形、jkitがダメなものはやっぱだめで、もっと詳しくいえば調子が出ないのはfontmanです。もともとソリッドステート機(ノースピンドル機)に最適化された、フォントをディスクから直接読込む特殊な省メモリフォントドライバですから、肝心のディスクドライブが別OSのファイルシステムに怪しいドライバかましただけのパチモノでは、ひとたまりもありません。
CGA汎用フリーウエア群を使ってみる(詳述)
FontXとDspCCを使ってみましたが、これは通りました。そこで、こんどはこちらを解説します。
用意するもの
-
FontX
-
DspCC(FHPPCメンバー限定のため、入手できなかったらyadcを代用。→yadcを使った設定
)
-
通称"げんちょもフォント"
スキーム
- PocketDOSをインストールしたフォルダ(PocketDOSから見るとここはb:ドライブになるので、以後CEからフォルダを観ている時でもb:ドライブと呼称します)にドライバ類を置いとくディレクトリを作ります。やはり\free\とでもしましょう。
- 拾ってきたFontXとDspCCを解凍してこのb:\free\に送ります。
- フォントをいれるディレクトリを作ります。これまた安直にb:\font\としておきます。
- 次は当然このディレクトリにフォントを解凍します。
- さて、ここまでのおさらいです。今度は、仮想ディスクという枠が填まってませんから倹約した分だけ効果が出ますので、b:\free\の中に本当に必要なものだけ残してみます。
CHEJP COM 749 97-05-27 1:00
DSPCC COM 22,232 97-05-27 1:00
$FONTE SYS 43,168 96-06-27 17:26
DCCLOAD COM 283 97-05-27 1:00
VMT COM 449 97-05-27 1:00
PLAINLX ATR 64 97-05-26 2:55
GEN9808X FNT 2,582 96-01-21 21:43
GENHN08X FNT 2,065 96-01-21 21:42
GENZN08X FNT 110,706 96-01-21 21:41
- B:\font\に¥$FONTX.INIというファイルを作ります。節約して"げんちょもフォント"だけの例としますと中身はこうです。
[FONT]
genhn08x.fnt
genzn08x.fnt
gen9808x.fnt
- 今度は起動ファイルです。b:\config.sys末尾に以下の2行を書き足してください。
DEVICEhigh=b:\Free\$fonte.sys /P=b:\font\
DEVICEhigh=b:\Free\dspcc.com hs=off
- b:\autoexec.batの末尾に以下の4行を書き足してください。
path b:\free;%path%
dccload b:\free\plainlx.atr
chejp
vmt 73
- おさらい2です。念の為、前述のPoketDOSの独自コマンドの利用の薦めと合わせて、最小構成の起動ファイル全文を示します。これで起動すれば、日本語表示は可能になっているはずです。
b:\config.sys
FILES=24
DEVICEHIGH=A:\DOS\EMSMEM.SYS
DEVICEhigh=b:\Free\$fonte.sys /P=b:\font\
DEVICEhigh=b:\Free\dspcc.com hs=off
DEVICEhigh=a:\dos\ansi.sys
b:\autoexec.bat
SETDRIVE M: "\My Documents"
setdrive e: "\storage card2"
prompt $p$g
path b:\free;%path%
SETCOM COM1: COM6: ;(実際に使うシリアルポートを指定してください)
dccload b:\free\plainlx.atr
chejp
vmt 73
追記
- 現在私の環境では、日本語デフォルトのビデオモード03の生dosの表示がおかしいので(V-TEXT対応アプリは正常動作します)25行表示にはモード73を適用しています(autoexec.batに盛込み済み)。…かつては動いていたような気もしなくもないところが一寸気味悪いんですが。
- 勿論、容量に余裕があればフォントを追加することができます。「赤城フォント」も「ぱうフォント」も使えます。しかしDspCCはフォントを伸長(も)してくれるので、フォントを追加しなくても下画面内に見えてる総ての表示モードが利用可能です。実際、下画面ではげんちょもフォントで14行表示をしています。
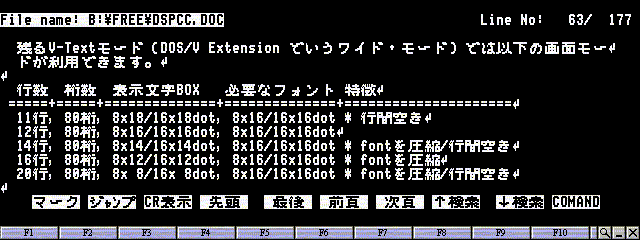
- @niftyにアカウントがなくDspCCが入手出来ない場合、速度が落ちますが前頁で紹介したyadcでも動作します。もう一つ、DISPCというドライバも入手しやすいのですが、PocketDOSとの組合わせで挙動不審を報告してくださっている先達サイトがありますし表示モードが制限されますので、yadcのほうをお薦めします。
- 今回はfontを絞ったため、$fonte.sysを用いても(ええ、勿論使えますとも!)18秒で組込み行程が完了します(赤城とぱうも組込むとXT-CEの際と全く同じく55秒間、下に示した画面のまま滞ってしまいます)。しかし、…勝馬投票など運用上一刻を争う場面も予想されるなら、先達の御薦めのとおり$fontm.sysを利用した方がいいかもしれません(ドライバごとコンベンショナルメモリにロードすることをお忘れなく。devicehigh=のままだと、エラーと文字化けの後、固まります)。ただし、この場合はフォントの種類だけメモリが圧迫されますし、大きいフォントはファイルサイズも大きいので、使えるのは事実上げんちょもフォントだけでしょう。
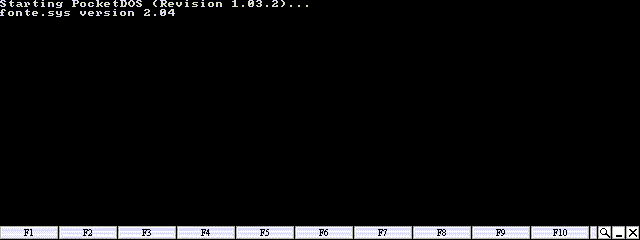
やり残している事
- XT-CEの時と同じ事情で、かな漢字変換FEPを組み込んでいません。解決しました。
- この日本語環境でも「痕forLX」は動作はします。しかし…いやだー、こんなガングロ初音ちゃんじゃない〜。どうにかならんもんでしょうか…と書いたら、なんと「痕forLX」の表示プログラム「ぐるぐるくん」作者の神楽さんより一言アドバイスを頂きました。
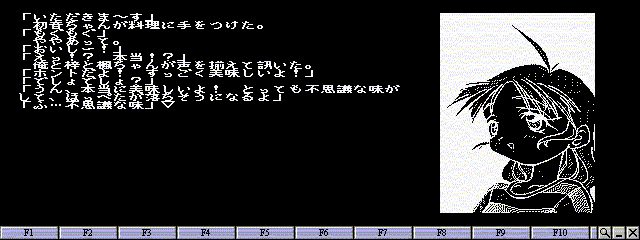
「終末の過ごし方 for LX」ができないのもXT-CEと一緒です(泣)。