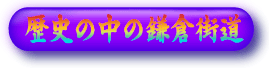 |
|
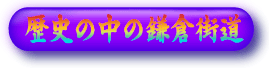 |
|
鎌倉・南北朝時代
|
鎌倉幕府成立後わずか7年で頼朝は世を去ります。頼朝の死後頼朝の家臣であった人々の権力争いが始まります。 13人の合議制にはじまる梶原景時の乱、 頼家と関係した比企能員の乱、そんな中に畠山重忠も北条時政によって 謀反人にさせられ重忠の嫡男重保はじめ郎党ことごとく殺されてしまいました。この事件は北条時政・義時父子の 対立の一つと考えられています。重忠が 討たれたその夜には時政と一緒になって重忠を鎌倉におびき寄せた稲毛重成が、 責任を追及されて三浦義村に殺されています。結果時政も鎌倉から 追放されることになりました。その後、 父時政を追放した義時は侍所別当和田義盛も 葬らせてしまいます。そして実朝暗殺とこのあたりの事件は黒い ベールに隠された謎が多くしそんでいますが最終的に義時が 北条執権政治を確立するのでした。 1221年後鳥羽上皇が北条義時追討の院宣を発します。いわゆる承久の乱ですがこの鎌倉幕府最大の危機に 鎌倉方は上洛して朝廷を攻めるか、 あるいは足柄・箱根あたりで朝廷軍を迎え討つか意見がわかれました。 この時北条政子は武蔵の武士達に噦上洛せずは、更に官軍を敗り難きか器と上洛を勧め幕府の方針は上洛に決定しました。 この戦で武蔵の国の武士達が数多く参戦しています。 上洛軍のうち東山道軍は鎌倉街道上道をおびただしい兵馬が通ったことでしょう。 承久三年の宇治河合戦では県下の武蔵武士たちは勲功を挙げその名を都人に知らしえたことでしょう。宇治河合戦交名に見られる 諸氏だけでも秩父氏、小代氏、河越氏、 山口氏、須黒氏、成田氏、猪俣氏、金子氏、仙波氏、安保氏等々。
鎌倉時代は日本の歴史の中でも政権が貴族から武士に変わった時代です。社会制度が改まったように宗教や文化の面でも大きな変革がありました。中でも仏教に関しては鎌倉新仏教と呼ばれる宗派が登場してきます。平安時代末期に法然により浄土宗が開かれた後に鎌倉時代始め頃に親鸞は浄土真宗を広めます。一方建久2年(1191)に宋より帰国した栄西は禅宗である臨済宗を広めます。鎌倉時代半ば頃には道元が同じ禅宗の曹洞宗を広めています。当初栄西の禅思想は布教を禁止させられますが、執権北条時頼は宋より蘭渓道隆を招き旧仏教から完全に独立した最初の禅宗寺院である建長寺を建立し臨済禅は権力者に受け入れられ京都・鎌倉に五山の寺院が建てられます。そんな中で建長年間頃に日蓮が日蓮宗を説き『立正安国論』を掲げます。これは権力批判と解され文永8年(1271)に佐渡に配流されてしまいます。この時、日蓮が佐渡へと向かった道が鎌倉街道上道であると伝えられています。上道の各地には日蓮の伝承が多く残されています。そして鎌倉街道でもう一人忘れてならない一遍の時宗があります。鎌倉街道上道沿いには時宗の寺院が数多くあります。その総本山が藤沢の遊行寺です。又同寺の所蔵する『一遍上人絵伝』には上人の勧めで大勢の人々が道普請に従事している模様が描かれていて街道研究の重要な資料ともなっています。
尊氏・高師直と足利直義の争いである観応の擾乱の後関東では南朝の宗良親王をいたたく新田義興・義宗らが挙兵し、 尊氏・高麗経澄軍と鎌倉街道上道沿いで両軍の戦いがつづきますが 高麗原・小手指原の戦いで尊氏方が勝利しほぼ決着をみます。 この戦いの最後の戦場地とされるのが鳩山町の笛吹峠です。ところで室町幕府の政治機関で関東を統治する鎌倉府が置かれたことにより 鎌倉時代以後もしばらく鎌倉はやはり関東の政治的中心であったことから鎌倉街道は重要な交通路には変わりなかったのです。 鎌倉府の首長は鎌倉公方と呼ばれ始め足利尊氏の子基氏が任命されます。 その頃はまだ、南朝の新田氏らと鎌倉街道上道沿いで 鎌倉公方と衝突がつづきます。入間川辺は両軍が衝突する要衝の地であったので、足利基氏はこの地をおらえるためしばらく ここに移りすみます。これが入間川御所と呼ばれるものです。 1365年下野の宇都宮氏の家臣、越後守護職芳賀禅可入道高名は 守護職を免職された不満から鎌倉公方基氏と対立し現在の毛呂山町の 苦林野で合戦となります。禅可の子二人が率いる芳賀軍は 小人数ながら勇敢に戦いましたが一族の多くを失い敗北してしまいます。 南北朝のさなかその危機を乗り切るために幕府は 半済令なるものを出します。これによって守護が国内の荘園・公領の年貢の 半分を兵糧米として徴収し、それを家臣の国人などに 分け与えます。そして守護は国司の権限を奪ってゆき国全体を支配する 守護大名へと成長していくのです。後の戦国大名の中には この守護大名から出ているものがあります。 武藏国における南北朝の対立は応安元年(1368)の武藏平一揆の乱を最後として終わりを遂げます。この反乱は越後と上野で挙兵した新田氏に応じて、武藏国の河越・高坂さの平氏が河越を中心におこした反乱でした。南北朝以後関東では前述のとおり鎌倉府がおかれその補佐役として関東管領がありました。先の苦林野の合戦で敗退した 芳賀禅可は越後国の守護でしたが基氏によってその守護職は上杉憲顕が 勤めるようになり関東管領にも任命され以後関東管領は 上杉氏が勤めることになります。上杉氏の中にあって山内上杉氏は守護として上野国を本拠地としていたため、鎌倉と上野国を 結ぶ鎌倉街道上道は後の公方足利氏と関東管領上杉氏争い、 あるいは上杉氏内部の争いで合戦の舞台となることが多かったのです。 都では足利義満が将軍の時が室町幕府の最盛期でした。南北朝の合体、三管領・四職の制と。 |
|