 |
イギリス |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ダービー 二日目(4月29日) | ||||||||||||||||||||||||||
| ダービー<マーケット> | ||||||||||||||||||||||||||
|
ダービーのまちは、特に変わったところはないが、落ち着いた雰囲気である。所々に小公園がある。 大きなドームの中にある市場に入ったが、ここも万国共通で、売っている物もディスプレイもほとんど同じであった。本屋もあったのでカメラ雑誌を一冊買った。中身はともかく、本の装丁や印刷は日本の本の方がはるかによくできている。 しかし、インターネットを活用するようにCD-ROMがついていた。車の雑誌も同じような体裁であった。記事も、中身は日本と大差なく撮影のノウハウが多い。カメラのインプレッションや販売記事は、ほとんど日本製のカメラのものであった。販売価格は、日本のレベルとしたら少し高い。 店内をあれこれ見て回ったが、どうもイギリス人は、どうでもいいことには無頓着のような気がする。店舗のディスプレイもなんとなくやぼったい。ファッションも、田舎街だからかも知れないが、アメリカで感じたような、センシティブな感じではない。タイやシンガポールのような色っぽさもない。しかし品数が多く、選択肢をたくさん用意している。 これは、その店が資金的に余裕があることかなと勝手に解釈した。日本であれば、売れ筋しかおいていない。 市場の2階には、中古のレコード店や雑貨店があり、見るだけでも楽しい。 少し危ない雰囲気の店員さんが多かったので、写真は撮らなかったが、英語が分かって話ができたら面白かっただろうと思う。中古のカメラ店では、オリンパスOM-10が淋しげにぶら下がっていた。 ここの市場に来て改めて感じたのは、イギリスも沢山の人種が暮らしていることである。 特にこうした市場では、いろんな人種の人々が行き来していた。 だから、私たち日本人でも違和感なく歩けるし特別な目線を感じることはなかった。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ところで日本で写真を撮るとき2本の指を立ててピースサインをするようになったのはいつ頃だろうかと考えた。少なくとも私が20歳くらいまではその仕草はやっていない。ところが私の子供たちが小さい頃にはもうやっている。ということは、1980年頃からかなと勝手に思っている。あれほど激しかった学園闘争やら安保闘争が、ある終焉を迎え、一応国内が落ち着き、いよいよ高度経済成長への階段を上り始めた頃か。 今は、子供にカメラを向けると必ずピースをするので、写真にならない。 なぜこんなことを書くかというと、息子に、「手のひらを内側にして指を立てるとイギリスではバッドマナー」といわれたからである。いろいろ試してみたが、確かにピースサインの時は手のひらを前にしているが、数を表現するときは手の平を内側に向けている。 市場の競りでもところによって違いはあるだろうが、確か手のひらは内側向けたと思う。長年の日常的な仕草をすぐに変更するというのはなかなか難しかった。国によって、仕草が違ってくるのは当然だがマナー違反となる仕草は気をつけなくてはいけない。それを絶えず意識していないと、買い物に行って言葉が通じなかったとき、思わずそのバッドマナーの表現となってしまっていた。だから買い物がうまくいかなかった。とはいいわけである。 買い物についてはもう少し。 おいしそうな飴があったので買おうと思ったが、「sweets」と書いているので、なんかこう甘すぎる感じがして買わずにいたが、イギリスでは「sweets」はふつうの飴のことだった。アメリカや日本の、「candy」なのだが我々は英語の授業では「キャンディ」で覚えた。 ついでにいえば、面食らったのは、エレベーターがイギリスでは「lift」である。入り口が「way in」、我々は「entrance」といっている。出口が「way out」、それに対しては「exit」である。 アメリカの人が、同じ英語圏でありながらロイヤルイングリッシュをわざわざ習いに来るわけが少しわかった。 勘定書のことは、「bill」で、米語では「check」である。ビリングサービスという本当の意味をイギリスにきて初めて知った。 まだある。英語では、映画館のことを「cinema」というが、米語では「movie theater」で、日本の最近できている映画館はほとんどが「シネマ」のほうを使っている。日本の外国語の使い方の「多国籍化」がおもしろい。 ついでにいえば、イギリスでは1階のことを「ground floor」2階が「first floor」である。米語では「first floor」が 1階で、「second floor」が2階なのである。 これは、ヒースロー空港に着いたときに居場所がとんちんかんになった原因になった。 あまり単純なことを聞くと馬鹿にされると思い、息子にも聞かなかったが、そんな微妙な違いがわからないまま異国に行くととんでもない間違いをやりかねない。ふつうにグランドフロアーといわれれば、ファーストフロアーを1階として、私なら間違いなしに地下にいくだろう。紀南なまりのため、日本国内でも言葉が通じにくい私にとって、異国での言葉の壁はエベレストよりも高いことを実感した。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ダービー<郊外> |
||||||||||||||||||||||||||
|
昼からは少し郊外に走った。景色は相変わらず放牧地で、遙か彼方まで続いている。 昔は森ではなかったかと思う。でないと、様々な童話が生まれにくい感じがする。 産業革命の時も、薪で蒸気を発生させていたという。 それはともかくも、このあたりの道が緩やかなアップダウンで、楽しいドライブができる。古びた扉にすり減った階段。 そして石段の間に生えたタンポポ。こういう景色っていいな。町の至る所でこういう景色に出会った。 あまり体格がいいとはいえない牛がたくさん放牧されていた。聞けば、イギリスの牛肉は堅くてあまりおいしくないという。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ダービーからどこをどう走ったかさっぱりわからないが、緑がいっぱいであった。 途中の街は、石造りの建物ばかりで、その地方でとれる石が微妙に違うらしく街によって壁の色も違っている。 石組みの仕方も違う。こちらへ来てのカルチャーショックというのが、この家作りにもある。 世界遺産のテレビや本で見る限りにおいて、石造りの建物は特別なものと思っていたが、ここイギリスはほとんどの建物が石造りであり、100年、200年と年月を経ているので特別なことではないのである。日本でいえば、合掌造りの里のような、または漆喰作りの家がすべてある感じである。 イギリスという近代国家の建物は、もっと近代的な素材で建てられていると思っていた。実際は、建物の何もかもが、煉瓦か石である。しかしこの建築方法は日本では通用しない。地震が来れば間違いなしに崩壊してしまうだろう。 日本では家の建て替えにコストがかかるが、こちらでは100年200年と耐用できるので、費用が少なくてすむ。その分文化的な他の用途に、お金を使える。だから15%という消費税にも合意が得られるのだろうか。 それと、家具や食器に至るまで、その家に備え付けで動くことはない。アパートでも身一つですぐ生活できるのである。引っ越しが楽である。息子のアパートもスプーンに至るまでアパートのものである。 これは合理的で、引っ越しの際の余分な費用が助かる。 行き当たりばったりに、小さな村に乗り入れ、少し散策したが、いい感じのところであった。メインの道沿いは車の往来も多いが、一歩中にはいるとひっそりとしている。 教会通りという名の通り、小さな教会がたくさんあった。写真の教会は中でも一番大きく一番風格のあるものである。後は、屋根に十字架があるので教会だとわかる程度である。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||







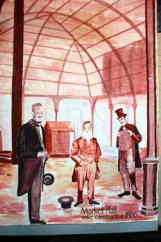















 >
> >
> >
>

 >
>









 >
>
 >
>