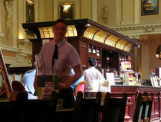|
イギリス |
|
||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
| ダービー 二日目(4月29日) | ||||||||||||||||||||||||||
|
さて、ダービーの街中に繰り出した。 街は考えていた以上にきれいで落ち着いていた。教科書などでも街のこんなディティールは教えない。 産業革命をしたほどの国だから、もっと喧噪があってたくさんの看板があると思っていたが、全くと言っていいくらいなかった。その代わり、バスに様々なメッセージがあった。しかしこれは合理的である。これは日本でもやっているので特にどうということはないのだが、街の中に看板や電柱のない景色というのは、いい。写真を撮るとき、邪魔になる看板や電柱・電線がないのは写真をするものにとってはありがたい。 街には、日本でいうところのシニアカーがよく走っていた。クラシックなたたずまいの街を、ほとんど無音でシニアカーが走りすぎるのを見ると、お年寄りやハンディのある人にとってこの国はサポートがいいのではないかと思ってしまう。実際はどうなのかは知らないけれど、どこかの国のように、弱者切り捨てはしないように思える。 途中の舗道上にテントがたくさんあり、カラフルな駄菓子や野菜などを売っていた。これは日本とほとんどかわらない。 この形式は万国共通である。 街には駐車場が要所要所にきちんとある。 街を車で移動して、駐められなかったことはなかった。聞けば、イギリスの交通取り締まりは、ことのほか厳しくて、ルールを守らないときっちり処分があるという。 それが本来の取り締まりというものである。 大阪の御堂筋と比較しても一目瞭然である。バス以外の車は駐まっていない。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ダービー <カテドラル> |
||||||||||||||||||||||||||
|
最初にいった有名な施設は、「ダービーカテドラル」である。ここを見終わると、入り口にいた恰幅のいいおじさんが「どこから来たのですかと聞いてきた。 「日本からです」というと喜んでくれて、是非訪問記帳簿にサインをして欲しいと言われた。 いわれて断ることも出来ないので、ローマ字と漢字で住所氏名を書いた。 ここダービーカテドラルは、日本語でもパンフレットを作っていた。それによると、 「この歴史的な教会は、10世紀の後期に創立されましたが、現在の建物は、16,18,20世紀に建設された部分からなっています。 壮観な65メートルの塔は1530年に完成され、イングランドで最も高い教会塔の一つです。最上部の近くには、(最大のもので1000Kgの重さを持った910個のベルからなる「リング」が釣り下げられ、どれも300年以上を経た古いものばかりです。 毎週日曜日には、イギリス古来の転調鳴鐘法に従って、ベルが鳴り響きます。 塔は夏の特定の日にに一般に公開されています。 教会の主な部分は、一続きになった「ネープ」及び「チャンセル」で、1725年から1727年にかけて、古典的な様式に再建され、1965年から72年にかけて東方向に拡張されましたが、その時中央祭壇の上に大天蓋が設けられました。 祭壇の近くには17世紀のビショップの座があり、これは小アジアの正教会に由来します。 ネーブとチヤンセルは、美しい鋳鉄のスクリーンとゲートで仕切られ、1730年頃に完成されま したが、それを作成した地元の鍛冶屋の作品は、遠くオックスフォードにまでも見ることができます。彼はカテドラルゲートを作成し(元来は町の民家のためのもの)、また町長の座席の鉄製部分 をも作成し、町のバッジ、紋章の鹿を取り入れました。反対側の州民席はモダンな鉄製部分を持ち、州の特色の多様性を現しています。 この古い中世の教会に由来する興味深い記念物がいくつかあります。例えば、有名なハードウイツク のベスの記念物がありますが、彼女はチユーダー時代には非常な影響力のあった貴族で、デボンシヤー公爵の祖先でした。 彼女は1607年に亡くなり、彼女の生前の命今によって作成された、南側廊の凝った記念物の下に埋葬されました。 現代産業との興味ある結び付きは、1987年にロールスロイスの学生徒弟が作成した、ステンレ スの移動洗礼盤です。これによって、時に洗礼の儀式を日曜日の主な礼拝式の時に行うことができ ます。 カテドラルの日常において、音楽は重要な要素です。 二つの聖歌隊と二つのオルガンが設置され、年間を通じてコンサートとリサイタルが開催をれます。 市の日常におけるカテドラルの主な役割は、勿論キリスト教の礼拝とミッションにあります」 とあった。 日本でいえば、京都や奈良をはじめとした、古くからあるいいお寺に匹敵するのだろう。 どこの国のものでも、民衆が崇拝し維持し続けてきたものは威厳があり見ていても飽きない。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
教会の圧倒的な荘厳さにびっくりして、表に出、次にいったところは、世界文化遺産の一つ、「シルク・ミル」を工業博物館にしているという。途中の公園のような所では。老夫婦が楽しげに何か話をしていた。緑の芝生がきれいで、散歩を楽しんでいる人も何人かいたた。あちこちチューリップがたくさん植えられていて、歩くものの目を楽しませてくれた。 世界遺産だが、そんな仰々しいものはなく、当時のスタイルだろうと思われる女工さんの絵を描いた看板が迎えてくれた。以前は機織機がガシャガシャと動き、ダーベント川には水車が回っていたのだろう。蒸気エンジンが水車に取って代わったとき、世界の歴史も大きくかわった。その中心がここなのである。 じつは、このダービーは、愛知県の豊田市と友好姉妹都市なのである。私がイギリスに行っているときにローバー社が工場を閉鎖ということで、これを最後にイギリスから自動車会社がなくなってしまった。その代わり、日本の自動車会社工場があって、ここダービーにはトヨタの工場がある。その縁で姉妹都市になったという。産業革命を起こした中心地に、200年近く経って当時はまだ武家社会で、鎖国をしていた日本の会社が、工場を造って海外に進出している。 歴史というのは面白い。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ダービー <インダストリアル ミュージアム> |
||||||||||||||||||||||||||
|
18世紀は、ダービーを産業革命の始まりの場所として最も注目すべき始まりの地である。 その歴史的シルク・ミルは、ダービーの工業博物館(Industrial Museum )になり、そして、産業革命を起こし、ダービーに富をもたらした開発の歴史と産業革命以来の工業の進歩をわかりやすく展示されている。 特に最近、改築されたギャラリーにおいては、ロールス・ロイスによって作られた大規模な 飛行機用エンジンの展示があり、飛行機用エンジンの歴史がわかる。イギリスを勝利に導いたとされる、第二次世界大戦のイギリス主力戦闘機スピットファイヤ( Spitfires )のエンジンであるマリーンエンジン( Merlin)も展示され、当時を思い起こさせてくれる。 また、産業革命とともに、鉄道の重要性も表現され、 1839年以来のミッドランドレイルウェイネットワーク及び新しい鉄道の展示もあり、 鉄道の歴史もわかる展示がある。 中には、実際の景色の中で自分が運転している感覚になるシミュレーターや、技術の進歩過程をたどったディスプレイがある。また電話技術の進歩の過程で、一世を風靡したステップバイステップ交換機の実物があり、実際にダイヤルすると相手に繋がることがわかるようになっている。 この地方は鋳物工場 ( Friar Gate を横断してブリッジを作った Andrew Handyside を含むこと )があったことから鋳物の技術や、煉瓦の作る方法などの展示もある。 なんかてんこ盛りの博物館であるが、楽しく見ることが出来る。 飛行機が好きな私にとって、ロールスロイスのマリーンエンジンの実物が見えたということはうれしかった。 スピットファイヤのエンジンやジャンボジェットのエンジン、さらにいろんなエンジンの実物を、見て手で触れられたことである。プラモデルで作ったことが懐かしく、「これがそのエンジンの実物なんや」という感じであった。 何故この辺が、産業革命の拠点となったかというと、まず川が近いので水車を動力にした自動織機が発明され、続いてワットの蒸気エンジンが出現して、にわかにその生産量を増やしたのである。 ここの博物館は、歴史的価値のあるものばかりなのに、展示はきわめてラフで、誰もが自由にさわれるようになっている。また、子供向けの展示もあり、大人も子供も楽しめる。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
ダービー <パブ> |
||||||||||||||||||||||||||
|
イギリスといえば、パブということで、昼食はパブで食べた。 何というパブかメモしていなかったのでわからないが、結構広く大きなパブであった。(後で聞くと、「Standing Order」という店ということである)店内は、お年寄りが多かった。聞けば夜は若者が多いとか。たくさんの料理を食べながらビールかワインを飲んでいた。これでは太る。 面白いのは、禁煙席と喫煙席が完全に分かれていて、喫煙できる方はスタンド形式となっていることである。 喫煙スペースは比較的若い人が多かった。 日本も、チェーン店などは、席が分かれているがテーブルなどは一緒である、こうして歴然とした差をつけているのはいい。これは世界的な傾向らしく、たばこを吸わない私のようなものにとって、日本ももっとまねをしたらいいと思っている。 周囲はお年寄りが多く、リタイヤした人びとが交流するのに格好の場のようであった。 店内は、本棚があり何となくアカデミックな本が並んでいた。 左隣のテーブルでは、おじいさんがビールを一人で飲んでいた。右隣のテーブルでは老婦人が二人、ワインを飲みながら楽しげに語り合っていた。いずれも年金生活をしている感じであるが、生活の余裕が感じられる方々ばかりであった。 そして驚いたことは、皆かなりの大食漢で、隣のおじいさんなどは、私がおなか一杯になった料理を、簡単に平らげてビールのお代わりをしていた。 料理は、こちらに来る前に、イギリス経験者から、「イギリスの料理は、おいしくないからやせてくる」と聞かされていた。 しかし、どんな料理を食べてもおいしい私にとって、気にならなかった。 ただし、世界各国でイギリス料理の専門店が少ない理由には、他の国の料理のような、「艶」がないことかなと、食べながら思った。素材も同じでドレッシング類も同じだけれど、日本料理のような「粋」、フランス料理のような「華」がない。 大衆的なパブで、それを望むのは酷かもしれないが、おいしくないと評価される理由がその辺にあるような気がする。 日本でいうところの「出汁」が味に生きていない感じである。 しかし、料理の味のうんちくを語るほどグルメでもなく、まわりの雰囲気もすこぶるよかったので、ビールを飲みながらおいしく腹一杯食べた。 街の角にはところどころに、「フィシュンチップス」を売る店がある。 開高健氏の「掌のなかの海」の、「・・・ポテトのフライといっしょにして新聞紙の三角袋につっこんでわたしてくれる。ごくざっかけな食べ物であって、料理といえるほどのものではない。街角のスナックである。つまみ食いのおやつみたいなものである。ずっと後になって東京で知り合ったイギリス人から--この人はケンブリッジ出身だったが--あれは新聞紙に秘密があってエロ新聞に包んでもらうといつまでもホカホカと温かいけれど、『タイムズ』なんかだとたちまちさめてしまうというんです、というジョークを聞かされたことがある。・・」というくだ りを思い出した。うんうんなるほど。 |
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||