|
競馬最強の法則 競馬で立派に妻子を養う男 木下健の方法 |
|
|
競馬最強の法則 競馬で立派に妻子を養う男 木下健の方法 |
|
|
'07 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
'99 1月号 '00 1月号 '01 1月号 '02 1月号 '03 1月号 '04 1月号 '05 1月号 06 1月号 |
|
|
「簡単お手軽ラップ風3分クッキング馬券術」はもともと、「ドカンラップ理論」に味を占めた?担当さんが、「もっと簡単なやりかたないですか?」というオーダーから始まったもんでして、私自身が普段実践しているものとは微妙に開きがあります。でもま一応こういう結果も出ましたんで一安心。とはいえこれはあくまで気楽な「出目感覚」使うレベルの方法で、いつでも百発百中なってことはないんで、その点注意して使ってくださいな~(^^;アハハ。
ハーツの凡走は「ラップ」で読めた? ジャパンカップが終わった翌日、担当さんと電話で次号の打ち合わせをしてるときに、「今回、ひょっとしたらハーツクライはあかんかも……と思ったんですけど、現実になってしまいましたね。ラップ的に見ると、凡走してしまう可能性が感じれたんで、今回の敗因のひとつにペースが関係してる可能性がなきにしも非ずやと思いますわ~」 繰り返しになりますが、まずは「ラップ理論」の大前提を確認しておきます。「ラップ理論」のキモは、 《各馬には各馬の、己が能力を発揮できるペース(=ラップ)がある。自分にあったペースなら好走するし、合わないと凡走する》 この理論は、似たような能力の馬が走る条件戦で威力を発揮しやすいですが、もちろんGⅠレベルの馬にも適用できます。ただしこのクラスになると、明確なタイプを分析するのはかなり複雑な作業になるのですが……。中でも、引退しましたがハーツクライはわかりやすい部類なんで、説明してみます。実は昨年の1月号で「ラップ的見地から有力馬を分析する」みたいな感じで書いたときにハーツクライを紹介してるんですが、担当さんはまったく忘れてはりまして……(~~;。ということは読者の皆さんが覚えてるはずもないんで、まずはそのときの原稿を抜粋。 ============================ この馬の場合なんかは脚質的にも非常にわかりやすいですね。 ゼンノが3着やった宝塚記念で2着に先着してますが、その宝塚での《中間タイム》はゼンノより0.4秒速い58.8秒 【図A参照 】。中間だけで先頭との差を1.4秒詰める脚を使いながら、さらに残り3Fを35.2秒で上がってこれるエエ脚が長く続くタイプってことになりますね(^^)。 ただしこういうタイプの馬というのは弱点も多く、前走の天皇賞秋のようなスロー過ぎて隊列が詰まった展開やと中間で動くに動けず32.8秒のほぼ限界と思えるような末脚を使いながらも6着に敗退してますね。もし仮に早めに動いてたとしても、先行馬も余力十分で無駄脚を使っただけに終わる公算が大ですね。 そういう意味では宝塚記念や産経大阪杯みたいに5Fを60秒を切るようなペースやと中間で使ったエエ脚が無駄脚に終わらんので結果は出やすい感じですね(図 B参照)。 ============================
昨年ジャパンカップ当時のハーツクライは、この原稿と書いたときとはまったく違う脚質なんで、単純に「60秒を切るほうがいい」とはいえませんけど、少し視点を変えてみますと、実は「脚質が違っても得意のラップにそう大差はない」ということがわかります。ということで 図Cをご覧ください。①②③はそれぞれ、 ①前半3Fタイム ②走破時計から上がり3Fを引いた前中タイム ③前中タイムから前半3Fを引いた中間タイム を意味してますが、これらを比較しやすいように距離別に並べ変えてあります。さらにわかりやくするために、先行したときは白抜きにしてます。またデビュー3戦目の若葉Sまではラップなど関係なしに基本能力だけで勝てた可能性があるので割愛しまし た。 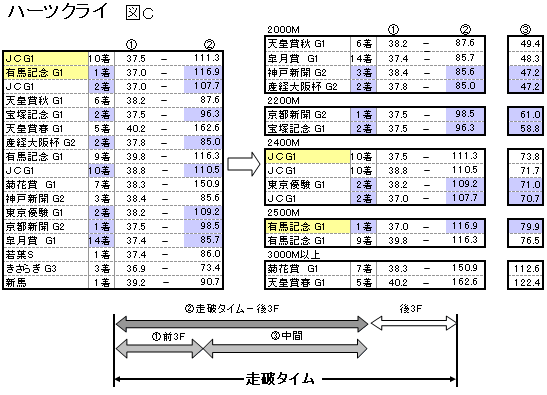
バルクのペースは苦手だった この図をよく見てもらえれば、ほとんどの場合、 「通過タイムが遅い場合に凡走している」 ことがわかると思います。ただひとつ、「なら、有馬記念はどうやねん?」ってツッコまれるとキツイんですけど、これは芝での馬場差がまったく考慮されてない単純に時計だけの比較ですんで、すべてきっちり理論通りにはいきませんわ。またこここでは、あくまで大まかな「ラップの傾向」と掴むのが目的なんで、そこまで神経質になる必要はないと思います(^^;。 とにかく、中でも興味深いのが2400m。同じ競馬場なんで、比較しやすいですね。 注目すべきは③の中間タイム。これによって「中間でどれだけペースが緩んだか」がわかります。ここに注目すると、先行した昨年のJCは「極端に中間ラップが緩んだレース」で、ハーツクライには思いっきり不得意なレースだったことが伺えます。 以上を総合するとハーツクライは、実は位置取りが問題なんじゃなくて、 「中間が緩むと能力を発揮でず、中間がきつくなると好走するタイプ」 の可能性が高いことがわかります。 惨敗したJCを覚えている方がおられれば、3~4コーナーで前の馬に乗りかからん勢いでつんのめっていた姿を思い出してください。私は、最近主導権を握っても控え気味にレースを進めるコスモバルクが生み出すペースは、「ハーツクライには走りづらいんちゃうかなー」となんて思いながら観戦してました。 いや、これが事実というんではありませんねん。惨敗の理由には、こういった可能性もあるかも、というてるだけです。決め付けているわけではないんで、その点は注意して読んだってくださいね~(^^;。
重賞の常連を分析してみた! 実は今回、ここまでディープな話をするはずやなかったんですわ。これは本題の前の前振りなんです。しかし前振りだけで8割の文字量を使ってしまいました(^^;アセアセ。で、やっとこさの本題は、 「芝の重賞の常連でゼニになりそうな、“ラップ的見地からのタイプ分け”」 です。芝の重賞の常連には、 「GⅠでは掲示板も無理やけど、GⅡやったら着くらいあるかも? 勝ち負けはGⅢかオープン特別やないとムリやろ?」 みたいな、強いねんけど微妙やねん・・・…って馬って、腐るほどいてますよね(^^;。こういう馬って、買ったときは凡走、買わんかった激走して悩んでる方も多いんではないでしょうか? かくいうこのページの担当さんがその典型でして(^^;、「ラップ理論でどうにかなりませんか?」っていうことらしいですわ(^^;。「読者の皆さんの役にもたつし……」って、もっともらしい理屈いうてますけどね(^^;。 ということで作ってみたのが表Dです。
|
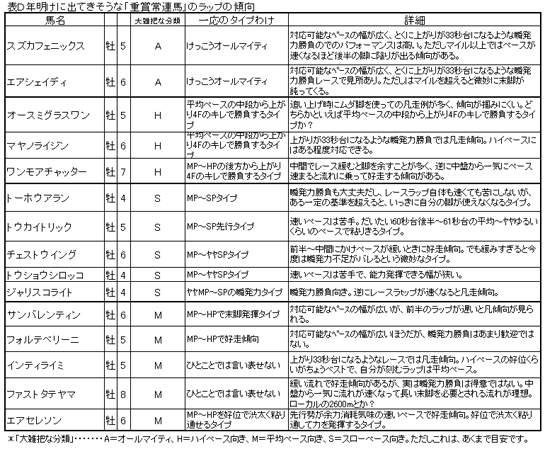 |
|
これは担当さんが出した、「年明けの重賞に出てきそうな重賞常連馬リスト」を私がラップ理論で一頭一頭分析したもんです。ご存知のように私は、稼ぎ場はもっぱら条件戦で重賞にはあまり興味がなくて、ろくにオープン馬の名前も知らんタイプ。それに「ラップ理論」は、馬場差の分析が難しい芝では、ダートよりは少し精度が落ちます。だから正直なところ、どこまでお役にたてるか自信はありません(^^;。でもま、重賞好きの担当さんの要望ってことで、ひとまず挑戦してみました。 一応いうておきますと、分析しながらもスズカフェニックスとエアシェイディは、「そのうちGⅡでもどうにかなるかも」って思いました。あくまで個人的な感想ですけどね(^^;。 あと表中の「大雑把な分類」は、馬券で役立てるために担当さんが強引に挿入したもんで、「絶対にこのタイプや!」ってもんでもないので、注意してみてください。 今回はちょっと強引やったかもしれませんけど、少しでも皆さんのお役立ちファクターになったらええんですけどね(^^)。
|
 |
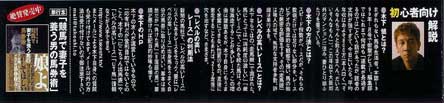 |
|
'07 1月号 2月号 3月号 4月号 5月号 6月号 7月号 8月号 9月号 10月号 11月号 12月号
'99 1月号 '00 1月号 '01 1月号 '02 1月号 '03 1月号 '04 1月号 '05 1月号 06 1月号
|