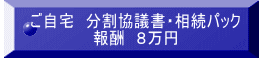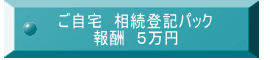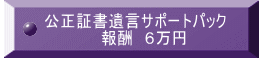成年後見制度について

「成年後見制度」とは、平成12年4月1日から、介護保険制度と共に新しくスタートた制度で、 認知症、知的障害、精神障害などにより、判断能力が十分でない方のために、援助者(成年後見人等)を選び、この援助者が、本人の財産管理をしたり、本人に代わって必要な契約をしたりすることにより、本人を保護・支援する制度です。
両親を亡くした未成年者のために親権者に代わる後見人が選ばれる「未成年後見」とは別に、判断能力が十分でない「成年者」のために援助者を選ぶ制度というわけです
「成年後見制度」には2種類あります
| 「成年後見制度」には、 | [法定後見制度] [任意後見制度] |
の2種類があります。 |
- [法定後見制度]
- 判断能力が不十分になった後に、 家庭裁判所によって援助者が選任されるという制度です。
この制度における援助者は、判断能力の程度により《成年後見人》《保佐人》《補助人》の3種類に分かれます。通常これらをあわせて「成年後見人等」 と呼びます。
詳しくはこちら
- [任意後見制度]
- 判断能力が不十分になる前に、将来に備えて、援助をしてもらう人を自分で選び、その人と、どのように援助してもらうかなどについて契約「任意後見契約」を結んでおくという制度です。
この制度における援助者を《任意後見人》と言います。
「任意後見契約」は、公証人により公正証書で作成してもらわなければなりません。
詳しくはこちら
禁治産・準禁治産との関係について
平成12年4月の法改正前は、民法に「禁治産・準禁治産」の制度がありましたが、平成12年4月から、新しく「成年後見制度」が施行され、
《禁治産者》は、⇒ 後見開始の審判を受けた《成年被後見人》とみなされ、
《準禁治産者》(心神耗弱の場合のみ)は、⇒ 補佐開始の審判を受けた《被保佐人》とみなされる
ことになりました。
従来は、禁治産・準禁治産者は戸籍に表示されましたが、成年後見制度が始まり、戸籍への記載に代わり、成年後見の登記がされるという制度に代わりました。
制度が代わると共に、従前の禁治産・準禁治産の戸籍の記載が削除されるわけではなく、従前の禁治産・準禁治産の戸籍の記載や後見人の権限は、従来どおり有効です。
戸籍の記載に抵抗がある場合や、成年後見制度を利用したい場合には、戸籍の記載を成年後見登記に移行する「移行の登記」を申請することができ、登記後、禁治産・準禁治産の表記の無い戸籍が再製されます。
成年後見登記制度について
成年後見登記とは、法定後見(成年後見、保佐、補助)および任意後見の当事者の住所・氏名や後見の内容を、登記するもので、東京法務局の後見登録課が、日本全国の登記を行っています。
- 登記の種類は次のとおりです
- ○法定後見の開始 … 家庭裁判所が申請
○任意後見監督人の選任 … 家庭裁判所が申請
○任意後見契約の締結 … 公証人が申請
○当事者の住所等の変更 … 本人、成年後見人等の 当事者
○後見の終了 … 本人、成年後見人等の 当事者
- この登記の内容を証明する書類
- ○後見の登記がされている方については、「登記事項証明書」
○後見の登記がされていない方については、「登記されていないことの証明書」
これらの証明書を申請できるのは、本人・配偶者・四親等内の親族・成年後見人等の一定の方に限られます。交付の申請は、東京法務局の他、全国の法務局及び地方法務局(本局)の戸籍課の窓口ですることがきます。
郵送(東京法務局宛)・オンラインで申請することも可能です。