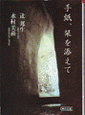|
|
|
|
1.続明暗 2.手紙、栞を添えて 3.本格小説 |
|
●「続 明暗」● ★★ 芸術選奨新人賞 |
|
|
1993年10月 2009年06月 1990/09/20
|
題名のとおり、漱石の未完作品「明暗」の結末を書いた“続編”です。
本書を読む直前に「明暗」を読み返したわけではありませんが、かなり漱石に似た雰囲気を出していて、よく書けているなあという印象を持ちました。会話の一言ずつが短いこと、文章が文きり調であること、形容詞に感じを使いたがること。漱石のみならず、明治期の小説の特徴だったように思います。 ストーリィは、漱石が書いても、そんなものになったのではないかと思われるものです。主要な登場人物は、津田、お延、津田の妹・秀、友人・小林、吉川夫人、そして清子。 この作品で最も感心したことは、何故清子が津田を見限ったかという問題に対して、解答を出したことです。「貴方という人は、最後のところで信用できない。結局、吉川夫人の言いなりになって、延の気持ちを考えないで行動するようなところがある..」 |
|
●「手紙、栞を添えて」(辻邦生共著)● ★★★ |
|
|
2001年06月
2003/11/22 |
なんと贅沢な一冊でしょうか。それもまあ、お手軽な文庫本であるというのに。オフ会で戴いた本なのですが、そうした経緯から魅力あふれる本に出会えるというのは、嬉しい限りです。
本書は、辻邦生さん、水村美苗さんという文学に精通したお2人による、文学を語った往復書簡集。1996.1.7〜97.7.27 2人の間で取り上げられるのは、国内外の今や古典的とも言うべき名作の数々。学生時代に、よく理解もできないまま盲目的に読みふけった作品が幾つもあります。 ※本書でとりあげられた作品を下記のとおり。それらを見ればこれ以上本書について語る必要はないでしょう。 |
|
※「手紙、栞に添えて」に取上げられた作品は次のとおり。青字は読んだことのある作品です。 |
| 水村美苗「続明暗」・「私小説」、辻邦生「西行花伝」、ディケンズ「ディヴィッド・コパフィールド」・「大いなる遺産」、吉川英治「宮本武蔵」、スピリ「アルプスの少女ハイジ」、オルコット「若草物語」、夏目漱石「坊っちゃん」、グリーン「失われた幼年時代」、J・ブロンテ「ジェーン・エア」、E・ブロンテ「嵐が丘」、二葉亭四迷「浮雲」、国木田独歩「忘れえぬ人々」、スピノザ「エチカ」、スタンダール「赤と黒」・「パルムの僧院」、樋口一葉「にごりえ・たけくらべ」、フローペール「ボヴァリー夫人」、中勘助「銀の匙」、バルザック「書簡集」、谷崎潤一郎「細雪」・「春琴抄」、「芥川龍之介全集」、永井荷風「摘録断腸亭日乗」、「ヘンリー・ミラー全集」、サンド「愛の妖精」、トルストイ「アンナ・カレーニナ」・「イワンのばか」、ドストエフスキー「貧しき人々」・「罪と罰」・「死の家の記録」・「地下室の手記」・「悪霊」・「カラマーゾフの兄弟」、ゴーゴリ「外套・鼻」、マン「ブッデンブローク家の人びと」、プルースト「失われた時を求めて」、リルケ「マルテの手記」、チェーホフ「中二階のある家」、幸田文「父・こんなこと」・「幸田文対話」、ラディゲ「ドルジェル伯の舞踏会」、太宰治「津軽」、ギッシング「ヘンリ・ライクロフトの私記」、ゲーテ「南イタリア周遊記」・「イタリア紀行」、ルソー「孤独な散歩者の夢想」、ソポクレス「オイディプス王」、アリストテレス「詩学」、ダンテ「神曲」、ブルクハルト「イタリア・ルネサンスの文化」、森鴎外「渋江抽斎」、ショーロホフ「静かなドン」、紫式部「源氏物語」、ボルヘス「伝奇集」、菅原孝標女「更級日記」、魯迅「阿Q正伝・狂人日記」・「魯迅選集」、カルペンティエル「バロック協奏曲」・「失われた足跡」、オースティン「高慢と偏見」 |
|
●「本格小説」● ★★ 読売文学賞 |
|
|
2005年12月 2003/02/25
|
本書を読む以前に、まず題名に戸惑いがありました。“本格”とは、いったい何を意味するものなのか。 著者自身の思い出を皮切りに、祐介という青年と知り合い、その祐介が冨美子という女性から聴いた話を著者に語る、という筋立て。そして、冨美子が物語ったのは、かつて彼女が女中奉公をしていた旧家にまつわる出来事という、まさに本格小説にふさわしい設定です。 |
|
●「日本語が亡びるとき−英語の世紀の中で−」● ★★ 小林秀雄賞 |
|
|
2009/03/07
|
本書表題の意味、副題を知ればある程度それは察することができます。 インターネットの普及、グローバル化の広がりによって今や普遍語の位置を獲得した英語。その英語と日本語を単に対極的に見比べるのではなく、言語という存在の成り立ちから考察を繰り広げていったところが、水村さんの面目躍如たるところ。 日本人なら誰でもきっと、英語も自在に操れることができたらどんなに良いだろうと思う筈。でもそこで考える英語とは、道具としての英語。その英語と日本語を並べて考えるのなら、日本語は単に道具に成り下がり、固有の文化としての言語の意味を失うことになる。 アイオワの空の下で<自分たちの言葉>で書く人々/パリでの話/地球のあちこちで<外の言葉>で書いていた人々/日本語という<国語>の誕生/日本近代文学の奇跡/インターネット時代の英語と<国語>/英語教育と日本語教育 |
|
●「母の遺産−新聞小説−」● ★★ 大佛次郎賞 |
|
|
2015年03月
|
「ママ、いったいいつになったら死んでくれるの?」 本ストーリィの母娘関係は極端な形で描かれていますが、老いて身体が弱り痴呆化も入り込んだ老親を、自らも既に中年から老年の域に至った子供が世話あるいは介護するという構図は、今の日本においては誰もが覚悟しなくてはいけない重い課題であると思います。 |