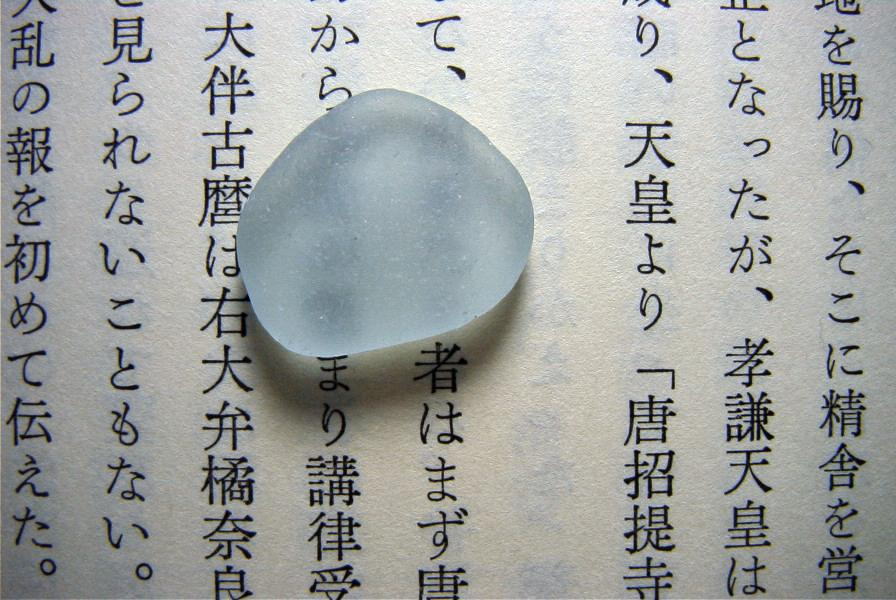とりあえずビール 2001
とりあえずビール 2001
First of all, beer! 2001
年賀状
- 2001年1月 年賀状で手書きの文字が全くないものは寂しい。数年前までは毛筆で宛名、本文とも全て手書きで書いていたが、書くほうも疲れるが受け取った方も疲れるのではないかと思い、宛名を手書きに、本分はパソコンで作ることにした。ただ、少しそっけないので、手書きの一文を添えることにした。これは今年の年賀状の写真で、98年に訪れた奈良の慈光院にある片桐石州作の4つの手水鉢と蹲のうちの一つを撮ったもの。
木蓮
- 2月4日(日)、今は「早春賦」の歌にある季節だ。外を歩くと椿や梅の一部は咲き始めており、木蓮の蕾もふくらんでいる。ただし「春は名のみの風の寒さ」は続いている。歌詞に「いかにせよとのこの頃か」とあるのが、いかにも人事異動の季節に思えて、なお寒い。「週間文春」連載の椎名誠さんの「新宿赤マント」の先週のタイトルが「二月はキライだ」であった。キライな理由のなかに、ビールがいまいちである、とういのがあり、これはこのページを「とりあえずビール」と命名した私にはよくわかる。私は2月は嫌いではないが、この頃の不安定な気持ちと天候は好きではない。あまり深いお付き合いはしたくない。春よ、来い。
ミッシャ・マイスキー
- 2月7日(水)、サントリーホールでハンガリー放送交響楽団の公演を聴いた。ドボルザークの「チェロ協奏曲ロ短調」とベートーベンの「田園」。チェロはミッシャ・マイスキー。配偶者を誘ったが、「来生たかおなら行くけど」とのことで、身代わりとして19歳の長男を犠牲者として推薦してきた。彼の趣味は「福山雅治」だが仕方がない。午後5時30分の約束の時間に、雨の溜池山王駅の13番出口に傘をさして出頭していた。我慢するのも人生だ。席はオーケストラの真後ろではあったが、それなりに楽しめた。風邪が流行っているせいなのか、チェロの独奏部で、咳払いがときおり聞えたが、致命的ではなかった。ただし最前列の一人の女性が熟睡していたのには他人事ながら少し緊張した。ミッシャは気づいていただろうな。アンコールは3曲。指揮者のタマーシュ・ヴァーシャは1933年生まれにしては若々しい。ホールを出たら雨が雪に変わっていた。
鑑真和上展
- 2月17日(土)、東京都美術館で「鑑真和上展」を見る。唐招提寺では開山忌でしか拝観できない鑑真さんが、金堂の平成大修理のために御自ら勧進なさっているとあれば、お目にかからないわけにはいかない。御像に対面すると、しばらくして、これはまぎれもなく鑑真さんご本人だと思えてくる。弟子達が師の入寂を予知して造っただけのことはある。さらに見るうちに、鑑真さんが命を賭けてまで日本に伝えようとした、あるいは伝えたかも知れない理想が千年を経て、日本人のどこに、どう残っているのかと、絶望にも似た気持ちがこみあげてきた。心の安らぎよりも、深く恥を感じた一日になった。
鈴木重子さん
- 3月4日、鈴木重子さんのCDを聴いた。昨夜のラジオのトーク&ミュージック番組でたまたま聴いて、今日さっそく山野楽器に行ってみた。Jazzのところに彼女のコーナーがあり、数枚のアルバムが並んでいた。その中から最近の(と思われる)「Just Beside You」を選んだ。ライナーノーツを見て少し驚いた。ご本人とファンの方には申し上げにくいが、昨夜のラジオからの想像とはかなり違った。どう違ったかは言えないが、少なくとも良い方に違ったとだけは言える。聴く人の傍で、聴く人のために語りかけている。「Just Beside You」のタイトルどおりだと思った。
興福寺
- 奈良の興福寺さんから4月〜9月の文化講座の予定のお知らせをいただいた。テーマは「奈良をめぐる中世神話」とのことだ。2000年は運慶・快慶の鎌倉の世界、99年は阿修羅の世界だったが、いよいよ中世に入った。中世は鎌倉、南北朝、室町時代の総称だが、藤原氏の氏寺である興福寺にとっての中世はどういうものだったかは興味深い。室町時代は農村が豊かになり、貨幣経済の浸透とともに「個」の思想が生まれ、今の日本人の原形を作った時代だと教わってきた。民衆、自治、銭、畳、一日3食、能。司馬遼太郎さんの85年の講演で、能が分かるのはなかなかの人で、仮に平安時代だと清少納言ぐらいにしかわからないもしれないが、庶民にはわからない。ところが、室町時代になると庶民にもわかるようになった。それがわれわれの文化の基礎になり、遺伝子に組み込まれた、と語られている。興福寺はこの時代も奈良一円を治めており、足利義満と並んで能の重要なパトロンでもあった訳で、4月からの講座ではそういう話も期待できるかもしれない。
イタリア・ルネサンス展
- 3月22日、健康診断のための休暇。帰りに上野の西洋美術館で『イタリア・ルネサンス-宮廷と都市の文化展』を見た。ボッティチェルリ、ラファエロ、ミケランジェロとダヴィンチなど、178点の作品が出展されていた。イタリアに何度行っても、とても全部を回りきれない60を超える美術館などからの一大作品群である。ルネサンスは1434年にコジモ・デ・メディチがフィレンツェを掌握した頃から始まり、東ローマ帝国の滅亡、大航海時代、宗教改革と続く。日本では土一揆から応仁の乱を経て戦国時代に到る時期で、蓮如に代表される宗教改革も始まっており、イタリアと日本でほぼ同時期に中世を破り、次の時代を作る動きがあったことは面白い。ルネサンス末期の1534年にイエズス会ができたが、その前年には信長が誕生しており、ザヴィエルが鹿児島にきた1549年には日本人は鉄砲で征服される民族ではなく、持ってきた鉄砲を買いつけて大量生産する能力を持っていた。歴史のきわどさであり、室町という時代がなければ、日本は圧倒的な富と武力を持ったルネサンス以後のヨーロッパを主人として迎えたはずだと思う。そんな気持ちで会場を巡ると、改めてルネサンスの巨匠達の精神の強靭さを思い知らされる。鑑賞するのにも体力と気力が必要だ。見終わった後で上野公園をややぐったりした気持ちで歩いた。桜開花までもう少し。
迷企羅と伐折羅
- 4月13日、新薬師寺の中田定観師から、私がかつてから抱いていた、同寺を詠った会津八一さんの歌への疑問についてお答えをいただいた。「鹿鳴集・南京新唱」にある、「たびびとに ひらくみだうの しとみより 迷企羅がたちに あさひ さしたり」という歌の、「迷企羅」は、「伐折羅」のことではないか、なぜ「迷企羅」と詠まれたのか、という疑問である。結果は「新薬師寺本堂」に詳しく書いたので省くが、会津八一さんはそのことをご承知だった。名前など、どちらでも良いことなのであり、私の勉強不足だった。物知り顔で書いたばかりに、何も知らないことがばれてしまった。とはいっても、そのおかげで中田定観師のご教授をいただいたことが嬉しかった。奈良を訪れたときにはぜひお目にかかりたい。
醍醐寺展、都内散策
- 5月5日(土)、醍醐寺展を見る。賑わっていた。10時40分に見終わった後、都内を散歩する。上野広小路(うさぎやの最中・どら焼き)ーアメ横(焼き海苔30帖、コッペパン)ー湯島天神ー神田駿河台ー山の上ホテル(クッキー「ふわふわ」)ー小川町ー気象庁ー大手町ー日本橋室町ー小舟町ー人形町(重盛の人形焼、三原堂の最中・どら焼き)ー水天宮まで。( )内は配偶者が買ったもの。まるで買い出しだ。しかも殆どがあんこ入り。水天宮から半蔵門線で帰る。
青葉台
- 5月12日(土)夜、横浜市青葉台フィリアホールで開催された混声合唱団”Yokohama
Rosenchor”定期演奏会へ行く。立原道造作詞、小林秀雄作曲の合唱曲集など約20曲を楽しく聴いた。最終曲はウェルナーの「野ばら」。帰る途中、「だが、たった一度も言ひはしなかつた 私はおまへを愛してゐると おまへは私を愛してゐるかと」(立原道造「爽やかな五月に」)「行ってしまった遠くの方へ すぎた日頃はよい日であつた」(堀口大學「すぎた日頃」)などの歌がいつまでも耳に残った。ちなみに、テノールのS氏は当然のことながらカラオケも抜群に巧い。近いうちに「TSUNAMI」をリクエストしたい。
室生寺再訪
- 6月17日(日)、久しぶりに奈良を歩いた。京都から近鉄で室生寺へ。室生口大野から室生寺までのタクシーの運転手は太田さんといい、以前、土門拳さんを室生寺まで何度も案内されたとのこと。現在72歳ということを復路、別の方からうかがった。途中、「大野寺は室生寺の西の門といわれています。真言宗なので長谷寺とも人の行き来があったのです。」などと名調子で説明していただいた。修復が終った五重塔は以前と変わった感じはなく、そこに佇んでいた。もちろん、柱や垂木は朱に塗られ、桧皮の屋根は以前の苔むしたものから比べれば当然にも新しかったが、人が変わってしまったような感じは微塵もなかった。もともとこの塔は少女のようでもあり、それが化粧をし直したような風情だ。少女といえば、金堂の十一面観音さんは昨年東京国立博物館に来られたときはとてもあでやかな印象を受けたが、この日は諸仏の中でつつましやかに立っておられた。門前の橋本屋の山菜定食で昼食。約1キロ上流の竜穴神社まで歩いて往復。
- 桜井に戻り、巻向下車。山の辺の道のあたりを歩いて景行天皇陵、射佐那岐神社、崇神天皇陵、黒塚古墳を訪ね、柳本へ。JR奈良に着いたのは5時半頃。商店街をまっすぐ興福寺まで歩き、猿沢池から中金堂発掘調査中の境内を抜けて夕陽の残る東大寺転害門、戒壇院へ。ここで陽は沈み、私も力尽きた。
辻邦夫さん
- 7月31日、辻邦生さんの「背教者ユリアヌス」を読み終わった。恋愛小説としても歴史小説としても面白い。キリスト教がローマという普遍的な国家との出会いがあってはじめて世界的な宗教になった、その経緯がよくわかる。ローマの世界が徹底的に「此岸」での人間の理想を追求したのに対し、キリスト教は「彼岸」での理想の実現を主張した。「彼岸」とは「精神世界」と言い換えても良い。「カエサルのものはカエサルへ」とはものごとを正確に理解した宗教家・キリストの言葉であったはずだ。だが、死後に楽園が本当にあると信じる人は、現世と自分の命を相対的に軽んじる。織田信長が「厭離穢土・欣求浄土」をスローガンにした一向宗と極限までに対立したように、ユリアヌスは現世でしか人間が実現できる理想はないと信じたが故に最後までキリスト教と相容れなかった。彼は西欧の精神史を形成する、その分水嶺に立っていたのだ、と思った。
- ところで、辻さんの作品に「フーシエ革命暦」(文藝春秋)がある。これは第2巻で終っている。辻さんが亡くなられたからだが、「文學界」の1989年4月までの連載分までが載っている。最後の文章はフランス革命の日の夜の、「その夜は、九時近くには、街々から人影はなくなった。夜に入って間もなく雨が激しく降りはじめたからだが、やはり人々は無意識の中にも何かある大きなものが音を立てて崩れたのを-そしてそれに力のすべてを使い尽くしたのを感じていたからであろう。ともあれ七月十四日はこうして長い長い一日を閉じたのである。」で終る。この続きをぜひ読みたい。「文學界」の続きの原稿がどこまであるか知らないが、一行でもよいから読みたい。
夏のオリオン
- 8月12日から1週間、国東に帰省した。35度前後の暑い日が続いたが、それでも朝方は肌寒いほどだった。夜明け前の東の空に三日月と金星、オリオン座が驚くほど明るく輝いていた。オリオンが冬の夜だけのものではないことを知った。千燈寺の不動山に登り、復路久しぶりに宇佐神宮を訪れた。
興福寺文化講座
- 9月14日、奈良興福寺文化講座のご案内をいただいた。10月から来年3月までのテーマは「能の視線」である。能の完成者である観阿弥、世阿弥父子は興福寺の儀式に参勤する結崎(観世)座の座長でもあった。講師は法政大学の能楽研究所西野春雄所長他の方々で、場所はいつもの日比谷の日生劇場。興福寺貫首の多川俊映氏の講話もある。師の話はおもしろい。いつも軽妙な語り口のなかに重要なテーマを伝えてくださる。仕事帰りにできるだけ参加したい。
稲村ガ崎、長谷
- 9月24日、抜けるような秋空だ。絵を描こうと思い、カンバスを抱えて出かけた。東林間から江ノ島に出て、さてどこにしようかと腰越漁港まで行ってみたが、気に入った風景がない。ついでだからと鎌倉に向って波打ち際を歩いた。風が強く、ときおり大きな波が足もとを掬うように襲うが、繰り返す波の音が快い。稲村ガ崎から振返ったら、海と江ノ島の向こうに白い雪をかぶった富士山がくっきりと立っている。これを描いたら銭湯の絵になってしまう。ペンキ絵描きは退職後の第二の職業として狙っている。今描くのは早過ぎる。間道を抜けて極楽寺まで歩くが、門前の狭い谷間にカンバスを広げる気はしない。坂を長谷の方に下り、ずいぶん久しぶりに長谷寺を訪ねた。観音堂につづく石段に萩の花が枝垂れ、秋の烈日が射している。十一面観音さんを拝観し、海を見た。すでに絵を描く気分ではない。門前の恵比寿屋で「黒餡女夫まんぢう」、帰りの藤沢のデパートの地下で華正楼の大月餅と中華饅頭を買う。同行しなかった配偶者からのリクエストだ。今日は何をしようとしたのか。まったく。
鎌倉 長谷寺の萩
楼蘭の宝石
- 12月2日、今年の秋は絵を描くこともなく過ぎた。先月父の三回忌を終えて、我に帰って辺りを見れば、周囲は既に晩秋から初冬の景色に変わっている。湘南海岸で拾ったガラスの破片は楼蘭の玉に見えないこともない。もとはラムネの瓶でもあったものか。
ウイルス感染
- 12月30日、ウイルス対策を終えて、3週間ぶりにホームページを再開しました。病に倒れた愛機BrezzaからDynabookにすべてのデータを移管しました。治癒したBrezzaは完全にリタイアさせたわけではなく、脇役に回ってもらっており、テレビとしても使っています。それにしても、ワームの影響はすさまじいものでした。12月11日から30日までの間、メールを未開封のまま全て削除し、一切の送受信を停止していました。あるいはお便りをいただきながらお返事を差し上げていない方もいらっしゃるかと思います。改めてお詫び申し上げます。

トップページへ
To the top page



![]() とりあえずビール 2001
とりあえずビール 2001