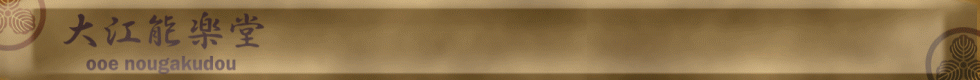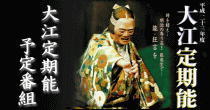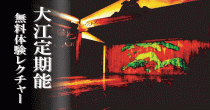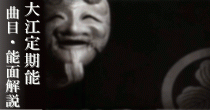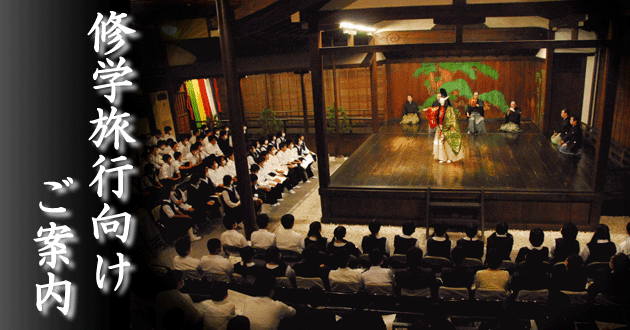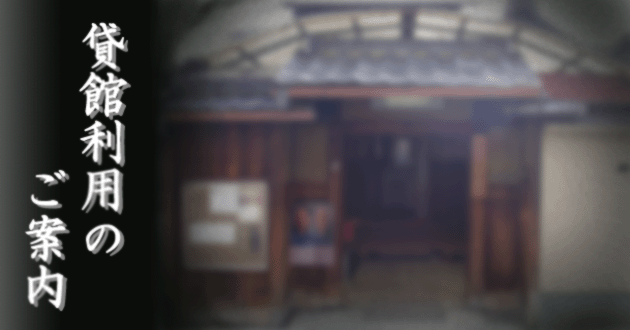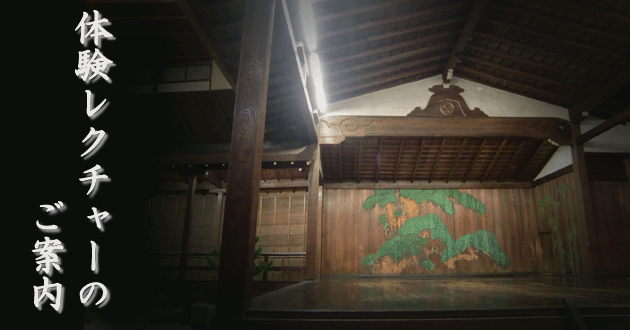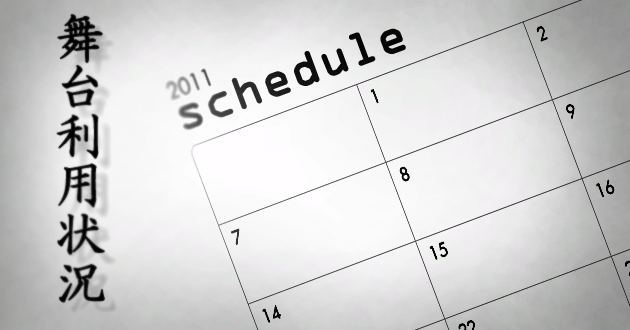能・藤について
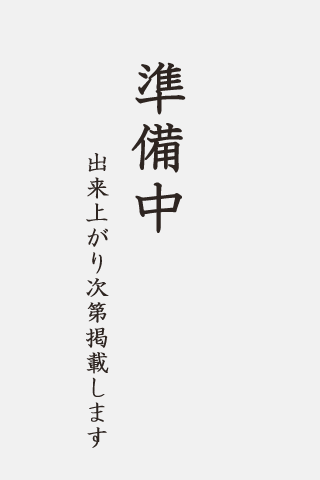
都の僧が加賀の国より善光寺へ向かう際に途中、藤の名所である越中の国多胡の浦(富山県氷見市)に立ち寄ります。折しも藤の花盛りであったので、僧は藤を眺めながら「おのが波に同じ末葉のしをれけり、藤咲く多胡の恨めしの身ぞ」という古歌を口ずさみます。すると一人の女が現れ、なぜ数ある藤を讃える古歌の中からその古歌を詠んだのですか、と僧を咎めます。僧はその女をあやしく思い身の上を訪ねます。すると女は自分は藤の精であると言い花の影に消えていきます。
<中入り>
多胡の浦で一夜を過ごそうと決めた僧は法華経を読誦して花の下に仮寝の夢を結ぼうとします。すると藤の精が再び現れ「読経のお礼に歌舞をなすために現れたのです」と伝えます。藤の精は春の夜の月に照らされる下、藤の名所多胡の浦の四季と藤の美しさ、また汀(みぎわ)の松に掛る藤の風情を謡い、舞い見せ、やがて曙の霞の中に消えてゆきます。
草木の精を主人公とした能はたくさんありますが、この藤という曲目は純粋に藤の美しさを表現している曲です。
能面「若女又は深井」について