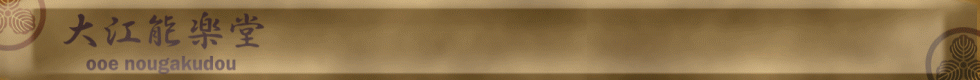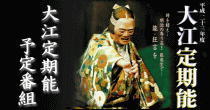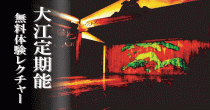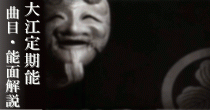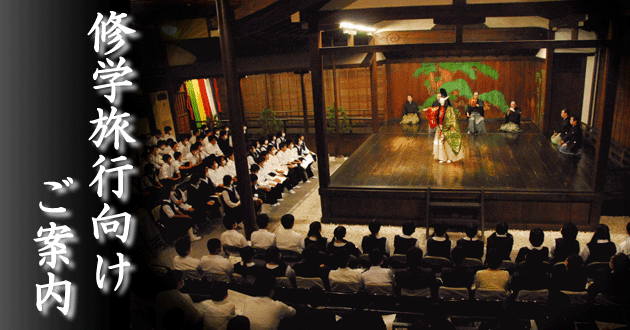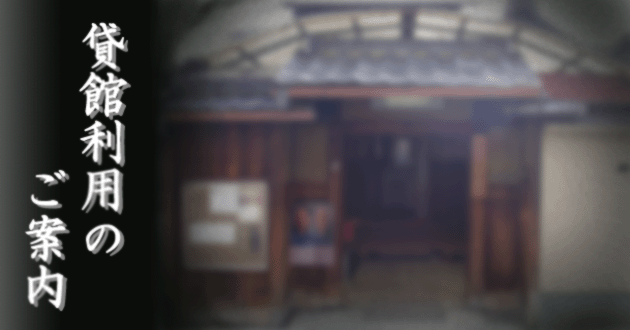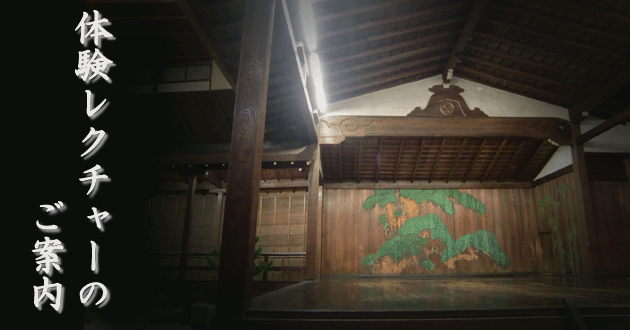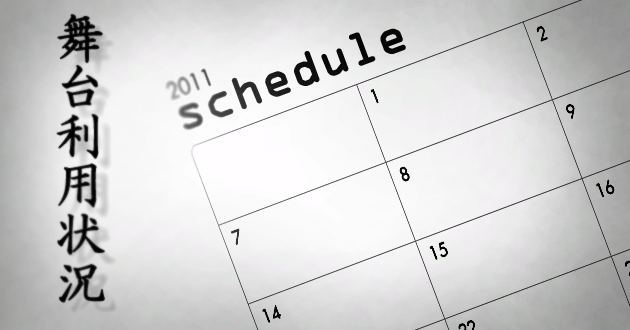能・海士について

房前ノ大臣(藤原房前)は讃州(香川県讃岐)志度の浦で没したという亡き母の菩提を弔うため従者を伴って遥々その地へやってきます。 すると一人の海人が現れたので、梅松布(藻)を狩るように命ずると女は、昔にも海底から名珠を取り上げるために潜った事があると言います。そして従者は女にその故事について詳しく語らせます。
ー昔、淡海公(藤原不比等)の妹君が唐の妃になられるにあたって唐土より三種の宝が贈られたが、その内、面向不背の玉だけがこの浦の沖で龍宮に取られてしまった。この事を淡海公は深く惜しまれ、身をやつしてこの浦に下り、海人乙女と契りを交わしその玉を取り返してくれるように頼みます。海人は玉を取り返したら我が子を世継ぎにすると言う約束をかわし、身を犠牲にして玉を龍宮より取り返し、その功により子が房前ノ大臣になったと語り、更に龍宮より玉を取り返した
有様を仕方話で語り、自分がその海人の幽霊だと明かし海中に姿を消します。
(中入)
大臣は浦の者からも玉取りの次第を聞き、亡母の残した手紙を読みます。するとそこには、自分がなくなってから13年間誰にも弔われず、今だ冥土の闇にいます。どうか弔ってください。とあり大臣は13回忌の追善供養を営みます。読経のうちに亡霊は龍女の姿となって現れ、法華経の功徳で成仏出来たと喜び舞をまいます。
能面「深井(フカイ)」について

能面「深井」は古くは、「深」や「深女」と書き「ふかいおんな」とも呼ばれていました。以前にも紹介しました若い女性の面とは違い、面全体に歳月を経た女性の表情が出ています。頬の肉付きは痩せており、筋肉のたるみによるえくぼ状の皺などがみられ、顎と額がやや突き出ています。ですが口元は若干増女にも似ており、若さも少し残っています。目はやや伏せがちに作られています。失った子供の行方を求め悲しむ母親や、夫と離れ物思いにふける心淋しい人妻などに使うことの多い面です。
名称の由来は年齢が深い、経験の深さ、心持の深さを示しているから深井と呼ばれている、或いはこの面の作者から深井と付けられた等、諸説あります。
深井の中にも若い表情の深井、老けた深井など種類があり、狂女物の曲目「百万」「隅田川」「三井寺」「桜川」などでも使われることが多い一方、普通の鬘物でも稀に使われることもあります。
能面「泥眼(デイガン)」について
後シテで使われる泥眼の解説はこちらでご覧ください。