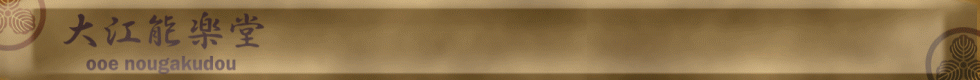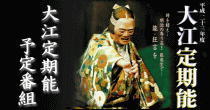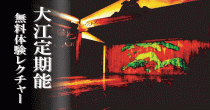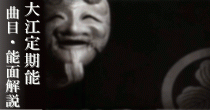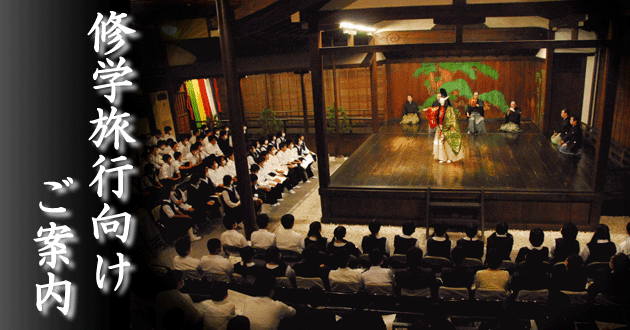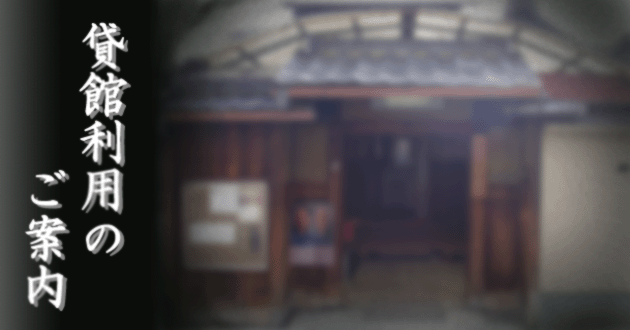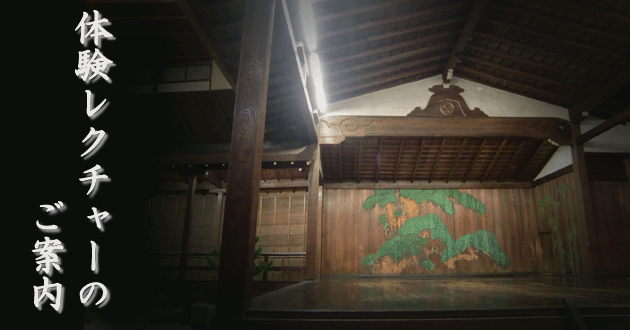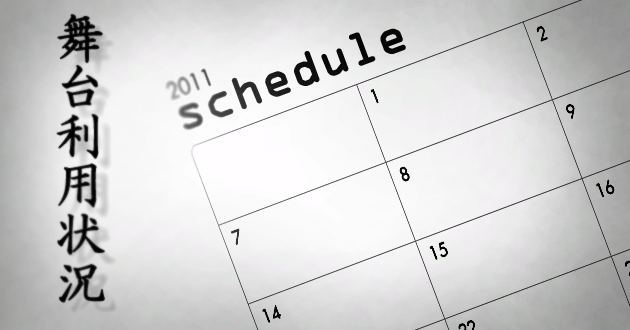能・東北について

東国より都へ上ってきた旅僧が東北院の和泉式部の住居跡を訪れます。花盛りを迎えている一本の梅の木を見て感じ入っていると一人の美しい里女が現れ話しかけてきます。里女は、その梅は現在「好文木」「和泉式部」「鴬宿梅」など様々に呼ばれているが、以前此処が上東門院の御所であった頃、和泉式部が植え「軒端の梅」と名付けた梅なのですとその由緒を語ります。そしてあの方丈は和泉式部の寝床をそのままに残したものなのですと教えます。「軒端の梅」は昔の主人・和泉式部を慕うかのように年々色も香も増して咲き続けていると伝え、実は私こそこの梅の主の和泉式部なのですと明かして花の影に消え失せます。<中入り>旅僧は東北院門前の者からも和泉式部の物語を聞き、梅の木陰で夜もすがら読経します。すると式部の霊が在りし日の美しい上臈の姿で現れます。そして、あなたが読誦していた法華経をその昔、藤原道真が高らかに誦しながらこの門前を通られるのを聞いて、「門の外、乗りの車の音を聞けば、我も火宅を出でにけるかな」と呼んだが、その功徳により死後火宅の苦しみを逃れ歌舞の菩薩になったと語ります。更に、和歌の徳や東北院の霊地であることを讃え、美しい舞を舞いやがて暇を告げて方丈に入ったかと思うと、僧の夢は覚めます。
能面「若女」について
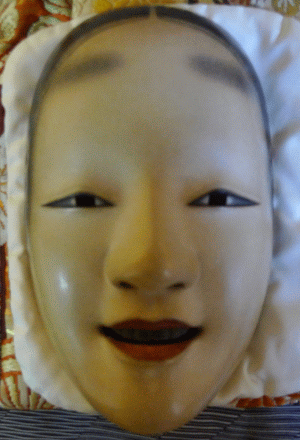
能面「若女」は節木増(昔、増女を節のある檜から作った面)と大変よく似ています。毛描は分け目から2本、鬘から下に3本、その2つを橋掛けるように3本描かれています。この点は節木増とは若干違います。ですが面の部位のつくりは大変似ております。小面よりも顔の部位(目、鼻、口)が詰まっており、全体が面の下のほうによっています。それにより小面よりも額の部分が広くなっており、顎の部分が短くなっています。頬の肉は小面よりも引き締まっており、理性的で品格のある顔立ちをしています。