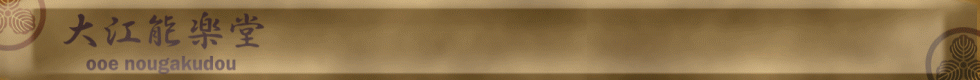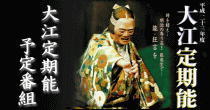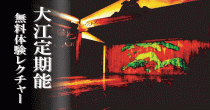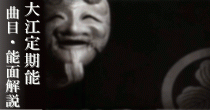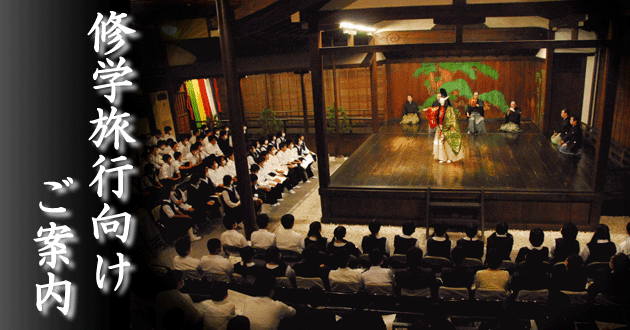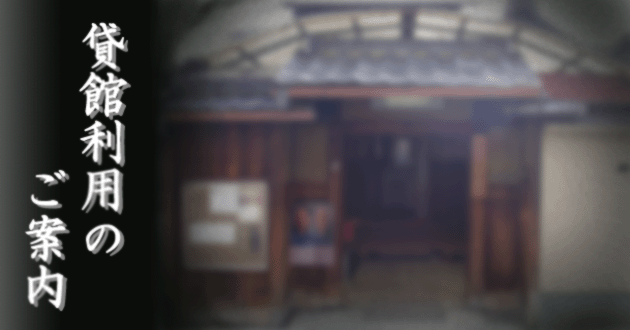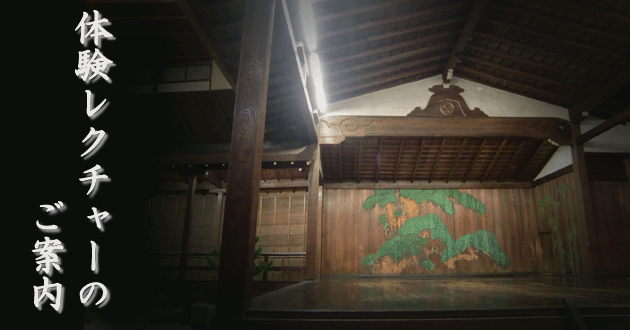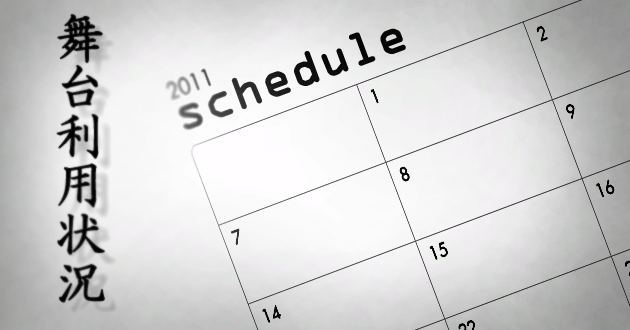能・安達原について

諸国行脚の紀州(現・和歌山県)那智の山伏、東光坊祐慶(とうこうぼうゆうけい)(ワキ)の一行が、陸奥・安達が原に着きます。荒野を行く途中に日が暮れてきたので、一軒の庵を見つけ宿を乞います。その庵から女(シテ)が一人現れ一度は断りますが、一行の所望に応じて迎え入れます。庵の内で祐慶が見馴れぬ枠桛輪(わくかせわ)(糸繰り車)について尋ねるので、女はそれを持ち出して糸を繰って見せます。やがて夜も更け寒くなってきたので女は、寒さをしのぐ薪を山へ採りに行くと言います。留守の間、閨(ねや)の内を決して見なさるなと言い置いて出かけます。
《中入り》
能力(アイ)は、女があまりにしつこく閨の内を見るなと言ったのでかえって不審に思い、祐慶(ワキ)に覗く許しを得ようとしますがなかなか許されません。能力(のうりき)は、山伏達(ワキ・ワキツレ)が寝入ったのを見て、そっと閨を覗きます。すると、そこには人の屍骸が山と重なっています。驚いた能力は、ここは鬼の棲家だと祐慶に告げます。祐慶も主の閨を見て、夥しい屍骸の数に驚いて一行は逃げ出します。それに気付いた先ほどの女は、恐ろしい鬼女の姿となって閨の内を見たことを恨みながら取って喰おうと追ってきます。山伏達は必死に祈り、鬼女は終に祈り伏せられ夜嵐に紛れて消え失せます。
『道成寺』『葵上』『安達原』この三曲は三鬼女とも呼ばれている曲目です。先の二曲が女性の恨みや執心を描いているのに対し、この安達原は世の無常さや人間の悲哀さを描いている作品です。前場では枠桛輪によって紡ぎだされる糸のように女の口から浮世の無常さ、若さを失い老いても尚生き続けて行かなければならない辛さが語られます。後場では、人の陰の部分を他人に見られた人間の恨みや悲しさを般若の面を用いて表現します。また『祈り』と呼ばれる鬼女と山伏のせめぎ合いの部分も見どころの一つです。
能面「深井」について
深井についての解説はこちらにございます。
能面「般若」について
般若についての解説はこちらにございます。