| トップページへ | 研究指針の目次 |
目次
211.1 まえがき
211.2 都市化と最高・最低気温の関係(復習)
211.3 用語の定義
211.4 解析方法
211.5 気温上昇率の季節ごとの比較
211.6 田舎と都市における昇温率の季節変化
(1)田舎観測所
(2)都市観測所
まとめ
文献
付録
付録1 図211.9
付録2 一覧表
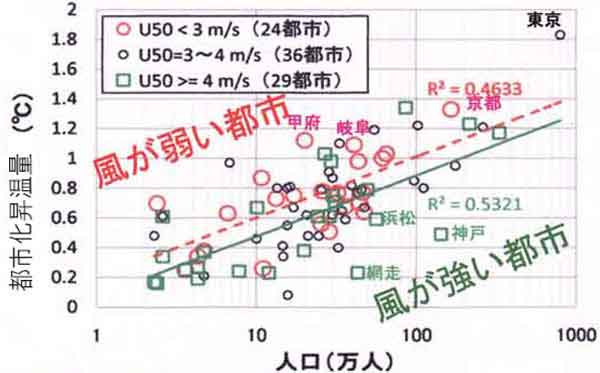
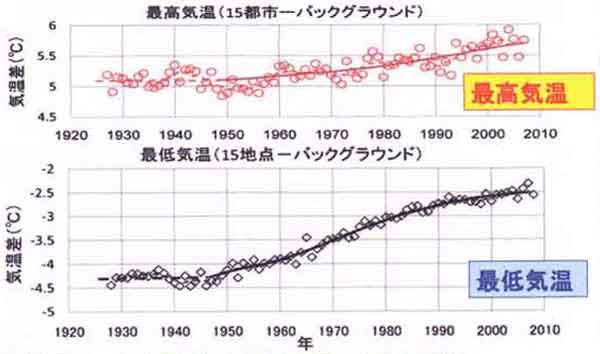
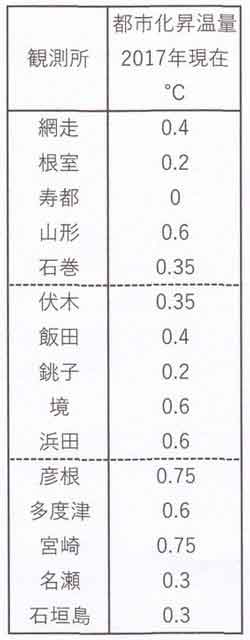
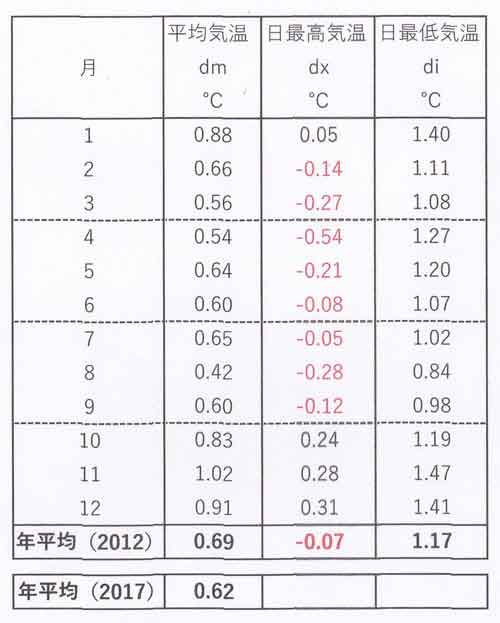
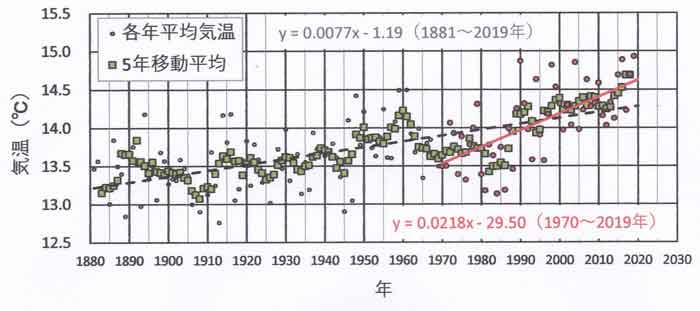
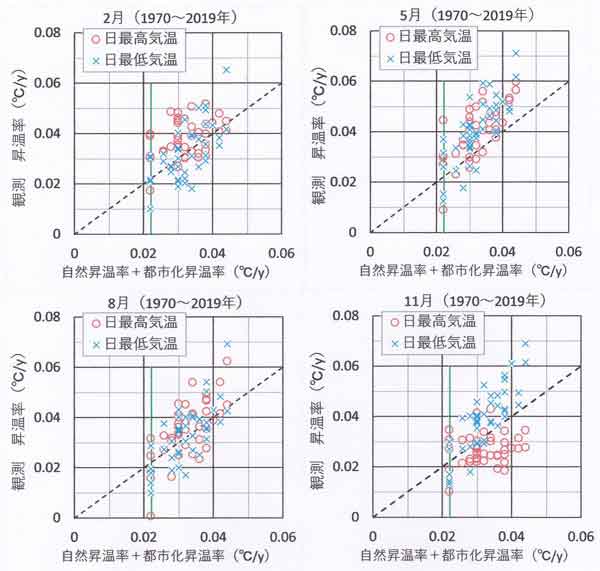
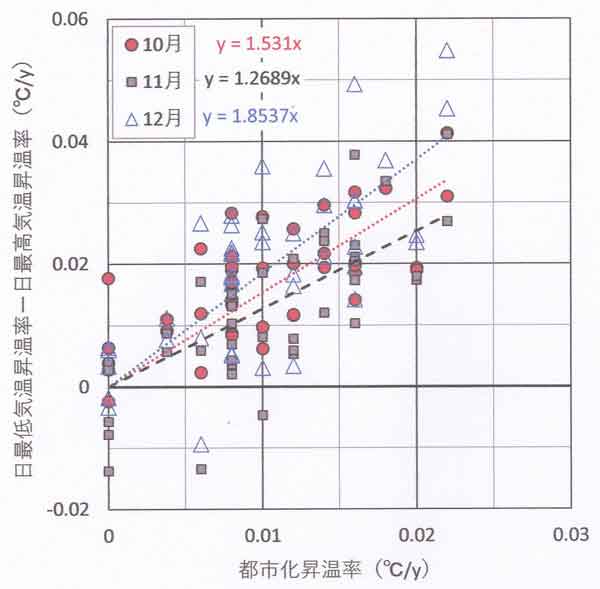
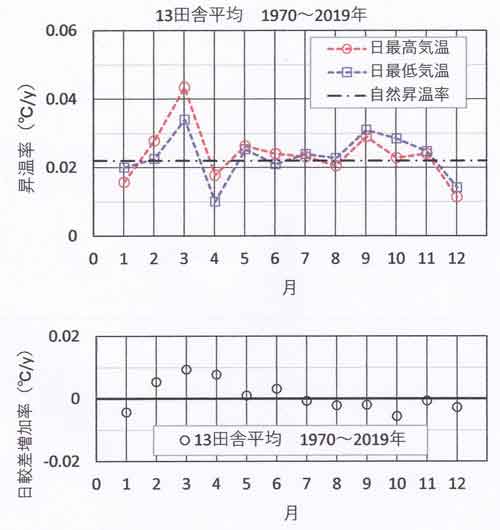
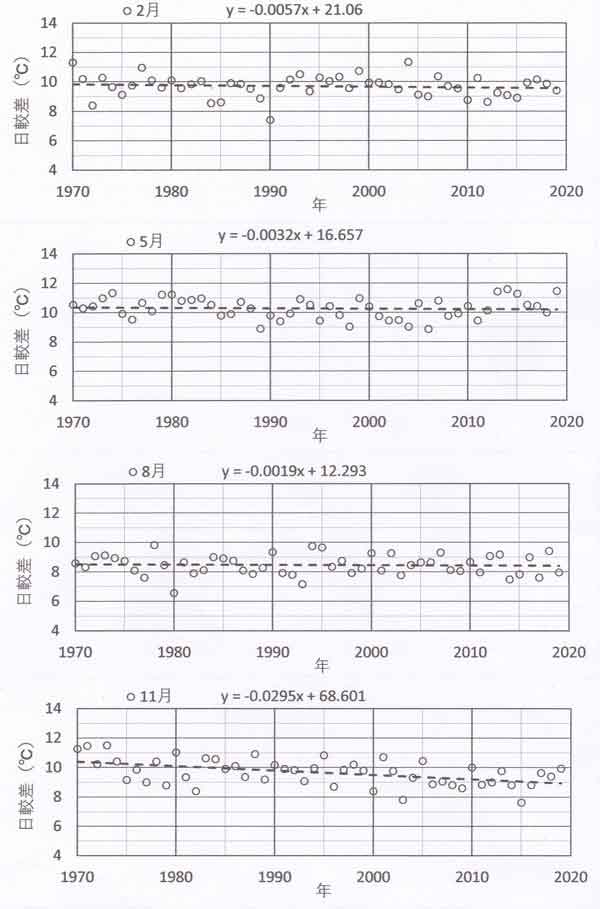
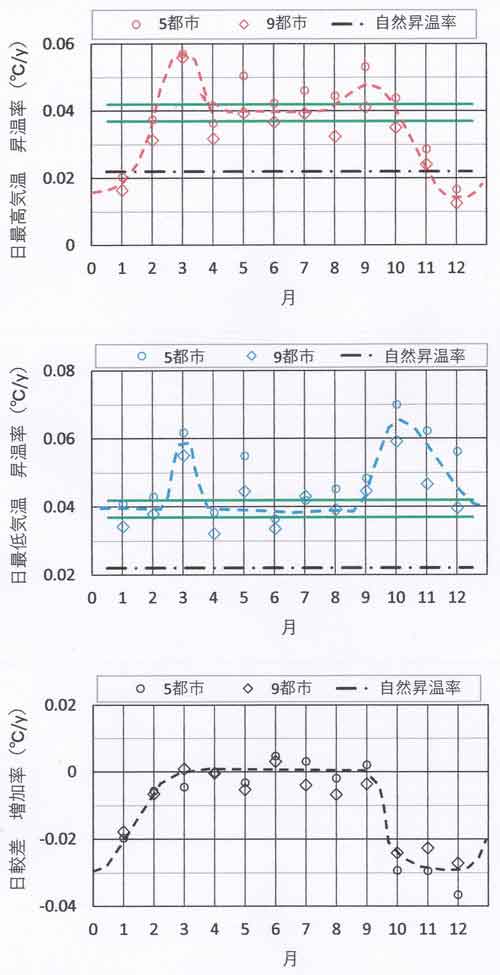
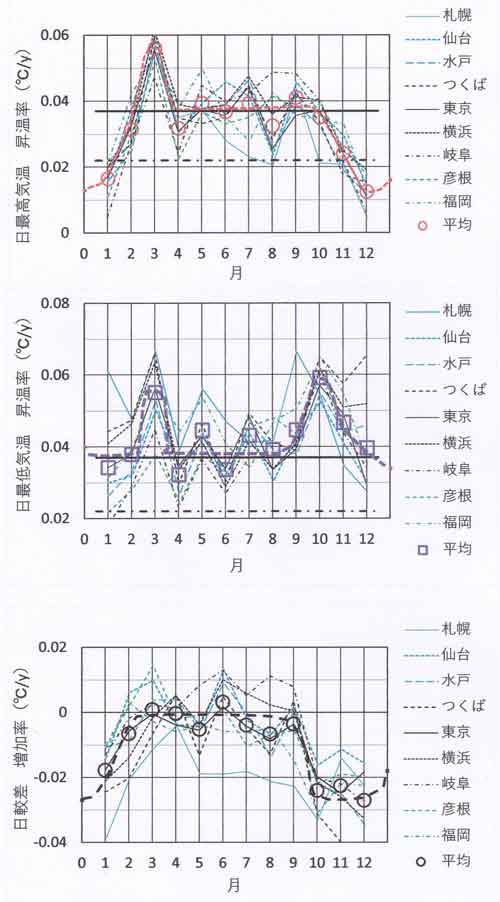
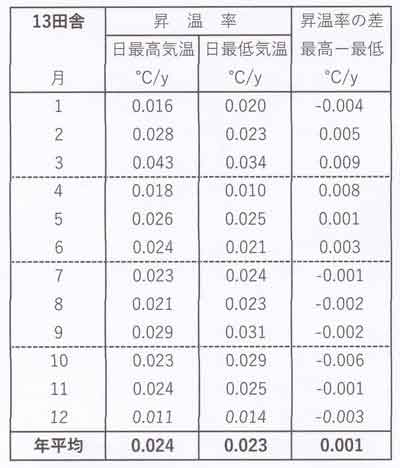
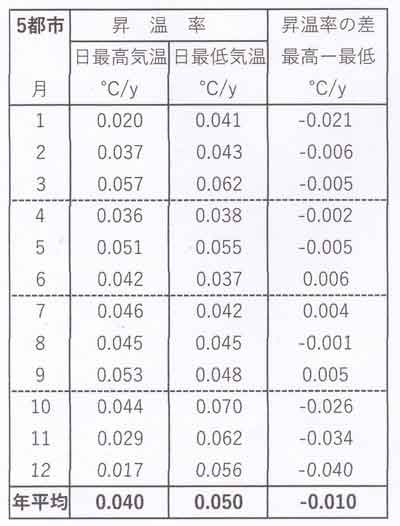
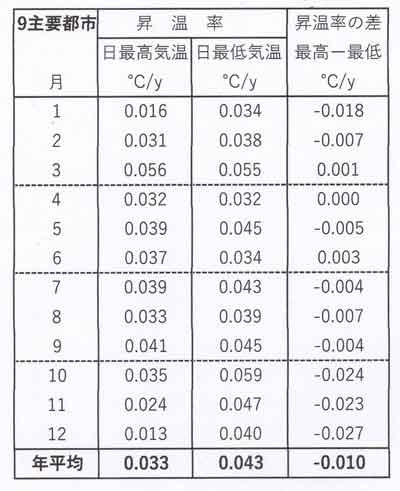
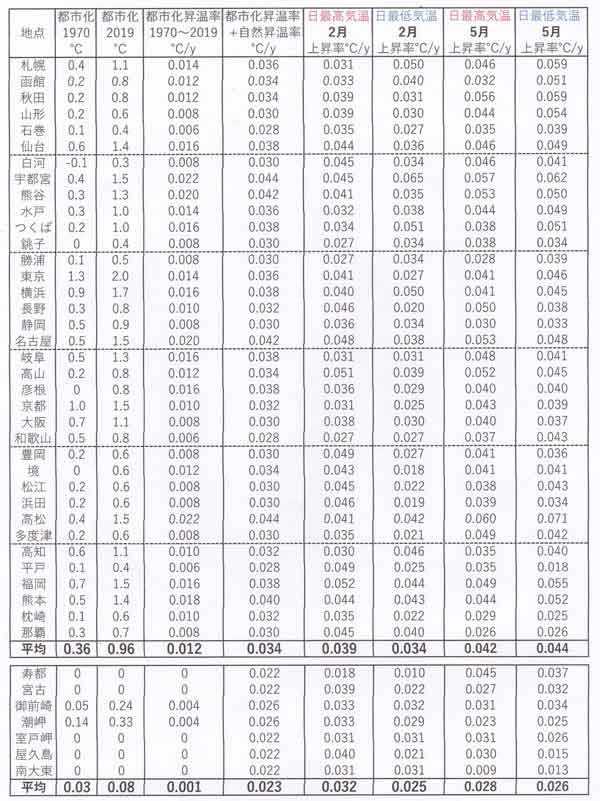
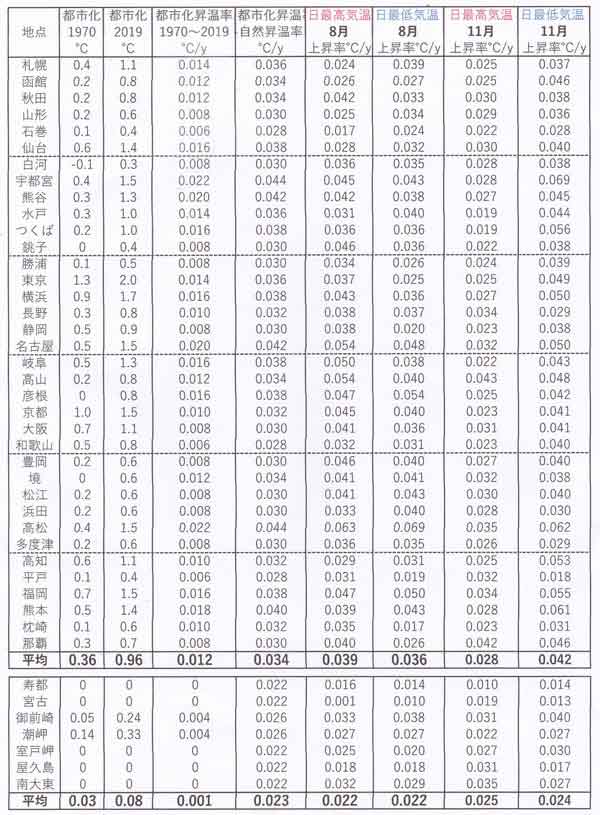
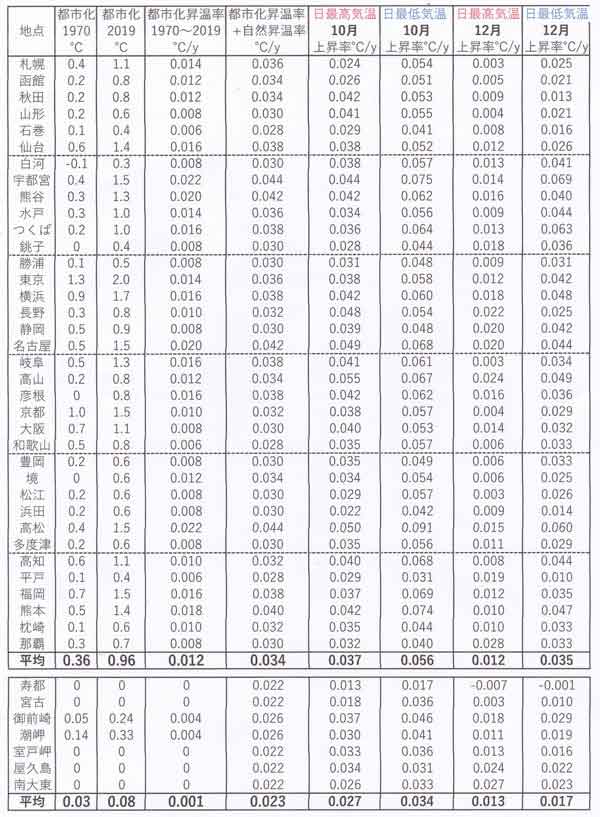
| トップページへ | 研究指針の目次 |