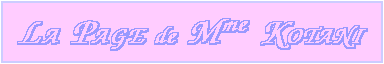 |
「VOW同人誌」連載エッセイ
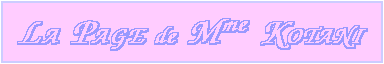 |
熱帯異常気象と地球環境学が専門のザイール人の大学教授との出会いは、私のものの見方を大きく変えた。
「北半球での大量生産・消費されたフロンガスの南極のオゾン層破壊、
中国大陸での石炭燃焼に伴う煙が一原因の日本での酸性雨、地球の肺とも言うべき熱帯雨林は東南アジアでは瀕死の状態、
南米アマゾンでは1年に1700万haが消失、残る中央アフリカの熱帯雨林もいずれ消える運命にある・・・
環境問題一つ取り上げても一地域、一国では問題を解決できない現状である。
自然を地球全体の大切な資源と考え、この限りあるものを地球全体の民で守らなければならない」・・・と。
アフリカの環境破壊はアフリカの貧困と無関係ではない。
そこで、アフリカ人の自立を助け、内在的可能性を引き出し、アフリカ人自身が自発的に環境に優しい開発を計り、
"Think globally, act locally"を実践せねばならないと熱く語り、自らこのための
支援運動を提唱・実践しているのである。
地球規模でものを見るということ、地球環境を守るというこの当然のことがなかなか簡単ではない。
この観点に立ってものを考えようとするとき、特に日本は後進国の部類にはいるのではないかと感じるのである。
この巨大な地球という生活空間に変化を与えようなんて大それたことは考えもしないし、できもしないが、指を加えて眺めるばかりで何もしなかったり、批判だけしているよりは、各自が自分のテリトリーでできることを実践すればよいのではないだろうか。
しかし、この単純な理屈が日本ではなかなか市民権を獲得してないという印象をアフリカの支援活動を通し受けることが多い。
私の印象では日本人は何に対しても「これはこうだ、あれはああだ」と枠を決めつけてしまおうとする傾向があるように思う。
自分の気持ちや意見の表明となると、状況に応じてのらりくらりと交わしたり、曖昧な言葉を都合良く使うのだが。
狭い国土に大勢がひしめき合っているなかで、うまく生き延びるための生活の知恵なのかもしれない。
時にはジャングルの法則の如く弱者を抑えつけ、時には出る杭が打たれないように「右に倣え」なのである。
もちろん各々の個性や置かれた環境によって異なってくるが、島国で、単一言語を使い、直接自分で異文化の交流をする機会は他国の人に比べて少ないのは確かである。
今、この枠を飛び出して様々な異文化を知り、生き方を問直してみる時ではないだろうか。
先に行われたタヒチ近海でのフランスの核実験後、強く感じたことである。
私のフランス語熱を知っている人達の多くが顔を合わせば、
「もうフランス語は止めたら!」
「フランスの話はしない方がいいよ!」とアドバイスに忙しかったのである。
 |
環境問題に関与した人、興味ある人を始め様々な人がタヒチ島に集結し、パペーテの町を焼き払っていたその時、偶然、私はフランス人の友人家族とその家族を訪ねてはるばる日本までやって来たフランス人夫婦と食事を共にしていた。
食後、テレビに映し出されるタヒチの様子にしばらく無言が続いたが、日本人と同じように公立の中学に通っている友人の息子が悲しそうにつぶやいた。
「又、学校で皆から僕が悪い事をしたように言われる」。
日本人にとって、政治レベルのことであろうが、個人レベルのことであろうがそんなこともお構いなく、
目の前に見えたことや自分の知りえた情報のみが全ての判断基準になるのである。
そのことで誰かがどんなに傷つこうが無神経なのである。
自分達の日常生活に、即座に、しかも、直接に響いてこないから、無責任なレッテルを貼るのである。
つづく
 人間・この彷徨の旅路:part3
人間・この彷徨の旅路:part3
 HOME PAGE de Mme KOTANI
HOME PAGE de Mme KOTANI