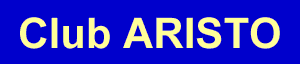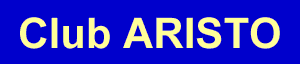[純正ヘッドランプの分解]
つぎに、ARISTO純正のディスチャージヘッドランプユニットを分解し、マルチプロジェクターヘッドランプを取り付けられるよう加工しました。あわせて、今回の移植のキモである、「オートレベリング機能」の動きについても調べてみました。
| [写真11] |
|
 |
- ARISTO純正のディスチャージヘッドランプユニットです。(写真11)
- 現車に付いているものを取り外してしまうと、作製中は車に乗れなくなってしまうため、今回は新品のユニットを用意しました。
- 写真は、後期型のブラックメッキ仕様です。
|
| [写真12] |
|
 |
- クリヤカバーとヘッドランプユニット本体とを分離します。(写真12)
- 分離するためには、両者の隙間を埋めている防水コーキングを温めて柔らかくします。
- これには、業務用のヒートガンで熱する方法と、熱湯に浸けて温める方法とがあります。
- ちなみに、失敗した場合には、ヘッドランプユニットのカバーだけを購入することができます。
-
| 品名 |
品番 |
価格 |
始期−終期 |
| ヘッドランプユニット RH |
81130-30871 |
22,200円 |
9808〜0008 |
| ヘッドランプユニット LH |
81170-3A421 |
|
| [写真13] |
|
 |
- レンズ本体のハウジングが干渉してしまうため、ヘッドランプユニットの一部を加工します。(写真13)
- リフレクターの円筒形に張り出している部分を、奥から30mmほど削り取ります。
- ちょうどこの部分は、「高輝度白色LEDポジションランプ」を取り付けた際に、光が遮られてしまうところでもあります。
- 削り取ることにより、白色LEDの光を活かすことができます。
- なお、リフレクター表面は、非常に傷つきやすい素材で出来ているため、取り扱いは慎重に行います。
|
| [写真14] |
|
 |
- リフレクターを加工したついでに、全体をGT-R(BNR32)の純正塗装色である「ガングレーメタリック(KH2)」に塗装してみました。(写真14)
- あわせて、ターンシグナルランプ(ウィンカー)のクリヤ化も行いました。
- リフレクターを塗装する際は、必ず600番と1000番のサンドペーパーを掛けて、足付けをしておきます。
- ただし、ウィンカーの入る部分だけはマスキングして、メッキを残しておきます。
- (芸が細かいでしょ?)
- ウィンカーのクリヤ化は、レンズとリフレクターとの間に、オレンジ色のプラスチック板が入っているので、これを取り外します。
- リフレクターのブラックアウトとウィンカーのクリア化により、フロントマスクがどのように変化するか、とても楽しみです。
|
| [写真15] |
|
 |
- HIDバーナーが取り付けられるリフレクターです。(写真15)
- ユニット本体へは、3ヵ所で固定されます。
- 上側の2つは、ボルトで固定され、左右および上下方向への光軸調整ができるようになっています。
- 下側の1つは、オートレベリングの制御用モーターのシャフトに繋がります。
- 今回は、3ヵ所に付いている固定用のコネクタを、そのまま流用します。
- コネクタは、上下にある小さなツメで固定されているため、ツメを折らないように慎重に取り外します。
|
| [写真16] |
|
 |
- これが、ヘッドランプのオートレベリングを実現するための制御用モーターです。(写真16)
- モーターが回転することによって、シャフトが上下に伸び縮みするようになっています。
- 実際に、モーターを外した状態で実車に繋ぎ、どのような動作をするか実験してみました。
- イグニッションをONすると、制御系の正常性をチェックするため、いったん最も縮んだ状態になり、すぐに通常の状態に戻ります。
- その差は、約5〜6mmほどでした。
- フロントとリヤのシャフトの部分にハイトセンサーがあり、前後の傾きの違いから車の加重状態を割り出し、モーターを駆動してリフレクターの角度を調節し、適正な光軸となるよう制御しているのですね。
|
[ハウジングのメッキ加工]
HIDバーナーからの放射光の有効活用とヘッドランプ本体の外見向上のため、ハウジングをメッキ加工することにしました。
| [写真17] |
|
 |
- ハウジングをメッキ加工したものです。(写真17)
- 新型CIMAでは、マルチプロジェクターヘッドランプの周りはリフレクターで覆われていますが、今回の移植では、ヘッドランプ本体をそのまま利用します。
- ハウジングの元の状態では、金属の素地が剥き出しになっています。これでは、せっかくのHIDバーナーからの光が吸収され、熱に変わってしまいます。
- そこで、ハウジングをメッキ加工することにより、リフレクターとしての機能も持たせることにしました。
- 表面を鏡のようにピカピカにするためには、クロームメッキ処理をします。
- これにより、HIDバーナーの放った光を有効に利用できるだけでなく、ヘッドランプ本体の外見を向上することができます。
|
| [写真18] |
|
 |
- ハウジングには、右用と左用とがあります。(写真18)
- その違いは、ハウジングの側面にある四角い穴の位置です。
- この四角い穴があることによって、前方に光を収束するだけではなく、側方にも満遍なく光を広がらせています。
- 単にヘッドランプとしてだけではなく、コーナリングランプとしての機能も持ち合わせているのですね。
|
[バックプレートの作製]
マルチプロジェクターヘッドランプを純正ユニットに取り付けるため、バックプレートとステーを作製します。今回も、原寸に合わせて図面を起こし、金属加工屋さんにレーザー加工をお願いしました。
| [図面1] |
(画面をクリックするとPDFファイルを表示します) |
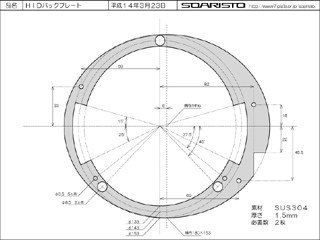 |
- ヘッドランプ本体を固定するためのバックプレートです。(図面1)
- 強度を考え、1.5mm厚のステンレス板(SUS304)としました。
- 左右対称です。
|
| [図面2] |
(画面をクリックするとPDFファイルを表示します) |
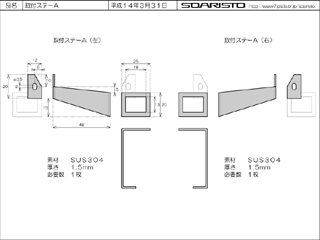 |
- バックプレートを固定するための取付ステーAです。(図面2)
- 右用と左用とがあります。
|
| [図面3] |
(画面をクリックするとPDFファイルを表示します) |
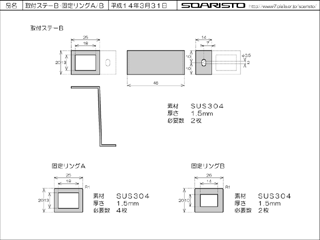 |
- バックプレートを固定するための取付ステーBと、固定リングA/Bです。(図面3)
- 固定リングAは取付ステーAと取付ステーBに、固定リングBは取付ステーC1/C2に、それぞれ組み合わせて使用します。
- 左右共通です。
|
| [図面4] |
(画面をクリックするとPDFファイルを表示します) |
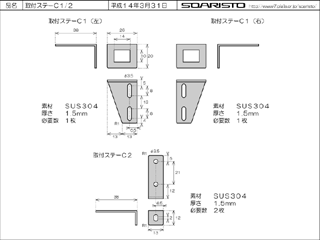 |
- バックプレートを固定するための取付ステーC1/C2です。(図面4)
- オートレベリングの制御用モーターへの取付位置を調整できるよう、長さを38〜46mmの間で可変としています。
- 取付ステーC1は右用と左用とがあり、取付ステーC2は左右共通です。
|