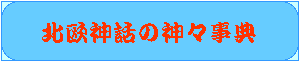 戻る
戻る
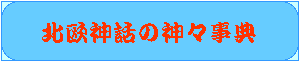 戻る
戻る
ハィニル / ヘーニル ![]() <音声クリック『エッダ』神話の中でもその重要さはあまりないとされてきた神。神話体系の中でもどのような位置を占めるかは明確ではない。
<音声クリック『エッダ』神話の中でもその重要さはあまりないとされてきた神。神話体系の中でもどのような位置を占めるかは明確ではない。
『巫女の予言』17節以降では、オゥジン、ハィニル、ロズルの三神が人間創造の神話挿話に姿を現しています。ハィニルは人間に「理性」を与える役割を担っています。「レギンの言葉」や「詩語法」37章には別 の三組の神としてオゥジンとロキに加えた三人目の神として登場します。しかしここでは目立った役割を果 たしてはいない、と考えられてきました。『巫女の予言』63章では、ラグナロクの後の新しい世界の中に現れるアゥス神族の中の一人に彼の名前が挙げられています。スカルド詩人ショウゾゥルヴル・ウール・フヴィーニによる『ホィストロング』の中でもシャツィの登場する神話に名前が挙げられています。ルドルフ・ジメックなどは、特別 な役割を与えられてはいないとしていますが、リチャード・ノースは、ロキとハィニルとの親密な関係を示す非常に稀な資料と解釈します。>『ホィストロング』追記参照
ハィニルの持つ受動的な性格は、スノッリの語るヴァン神族との戦争の神話挿話の中で語られます(「イングリンガ・サガ」4章)。アゥス神族はハィニルをヴァン神族に人質として与えます。ハィニルは背が高く、美形の男とされます。そのため、ヴァン神族は彼を首長にすえるのですが、ハィニル自身は賢いミーミルの助言に全て頼ります。しまいにはヴァン神族はこのことに気がつき、ミーミルの首を切るのです。
ハィニルは様々なケニングで描写されます。「素早いアゥス」「長い足」「裕福な王」などというケニングがありますが、如何なる意味なのか、今では不確かなものばかりなのです。
ハィニルの神話体系内の役割についての解釈は、非常に様々です。「大空・天空の神」「雲の神」「太陽神」あるいは「水の神」特に白鳥や鷺の姿の「鳥の神」が有名であり、オゥジンの知的能力を表す鳥の姿をした分身、という説まであります。これらの解釈はどれも不確かです。ド・フリース説による、「沈黙の神」「儀式を行う神」という解釈は、なかでも妥当性の高いものです。ノースは「若い雄鳥」を示す名前の語源的解釈から「勇猛果敢な性格」を読もうとしています。
バウギ / ボイギ Baugi<--音声をクリック スットゥングルの兄弟。オゥジンが蜜酒を盗むための手助けをしました。
兄スットゥングルと違って『エッダ詩』の中にはこの名前は登場しません。ラティという名の錐を使って、スットゥングルの娘グンロズのところまで届く穴を開けます。その穴を、オゥジンは蛇に姿を変えて、通り抜けるのです。バウギの名は、スノッリの「詩語法」にのみ残されています。巨人たちの名前を羅列する中にバウギの名も入っていますが(430番)、スットゥングルと兄弟であることは、スノッリの創作でしょう。>画像へ
『ハウク本』>『ホィクルの書』を見よ。
パウルス・ディアコヌス(Paulus Diaconus)(720年頃〜799年)ランゴバルド王国の貴族の生まれの僧侶。
パヴィアのランゴバルド王家の宮廷で教育を受けた後、アクイレイアにて助祭職に就いた。後にモンテ・カッシーノ修道院で過ごす。782年から786年の間、彼はフランク王国のシャルルマーニュ(カール大帝)の宮廷にいた。幾つもの書物を残したが、北欧神話に関わりのある最も重要な文献は『ランゴバルド族の歴史』(790年頃)である。その第一巻で、ランゴバルド族の起源や神話的伝承に言及している。これが北欧神話の理解に大いに貢献しているのである。、
ハッディングス:ハンディングス・サガを参照のこと。
バルドル:バルドゥル:バルデル(ON Baldr<--音声クリック, OE, OHG Balder) はゲルマン神話の中で最も重要な神の一人で、アィシルの一人。「バルドルの死」がゲルマン神話の中で中心的な役割を果たすのは確かだけれど、第二メルセブルクの呪文の中の短い言及を除くと、全ての資料はスカンディナヴィアの文献にのみ認められるのです。
スカンディナヴィアの文献資料は、大きくアイスランド−ノルウェー伝承とデンマーク伝承の二つに分けることができます。アイスランド人のスノッリはバルドル神話について最も詳しい記述を提供してくれています。『ギルヴィの惑わし』22章の中では、彼は簡潔にバルドルのことを「オゥジンの第二子であるバルドルについてはただ良いことだけが伝わっている。彼は全ての中で最もよく、誰もが彼については賞賛の言葉だけしか口にしない。彼の姿はそれは美しく、彼から光が出るほどまでに輝いて見える・・・彼はアィシルの中で最も賢く、最も弁が立ち、最も人に好ましい。ただ、彼について一つだけ問題なことがある。それは彼の決意は、長くは続かないことだ。彼はブレイザブリクに住んでいて、そこは天にあり、まったく汚れないところなのだ」
彼の母はフリッグ(『ギルヴィの惑わし』22章;「詩語法」21章)で、彼の妻はナンナ、彼の息子はフォルセティ(『ギルヴィの惑わし』32章;「詩語法」5章)です。バルドルはフリングホルニという船の所有者で、ドロイプニルという指輪も持っています(「詩語法」5章)。ラグナロクの後に彼はヘルから兄のホズルと共にやって来て、新しい世界に住むのです(『ギルヴィの惑わし』52章;『巫女の予言』61節)。
これに加えてスノッリは、そのエッダの中で、最も長い一節をかけてバルドルの死とその葬儀について詳細に語るのです。
バルドルを傷つけぬように、女神フリッグは全ての生きているものとそうでないものとに、バルドルを決して傷つけぬという誓いをたてさせ、唯一ヤドリギを除いて全ての事物から誓いをとります。ロキはそのことを聞くと、神々がバルドルの無謬性をためしながら、ものを投げても彼が傷つくことがないことを楽しんでいる場所に出てきます。ロキは盲目の神ホズルの手にヤドリギの枝を押しつけて(図版「ホズル」参照)、投げろとすすめます。ホズルがそれを投げると、それがバルドルの致命傷になったのです。(図版参照)。
このことは神々と人間との大いなる損失となりました。フリッグの願いによって、オゥジンの息子のヘルモゥズルがヘルの所まで馬で行き、バルドルを返すように言います。ヘルは、一つの条件を出し、それがかなえられればよいと答えます(図版参照)。すなわち、世界のすべてのものがバルドルの死を悼んで泣けばよいと言うのです。全世界はそこでバルドルの死を嘆くのですが、ただ一人、女巨人のソック(図版参照)だけが泣かないのでした。スノッリはこの女巨人は実はロキが変装したものだったと仄めかしています。しかしいずれにしても、そのようなためにバルドルは死の世界に留まることになりました。
一方神々(アィシル)はバルドルの葬儀の準備を整えます。バルドルは、夫が死んだ為哀しみのあまりに死んだナンナとともに、バルドル自身の船フリングホルニの上で荼毘に付されます(図版参照)。オゥジンは指輪ドレイプニルを、火葬に伏すために組まれた薪の上に載せるのでした。
スノッリが「バルドルの死」や「ヘルモゥズルのヘルへの下降譚」を物語るために用いた資料を探るとき、今は失われた詩篇についての疑問が持ち上がりました。バルドルの葬儀について語る中で、スノッリは「フース・ドラゥパ(家の讃歌)」に語られた形をなぞりました(「フース・ドラゥパ」は983年にウッギの息子ウルヴルというスカルド詩人によって書かれた詩で、アイスランドの祭礼のための館の木彫りについて描写したものです)。この資料に加えて、バルドルの死について語るエッダ詩片が幾つかあります(「バルドルの夢」「巫女の予言」31-33連、「ロキの口論」28連)。「巫女の予言」では、バルドルの死はラグナロクに続く端を発したものとされています。「ロキの口論」ではバルドルがもはや生きていないことは、ロキの過失によるのだ、と記されています。このことは、バルドルの死の原因となったこと、あるいはバルドルがヘルから戻れなかったことの原因のどちらも表している可能性があります。バルドル神話の中におけるロキの役割は、確かに古い伝承からのものだと思われます。
「バルドルの夢」についての予示的な記述は、デンマークにおけるこの神話伝承との関わりを示しています。というのも、この「バルドルの夢」の中には、ホズルへの復讐と、その復讐を成し遂げるためにオゥジンが女巨人のリンダとの間に復讐者を生ませたことが書かれていますが、これはデンマーク人歴史家のサクソ・グラマティクスの記述と合致するのです(『デーン人の事跡』三巻69章以降)。ナンナはバルデルスとホゼルス(ホズルのサクソによるラテン語形)の間の争いの種となります。初めはバルドルはナンナを手に入れたホゼルスに破れるのですが、その後の一連の勝利によりバルドルはデンマークの王となります。一方、ホゼルスは魔術を用いて、バルドルに唯一致命傷を与えることのできる剣で彼を刺してしまうのです。サクソは更に話を続けて、オゥジンがリンダを手に入れ、バルドルの復讐者であるボウスを産ませたことを綴ります。ボウスはホゼルスを殺しますが、彼自身も同時に死んでしまうのです。
バルドルがデンマークの王という話はサクソの創作ではなく、バルドルとレイレのデンマーク王朝とを結びつける古い伝承によっているのです。このことはアイスランド語で書かれた『ビャルキの言葉 Bjakamal』にもほのめかされていますが、また、バルドルの住まいがブレイザブリクという名前であるという事実が、17世紀のスウェーデン人の年代記作者ヨハンネス・メッセニウスによりデンマークのレイレ近くの(!)地名にブレデブリケ (Bredebliche) というものがあることを発見されたことにも促されています。
そういうわけで、バルドルがデンマーク王朝の神話的祖先であったことが考えられ、その仮説は、デーン人の影響のあるアングロ・サクソン年代記に記された王の系図に、バェルダェイという名がバルドルに置き換えられていることからも証明されます。
バルドルの名前の語源についても十分に説明されてはおりません。語源的解釈は例外なくどれもバルドル神話のそれぞれの解釈に基づいているのです。最も古いものは、この語の語幹をインド・ヨーロッパ語の語根*bhel-(白)(Cf. リトアニア語 baltas)から来ているものとし、それゆえ、彼を「光の神」と(ちょうどスノッリが語るように)解釈するのです。しかしながら、この考え方の他に、BaldrはOE bealdorと関係があり、実際の所「主人、主」を意味すると考えられます。したがってOHGの第二メルセブルクの呪文中の balder はこのように「人間の高貴な人物」を表すと理解するのです(この解釈はクーン教授によって猛反対を受けています)。もしもBaldrの名が、ON baldr(形容詞)、OHG bald ModE bold (「勇敢な」)と関係があるのなら、戦いの神としての性格を表すと思われます。しかしながら、それを証明する資料は全てのバルドルを記す資料にはぴったりと合うものはないのです。シュレーダーは、bold の語源のインドヨーロッパ語*bal-ora-m 「力」という語形から、バルドルに豊饒神としての「力」を見ようとしています。
「ハールバルズルの歌」 Hárbarðsljóð
『詩のエッダ』中の神話詩の一つ。他のエッダ詩篇とは形式において異なり、フォルニルジスラーグ(古式旋法)とリョウザハゥットル(詩旋法)からなる詩節(スタンザ)に、旋法外の韻律を持つ詩節や、ほとんど口語的とも見える詩節が挿入されながら構成されている。とはいうものの、これは恣意的なものではなく意図的な挿入であり、詩全体ははっきりと秩序だったものと言える。
この詩の内容もまた、他の詩とは異なっており、ソールが巨人達の国から、疲れ切った旅人の体で帰ってくるところへ、オージンがハールバルズルと名乗る渡し守に扮しながら、ソールを渡し船に乗せて川を渡ることを断る。その代わりにオージンは、ソールは自分を強い者のように見せながらも知性も勇気もない農民そのものだとバカにする。そしてオージン自身の(恋の)冒険譚を語るのである。「その間お前は何をしていたのだ?」というオージンの問いに、ソールは巨人達との戦い(フルングニルやシャツィ)をしていたのだと答える他はなかった。
この歌の最高点となる言説からこの詩の性格が示されている:「戦場で倒れた領主たちをオージンは受け取り 農奴の輩をソールは受け取る」(24節)。G. W. ヴェーバー博士はこの節について次のように註釈を付ける「この詩の詩人の立場はこのような詩節から明らかである。すなわち戦いが体に染みついたヴァイキングとしての自信に溢れた詩人かつ王侯貴族に付き従う身分の者としての立場である。オージンへの追従を世俗の詩に読み込み、オージンの複雑な人格に比べて単純素朴、精神的深みに欠ける農民達の守護神を嘲笑するのである」。
旅をしている主人公が渡し守に川を渡すのを拒まれるという、この詩に語られる状況は古北欧文学の他の箇所にも見出されるものであるが、特に類似した例としては、中高独語詩『ニーベルンゲンの歌』で、ドナウを渡るハーゲンと渡し守とのやりとりがある(『ニーベルンゲンの歌』1480行以下))。
この詩は、異教時代に終わりにかけて(恐らくはハロガランドで)作られたと見なされている。異教時代において、或る神を嘲笑すること(特に他の神を賞賛する場合に)は、涜神的なものとは思われなかった。エッダ詩においては「ロキの口論」のみがこの点において「ハールバルズルの歌」と類似しており、「ロキの口論」の創作年代が、より遅い時代である可能性が否定できないことを考えると、「ハールバルズルの歌」の創作年代についても注意が必要であろう。
ビフロスト ![]() ミズガルズルとアゥスガルズルとを結ぶ橋で、「虹」のことだと見なされています(「グリームニルの言葉」44連、「ファゥヴニールの言葉」15連、『ギルヴィの惑わし』40章)。
ミズガルズルとアゥスガルズルとを結ぶ橋で、「虹」のことだと見なされています(「グリームニルの言葉」44連、「ファゥヴニールの言葉」15連、『ギルヴィの惑わし』40章)。
この橋は神々によって天と地を結ぶものとして建てられたと考えられていました(『ギルヴィの惑わし』12章)。ビフロストは天界ではヒミンビョルク(「天の城」の意)で終わっています。そこにはヘイムダッルルがいて、巨人達が住んでいるところからこの橋を守る番をしているのです(『ギルヴィの惑わし』16、26章)。毎日神々(アィシル)はウルザルブルンヌル(『ギルヴィの惑わし』14章)にある集会に、この橋を越えて向かうのです。そこでこの橋には「神の橋(アゥスブルー)」という別名がついているのです。ラグナロクに際しては、ムスペッルの息子達が憎しみに満ちてビフロストを駆け抜け、そのときにこの橋は落ちることになっているのです。
ビフロストの意味は、「天への揺れる道」(<ON bifa「揺れる」)というものか、或いはもしビルロストという語形がより古いものだとするならば、「消えてしまう前に目に映る虹」を意味するでしょう。「多くの色を持つ道」という解釈は根拠の薄いものと思われます。しかしながら、スノッリのビフロストは虹であるという説明は、ヤン・ド・フリースの言う、ビフロストは「銀河である」という解釈にまさって説得力があります。一方、死者の世界へと続くギャッラルブルーは、多くの非ゲルマン地域のものと共通する、異界へと続く橋であって、ビフロストとは混同するべきではない別物です。
ヒャズニンガヴィーグ「ヘディンの戦士たちの闘い」
ビルロスト アゥスガルズルへ続く橋として呼ばれている名です(「グリームニルの言葉」44連、「ファゥヴニルの言葉」15連にのみ現れるのです)。
すなわち虹のことです。この名は恐らくON bil「一瞬、稀弱なもの」から来ていると思われ、恐らく天に続く橋の元々の名はこちらだったのでしょう。ですが、『スノッリのエッダ』ではビフロストとだけ呼ばれてはいますが。
ヒミル Hymir<音声クリック 巨人の一人。ソゥルがアゥス神たちがビールを醸造するための大釜を手に入れたいと願ったのは、まさにこのヒミルからです。
ソゥルのヒミルとの冒険譚は、エッダ詩「ヒミルの歌」やその変更バージョンのスノッリの書物(「ギルヴィの惑わし」17章)に見られます。スノッリのものでは、強調点はソゥルとミズガルズ蛇とのことに置かれています。ここでは、ヒミルは、ミズガルズ蛇のかかっていた釣り糸のロープを、恐怖のために切ってしまうのですが、そのためにソゥルの怒りを買って、船の外に投げ出されてしまうのです。
一方、「ヒミルの歌」の中ではヒミルは重要な役割を担っています。アゥスたちがビールを醸造するために用いるべく、ソゥルが奪わなければならない大釜を持っているのがヒミルなのです。ヒミルはティールの父親として名前を挙げられますが、明らかにここではアゥスの敵方の巨人として登場します。実際、多くのソゥルの冒険譚に登場する巨人たちの典型として描かれており、最後はソゥルに殺されるのです。
スカルド詩の中に見られる、より古いケニングの中にもヒミルへの言及があります。しかし、その場合にすらも、ヒミルが巨人であること以上には深い説明は見られません。しかしそれでも、この事実は、12-3世紀に「ヒミルの歌」が歌われ、スノッリが著したのが初めてなのではなく、その時代以前にも、神話的物語の中に登場する人物としてヒミルが知られていたことを証明してくれます。
「ロキの口論」34節では、ヒミルの娘は、ニョルズルの口を便器として用いたらしいことが語られます。「ヒミルの歌」にはそのことは言及されません。けれど、だからといって、ヒミルの娘とニョルズルとの面白い逸話が知られていなかったとは言い切れません。
ヒミルがティールの父親だという言及が「ヒミルの歌」5節に出てきます。一方スノッリの書物にはティールの父親はオーディンとなっています。古代の「神」の一人が、「巨人ヒミル」へ「降格」したと考えることも可能と思われます。
ヒュミル>ヒミルを見よ。
ヒュロッキン Hyrrokkin 女巨人。ヒョルッキンとも。「炎により萎んだ者」の意。
>こちらの画像は'Runes&Vikings'サイト管理者であるWarhornさんからの御提供です<大感謝デス
スノッリの『エッダ』に登場する女巨人(『ギルヴィの惑わし』49章)。バルドルを葬る場面で語られます。以下、『ギルヴィの惑わし』より谷口幸男訳(一部改編)で引用します「アース神たちは、バルドルの死体を担いで海辺へ運んだ。バルドルの船はフリングホルニといって、あらゆる船の中で最も大きかった。これを神々は海に浮かべて、バルドルの葬式をしようと思った。ところが、船は動かなかった。そこでヨーツンヘイムにヒュロッキンというなの女巨人を迎えに人がやられた。それから女巨人がやって来たが、狼に乗り、手綱は毒蛇であった。そしてさっとその乗り馬(訳注 狼のこと)から飛び降りたが、オージンは四人のベルセルクたちを呼んでその馬の番をさせたが、四人を地面にそれを投げ倒すことでやっと取り押さえることができた。さて、ヒュロッキンは船の船首に廻って、ぐいっとそれを海に押し出した。するとその一押しで船は猛然と動き出し、船の下の木のコロからは火が飛び、全地が震えた。するとソールが怒り、ミョルニルを握った。神々が皆でソールを鎮めなければ、女巨人の頭を砕いていたことだろう。このようにしてバルドルの遺体は船に運ばれた」
上記引用文中にある「馬」という言葉が気になりますね。「女トロル(女巨人)の馬」というのは「狼」を表すケニングなのです(例えば『ヘイムスクリングラ』の「シグルズルの息子ハラルドルのサガ」82章には、「死が、王よ、貴方を襲うのではと、怖れるのです。トロルの貪欲な馬に餌をあげるのではないかと」という詩の一節が出てきます。ここでの「トロルの貪欲な馬」とは「狼」を表すケニングで、「狼に餌を与える」というのも、つまりは「自分が戦で死に、死体を狼が食べ漁る」という様子を表す詩的表現なのですね。言うなれば、このケニングのもとになっている神話的逸話が、スノッリの『ギルヴィの惑わし』に記されていることになるのです。
なお、ヒュロッキンは、ソールの怒りを完全に逃れられたわけではないようです、というのも、ソルビョルン・ディーサルスカルドの詩の中で、ソールに倒された女巨人の名前の中に、ヒュロッキンの名が挙げられているからです。
ヒュンドラ>ヒンドラを見よ。
ヒンドラ Hyndla 彼女の名前を付けられた詩に登場する女巨人の名前。
「ヒンドラの歌」に登場する彼女は、明らかに家系や王の系譜について類い希なる知識を持っています。彼女の住まいは洞穴であり、女巨人としては典型的な住まいです。一方彼女の乗る獣は犬であり、これは巨人としては、とてつもなく例外的な乗り物です。おそらく、詩人は、系図についての膨大な知識を、全ての生き物の中で、この女巨人に付加させ、ヒンドラという名前を与えたのだと思われます。
フェンリス狼 Fenrisúlfr (英語 Fenris wolf)フェンリルを見よ。
フェンリル Fenrir 神話的な狼。ロキが女巨人アングルボザの間にもうけた子供の一人。フェンリス狼とも呼ばれます。
アース神族はフェンリルを縄目にかけて捕らえるのです。しかしながら、ラグナロクにそこから逃げ、オージンを喰らい、オージンの息子ヴィーザルによって殺されるといいます。
フェンリルに関する神話物語はスノッリによって次の四つに分けられると考えられます。(1)フェンリルを捕らえる話。これによって、ティールは片腕を失います。(2)ラグナロクに於いて、オージンとヴィーザルのフェンリルとがそれぞれフェンリルと戦います。(3)恐らく、ガルムルが吠えたけり、逃げる時の描写はフェンリルのことかもしれません。(4)太陽が狼によって食べられてしまう話。
10世紀に活躍したノルウェー生まれのスカルド詩人エイヴィンドルの作「ハーコン善王の言葉」第20節には、フェンリルがラグナロクの時に解き放たれて世界を駆け回ることが仄めかされています。もしかしたら、スノッリはこの断片的な神話的エピソードに触発されて、民話モチーフによく使われる目に見えない縄目の話とティールが片手を失う神話的エピソードとを掛け合わせた話を作ったのかも知れません。
『ギルヴィの惑わし』第34章では、ロキがどのようにして女巨人アングルボザとの間に三人の子供をもうけたかが記されています。三人の子供とはフェンリル、ミズガルズ蛇、ヘルのことです。神々はフェンリス狼を育てますが、あまりにも強くなったので、彼をつなぎ止めようということになったのです。最初彼らは「レージング」という紐で彼をつなぎ止めようとし、次にはドローミという綱で彼を縛ろうとしますが、フェンリルは両方とも壊してしまい、自由になってしまいます。最後にドワーフたちの手によるグレイプニルという縄目によってフェンリルは縛らろうとするのです。けれどフェンリルはその縄目を見た時、神々は本当に自分を縛ろうとしているのを感じとり、縄目がかけられる間おとなしくしている条件として、一人の神が手をフェンリルの口に差し入れておくようにしろ、と言います。神々はたじろぎますが、一人ティールだけは恐れずにその手をフェンリルの口に入れるのです。フェンリルが縄目を壊すことができないと分かった時、口を閉じ、これによって、ティールは右手をなくすのです。神々はアムスヴァトニルという名の湖にあるリングヴィという島にフェンリルを置きます。そして、ゲルギャと呼ばれる鎖で、グレイプニルをさらに締め上げ、スヴィティという石を使って、ギョッルという岩にその鎖を打ち付けました。最後の仕上げに、神々は一本の剣をとり、それをフェンリルの口に入れ、フェンリルが口を閉じないようにします。もちろん、フェンリルは大いに吠え声を上げ、開かれた口からは涎が流れ続けます。それがヴァーンという川になるのです。こうしてフェンリルは縛り上げられ、ラグナロクと時まで自由になることはかなわないわけです。
ティールの右手が失われることは、「ロキの口論」の38-39節にも言及され、そこではフェンリルはフローズヴィトニル(名高き狼)と呼ばれていますが、「ロキの口論」が作られたのは遅い時期と考えられているので、ティールとフェンリルの神話が遙かな昔から知られていたかどうかはわからない、とされています。
フォッラ Vollaは第二メルセブルク呪文に名を記されている女神です。
他にこの名は記録されていませんが、恐らくはスカンジナヴィアのフッラと同じではないかと思われます。仮説としては、フォッラと、同じく名が挙げられているフォルは、南のゲルマン語で表された、スカンジナヴィアのフレイヤとフレイルの兄妹のことではないかと考えられます。
フォルニョウトゥル ![]() ノルウェーの先史時代についての伝説に登場する(巨人?)一族の先祖。
ノルウェーの先史時代についての伝説に登場する(巨人?)一族の先祖。
『オークニー諸島の人々のサガ』冒頭に書かれています(「ノルウェーの創始」)。また『フラト島の書』の中にも少し異なる記述が残されています(「如何にノルウェーが建てられたか」)。
フォルニョウトゥルは王と呼ばれていますが、その子孫の名前から、その系図は神話的なものであるのは明らかです:フォルニョウトゥルには三人の息子がありました。フレール(「海」)、ロギ(「炎」)、カリ(「風」)です。ヨークッル(「氷河」)またはフロスティ(「霜」)がカリの息子と言われています。いずれの場合もカリはスナィル(「雪」、つまり英語のスノー)の祖父と言うことになっています。そのスナィルもソッリ(「冬の月」の名前の一つ)の父親と言うことになっています。「如何にノルウェーが建てられたか」の異本によれば、スナィルの子供達はソッリ、フォン(「雪崩」)、ドリーヴァ(「一陣の吹雪」)とミョッル(「粉雪」)であると記されています。この冬の家系からわかることは、中世全盛期の文献に描かれるノルウェー前史時代の最初期には、元々は「霜の巨人」の家系がすべて記されていたのではないかと言うことです。また一方では、現在残っている名前の羅列は後世の発案ともかんがえられます。
その中でフォルニョウトゥルの語源だけが問題になっていて、多くの解釈がなされてきました。この名前をforn-jotrと読むならば、可能な読みは「古いユトランド人」(グリム説)あるいは「巨人の祖」(ヘルクヴィスト説)となります。for-njotrならば「かつての所有者」(ウーラント説)、または「破壊者」(ヨゥンソン説)となります。もっともありえないと思われる解釈はforn-njotrで、「生贄を喜ぶもの」(ノレーン説)ですが、forn-thjotr「古き吼え声の主」というコック説は、すくなくとも他の巨人にはあてはまりそうです。13, 14世紀の写本に見られるfjor-njotrという綴り方からわかることは、フォルニョウトゥルは当時は「命の巨人」(fjorは「命」の意)と理解され、つまりはイーミル(ユーミル)と同一視されていたことであろうということです。
古英語にはfornetesfolm(Fornjotr+folm「手のひら」)という植物の名前がありますが、実のところ、どの植物を表すのか明確ではなく、つまりは、この語が北欧の影響をどの程度受けていたのかは不明なのです。けれど、もし北欧の影響下にある語であるならば、この巨人が如何に広く知られていたかを示すことになりましょう。
フォルニルジスラーグ Fornyrðislag 「古式旋法」主に詩のエッダに用いられている韻律。
古英語の頭韻詩に用いられた韻律に似た、より古い物語詩に用いられる韻律である。古英語の頭韻詩は、四つの拍からなる半行を基本と考える。
その強勢のリズムによってA〜Eの五つのパターンが、Sieversによって提唱され、今日までその考え方を基本として韻律分析が行われている。
A: 強-弱-強-弱 Njarðar dóttur (ニョルズルの娘)「スリームルの歌」91a
B: 弱-強-弱-強 es engi veit (誰も聞いたこともないこと)「スリームルの歌」7a
C: 弱-強-強-弱 es harðhugaðr (意を決する者である)「スリームルの歌」127a
D: 強-強-微弱-弱 Hló Hlórriða (喧騒な乗手(ソール)は笑った)「スリームルの歌」126a
E: 強-微弱-弱-強 Laufeyar sonr (ラウフェイの息子(ロキ))「スリームルの歌」81b
『ラクサゥ谷の人々のサガ』29章にはクジャクのオゥラヴルというアイスランド人がヒャルザルホルトに豪奢な館を建てたことが記されています。館の壁には木彫りの装飾があり、ゲルマン神話の場面 について描写してありました。ウッギの息子ウルヴル(ウルヴル・ウッガソン)というスカルド詩人が、婚礼のお祝いにと、オゥラヴルの館に架かっている木彫りの壁板について語った詩を詠いました。サガの中では980年から985年の間のことと記されています。ウルヴルはロキとヘイムダッルの間の争い(ブリーシンガメンを参照のこと)、ソゥルと「中津国蛇」との間の争い、そしてバルドルの葬儀の詳細な説明などを詠いました。『スノッリのエッダ』の中に12半スタンザのみ残されていますが、スノッリ自身によれば(「詩語法」8章)もっと長いものだったことがわかります。『エッダ』の中に、スノッリはフースドラゥパの中にある神話素材を豊富に用いていることは明かです。
フッラ Fullaはスノッリによれば(「詩語法」第一章)、アィシルの女神たちの一人です。
別のところでスノッリは、フッラはフリッグの使いの女神と言っています(『ギルヴィの惑わし』35章、「詩語法」19章)。フッラはフリッグの小箱(宝石箱のようなもの)を運び、彼女の靴の手入れをし、彼女の秘密の相談相手です。彼女は処女神で、流れる髪と額につけている金の飾りをもっています。フッラの環といえば、詩の中では黄金を指すケニングになります。フッラの名はまた詩人たちによって「女性」を指すケニングの中にも使われているので、フッラとは女神であることも確かです。スノッリは『ギルヴィの惑わし』の49章にはバルドルがフッラに黄金の指輪を贈っていることを書いていますが、これも黄金を表すケニングの中にフッラの名が知られていたことの証明でしょう。
フッラの名が10世紀のスカルド詩の中にも登場することから、その名から類推された「満たし fylla」の意味の擬人化説は誤りで、南ゲルマンのフォッラと同一の者と見なすことができます。しかしまた一方でこれはこの女神が実はどのような女神であったか確定できないことも示しています。一人の人格を持つ女神なのか、あるいはフレイヤの別名なのか、それとも、フリッグとの関係が示唆されることから、もともとはフリッグのことであったのか、それは諸説入り乱れています。トップへ
フノッス Hnoss (古北欧語で「宝物、宝石」の意)。
スノッリの『ギルヴィの惑わし』35章、『詩語法』20節、35節に依れば、オーズルとフレイヤの娘の名前。またスーラにも名前が挙げられています。全ての高価なものは、彼女の名前で呼ばれるのです。スールルにはフノッス(すなわち「宝石」)の同義語として、ゲルセミ(古北欧語で「宝石、宝物」を意味するもう一つの語)の名前が挙げられており、名前の羅列の中ではフレイヤの娘の一人となっています。これはスノッリがスカルド詩のケニングからとってきたのか、それとも自分自身で作った名前なのかはわかっていません。
ソゥルの母親の名前として何度か言及されています(「ハルバルズの歌」56節「巫女の予言」55節)。この名はソゥルの母ヨルズの別名に過ぎないようにも思われます。というのも、スノッリはフョルギンを、特定の女神としてとりあげてはいないからです。「詩語法」の56章(詩317番)や詩501番に出てくる例も「大地」のヘイティ(heiti「詩的異名」)として現れるのみです。とはいえ、現存のスカルド詩には出てこず、「詩語法」に見られるひとつのスカルド詩(恐らく10世紀)317番に出てくるのみです。このスカルド詩は作者不明であって、フョルギンの名前の正当性には注意が必要だと言えましょう。
彼についてはスノッリ「詩語法」19章の言及と、後期のエッダ詩である「ロキの口論」26節のみが資料として存在します。従って、フリッグの父としてのフョルギンはソゥルの母のフョルギンからの類推によって創作された可能性があります。一方で、リトアニアの異教神ペルクナス Perkunas(雷神)との関連も従来より指摘されてきました。「ロキの口論」については、アースグリムさんより掲示板で、その解釈について御質問がでました。菅原邦城著『北欧神話』(東京書籍、1984) p.259には、フリッグはフョルギンの「愛人あるいは妻」という解釈が採用され、これは山室静著『北欧の神話』での見解と同じなのです。
>さらに、山室静著『北欧の神話』では、フリッグはフィヨルギュンの妻で、 >フィヨルギュン=オーディンと。 >ですが、「古エッダ」の翻訳書谷口幸男訳『エッダ』と松谷健二訳『エッダ >グレティルのサガ』では、フィヨルギュンの娘と書かれています。 ([BBS REPORT]: 599, 07/07/2000)原語は
となります。これはMuch (1898)が「妻」と解釈して以来、何人もの学者がそのように解釈しておりまして、山室氏はその当時の学説を取り入れたのだと思われます。それに対して、ターヴィル・ピーターは、文脈的に「愛人」とした方がよい、と解釈しています(97)。一方、もっとも標準的と思われるNeckel-Kuhn両氏の版では、決定はされず、娘、妻、両方の可能性を示唆しています。それに対して、Geringを初めとする、主流派は、スノッリの解釈どおり、これを「娘」と捉えています。いずれにせよ、スノッリがmaerという語を「娘」と解釈した以上、中世ではそのように捉えられていたと理解することは自然だと思われます。Hollanderを初めとする、現在標準的と見なされている訳のほとんどは「娘」と訳しています。アーシュラ・ドロンケ教授の最新の版では、フョルギンは、ソゥルの母親のヨルズの夫だったのではないか、と言っています。とはいえ、フョルギンとオゥジンとは別者で、フョルギンとヨルズの二人が連れ添っていたのは、アゥス神族よりも前の異教神の時代だということを強調しています。したがって、フョルギン=オゥジン説は、ここでは否定されています。
フョルスヴィズル ![]() 1 古北欧語「非常に賢い者」スールルに名前が挙げられたドワーフの一人。
1 古北欧語「非常に賢い者」スールルに名前が挙げられたドワーフの一人。
フョルスヴィズル 2 Fjölsviðr「グリームニルの言葉」47節に登場するオージンの別名の一つ。
オゥジンが神々の中で最も賢いことを示唆している。
フョルスヴィズル 3 Fjölsviðr<音声クリック 古北欧語「非常にものを知る者」
後期エッダ詩の一つ「スヴィプダグルの言葉」の後半に登場する、恐らくは女巨人を守る護り手で、自身も女巨人であるかもしれません。ホランダーは『エッダ』の翻訳では、彼女をオージンと同一視しています。
女巨人メングロズは炎の壁に囲まれた館に住んでいます。フョルスヴィズルは、その館の護り手で、そこにやってきたスヴィープダグルからの問いかけに神話的知識を披露します。それで、「スヴィプダグルの言葉」のこの部分は「フョルスヴィズルの言葉」とも呼ばれます。ルドルフ・ジメックは、2とは同一視できない、と記しています。
フラィスヴェルグル Hræsvelgr 「古北欧語 死者を食らうもの」 『ヴァフスルーズニルの言葉』37節によれば、巨大な鷲。
世界の北の果てに座る巨大な鷲で、その翼の羽ばたきによって風をつくると言われています。巨大な鳥のはばたきによって風が起こされるという考え方は、他の文化の中にも見つけられます。鷲は死者の肉を食らうので、フラィスヴェルグルというこの名前もふさわしいと言えるでしょう。その巨大な体躯から、この鷲は巨人であろうと言われています(そして実際「スールル」では巨人の名前の一つとして挙げられてもいるのです)。すなわち、この名前からフラィスヴェルグルというのは死肉を食らう悪鬼だという説はまったくの誤りでありましょう。
ブラギ 1 (Bragi enn gamli Boddason「ボッディの息子老ブラギ」とも。)我々の知る限り最古のスカルド詩人。
彼は(ノルウェーで?)9世紀に詩を書いたとされますが、様々な資料からもそれ以上の正確な年月については知ることができません。12-13世紀のスカルド詩人のリスト(Skaldatal)の中ではブラギはスウェーデンの伝説の王ベリBeliの詩人だったと呼ばれています。しかしまた一方で、西暦830年頃聖アンスカルが訪れたビルカBirka(ヴァイキング時代のスウェーデンの交易で栄えた場所)の王ベルンと同一視されている、スウェーデン王「ハウギのビョルン」のスカルド詩人とも言われています。これらの情報から、ブラギは830年には成人した男性だったと考えられます。けれどもアイスランドの資料(『植民の書』『エギッルのサガ』)で彼が家系に記されているものを見ると、ブラギは835年〜900年にかけて生きていたことがほのめかされています。
個別に残存している数スタンザを除けば、ブラギの『ラグナルの賦』の20半スタンザはスノッリの『エッダ』によって私たちに残されているのです。これは「楯の詩」と呼ばれるものの一つで、楯に描かれた伝説的あるいは神話的場面 を説明したものなのです。
中世においてすでにブラギは最初のスカルド詩人として有名で、ブラギ神と詩人ブラギとは同一視されていた可能性は非常に高いと思われます。もしそうであるなら、彼は死後たった100年で神話的人物と見なされていたと云うことになるのです。
ブラギ 2 Bragi 詩神。
スノッリは彼を『詩語法』1章で、神々の名前に含めています。『ギルヴィの惑わし』25章ではスノッリは次のように語ります:
「アィシル(アゥス神族)の一人はブラギという。彼はその知恵によって高名を得ており、特にその弁舌と言葉の巧みさで有名である。彼は詩芸について深い知識を持っており、詩芸(ブラグル bragr)は彼の名前をとって名付けられている。余人より言葉の巧みな者は、詩人あるいは女詩人と呼ばれるのである。彼の妻はイズンである。」
『エッダ』詩の中では、『グリームニルの言葉』44節だけがブラギの名前を神話的文脈の中で用いています。もっともそれは詩人ブラギ(ブラギ1)を指しているようにも思われます。『ロキの口論』(8-14スタンザ)の中でブラギはアィシルの一人としてロキと議論します。ここでもイズンはブラギの妻と言われています。それ以外では、彼の名前は『シグルドリーヴァの言葉』16節にのみ現れます。ここではルーン文字とのなんらかの不明瞭な関わりが示唆されています。ブラギの名はスカルド詩の中でも多くは言及されてはいません。『グレッティルのサガ』の一つのスタンザで、イズンの夫として一度言及されています。それ以外では『ハーコンの歌』14節(961年)と『エイリークルの言葉』3節(954年)にのみ現れ、両方ともヴァルホッルに諸侯を招き入れる者として登場しています。この二つのスカルド詩では、詩人ブラギが神の一人として現れていると考えるべき根拠はないようです。詩人ブラギは単にヴァルホッルへの入場を許されるに値された英雄の一人としてのみ考えるべきでしょう。
特にスノッリの『エッダ』と『ロキの口論』という12-13世紀の書物にブラギは神として現れていることから、この詩神は、9世紀の大きな尊敬を集めた詩人から改めて作られた可能性が大きいと思われます(モック説、ターヴィル=ピーター説)。[12世紀ルネサンスの影響から]中世最盛期のアイスランドに起こった学術的ルネサンスの中で、ゲルマン神話を整合的に取り扱ったという事実を考えるとき、このような神格化が必ずしも異教時代に行われたと見る必要はないのです。
スノッリはブラグル bragr「詩芸」は、その名前を詩神ブラギからとられたと言っていますが、bragrはまた「首長、主人」を意味し、またブラギという固有名詞もこの神を表す以外に歴史的あるいは創作的人物に使われたということがあるので、ブラギと「詩芸」との関連性はもともとから存在したわけではないと思われます。むしろ、詩人ブラギが神格化される過程でおそらくは考案された考え方でしょう。
ブラギ 3 「首長、主人」を意味することから。エギッル・スカッラグリームスソンの「首を贖う歌」31節に登場するオージンの別 名。
フラテイヤルボゥク![]() 「フラト島の書」:はアイスランドの写本(GkS 1005 fol.)で、225葉の大きな二つ折り皮紙〔フォリオ〕に、二行だてで書かれています。
「フラト島の書」:はアイスランドの写本(GkS 1005 fol.)で、225葉の大きな二つ折り皮紙〔フォリオ〕に、二行だてで書かれています。
「フラト島の書」は二人の司祭ソゥルズルの息子ヨゥンとソゥルハッルルの息子マグヌースによって、1387年から1390年にかけて書かれました。その後、1391-94年の間にその間の年代記を、巻末に徐々に付加されています。マグヌースはまたこの本の挿し絵を全て描き、また序文ではこの書の二人の写字生の仕事について、その担当箇所を説明しています。ここにこの書の所有者も記されています。すなわちハゥコンの息子ヨゥン(1350-1416以前に没)は、北アイスランドのヴィージダルストゥンガの裕福な農民で、彼のためにこの書が書かれたのだと思われています。
ヨゥン・ハゥコナルソンの死後、この書の所有者がどうなったのかは不明ですが、15世紀後半にビョルンの息子ソルレイヴルという西アイスランドの執政官の所有となっていることがわかっています。オリジナルの202葉に23葉を加えさせたのは彼なのです。その後この書は1647年までソルレイヴルの子孫に受け継がれ、フィンヌルの息子ヨゥンというブレイザ・フィヨルド(西アイスランド)のフラト島の男が――この男のいたところからこの書の名前がつけられたのです――スヴェインの息子ブリニョゥルヴルという司教に献じています。1656年にはこの司教はデンマーク王フレデリク三世に贈り物としてこの書を献じました。その後1971年までこの書はコペンハーゲンの王立図書館にあり、その年にレイキャヴィークのアゥルニ・マグヌーソン研究所に移されました。
「フラト島の書」はアイスランドで書かれた写本の中で最も大きく、その見事なゴシック調の挿し絵によって、最も美しい写本と言われています。テクストは、ノルウェー王の一連の歴史となるように配され、それぞれの王たちのサガに、さまざまなサガからの部分(サゥットゥル)や関連するサガ全部が挿入され、編み上げられています。
基本構成は次の四つのサガです:1『トリッグヴィの息子オゥラヴル(オーラフ)大王のサガ(いわゆる「最長のサガ」)』、2『オゥラヴル(オーラフ)聖王のサガ(いわゆる「独立したサガ」)』、3『スヴェッリルのサガ』、4『ハゥコンの息子ハゥコンのサガ』です。23葉の付け加えられた部分には幾つかの話(サゥットル)の他、『モルキンスキンナ』版の「マグヌース善王のサガ」「ハラルドゥル・ハルズラジ(厳王)のサガ」を含んでいます。後から付け加えられたこの二つのサガは、元々の一連の王のサガでは扱われなかったオーラフ聖王とスヴェーリル王の間の時代(1030-1177年)を埋める役割を果たしています。おそらくハゥコンの息子ヨゥンは、すでにこの時代をカヴァーする王のサガの写本を持っていたのでしょう(その写本は現在『フルダの書』(AM 66 fol.)と呼ばれるものであると考えられています)。
二人のオーラフのサガ(トリッグヴィの息子と聖王)は、この書を構成する四大サガの中でも特に長い二編で、このサガの別ヴァージョンは他の幾つもの写本にも書き残されてはいますが、『フラト島の書』ほどの量をもったものは他にありません。
他の関連したサガの中には『ヨームス・ヴァイキングのサガ』、『フェロー島の人々のサガ』(これはおそらくオリジナルのサガそのものであり、他には残されていません)、『オークニー諸島の人々のサガ』(他には記されていない箇所を含んでいます)、『ハッルフレズルのサガ』(独特のヴァージョンを含んでます)、『グリーンランド人のサガ』(他に残されていません)、そして『義兄弟のサガ』(他には残されていない部分を含んでます)。
『フラト島の書』の中に記されている内容は四十から五十の写本から書き写されたものです。ということは、この書を書いた写字生は、その資料を修道院か司教区の中心の図書館で見いだしたのだと思われます。恐らくはシング島かレイニスタズルの修道院か、司教座のあったホーラル(北アイスランド)の修道院かでしょう。
ブリーシンガメン ![]() 古北欧の後期資料に従えば、フレイヤに属する宝石のこと。
古北欧の後期資料に従えば、フレイヤに属する宝石のこと。
後期資料とは「スリムルの歌」13,19節「ギルヴィの惑わし」34章「詩語法」20章です。
写本に現れる語形は「ブリーシングたちの首飾り」という意味ではありますが、語源的にはノルウェー語のbrisa「輝く」と関わりがあると思われます。現存するこの名前は、もしかすると、古英語詩『ベーオウルフ』の中にあるBrosinga meneという語からの影響かも知れないとも考えられています。
この首飾りの盗みについてのコメントは難しいと思われます。なぜなら、資料となるものが断片的、かつ不統一だからです。古北欧における資料からわかることは以下のことです:
1 ロキは「ブリーシングのベルトを盗んだ者」と呼ばれています(スカルド詩人ショウゾゥルヴル・ウール・フヴィーニの『ホイストロング』9世紀による)。
2 ロキは「ブリーシンガメンを盗んだ者」と呼ばれる(スノッリ「詩語法」16章)。
3 フレイヤの首飾りはブリーシンガメンと呼ばれている(スリムルの歌13,19節、「ギルヴィの惑わし」34章、「詩語法」20章)。
4 14世紀後半に書かれた『ソルリの話』では、ロキは、オーディンの命令によって、フレイヤの首飾り(ここでは名はない)を盗む。
5 『フースドラゥパ』(10世紀)において、ヘイムダッルルとロキは、シンガステイン(歌の宝石」という名で呼ばれていると思われる物をめぐって争っている。
6 スノッリは「詩語法」8章の中で、ヘイムダッルルとロキが、アザラシの姿で、ブリーシンガメンをめぐって争ったことを記録している。おそらくは、『フースドラウパ』の現在では喪失してしまっている部分に依拠していると考えられています。
7 スノッリはヘイムダッルルを「フレイヤの首飾りをもたらした者」と読んでいます(「詩語法」8章)。
これに加えて、古英語詩『ベーオウルフ』1197-1201行に、ハーマがブローシンガ・メネをエオルメンリッチの宮廷から盗んだことが語られています。
ブリーシンガメンの意味や、その盗みにおけるロキとヘイムダッルルの果たす役割を示すこれらの資料から、一つの神話エピソードを再構築するのは不可能でしょう。フレイヤの首飾りの盗みについての最も詳細なヴァージョンは、『ソルリの話』ですが、これははるかに時代を下った時期に書かれたもので、おそらく、この話の中で十分な文学的機能を果 たすべく、大きく手を加えたものであろうと思われます。『ソルリの話』は「ヒャズニンガヴィーク(ヘジンの戦士の戦い)」についての物語です。これによれば、黄金の首飾りが四人のドワーフ(アルフリッグ、ドヴァーリン、ベルリングル、グレルル)によって作られます。フレイヤはこの首飾りを手に入れるために、それぞれのドワーフと一夜を共にしなければなりませんでした。ロキがこのことをオーディンに告げると、オーディンはロキに、その首飾りを盗んでこいと命じます。ロキはフレイヤの寝所に、蝿の姿になることで、ようやく入り込めるのですが、フレイヤはネックレスの上に寝ているので、ロキは彼女を刺し、寝返りを打ったところで宝石を盗むのでした。フレイヤはオーディンに首飾りを返すように求めますが、オーディンは二人の王を永遠に戦い続けさせるようにしむけることを条件として出したのでした。フレイヤはその条件をかなえ、「ヒャズニンガヴィーク」が行われるのでした。
この話の元が古代の神話に遡るとしても、ヘイムダッルルとロキの戦いの意味は不明のままです。なぜなら、ここにはヘイムダッルルが首飾りを取り戻す過程が記録されていないからです。
ブリーシンガメンとその盗みについては、様々な解釈が為されてきました。ムッフの説は、これは火を盗んだことを表すとします。彼によれば、ロキはアザラシやサケの姿で現れるが、これはロキの「水」の性質を表す、ということになります。自然神話的解釈によれば、ブリーシンガメンへの二つの説明がなされます。二つとも、古ノルド語ブリーシングル、ノルウェー語ブリシング=「火」と関わりがあります。ピピングによれば、ブリーシンガルというのは、オーロラの光を表します。この輝きは、戦いで死んだ兵士で、オーディンに捧げられたものの魂のシンボルなのです。より古い説に寄れば、ブリーシンガメンは、昇る太陽のシンボルだと解釈されます。すなわち、首飾りの形で豊饒神であるフレイヤへの崇拝儀式と結びつく、というものです(ミューレンホフの説)。青銅器時代のスカンディナヴィアから見つかった、民族移動期の首飾りをつけた裸体の人形は(図版フレイヤの護符参照)、この証拠であると考えられています(ストレム説、ユングナー説)。
『フースドラウパ』におけるスタンザについてはすでに述べましたが(上記資料5番)、ペリングは、このスタンザに出てくるケニング hafnyra 「(腎臓の形をした)ウミシイタケ」とブリーシンガメンとを結びつけて考えました。この語は、ペリングによれば、腎臓の形をした果 物で、西インド諸島にはえているのですが、メキシコ湾流にのってスカンディナヴィアに流れてきた物だそうです(ノルウェー語vettenyrer)。この果 物は、お産の時の護符 birth stone として用いられていたというのです。すなわち、お産の時にベルトのようにして腰につけたもので、のちには首飾りのように首に巻くようになったと言うことです。
実のところ、この『フースドラウパ』の詩節からは、ヘイムダッルルとロキが本当にブリーシンガメンをめぐって戦ったのかどうかは定かではありません。ケニング hafnyra は、「島」あるいは「船」を表すケニングとしての方が普通と思われるからです。
ヘレン・ダミーコは、『ベーオウルフ』の中に登場するハーマとエオルマンリッチの性格描写 がないところから、魅力的ではありますが、決して説得力を持っているとも思えない説を出してきました。古英語のハーマ hama は、「コオロギ」を表しますが、すなわち「虫」=「(この場合は)蝿」を表し、一方エオルマンリッチは、文字どおりは「世界の主権」を意味するので、「オーディン」を意味するのだと言うのです。
これら多くの解釈にも関わらず、いや、だからこそ、古北欧神話におけるブリーシンガメンの意味、またロキとヘイムダッルルの戦いの機能は、不明のままであると言わざるを得ないのが現状です。
フリズキャゥルフ Hliðskjálf オージンの、あるいは彼の館の名前。
フリズスキャゥルフはエッダ詩群の中には言及されてはおりません。ただ、『グリームニルの言葉』と『スキールニルの言葉』の序文(明らかに初期の時代のもの)でのみ現れるのです。いずれの例からも、フリズスキャゥルフは、神々が全世界を見渡す座を意味するように思われます。
一方、スノッリには『ギルヴィの惑わし』16章で、フリズスキャゥルフは以下のように描かれています:「フリズスキャゥルフが見られるのはこの館(ヴァラスキャゥルフ)の中においてである。高座とも呼ばれる。「全ての父」がこの玉 座に座るといつも、彼は全世界を見渡すことができるのだ。」 しかしながら、『ギルヴィの惑わし』8章では、フリズスキャゥルフは玉 座ではなく、その玉座が置かれている場所だとされています:「フリズスキャゥルフと呼ばれる場所がある。「全ての父」がそこで玉 座に座ると・・・」
フリズスキャゥルフは、『ギルヴィの惑わし』49章でも同様の意味合いを持つものとして言及されています。そして、語源的に見ても、この用法の方が正しいのです:hlið は「開いたもの」を指し、skjálfは、絶対の確証を持って言うことはできないとはいうものの、対応する古英語 scylf, scelf から「塔」を指すと考えられます。中期オランダ語ではschelfは「足場」を意味するので、フリズスキャゥルフは「(扉の)開いたところにある足場、見晴台、観測場」という意味であろうとも思われます。
V・キールの説では、玉座フリズスキャゥルフからオージンが世界を見る「超自然的な」景観を得るということは、巫女がシャーマンのように異界を見る視力を得ることができるようにする魔術的な台である「セイズヒャッルル」seiðhjallrとの関連があると見ることができるようです。
G. W. ヴェーバーの意見では、ソゥルとミズガルズ蛇の神話絵画も描かれたアルトゥーナにある絵画石碑には、フリズスキャゥルフが描かれているというのです。異教時代の護符に椅子の形をしたペンダントが見られることは珍しくはありません。とはいえ、果 たしてそれが(ドレシャーやハウックの唱える説のように)フリズスキャゥルフを表しているのかどうかは確かとは言えません。いずれにしても、アルトゥーナの石碑に描かれた絵図と護符に象られた椅子の形には共通 点は見られません。
M.オルセンの説に従えば、オージンとフリズスキャゥルフ、オージンの息子ヴァーリとヴァラスキャゥルフ、またオージンの別 の息子ヴィーザルと*ヴィーダルスキャゥルフ(ノルウェーの地名ヴィスキョール Viskjøllに名残がある)といった繋がりは、オージンの別名でもあるスキルヴィングル Skilfingrの名前との関連を示しているというのです。Skilfingrという名は、そこからスキルヴィンガル王家の名前に由来すると思われます。スキルヴィンガル王家の名は、『イングリンガ・タル(イングリング王家のリスト)』18節や『ヒンドラの歌』11、16節に言及されていますが、古英詩『ベーオウルフ』の中に登場するシュルフィング族と同一のものなのです。『ベーオウルフ』の中では彼らは伝説の時代にスウェーデンを支配した一族なのです。この説に寄れば、フリズスキャゥルフもヴァラスキャゥルフも、さらに*ヴィーダルスキャゥルフもともに、オージンの王家の人々を祀った地名と言うことになります。
このような諸説が出るのも、その語源的に不明瞭な語自体に原因がありますが、10世紀のスカルド詩人ハッルフレズル・ヴァンドラィザスカゥルドの詩中にも言及されていることから、一つだけ確かなことは、フリズスキャゥルフは、語源も不確かなほど古い造語であるということです。
フリッグ Frigg はスカンジナヴィア神話中の神々の中でも、重要な女神です。女神たちの中でも、ヴァン神族のフレイヤを除けば誰よりも位 が高いのです。 古英語の形はFrigですが、北欧の異教徒たちが信じるフリッグはFricg、Frycg、Fricgeのように書かれる例があります。
フリッグはオージンの妻で、バルドルの母。そしてフョルギンという名以外わかっていない者の娘です(『ロキの口論』26、「詩語法」19章)。彼女はアゥスガルズル(のフェンサリル)に住み、彼女に使える女神はフッラとグナゥ(『ギルヴィの惑わし』35章、「詩語法」19章)といいます。彼女の持ち物は鷹のドレス(「詩語法」18、19章)です。スノッリのエッダでは、フリッグの役割はバルドル神話の中に特に限定されていますが、その中で、バルドルを傷つけないことを世界中の者に誓わせるのが彼女なのです。そしてまた、下界にバルドルの賠償をさせにヘルモーズルを遣わすのも彼女です。人間の争いに干渉する夫婦の神として―応援をするのは敵同士だけれども―フリッグとオージンはエッダ詩『グリームニルの歌』の導入部の散文と、ランゴバルド王国の歴史に登場します(パウルス・ディアコヌス著『ランゴバルド王国史』)。ウォーダン(=オージン)はヴァンダル国を支持するのですが、その妻フレア(=フリッグ)はランゴバルド側を支持し、最後には巧みな奸計を持ってランゴバルドが勝利します。
フリッグについてのもう一つの神話は、スノッリによる『イングリンガ・サガ』三章にあります。オージンが放浪している間、彼の兄弟のヴィリとヴェーはオージンの他の財産を所有しただけでなく、オージンの妻のフリッグをも共有します。最後にはオージンが戻り、自分の権利を主張することになります。この神話は『ロキの口論』26にも言及され、そこでロキはヴィリとヴェーと寝たことでフリッグを非難するのです。サクソによるオージン放浪についての言及ではフリッグはそれとは異なる役割を演じます(『デンマーク人の事跡』一巻25章以下)。そこではフリッグは、オージンの名声をうらやみ像を壊させ、奴隷と浮気をするのです。このことを恥じたオージンは放浪の旅に出るのです。
ゲルマン大移動前の時代には、フリッグはスカンジナヴィア以外の地で広く知られていたようです。メルセブルクの第二呪文の中では、フリーヤ Frîja(古高ドイツ語によるフリッグの名)は、大変活躍し、崇拝されていたため、3世紀と4世紀では既に、ローマの週の名前を翻訳する際、フリッグはヴィーナスと明らかに同じだとみなされ、dies Veneris (ヴィーナスの日)が古高ドイツ語 Friatac、古英語でFrigedeag すなわち今日のFriday(金曜日)とされました。興味深いことに、スカンジナヴィアでは、本来の*Friggjardagr という言葉としては残されず、南ドイツの言葉 friadag がそのまま借入され、古北欧語 friadagr として取り入れられたのです。紀元1000年頃までは、Frigg は北ヨーロッパよりも南ヨーロッパで人気が高かったようです。
女神フリーヤ Frîja またはフリッグ Frija / Frigg がヴィーナスと同一視されていたという事実はフリッグの性質のある部分を示しています。フリッグの名前を解釈することで、そのことはさらに証明されましょう。Friggという言葉は明らかに、古サクソン語 fri、古英語 freo (「女性」)、サンスクリット語 priya (「愛する者」)と同じ語根を持っています。従って、フリッグは、元々は、女性たちのための女神、絆の女神、あるいはおそらく愛の女神だと理解できます。フリッグを巡る長い伝承から、彼女が非常に早い時期からオージンの妻と見なされてきたということは疑い得ません。キリスト教の文書の中にもオージンとフリッグはゼウスとヘラの性質を持った神々の夫婦として出てきます。
[追記17/May/2003]なお、ワーグナーの楽劇「ラインの黄金」「ワルキューレ」に登場するヴォータンの妻である女神はフリッカ(Fricka)という。
ブレーメンのアダム(『ハンブルグ司教座教会史』第四巻26章)が、ウップサラの神殿にて、ソールとウォーダンと共に奉られていたとして名前を挙げている神。その記述に依れば「大きな男根を持つ」神とされた。これは明らかに豊饒神フレイルを意味すると思われるが、フリッコ Fricco という名前の語源は、その綴りからは多少の難しい問題が残る。この名前はフレイル神(Freyr / Frø)とは一致せず、アダムはフリッグと混同したかもしれない。ただ、*friðkan (「恋人」を意味すると推測されるゲルマン祖語からの再建語形)を語源に持つフレイルの別名という説もあり、その可能性は否定できない。
フリングホルニ(ON「舳先に輪のある船」)スノッリによれば、バルドルが荼毘に付される船(『ギルヴィの惑わし』48章、「詩語法」5章)。
この船が異教時代から既にバルドルと結びついて考えられていたとは考えにくく、スノッリがこの名を創作したということの方が可能性は高いのです。スノッリがバルドルの葬送を書くための資料はウルヴルのスカルド詩『フースドラゥパ(館の讃歌)』ですが、そこには980年に作られた木彫りの装飾に描かれた神話的挿話が説明されていたのです。この詩の失われてしまった部分についての知識があったのか、あるいはこの木彫りのことを個人的に知っていたのか、スノッリは船の舳先には輪があることを知っており、そのためにこの名を与えたのです。青銅器時代に遡る石碑の彫刻画の中に多くの証拠を見ることができますが、10世紀までの長い図像学的な伝統に、太陽のシンボルを持った船の描写も含まれます(舳先の輪とはこの太陽のシンボルを示すことは明らかだとされます)(Simek 1977)。
太陽との結びつきを持つ船は、明らかに豊饒神の持つ船と関わりがあり、ちょうどフレイルの船スキーズブラズニルのように、スノッリは、バルドルの葬送場面(図版参照)と言うことで、このフレイルとの関係を認識できず、改めてフリングホルニという名を付けたのです。
基本的には交わることのなかった二つの伝統がフリングホルニの中に(より正確にはその船の記述の中に)混ざっているのが認められます。一つは豊饒神としてのフレイルの太陽船スキーズブラズニル、もう一つは、ヴァイキング時代に広まっていたことからスノッリが知っていたとも思われる船葬風習の埋葬船の伝統です。そのようなわけで、フリングホルニは異教時代以後(最も早くとも異教時代の末)に学究的に構築されたものと見るべきなのです。この船はバルドルの埋葬という関係があって初めて彼と関連づけられたものなのです。
フレイア Freia は、ワーグナーの楽劇『ラインの黄金』(Das Rheingold)に登場する女神で、フレイヤとイズン(すなわち金のリンゴの守り神)の二人の女神の性格と役割を併せ持ちます。コロラトゥラ・ソプラノによって演じられます。
フレイヤ Freyja は、古ノルド語で「女性、女主人」を意味する語で、古北欧神話の中で最も重要な女神であり、恋人たちのための美しい女神です。(図版6-1参照)
彼女はヴァン神族に属し、ニョルズルの娘且つ妹であり、フレイルの妹(そして恐らくは元々は彼の妻)です。エッダ神話によれば、彼女の夫はオズルといい(彼はその他には登場しません)、彼との間に二人の娘(フノスとゲルセミ)がいます(『ギルヴィの惑わし』第35章)。娘たちの名前の意味は両方とも同義で「高価なもの」を指し、これは時代が下ってしまったために元々はフレイヤ自身を指す言葉だったものが、単に詩的言い換えによってその性格を他の人格に移されたに過ぎません。
スノッリは彼女を「女神たちの中で最も高名な女神で、天国のフォルクヴァングルと呼ばれる所に住み、死者たちの半分を彼女が受け取る。もう半分はオージンが受け取るのだ」と言っています(『ギルヴィの惑わし』24章、『グリームルの歌』14節)。また「彼女の館はセッスルームニルと呼ばれ、大きくそして美しい。フレイヤが旅するところどこへでも、彼女は猫に駆けさせ、その引く車に乗っていく。彼女は恋の歌が好きで、愛に関する事柄について彼女の名前を呼ぶのはよい」と続けています。
猫の引く車の他に、彼女の持ち物は、鷹のドレスがあります(フリッグも同様;「スリムルの物語詩」3;「詩語法」1章)。もっともホランダー(Lee Hollander, The Poetic Edda, 280, f.n. 10)はこれはフリッグとフレイヤの混同だとしていますが。そして猪のヒルディスヴィーニもおそらく飼っているのでしょう(ヒンドゥラの詩7)。中でも最も重要なのは彼女のネックレス、ブリーシンガメン(図版フレイヤの護符参照)です。
フレイヤは古北欧語文献の中では数多く言及されています。「スリムルの物語詩」では、巨人スリムルはフレイヤと結婚するまでは盗んだ鎚ミョルニルをソゥルには返さないと言います。「ロキの口論」30篇では彼女は体を売っていると罵られ、一方で「ヒンドゥラの詩」では一人の女巨人と知識の競い合いをし、「オッドゥルーンの嘆き」の中ではフリッグと共にフレイヤは助力を請われております。
スノッリはフレイヤの最も美しく、最も重要な女神である立場を強調しています。巨人たちの冒険譚で、フレイヤが女神たちの代表として何度も現れ、巨人たちの欲望の的とされます。それは「スリムルの物語詩」ばかりでなく、巨人の大工職人の話や巨人フルングニルのエピソードにも語られています。
10世紀のスカルド詩人たちもしばしばフレイヤの名を挙げ、スケッギの息子ヒャルティの唄う挿話は、フレイヤが異教の中で如何に重要な位置を占めていたかを示しています。ヒャルティは999年の全島集会での異教とキリスト教との闘争において、フレイヤを揶揄する詩を吟じています:「神々を罵ることは我が本意にあらず;(されど)我が目にフレイヤは娼婦なり」と(Jakob Benediktsson, ed. Islendiangabok (Islensk Fornrit I, 15-16, f.n. 7))。この詩のために彼は不敬罪として、法の守護を受けない者とされてしまいます(『アイスランド人の書』7章)。
フレイヤはヴァン神族(ヴァニル)の出で、従って豊饒の女神と言うことになります。彼女はまたアゥス神族(アィシル)に魔法を教えたとされます。すなわちヴァン神族からもたらした知識のことです(『イングリンガ・サガ』4章)このことについてスノッリは、ヴァン神族の間では近親相姦は普通であったと述べています。フレイルとフレイヤの兄妹神はそのようなわけで、兄と妹の恋人あるいは夫婦と見なされていたことでしょう。フレイヤがアゥス神族の一員となってはじめて彼女は夫がいると言われるのです。夫とはオズルで、長い間帰ってこなかったと言われています。そのためにフレイヤは黄金の涙を流して悲しんだ、と。(『巫女の予言』25、ヒンドゥラの歌 9-10、『ギルヴィの惑わし』35章)そしてその話は10世紀には既に知られていたことはわかっています。
スカルド詩の中で、フレイヤはスノッリも列挙している次の名で登場します。すなわち、マルドッル、ホルン、ゲフン、シール、そしてヴァナディースです。この名はフレイヤの家庭の守り神としての性格を表しています。シールという名前は、フレイヤが兄のフレイルと同様、野豚を飼っていたことを示しています。ヒンドゥラの歌の中ではフレイヤは猪ヒルディスヴィーニに乗りさえするのです。
『ヒンドゥラの歌』の中で、フレイヤはまた「自分の庇護者であるオッタルは彼女のために祭壇を作り、そこで生け贄を捧げた」と自慢しています。そして事実(文献にはその他にはフレイヤ信仰について記されてはいませんが)、スウェーデンやノルウェー各地のかなりの数の地名によって、フレイヤへの礼拝が行われたことが示されています。ノルウェーのフロェイホヴ(は*Freyjuhofすなわち「フレイヤの神殿」から来ています)やスウェーデンのフロェヴィ(は*Freyjuveすなわち「フレイヤの社」から来ています)などは公に儀式が行われていたことを示しますし、それ以外にも純粋に家庭内で、守護神あるいは愛の神への供儀が行われていたことが考えられます。
その他スウェーデンやドイツで船の名前にフレイヤの名前が使われていて、9世紀末からはドイツやイギリスでヨットの名として有名です。トップへ
フレイル Freyr 古ノルド語で「主人」の意。ヴァン親族の中で最も重要な神で、ゲルマン神話の豊饒神の中で最も力強き神。(図版参照)
フレイルは、妹のフレイヤと共にニョルズルの子です。フレイルはフレイヤの兄で、ヴァン神族の習慣に則り、恐らくは元々は彼女の夫だったでしょう。しかしやがて彼はアゥス神たち(アィシル)と共に女巨人のゲルズルに求婚し(スキールニルの言葉、『ギルヴィの惑わし』37章)、彼女と結婚します。(図版参照)
フレイルは自分の船スキーズブラズニルをもっており(『ギルヴィの惑わし』43章、「詩語法」7、35章)、また猪グッリンボルスティを飼っています。スノッリによれば、その猪はフレイルの車を引いているのだそうです。壮麗な装飾を別 にすれば、このような持ち物についての伝承は古いものと思われます。というのも、猪は豊饒のシンボルとしてヴァン神族と関係が深く、また他の場合でも彼はスウェーデン王家とも結びついていて、さらに航海との関わりも同様にニョルズルやフレイルといったヴァン神族にまでさかのぼることができるからです。
フレイルの住まいはアルヴヘイムル(「グリームニルの言葉」5)であって、これは彼が最初の歯が抜けたときにお祝いに神々から贈られたものなのです。スノッリは『ギルヴィの惑わし』の23章以降に次のように言っています:「フレイルは神々の中で最も高貴である。彼は日の光と雨とを治め、それによって大地の生産を支配する。良い収穫と平和のために彼の名を呼ぶことはよい。彼は人間の繁栄を見張っている」
フレイルはラグナロクのとき、火の巨人スルトゥルとの戦いで倒れます(『巫女の予言』52節;『ギルヴィの惑わし』52章)。その戦いでフレイルには剣がないのです。スノッリによれば、彼はそのつるぎをゲルズルに求婚するため召使いのスキールニルを使わしたときに、スキールニルにつるぎを貸してしまったからなのです。ただしこの戦いということについては、フレイルは「ベリの殺人者」とは言われております。スノッリは(全ての資料の中で彼だけが)、『ギルヴィの惑わし』37章で、他には名の出てこないこの巨人を剣はなくとも鹿の角で倒すことを記しているのです。
『イングリンンガ・サガ』における、エウヘメロス的な解釈のなかで、スノッリはフレイルの人生のまったく異なる側面を知らせてくれます。フレイルはスウェーデンの王で、ウプサラに居を構え、ゲルズルと結婚し、フョッルニルを生むと。「フロジの平和」は彼の治世の時にはじまり、イングリング王朝の名は、フレイルのもう一つの名、イングヴィから来ているのです。フレイルが死んだとき、彼の死はスウェーデン国内で三年の間秘密にされ、彼の死体は火葬にはふされませんでした。それはフロジの平和が終わることを恐れたからなのですが、そのかわり、彼は生け贄を捧げられるようになったのです。
長年の間、フロジとフレイルは同一人物と見なされてきたことは、人々に認められております。また、スノッリの言う、フレイルがスウェーデンの中で特に愛されたという事実は疑いないことです。それも、儀式が行われた地名(やその他の資料)から証拠立てられているのです。ブレーメンのアダムもウプサラの寺院について言及していて、そこにはソゥル、ウォーダン、そしてフリッコ(すなわちフレイル)の像があったと証言しています。フリッコの像は「大きな男根」(cum ingenti priapo)によって崇められていた、と記されています。アダムはまた、ウプサラに於いて行われた儀式の中で歌われた卑猥な歌についても言及していて、これは豊饒祭の儀式だとする観点から見ると、理にかなっているとおもわれます。
フレイル信仰についての奇妙な話がアイスランドの『フラテイヤルボゥク(フラト島の書)』の中に残されているのが確認されています。そこには、アイスランド人の放浪者グンナル・ヘルミングル(祝福されたグンナル)がどのようにしてフレイルの尼僧の庇護を得たかが記されていました。尼僧は馬車で各地を旅をし、フレイルの像を携帯していました。グンナルはまもなくこの像の代わりをし、そのようにして各地への旅を続けました。この尼僧が身ごもると、ひとびとはそれを良い兆候だとみなしたということです。この話は時代が下ってからの事件を語っています[し、ある種、おおらかな猥談のような雰囲気も見られ、中世のファヴリオーのジャンルに入るでしょう]が、この話は、タキトゥスが語るネルトゥス神の行進についての逸話と合致します。またヴァン神族が良い収穫と豊饒とをもたらすという信仰にも合致するので、この話が外国の猥談話の影響にあるという仮説をむりに作り出す学者もいますが、その説は支持しなくともよいと思います。
サクソはまた、ハッディングス(彼はニョルズル神と共通する性格をたくさん持っているのですが)のフロェーブロットについても記して、その起源をハッディングスに求めています。このようなフレイルに対する生け贄の儀式は、特にスウェーデンにおけるそれは、多くの文献に記録されています。フレイル神に対する儀式に基づく地名も、スウェーデン東部には特に多く、ウプサラにおける生け贄について言及される場合、それはフレイルに対するものだと考えられます。
フレイルに属するものについて言えば、スウェーデンの王たちは猪に対して特別な愛情を抱いていたかに見えます。グッリンボルスティを参照のこと。たとえばスウェーデンの王冠の宝石はスヴィーアグリッスと言いますが、「スウェーデンの猪」という名です。ウプサラや東部スウェーデン地方はフレイル神信仰の中心で、この信仰は特にイングリング王朝の王たちによって拡げられました。彼らはフレイルを自分たちの祖先だと見なしていたからです。
フレイルがスウェーデン以外の地でも信仰されていたことについては、例えば彼の特別 な地位などは、「フレイルにニョルズル、そしてかの全能のアゥスよ、助けたまえ!」という祈りの定型の文句に表れています。ノルウェーのヤールのフラジルによって捧げられた生け贄について、初めの一切れは、オージンに、しかし二番目の贄については、ニョルズルとフレイルにと言われています。もちろん、このことが記されている『善王ハーコンのサガ』十四章の記述はおそらく歴史的な正しさを持っていないかもしれませんが。アイスランドでは「フレイスゴジ」すなわち「フレイ神官」というあだ名をもった人が何人も歴史資料に見つけることはできます。またアイスランドの後期のサガの中でフレイル信仰者が鞄の中にフレイルの護符を持ち運んでいたこと(ヴァトン谷の人々のサガ第十章)の記述は、ヴァイキング時代の小さなお守り(スウェーデン、レリングにて出土)が証拠立ててはくれます。それを見れば、男根崇拝は明らかです。(図版参照)
フレイルが、スウェーデンの主要な神であること以上に、彼はスウェーデンの・イングリング族の王家の先祖だというのは明らかで、それでイングウィとかイングヴィーフレイルという彼のあだ名を持っている。このあだ名はロキの口論43章で、また、『オゥラヴルのサガ』のなかでも言及されている。
- フロェーブロット
「フロェーへの生け贄」の意。
サクソによれば、これはウプサラに於いてフロェー神にささげる生け贄のスウェーデン語の表現だといいます。『デンマーク人の事跡』第一巻にあるサクソの説明では、この生け贄の儀式は、ハッディングスがフロェー神(=フレイル)に捧げた償いの生け贄から始まっているというのです。ハッディングスは人間を生け贄として捧げています。ハッディングスはこの儀式を毎年続け、彼の子孫たちによって受け継がれました。しかしながら、別 の資料によれば、ウプサラにおける大祭儀は9年ごとにしか行われなかったといいます。このことはサクソも知っていたようです(『でデンマーク人の事跡』第四巻)。
ハッディングスがフロェーに「黒い皮の生け贄が行われた」(furvis hostiis)というサクソの記述が何を表すのかはわかっていません。戻る
月を追いかける狼ハティの父狼の名前だと、スノッリの『エッダ』『ギルヴィの惑わし』第12章、また『グリームニルの言葉』第39節で言われています。「ロキの口論」第38節ではフェンリルのことだと言われています。多くの学者によってもフェンリルのことだと見なされています。
『グリームニルの言葉』25節(また『ギルヴィの惑わし』38章)によると、ヴァルホッルの上に立ち、ライラズルという樹の葉を食べるのです。清らかな蜜酒がその乳房から流れ、エインヘルヤルの杯に注がれます。『ヒンドラの歌』46-47節の中ではヒンドラはフレイヤのことをヘイズルンと同じくらい色情であると言って貶しています。「ヘイズバンヌル」「ヘイズドロイプニル」という言葉から、ド・フリースは、「ヘイズル」という言葉は、捧げ物としての蜜酒のための儀式用語だったのだと結論づけています。そうでないとすると、この語の意味は不明となってしまいます。この、蜜酒を与える山羊という考え方は、創世記の養い親としての雌牛(オイズムラを参照)についてのイメージの北欧神話化だと思われます。これに比べられる考え方は、ギリシャ神話の山羊、アマルテイアに見られます。アマルテイアの角は豊饒の角(ゼウスに授乳したと伝えられる角)なのです。
北欧の神々の一人。アィシルの一人。神々(アィシルたち)の守護をしていると考えられています。ヘイムダッルルへの言及は、エッダ詩群の中には何度も見られますが、スカルド詩の中では、僅かなものしかありません(フゥス・ドラゥパ10節;及びその他の後期のスカルド詩のみ)。しかしながら、異教神話体系の中では重要な役割を果 たしています。
『巫女の予言』第一節や、リーグルという偽名で現れる『リーグルの歌』でも、彼はすべての人間の父と言われています。(『巫女の予言』では「聞け、位 の高き者も低き者も、すべてヘイムダッルルの血縁の者たちよ」(Hauksbok)と人間に呼びかけ、『リーグルの歌』では、ヘイムダッルルはロキの宿敵です(『ロキの口論』48節)。両者はラグナロクにおいて相打ちになるのです(『ギルヴィの惑わし』51章)。スノッリはヘイムダッルルについて「彼は『白のアゥス』と呼ばれ、偉大で聖なる者だ。また彼は9人の姉妹から生まれた」と言っています。
彼はハッリンスキジ
<音声クリック>、またグッリンタンニGullintanniとしても知られています。というのも彼の歯は黄金で出来ているからです。彼の馬はグッルトプルといいます。彼はビフロスト(橋)の近くのヒミンビョルクに住んでいます。彼は神々の警備をしていて、空の果 てで山の巨人たちから橋を守りながら座っているのです。彼は鳥よりも眠りが少なく、昼も夜も100マイル先まで見ることが出来るのです。彼は草の生い茂る音、羊の毛の伸びる音、またそれよりも大きな音すべてを聞き分けることが出来るのです。彼はギャッラルホルンというラッパを持っていて、その音は世界中に響き渡るのです。ヘイムダッルルの剣はホヴズ
(「人の頭」;『ギルヴィの惑わし』27章)といいます。
ヘイムダッルルは「人間の頭」によって殺されるということを表すと思われるこの不思議な記述に加えて、この神に関しては他にも多くの不可解ともいえる記述があります。
ヘイムダッルルはすべて姉妹である9人の母親を持つ、という記述は、9人のアィギルの娘たち、すなわち波のことを指していると理解されます。別 のところでは(『ヒュンドラの歌』35-37節)、明らかにこの9人の母親は女巨人たちと言及されています。そしてこの9人の名は、アィギルの娘たちの名とは一致しておりません。
ヘイムダッルルの形容的な呼び名ハッリンスキジは「スールル」の中で牡羊の名前としても用いられています。またヘイムダリ heimdali もそのように用いられていますが、またこれはヘイムダッルルの語形の一つとも考えられます。ちょうどソゥルが牡山羊、フレイルが猪、またオゥジンがカラスや狼と結びつけられているように、おそらくヘイムダッルルも牡羊との結びつきがあったのでしょう。更に話を進めるならば、ゲルマン人の間で牡羊が一般 的な生贄の動物なのは疑問がないので、ヘイムダッルルを羊の姿をした神として見たがる者も多くありました(ON
'羊', Gothic
'生贄')。さらに彼を聖なる獣として考えていたのかもしれません。
神々の番人としては(「グリームニルの言葉」13節、「ロキの口論」48節)また天の橋ビフロストの警護として、ヘイムダッルルはラグナロクの始まりに、自分のラッパを吹き鳴らして神々に知らせるのです(「巫女の予言」45節、『ギルヴィの惑わし』51章)。ド・フリースはこのことからヘイムダッルルは神話世界の第二種類の神々の一人として列せられるべき者と見なしています。神話世界の第二種類の神々とは力の神々。ソゥルは戦士として、ヘイムダッルルは警護をする者としてその範疇に入ります。
しかしながらデュメジルはヘイムダッルルを原初の神としてみなしています。ちょうどローマ神話のヤヌスやマハーバーラタのなかのディヤウスのように、神々の父としてではなく、長命の始まりとしての神と見なすのです(それは彼の九つの命に象徴されています)。この場合、スノッリが語るヘイムダッルルはオゥジンの息子であるという記述は不正確なものとなります(『詩語法』8章)。一方、シュレーダーは、ヘイムダッルルはインドのアグニのような炎の神に対応すると見なしています。
ブリーシンガメン(フレイヤのネックレス)を巡る戦いの中におけるヘイムダッルルの役割(「フースドラゥパ」中のウルヴルの記述)はなお一層不可解なものといえます。また、彼の輝く姿や、歯が黄金で出来ているという記述ももう一つの謎です。自然神話的な単純な解釈としては、彼は夜明けと昼の神であるということです。もっともこの解釈はすでに否定されて久しいですが。オールマークの解釈は、ヘイムダッルルは太陽の神で、三日月が彼の住まいを表しているというものですが、その興味深い考え方は別 にして、説得力には欠けたものと言えるでしょう。
もう一つ、さらに不可解なことは、ヘイムダッルルの「聴くこと」についての言及です(『巫女の予言』1節、27節)。これは聖なる樹、すなわちおそらくイッグドラシルの下に置かれているのですが、おそらくはヘイムダッルルのギャッラルホルンについての言及だと思われます。「聴くこと」という言葉自体は、ヘイムダッルルの卓越した聴覚を意味するのだとは思われますが、そうでないとすると、ちょうどオゥジンの片目のように、約束の手形として、世界-トネリコの根本にあるミーミルの泉の中に耳がおいてある、その代わりのことを意味しているのかもしれません。
ヘイムダッルのあだ名のヴィンドレール
もヘイムダッルル自身のどういうところがその名を受けるにふさわしいかは不明です。
ヘイムダッルルの新しい側面にこれまで数多くの研究が光を与えてきたとはいえ、今日でさえ、我々はヘイムダッルルという神の正確や役割について完全な理解からは程遠いところにいるのです。
おそらくは、後世の詩的表現で、地下世界「ヘル」を擬人化したものでしょう。女神ヘルを用いたケニングは、初期のものとしては、10世紀末から11世紀にかけてのものです。地下世界はヘルの住まいであり、かつ彼女の支配する世界でもあります。
地下世界を表す典型的なケニングとしては、「ヘルの館 (salar Heliar)」(『巫女の予言』43節)や「ヘルの家 (rann Heliar)」(「バルドルの夢」2節)などがあります。
最も詳しいヘルの描写は、スノッリの『エッダ』(『ギルヴィの惑わし』34章)になります。そこでは、ヘルはロキの娘、すなわちミズガルズル蛇やフェンリス狼の姉妹と記されています。スノッリの描写によれば、ヘルは半分が黒く、半分が白く、病的で恐ろしい顔つきをしている、といいます。スノッリは彼女の住まいを寓意的に描いているが、それは明らかにキリスト教の伝統に則ったものです。
全体として、ヘルという女神への信仰が、キリスト教化以前に北欧に存在したという証拠は見いだすことができません。
ベルセルクルについての最古の言及は、スカルド詩人ソゥルビョルン・ホルンクロヴィによって作られた「ハラルドルの歌」という賛歌の中に見られます。ノルウェーのハラルドル美髪王はハプルスフィョルドでの闘いに勝利します(872年頃)。その闘いにはベルセルクルたちとウルフヘジンたちが参加していました。ベルセルクルについてほのめかした言及は、比較的新しいエッダ詩や12世紀から14世紀のスカルド詩の中で7回しか見られません。異教時代にまでさかのぼれる言及は、唯一ヴィーガ・スチュールによって歌われ、『エイル谷の人々のサガ』の中に引用されているものにしかすぎませんが、それすらも、決して確かな証拠とは言えないのです。
13世紀にスノッリはベルセルクルへの詳述を『イングリンガ・サガ』の6章の始めで行っています。「オゥジンの者たちが(闘いへと)赴くときは、鎧を着ず、犬や狼のように荒々しい。彼らは楯に噛み付き、熊や雄牛よりも強い。彼らは多くの者を殺せるが、彼ら自身は火によっても鉄によっても傷つかない。これが「ベルセルクルの怒り (berserksgangr)」と呼ばれるものである」
アイスランドのサガ文学の中では、ベルセルクルは二つのステレオタイプに分けられます。一つは、エリート戦士集団の一員として(だいたい12名のグループにわけられますが)、高名な王に仕えるのです(『エーギッルのサガ』『ヴァトン谷の人々のサガ』『フロールヴル・クラキのサガ』)。もう一つは、厄災をもたらす者としてのベルセルクルで、(独り、あるいは二人ずつ、もしくは12名のグループ集団で)農夫(北欧での農夫は闘いにも従事しました)に決闘を挑み、かつ/または、彼らの妻や娘を要求したりします。そして唯一サガの英雄によってのみ倒すことが出来るのです。そのような英雄は男性英雄的にステレオタイプの英雄的行為を行うのです(『グレッティルのサガ』『ヘイズレークルのサガ』)。
中世アイスランド文学の全盛期、あるいは中世後期アイスランド文学の中に見られる定型的なベルセルクルのイメージは、語源的にも、また(スノッリに特に見られるような)記述の中に残された古いイメージからみても、その源泉を「古代ゲルマン時代に覆面 を被り、宗教的儀式に於いて忘我を味わうような戦士たち」に求めることが出来ます。
語源的にベルセルクルとはber-「熊」と-serkr「シャツ、皮」からできている言葉です。ベルセルクルと頻繁に並列的に言及される「ウルフヘジン(「狼の皮」の意味)」を参照しても、彼らが皮を被った戦士たちであったことが伺えますし、それはスウェーデンから出土したヘルメットに描かれた、ヴェンデル様式(トルスルンダ 6-7世紀)の装飾にもその証拠を求めることが出来ます。ベルセルクルのber-という部分はスノッリによっても、また19世紀に至るまで、berr-「裸の」と同じと誤解され、「裸で戦場に赴く者」というイメージを与えました>イメージ画像(日本のあしべゆうほ著『クリスタルドラゴン』参照)。また、タキトゥスの『歴史』二巻22章の記述もこの解釈を裏付けてしまいました。
スノッリは、いずれにせよ、ベルセルクル、ウルフヘジンたちとオージンとの関連について、彼らを「オージンの戦士である」と述べています。オージンはまた「忘我」の神でもありました(オージンの名は古北欧語o'![]() r「怒り、激情」と関連があります)ので、「忘我の儀式」が彼に捧げられた、と考えられます。「ベルセルクルの怒り」という表現、またその特徴はいかにも「忘我の境地」を表していた言葉に遡ると考えられています(>ベルセルクルのイメージ画像その2を参照)。そしてまた、この境地は、シャーマニズム的なトランス状態を意味しているとも考えられています=火や傷の痛みに対する無感覚や、流血に対する無感覚。
r「怒り、激情」と関連があります)ので、「忘我の儀式」が彼に捧げられた、と考えられます。「ベルセルクルの怒り」という表現、またその特徴はいかにも「忘我の境地」を表していた言葉に遡ると考えられています(>ベルセルクルのイメージ画像その2を参照)。そしてまた、この境地は、シャーマニズム的なトランス状態を意味しているとも考えられています=火や傷の痛みに対する無感覚や、流血に対する無感覚。
従って、ベルセルクルやウルフヘジンといった考え方は、スカンディナヴィアの仮面 を被った古い宗教儀式の特別なやり方にその始まりがあるのだ、と考えられます。そしてそのことは、オージンに捧げられた、特殊な、仮面 を被る宗教的儀式がかつてあったことの証拠ともなっています。
後に三つに分冊化されました。「レイキャヴィーク AM371 四つ折本(クウォート) (Reykjavik AM371 4to)」という写本番号を持つ分冊は、レイキャヴィークのアールニ・マグヌースソン研究所所収。「コペンハーゲン、AM544 四つ折本」および「コペンハーゲン AM675 四つ折本」(Copenhagen AM544 4to, Copenhagen AM675 4to)という写本番号を持つ分冊はコペンハーゲンのアルナマグナイアン研究所所収です。この写本はエルレンドゥルの息子ホィクルの名に因んで名付けられました。ホィクルは「AM371 四つ折本」の一葉に自署(この写本のページは17世紀に失われてしまいましたが)していることで、名前がわかっております。三つの分冊はいずれも破損していますが、特に「AM371 四つ折本」の破損はひどいものです。『ホィクルの書』の元の写本は、おそらく210葉から成っていたと推測されますが、現在は141葉(西洋中世の写本はページ数で数えず、「葉」と、その裏か表かでページを数えます)が残っています。
ホィクル・エルレンヅソンは、アイスランド生まれ。1294年にアイスランド法律家として名前が挙げられているのが見られてます。数年後、彼はノルウェーに渡り、法律家として、1334年に亡くなるまでノルウェーで働きます。現存する二つの特許状(1302年と1310年のもの)に彼の名前が見られ、その筆跡は『ホィクルの書』の大部分に見られる筆跡と同じものです。この写字生はホィクル本人であることが確実と目され、アイスランド人のものとして認められているで最古の筆跡とされています。
「AM371 四つ折本」は全体にわたって ホィクル自身の手によって書かれた写本です。「AM544 四つ折本」の22葉目から107葉目において、恐らく彼に仕えたアイスランド人写字生によって書かれた部分が交互に見られます。上に挙げた1302年と1310年の特許状に見られる細かい異体字を比べてみると、古文書学的な見地から、「AM371 四つ折本」と、「AM544 四つ折本」の22-59葉と39-107葉は、1302年から1310年の間、恐らくは1306〜1308年に書かれたと思われます。この時期ホィクルはアイスランドへ仕事で戻っています。一方「AM544 四つ折本」の60-68葉は1310年頃以降に書かれています。
ホィクル自身によって、あるいは彼のために書かれた上記の部分では、主に三種類のテキストが筆写されています。1:歴史的、あるいは準歴史的作品。2:数学的論考。3:ラテン語から翻訳された、哲学的、あるいは神学的対話集です。
さて、「AM371 四つ折本」には、ホィクルの手になるアイスランドの二つの歴史的著作が筆写されています。すなわち『植民の書』と『キリスト教のサガ』です。
「AM544 四つ折本」には、ホィクルの筆写した準歴史的著作が二つ記されています。『トロイ人のサガ』(22-33葉。ダレース・プリギュウスの著したとされる『トロイの没落』と、ラテン語訳イーリアス、またその他の翻訳資料を編纂したもの)と『ブリテン人のサガ』(36-53葉。ジェフリー・オヴ・モンマスの『ブリテン王列伝』の翻案)がそれで、後者には、シングエイリのベネディクト会修道士グンロィグル・レイフスソン(1219年没)が訳したとされる、Merlínusspá(『マーリンの予言』)の韻文訳を含んでいます。それに続いては、グリーンランド(とアメリカ大陸)に関わるサガが二編:『フォーストブラィズラ・サガ(義兄弟のサガ)』(77-89葉)と『赤毛のエイリークルのサガ』(93-101葉)。また、二編の短いサガ:『ヘイズレクルのサガ』(72-76葉)と『スカルド詩人たちのサガ』(ハラルド美髪王のスカルド詩人たちのサガ;101-104葉)。そして最後に三つの「話(サィットゥル)」がある:「ヘイミングルの話」(69-72葉)「ウップランドの王たちの話」(104-105葉)「ラグナルの息子たちの話」(105-107葉)。「AM544 四つ折本」には、その他、ホィクルの手になる数学的論考があります:『アルゴリスムス』(90-93葉;アラビア数字の記数法についての教科書)と『プログノスティカ テンポールム』(107葉;ラテン語による暦法、ただし破損がひどく読みとりが困難)。さらには、『肉体と魂の対話』と呼ばれている二編の対話集があります(60-68葉)。最初の対話は「恐れと勇気の対話」というもので、小セネカの対話篇De remediisを短く26篇にまとめたものの翻訳(原典はPhilippus Gualterus de Castellioneが12世紀末に書いたとされる)と、サンヴィクトワールのフーゴ(1096-1141;パリのサンヴィクトワール修道院の神学者。百科全書を著したことで有名)の著作の翻案です。
『ホィクルの書』のその他の部分は、写字生も異なり、内容も製本編集も様々な三つの種類に分かれます。
まず、地理的、年代史的、また神学的な内容の小冊子集。三つの説教を含みます(「AM544 四つ折本」1-14葉)。また、同様の内容ではありますが、より内容の濃いものもあります。「イェルサレムの見取り図」や『巫女の予言』がそれにあたります。「聖書注解(「AM675 四つ折本」)」は三つの部分に分かれます。第1の部分はほとんどノルウェーの写字生によるものです。学者によってはフェロー諸島出身の写字生の手のものだという人もいます。2番目の部分は、やはりほとんどがノルウェー人の手によるものです。第3の部分は、字体は混同しており、明らかではありませんが、恐らくアイスランド人の手によると思われます。ホィクルが直接このような箇所を写本に加えたのか、それとも後世の人の手に依るのかは明らかではありません。第二番目の部分の最後の数ページを除き、上記の全ての部分は、恐らくホィクル自身の手になる部分と同じ頃に書かれたようです。すなわち14世紀初めになります。しかし、『巫女の予言』(20-21葉)はアイスランド人の手により、14世紀半ばに書かれたとされます。恐らく18葉裏の最後の数行と19葉もそうでしょう。この部分は明らかにホィクルの亡くなった1334年より後に書かれたと思われます。
14世紀から16世紀までのこの写本の持ち主が誰であったかはわかっていません。状況証拠から、1600年頃は、ウェスト・フィヨルド(アイスランド西部)の富裕な農場の持ち物であったと考えられます。17世紀前半には、ルネサンス精神溢れる歴史家によって、用いられていたことが知られています。賢者ヨーン・グズムンズソンとスカルズアー農場のビョルン・ヨーンスソンがその代表者です。1650年代には、写本収集家である(司教座のある)スカールホルトのブリニョールヴル・スヴェインスソン司教が「AM544 四つ折本」を持っており、また「AM371 四つ折本」の、自分の為の写しを持っていました。アールニ・マグヌースソンは、「AM371 四つ折本」(と恐らくは「AM675 四つ折本」も) を1690年代に、ブリニョールヴル司教の後継者から手に入れたようです。「AM371 四つ折本」オリジナル(もしくは、現在残っている部分だけかもしれませんが)は、もう少し後、18世紀初めに手に入れたと思われます。
中世アイスランドの写本に見られる編纂方法は、書かれた書物の内容毎に写本に収めるやりかたでした。しかし、それとは対照的に、『ホィクルの書』はその編纂の始めから完全に個人趣味による書物収集と言えます。すなわち、ホィクルが、助手の手助けも交えて、自らの手で筆写した写本なのです。例えば『ホィクルの書』に収められた『植民の書』は、ホィクルの手によって拡大版となったヴァージョンです。それらを研究すると、ホィクルが他で書いた書物をも編集し、そして多くは内容をコンパクトにして書き加えていることがよくわかります。このような方法によって、書物を集め、編纂し、まとめた『ホィクルの書』は、写本伝統の中でも特異な位置づけをされているのです。(グンナル・ハルザルソン&ステファン・カールスソン)
この詩は詩人ショゥゾゥルヴルがソルレイヴルという人物からもらった楯に描かれていた神話的絵画を描写 するもの。詩人は自分のもっている神話的知識によって、楯に描かれた絵画を想像力を広げて説明していると思われます。二つのモチーフが主な詩の内容となっています。すなわちシャツィによるイズン強奪とそれに対するロキの冒険、またソゥルの巨人フルングニルとの闘いの模様です。
ホイストロングは北欧神話の最古の文献資料の一つです。スノッリ自身すらこの詩を利用して神話編纂を行っているのです。
ホルツマーク(ノルウェーの北欧神話学者)は、『ホイストロング』をゲルマン人の崇拝演舞を描いたものだという意見を示しましたが、今日では否定されています。
[追記]リチャード・ノース氏に寄れば、『ホイストロング』の中のハィニルの役割は、それ以外の資料に見られない機能を表しています。すなわち、ロキとの親密な関係です。ロキは「ハィニルの勇気を試すもの」というケニングを与えられていますが、またロキはハィニルへの友情からシャツィを攻撃し、一方ハィニルはロキの安否を気遣うという情景が描かれているのです。ハィニルは「若い雄鳥(喧嘩好き)」という名前の意味を持つ故、「ハィニルの勇気」を試すということは、決して「脆弱な性格の神(ハィニル)が肝を冷やす」という意味ではあり得ないのです。従って、ここではロキとハィニルとの非常に親密な関係がほのめかされていると考えられるわけです。
アイスランドの全島集会場を見下ろす位置にある岩で、「法の宣言者」による法の朗唱などがここからなされる他、公衆に訴えようとするものはここから語り掛けました。人々の集まっている空間を見下ろし、絶壁を背にする形になり、この絶壁に向かっても会衆の方に向かっても声はよく反響して聞こえます。アイスランドのシングヴェッリル国立公園の中に今でも名所として残っています。(『サガ選集』p. 266.加筆あり)トップへ
あるいは「法を語るもの」とも言う。アイスランドの全島集会体制に於いて、多少とも報酬を受け取る唯一の公人。任期三年、再選可。報酬財源は没収財産。1271年廃止。その主な任務の第一は集会の開始を合図すること。第二に訴訟上法的手続き等法知識を必要とするものにそれを与えること。第三に毎年すべての法の三分の一を「法の岩」から朗唱すること(つまり三年任期中にすべての現行法を朗唱することになる)。第四に新規に採択された法を「法の岩」から朗唱することによって発効させること。このうち、第三の機能は、12世紀初頭に法が多くなりすぎ、書き留められるようになったためなくなった。公務員とも言えず、支配者でもなかったが、法的共同体としてのアイスランド社会の指導者であり、実際にこの職務に就いたものは社会の最有力者であった。(『サガ選集』pp. 265-66. 部分的に加筆あり)
『巫女の予言』62節との関連で、スノッリはホズルとバルドルはともにラグナロクにやってくると語る(『ギルヴィの惑わし』52節)。スカルド詩の中ではホズルとバルドル神話との繋がりは全くと言っていい程なく、彼の名前はケニングの中でも数度のみ、それも神話的人物だということ以上の意味はわからないような言及の仕方なのである。
古英詩『ベーオウルフ』の中にみられるあるエピソードがバルドル神話に近いものだと考えられている。そこに出てくる二人の兄弟が似た名前を持っているからである。![]() (ホズル?)が兄弟のHerebeald (バルドル?)を悲劇的な事件の中で殺してしまうのである(『ベーオウルフ』2434行以降)。しかしながら、バルドル神話との類似点は矢をつかうところと二人の名前のみである。したがって、二つの繋がりは特に信憑性のある推理とはいいかねる。
(ホズル?)が兄弟のHerebeald (バルドル?)を悲劇的な事件の中で殺してしまうのである(『ベーオウルフ』2434行以降)。しかしながら、バルドル神話との類似点は矢をつかうところと二人の名前のみである。したがって、二つの繋がりは特に信憑性のある推理とはいいかねる。
デュメジルは、インドの神話の中に類似のものがあることを指摘している。そこでは無敵といわれた「バルドル」が盲の「ホズル」によって殺されるのである。したがって、デュメジルはホズルに、インド・ヨーロッパの伝承の中における盲の神の役割を見ているのだ。
トップへ