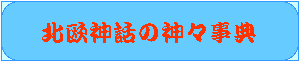 戻る
戻る
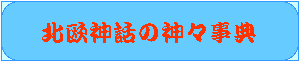 戻る
戻る
カ
『グリームニルの言葉』第44節によれば、犬と解されている神話的な生き物。『巫女の予言』44、49、58節では、黙示的幻視の中で名前が言及されるだけですが、そこでは、グニパヘッリルの前で繋がれていて、吠え猛るものとされています。スノッリの『エッダ』「ギルヴィの惑わし」の中では、ラグナロクにティールと戦う者とされています。これをスノッリ自身の解釈によって挿入されたエピソードと考えることもできるのだそうです。多くの学者によっては、『バルドルの夢』の中に現れるヘルにいる犬と同一視されています。また一方では、フェンリス狼の別名だと解釈されています。この場合、繋がれているという描写には説得力があります。多くのケニングの中にガルムルの名前が見られることから、ガルムルは北欧人の神話ではかなり有名な存在だったことが推察されます。
キ
ギャッラルブルー ![]() (「ギョッル川にかかる橋」の意味)北欧神話の中に見られる、地下世界の川にかかる橋。
(「ギョッル川にかかる橋」の意味)北欧神話の中に見られる、地下世界の川にかかる橋。
この橋の名は、時代が下ってからしか記録されておりませんし(スノッリと彼の甥の、ソルズルの息子ストゥッラによってのみ)、また、中世の神秘文学の影響を色濃く受けたものです。『ギルヴィの惑わし』第四十九章では、スノッリはこの橋は「きらきら光る黄金」で覆われている、と描写しています。
ヘルモゥズルは、ヘルに向かう途中、北に向かってヘルヴェーグル(ヘルの入り口の門)へと続くこの橋を渡っています。この橋の守り手は召使い女のモゥズグズルです。
たとえ断片的な記述であれ、サクソ(一巻、第三十五章)に描かれるハディングスの地下世界への旅や、「古き時代のサガ」(Fornaldarssogur)や中世後期の伝説的ロマンスに登場することからも、ギャッラルブルーの[すなわちヘルに続く橋という]概念が、中世スカンディナヴィアに広まっていたことは明らかです。
巨人
北欧神話において、二つの点で巨人は重要な役割を担っています。第一に世界の創造についてのゲルマン人の神話の中に登場する巨人がおり、第二に、神話的エピソードの中に登場する巨人がいます。
巨人は人間と神々との関わりにおいて、肯定的にも否定的にも作用しています。巨人は、神々や人間の住む世界の外にあり、寒さと危険に満ちている「ウートガルズル」に住んでいます。巨人の概念は、たぶん、特に冬の様子に見られるような、人間の理解力を圧倒し、人間の経験する閉じた世界の外に存在した、自然の様々な現象を観察して生まれたのかも知れません。たとえば「霜の巨人」の存在は、そのよい例でしょう。このように考えるとき、巨人は自然の精霊とも言え、この世界に元々存在した者のひとつとも言えるわけです。
ゲルマン神話において、世界の創造はひとりの巨人「イーミル」から始まっています。そして太古の巨人族の娘から神々の先祖たちも生まれています。たとえば、オージン、ヴィリ、ヴェーは女巨人ベストラから生まれています。神族と巨人族のはっきりとした区別は、北欧神話には見られません。というのも、時に神々は巨人族の娘を誘惑したり、彼女達と結婚したりしているのです。たとえば、ニョルズルはスカジと、フレイルはゲルズルと結婚し、オージンはグンロズを誘惑しています。また巨人たちも、力を用いたり、平和的な交渉を持って、女神達をなんとか手に入れようと試みますが、失敗しています。たとえば、シャツィはイズンを、スリームルはフレイヤを、フルングニルはシフとフレイヤを手に入れようとします。アース神族は巨人族と仲良くすることもあります。その様子は、海の巨人アィギルの館での宴会などに見られます。太古の巨人には、たとえばミーミルやヴァフスルーズニルなど、非常な賢さを持っていると描かれる者が幾人もいて、神々でさえ、その知恵を敬うのです。
しかしながら、ウートガルズルの力ある住民である巨人達は、神々や人間たちの閉じた世界への耐えざる脅威の象徴でもあります。ここにおいて、アース神族の最も力強き神ソールは、その時間のほとんどを巨人との戦いに費やすのです(現存する資料では、ヒーミル、スクリーミル、スリムル、シャツィ、フルングニル、スリーヴァルディとの戦いが語られます)。このような事実から、時を経るにつれ、巨人の持つ否定的な側面が、ゲルマン人の神話では上位を占めることになったようです。我々の典拠とする文献はすべて異教時代の終わりからキリスト教時代にかけてのものですが、異教神話の登場者たちを悪魔とみなすキリスト教的解釈が巨人の否定的イメージをさらに強めたことは明らかでしょう。
それでも、巨人族の様々な者が異教時代からすでに登場しています。巨人を表す元々の語は古北欧語のヨートゥン(jötunn;複数ヨートゥナル jötnar)、古英語のエーオテン(eoten)があります。これは巨人一般を指す語で、否定的な含意はありません。他方、古北欧語のスルス(þurs;複数スルサル þursar)あるいはスッス(þuss;複数スッサル þussar)は、異教時代の終わりでもすでに否定的な意味を含んでいました。これはルーン文字の一つスルスが黒魔術において働いていたことからも明らかです(「スキールニルの言葉」36節)。トロルは悪辣な怪物としての巨人を指します。中世においては、トロルは巨人とは異なる別の悪い生き物と考えられ、区別されました。
キリスト教の影響が強まっていったことによって、巨人をより害の少ない存在として描く傾向が見えてきました。彼らを悪魔的なものと見なす一方で、中世最盛期の文献の中には、巨人が今日の民話に見られるようなものと考えられていた事実が見られます。巨人は破壊行為を行うものであるが、頭が弱く、結果として知恵を用いて負かすことができる、というものです。古北欧語文献において、10世紀から13世紀までに見られる巨人の名前から、このような巨人観が確認できます。そこでは巨人や女巨人は、汚く、毛深く、醜く、バカで、特にうるさい存在として描かれるのです。
ギルヴィ Gylfi 神話的伝説のスウェーデンの王。
スノッリに寄れば、中世の学究的な理解では、アゥスたちよりスウェーデンの支配を受け継いだといいます(『ギルヴィの惑わし』序章;『イングリンガ・サガ』5章)。『ギルヴィの惑わし』本文では、スノッリはギルヴィを枠物語の主人公として用いています。スノッリの『エッダ』のスールルでは、ギルヴィは「海の王」として挙げられていますが、これは彼の名前の語源からも(ON gjalfr「海、波」)、イングリンガ・サガの中で彼が担う役割からも、適切と思われます。イングリンガ・サガの中ではスノッリの『エッダ』序章と同じく、ゲフィュンが耕し、スウェーデンから引き離した土地(すなわちシェラン島)を彼女に与えています。恐らくギルヴィは元来は海の巨人の一人であったと思われます。
ギンヌンガ・ガップ Ginnungagap エッダの創世神話の中で、世界の創造の前の宇宙的な空虚のこと。
『巫女の予言』第三節には
「イーミルが住まう 遙かな太古
砂の浜もなく 海もなく 冷たい波もなく
大地もなく 上に天もなく
穴はうつろであった しかし育つ草もなく」
とあります。このことから『巫女の予言』を書いた詩人は、ギンヌンガ・ガップを創世以前の空虚とみていたことがわかります。スノッリは『ギルヴィの惑わし』第四章の中で、どのようにして、氷のニヴルヘイムルがギンヌンガ・ガップの北に存在するようになり、炎のムスペッルスヘイムルが南に存在するのかを語っています。
フヴェルゲルミルと呼ばれる泉がニヴルヘイムルの中にあって、エーリヴァゥガルと呼ばれる河の集まりを生み出します。それは毒気に満ちていて、ギンヌンガ・ガップの北で凍り付くのです。ムスペッルスヘイムルからの炎の破片が、静寂の中にあるギンヌンガ・ガップの中で氷の上に落ち、そこに命が宿ります。それが創世の巨人イーミルの誕生です。同時に創世の雌牛オイズムラも現れるのです。初めの神々であるオゥジン、ヴィリとヴェーはその巨人を殺し、ギンヌンガ・ガップの真ん中にその体を投げ入れます。そして彼の体から大地を作り上げるのです(『ギルヴィの惑わし』第七章)。
スノッリは『ギルヴィの惑わし』第十五章の、世界トネリコのイッグドラシッルがある場所について語るところで、再びギンヌンガ・ガップについて言及しています。トネリコの根の一つは「かつてギンヌンガ・ガップのあった、霜の巨人たちのところにある」といいます。
後に、ブレーメンのアダムの書いた教会史の用語解説(四巻39章)のおかげで、ギンヌンガ・ガップの概念はエッダに限られたものでなく、スカンディナヴィア全体に広くあったことがわかります。そこにはimmane baratrum abyssi 「恐ろしい地下の深淵」をGhinmendegopの意味としています。
ギンヌンガ・ガップの語源的な意味の解釈は困難です。ヤン・ド・フリースは、その詳細な研究で、ギンヌンガ・ガップは「大きく口を開けた虚ろ(うつろ)」というよりはむしろ、「不思議な(あるいは創造的な)力に満ちあふれた虚ろ」という意味であると言っています。
中世のアイスランド人たちが考えたギンヌンガ・ガップの地理的位置について、カッシディは、世界の端の深淵をギンヌンガ・ガップと呼んだ、という結論を出しています(とはいえ、この結論が、彼の牽強付会な説だという意見もあったりします)。しかし中世後期には、世界を取り囲む大洋が大西洋と繋がる溝があり、それがギンヌンガ・ガップだと考えられていたようです。
クヴァシル Kvasir
アース神族とヴァン神族の二つの神族が「ヴァン神族との戦い」のあと、和平を結ぶのであるが、その時彼らは一つの壺に唾を吐き入れ、そこから全ての生き物の中で最も賢いクヴァシルを創ることによって和平の誓いを結んだのであった。
二人のドワーフ(フャラールとガラール)はクヴァシルを殺し、その血に蜜を混ぜて蜜酒を造った。それを飲むものは誰でも詩人になれるのであった(スノッリ『詩語法』第一章)。これが、蜜酒(あるいは「詩人の蜜酒」とも「スカルドの蜜酒」とも言われるが)が、「クヴァシルの血(Kvasis dreyra(エイナール・スカーラグラム『ヴェッレクラ』1節)」と呼ばれるかの理由である。
『ギルヴィの惑わし』第五十章ではスノッリはクヴァシルを「アース神族の中で最も賢い者」と記しているが、『イングリンガ・サガ』第四章では、ヴァン神族の中で最も賢い神として、アース神族への人質として渡されたと述べている。このように齟齬を来しているのは、これが別の伝承に基づいていることに起因するのではないだろうか。
もともとクヴァシルという名前は、木の実の果汁を指すもので、それが果汁を発酵させてできた飲み物(ノルウェー語kvase、ロシア語kvasを参照)を指すようになったと思われる。太古の文化において、このように発酵させた液体を造るには、果実を噛んでそれを容器に吐き入れる、共同体の儀式的な慣習があった。北欧神話のクヴァシル創造と明確に対応すると思われる。
スノッリが太古の神話を忠実に記していることの証拠としては、10世紀のケニングに現れる「クヴァシルの血」(上述)という表現があるが、その他に、クヴァシルと蜜酒盗みが結ばれている神話が、インドのソーマ(神々の飲み物)をインドラが盗む(鷲の姿かインドラ自身の姿で)という対照神話の存在がそれを裏付けている。両方の神話の要素を比較することで、クヴァシル伝説が、インド・ヨーロッパ起源の古い神話だと結論づけることができよう。
スノッリにおけるクヴァシル伝説はヴァン神族との戦争を語った後に位置している。唾を混ぜることでやり方が、和議を結ぶ中心になっていることから、この伝説がいかに古い神話に基づいているかがわかる。というのも、唾を混ぜるという行為も、飲み物を共同で醸造するという行為も、和議を結んだり、共同社会を形成したりする際の太古からの民俗的な重要な儀式として多数の民族の中に存在することが知られているからである。
さらに、デュメジルはクヴァシル伝説の中に反映されているこの儀式が、インド・ヨーロッパ共同体に於ける制度の三種機能を統一するシンボルにもなっていると解釈している。すなわち、アース神族とヴァン神族はもともと一つの民の中の、宗教に拘わる階層、統治や戦争に拘わる階層が、平和時に大地の生産に拘わる階層と対立していたものが、和解に到る過程を示している、と解釈するのである。
グッリンボルスティ![]() Gullinbursti, Gullinbyrstiという異綴りも。古北欧語「黄金の剛毛(を持つ豚)」の意。
Gullinbursti, Gullinbyrstiという異綴りも。古北欧語「黄金の剛毛(を持つ豚)」の意。
この名はスノッリの著述の中にのみ見られます(『ギルヴィの惑わし』48節、「詩語法」7節)。おそらくはスノッリが、ウルヴルの『フースドラゥパ』にある「イノシシ」のためのケニングについて説明をするために思いついた名前でしょう。
グッリンボルスティはスリズルグタンニ(「危険な牙を持つ者」)とも呼ばれますが、フレイルの乗る車を引き(『ギルヴィの惑わし』48節)、夜も昼も、空中も水上も、いかなる馬よりも早く走ることができ、その体毛も明るく輝くのでありました。グッリンボルスティはブロックルというドワーフによってこしらえられました。このようなおとぎ話的な要素は、唯一スノッリの粉飾ということで理解できそうです。
986年に既にウルヴル自身も、イノシシはフレイルとの拘わりのある動物として承知していたということがあります。またソナルブロートは(ソナルゴルトルというイノシシの生贄)、歴史の早くから収穫を祝福するもののようにみなされていました。確かにフレイルとイノシシとを結びつけることは広く認められたつながりではありますが、文献的な史料が常に伴われる、というわけではないのです。それでも、スウェーデン王のシンボルとして、指輪に据えられたイノシシやスウェーデン製のヘルメットの上に見られるイノシシは、ヴァン神族との繋がりをほのめかしてはいるのです。
グニパヘッリル Gnipahellir 古北欧語「上部がせり出している洞窟」の意?
神話的な地名。詳しいことはわかりません。『巫女の予言』44、49,58節に登場して、この場所の前でガルムルが繋がれて、吠えていると言及されますが、ラグナロクにあたり、ガルムルは縄目を切って走り出す、というのです。グニパヘッリルがヘルの入り口に続くと解釈されることも多いです。その根拠はガルムルとヘルの犬とを同一視することによります。ガルムルとヘルの犬を同一視しないドイツの学者ジメックなどはこの解釈には反対しています。
グラズヘイムル![]() 「輝く家、または喜びの家」オゥジンの住まい(「グリームニルの歌」8節)、またヴァルホッルの置かれているところでもある。スノッリは『ギルヴィの惑わし』14節において、一つのhof(ホフ、寺院)であり、オゥジンと12人のアゥス(神々)たちが高座を持つところとして描いている。またスノッリの記述に寄れば、内も外も黄金のようであり(=つまり輝いていて)、地上で最も良く、かつ大きな建物である。
「輝く家、または喜びの家」オゥジンの住まい(「グリームニルの歌」8節)、またヴァルホッルの置かれているところでもある。スノッリは『ギルヴィの惑わし』14節において、一つのhof(ホフ、寺院)であり、オゥジンと12人のアゥス(神々)たちが高座を持つところとして描いている。またスノッリの記述に寄れば、内も外も黄金のようであり(=つまり輝いていて)、地上で最も良く、かつ大きな建物である。
グングニル 古北欧語 Gungnir 「振るうもの、振り回されるもの」の意。
オージンの槍。オージンを連想する持ち物とされる。
9世紀の詩人ブラギもすでにオージンのことを「グングニルを振るう者(Gungnis váfaðr)」と呼んでいます。エギルはオージンを「槍の主人(geirs drótinn)」とも呼びます。コルマークルはフロプトゥル(オージンの別名)のことを「グングニルを運ぶ者」と呼びました。オージンは自分を犠牲にしたとき、自分を槍で傷つけていますし、このような傷は、オージンへの生け贄を捧げた記録によっても知られています。また、オージンとニョルズルとが互いに槍で傷つけ合いながら、自分たちをオージン自身に献納する様子を、「イングリンガ・サガ」第9章でスノッリは描いています。オージンは戦場で、この槍を持って戦士を殺し、自分で彼らを連れ去るのです。敵方に投げつけるはじめの槍は、相手をオージンに捧げるという意味が込められます。
スノッリによれば(「詩語法」第9章、第33章)、グングニルは、他の神々の持ち物と同様に、イーヴァルディの息子たちというドワーフの鍛冶屋によって作られました。これはロキが彼等に造らせたのです。「シグルドリーヴァの言葉」第17節によりますと、グングニルの槍の刃には、ルーン文字が刻まれているそうです。実際に考古学的発掘物の中には、民族移動期の槍に刻まれたルーン文字があります。青銅器時代のスカンディナヴィア南部の岩に掘られた絵画から、オージンと確実に見られる「槍の神」」への信仰が証拠立てられます。ヴァイキング時代の絵画石碑には槍を持つ騎士の姿がオージン自身だと見なされています。それは彼に伴う鳥たちや、時に八本足の馬「スレイプニル」が描かれているからです。
しかしながら、ドイツのシュヴィーテリングの学説に言われるように、槍の神オージンが「隆盛」となる一方で、剣の神ティールが「没落」していくという北欧神話の傾向が、そのまま剣から槍へと戦法が変わっていった事実を反映するという可能性は低いと思われます。槍という武器は、正義の神ティールと同じように、支配の神オージンにとっても権威を持つ者の象徴として重要だったことでしょう。
ゲフィュン Gefjun / Gefjon アィシルの女神の一人。『エッダ』に描かれるエピソードは次の通 り>『エッダ』からの抜粋>ゲフィュンの銅像(コペンハーゲン)
スノッリがイングリンガ・サガ5章と『ギルヴィの惑わし』1章で語るスカンディナヴィアの女神。オージンがスカンディナヴィアへの大移動する途中フューン島のオーデンセ(オージンの島)に留まります。そこでゲフィュンを北へ送って、自分たちの土地を探しに行かせます。スウェーデン王のギルヴィはゲフィュンに耕すための土地を与え、彼女は自分の四人の息子を雄牛に姿を変えます。彼女は巨人との間にその四人の息子をもうけたのです。彼女は四頭の雄牛を鋤の前につなぎ、スウェーデンからシェラン島をとってきてしまいます。スノッリはさらに、このシェラン島はかつてはスウェーデンのメーラレン湖があったところの土地だという説を加えて記します。後にオージンの息子のスキョルドゥルがゲフィュンと結婚し、二人はレイレに住んだとスノッリは語ります。
スノッリのメーラレン湖への言及は明らかに後世の追加であり、もともとはこれはスコーネとシェランの間にあったオェーレスンドに関する起源論的な言い伝えであったでしょう。この伝説をスノッリは「最古の詩人」ブラギの書いた『ラグナルの賦』13節(9世紀;現存するスカルド詩の中で最古のもの)にあるゲフィュンとギルヴィについての言及と結びつけたのであって、もとからこの言い伝えと『エッダ』の言説とが同じであるとは限らない、と現代の学者は考えています。
昔の学者たちはゲフィュンをフレイヤ、あるいはフリッグの別名と解釈してきました。これは「ロキの口論」20節においてロキはゲフィュンをネックレスと引き替えに「白い若者」あるいは「美しい若者」に自分を差し出した、といって非難するからです。しかしながら、「ロキの口論」はけっして古い詩ではなく、その非難についてもあまりにもステレオタイプ的であって、その意味内容に重きを置く必要はないという節の方が優勢です。いずれにせよ、たとえゲフィュンがフレイヤと同一視され得ないにしても、彼女は豊饒と守護の女神と考えてもよい理由があります。彼女の名前の意味は「与える者」だからです。確かにゲルマンの女神のほとんどは同じ役割を担っています。が、特にアイスランドの「ステョルン(「(神の?)支配」の意)」という中世の有名な書物においては、ゲフィュンは女神アフロディテーと同一視されているのですから、豊饒の女神という理解は中世において主流であったでしょう。
トップへ