| トップページへ | 研究指針の目次 |
目次
45.1 はじめに
45.2 気温観測の補正
(1)観測方法の変更
(2)都市化の影響
(3)日だまり効果
45.3 日本のバックグラウンド温暖化量
(1) 100年間当たりの気温上昇率
(2) 気温ジャンプ
(3) 太陽黒点数と気温の関係
(4) 火山噴火と気温の関係
(5) 海洋変動との関係
45.4 気象災害の時代変遷
45.5 都市の熱汚染量
45.7 まとめ
参考文献
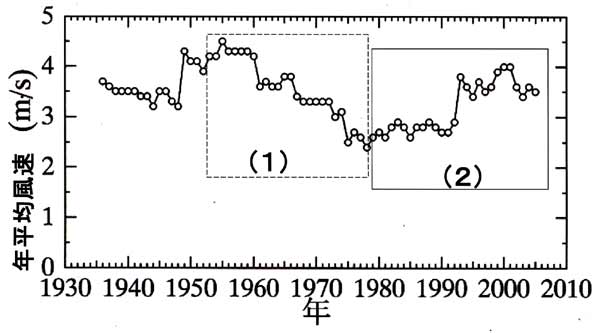
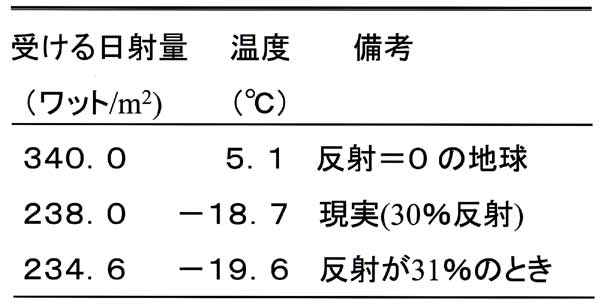


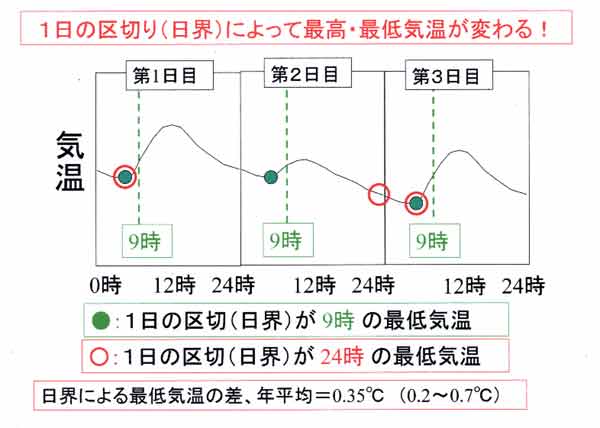


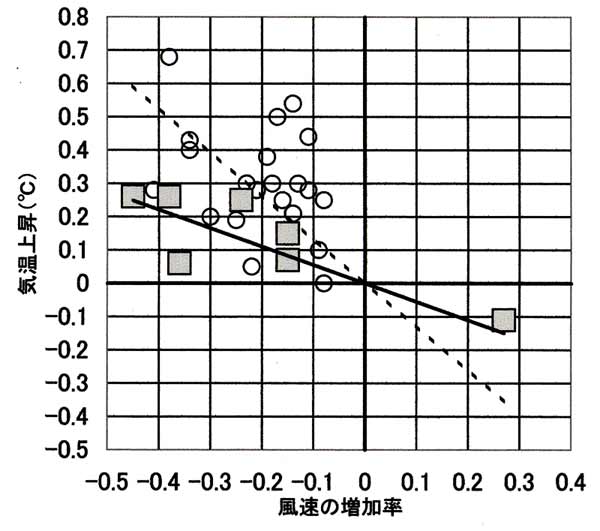

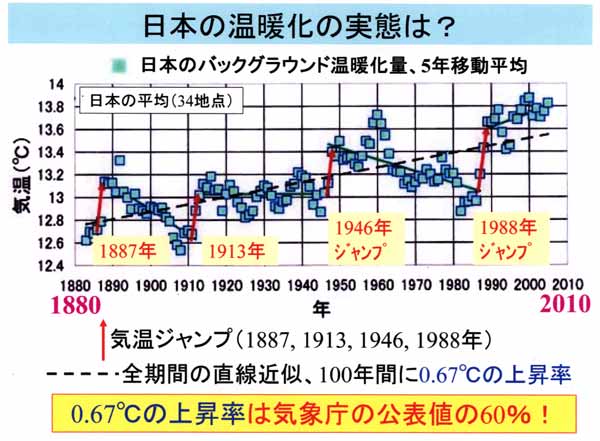
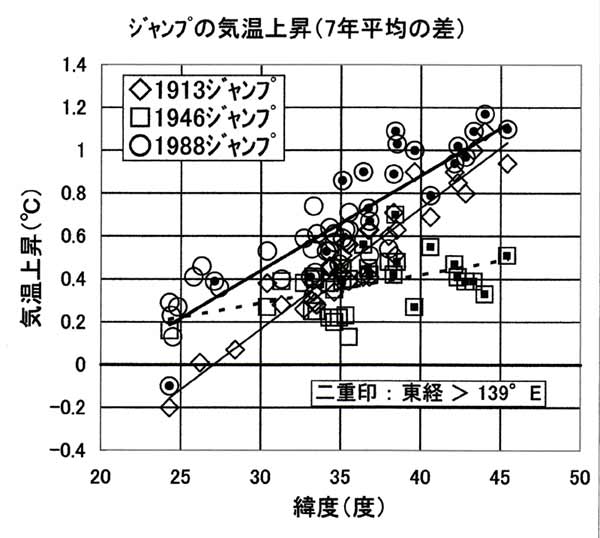
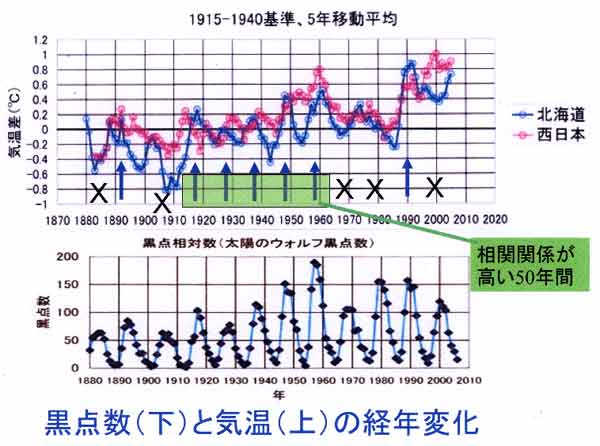



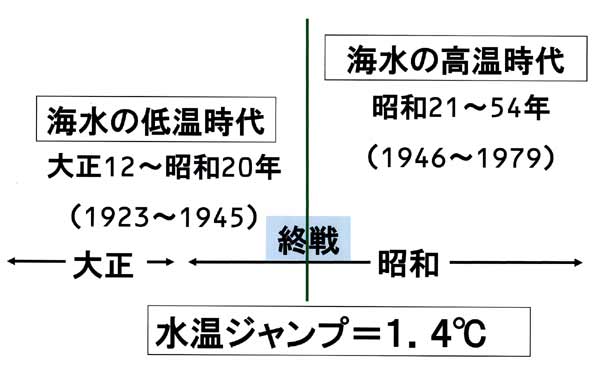
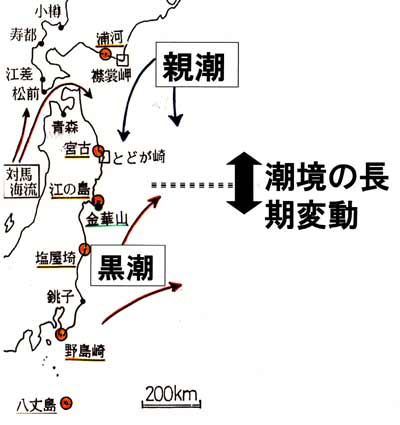
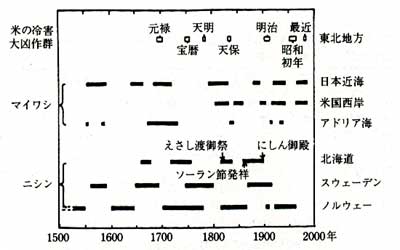
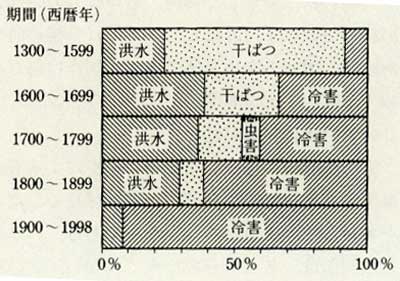
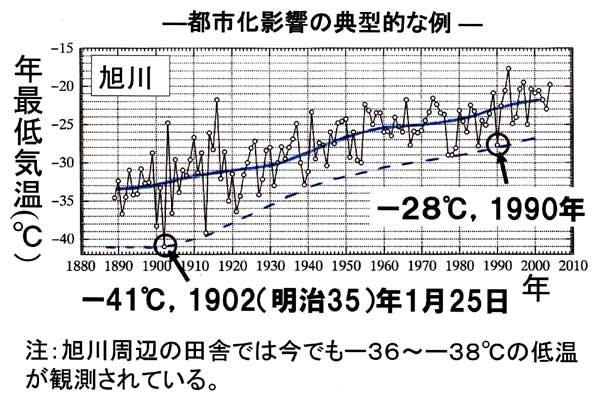
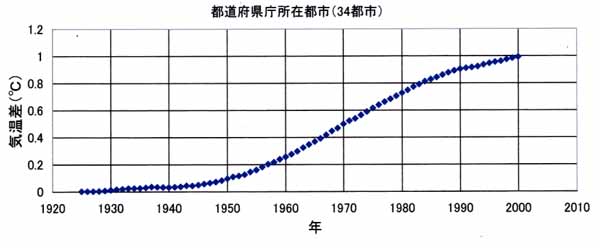
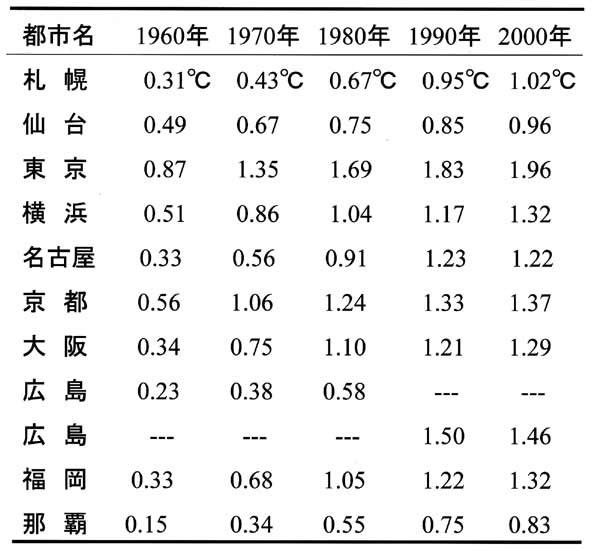
| トップページへ | 研究指針の目次 |