「農産物の緊急輸入制限に関する質問主意書」
小沢和秋、赤嶺政賢の両衆議院議員が提出
十月三十一日、日本共産党の小沢和秋、赤嶺政賢の両衆議院議員は、「農産物の緊急輸入制限に関する質問主意書」を提出しました。十一月十七日には、福田康夫・内閣総理大臣臨時代理から答弁書(内閣衆質一五〇第二四号)が送られてきました。以下、質問と答弁を紹介いたします。
輸入野菜の急増が、国内産野菜の価格暴落の大きな要因
○小沢和秋・赤嶺政賢衆院議員
WTO協定の発効以降、農産物の輸入が激増している。生鮮野菜だけをみても、一九九二年から一九九九年の七年間に一例を上げればタマネギ六倍、ブロッコリー四倍、ゴボウ十七倍、サトイモ五倍、ニンジン・カブ十七倍、シイタケ六倍等と輸入が急増している。これに加えて乾燥、塩蔵、加工品を含めるとその増加は膨大な量となる。
生産コストが安い海外からの輸入野菜の急増は、国内産野菜の価格暴落の大きな要因の一つとなっている。産地においては産地廃棄を余儀なくされるなど大変深刻な実態が浮き彫りになっている。
福岡県では、キャベツ一㎏で三十二円、ハクサイが十五㎏(五~六玉)で二百円前後、レタスが一㎏五十円というように出荷経費も出ないところまで価格が下がっている。
佐賀県では、国内生産量第二位のタマネギが輸入の急増から価格が暴落し、県内で三千トンもの産地廃棄が余儀なくされている。
長崎県では、県の特産品であるバレイショ(加熱)の輸入が九十二年の約一・六倍に増え、生産者から運賃や箱代にもならないと悲鳴が上がっている。
大分県では、国内生産第一位の乾シイタケが九十三年から激増した輸入品により大打撃を受け、県下のシイタケ農家数は高齢化とあわせて、九千四百六戸(八十九年)から五千四百二十二戸(九十八年)にまで激減している。
宮崎県では、キュウリ・ピーマン・トマト等の施設栽培の生産農家は大打撃を受け、経営の継続すら危ぶまれている。特にピーマンの輸入量は九十二年からの七年間で二千二百倍にも激増し、ピーク時の九十一年度の半値以下に暴落している。
鹿児島県では、カボチャの輸入が増え、価格は運賃・箱代等を含め二百円ないと引き合わないというのに、一㎏当たり平均百二十九円にしかならないところまで暴落している。
また、野菜ではないが、熊本県の八代地方の農業の基幹作物であるイ草・イ製品は中国からの安価な畳表の過剰輸入に押され、畳表の平均価格は九十六年の千三百八十円から今年度八百五十円前後(落札価格)まで下落している。
沖縄県でも、外国野菜の大量輸入や基幹作物であるサトウキビの価格保障制度の破壊などで、農業の衰退をまねいている。
このままでは、農産物の安定供給を図ってきた農家の生産意欲は著しく減退し、その役割を果たすこともままならない。コメの輸入自由化や減反政策により、米作から野菜生産へと転換したうえでの輸入増による価格の暴落だけに、政府の責任は重大である。輸入農産物が増加し続けるなら、生産農家は生産の縮小・離農を余儀なくされ、国内農業は衰退どころか壊滅せざるをえない危機的状況に瀕している。
そこで、次の事項について質問する。
Q1過去十年間の野菜の生産量、輸入量、価格の推移は
○小沢和秋・赤嶺政賢衆院議員
指定野菜十四品目の過去十年間の国内生産量および輸入量、ならびに生産者価格の推移を政府はどう把握しているのか。また、それについてどう考えるのか。
A1輸入は国産野菜の不作等による不足を補うため
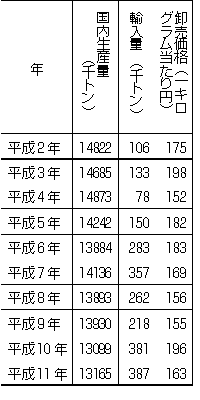 ●福田康夫・内閣総理大臣代理
●福田康夫・内閣総理大臣代理
野菜生産出荷安定法(昭和四十一年法律第百三号)に定める指定野菜十四品目の過去十年間の国内生産量、輸入量及び卸売価格の推移は、別表のとおりである。
国内生産は、野菜消費の減少等により減少傾向にあり、輸入は、主として国産野菜の不作等による不足を補う形で行われている。卸売価格は、天候による作柄の変動等に応じて変動しており、価格の上昇傾向又は下落傾向が一貫して続いているという状況ではない。
Q2価格暴落の要因は輸入急増ではないか。直ちに調査を
○小沢和秋・赤嶺政賢衆院議員
生鮮野菜の価格暴落要因の一つは輸入農産物の急増であることが、広く指摘されている。政府はこれを認めないが、その根拠はどこにあるのか。また、生産と流通の実態を機敏につかまなければ、このままでは生産地の崩壊はまぬがれない。ただちに輸入品との因果関係の調査や、損害額の算定を実行すべきと考えるがどうか。
A2要因は天候に恵まれ出荷が増えたから、輸入の影響は各都道府県から情報収集中
●福田康夫・内閣総理大臣代理
生鮮野菜の価格は、野菜供給全体の八十五パーセント程度が国内生産により供給されている我が国の野菜の需給構造の中で、天候による作柄の変動等に応じて変動しており、本年前半に卸売価格が総じて平年値(平成三年から平成十一年までの九年間の平均値)を下回る価格で推移したのは、その期間が天候に恵まれ、国産野菜の生育が順調であったため出荷量が増加したことが主因であると考えている。
なお、野菜の輸入による国内の野菜生産への影響について実態を把握するため、現在、農林水産省において都道府県等を通じて情報の収集に努めているところである。
Q3全国でセーフガードを求める意見書があがっている。直ちに措置を
○小沢和秋・赤嶺政賢衆院議員
農産物の緊急輸入制限を求める意見書、請願等が各地の九月地方議会で採択されているが、政府はこれまでに採択した自治体の数やその内容を把握しているか。また、この意見書等の趣旨を真摯に受け止め、WTO協定にもとづき、緊急輸入制限(セーフガード)の措置をすみやかに行い、無秩序な輸入の抑制と監視体制を強化すべきと考えるがどうか。
A3意見書は全国で三百九十五議会、発動への調査を開始する状況にない、輸入による影響の把握に努める
●福田康夫・内閣総理大臣代理
農産物についてセーフガード措置の発動を求める意見書を採択し、これを政府に提出した地方公共団体の議会の数は、平成十二年一月一日から十月三十一日までの間で三百九十五であり、その主な内容は、輸入の急増している農産物についてセーフガード措置の発動を求めるもの等であると承知している。
農産物に係るセーフガード措置の発動に当たっては、関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)等関係法令により、農産物の輸入増加の事実及びこれが我が国の農業に与える重大な損害等の事実についての十分な証拠がある場合において、これらの事実の有無につき調査を行うことが要件とされているところ、現在、農林水産省において、農産物についてその輸入動向と輸入による国内の農業への影響について情報収集に努めているが、政府としては、セーフガード措置の発動に向けた調査を開始する状況にあるとの認識には至っていない。今後とも農産物の輸入動向と輸入による国内の農業への影響の把握に努めていく考えである。
Q4日本ではセーフガードの発動はない、他国はどうか
○小沢和秋・赤嶺政賢衆院議員
WTO協定では、特定産品の輸入急増によって国内産業が重大な被害を受け、また受ける恐れがあることが政府の調査によって明らかになった時、緊急輸入制限を発動させることができると規定されている。しかし、わが国では自国の農業を守るために一度もこの規定が発動されていない。他国におけるセーフガードの発動状況について、政府はこれはどう把握し、どう評価するか。
A4世界の発動件数は二十五件
●福田康夫・内閣総理大臣代理
世界貿易機関の設立以降、世界貿易機関に通報されたセーフガード措置(暫定的なセーフガード措置を含む。)の発動件数は、平成十二年十月三十一日現在までに、二十五件であると承知している。
これらの措置は、各国の政府が、セーフガード措置の発動の対象となる産品の輸入動向と当該産品の輸入による国内産業への影響等について評価した結果、セーフガード措置の発動の要件を満たすものと認めて講じたものと考えている。
なお、これらの措置の中には、世界貿易機関の紛争解決手続の下で、セーフガードに関する協定等との適合性が争われているものもあると承知している。
Q5農家の経営維持へ積極的な価格保障を
○小沢和秋・赤嶺政賢衆院議員
野菜農家の経営維持と生産力の確保を図るため、政府としての積極的な価格保障が強く求められる。生産者及び産地に対する具体的な支援策をどう強めるか明らかにされたい。
A5指定野菜への交付金制度があり、逐次交付し対応
●福田康夫・内閣総理大臣代理
野菜の価格低落が生産者の経営に及ぼす影響を緩和するため、指定野菜について、価格低落時に野菜供給安定基金から生産者に対し交付金を交付する制度が設けられており、これまでも逐次交付金が交付されてきたところである。今後ともその適切な運用に努めるとともに、機械化一貫体系の導入や消費者に対する野菜の栄養・機能についての情報提供等野菜の生産から流通、消費にわたる各般の施策を総合的に推進していく考えである。
Q6輸入野菜の安全性に約半数が不安。残留農薬の監視結果を明らかにし、原産国表示の徹底を
○小沢和秋・赤嶺政賢衆院議員
本年七月に実施された世論調査の結果で、外国からの農産物の安全性について約四十七%の人が不安があると答えている。農産物の輸入が急増している現状の下、安全・安心な農産物確保がますます求められるが、輸入農産物の残留農薬の監視結果について明らかにされたい。また、JAS法表示にもとづく原産国表示の徹底状況について、どう把握しているか。
A6残留農薬基準に不適合なものは積戻しなどの措置をとった。原産地表示の徹底は指導する
●福田康夫・内閣総理大臣代理
輸入農産物の残留農薬の監視は、検疫所における輸入食品の検査の一環として行われており、厚生省において平成六年度から毎年集計結果を公表しているところである。平成十一年度には五千二百十六件について検査が実施され、このうち食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づいて定められた残留農薬に係る基準に適合しないものは三十件であり、当該農産物については積戻し等の措置が講じられた。
また、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)に基づいて定められた生鮮食品の品質表示基準による原産地の表示の実施状況については、農林水産省において本年七月中旬から下旬にかけて全国の約千店舗の百貨店、スーパーマーケット等で生鮮食料品を対象として調査を行ったところ、販売している生鮮食料品のうち、すべて又はほとんどのものに原産地の表示を行っている店舗の割合は、野菜、果実及び肉類についてはそれぞれ約八割、水産物については約七割という結果であり、引き続き、原産地の表示の徹底を指導していく考えである。