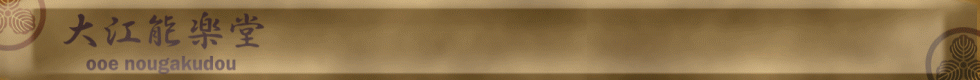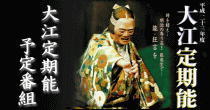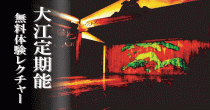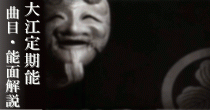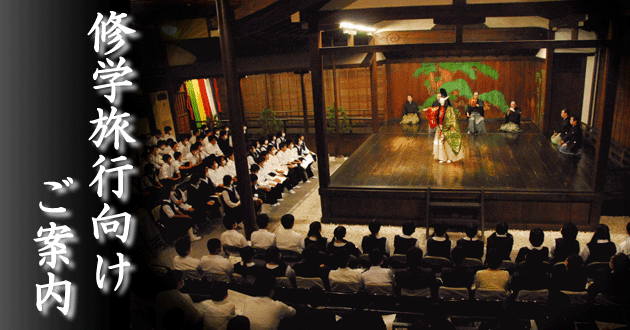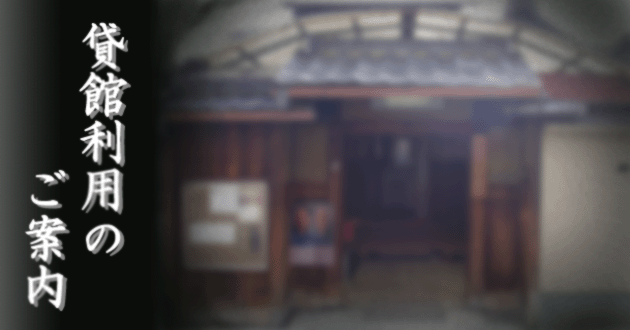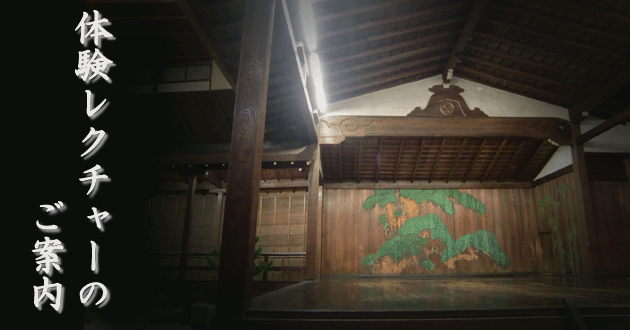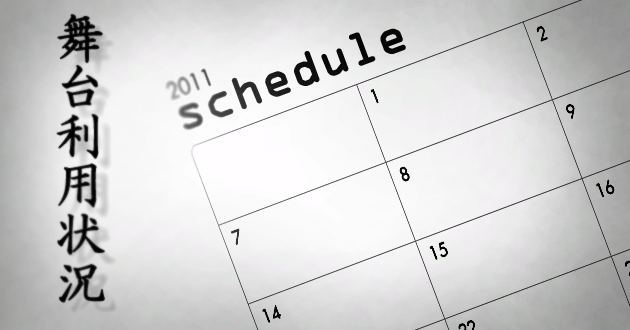能・杜若について

諸国一見の旅僧(ワキ)が東国に下る途中、三河国(現・愛知県)にやってきます。とある澤辺に美しく咲いている杜若を見つけ眺めていると、そこに言葉をかける一人の女(シテ)が現れます。僧は杜若の美しさについ見とれていたのだと言い、ところの名を聞きます。すると女は、ここは八橋という処で、古歌にも読まれた杜若の名所であると答えます。昔、在原業平が東下りの時ここで休み、「かきつばた」の五文字を句の頭において “からころも きつつ馴れにし つましあれば はるばる来ぬる たびをしぞおもう” という歌を詠んだことも教えす。やがて僧は勧められるままに女の庵に行くと、女が高子の后(二条后)の唐衣に業平の形見の初冠を着けて現れます。僧が驚いて素性を尋ねると、女は杜若の精であることを明かします。そして業平は歌舞の菩薩の生まれ変わりであることや、業平の詠んだ歌の功徳で非情の草木も成仏することができたことを述べます。更に「伊勢物語」に書かれた業平の数々の物語を語り、舞を舞い、成仏できた様を見せ、消えていきます。
能面「若女」について
若女についての解説はこちらにございます。