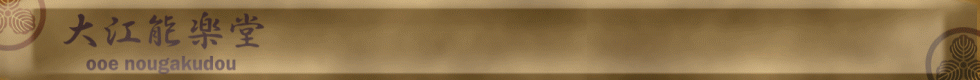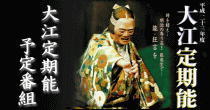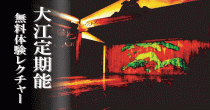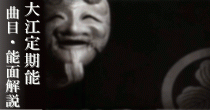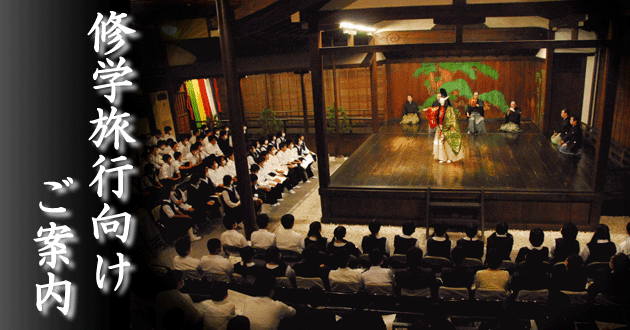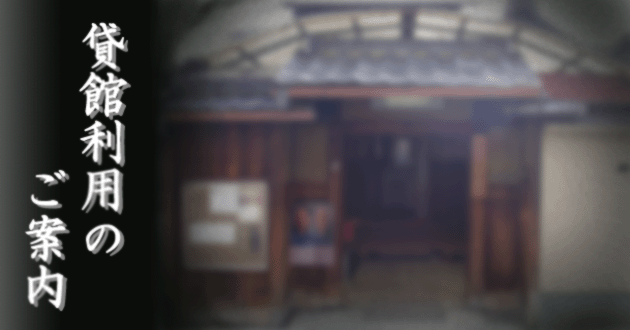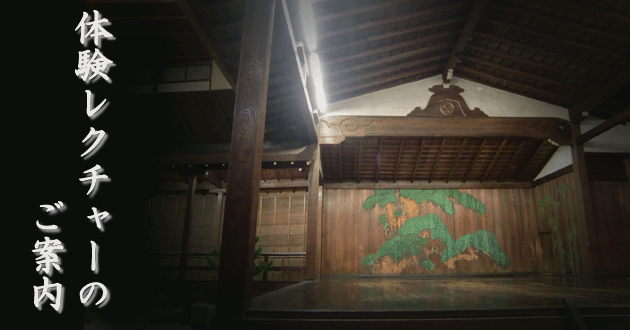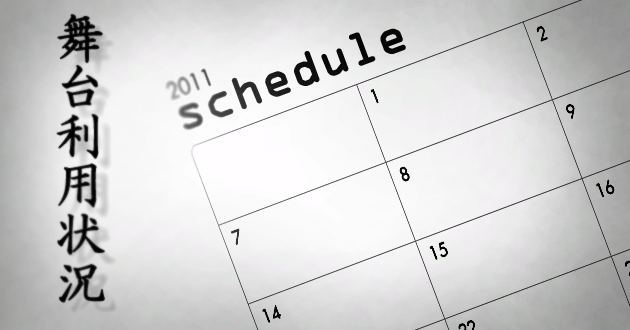能・葵上について

光源氏の北の方であり左大臣の息女・葵上が物の怪に悩まされていました。貴僧・高僧を召して様々の大法秘法の加持祈祷、医療などを施しましたが、その効果が現れないので、朱雀院に仕える廷臣が梓の弓によって亡霊を呼び寄せる呪法を行う照日ノ巫女を呼び寄せます。すると照日ノ巫女が鳴らす梓の弓の音にひかれて破れ車に乗った女(前シテ)が現れます。女は、六条御息所の怨霊であることを明かし、源氏の愛を失った恨みを述べ、葵上に祟りをなそうとします。巫女は、御息所の心を怯ませようとしますが、怨霊の嫉妬の心は益々募り、葵上を幽界へ連れ去ろうとします。《物著》廷臣は、照日ノ巫女の力でも効き目がないので、今度は急いで横川ノ小聖という行者を呼び迎えます。廷臣は駆けつけた行者を葵上の枕元に案内します。行者が直ぐに祈祷を始めると、御息所の怨霊が鬼女の姿で現れます。怨霊は行者を追い返そうと激しく争いますが、やがて行者の法力に屈し、祈り伏せられて、終には心和らげて成仏します。この作品は、源氏物語「葵」の巻に取材したものです。作品名となっている『葵上』は実際には舞台に登場しません。舞台上正先に出された小袖によって葵上が寝ている体を現します。舞台は葵上の寝所であるのです。このように能は最小限の物と役者で上演されます。このような演出は他の演劇では無い、能楽の優れた演出方法だと言えます。
能面「泥眼(デイガン)」について
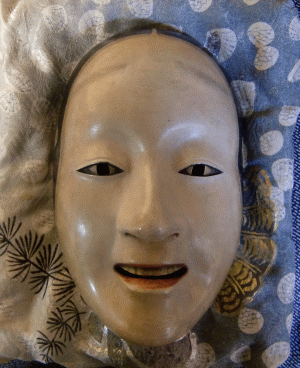
能面「泥眼」は本来「海士」などで使われることの多い面であり、女人が成仏し菩薩となった際の相貌を表しているといわれています。
名前の由来は金泥を施した目を持っている女面であるからの命名で、金泥は鞏膜の部分に塗ってあります。この工作は人間を超越した存在の表現方法です。女面ですが口は両端を後方に引き、全体がまゆ型に似ており、金泥を施した歯、毛描も適度にみだれ妖気の漂う霊的にかなり厳しい相貌をしています。室町末期においてはこのすさまじさが女の生霊の面としてふさわしいと考えられだし、「葵上」や「鉄輪」の前シテで使われるようになったと言われています。厳しい相貌ながらも女性の美しさと品の良さが残されているため、「葵上」の六条御息所のような上流婦人に最適なのかもしれません。
後シテでつかいます「般若」の解説はこちらにございますのでご覧ください。