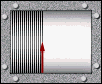
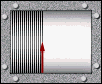 |
自宅の地震・津波・火災対策 |
政府は太平洋プレートの沈み込みを原因とする海溝型地震の予知に熱心であった。しかしその手段としての地震計やGPSによる観測網充実の方が目的となって 予報という目的を忘れてしまったようである。結果として唯一実用化できそうなのはP波を分析して逃げる数秒から数十秒の時間を与えるという緊急地震速報シ ステム位しかない。
民間の予知研究は地震計網などという金のかかるものを必要としない電磁放射、電離層プラズマ密度変化、地震雲などの前兆現象 をこつこつと研究してそれなりの成果をだしているところもあるが 、国家としての研究支援はしていないのも奇妙である。
とはいえ予測のための観測網は世界でトップレベルとなり、新しい知見や精度の高い震度や加速度の予測が可能になってきた。
いずれにせよ、兵庫県南部地震と中越地震の経験から建物の倒壊防止と地震後の火災やインフラストラクチャー喪失対策、ならびに復興費対策が重要であること が明らかになった。緊急時は政府機構が無力となると考えて住民は自衛するしかない。以下考察してみよう。
2007/09/02に産業技術研究所の活断層研究センターは浜岡原発の隣でボーリング調査し、1,000年に一度の頻度で大きな隆起を伴う超東海地震が発生し ていると発表した。
2011/3/11の東日本地震では津波がクローズアップされ、東南海地震が予告されている。しかし2013になって鎌
倉は関東大震災と同じフィリピン海プレートの下に沈み込む太平洋プレートの海溝型直下地震で震度7の揺れが今後100年間に発生しそうだという。
鎌倉における海溝型地震の発生確率
鎌倉での地震調査委員会が公表している海溝型地震の発生確率は相模湾では相模トラフによるもので、東海地震の確率より低い。
| 名称 | 予想される地震の規模(マグニチュード) | 30年以内の発生確率(%) |
| 相模トラフ | 7.9 | 0.8 |
| 東海地震 | 8 | 87 |
鎌倉における直下型地震の発生確率
鎌倉での直下型地震の震源となる断層は地震調査委員会の公表資料によれば以下の3つである。
| 断層の名称 | 予想される震度 | 30年以内の発生確率(%) |
| 三浦半島 | 6.5(武山) 6.7(衣笠・北武) 6.0(引橋) | 3以上だったが2011/1に10%東北地震後更に上昇 |
| 伊勢原 | 7.9 | 0.1未満 |
| 神縄・国府津ー松田 | 8.0 | 3以上 |
中越地震の発生確率が3%以上だったことから、確率からみれば三浦半島と神縄・国府津ー松田が要注意ということになる。なかんずく神縄・国府津ー松田は震 度8.0であるから中越地震より被害が大きいと予想できる。 ちなみに、1923年の関東大震災は城ヶ島南西10kmの海底が震源地であった。
2008/11に産業技術研究所は小網代湾の海底の堆積土を分析して、津波を発生させるM8クラスの地震は1923年の関東大震災、1703年の元禄地 震、1293年の鎌倉大地震だったと発表した。これから周期は200年と400年であったことにな り、規則正しいものでもないと分かる。

赤線が断層群
震度予想
東海地震などの地震が発生したとき、自宅のある七里ガ浜の台地での震度と加速度を原発立地の最大加速度の推定法を使って推算してみよう。
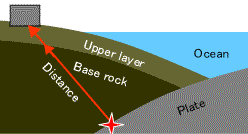
震源と解放基盤 表面の定義
| プレートまたは断層名 | マグニチュードM | 震源の深さD(km) | 震央距離(km) | 震源距離X(km) | 震度I | 解放基盤表面の最大加速度(ガル) | 表層地盤の最大加速度(ガル) |
| 東海プレート地震 | 8 | 15 | 145 | 146 | 4.7 | 76 | 159 |
| 三浦半島の衣笠・北武断層 | 6.7 | 10 | 10 | 14 | 5.6 | 236 | 479 |
| 神縄・国府津ー松田断層 | 8 | 10 | 28 | 30 | 6.1 | 477 | 963 |
このように海溝プレート型地震である東海地震は発生確率は高いが距離が遠いので脅威ではない。むしろ近距離の直下型地震が発生確率は低いが怖いとい える。三浦半島の衣笠・北武断層は至近距離だがマグニチュードが小さいので震度もそこそこだが、神縄・国府津ー松田断層はマグニチュードは海溝型に近く、 かつ至近距離にあるので最も危険ということになる。
相模トラフや伊勢原断層は至近距離にあるため、もし発生すれば甚大な被害が予想されるが発生確率は0.8%以下であるので予測の対象とはしなかっ た。
家屋の剛性
グリーンウッド氏の自宅は1979年確認申請の木造軸組み構造の62.9m2の総2階建である。1981年の建築基準法改訂前の設 計である。しかし標準設計より開口部を減らし、大部屋を標準仕様より小さくしたうえ、建設時に特別仕様とし追加費用100万円余計に支払って旧建築基準法 の基づく設計では必要とされない対角線方向の筋交いの長さが底辺の3倍となる一対のクロス筋交いを持つ耐力壁19個を開口部の無い外壁および内部仕切り壁 全てに入れ、アンカーボルトは38本、金具を多用し、屋根 、外壁は合板にスレート張りして軽量化してある。軸組み工法と9mm厚の合板を併用するツーバーフォー的なパネル構造のハイブリッド効果も含めて耐震対策 はこれ以上できないまで行った。金具を多用したとはいえ、当時はまだ筋交い金具は普及していなかったので使わなかった。
築後30年にしてケーブル類を天井裏・壁裏に通すためにダウンライトをはずしたとき、1階居室天井裏から廊下と居室の間の内壁の筋交を覗いた写真が下であ る。案の定、筋交い金具は使っていないし、期待に反し、筋交の角度が浅い。

1階居室天井裏のブレーシング1 2010/6/15撮影 |

1階居室天井裏のブレーシング2 |
柱、梁、筋交いに使用した木材は米ツガである。米ツガの木材強度すなわち引っ張り強度を690kg/cm2、 圧縮強度を350kg/cm2、安全係数を6、筋交いの寸法は10cm x 5cmである。耐力壁の 柱、梁、筋交いは相互に角度の変化に抵抗しないように連結されているトラス構造になっていると考えれば水平方向の力のベクトルは対角方向のベクトルの3分 の1となるので 筋交い金具を使えば;
圧縮耐力=350 x 10 x 5 x 19 / 6 / 3 / 1000 = 18.5 トン
引っ張り耐力=690 x 10 x 5 x 19 / 6 / 3 / 1000 = 35.4 トン
水平耐力合計は53.9トンになる。筋交い金具がなければ筋交いに引っ張り力が発生しないので圧縮側のみ有効となり水平耐力合計は18.5 トンになる。
ツーバーフォー的に使用しているパネル構造のハイブリッド効果も期待できるが、釘の腐食も考慮して計算上は無視することにする。
1階面積62.9m2の総2階木造住宅の地震の影響を受ける荷重を概算してみるとスレートの比重を2.7、石膏ボードの比重を 1.0、 米ツガ製の柱、梁、筋交いなど軸組みの比重を0.42、合板の比重を0.5、断熱材の比重を0.05とし、一階の壁の半分は基礎に直結しているためその荷 重の半分だけが耐力壁にかかると仮定してエクセルで概算すると ;
| 部分 | 自重(トン) |
| 屋根部 | 5.1 |
| 2階壁部 | 5.4 |
| 2階床部 | 0.9 |
| 1階天井と1階壁部の半分 | 3.3 |
| 自重合計 | 14.7 |
2階にある家財一式を4トンと見積もれば、耐震設計にかかわる総荷重18.7トンというところか。このうち書籍は1.5トンである。
木造低層住宅では姉歯建築士で話題となっている建物を等価1質点モデルに置き換え、応答スペクトル図を描き、建物の固有周期に相当する地震外力を適用する限界耐力計算を採用 する必要はない。地震の振動の加速度がそのまま建物に作用すると仮定すると 質量 m、力 F(トン)、加速度 g (ガル、1gal=1m/sec2)に関するニュートンの公式
m = F/g
から
家屋・家財の質量m = 家屋および家財総荷重18.7トン/地表の重力の加速度980ガル=0.0191 (トン/ガル)
ここで
従って筋交い金具があれば;
家屋が耐えられる地震の最大加速度α = 水平耐力53.9トン/0.0191 (トン/ガル) = 2,821ガル
筋交い金具がなければ(我が家);
家屋が耐えられる地震の最大加速度α = 水平耐力18.5トン/0.0191 (トン/ガル) = 968ガルとなる。
関東大震災の時は330ガル、兵庫県南部地震では地表の最大加速度880ガルが観測されたが、仙台の丘の上にあった地震計は1,000ガルを記録したとい う。そして今回の中越地震で は過去の記録としては最大の2,515ガルが記録されている。中越地震には耐えられないが関東大震災には耐えられるということになる。
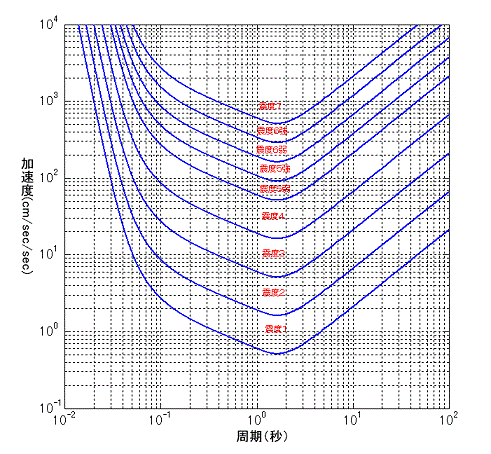
震度Iと加速度αの相関はいろいろあるが3つの推算法で大きな差がでる。上図は気象庁の換算図だ。家の固有周期を 0.55secとすれば
| 震度I | 周期
0.55secの加速度(ガル) |
地震被害想定支援マニュアルによる加速度(ガル) | α=100.5*I-0.6式による加 速度(ガル) |
| 4.4 | 45 |
109 |
41 |
| 5.0 | 80 |
239 |
82 |
| 5.4 | 140 |
378 |
124 |
| 5.6 | 160 |
523 |
165 |
| 6.0 | 260 |
827 |
249 |
| 6.1 | 270 |
984 |
291 |
| 6.2 | 300 |
1,144 |
333 |
| 6.4 | 410 |
1,472 |
417 |
| 6.8 | 750 |
2,328 |
628 |
| 7.0 | 800 |
3,222 |
840 |
| 7.5 | 1500 |
6,065 |
1,477 |
地震被害想定支援マニュアルの推定法に準拠すれば筋交い金具がある場合の2,821ガルは震度6.9に、無い場合の968ガルはほぼ震度6.1に相当する。
我が屋は筋交い金具がないので三浦半島の断層に起因する地震には充分耐えられるが、30年に3%以上の確率で発生する神 縄・国府津ー松田伊勢原断層地震にギリ ギリ耐えられるかどうかということになる。そして関東大震災と同じ海溝型直下地震の震度7では倒壊するという結論になる。
ただ無視した合板効果を考慮すればもっと強いはずである。
参考までに建築基準法が改正になった木造住宅耐震補強事業者は1981年より前の設計ではマグニチュード7.2の地震での注文住宅の倒壊の危険性65%、 分譲住宅の倒壊の危険性35%というので特注の筋交いを入れて剛構造にしたことで普通の家屋より耐震性は優れていると言える。
建設時に資金繰りが苦しいなか総工事費の8%に相当する100万円の追加工事をしたのは正解であった。
地盤との共振
グリーンウッド氏の自宅が建っている場所は45度傾斜面から平らな地形に移る突出角部分であるが、鎌倉特有のやぐらが掘れるような硬い砂岩上に直接基礎が 敷設されていて、地震の卓越振動数は高いと予想される。 多分直下型の神戸地震の ように地震の周期が1秒(1Hz)近くではないかと推定している。家屋の固有振動数が地震の卓越振動数に共振してしまってはいくら剛構造でももたない。
一般に建物の高さが高いほど(筋交いが長いほど)、また材質が柔らかいほど (ヤング率が低いほど)、重いほど、家屋の固有振動数は低くなり、ゆっくりとゆれる。東京のように厚い堆積層に乗っているいると関東地震のように周期が8 秒(0.1Hz)のゆっくりした地震に見舞われ、東京の下町では木造家屋.の被害が大きかったという。 山の手では土蔵の被害が大きかったという。
最近発見された1944年のM8の東南海地震では周期3秒と周期10秒の波が卓越していたという。周期3秒というと40階建てのビルが、また周期10秒と いうと超高層ビルや石油タンクが共振しやすい。
グリーンウッド氏の自宅は高さはないが木質系なのでやわらかく、 軽量なので固有振動数は低いだろうと推定されるがどうか。そこで耐力壁の交差する筋交いをバネとみなして固有振動数がどのくらいかチェックした。
耐力壁の各要素はトラス構造になっていると考えれば、クロスにある筋交いはバネの役割を果たしていると見なせる。このときバネ定数kは
k = E a / L (kg/cm)
ここでEは筋交いの米ツ ガのヤング率 = 99 (kg/cm2)
Lは筋交いの長さ(耐力壁の対角線長さ)、ないし自由振動距離= 270 (cm)
aは1対の筋交いの断面積 = 10 x 10 = 100 (cm2) であるから
k = 99 x 100 / 270 = 36.6 (kg/cm)
固有振動数f は
f=(1/2p) SQRT(k/m) (Hz)
ここでmは耐力壁1個が担当する家屋の質量である。家屋の質量が0.0191 (トン/ガル)、耐力壁の数が19個であるから
m = 0.0191 x 3 / 19 = 0.00302 (トン/ガル) = 3.02 (kg sec2/cm)
ここで質量が耐力壁の対角線方向に作用する力のベクトルはトラス構造のため水平方向の3倍になるとしている。
f=(1/2p) SQRT(k/m) =(1/2p) SQRT(36.6/3.02) = (3.48/2p) = 0.55 (Hz)
通常、建設構造物の固有振動数は0.1 - 10Hzの範囲にあるというのでグリーンウッド家の木造家屋の固有振動数の0.55Hz(周期1.8秒)はその範囲内だ。直下型の岩盤での卓越振動数の 1Hzより低い振動数である。
これを検証するには高性能な加速度計を設置し、柱を手で押して実測すればよいのだが高価だ。業者に測定を頼むにもコストがかかる。手作りの固有振動数の違 う振り子を沢山天井からぶら下げて柱を力いっぱい押してどれが共振するか観察すればいいのではと空想している。
さて浜岡原発の新耐震指針の応答スペクトル図から神縄・国府津ー松田断層を震源とする地震の解放基盤表面の最大加速度477ガルに対応する周期1.8秒の 表層の基準地震動の加速度は下図から500ガルとなるので多分地 盤との共振は避けられるとい うことになる。
追加対策
全ての窓の無い壁にクロスの筋交いをいれツーバーフォー的なコンパネを使っているため、卓越振動数が1Hz地震波のスペクトル図を見ると、最大振幅は 250カインで40カインが長時間持続することがわかっている。(1kine=1cm/sec) 岩盤との共振はしにくいと分かったが、それでも万全を期すには振動のエネルギーを熱に変換する制振機構を追加しなければならない。
①オイルダンパーを使う方法:
加速度エネルギーを熱に変換減衰させるオイルダンパーを使う制振機構。本来、建物の4隅に2セットつけるのが理想だが、美観と構造上不可能である。美観を 配慮すれば母屋に作りつけのガレージ内の1隅に2セットの制振機構を追加する程度であろう。以下に図解する。オイルダンパー1個は家の横応力の10%程 度、すなわち2トンの力でピストンが40cm/sec動くものでよいのではないか。
欠点はガレージの収容能力が減ることである。 それにガレージ内の1隅に2セットでは不十分で対角にある玄関にも2セット設置しなければならない。無骨なフレームをどう機能美にかえるかが腕の生かしど ころであろう。
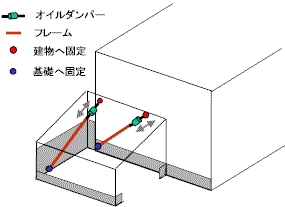
ガレージ内に付加する1隅に2セットの制振機構
②ゴムの粘弾性で減衰させる方法
建物自体をゴムの上に設置する方法は既設の我が家には適用できない。ミサワホームが販売しているエムジオ(MGEO)は 壁の中に亜鉛メッキ鋼板製の幅91cm、高さ273cm、重量約170kgの制震パネルを埋め込み、 パネルの変形を複合テコの原理で増幅して高減衰ゴムで熱に変換し減衰させる方法。
かなりエレガントな方法だが、全ての壁にクロスの筋交いを設置している我が家には適用する隙間がない。この価格は1個20万円程度で4個設置でよいとされ ている。
③ワイヤーブレース工法
平塚市の一級建築施工管理技師、福井義幸さんらが開発した柱と基礎部分をワイヤでたすきがけに結ぶ方法。筋交を金属部材で施工する耐震装置とも言える。こ の方法は1個20万円程度で4個設置でよいとされている。外見は悪いが壁をぶち抜けば強固な耐震構造となるはず。これが最もローコスト工法であろう。
2010年には今の床がぼこぼこになり壁紙も汚れたためこの回収工事に合わせ今の壁のなかにワイヤーブレースをクロスに入れることを検討してみよう。
国土交通省は2005年度の税制改正要望に、住宅やオフィスビルなど各種建築物を耐震改修した場合、持ち主の所得税額や法人税額から工事費用の10%程度 を控除する制度の創設を盛り込んだとのことである。ただ適用工法を国土交通省承認済のものに限定した硬直したシステムになるのではないかと危惧している。
<固定資産税の優遇策利用>
鎌倉市は市の指定する耐震補強をすれば3年間の固定資産税を半額にするというが、工事費がかかるため、10年間くらい半額にしてくれなけば、その気にはな らない。
<家具倒壊対策他>
倒壊しやすい家具は金具等で建物に固定する。(済み)
地震時はまず出入り口のドアを開けて避難口を確保したのち、火を消す。
靴をベッド脇に用意しておく(済み)
ベッドに落下物防備カバーを設置する(未)
家具類の固定
全ての本棚はL型金具で壁かH型金具で天井と固定した。

L型金具 |

H型金具 |
インフラストラクチャー喪失対策
自然災害により自宅、水道、ガス、電力、電話、交通機関、道路などインフラストラクチャが破壊され、かつ地震後1週間、 一切の公的機関による支援が期待できないと想定し てサバイバルするにはいかなる準備が必要か検討した。
この対策は自然災害だけでなく、ハーパーインフレーションなどの人為的災害で食料などが市場に出てこなるリスクにも有効
である。
<サバイバル用品の家屋外の備蓄>
家と自家用車が倒壊または火災で全て失われることを想定して、自宅敷地内の屋外にサバイバル用品を収納した防水箱を半分地中に埋めておくことにする。サバ イバル用品防水収納箱のコンテンツは
●エコノミー症候群防止のための大人2人収容のレジャー用に使った中古のテント、シラーフ、マット 、LPGストーブ、キャンプ用炊事・食器セット一式。
●飲料水として2012年購入の2リッターの水詰ペットボトル12本。
●非常食として、アルファ米、缶詰食品、レトルト食品。2018/10屋外に放置しておいた箱をあけた。中からボト ル入りの飲料水、缶詰の乾パン、アルファ米、缶詰食品、医薬品が出てきた。アルファ米の賞味期限は2014年となっている。賞味期間5年として2009年 に購入したものだろう。ほぼ9年間放置して置いたことになる。乾パンをいれた缶詰3本は少しさびているが、中身は変化なく、おいしくいただいた。アルファ 米はお湯 をいれて10分放置すれば問題なく、たべられる。赤飯の缶詰は携帯固形燃料で沸かしたお湯で温められるように親切にもアルミフォイル製のバットとセットに なっており、そこに梅漬と塩もプラスチック袋に入れてあった。残念ながら中の梅漬けの液体が漏れてアルミと鉄製の缶詰の間で電池回路を構成し、缶詰に穴が 開き、中の赤飯は腐っていた。防水収納箱のなかに虫の卵が沢山生みつけられていたので水洗し、飲料水は戻す。
●情報収集用として太陽電池だけで働く中国製のAM/FMラジオ、兼LEDフラッシライト、兼蛍光灯、兼携帯電話充電器。ただし携帯充電はハンドルをまわ しての発 電のためしんどい。結局すべてゴミとなった。

太陽電池だけで働くAM/FMラジオ
●60Hz、850W非常用ガソリンエンジン発電機と24時間連続出力用ガソリン18リッターと潤滑油360cc。ただしこの中国製品は電気系統の不良で 使えなくなったので処分。

60Hz、850W非常用ガソリンエンジン発電機
●倒壊した家から日用品回収のため、解体用ノコギリなどの工具は一次屋外保管したが、ガレージに戻す。
浮かぶ別荘への備蓄
直下型地震では津波の恐れがないので利用可能性がある。東京湾横浜ベイサイドマリーナに係留してあるROCA号への備蓄は検討の価値あり。20リッターの水タン クには常時清水が備蓄されているし、4名のベッド、トイレ、キッチン、太陽電池稼働ラジオは完備しているので寝具と備蓄食料を追加するだけでよい。ただ現 在のコンピュータ管理のセキュリティーシステムが停止すると、港内にアクセス不可能となることも考えなければならない。マリーナまでの移動法としては自転 車を考える。
浮かぶ別荘は売却してもはやない。
<火災対策>
もし水道が生きていたら類焼対策として庭木や家屋への放水を行えるが、水源を絶たれたらお手上げである。非常水槽は150リットルの散水用雨水貯留タンク しかない。しかしこれも地震で倒壊しているだろう。地下に設置する非常水槽が望ましいがコスト的に未検討である。
復興費対策
家屋総合保険に地震特約を追加する。日本では通常40%カバーとのこと、残りの60%はスエーデンの保険会社でカバーし ていると レッドウィングさんが教えてくれた。
浜岡原発事故対策
その後、古長谷稔著「放射能で首都圏消滅」で浜岡原発の直下10-20kmには 東海地震を引き起こすフィリピンプレートの境界面があり、1981/7/20に原子力安全委員会が決定した古い耐震設計審査指針に 準拠してきめた限界地震の基準地震動S2=600ガルに不安があることを知った。 耐震設計基準は2006年に改訂されたが、既設原発には遡及されない。中電は新基準に準拠して基準地震動Ss=800ガルとして配管系などを補強している 程度であるが原子炉は手付かずである。 2012/4/1 内閣府は南海トラフ地震についての有識者の検討結果を発表しました。マグニチュード9.1を想定すると浜岡の最大津波は21m(現想定14m)震度7とい うことである。周期0.2secでの加速度は1,500ガルとなり制御棒挿入障害が発 生し、原子炉が暴走する可能性は否定できない。万一発生放射能が漏れたとき、風下200kmにある首都圏にある我が家は放射能汚染の可能性ありと知った。 チェルノブイリ事故では炉心から320km以内でヒトが住んではならないとされる15キューリー以上の汚染が発生しているのだ。
もし事故が発生して1週間自宅に閉じこもったあと自宅周辺が放射能で汚染されていることが判明したら自宅を捨てて安全な土地に移住しなければならなくな る。原発の少ない北海道などに安い土地をあらかじめ購入しておけばなお良い。そして中部電力など破産しているだろうからインドのポ バール事故のとき活躍した米国の弁護士のような辣腕弁護士でも雇って、日本政府と原子力委員会の委員相手に損害賠償保証要求をするしかない。自然 災害だから保証できないと反論するだろうが、通産省と原子力委員会が耐震設計審査指針の 改訂を怠った怠慢の罪という論理で戦うための証拠を集めておくのだ。2006年の改訂に携わった委員達は首を洗っておいたほうがいいだろう。
津波対策
今回の東北大地震は史上最高の津波遡上高で40.5m。これまでの津波の「遡上高」の最高値は「明治三陸津波(1896年)」で、岩手県大船渡市の 38.2mであった。我が家はほぼ海抜35mだから少し不足。同じ町内の高台に避難する必要あり。
神奈川県は東北大地震後、南関東地震時の津波高を従来の5mから14.4mに変更した。遡上高の想定はこれからという。
火災対策
SECOM警備保障会社の火災報知器システムで監視。調理台上に設置する火災報知器と廊下に設置する煙検知器からなる。
他に寝室に東レ製ナイロン使用のスモークフッドを常備。

スモークフッド
November 11, 2004
Rev. February 20, 2019