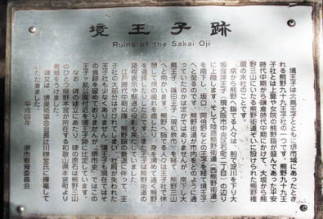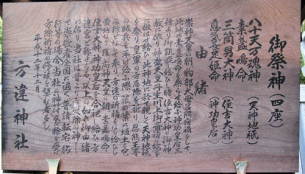|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| 境王子~方違神社~反正天皇陵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
<境王子> 境王子は、大阪の少年鑑別所や刑務所との間を西に右折すると住宅街の一角にある。 小さな地蔵様と境王子を示す石碑がある。  石碑は本宮町が寄贈したそうである。 境王子または堺王子は後に熊野神社となり、現在堺市戎之町東の菅原神社に合祀されている。 ここも住宅街にひっそりとあるので、うっかりすると見落としてしまう。 ポイントは刑務所である。 境王子を示すものは碑だけで、かわいいお地蔵さんが片隅にある。 こぢんまりした公園風になっているが、センスのない犬のウンチ除け看板があり興ざめである。 熊野が世界遺産登録された後、心配なのはこのあたりのセンスなのである。 周辺は住宅街で、道もそれほど広くなく、快適に歩けた。人通りはほとんどなかった。 この道もかなり複雑でわかりにくく、地図と首っ引きであった。 ただし、古道は南に延びているので、お日様を追いかけて進んだ。 所々にお地蔵様がある。 またこの辺の、下水道のマンホール蓋はなかなか粋である。
<方違神社> 熊野古道は、境王子から南に歩き住宅街を抜けるとJR堺市駅へと続く広い道に突き当たる。 その道に沿って右折すると、方違神社がある。この神社の名前を、はじめは「かたちがい」と読んでいた。 しかし本来は「ほうちがい」というらしい。 由来は、パンフレットでは、祭神は、八十天萬魂神、神速進能男神、三筒男神、息長足日命で、崇神天皇のころ、国内に疫病流行して、同床共殿に祀られていた天照大神を笠縫邑、倭大国魂神と大物主神を祀ったとかかれている。 この時、物部大母呂隅足尼(物部氏八世の孫)を遣わして、この地に素盞嗚尊を祀ったともあった。 また神功皇后の帰還時、住吉の大神の御託宣によって神武天皇が丹生川上神をお祀りの故事にならって、此地において天神地祇を祭り、皇軍の方忌除を祈り、忍熊王等の賊兵を平げたと伝わる。 そのあたりはとても覚えられない。漢字もまず書けないだろう。 なぜ、三国ヶ丘などと呼ぶのが不思議であったが、摂津国住吉郡、河内国丹治比郡、和泉国大鳥郡の境界であり方位がないことからだという。 おりからの初詣と、今年家を建てたり改築したりする人でごった返していた。  社務所の方が3名いて、 「**様はどういうことでお参りですか?」 「はい、トイレを水洗に改築するのでお払いをしてもらいに来ました」 「今のご住所とトイレの方角を教えてください」 などといろいろ聞いてお払い用の用紙に書き込んでいた。 最後に、プラスチックの番号札を渡しながら、 「はい、それではトイレの増改築にさわりがなく家内安全をお祈りいたしますので、この番号札の番号が呼ばれたら、お入りください」 といって、少なくない金額を請求していた。 朱印を書いてもらうのに、結構時間がかかり後ろに並ぶ方に気の毒であった。 私は家を新築するときも、こうしたお払いは地鎮祭の時だけであった。 ただし、南天を鬼門(北東)のところに植えておけということで植えた。それが今はびっくりするくらいに増えてしまっている。 この方位というのは、日本だけではなく世界各地に形をかえてある。それらは、ほとんどが太陽や月、そして季節に微妙に絡んでいる。日本の特殊なところは、それらが神道や仏教など、宗教の枠がないことである。 神道と仏教そして陰陽道などが混在している。いずれにしろ、明治以前は神と仏が同居していたのだから、日本人のフレキシブルさの表れで、悪くいえばけじめがないということか。 でもそのおかげで、権力闘争や権力による特定宗教の禁止はあったが、それ以外での宗教戦争的なものは少なく、ある程度の平和を維持してきたともいえる。この狭い国に、過激な宗教があったら大変なことになる。  道は、南の方角に行く。道を間違えないように、パンフレットを見ながら歩いた。 私のような方向音痴こそ方違神社で拝んでもらったらよかったのかなと思った。 ここ堺は、「てくてくろーど」としてハイキングコースを指定している。 コースの標識は決してわかりやすいとはいえないが、歩くものにとっては目安となりありがたい。
<反正天皇陵>  熊野古道は、このあたりから古墳やら天皇陵が続く。 実はここで道を間違えて、堺東の駅まで行ってしまった。 いったん戻ってもう一度道を取り直した。 じつは、歴代天皇のそれぞれについてはほとんど知らない。 それで少しこの反正天皇について調べた。 この天皇は、仁徳天皇の第三皇子で履中天皇の同母弟で、履中天皇が即位前に住吉仲皇子と皇位を争っていた際、兄のために住吉仲皇子を討った功績が認められ、履中天皇の実子をさしおいて皇太子となったという。 即位後には歴史に業績をとどめることはないが、五穀豊穣で太平の世だったことが伝わっている。  でもこれはすばらしいことである。 天下太平をきちんと守るということは大変なことなのだから。 やはりここも立ち入り禁止で、当然といえば当然だけど、中にある宝物など公開して欲しいという気がする。 でもやっぱりお墓だから仕方ないかな。 しかしエジプトなどはいろんな墓を見つけて、歴史を解き明かしている。 ひょっとして、歴史が覆る記録が出てくるかも。 仁徳天皇陵では秀吉が狩りをしたという。この反正天皇陵も、木が生い茂り森をなしている。 ウサギや狸などがいれば、ここは天国だろう。 反正天皇陵を過ぎてすぐに、三国ヶ丘高校がある。 さらに行くと、王子や方違神社の祭礼などにその水を使われたという、閼伽井跡がある。 しかし門が閉まっており、中に入れなかった。 こうして大阪の街中を歩いていると、田舎よりむしろこちらの町並みの方が懐かしい気がする。 昔の横町の感じがよく残っている気がする。 田舎の古い家屋は別にして、年代的に私の記憶の中の町並みはこのような風景なのである。 道はさらに南に続くが、突如として竹内街道の起点を示す石標があった。 ここから奈良方面へ向かうのである。
▲ページトップに戻る
|
||||||||||||||||||||||||||||||||