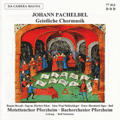
Da Camera Magna 77 011
Geistliche Chormusik/Pachelbel, Johann//Motettenchor Pforzheim, Bachorchester Pforzheim
前(期)バロックの人、ヨハン・パッヘルベルの合唱カンタータ2曲とモテット(Motette)6曲を収録した宗教合唱曲集。賛美歌(Psalm)No.93と99を含み、短いもので3分、長いものは13分を越える簡素で心地良いメロディと演奏。内容はハレル~ヤくらいしかわからない……というか、言葉がわからないことの幸せというべきか。雰囲気だけを受容するには格好の素材にして清浄感に溢れたステレオタイプ。原則4声だが、カンタータ「Christ lag in Todesbanden(キリストは死の床に横たわる(?曖昧))」の弦楽器とオルガンを伴奏にしたバス独唱が痛切かつ慰藉に満ちて特に素晴らしい。後継の偉人バッハの崇高美に比べると親しみ易いメロディと和声の調和、明るく肯定的な調性と、根底に流れるどうしようもない悲哀の対比バランスが絶妙にして真似ができない境地といえよう。
指揮とオルガンはロルフ・シュヴァイツァー(Rolf Schweizer)。1987年のディジタル録音。廉価盤だが音質は非常に良い。
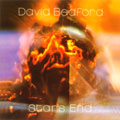
Virgin CDV2020
Star's End/Bedford, David
既に70代になるベドフォードの1st交響曲と思われる。王立音楽院作曲出のエリートで後にイタリアの現音作家ルイジ・ノーノ(Luigi Nono)に師事するが、60年代末期、突如エヤーズ(Kevin Ayers)の『Joy of a toy』で鍵盤弾きとして世俗界に出現、そのままホールワールド(The Whole World)の一員として、70年代前期を過ごす。エヤーズの初期作で鍵盤以外にアレンジ、オーケストレイションの才を存分に発揮する。そのホールワールドにおける10代のベース担当、オールドフィールド(Mike Oldfield)の出世作『Tublar Bells』他でのアレンジメントが功を奏したのか、ヴァージンから初作交響曲としてリリースされたのが本作。以降数作をリリースするが、ヴァージンの変節と共に発表の場を失い、本来の現音畑に退却の後、大成する。映像を眺める限り、かなりすっとぼけた変人のように見えるが、楽譜に代わるグラフィック表記の開発等教育的な成果を含め、極めて学求的な人のようです。
46分ほどの、なかなか興味深く現代的な全1曲。ミニマルでノイジーというあたりはこの時代のお約束だろうが、けっこう劇的な盛り上りや抒情的フレーズの断片的挿入等も計られており、前衛に突っ走っちゃいましたと云うほどではないあたりはイングリッシュ・プラグマティズム。タイトルはその名の通り超新星爆発を指すと思われる。演奏はRPO。共演者としてギター・ベースでオールドフィールド、打楽器でクリス・カトラー(Chris Cutler)の名がクレジットされており、両者ともにそれなりに目立っている。
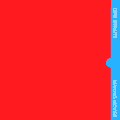
Vertigo
800 050-2
Making movies/Dire Straits
毎度お馴染み、饒舌ながらもストイック、ノリノリながらもおっさん。1980年リリース、アメリカ移住後の3作目。ちなみに弟は前作を最後に脱退しているのでこの時点はトリオ編成。次作に通ずるダイナミックな展開と、タイトル通り映画のワンシーンを髣髴とさせる抒情的ながらも叙景的な要素がふんだんに盛り込まれた佳作にして円熟の極み。ゲストの鍵盤(次作以降は常駐)が多用され始めたのもここから。弟の跡を埋めるというよりはノップラーのギターと対に成った位置付けで、簡素でシャープ、さり気ない才気をちりばめた如何にも英国的なギター・バンドから、よりゴージャスで華やかさを増し、8分越えの長曲やプログ紛いの複雑な展開に拘った独特の抒情演歌を繰り広げる。売りであるノップラーのギターのトーンも枯れた味わいから骨太でアグレッシブなトーンに変化しているが、彼等のアイデンティティと云ってもよい軽妙洒脱さは相変わらずで、マンネリながらも安心できる内容には違いない。
所有盤は96年のリマスター。分解能が高く表情豊かでありながらもクリアで言うことなし。
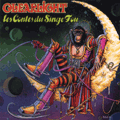
Clearlight Music
C8M-003
Les contes du singe fou/Clearlight
クリアライト三作目。今作以降は英Virginからのリリースが途絶え、地元フランスのマイナー・レーベルへ移籍。所有盤は教祖になって以降、宗教カルトに寛容なアメリカ移住後の自前レーベルからのリマスター・リリース。一応、GongやZao人脈を生かしたバンド形態による全1曲の組曲と思われる。かなり達者なリズム隊入り、インプロとアレンジが相互に侵食し合い、前半英詩、後半仏詩の歌入りで極めて抒情的、聞き易いが、前作までの流麗あるいはコケティッシュなオリジナリティは失われ、初期ジェネシスの亜流みたいなことを延々と繰り広げている。ほぼ、全編を通じて流れる首領ヴルドー(Cyrille Verdeaux)のピアノとロックウッド(Didier Lockwood)のヴァイオリンの絡みが肝なのだろうが、ミニマル色や民俗色は排除され、ロック色が前面に出て、売れなかったであろう前2作からの反省に立った英米風のシンフォニックなメリハリ付けと、「Supper's ready」あたりからの援用が本来持っていたはずの興趣を著しく削いでいる。
タイトルは『いかれた猿の御伽噺』といった意。“いかれた猿”とはそのまま人類の暗喩だろう。歌詞から類推するには、微妙な新興宗教色が加味され初め、内容的理解への意欲と努力を悉く阻害する。
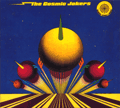
Spalax 14293
Cosmic Jokers/Cosmic Jokers
どろどろ宇宙サイケ第1弾。旧LP片面ずつを使い切った「銀河系冗談」と「宇宙悦び」全2曲という世俗を超越した荒唐無稽な潔さ。Ohrレーベルのチーフ・エンジニア:ディーター・ディエルクス(Dieter Dierks)の下、ヴァレンシュタイン(Wallenstein)のユルゲン・ドラーゼ(Jürgen Dollase)、アシュラのグトシンク(Manuel Göttsching)+グロスコプフ(Harald Großkopf)、及びクラウス・シュルツェ(Klaus Schulze)によって構成される楽団名は「宇宙バカ」乃至は「宇宙アホ」。社長や社長秘書を製作者に、レーベルの総力を挙げたオチャラケ。オリジナルはOhrから4chステレオによるリリース。所有盤はフランスSpalaxの94年CD。
前半はアシュラ風のブルーズ調、後半は鍵盤中心のシュルツェ調とでも云えばよいか。力関係は不詳だが、崩れすぎない抒情風味はドラーゼの為せる業か。ともに歌なし(変調ヴォイスの朗読はあり)の即興。生に近い一発録りで、次作以降とは異なりあまり手は加えていないと思われる。シュルツェの鍵盤を主役にとクレジットにはあるが、その他もバランスよく演じている。抑揚とテーマらしきものもあり、これまた生音に近いリズムが入るので、薬物系どろどろサイケのわりには聴き易い方向性を狙っているように思える。
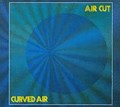
Repertoire
REP 5061
Air Cut/Curved Air
過渡期の特異点あるいは仇花として異様に世評が高く、代表作扱いされることも多い、カーヴド・エアの4作目。楽団名は“つむじ風”の意で、アメリカのミニマル現音作家テリー・ライリー(Terry Riley)の著名作『A Rainbow in Curved Air』に感銘を受けた屋台骨にしてギター・鍵盤奏者フランシス・モンクマンの命名とされる。そのモンクマン(Francis Monkman)と看板ヴァイオリン弾きのウェイ(Darryl Way)を失いながらも、もう一方の雄じゃなくてどう見ても場末のスナックのママ、ソーニャ・クリスティーナ(Sonja Kristina)が中心になってメンバーを掻き集め、再建にこぎつけたのが本作にあたる。もっとも次作ライブではあっさりモンクマンとウェイが復帰しており、出入りが激しく方向性が定まらない。
60年代末期の薬物ヒッピー・アシッド・サイケ・フォークと前期バロック・クラシック趣味とVCS3びよんびよんのごちゃ混ぜを大人の女の魅力で何とかまとめ上げていた前作までに比して、先鋭感は薄れたがよく練りこまれ、丁寧にアレンジされポップ領域に一歩近づいた完成度の高い楽曲は聴き易い。フォーク向きのクリスティーナが無理矢理ロックを歌っていても、曲の出来が良いので決して悪く聞こえない。新人デビューのジョブソン(Eddie Jobson)は、結局クラシック・ヴァイオリンに範を見て、そこから抜け出せなかったウェイよりははるかに柔軟に追従するが、所詮は10代の若さと軽さ、底の浅さが垣間見えてしまい面白味は薄い。テクニックと後の経歴はそうそうたるモノだが、今ひとつ中途半端でパッとしない器用貧乏さは持って生まれたものか。
個人的には、後に中期キャラヴァンに移籍する、歌って曲も作れ、笛まで吹けるベース奏者ウェッジウッド(Mike Wedgewood)と、無名だが有能でカシャカシャしたシャープなリフでぐいぐい押してくるギターのグレゴリー(Kirby Gregory)の貢献を高く評価する。権利関係の混迷で長らくCD化がされていない迷盤だったが、近年ようやく再発された。所有CDは2006年の再発リマスター。

Tone Casualties
tccd 9945
La Luna/Czukay, Holger
極めてマニアックな様相では一世を風靡したともいえるドイツのカン(CAN)のベース、ホルン奏者にして音響作家である、ホルガー・チューカイの近作ソロ・アルバム。96年5月17日に行われたチューカイのスタジオでの電子夜儀式の模様を納めた一発録り、47分に及ぶ全1曲。全編、ミニマルなリズムとアンビエントな月の遷移と位相。クールで蒼白いまでのひんやりとした触感。寄せ付けない怜悧と浸りたい温もり。うねる波の如き音響に、部分的にu-sheなる女声による詩の朗読が乗る。
ラ・ルナ
宇宙の母たる月の女神
我らに感覚と知恵を与えし生と死の女王
我ら夜を照らすおまえの光を必要とす
偉大な女神の鏡
あらゆる創造の周期において
時を産むもの
成長は破滅を衰退させる
宇宙の母
それはわたしがかつて目にしたものとは異なって見える
異質なる月
ラ・ルナ
月の女神
得意中の得意領域、あるいは特異中の特異領域での作品ということだが、聴いている限りにおいてはいつものひょうきんなユーモア感は皆無でシリアス。安直なテーマや調性も特にないので好悪は人それぞれだろう。
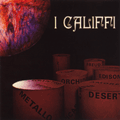
Fonit Cetra
CDLP 420
Fiore di metallo/Califfi, I
フィレンツェ出自の70年代イタリアのプログ・ポップ、カリッフィの唯一作。60年代のビートバンドを核とした発展系という意味ではよくあるパターンだが、けっこう上手いし、なかなかツボを心得たSEや教会オルガン独奏などといった異物挿入っぷりが新鮮で興趣に富む。基本的には綺麗で親しみ易いメロディに、緻密で的確なリズム、華やかさは感じられないが、堅実で丁寧に作り込まれた品行方正な70年代の良心が懐かしい。
ベースのフランコ・ボルドリーニ(Franco Boldrini)とドラムの弟? を軸とするオーソドックスな4人編成で、ドラムが主唱を兼ねているようなので、暑苦しくないさっぱり系の抒情歌が北イタリア風の洗練の下に展開される。ドコドコ・ボカボカした太鼓はこの時代特有のイタリアの音。プログの仮面は被ってみたものの、根っこのハードなビート・サイケは隠し切れなかった。なんだろうね? 偶然かもしれないが、意図したことなら鮮烈な、ちょっと外したようなアナログ・シンセのメロディ展開が面白い。タイトルは「偽ものの花、金属の花」という曲からとられたと思われる『金属の花』、いや、『ブリキの花』と意訳すべきか。カリッフィはイスラムの首領を表すカリフの複数形だが、よくある偽悪趣味風に“悪賢い男・女たらし”といった意味と思われる。尚、2000年代になって復活ライブを行っている模様。
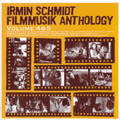
CDSPOON52/53
Filmmusik anthology Volume 4 & 5/Schmidt, Irmin
元CANの鍵盤奏者にして現音作家シュミット老の近作ソロ。94年にリリースされた『78-93』選集がCD3枚組だったので、その続きの『4,5集』という意図なのだろうと思われる2CD。2時間越えの全33曲はヴィム・ヴェンダース、シュテファン・ヴァグナー等、概ねドイツ人監督の商業映画実作のサウンド・トラック。いわゆる日本では商業公開されないタイプの映画ばかりのようで、実際に映画館でお目に掛かることはないのだろう。
サウンド・トラックなので軽やかなリズムが導入されたものから無調に近いものまで、ミニマルから懐古調まで曲想は千差万別ではあるが、先鋭でありつつも不思議に馴染んだクールなトーンは共通している。極めて叙景的でありながらも映像(あるいは作業)を邪魔しないアンビエントな方向性と、音楽単独として聴ける趣向とセンスが高いレベルで融合した正真正銘のプロの作品。妙な力みや、あざといくどさの欠片もない安心できる気持の良さは出色もの。

Virgin Records
CDVE11
Plight & Premonition/Sylvian, David + Holger Czukay
元ジャパンのデヴィッド・シルヴィアンと元カンのホルガー・チューカイによる幽玄コラボ第1作『誓約と予感』。86-87年の録音。前半「誓約(副題:渦巻状の冬幽霊)18:30」、後半「予感(副題:空っぽの巨大鋼鉄船)16:21」の全2曲によるひたすら耽美なノンビート・ロマンティック・アンビエント。特に主題らしきものはないが、無調風の退屈な展開と忍耐を要する音響の連なりは極力避けられており、極めて夢見心地の気持良さと、ときおり貫入する鮮烈な刹那が類稀なセンスで構築された浮遊感溢れる音のタペストリー。チューカイ得意の音響コラージュを細密にミックスダウンした前半と、より即興に近い一発録りといわれる後半ともに、視覚を喚起する疑似体験的ともいえる音響となって静謐に忍び寄り、聞きたくない音響が溢れる日常を封殺する。
森に横たわる朽ちた木と絡まるヴィニルという湿った暗鬱なスリーブデザインはYuka Fujiiなるシルヴィアン作系列でよく見る名前。本作の第2弾が以前1488で紹介した『Flux + Mutability』になる。
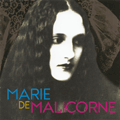
le roseau
ROS105
Marie de Malicorne/Yacoub, Marie
タイトルは『マリコルヌのマリー』。マリコルヌは70年代~90年代にかけて存在した西フランス・ブルターニュのモダン・電化トラッド楽団。その主唱の一人がマリー・ヤクー。現在もソロで活躍する楽団長ガブリエル・ヤクーの実妹。本作はマリー・ヤクーが歌う75年~2005年の30年間に渡る作品のリミックス、再録、再編集、未発表作、新録計14曲のコンピレイション。すべてリマスターされ、恐ろしいほどのディテール。+歌詞のpdfファイル付。
新録曲は声が掠れて渋みが増しているが、頑迷なまでの土俗と凍りつくような透明感が同居して、クールでありながらも柔らかさを失わないマリーの歌とコーラスが存分に聞ける。ケルト末裔悲哀純トラッドから現代室内楽風、あるいはシャンソン、ポップまでとジャンルは幅広い。基本的に派手さの欠片もないが、マリコルヌの斬新なアレンジと手堅くソツのない演奏も唸らせるものがある。もちろん、手回し風琴を操るマリーちゃんも最高だぜ。
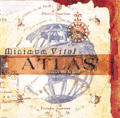
Musea
FGBG 4533.AR
Atlas(vers un état de Joie)/Minimum Vital
ライブを除くと6年ぶりにリリースされたスタジオ盤6作目。前作でゲストだったコルシカ人男性歌手が正式構成員となり、男女主唱歌手を擁する6人組という大所帯と化した。元々あまり派手ではない、ソーニャちゃんのくったりした声が若干背後に埋没しているのは個人的に残念。非常に力の入った意欲作だが、それでいて緻密なディテール表現も失わない完成度の高さは見事。前作の煌びやかな部分をいっそう発展させた、ゴージャスなまでの華麗さと気品溢れる情緒、分厚いアレンジと、それを支える気持ち良いほど完璧でテクニカルな変拍子とコーラス・ワークが聞きどころか。ドラム交代のせいか奇数拍子は明らかに減っている。概ね明るい曲調とダイナミックで凝った展開、濃密な情念と湿り気は減退して爽やかな軽やかさ、古楽趣味は相変わらずだがフランス南西部のケルト末裔少数民族臭漂うトラッド色も薄れる方向にある。
タイトル『アトラス』はギリシャ神話の男神。大地が球であることが一般に認識された大航海時代、メルカトルが作った世界地図帳の扉に用いられ、後には地図の代名詞、あるいは商品名としても頻繁に耳にすることになる。副題は「歓喜(の国)へ向けて(の航海)」の意。
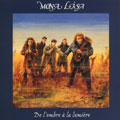
Musea
FGBG 4251.AR
De l'ombre à la lumière/Mona Lisa
90年代ネオ・プログ・ブームに便乗したドミニク・ル・グネ(Dominique le Guennec)による新生モナ・リザの初作にして恐らくスタジオ録音唯一作。ル・グネ以外の構成員は70年代モナ・リザとは関係がなく、ギター・鍵盤・ドラムは80年代末~90年代初期のフォロワー:Versailles(ヴェルサイユ)のメンバー。
メロトロンやハモンド・オルガンといったヴィンテージ鍵盤を多用した、懐古的で回顧的なまでの曲調や演劇趣味。リズムやアレンジ、録音、音色はもちろん90年代風でもあるのだが、醸し出される雰囲気や目くるめく破天荒な展開は、いやぁ、もろ70年代のモナ・リザそのまんま。場末のサーカスの舞台裏のような、微妙な荒っぽさと安っぽさが漂い、テクニックもお世辞にも上手いとはいい難いあたりも見事に継承されている。さすがにこれを今何故? と存在意義に疑義が生じてしまう部分も無きにしも非ずだが、時代遅れといわれても決してなくなることのない演歌として捉えるべきか。タイトルは『影から光へ』
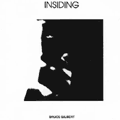
Mute Records
CDSTUMM71
Insiding/Gilbert, Bruce
全2曲。「Bloodlines(血統)」はアシュレイ・ペイジ(Ashley Page)による1990年初演のバレーのための音楽、「Insiding」は同製作者1989年のTVフィルム『Savage Water(荒ぶる水)』のための音楽の抜粋とされている。ブルース・ギルバートは1946年生まれ、パンク/ポストパンク/オルタナのワイア(Wire)の、クールでシニカルなギター奏者による個人名義4作目。第1期ワイアの後のDomeに連なる、第2期ワイア末期・以後のミニマル・アンビエント・アヴァンガルド。冷え冷えとした虚無と感情を削ぎ落としたインダストリアルが、かなり危うい地点で成り立っている絶望的な未来への祝辞。
個人的には1期よりもエレクトロ風の趣向が強い2期Wireに惹かれる性質なので、そのWireの中でも最もぶっ飛んでいるギルバートの諸作は気持ち良いほどツボに嵌る。延々と反復し、唐突に消えるリズム。あらゆる意味性を剥奪され、突き放されて路傍の排水溝に転がっている死蝋化した半透明な死体のような調性と構成。凍てついた凍土を掘り返しているような徒労感。セカイという強制収容所に囚われた知性の末路。

Lowlands Low 001
C.O.D.Performance/Présent
“C.O.D.”というのは“Chemical Oxygen Demand”(化学的酸素要求量)なのか“Cash on delivery”(笑)なのか、どこにも何一つ解説がないので不詳であるが、プレザン過渡期の繋ぎ作。親分の性格の悪さ(推定)が仇となり当初の楽団形態はあっさりと破綻し、頭領ロジェ・トリゴー(Roger Trigaux)と息子・レジナール・トリゴー(Reginald Trigaux)による世襲継承の儀式的な私小説アルバムとしてのプレザン。かなり即興的な一発録りと思われ、適度に鍵盤等も用いられているようだが、基本は二人して足でバスドラを入れながらギターを弾いている模様。ロック・マインドに拘らずバルトークの再来、あるいは超越を目指すUZに比して、プレザンは思い切りの悪さ、あるいはキワモノ臭が漂い、あくまでこけおどし風ダイナミズムを失わないことで安定した聞き易さを担保する。
暗鬱な西洋風地獄絵図の細密ジャケ絵は息子トリゴーの作。
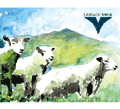
Mute Records
LCDSTUMM 276
Volk/Laibach
今となっては、85年スタートの老舗大御所。タイトルはドイツ語で『国民』の意。スロヴェニアのライバッハと同郷のSilenceなる2人ユニットの共作。そのサイレンスのボリス・ベンコ(Boris Benko)という人が歌のお姉さんなのだろう。全32ページ・ハードカバーの水彩画とクレジットが記載された特種ジャケット。ラストは確かな視点で選り抜かれた辟易するほど極めて「思い上がった」著名“学者”や誰もが知っている“政治家”の言辞が論評抜きでびっしりと2ページ渡って記載され、世界の構造理解の一助となろう。
ドイツ・アメリカ・イギリス・ロシア・フランス・イタリア・スペイン・イスラエル・トルコ・中国・日本・スロヴェニア・ヴァチカンにライバッハが主宰する仮想国家NSKを含め全14曲の解題+改竄されたNational Anthems、すなわち国歌集となっている。歌詞を含め悪意と皮肉、絶望を込めて徹底的に改竄されたものから「君が代」のように、そのまま+英訳で歌われるものまで、ヒエラルキーは強く感じられ、原型を留めないものからほぼオリジナルまでいろいろ。インダストリアルなビート感は薄くはないが、キッチュとコケオドシは控えめで、やはり歌に重点が置かれた構成といってよいだろう。ちなみに歌詞は“敢えて”表記されていないと考えるべきだろう。
ステレオタイプな批評に陥ることなく、自らのアイデンティティを皮肉ってすらいるコンセプトが興味深いうえ、楽曲(アレンジ)の出来も大変素晴らしい。特に冒頭、哀感漂うドイツから歓喜と黎明のロシアまでの流れはぞっとするほど秀逸にして、心底圧倒される。ドイツは1797年ハイドン作の「Das Lied der Deutschen」で1922年ワイマール時代に制定されたもの、ロシア国歌は紆余曲折を経てソ連時代のものが復活。同作者によって新たに歌詞が振り直されたもの。コーラス部のロシア語メロ最高! それに比して、以降のフランス、イタリア、スペインあたりの穏やかさは何なのだろうね?