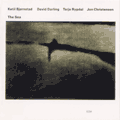
ECM 1545
The Sea/Bjørnstad, Ketil/David Darling/Terje Rypdal/Jon Christensen
ノルウェーのピアノ奏者、ケティル・ビョルンスタのリーダーアルバム『海』第一集。ピアノ、チェロ、エレキ・ギター、ドラムによるカルテット。後に同一メンバーによる第二集が出ている。フランツ・カフカの『人魚の沈黙』の一節、「ところで人魚たちは、歌よりもはるかに強力な武器をもっていた。つまり、沈黙である」をモチーフにした連作。
ECMらしく恐ろしくクリアな録音。全曲インスト。ポリリズムの上を走るピアノ、チェロ、ギターの静謐にして狂おしいまでの官能と艶やかなまでの悲劇。12の表情を持つ潮は12の楽章に分かれた類稀な純粋美によって描かれる。正直言ってこれのどこがジャズなのよ? と云いたくなるほどジャンルは完全に超越して、言葉では表し難い。零れ落ちる結晶のような音符は水晶よりも透明で痛々しいぐらい清冽だ。ベタ凪から嵐まで、流れる潮からたゆとう溜りまで、海の事象を音のみで表現した感性には深く共感できるものがある。

OEHMS OC 351
Musik aus Russland-Das grosse Morgen- und Abendlob/Rachmaninov, Sergei //Chor des Bayerischen Rundfunks
セルゲイ・ラフマニノフ(Sergei Rachmaninov:1873-1943)はロシアの没落貴族出、叙情的ロマン派作曲家兼ピアノ奏者。革命直前にアメリカに移住、食うために卓越したピアノ奏者の腕を生かさざるを得ず、移住後の作曲数は少ない。西欧合理主義のチャイコフスキーの後継者でありながらも、ロシア特有の民族主義的な、あるいは“母なるロシア”への憧憬に満ち溢れた趣向を隠せない典型的なロシア人。
62分強にまとめられた本作は、ロシア革命直前の1915年に書かれたロシア正教会晩祷のための混声四部合唱曲で、二作ある宗教曲の一つ。作曲家としての絶頂期の作品であり、一般的にも評価の高い名作とされている。『晩祷』は、正教会の奉神礼祝文のうち、徹夜祷を構成する時課経の3つの部分(晩課・早課・第一時課)に曲付けされ、全15曲で構成されている。うち10曲は奉神礼聖歌から歌詞が取られ、残りがラフマニノフ・オリジナルの模様。徹夜祷というのは徹夜で行われるお祈り宗教儀式なのだろうが、もちろん実際には見たことも聞いたこともない。と思ってニコライ堂のWebを見てみたら徹夜祷というのもやっているのね。若い頃、毎日のように前を通って建物を眺めていたが、雑然とした周囲に比べちょっと空気の色が違うのだよなぁ。その差異がそのまま現出したような、ひっそりと冷たく、色味が薄れ漂白されたような儚さがしっとりと染み渡る。
演者は南ドイツのバイエルン放送合唱団で、2004年の新しい録音である。OEHMSはドイツBMG傘下の廉価盤レーベル。新譜でもおおむね500円以下という充実した内容価格比を誇る。
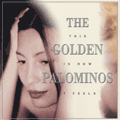
Restless
7 72735-2
This is how it feels/The Golden Palominos
ニューヨーク・アヴァン・ガルドとしてスタートしたGPの6作目。2作目以降はポップ色が増してダンス・ミュージックとしても十分楽しめる内容になっている。当作は自作自演歌手ローリ・カーソン(Lori Carson)が参加した初作で、フィアー(Anton Fier:ドラム)、ラズウェル(Bill Laswell:ベース)のトリオ作が全12曲中9曲を占める。変化に富んだ次作『Pure』のようなカラフルさはまだなく、ひたすら重低音の効いた重いリズムの上をカーソンの舌足らずで気だるく、少女っぽいが必要以上にエロい声、あるいは歌が流れる。歌詞の中身も眉を顰めるほどHだが、息遣いから喘ぎ声まで、ぬっちゃりと湿り気を帯びたカーソンの御声は、必要以上にクールで色気の欠片もない無機的なリズムとの対比で恐ろしく際立つというか、狙ってるのがモロ聞こえ。無垢と官能が同居したまま、ぬめるような漆黒にとろとろと蕩けだしていくような危うさが心地良い。
残り3曲は声質の似ているリンダ・カヴァナー(Lynda Kavanagh)が歌うが、ジャクソン・ブラウン(Jackson Browne)の「These days」のカバーは曲調がも爽やか過ぎて、良い意味で一筋の光明のように浮いている。ジャケ写真はうら若き当時のカーソン。

Reprise 2138-2
Penguin/Fleetwood Mac
第二期(つまりボブ・ウェルチがソングライターだった時代)の三作目。LPも持っているはずだが、最初に聞いたのは高校生の頃だったか。物憂げでかったるい晴れた午後の記憶。日影の地べたに寝転んで見上げた空に雲はなかった。『枯木』の次作にしてカーワン(Daniel Kirwan)遁走の結果、ウェルチと女マクヴィーに任すにゃ荷が重いと思ったのか思わなかったのか、ミック親分が連れてきた新加入が数人いるが、意味があったとは思えない。まだ若いウェルチ+マクヴィーの刺激剤として計ったなら、なかなか上司としては有能だろう。
カーワン不在で英国フォーク色は壊滅。明快なオリジナリティを確立しつつ成長著しいウェルチ+マクヴィーでポップ・ロック色が濃厚になるも、ブルーズ畑の新加入が浮きまくった抵抗勢力という扱い。おかげで誰が書いた曲かで、ジャンルが異なるという奇天烈なことをやっております。今はMac=三期みたいに捉えられてしまうから日の当たらない時期ではあるが、どっちつかずで中途半端であり、変化に富んで斬新ともいう。曲の出来はマクヴィー作の三作が秀逸。このあたりから、瑞々しいハスキーヴォイスを披露するマクヴィーの才気が一気に開花する。こういうとなんだろうが……、Macってクリスティン・マクヴィーなんだろうと今も昔も思っている。

WSM/Rhino
8122-76171-2
Chicago Transit Authority/Chicago Transit Authority
シカゴの1st。楽団名は実在の運輸団体(シカゴ市交通局といった意味?)からとられたため、アルバムリリース後にクレームがついて『シカゴ』と改名を余儀なくされた。デビュー盤でありながら当時はダブルLPでのリリース。以後、3rdまでは二枚組、4thに至っては4枚組、シングルでリリースされるのは5作目が初めてという、買う側にとっては困ったちゃんでもあった。(4thは知らんが、現在のCDは全て1枚) 3人のブラス・セクションを加えた7人組という大所帯でスタート。当時は前衛的なジャズ・ロックという範疇で評価されていた記憶があるが、今聴き直すと、若干サイケ+ヒッピー風味の入ったストレートでパワフルなロックという趣で、シンプルでかつ、とても躍動感に溢れている。古い音源だがライノ・リマスターで音質は非常に良い。
当時のアメリカではベトナム反戦、仏独でも学生運動が花盛り、日本では70年安保という時節を反映して極めて反体制色の強い内容が込められているが、その当事者たちがいまやすっかり体制の権化にして僕(しもべ)と化しているという意味において、内容的には色褪せたどころか、純粋にしらけさせるものがある。煙に巻くような当人達の言い訳も見苦しい。若気の至りといえばその通りだが、個人的には詐欺に近いと考える(笑)。

disconforme sl
DISC 1962 CD
Edge of time/Winstone, Norma
60年代中期デビューのイギリス人ジャズ歌手、ノーマ・ウィンストンの遅いデビュー作。プログレ・ジャズというらしいが、ジャンルとしてはよくわからない領域ではある。イギリスの場合、ジャズとロックの境界は極めて不分明だが、ニュークリアス(NUCLEUS)やニール・アドレイ(Neil Ardley)あたりと接点があったようだ。必ずしも過去の人というわけではなく、ECMからAZIMUTHという楽団形態でリリースがあるし、現在もコンテンポラリィ・ジャズを演じているようだ。
ウィンストンのヴォーカルは歌を歌うというよりはアンサンブルの中の一つの楽器としてのヴォイスの可能性を追求したという趣。歌詞を歌う以外にもスキャットや声楽的なアプローチが目立ち、ときにはゆるりと妖しく、ときには前衛的かつアグレッシブに存在感をアピールする。バックを固めるのは夫君ジョン・テイラー(John Taylor)をはじめとする英ジャズ界の重鎮の方たち。渋いけれどエアコンの効いた湿度の低い環境に最適の音源。99年のディジタル・リマスター。

Akarma AK 220
Pieces of me/Hoyle, Linda
6面紙ジャケット仕様の再発リマスター。リンダ・ホイルはアフィニティ(Affinity)のボーカルのお姉さん。グループ消滅?後、ニュークリアス(Nucleus)をバックに従えて録音したおそらく唯一のソロ・アルバム。ギター:クリス・スペディング(Chris Spedding)、鍵盤:カール・ジェンキンズ(Karl Jenkins)、ベース:ジェフ・クライン(Jeff Clyne)、ドラム:ジョン・マーシャル(John Marshall)ということで、演奏に関しては語ることはない、というか折り紙つき。
全11曲はロック色の強いものからシックなバラード、ジャズ、ブルーズ・スタンダードからジェンキンズ編曲・指揮のオーケストラをバックにしたクラシカルなものまでとりとめがないまでに多様。うち8曲がホイルとジェンキンズのクレジットによるオリジナルで、アレンジ、メロディ共に一級品である。伸びのある色香とハスキーから中庸な透明感まで変幻自在のヴォーカルを聴かせるリンダ嬢の歌唱も表現力豊かでお見事。ゆっくりとしたテンポの曲を淡々と歌う様にはぐっと惹き込まれ、線は太いが潔癖で突き抜ける。スピーカーの前に現出する深みのある音像は乾いた生身の実在感を持って息づいている。渋い色彩ながらも視覚的に決まったジャケ・デザインも格調高い。相反する要素が複雑に入り乱れ、統合され、奇跡的に嵌った構図を生み出したように思える。

AAEVP3
New & Improved/Julianne Regan & Mice
年柄もよろしくチューチュー・マイスのおそらく唯一作から。ブリッチェノ脱退で啼かず飛ばずに陥ったオール・アバウト・イヴは三作目の製作をリーガンのソロでなければ出さないとレコード会社に引導を渡されて移籍、なんとか三作目のリリースに漕ぎ着けるがやっぱりお払い箱で再移籍を余儀なくされたが、その判断は概ね正しくて結局四作目リリース後に廃業した。
そのリーガンがかつて見た夢をもう一度と、古い知人でギター奏者、Tim McTigheの全面的なバックアップの下にリリースした復帰作が1999年の『Because I can/Mice』で、本作はそれにシングルB面曲と未発表宅録デモ類を加え、70分越えまで収録した「改良」ヴァージョンである。全曲リーガン自身の解説付。グランジっぽいメタル・ギターも一部リーガンが弾いているのかな?
ストレートでアップテンポな曲調が増え、かつてのしっとりとした暗さは陰を顰めがちではあるが、まぁ、内容はともかくとして、個人的にはけっこう気に入っている。ノイズ風のエレクトロニクスの導入はMcTigheの趣味かな? 相変わらず上手くないし、曲作りにも意気込みが空回りしたような無理が目立つ。歌も一本調子で大方が期待していた部分を敢えて外すようなちぐはぐ感が否めないのだが、気持ちはとてもよくわかる気がする。彼女自身、女の子がロングドレス着て歌うこととオバさんがミニスカート履いて歌うことの間には、越えることが難しい冷厳たる現実が横たわっていることに気づいていたからに他ならないということだろう。2000年になってマイスはAAE復活の母体として発展的解消を遂げるが、ブリッチェノ抜きの復活AAEは、結果的にシングル1枚とライブアルバム数枚を出しただけで、時代の狭間に埋没するように誰に省みられることなく消滅していった。
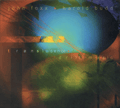
Edsel MEDCD 727
Translucence + Drift music/John Foxx + Harold Budd
ブライアン・イーノとの共同作業で名前を聞くことが多いアメリカのアンビエント系現代音楽家ハロルド・バッドとフォクス御大の共同名義アルバム2CD、6面デジパック。フォクスとしては同時期(Cathedral Ocean 2と同年)の聖堂大海シリーズとは趣が異なるが、BGMとは一線を画した媚のない純粋さと突き詰めようという意志が感じられる佳作である。
1枚目は「Trancelucence(半透明)」と銘打たれた全12曲、バッドのシンプルな音響ピアノを主役に純粋耽美が残響深く空疎な音空間に淡々と響き渡る。それなりにメロディらしきものもあって7曲目なんぞは瑞々しくリリカルな情感がゆるりと漂い滴る。
2枚目は「Drift Music」で全15曲が収容されている。光の回折現象の如く転回し、浸透し、隠された帳の向こう側までにも、ひたひたと絶え間なく打ち寄せる音の静謐。微妙に位相を変えながら、控えめでくぐもった背景音の連なりだけで構成された光や液体と同じように流れゆく、あくまで波動としての音楽のようなもの…とでも言おうか。聴覚で知覚される研ぎ澄まされた美意識だけで成立しているような形而上的音楽に極めて近い。

Brain 811842-2
Dune/Klaus Schulze
「Dune(砂丘):29'52」「Shadow of ignorance(無知の暗がり):26'20」の全2曲。アルバム11作目ぐらいだが既にあやふや。タイトル曲の元ネタは『Dune/砂の惑星』というフランク・ハーバート作のアナクロSF大河長編で、著者死亡により未完となっていたはず。85年頃に映画も観た記憶があるが、カルトなのかヒロイック・ファンタジーなのか中途半端で出来は今一つだった。
サポートとしてチェロ奏者がクレジットされている「Dune」はリズムレス+メロディレスな音響。あまりにも荒涼で寂寞とした世界観は初作『Irrlicht』に通ずるものがあるが、むしろ硬質さは薄れ、ゆったりとした冷やっこさが生チェロの悩ましさと相まってひたひたと触感に押し寄せる。ラスト直前に突然テーマらしき反復メロディが鳴り始めるが、ありゃりゃ、時間切れのようにフェイドアウトしてしまう。冗談抜きで、本来先に続きがあるものをLPの収録限界がきたから終わりにしたよんという趣。
後半はシーケンサが作る単調なリズムの上を長大な歌詞が淡々と抑揚なく呟かれていくという展開。英サイケの人、ブラウン(Arthur Brown)によって詠まれる観念哲学詞はシュルツェ作の英詩という珍しい構成。あらゆる感情を寄せ付けない鋼のようなモノクロームな鈍色の非情さに微妙に湿度がのり始めた。

Spalax 14217
Seligpreisung/Popol Vuh
ポポル・ヴフ四作目。前作『Hosianna Mantra』に引き続き聖書を題材にした全8曲の宗教小品で、トータル29分と今ならミニ・アルバムかマキシ・シングル並みの補遺集。歌詞は「マタイの福音書」からとられた宗教説諭集らしいが、例によって中身には興味もないし、異教徒として関わりたくもない。そういう意味では本質的な理解には程遠く、神秘だの瞑想云々からのアプローチではその世界観の半分しか認知できないような気もしている。
前作のハイライトでもある朝鮮人ソプラノの美声は不在で、首領フリッケが歌っているようだ。フィッシェルシャーの妙な(つまりDüül風な)ロック・ドラム、ファイトの電気ギター入りで、それなりに変化に富んだアレンジが為されているが、前作からソプラノを抜いただけともいえる。次作では復活しているのでやはり繋ぎとしてのリリースなのかな。概ね穏やかで緩いテンポ、詠唱的な歌と淡白なアンサンブルによる素朴で高潔な曲調。淡々とした明るい流れ。めりはりや躍動感とはほぼ無縁なポポル・ヴフとしかいいようのない特異性は既に確立されている。

fonomusic
CD-1068
Hablo de una tierra/Granada
『大地を語る』といった意味合いのエスパーニャのグラナダ初作。大ぶりの柘榴を積み上げたテーブルで、微妙に滑稽さを漂わせながらも黒尽くめで決めるのが全曲を作り、親分風を吹かす大男カルロス・カルカモ(Carlos Càrcamo)。当初は一応バンド編成だったらしく、裏ジャケには4名の“如何にも”な容貌のスペイン親父たちがど~んと脂っこくポーズを決めている。ああ、臭いそう。
グラナダの3作のなかでは最も濃厚な民俗色をもちながらプログ風の展開と構成、滴るほどのメランコリックな叙情性を醸しながら、上手くはないがさらりと流れるリズムといった妙に相反する要素が見え隠れするあたりが斬新にして非常に壷を押さえた全6曲。もっとも、カルカモの思惑としては濃厚なアンダルシア色(田舎)というよりはカスティーリャ風(都会)の洗練を目指し、ジャズロックに重きを置いているように思う。ギタッラ・エスパニョラにのせた歌ものもボーカルをイコライズ処理し、リヴァーブを掛けることで必要以上に濃くなりすぎないような方策が採られているようだ。水の流れのSEやメロトロンが奏でる湿っぽいメロディ、ときに炸裂し、ときにふわりと漂うカルカモ・フルートも情緒的かつ素朴で微笑ましい風情ではあるが、地域と年代、風土を考えれば才気煥発にして先進と捉えるべきだろう。

Crammed Discs
CRAM 102
1981
Desire/No tears/Tuxedomoon
ベルギーのクラムド・ディスクの稼ぎ頭だったのか、名前が売れていただけかは知らないが、妙に突出していたタクシードムーンの2ndアルバム『Desire』(81年)に78年のEP『No tears』をカップリングした再発CD。CDの銀盤をケースから抜くと、「ハミングできないメロディ」と書かれているが、そうでもなくてけっこう流して聞いていると気持ちよい。ジャケットはオリジナルとは別物。
78年の『No tears』はアメリカ西海岸時代の全4曲。時節柄トチ狂ったポスト・パンク色が色濃く重いエレポップ。攻撃的な切れ込みと鬱なアンビエント色の二律背反というか股裂き状態が斬新にして陰鬱。
『Desire』は黄昏たメランコリックなメロディと人工的で舞踏的だがわざと外したような現代音楽リズムが微妙に爛れた欧州風の頽廃感を余すところなく表出していて、しかも陽気さと刹那さ、チープと重厚が錯綜し、毒気を帯びた煌びやかさが耽美を生むというわけのわからなさが、独特の隠微な心地良さのなかに見え隠れする。やがて傾倒していく演劇性もこの時点で既に萌芽の兆しが感じられ、演者トン(Winston Tong)の上手いのか下手なのかよくわからない、口が開いたまま締まらないような濁音ボーカルも十二分に叙景的だ。ポップでコミカルな余裕すら感じさせる一方で、巧妙に隠されている先鋭的な才気に気付くと、もう抜けられない。

コロムビア
COCQ-83686
Encore Best/田部京子
どこで、どこから知り得たのか今となっては記憶も曖昧。吉松隆の新作ピアノ曲の初演者というあたりが端緒か、あるいは「無言歌集」か。これはCDデビュー10周年記念盤ということで、アンコール小曲集のようなもの。本人による曲目解説付。彼女の業界での位置付けは正直言ってわからないし興味もない。最初に、名前も知らずにその音を小耳に挟んだとき、その繊細で研ぎ澄まされた、端正で硬質な透明感に心打たれた。思わず振り返って、音の出所を探したというやつ。日本人には珍しい輪郭のはっきりした音符でありながら、流れるような瑞々しさとメランコリィも印象的だった。見た目の派手さは欠片もなく極めて地味。控えめでありながらもテクはある。テクはあるけどひけらかさない。曲解釈に一貫性と深みがあって、ある種の潔癖感に貫かれた表現の方向性に親密さを感じた。
全17曲。選曲はかなりベタなものから、ちょいとほくそ笑むようなものまで多様性に富んでいる。シューベルトに代表されるドイツものがやはり良いが、プーランクの「エディット・ピアフへのオマージュ」や、マイナーなロシアものも目を見張らせる。

BGO Records
BGOCD98
Sweet deceiver/Kevin Ayers
暗鬱にして繊細、天才の名をほしいままにエキセントリックぶっていた初期のイメージが崩れ、元来のダラシナく脳天気な南国的陽性さが隠し切れなくなったソロにして7作目くらい。復活ライブ後、30過ぎてのスタジオアルバム。オリー・ハルソル(CDには何故かOllie Haircutと記載)のギターはすこぶる元気で、ゲストでエルトン・ジョンがピアノまで弾いている。前作を髣髴とさせるシリアスで不可思議なコード使いの暗めのプログ曲やバラードもあるものの、ボサノヴァやカリプソまがいのお茶らけ加減は後に繋がる変遷の端緒ともいえよう。独特の微妙に緩いポップを聴いていると、年齢的に小難しいことが馬鹿臭くなって享楽に走るのはとてもよくわかる。全9曲。緩いながらも手の込んだアレンジは斬新で異彩を放っているあたりは期待を裏切らない。共同プロデュースはオリー・ハルソル。再発レーベルBGOの92年、リマスター。

Venture CDVE43
Flux + Mutability/Sylvian, David/Holger Czukay
88年、カンのスタジオで生録音されたコラボレイト第2作。シルヴィアンは未聴の元ジャパンの歌手(だったかな?)で独立後アンビエントに傾倒した人、チューカイはドイツ人、カンの現代音楽+音響作家兼ホルン奏者。1979年にイラン国営放送を自作にミックスしたコラージュ怪作「Persian Love」でオチャラケながら業界にそれなりの地位を築き上げた偉人。他にカンの元同僚リーベツァイトが打楽器で、カローリが前半でギターを入れているようだ。チューカイの師匠であるカールハインツ・シュトックハウゼン(Karlheinz Stockhausen:1928-2007)の息子の名前もクレジットされているが、まぁ、多分あまり関係はないだろう。
前半「Flux(絶え間ない変化)16:52」はチューカイ得意のアンビエント音響コラージュの基盤に、シルヴィアンのメランコリックなセンスがたゆとう。ゆったりとしたリズムと取り留めのないフレーズの断片がうねるような位相で攪拌された確信犯的な悦楽。倍長くてもよい。
後半「Mutability(移ろい、無常)21:02」は導入部の法悦の真美にノックアウト。柔らかな光に包まれた蕩けそうで、没我的なまでの崇高感に侵食される。チューカイはプロデュースとエンジニアリングに徹し、彼のシニカルでユーモラスな視線が薄れた分、滴るような耽美で覆い尽くされた稀に見る儚さと恍惚が春の海のように広がっていく。言葉は不要だ。