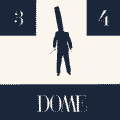
Dome 34 CD
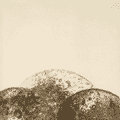
Dome3
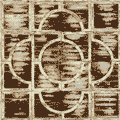
Dome4
1982
3,4/Dome
いきなり冷え冷えと寒々しい。その名の通り『3』と『4』のカップリングCD。この後『5』にあたるものがリリースされているが、近年ワイア自体も再編されてロック色の強い新作が出ているようです。“ようです”というのは興味が薄れつつあるからで、パンクもロックもプログも、そして多分音楽すらなくても困らないのではないか? と疑問符がつきはじめて10年程が経った。昔は耳栓して(多分周囲には騒音を撒き散らしながら)通勤電車に乗っておりましたが、今は四輪車ですら無音であることが常態と化している。アクセルを踏むと聞こえる過給機の高周波とエンジンの振動、風切音だけで十分のような気がするし、敢えてCDを聴いても音が悪過ぎる。遠いのか遠くないのか不詳だが、いつの日か海の音、山の音、野を渡る風の音、断崖を打ち砂を引く波の音、流れる音、葉が落ち花が舞う音、そんな音だけが支配する環境に身を置きたいものだ。
『3』は壊れたタイトルを持つ壊れた音楽。『4』は良く言えばアンビエント、どちらかというと境界線の向こう側でひっそりと聞こえていそうな現実感のない空疎な虚構。どちらも一般性には欠けるかもしれないが、音楽であることを自ら止めることによってあらゆる束縛から逃れ、聴取者という商売におけるお客様を無窮の虚空に放逐することによって自由を享受した脱音楽音響の試み。でもソビエト・フランスみたいだぞぅ。
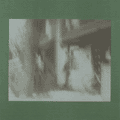
COMM44
Philipp Schatz/Village of Savoonga
こちらも負けず劣らず冷え冷えとした、おそらく四作ほどがリリースされているアルバムの二作目。主としてテクノ? ノイズ? 方面の重鎮であるマルクス・アッヒャー(Markus Acher)、クリストフ・メルク( Christoph Merk)、ヴォルフガング・ペッターズ(Wolfgang Petters)等が主要人員らしい(もちろん聞いたことすらない)が固定化されてはいないらしい。中身はスパルタの同名映画とムルナウの無声映画『Nosferatu』のサウンドトラックらしいが、不詳である。映画タイトルでもある『Philipp Schatz』はどうやらエッセンハイム(Essenheim)の300年程前の司祭を指す人名のようだがこれまたよくわからん。針飛び風のループとブランコの鎖が軋むようなノイズが巧みに織り込まれた暗黒ノイズ・アンビエント。ノスタルジィを誘うぼやけた感触と、寒々しい無機質な肌触りが織り成す冷酷で絶望的な彼岸の心象風景。赤く傾いた夕陽に照らされた砂場、軋む無人のブランコ、足踏みオルガンのチープで虚ろな音色。霞がかかったように滲んだ景色。
ちなみにユニット名である“Savoonga”はベーリング海、セント・ローレンス島北岸、北緯63.7度にあるエスキモーの村の名前。
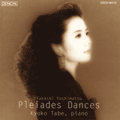
DENON
COCO-80115
プレイアデス舞曲集/吉松隆・田部京子
今年の冬は愚図ついた天気が続いた。冬空といえば昴、昴といえばプレイアデス、乙女チックなタイトルとは裏腹に中身は優れてリリカルかつ清廉な五つのピアノ曲集です。弾きこなす田部の力量もしなやかで節度良く気持ち良い。ベートーフェンのピアノソナタは三部構成30分、1時間越えなど当たり前だけれど、プレイアデス第一集から第五集は1分弱から3分、全35曲の小品集。内スリーブには作者、演奏者、評論家? による明解でかつとても良い文章が綴られているので、正直それ以上に書くことも書けることも何もない。プレイアデスは七つ星。七つの音(アンチ12音主義というのか?)と七つの旋法、3拍子から9拍子までの七つのリズム、各集7曲で構成された清楚で純粋な現代音楽。
多分こんなことを書いている人はいないはずなので敢えて書いてみよう。
「III」
01:さりげない前奏曲
02:左寄りの舞曲
03:球形のロマンス
04:右寄りの舞曲
05:聖歌の聞こえる間奏曲
06:過去形のロマンス
07:多少華やかな円舞曲
「IV」
08:前奏曲の記憶
09:静かなる雨の雅歌
10:西に向かう舞曲
11:間奏曲の記憶
12:遠く暗い牧歌
13:東に向かう舞曲
14:アレルヤの季節
「V」
15:前奏曲の映像
16:暗い朝のパヴァーヌ
17:午後の舞曲
18:傾いた哀歌
19:夕暮れのアラベスク
20:真夜中のノエル
21:ロンドの風景
「I」
22:フローラル・ダンス
23:ほぼ二声のインヴェンション
24:アップル・シード・ダンス
25:水によせる間奏曲
26:リーフレット・ダンス
27:ほぼ三声のインヴェンション
28:プラタナス・ダンス
「II」
29:消極的な前奏曲
30:図式的なインヴェンション
31:線形のロマンス
32:鳥のいる間奏曲
33:断片的な舞曲
34:小さな乾いたフーガ
35:積極的なロンド
サティ? グリーク? 曲名を見て興味を引かれた向きには、豊かなイメージを喚起する優れた作品となるでしょう。CDの収録順は何故かIII→IV→V→I→IIとなっている。
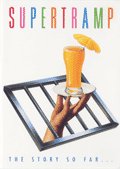
A&M
069 493 222-9
The story so far.../Supertramp
カン(CAN)のDVDを見ているとどうも字幕と音声を追っかけてしまって疲れる(最近、なんと日本語字幕付であることに気付いて驚いた)ので、これならお気楽そうで大丈夫だっぺ、と叩き売っていたのを購入したスーパートランプのDVD。一応、ドルビーで5.1chなのだなぁ。だからなんだと、システムをお借りして視聴してみましたが、音質映像共に大変良好です。映像は盛りをちょっと過ぎた1983年のミュンヘンでのライブが中心で、『Crime of century』、『Breakfast in America』の曲が大半を占めている。その他に若干の最近のインタビューや80年代後半の落ち目になってからのプロモビデオが含まれています。肝心の頭二人の確執はさらりと逃げてしまって今ひとつ。大人だねぇ。
随分に前に『Crime of century』のしょうもないレビューを書いたっきりで、ことスーパートランプに関しては停滞しておりましたが、中期の作は漸次、傾向は推移していくもののどれもそれなりの質と内容をもったものです。リチャード・デイヴィス(Richard Davis)とロジャー・ホジソン(Roger Hodgson)という二人の鍵盤奏者兼歌手の確執というか競争意識が緊張感と切磋琢磨を生んで、楽曲にスリリングで新鮮な展開をもたらしていたわけです。従って、80年代中期のホジソン脱退後は気の抜けたジントニックのような無残な状態を晒すことになる。メガ・ヒット曲を作曲したのがホジソンだったということもあるが、ソロになってからのホジソンの曲もバリエーションに悉く欠けているところをみると、水と油が程よく交じり合うことが不可欠だったのだろう。
ライブ映像はセットリスト通りではないだろうが、レコードと同様にデイビィスとホジソンが交互に脚光を浴びるような作りになっている。ホジソンはギターも弾いているが、二人の位置が曲に応じてころころ入れ替わるのが面白い。サポートも含めて非常に質の高い演奏でライブだからという妥協もないし、かといってレコードと同じという詰まらなさも回避して、十分堪能できる、心迫る内容になっている。でもやっぱり、「School」に「Dreamer」だよなぁ。
DVDはどうでも良いペラ紙一枚がケースに入っている(入っているだけマシともいえるが……)A&MのUSA製のようで、リージョン0でNTSC。
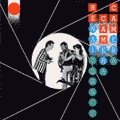
Repertoire Records
REP 4628-WY
Camera Camera/Renaissance
1996年の再発CD。第二期ルネサンスの『Azure d'or』の次作にして最後から二番目のアルバム。第二期の初期から中期は日本では異常に評価が高く面食らうのだが、これは糞味噌に貶されるというか評価の対象にすらならない末期の作。ルネサンス人気というのは結局のところビートルズにおけるマッカートニーのバラード人気やキャメル人気と同質なのだろうが、2000年には敢えて『Tuscany』なる再編盤が国内でリリースされるあたり、彼等もマーケッティングは怠っていないというか、購買対象を見据えたしたたかさは失っていないのだろう。スリーブ・デザインの雰囲気も大きく変わり、前作には感じられたある種の品とネオ・クラシック風の要素はほぼ消え失せた。けばけばしく若作りしている裏スリーブはさすがに見るに耐えないが、楽曲の出来そのものには遜色があるわけではない。意識的に歌い方を変えているあたりはそれなりの新機軸なのだろう。節操なくケイト・ブッシュみたいだったり「お吉サン」なる芸者まで出てきて面白いやら……。
ルネサンスの楽曲を特徴付けていた鍵盤のタウトも既におらず、アナログ・エレポップしているキーボードが薄っぺらくて物悲しい。内容的には時代の波に合わせたポップ化というよくあるパターン。
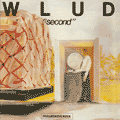
Musea
FGBG 4187.AR
Second/Wlud
その名の通りの『二作目』に未発表曲、シングル曲計5曲を加えた97年の再発CD。アルバム曲は全曲インストの硬質ジャズ・ロック。ボーナスは歌入りの可愛らしい短曲メロディアス・ポップ。上手いボーカルではないが素朴な雰囲気が田舎風のフランス語にとてもよく合う。ラスト「生き残ったアザラシ」に至ってはピアノ弾き語り。前半との落差がまた凄い。個人的には甲乙つけ難いが、まぁ、言わんとするところは前半なのだろうなぁ。相変わらずのデモ・テイク並の酷い録音だが、楽曲はいっそうこなれて質密にして流麗、垢抜けなさとリリカルさが同居しつつも破綻しない楽曲の構成が面白い。良いプロデューサと資金に恵まれていたら、モナリザやワパスー並のものが残せたのに……と思わせる。

Farewell Music
Liars dance/Liars Dance
スイスのアシッド・サイケ・フォークらしいが、詳細は一切不明である。ググってもほとんど情報がない。女性ボーカルを含むトリオ編成でリリカルかつ穏やかな曲調が特徴。歌詞、その他すべてが英語表記でスイス・ローカルな部分は微妙に乾いた暗鬱さ以外ほとんど感じられず、ゼペリン(Led Zeppelin)のカバー(「That's the way」だな)まであるところからもイングランド・トラッドの影響が顕著である。美しいメロディと素朴な情感が醸し出す歌と、器楽の部分はバロック風の展開とアンサンブルを秘めながらも冬枯れの絶望感を纏っているようだ。狙っているわけではないだろうが、ときおり表出する往年のコーマスの再来を思わせる病的なエキセントリックさが不気味。

OPUS ONE
14
Line drawings, etc/Leo Kraft,etc
アメリカの現代音楽家レオ・クラフト(Leo Kraft:1922-)による1972年度作品「Line Drawings」他、4作品が収められたコンピ盤と思われる。声楽曲から器楽曲、果ては協奏曲からシンフォニィまで、多種多様な作品を発表している作曲家のようだ。どうもジャケットの表記と曲順が合致していないようだが、ほとんど何も記載がないのでどうしようもないな。聞こえてくる音を頼りに類推するにはこんな感じか。曲名の後ろは演者のようです。
1;BARBARA KOLB 「Rebuttal」 George Hirner, Gary McGee, clarinets
2;LEO KRAFT 「Line Drawings」 Paul Dunkel, flute, Richard Fitz, percussion
3;DAVID COPE 「Cycles」 J. Martin, flute; David Cope, contrabass
4;RONALD PERERA 「Reflex」 Ernst Wallfisch, viola; with electronically derived sounds
5;MAX SCHBEL 「Moonwave」 ?
主にフルートを主体とした管楽器による作品ですが、古典的な要素は皆無。総じて無調。能か狂言を思わせる間と余韻、跳ね回るフルート、ビオラが刺激的な情緒を喚起する。 これはおそらく1970年代後半にリリースされたLPですが、今でも同じものが売られているようです。
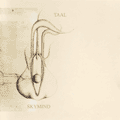
Musea
FGBG 4483.AR
Skymind/Taal
主にフランス人で構成されていると思われるメタル・チェンバー、ター(ル)の二作目。タイトル、曲名、歌詞共に英語、Taalはオランダ語(“言語”の意)だからタールと読む方が適切かもしれない。ダブル・パーカッションのロック楽団にフルート、バイオリン、ビオラ、チェロの管弦楽隊を加えた10人編成の大所帯。
多様なアンサンブルが可能な編成のわりに抑揚に欠ける一本調子で、品のなさ過ぎるメタル・ギターが煩いことを除けば、それなりにテクもあり、創出されるSFチックな世界観の表現力も及第点だろう。弦楽隊はギターに負けない音圧で録音されていますが、如何せん発情した筋肉男のような爆音ギターがでしゃばりすぎで弦楽隊の存在意義が薄れているし、ラウドなクリムゾン調デス・メタルはさすがに戴けない。民族調のダンサブルな曲やバロック趣味が横溢するノスタルジックな楽曲、如何にもフランス風な大道芸的展開など意欲的で面白い部分もあるので、ギターがいなくなることを期待しておこう。

Spoon
32/33/34
Anthology-Soundtracks 1978-1993/Irmin Schmidt
カンの理論的支柱であり鍵盤奏者、イルミン・シュミットの三枚組アンソロジィ。副題が示す通り、映画と劇伴用に作曲された楽曲が収録されている。もっとも最長でも14分ほど。計43曲、3時間半を越すボリュームは現代音楽としては特段びっくりすることはない。アンビエントからファンクまで、古典から現音までジャンルなど存在しないかのような楽曲の幅の広さと、そのすべてにおいてちょっと捻られた非尋常さは重苦しくもなく軽薄でもなく優れた20世紀の音楽の完成形を呈示しているといえるだろう。いみじくもかつてから自ら自身で述べているようにシュミットは表現をしない。ただ音楽を作るだけである。
サポートはいつものカンのメンバーが主体。そういえば、ジャキ・リーベツァイトも“わたしは音楽家ではなくて打楽器奏者である”と語っているなぁ。 1937年の生れだから既に70歳目前ですが、近作としては97年に『Gormenghast』なる現代オペラ作品を発表しております。

Island
IMCD 303
To Markos III/Nirvana
アイルランド人とギリシャ人のポップ・デュオ、ニルヴァーナ三作目。別名『Black Flower』ともいわれる。意味ありげなタイトルはあまり深い意図はなさそうで、資金援助をしてくれたスピロプロスのギリシャの叔父さんを指しているようだ。レコード会社に発売を拒否されて原盤権を自ら買い取ってリリースに漕ぎつけたらしい。失意のスピロプロスはこれにてギリシャに帰ってしまったようで、ニルヴァーナは以後、一人ユニットと化す。初期三作は製作年度も接近しているせいもあってそれほど差異はない。メロディアスでサイケなポップではあるがその構築的な感覚は、当時のサイケ・ポップをアール・ヌボーとするならば線形デコラティブと幾何学的なストイックが共存したようなアール・デコに近いものを感ずる。何の骨だか知らないが、赤いマニキュアと対比される繊細な白骨をあしらったスリーブも秀逸。
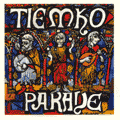
Musea
FGBG 4057.AR
Parade/Tiemko
こちらも三作目。相変わらず美麗でクール、耳障りのお洒落な音でありながら、どうしようもなく変てこで無調なメロディと変転するリズムを紡ぎだすトリオ。伝統的なジャズロック・フランセとサン・サーンスやビゼー、ラヴェルを思わせるフランス近代音楽が基調であることは否定できないが、楽曲の緻密な構築性と新鮮な展開は明らかに現代音楽的な色彩を帯びたもの。ここに来てポップ・ロック風のお約束や常道は完璧に排除する方向に舵を切ったといっても差し支えないだろう。造り上げられた迷宮は幾重にも回廊が取り囲み、微妙な重なりが僅かな色調の変化をもたらす鉛入りガラスの透明度。デジタル楽器とアコギやドラムの生音の対比、鉄琴やハープなども独特の透明感をもって浮遊している様は極めてスュルレアル。全曲インスト。
インナースリーブには各曲ごとに故デローネ作のイラストが添付され、強烈なジャケ絵も同氏作。曲は最長7:28とコンパクトになって全9曲。「Good bye Mr.Prog」なるなんとも意味深な曲では、露骨なバリバリの変拍子、唐突な展開、民族調のメロディでプログ氏をおちょくっているシニカルな視線が楽しい。
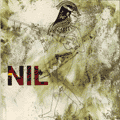
Legend Music
LM 9003
Nil/Nil
ほとんど何も資料がなくて詳細が不明なニル。おそらく唯一のアルバムと思われる。ジャケの雰囲気からもわかる通りニルはアレクサンドリア東方で地中海に注ぐ大河のこと。アラビア語でアンニール(An nile)というらしい。
基本はギターのペトー(Michel Peteau)とドラムのロッシーニ(Stéphane Rossini)を中心にしたデュオでライブ・プロジェクトのようなものだったらしい。録音もデモ・テイクないしはライブでお世辞にも良いとは言い難い。基本は即興主体のズール・タイプのアングラ・ジャズ・サイケで、著名人(!)としてはジャニク・トップ(Jannick Top)あたりが部分的に参加しているところが目を惹くところ。ポップでメロディアスな英語歌のバラードもあるなど、フォークタッチからシリアスまで玉石混淆だが、荒々しさのなかにも才気とセンスの息吹は感じられるか。
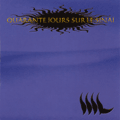
Nil Records
Quarante jours sur le Sinaï/Nil
こちらのニルは最近のもの。自主レーベルからのリリースと思われる。70年代のものとはまったく関連はないようです。中身も継承されている要素はまったくないので名前が同じだけという偶然でしょう。Acte I(36'16)、Acte II(26'42)の二部構成のスタジオ・ライブ。一般的なカルテット編成に女性ボーカル、チェロ、ハープ、サックス等が加わったもの。シリアスで精緻なアレンジ主体。豊かに響くチェロ、ストリング音の硬質なメロトロン、切れ込むシャープなリズムとアンサンブルも完璧なまでに気持ちの良い透明感をもって迫ってくる。つぼに嵌った構成、展開も非常に良く練られている。一発録りと思われるテクニックも申し分ないだろう。次作にも十分期待できそう。
タイトルは『シナイでの40日間』の意。もちろんシナイ半島を指す。プラトンの箴言やらダンテ、エジプト古代神話、発掘された古代エジプト碑文、エルメス文書等からの引用と薀蓄で構成されたトータル・アルバム。透明な女性ボーカルはフランス語だが、英語のテキスト付。
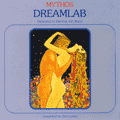
OHR 70020-2
Dreamlab/Mythos
ドイツのミュートス、75年の二作目。ジャケットのクリムト崩れのようなダサ絵とは裏腹に、中身はヴェルナー・フォン・ブラウン(Wernher von Braun:1912-1977 1944年に実戦配備された弾道ミサイルV2の開発者、<中略>後にアポロ計画のサターンロケットを開発)に献呈された宇宙賛歌のようなもの。前作もそうだがハードSF趣味をドイツ象徴主義的叙情で描き上げようという路線は変わらない。首謀者であるシュテファン・カスケ(Stephan Kaske)以外は総入れ替えの模様で、タイトルも英語、歌詞も英語と海外進出を図ったのだろうが見事に失敗したなぁ。もっとも、どうあがいてもクラウトの範疇を外して評価の得られる音楽ではないだろうに……と思うのだが。
ギターのアルペジオの上を走るカスケのフルートというアンサンブルが主調のB級コズミック・サイケ・フォーク。たゆとうアンビエント感を心地良いと感ずるか、たるいと感ずるかが評価の分かれ目。女性コーラルはオール(Ohr)の社長ロルフ-ウルリッヒ・カイザー(Rolf-Ulrich Kaiser)の社長秘書にしてコズミック・ジョーカーでは顔を晒している“Starmaiden(星の淑女)”ことギーレ・レトマン(Gille Lettmann)。
「Expedeitions(遠征)」
時間の喪失、空間の喪失
希望と死のあいだで瞬く星屑のように
無菌の水、無菌の食い物
人工的な空気と大地
それでもこの限られた宇宙船のなかには
その使命を果たすために
一つの目的に向かって進む
考える生物がいる
それが人類だ
われわれはパラダイスに辿り着けるだろうか
水と空気を見つけ出せるだろうか
同じ種が存在するだろうか
これは希望のない、死の惑星だろうか
一つの銀河がわれわれの行く手を阻むのだろうか
まだ知らぬ未来
しかし戦う準備はできている
まだ知らぬ生物に対して
われらの子孫が生き延びて、笑い、楽しめるように
書庫を発掘していたら子供のころに読んだSFジュブナイルを見つけた。300ページほどの文庫本ですが、あまりに稚拙な展開や描写に苦笑しつつもついうっかり1時間ほどで再読してしまった。西崎義展企画、今やバイアス思想の伝道師になったらしい豊田有恒原案、石津嵐著(ソノラマ文庫のシリアル1)とあるが後のTVや映画(未見)とは違ったSFらしい結末がとても気に入った記憶が残っている。
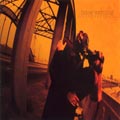
Metal Blade
3984-14324-2
Disconnected/Fates Warning
締めくくりは五年程前、No.1で取り上げたフェイツ・ヲーニング久々の登場。何故FWをトップにもっていったのかは実はよく憶えていたりする。「あぁ、ここは○○系か」といった的を絞られたくないと云う理由もあったのだが、ドリーム・シアター(Dream Theater:まぁ、とはいっても聴いたことすらないのだが)やラッシュ(Rush)の陰で完璧に黙殺される80年代前半からの先駆者として、その高質なレベルと先進性に個人的に好感を覚えたのが最大の理由であった。
メタリックでありながら抑制の効いたギターと卓越した精緻なパーカッション、決して喚かない説得力に満ちたボーカルと、どれをとっても聴くに値する価値を兼ね備えた完成度の高さは惚れ惚れする。おそらくこれ以外の解は見つからない極限にまで突き詰められ、夾雑物の排された硬質で透明な結晶のようなもの。中世楽曲のような法理と数学で構成された純粋な楽理の如く無駄音一切なし。世間的にはプログ・メタルで一括りにされるらしいが、メタルでもロックでもなく、自らの進む道をただ突き進む、ひたすらストイックな中年オジサン集団の日々是精進がこの上もなく気に入っている。