
日本コロムビア
PLCP-110
After the heat/Eno + Moebius + Roedelius
76年の『Tracks & Traces』、77年の『Cluster & Eno』に続き、ボウイーのベルリン諸作を挟んだ70年代の一応アンビエント・コラボ三部作のラスト。尤も従前と趣はかなり異なる全10曲。クラスターを前にするとイーノの持ち味はポップな歌ものに収斂されてしまうせいか、得意の歌ものまでが混入されて先鋭感は著しく薄れ、アルバムとしては統一感に欠けて寄せ集め的な印象が拭えない。
Cのクラスター側からみれば、ある程度ポップなメロディというものが持つ力は、決してアンビエントとは相容れないものではなく、むしろシンプルな位相のズレを先鋭化する効果として次作以降に展開されていく懐かしさすら感ずる安息感の萌芽がみえる。個々の曲、特にインスト曲はタイトル通り熱気が去った後の乾いた火照りのような、ヒリヒリするような気だるさと湿布のような冷ややかさを保ち、奇矯なリズムと共に極めて触感的な音の手触りは産毛が逆立つような感触すらある。録音はコニー・プランクのスタジオ。生温い風に僅かな湿り気がのりはじめた乾いた夏の夕べに。
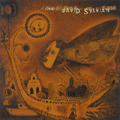
Virgin
7243 8 47071 2 5
Dead bees on a cake/Sylvian, David
87年の『Secrets of the Beehive』に続き12年ぶりにリリースされたソロ4作目。得意のアンビエントを基調に、アメリカ移住後のブルーズやジャズ、ロックの構成やアレンジを借りた、角のとれたマッタリ風味が漂う佳作。シルヴィアン自身の歌謡までがシンプルにして虚飾の欠片もない自然さが横溢しており、丁寧に作り込まれた淡々と衒いのない70分オーヴァー全14曲として結実した。元々、才能が零れ落ちるわけでも器用なわけでもないから、前作の時代の先端であろうとした意識がすっかり抜けて地道に自らを見詰め直すことが、逆に本来の個性を際立たせる結果に繋がったともいえるだろう。そのあまりにも内省的、あるいはプライベートな繊細さを心地良い親密さと捉えるならば、ひっそりとした安寧と慰藉に浸れることだろう。
ということで、深夜というか明け方、グラスを片手に沈降していく意識の流れに身を任せるとき、白みはじめた夜気を身にまとうようにデヴィシルの声はあまりにも心地良い。ジャケ画は何故だか『東京漂流』を書いた藤原新也の銅版画。

MTM 20 CD
Geologies/Zazou, Hector
70年代ZNRの末裔の一人、多作なエクトル・ザズーがベルギー・クラムド・ディスクのMade to measureシリーズVol.20としてリリースしたフル・アルバム。ザズーのMtMシリーズとしては『Reivax au Bongo』、『Geographies』に続く第三弾で、乱発するコマーシャルなアルバムと異なって比較的ZNRの継承に近い趣を持ったアンビエント・エレクトロ・チェンバー。極めて親密な情緒と細密なまでの丁寧さが朽ち果てた箱庭にぶちまけられたような刹那的な美学を構築し、その構造が隙間なくみっしりと徹底すればするほど、全体像が暈けていくような不安と隔絶。そんなものが一切合財積み重ねられたディテールだけの城のように、典雅な透明感と冷涼な不透明感が位相をずらしながら恐ろしく気持ちの良い音を奏でている。一応、トータル・アルバムのような作りにはなっている、ほぼ歌なし全13曲。
ザズーのシンセ+打ち込みと、ジュルベルヌ(Julverne)のジュノー・ジリ(Jeannot Gillis)が率いる弦楽四重奏団Le Quatuor Halvenhalfや、ユニヴェール・ゼロのディルク・デッシェメカーのクラリネット等ゲストの生楽器とのセンスよい絡み合いが聴きどころ。極めて上質にして才気が迸る。陳腐作とまっとうな作品の落差が激しすぎるのはそれなりに有名になってしまった報いなのだろう。ジャケ絵はトーマス・ベントン作「Persephone」。ギリシャ神話の女神ペルセポネといった方が通りはよい。

tôt Ou tard
0630-18441-2
Joseph Racaille/Racaille, Joseph
一方、ZNRのもう一人の末裔、ジョーゼフ・ラカイユは長らく裏稼業と黒子で沈黙を守っていたが、2000年を目前にしてあまりにも唐突にソロ・デビューを飾った。ラカイユ自身のあまり上手くない歌とピアノが、アルハンブラ(スペインの)なるおフザケが極まったラテン管弦楽団やウクレレ・バンドのアラビア風マンボのリズムに乗ってノホホンとシャンソンしちゃうという、かつてのZNRを期待する人には絶句間違い無しの俊作。シリアスさも繊細さも欠片も感じられない脳天気、常夏歌謡が炸裂する古のノスタルジックでチャチャチャ。鼻母音炸裂のフランス語が弛緩っぷりに更に拍車をかけて、ダンスホールで口説いたねーちゃんとどこへしけこもうかというスケベ心丸出しのニヤニヤ笑い。
「Un(一つ)」
そんなに喚くな!
泣かなくてもよいじゃないか
バスが片腕を捥いでいったからといって
――右腕
そんなごたいそうなもんじゃない
まだ一つ残っているじゃないか
が、その隙間にさり気なく挟まれる人を食った純室内楽風な器楽展開や数え歌、小品との差異はよりいっそう強調されて、統一された色合いの中に隠された色盲検査の図案のように淡く彩度の落ちた妖しさを湛えている。その、そこはかとない軽妙洒脱さ加減が売りなのだろう。この路線はその後の数作も基本は同じでおちゃらけ具合は邁進していく。もう真面目に作るつもりは更々ないんだろうな(笑)。
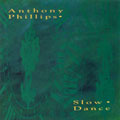
VJCP-65
Slow Dance/Phillips, Anthony
ジェネシスの初代ギター奏者による14作目のソロ・アルバム。シンプルで習作的だった『PP&P』シリーズとはかなり趣が異なる緻密さと荘重なオーケストレイションが特徴的である。おそらくアカデミックな師について基礎的な積み上げを再構築したのだろうと思われる。技法的にもクラシカルなアレンジが多用され、繊細で柔和にしてリリカルなメロディは健在だが、非常に洗練されたクールな感触を受けるという意味で半生の集大成的な位置付けになるような気もする。木管の生楽器とシンセのアンサンブルもこなれて丁寧で、自然で豊かな情感を紡ぎだしているだろう。劇的な展開やロック風のアンサンブルは皆無であるが、上品な穏やかさ、或いは現世感の無さは自らの風土と伝統を率直に体現したものなのだろう。唐突ではないが、微妙に繋がりを外すような展開は意外に耽美的にすら聞こえ、意図したものならばなかなか斬新なのかもしれない。
「Slow Dance part1」と「part2」のみの全二曲、インストのみ。クラシカルな生楽器が多用される前半に比して、後半は若干コンテンポラリでアップテンポ。BGMとは完全に一線を画した領域で、冷やっこくかつ気持ちが良い。

DENON
COCO-70803
朝の歌:エルガー作品集/Elgar, Edward//加藤知子
中世のパーセル以降、少なくとも音楽を生産する場所としては不毛の地であったイングランドに19世紀末、突如花開いたエドワード・エルガー(1857-1934)のヴァイオリン小品集+ヴァイオリン・ソナタ。繊細にして優雅、楽天的でもなく、悲愴に走るわけでもなく、あくまでも穏やかにして清廉な気品に溢れたメロディは憂愁の境地に達している。作風は保守的なイングランド人らしく古典派~ロマン派の範疇で、エキセントリックにも前衛にも走らずに、その枠の中で最上を目指すというタイプ。現代のイギリス音楽にもこのあたりはそのまま踏襲されていて、そのバランス感覚と突き抜けてしまわない踏みとどまり方は、やはり功利主義の賜物なのだろう。
弾き手は加藤知子、ピアノは江口玲。代表的なヴァイオリン奏者らしいが、位置付けなど詳細は不詳。残響多めで音に切れ目がない、しっとりめの音色は艶やかで情感豊かに迫ってくるあたり個人的には好みの音であり、テクニックや表現力も滴るほどに豊かなのではないかと思っている。「夜の歌」「朝の歌」「愛の挨拶」「気紛れ女」「マズルカ」と、誰でも知っている有名どころは全て網羅されているが、やはり聴きどころは「ヴァイオリン・ソナタ(Op.82)」であろうか。特に第三楽章のロマンティックな躍動感、中間からの一気に花開くような艶やかさにはぞっこん惚れこんだ。97年の国内ホールでのデジタル録音。コロムビア再発廉価盤。

Spalax 14922
Cyborg/Schulze, Klaus
73年の二作目。95年の再発spalax盤、6面デジパック。ジャケはこれがオリジナルらしいが、73年当時は2LPでのリリースで、国内には酷く想像を掻き立てる冷やっこい絵柄のBrain盤が出回っていた。LPの片面1曲構成の計4曲、計約100分。チェロx12、ダブルベースx3、ヴァイオリンx30、フルートx4なる編成のコズミック・オーケストラとの共演という体裁だが前半で聞こえる肝心のオケの音は徹底して音響処理されていて、クラシカルな生音は完璧に封印されている。前作ほどアグレッシブではなく、淡々としながらも冷涼、あるいは極めて虚無的な音響が延々と押し寄せて、サイケ風のギミックと変調電子音が彩りを添えるという、およそ所謂“音楽”とは縁遠い音響ではあるのだが……、この全ての感情を排し、極限にまで青灰色に侵されたような冷たさが実に心地良い、と言ったら多分人間としては拙いのだろうな。
主題は『サイボーグ』すなわち、「サイボーグ、それはあるひとつの電子的に構成された存在であり、千年の命を持った音響的精神薬理学の愚者たることを待ち望む(超テキトー訳)」ということらしい。個人的に初期シュルツェの世界はイヴ・タンギー(Yves Tanguy:1900-1955)のスュルレアリスムのイメージを髣髴とさせる。澱んだ水銀の海底で微細振動と相互共鳴にピチピチとたゆとう無機と有機の純粋合成異物にして見果てぬ夢の残骸は、あくまでも不透明で圧倒的に孤独だ。

Vinyl Magic
VM010
Il Sogno/Zauber
Zauberは“ツァウバー”でおそらくドイツ語の同じ単語を意図して、「魔法」、あるいは「おまじない」、「魅力」といった英語のcharmに相当する語なのだろう。78年の1stアルバムということで、時期を見誤ったかなり後発の部類といえる。おそらくこれ一作で消散したのだろうが、90年代に復活して以後現在に至るまで、忘れた頃にぽつぽつと数作のアルバムが出ているようだ。ドイツ語の楽団名を冠しているものの、構成員は名前を見る限りイタリア人で、歌詞もイタリア語、音も紛れもない北イタリア(トリノ)伝統の端正で上品な70年代リリカル・プログ。
主唱の女性以外にピアノ、フルートが女性で、更に鍵盤、ベース、ドラムの男3人が加わりながらも全員が鍵盤やアコギを弾いているという若干変則的な編成であったらしい。タイトルは『夢(ソンニョ)』。「バッハのワルツ」ではじまる全10曲。歌なし7曲とそれなりに意欲的。アンサンブルは荒っぽさは皆無で丁寧かつ安定してまとまっている。派手さや仰々しさははなく、(90年代のリマスターとはいえ)録音も古くよろしくないが、センス良くまとまった隠れた佳作。
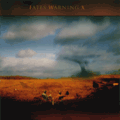
Metal Blade
3984-14500-2
FWX/Fates Warning
タイトルFWX=Fates Warning Xで、その名の通り10作目のアルバムを表す。隅々まで行き渡った抑制、緻密で完璧なアレンジとそれをこなすアンサンブルは益々極まって、前作『Disconnected』を凌駕しているといえよう。最小限のトリオ編成だが太鼓奏者は今作限りと事前に公表されている。
虫の音に被る生ギター、着陸する航空機の騒音が周囲を圧して、やがてメタルなリフに引き継がれていく導入部の臨場感は秀逸。更に、コンセプト・アルバムというわけではないが、中間部はかなり意表を突いた仕上がりになっている。複雑な展開と転調、無調に近い(敢えてだろうが)極めて憶えにくいメロディと重くのれないリズム。そしてもちろん、暗い。底なしの闇とは異なる、曇った冬空のような硬く厳しく冷たい暗さ。アルバム毎に加速度がついて地味に、暗くなるなぁ(笑)。今回は鍵盤の使用も控えめで、シンプルさを装いながらも凝った意匠がさり気なく提示されているのだが、構築された伽藍は堅固にして隙がない。のたくるような苦悩と抑鬱、堅固な意思とぶれない志向、この捉えどころのない調の音圧にとっぷりと浸かっていると、削りだしのステンレス素地板に押し付けられているような痛みすら感ずるようだ。一部、無調に走ったところが賛否の分かれ目にして下手すりゃ存続の瀬戸際だろうが、個人的にはその意欲を買いたい。ちなみに現時点(2008年秋)での最新作。
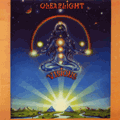
Clearlight Music
C8M-105
2000
Visions/Clearlight
クリアライト4作目にしてフランス時代のラストと思われる。英Virginに切られ、当時3作目以降の情報は完全に途絶したが、フランスでは細々とリリースが続いていたのだろう。極めて西洋人的な薄っぺらい東洋神秘思想への安直な傾倒ぶりが鼻に付きだしたのもこの頃か。すべてインスト、全6曲にボーナス7曲で倍に膨れ上がった2000年の再発リマスター。エンハンスドCDだが自Webと繋がらないリンク集のしょぼい画面が出てくるだけで敢えて見るべきものはない。
今ひとつ時流に乗れず、おかしな方向に逸れてしまったが、首領ヴルドー(Cyrille Verdeaux)の曲、アルペジオ・ピアノもZNR三人組の中では音楽的にいちばんまともな質を持っているといって差し支えはないだろう。冒頭「愛の螺旋」の喘ぎ声の安直さには先が思い遣られたが、ディディエ・ロックウッド(Didier Lockwood)のヴァイオリンとディディエ・マルールブ(Didier Malherbe)のサックスの競演はスリリングで、繊細に絡むブーレ(Christian Boulé)のギターも聴かせる内容を持っている。印象派の末裔のようなピアノとアンビエント・ミニマルが渾然一体となって奏でるゴング風の迷宮絵巻は思いのほか清冽で、万華の色彩感を醸し出している。大枠以外はほぼ即興と思われるアレンジもテクニックに裏付けられて聞き込むほどに味が出るじゃないか。久々に聞き返して、再認識した次第。
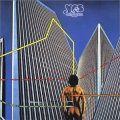
Elektra/Rhino
R2 73793
Going for the one/Yes
31年前、初聴時の感触が悪くてその後長らく興味を持てなかった7作目くらい? ジャケ絵もロジャー・ディーンからヒプノシスに変わり、時代の趨勢に合わせたイメージ・チェンジの涙ぐましい努力も安直な妥協にしか思えなかったのは、今思えば若気の至り。数年前にライノのリマスターが出たので、ようやく聴き直す気になった。今風の国内受けしそうな不自然な音質改悪がない上に、全5曲に+7曲(うち4曲が未発表音源)のボーナス付で言うことなし。
前作『継承者』の新任鍵盤、モラーツは製作中に遁走した模様で、ウェイクマンが返り咲き。ということで黄金期の再来なわけだが、世相なのか、ドラムの音を明るく軽くパタパタにした結果、芯のない不透明な音像になってしまって締りがない。曲は大作1曲を除いて比較的コンパクトにまとまり、リズミカルな部分とメロディアスな部分を交互にバランスよく配置しているあたりはいつものイエスなのだろうが、構成の綻びを力技のアレンジでカバーするような部分も散見され、斬新な才気に乏しく、自己陶酔的なコテコテの厚塗りと香水垂れ流したような粉飾には腰が引けてしまう。この違和感は時代なりに弾けようと努力している曲調とあくまでクラシック基調のウェイクマンの職人鍵盤の齟齬だと考えているが、長らく付き合ってきたエンジニア兼プロデューサ(Eddie Offord)の手を離れたあたりで、フレームワークが崩壊し抑制が効かない部分もあったのだろう。タイトルは『ひとつ(の何か)を追い求めて』といった意味だろうが、概ね肯定的な内容で方向性としては良かったのだろう(ね?)。
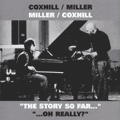
Cuneiform Records
Rune 253/254
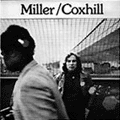
LP-1973
2007
Lol Coxhill & Steve Miller - [complete works]/Miller, Steve + Lol Coxhill
1973年のコラボ名作『Miller/Coxhill(裏返すとCoxhill/Miller)』に翌年の『The story so far.../...Oh really?』、中間に未発表曲やライブを加え、2007年になってようやくCuneiformからリリースされた待望の初2CD。初めて聴いたのは76年ごろか。カンタベリ・オタクだった友人にLPを借りて、当時、唯一の手段だったカセットテープに録音した。一聴して虜になった。聴き過ぎてテープが切れて、何度も借りなおして録音しなおした記憶が残っている。うち2本が残り、15年ほど前に1本切れて、今手元に残るのは79年に録音したもの。経年変化も加わって左右のバランスは滅茶苦茶だし、音はこもるしで今のレベルからすれば聴くに堪えないが、ときおり棚の奥から取り出してはデッキにかけていた。
当時はコピーなんぞも個人でホイホイ使えるようなものではなく、カセットのケースには手書きでクレジットを書き写しているのだが、筆跡を見ると30年の時間を挟んで基本的にこの頃から進歩していないんだなと思ってしまう(笑)。
スティーブ・ミラー(故人)はハットフィールズのフィル・ミラーの兄で、元デリヴァリィ(Delivery)から『Waterloo lilly』期のキャラヴァンへと渡り歩いたピアノ奏者。コックスヒルはケヴィン・エヤーズ(Kevin Ayers)のホールワールドにいた現音+ジャズ管楽器奏者。
管楽器とピアノだけのアンサンブルに加え、ミラーの曲では弟のフィル・ミラー、バスの“リチャシン”、ピップ・パイルのドラムが加わり、実質的にそのまま名前を変えたのが初期ハットフィールズということになる。オルガンやムーグを用いずに、ほとんどスタンウェイやブルスナー(Bluthner)の生ピアノだけで構成された繊細な色彩の淡さ、即興の荒さと自然さ、しっとりとした空気感を漂わせるA面3曲の流れは悩殺絶品を通り越して、平伏すしかない。後半(LP-B面)はコクスヒル主導の即興アヴァン・ガルドにしてフリー・ジャズというの? 二作目との中間に挿入されたライブ音源や後のハットフィールズの原曲も興味深い。個人的に極めて思い入れ深いものがあるが、カンタベリィ音楽のコアというか本質を余すところなく表現した一枚といって差し支えないだろう。

Blueprint
BP246CD
Mainstream/Quiet Sun
誰もが知っているわけではないが、知っている人なら誰もが評価する、いわゆる「名盤」というもの。中弛みの1975年リリース。フィル・マンザネラ(Phil Manzanera)のソロ『Diamond Head』の合間を縫って録音された発展系にして、70年代初期のクワイエット・サン結成時の回顧的意欲作。情報のない当時ですら、印象的なジャケと共にそれなりに話題になっていたと記憶している。This Heatのチャールズ・ヘイワード、Roxy Musicのマンザネラ、カンタベリの人;ビル・マッコーミック、鍵盤のみ前歴不明なデイヴ・ジャレット(Dave Jarrett)によるコンプレクスにEnoが参加という形態。演じるはスリリングでちょっとギクシャクし、ノイズっぽい前衛風味を湛えながらもリリカルさを失わないジャズ・ロック。初期ソフト・マシンの職人的継承者にして、より有機的(ポップ)になった“801”、より無機的(ノイズ・パンク)になった“This Heat”の原型と捉えることもできるか。堅実なミドルクラス風英国趣味の上に横溢する斬新なインテリジェンスはカンタベリィ愛好者の嗜好をくすぐったものだ。
ヘイワードやマンザネラのクールな賢さとは趣が違う、唯一、リリカルな部分を担っているともいえるジャレットの鍵盤のしっとりとした瑞々しさが気持ち良い。冷徹な技巧と奇数変拍子の饗宴に埋もれかかった可憐な徒花か。全7曲ほぼ歌なし。ヘイワードといわれる歌は下手糞だが、場をわきまえて雰囲気を壊すほどではない。
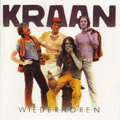
Fünfundvierzig 105
Wiederhören/Kraan
サックス+鍵盤の5人組からサックス担当が一時帰休した6作目。超絶テクには益々磨きがかかり、爆速変拍子が稠密に唸り捲くるアンサンブルにはもはや呆れる外はなく、中近東ジャズロックフュージョンひょうきんポップでありながら、鍵盤のインゴ・ビショフ(Ingo Bischof)の繰り出す摩訶不思議で幻惑的なフレーズが例えようのない煌びやかな浮遊感を作り出す怪作にして快作。ヘロヘロに弛緩した歌や妙にかったるい大人の曲調も滑稽洒脱だが、「フォルガス・アホイ(Vollgas Ahoi:ひゃっはー・全速力w)」に代表されるそのまんま全楽器問答無用の弾き捲くりの馬鹿テク疾走大会も、裏を返せばいやにクールで生真面目、かつ緻密に練り込まれたアレンジであるところがドイツ人的職人芸。それでいて、タイトな曲調は概ねポップで歌無しでも歌えそうな聴き易さはなかなか希少な部類に入る。CDは2000年のリマスター。音質は良い。
ドラム奏者ヤン・フリーデ(Jan Fride)最後(といいつつ、やっぱり後に復帰)のアルバムということで『さよなら』というタイトルなのかどうかは知らない。ちなみに、「さようなら」は普通の場面ではauf Wiedersehen(再び+見る)だが、電話やラジオでは「聞く」という意味のhörenを使って「再聞」と表現する。ん、まぁ、そういうことか。
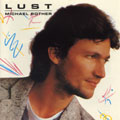
Random Records
398.6584.2
2000
Lust/Michael Rother
ローターのソロ5作目。タイトルは『歓喜』の意。フェアライトのコンピュータ・システムを使った最初の録音で、ギター以外はすべてサンプリングと思われる個人宅録のようだ。ギターからシンセ主体への移行期ともいえ、今聞けば当時のディジタル機器の安直なチープさ加減はどうしても免れないが、使いこなしは上出来で25年前としては画期的ともいえる斬新さであったであろう。手法は既に過去のものではあるが、シンプルだが流麗かつ甘美で心地良いメロディとリズムという音楽としての魅力は今も尚輝きを失わない。前後作のなかでは曲の出来も最も良いだろう。派手さや劇的な展開とは無縁な人ではあるが、冒頭「椰子の庭」やラスト「脈動星」のように、微妙なノイズを織り交ぜながらも、しっとりとした暗い夢見心地の表現には類稀なものを持っている。
全6曲インストに94年のボーナス3曲を加えた2000年の再発リマスター。90年代の曲は、さすがに隙がない。
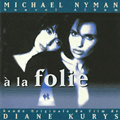
Virgin Venture
8399492
À la folie/Michael Nyman
映画『À la folie』(“熱烈に”“夢中になって”といった意。邦題:『彼女たちの関係』)のサウンドトラック。曲は92年の『The Piano(邦題:ピアノ・レッスン)』のヒット以来、引く手数多で知らない人はいないほど著名になった現代音楽の立役者ナイマン。残念ながら原盤は既に廃盤のようで、現在は『6 days, 6 nights』と英タイトルになって再リリースされている模様。音源は未所有で90年代末期に友人から借りたもの。時折思い出して原盤を探しているのだが、見かけない。
狂気を秘めたロマンチックな主題が展開されていく全16曲。11曲目はハーパー(Roy Harper)の「Another day」みたいだが、他は全編ほぼ弦楽ミニマル。不協和音ぎりぎりのアンサンブルが狂気と熱情を煽り立て、追い込まれるような切迫感と突き上げるような情念が迸るわりには、極めてリリカルにして流麗。はっとするほど可憐で響きのよいメロディとリズムが満載である。演ずるはナイマン(ピアノ)+16名編成(弦9+管6+電気ベース)のマイケル・ナイマン・バンド。ちなみに映画はディアーヌ・キュリスのおっかないというか、後味のよろしくない愛憎劇。