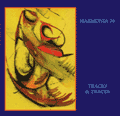
Rykodisc
RCD 10428
Tracks & traces/Harmonia 76
1976年にイーノが渡独して初めてハルモニアとコラボレイトしたときの発掘音源。翌年の『Cluster & Eno』の原型であり、後にイーノが提唱することになるアンビエントなる概念を実践したもの。76年にForstのハルモニア・スタジオで録音された。20年後の97年リリースですが、ジュエルケースではなくて、妙に安っぽいポリプロピレン系プラスチックのスリーブ一体型ケースに収納されている。ジャケ絵はマネージメントを務めるローデリウス夫人によるもの。
ハルモニアということからもわかる通り、後のコラボレイト作品には加わっていないローター(Michael Rother)が地味にギター、キーボードを弾いておる。リズムマシンの使いこなしはノイ! 譲りでもあるわけで、ローターの貢献度は非常に高い。「Almost」「Les demoiselles(未婚の婦人たち)」「Trace」等、後半の絶妙に枯れた曲の出来が素晴らしい。
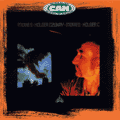
Spoon
CD 35
Movies/Holger Czukay
「プールで一緒に涼もうよ」って、アイスクリーム・ソーダが食べたくなるチュカイのソロ。とはいっても、シュミット(Irmin Schmidt)、リーベツァイト(Jaki Liebezeit)、カローリ(Michael Karoli)+コニー・プランクと実質カン以外の何ものでもないわ。有名なのはもちろん「Persian love」。エスニックに軽やかに刻まれるルンバのリズムとコーランのサンプリング。個人的にペルシャといえばゾロアスターだと思うが、イランと考えればシーア派イスラムだから、まぁ、いいのか。内容的には現代でも全く遜色のない高度なコラージュとサンプリングによるプログレッシブな音響テクノ。でも恐ろしくポップでファンキィで諧謔たっぷりなところがチュカイの真骨頂なわけで、人を食ったおっさんぶりは相変わらずです。

PSEUDONYM
CDP 1015DD
Beyond expression/Finch
前作よりもこなれたのは当然としてもより一層メロディアスにリリカルに深みが増した二作目。フィンチの場合、音以外には言及する意味はないのだろうが、目を背けたくなるジャケのだささは相変わらず。「言葉では言い表せない/なんともいいようがない」というタイトルが表す通りの全三曲オール・インスト、抑揚のバランスが華麗さを惹きたてている。ほぼ完璧なアンサンブル志向でギターはナチュラルだし想像以上におとなしいのだが、伸び伸びとした気持の良い音だ。非常に緻密な展開で長曲をこなす構成力も並でないことは一聴してすぐわかる。キーボードの出番が増えてきちんと間をとった上品さも感じられる。昨今のハードプログのような聴く側のレベルに合わせたワンパターン・ロックに陥らない賢さは(昔のだから)当然として、しかしこのニムヴェーゲン、繰り出すフレーズがこてこての演歌調でおもしろい。
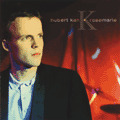
Polydor
543 074-2
Rosemarie/Hubert Kah
82年から84年にかけての初期音源からピックアップされたコンピ盤と思われる。スリーブの如何にもゲルマン面をしたあんちゃんがフバート・ケムラー(Hubert Kemmler)というのだろうね。どうでもよいけど。初期ものということで歌詞はドイツ語、ギターなんぞも若干煩くない程度に入っていたりして微笑ましい。極めて適切に加工された気持の良い音に、囁くような独特の甘々声がふわふわと漂っておりまする。ノイエ・ドイッチェ・ヴェレの一翼として、元々ローカルな一般人気はそれなりにあったそうですが、そのあたりも頷ける内容になっているでしょう。個人的には後期の黄昏エレ・ポップが好みだったのですが、地声でぶんちゃかぶんちゃかしてる軍楽隊のマーチ「Radio」とかも良いではないかと思い直しているところ。96年にケムラー一人ユニットで再開されて二枚ほど新作が出ているようです。

Mellow
MMP 132
Dietro l'uragano/Alphataurus
メロウ(Mellow Record)の発掘物で、1973年録音の全部で30分強の2ndアルバム用の音源らしい。リマスターされているらしいが音はあまり良くない。音質に若干差があるのでデモ音源も含まれているのだろう。元は赤井で録られたモノラル音源だそうです。1stで歌っていたこってり系の専任ボーカルは写真はあるものの、クレジットからは名前が消えている。最後の曲に少しだけドラムが兼任しているボーカルが入っていますが、自信なさげだし叩きながらは歌えないようだ。1stよりも展開は一層凝ったものになり、目まぐるしい転調をそれなりに達者なテクで支えている。特にドラムは手数の多いテクニカルな印象で1stのバタバタ感とは随分趣が違う。ラストの大曲でリリカルに発散する怒涛のストリング・シンセのこてこてぶりは相変わらずで、妙に安心した。

Columbia/Legacy
CK 85481
Tyranny and mutation/Blue Öyster Cult
今風に云えばメタル(な雰囲気)が確立された二作目。決して奇を衒っているわけではないし、それだけの才もないだろうが、建築的な構築性が彼等なりの美学になっているのだろう。LPはA面をRed side、B面をBlack sideと呼んでレーベルの色も塗り分けていたと思った。一曲目が「赤と黒」なのだが、その意味するところはカナダの騎馬警官らしい。もっともその文学趣味に長けた裏には、赤=軍人、黒=聖職者(逆に捉える解釈もあるらしい)というスタンダール(Stendhal(ペンネーム);1783-1842)流の解釈がこめられているのだろう。だっさい銀色のマントなどを背負ってひどく滑稽としか思えないのだが、当時は如何にもな過剰な演出が受けていたのだろうな。
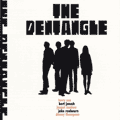
Castle
06076 81120-2
The Pentangle/The Pentangle
トラッドとジャズ・ブルーズの境界領域に派生した五芒星のデビュー盤。シリアスな緊張美と骨格の美しさは他に類をみない。それなりに著名だったフォーク+ブルーズのギターにダブルベース+ジャズ・ドラム、トラッドの歌姫と無茶苦茶な構成ですが、極めて高度なアンサンブル+インプロを繰り広げています。
フェアポートと並び称されることもあるが、電化トラッドに走ったフェアポートに比して、五芒星はアコースティック・ラジカル・トラッド、というのだろうねぇ。70年代に入って解散しましたが、10年ほどで復活を成し遂げ現在も続いておりまする。初期のステージの雰囲気なんか、実は大きな声では云えないがヘンリー・カウ(Henry cow)と似ているなぁ、とか密かに思っていたりするのだ。ジャッキー・マクシー(Jacqui McShee)が止まり木のような背の高い椅子に座って、両膝にきちんと手を揃えて置いて歌っているのが印象的です。
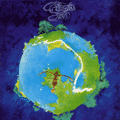
Waner/Atlantic
20P2-2052
Fragile/Yes
安売りに負けてライノのリマスターを3枚ほど買ってしまったのだが、『壊れもの』は忘れた。日本人向けには音圧だけ上げておけばリマスターで通っちゃうのだろうが、ここのレーベルのアナログのイメージを損なわないで、かつ明瞭度を上げる仕事は優れものだ。良いエンジニアを抱えているのだろう。再発だから当たり前といえば当たり前だが値段も合理的だし、スリーブもアメリカ人の仕事とは思えない繊細さにびっくり。
首にしたトニー・ケイの代わりにウェイクマン(Rick Wakeman)を迎えた全盛期の始まり。クラシック風の早弾きフレーズの頻発が日本人好みらしい。アンサンブルで聴かせる『3rd』と『Close to the edge』に挟まれてアルバムとしては意外に散漫なのだが、演じる方も聴く方もそれなりに思い入れの詰まったアルバムなようです。まぁ、可能性をとことん追求してみました的な意欲は素晴らしいし、それを実現するテクも(特にリズムセクションは)文句なし。オルガン系のケイに比べ、ピアノ教師ウェイクマンの端正な音使いで爽やかさと透明度が上がった。
昔はそれほどめだった記憶はないのだが、最近のポップ歌謡の相も変らぬロック風のリズムを聴いていると、改めてイエスというのは画期的だったのだなぁと改悛いたす次第であります。
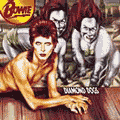
RCA
APL1-0576
Diamond dogs/David Bowie
ジョージ・オーウェル(George Orwell;1903-1950)の『1984』が元ネタ? になっているらしい初期の代表作。時代背景を鑑みれば政治的な意図がないとは云えないが、徒党を組むとロクなことがないというのは昔も今も全く変わりはない。個人的には『動物農場』の方がリアリティを感じるかな。結局この手の未来小説はその年をはるかに越えても、越えなくても結局人間の歴史を描いているに過ぎないのだが、社会と云うものはある時点を境に誰も望まない方向に変質していくもの。かつて辿った歴史の繰り返しなのだが、そのあたりが遺伝子に組み込まれた種としての限界なのだろうな。
ほぼコンセプト・トータルなアルバムですが、LP A面の流れが好きで「Rebel rebel」の頽廃的で格好良いリフにとどめを刺されたのだった。
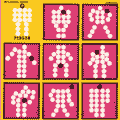
Waner
WPCL-603
In a model room/P-model
70年代末期、ドイツの先駆者の影響下に産声を上げたテクノ(というかエレ・ポップ)御三家の一つP-Modelの1stアルバム。P-ModelというのはPerson Model、すなわち“人型”の意なのでしょうか? 詳細不明。御三家の残りはヒカシューとプラスティックスだっけか。もっとも当時、平沢進はテクノと言われることを極度に嫌っていたそうですが、最近はもうどうでも良いみたい。かったるく暗鬱なものからピコピコ・ダンサブルまで千差万別ですが、元プログ楽団だっただけあって他の二者に比してさすがに楽曲の出来は抜きん出ていたように思う。微妙にチープに諧謔的でメイン・カレントとは距離を置いた差異化は“照れ”の裏返しなのだろうね。
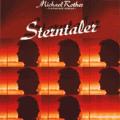
Random Records
SPV 084-26122 CD
Sterntaler/Michael Rother
コニー・プランクとの共同プロデュースによるソロ2作目。カンのジャキ・リーベツァイト(Jaki Liebezeit)のハンマー・ビートが聞けまする。名前の下に『Flammende Herzen』と記載されているように前作の続きでしょう。映画自体は見ようと思っても見れるようなものではないようで、あらすじくらいしかわからんな。CDはLPの6曲に93年の新曲とリミックスが計3曲。全曲インスト。
- 1;「Sonnenrad」
- 卍(まんじ)、日輪 吉祥 太陽が光を放つ状態を象形化したもの 右回転の卍(これは左回転)が正字とされる。う~ん、絶品ですね。明るい光の中でどんどん躰が溶けていくような恍惚。
- 2;「Blauer Regen」
- 青い雨 濡れそぼる雨音のようなギター。ノンビート。
- 3;「Stromlinien」
- 流線 格好良く気持良い鼕々とした透明な流れ。
- 4;「Sterntaler」
- 星のターレル(プロシアの銀貨) 英語風にいうならStar dollar。星条旗のドルを引っ掛けている?
- 5;「Fontana di Luna」
- 月の噴水 銀色に輝く。鉄琴の音が気持良い。
- 6;「Orchestrion」
- オルケストリオン(巨大な音楽機械) メジャーコードが冴えるギター・シンフォ。大団円。
- 以下は追加音源。
- 7;「Lichter von Kairo」
- カイロの灯り 広漠なアンビエント感漂う打ち込みとキーボード。
- 8;「Patagonia Horizont」
- パタゴニアの地平線 パタゴニアの印象? 冷たい透明感に翻弄される。パタゴニアはアルゼンチン南部の寒冷強風不毛地帯を指すのでしょうが、一度行ってみたいところだな。
- 9;「Südseewellen」
- 南洋の波 ゆらゆらと揺られ、いつのまにか固有振動数が同期してとりこまれてしまう液相の感触。
典型的な西洋人だろうに、昨今の同朋よりはよっぽど感覚的に近しいものを感ずる。節度ある的確な佇まい。「もののあはれ」というよりは「いとをかし」
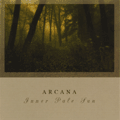
CMI 121
Inner pale sun/Arcana
スウェーデンはアルカナの4th。俗に云うゴス・アンビエント。GothはGothicの省略なのだろうが、元々はロマネスク以後、ルネサンス以前の200年程に流行っていた様式で、初期は北イタリア、北上してフランドル、ネーデルラントに至る。後期ゴシックの画家としてボッシュは昨今富に有名だな。建築的にはやたらに尖がらせた縦長デザインが偏重され、その一歩でも天に(すなわち神に)近づこうとする結果としての荘重さが特質です。とはいえど、何のことはない。ゲルマンは元々ゴートと云われていたわけだし、ローマ人に云わせれば、ゴート人のように野蛮で卑しいのがゴティックなのだからただ単に地をいってみただけなのだろう。「ゲルマンの深い森に分け入る神秘」みたいなキャッチフレーズが付きそうですが、我々が縄文回帰して銅鐸引っさげて土偶踊りでもしているようなものである。音楽に(あるいはその他の事物に)癒しを求める(た)ことはないので、ヒールなどと云う概念は健康食品みたいなものだろうとしか思えませんが、この暗い美しさには本能的に食指が動きます。
もちろん、先駆者としての80年代デッド・カン・ダンスの影響はあまりにも大きい。
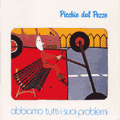
KICP
2841
Abbiamo tutti i suoi problemi/Picchio dal Pozzo
ポッツォの2ndは1stよりもアヴァン・ガルド。変拍子の連続と無調なメロディが、いつの間にか可愛らしい綺羅ゝ感にするりと入れ替わる。それでいてさらりとした暖かめの手触り感は他に類のない、聴けば聴くほど味がでる恐ろしく高度で奥深い突き詰めた世界が堪能できまする。1stで僅かに感じられたリリカルさもどこへやら、ジャズではなくて現代音楽系へのシリアスな傾倒ぶりは、デダルスと同じく北イタリア未来派に繋がる系譜に思う。左翼インディ、ロルケストラからのリリースで大手からは相手にされず4年も間隔が開いてしまったのだろうなぁ。「彼の抱えるありとあらゆる問題」についての省察が行われているのだろうが、歌詞はついていないし、多分あっても内容的にお手上げの雰囲気。

Virgin Dischi
SpaA 0 0777 7 88071 2 4
Semplicità/Matia Bazar
マティア・バザールの3rdアルバム。タイトル通りの純朴さ。アントネッラ・ルッジェーロのボーカルが後期ほどは目立たなくて、まだ自らの魅力を確立し切れていない部分はあるにせよ、十分に創意と工夫が相まって高質なポップに仕上っているとは思う。J.E.T組が歌っているのもあったりして興味深い。曲作りの巧みさは定評があるが、ルッジェーロのハイトーン・ボーカルは「È così(それがどうしたの)」あたりでようやく聴ける。総じてかなり凝った音作りで、このあたりはJ.E.T+ムゼオとしてのプライドだろう。個人的に強烈な新鮮さで衆目を集めるのは80年代のロベルト・コロンボ+エレクトロ・ポップ時代だと思うのだが、この頃も伸び伸びと豊かで気持良い。
♪♪オッキ グランディ コム イ~マーレ♪♪(海のように大きな目だね)
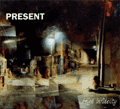
Carbon 7
C7-058
High infidelity/Présent
泣く子も黙るプレザン、現段階での最新作。「ジャキーン」「ブシュ」「ドサッ」と首切ってるわい。「売りに出された魂」「クリスマスにストリキニーネを(副題;サンタ・クロースの真実)」「鉄の夢」全三曲。相変わらずのプレザン節ですが、とうとう自ら無信心ものであることを曝け出してしまいました。なんとも冒涜的なタイトルですね。暗闇に赤基調だったふつふつと滾るようなベースカラーが、冷たく青く冴え渡る透明感に変転しつつあるようにも思う。強迫複合変拍子ポリリズムもエネルギッシュというよりは昨今のユニヴェール・ゼロを彷彿とさせる緻密でシリアスなものに近づいた。 金管の大胆な導入と、ピアノ、チェロの優美な絡み、これでもかと崩しまくる変態リズムを叩くカーマン(David Kerman)のドラム、そしてもちろんアンビエントなトリゴー親子のロングトーン・ギターと文句のつけどころのない格好良さ。
ユニヴェール・ゼロのキーボードでもあったピエール・シェヴァリエ(Pierre Chevalier)による静謐なメロトロンが冷やっこい。
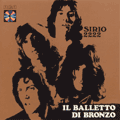
RCA
ND 71819
Sirio 2222/Balletto di Bronzo, Il
青銅バレエの1stアルバム。まぁ、70年、それも辺境のイタリアだからそれなり。2nd以降(というか昨今は別として『YS』だけだけど)の中心人物であるジャンニ・レオーネ(Gianni Leone)が不在なので実質別物といってよいでしょう。「シリウス2222年」というSF風のタイトルもどこを探しても歌詞がないのでお手上げ。2ndの歌詞は見つけたのでそのうち根性入れて調べてみようね。フォルムラ・トレの初期を思わせる重量サイケなのだが、それなりに達者でクリームあたりの影響と若干ブルーズ色が感じられるかもしれない。弦楽器とチェンバロによる「Medeitazione(黙想)」、アコースティックな民族調「Missione sirio 2222(2222年 遣シリウス使)」あたりが大方の琴線に触れるところであり、突然変異の前兆なのだろう。