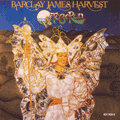
Octoberon/Barclay James Harvest
「Suicide ?(自殺?)」
私はふと気づいて目を覚ました
ベッドの片側は既に冷たかった
君は夜明けと共に行ってしまった
今、私の目には涙だけが残されている
私は空っぽの感情と共に起きあがった
歩道の騒音と心の静寂の中に
その朝、私は歩み出した
名もない男として通りに降り立った
“敗者”という名のクラブへ向けて
跛になってしまった犬のように
クラブのエレベータに乗って見晴らしの良い階に昇る
私は生涯会員-名前の抹消がクラブのする唯一のことだ-を返上したのだ
私は手摺を乗り越えた
下を歩く群集がゆっくりと後ずさるのが見えた
叫び声が聞こえた
「ちょっと待て! 車を動かすから」
肩を押す手を感じて
「さぁ、時間だ」と叫ぶ声が聞こえた
鋭い一押しを感じて
からだが空気を切り裂いた
歩道を全身で受けとめて
そして一体となった
リリカルで優しくも美しい曲が微かにフェイドアウトしていく。中身は実はとんでもなく黒い。曲とクロスフェードしてこの歌詞の実況が始まる。ベッドから起き上がり、着替えて外に出る。クラブ(ミドルクラス以上の主として男性が所属する社交団体)へと向かう靴音。歩道のざわめき。クラブの扉を開けて、一言三言。エレベータの蛇腹扉、電動モータ。屋上へ出ると靴音の反響が変わる。「Just in time」の一言の後、落下音と叩きつけられる音。
70年代中期の安定感と完成度の高い逸品。コーラスやオーケストラの入れかたもツボを押さえた必要十分で的確なものになっている。非常にこなれたプロっぽさで破綻がまったく感じられない。エンジニアにマンダラバンドのデビッド・ロール(Davie Rohlと記載されている)の名前がみえる。
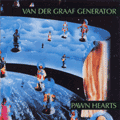
Pawn hearts/Van der graaf genarator
四作目にして第一期のラスト。75年に『Godbluff』で復活するまで、一番肝心な時期に存在しなかったことが、何とも云いようのないマイナーさ加減を生んだと思われる。全三曲と長もの好きには堪えられない趣向と、シリアスで学究的、構築主義的で緊張感溢れる楽曲は神々しいまでに完成度が高い。重暗さに射し込んだ一筋の燭光とか祟高とか荘重、厳粛などというのがVDGGを評するときに用いられる代名詞みたいなものなのだが、一つの想として教会音楽や宗教曲との類似性を狙ったと思われる。音楽性もハミルの声も類型的なそれらとは全く異なるものだが、やっぱり福音に聞こえてしまうのだ。どちらかといえばハミルの世界観は非世俗的かつ非宗教的で、超越的な自然性みたいなものへの希求と、その下での人間性の関連にあるような気がするが、皮相的でなく哲学的過ぎてよくわからん。
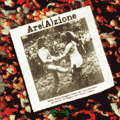
Are(A)zione/Area
正規ライブ盤。油が乗りきった時期のテンションの高さに圧倒される。アレアはライブ楽団なのだよねぇ。短いことを除けば録音もまぁまぁ。
ラストの曲はおそらく定番だったと思われる「L'internazionale(インターナショナル)」で、アレアはインスト曲として演奏しています。もちろん、フランス人であるピエール・ドゥ・ジュイテール(Pierre de Geyter)作曲(1888年)、ユジェーヌ・ポティエ(Eugène Pottier)作詞(1871年)の「L'internationale」が原曲の労働歌。その後、露語訳(1902年)、日本語訳(1922年):佐々木孝丸・佐野硯 訳詞を経て日本にも入ってきた、パリコンミューンを起源として、ロシア十月革命の後にはソビエトの国歌にもなった由緒正しい歌であります。
「L'internazionale(インターナショナル)」 佐々木孝丸・佐野硯 訳
起て飢えたる者よ 今ぞ日は近し 覚めよ我が同胞 暁は来ぬ
暴虐の鎖断つ日 旗は血に燃えて 海を隔てつ我ら 腕(かいな)結び行く
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ ああインターナショナル 我らがもの
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ ああインターナショナル 我らがもの
聞け我らが雄たけび 天地轟きて 屍(かばね)越ゆる我が旗 行く手を守る
圧政の壁破りて 固き我が腕 今ぞ高く掲げん 我が勝利の旗
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ ああインターナショナル 我らがもの
いざ闘わん いざ 奮い立て いざ ああインターナショナル 我らがもの
まぁ、こう書かれても頭で想像するだけで(世代の差は如何ともし難く)正直わからないんですけどね。スリーブ写真は'75年5月30日に行われた青年無産階級の祭典での雨乞い踊りだそうです。冊子もけっこう充実している(仏訳、英訳付)。サックスを手に林檎をかじるファリゼリ(Patrizio Fariselli)に、ミラノの労働者大会での一コマ等々、赤々と燃えていた時代なのだなぁ。歴史というものが構築されていく過程は、過去の事物を現在の視点から見てきちんと評価していくことの上に成り立つものだから、好きとか嫌いとかいうレベルで捨象されることなく、こういったものが記録され、誰でも手に入るように流通しているということは素晴らしいことなのだと思う。
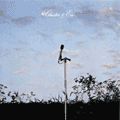
Cluster & Eno/Cluster & Eno
イーノとクラスターの関わりは76年のハルモニアの発掘音源『Tracks & traces』と77年の本作、78年の『After the heat』の三作が存在すると思われる。中でも質的に後のアンビエントに与えた影響の大きさというか、これがそのものといえる原型であろう。前後作ではイーノのボーカル曲まであったりするのだが、ここでは完全にクラスターに呑まれております。儚いまでの色の薄さと最先端の音響環境は、エンジニアリングと共同プロデュースを担当するコニー・プランクによるものだろう。みっしりと隙間なく埋めたてられた今のテクノは、コテコテに塗りたくった油絵みたいに加算するばかりで、とても西洋的で子供っぽいが、ここには無になろうとするための余韻と削ぎ落とされた本質がひっそりと息づいている。
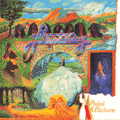
Paint a picture/Fantasy
メロトロン他のキーボードがそれなりに雄大でマイナーなたおやかさを醸し出すメロディ・ポップ。文脈的にはプログとして捉えられていたようだが、基本は60年代ビート・ポップとフォークの延長線上です。くすんだ地味な色合いが如何にも英国風。達者な安定感のあるテクニックで、それなりに作り込まれた質の高いアンサンブルなのだけれど、それを感じさせないさらっと儚げな雰囲気が全編を覆い尽している。ところどころ、はっとするような彩り豊かなメロディが新鮮で、あたかもくすんだグレーの隙間にやわらかなパステルカラーが垣間見えるようだ。未発表お蔵入りの2ndアルバムが、90年代になって発掘されています。

What we did on our holidays/Fairport convention
ボーカルがジュディ・ダイブルからサンディ・デニィ(Sandy Denny)に変わった二作目。同時にアメリカン・フォークへの傾倒からイングリッシュ・トラッドへの転換期でもある。ディラン他のカバーが二曲、トラッドが一曲、他はメンバー作。デニィ作の「Fortheringay」を始めとして、後を代表する佳曲ぞろい。ブルーズっぽいまったりとした曲も大人びてすぐれて快感だ。正にトラッド・フォーク・ロックとしてのフェアポート黄金時代の幕開けにふさわしい。デニィの朗々と響く儚くも寂寥感をあおる声と、しっとりとした堅実なアンサンブルが喩えようのない豊かな渋みを醸し出しておりまする。
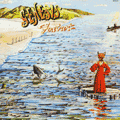
Foxtrot/Genesis
黄金時代にリリースされた4作目にして、次作『英国量り売り』とどっちをとるか甲乙つけがたい良作。中身は諧謔趣味と上流滋味に溢れた怪奇ファンタジィ。当時は冒頭の8分の7拍子にかなり面食らった憶えがあるのだが、怒涛のように席巻されてしまったのは今となっては懐かしい記憶。長曲の構成には粗というか、なし崩し的な展開が目立ち、アレンジの完成度は『子羊』に譲るが、メランコリックなメロディと、「8分の9拍子の黙示録」に代表される奇数拍子を多用した強引なまでの前衛たらんとする心意気は高く評価されるべきだろう。前作から受け継いできた“いかれファンタジィ”路線はここで一応完成をみた。ジャケ絵右の赤い服の女性は狐頭なのだが、ゲイブリエルも狐の被りもので歌っていたなぁ。
まぁ、どうでもよいことなのだが、一度でいいから「Supper's ready. Sir」とかって言われてみたいもんだなぁ。うむむ、マッシュルームがたくさん入ったキドニー・パイが食べたくなってきた。

Walkin' the desert/Ashra
88年にベルリン・プラネタリウムの「砂漠の音」展で行なわれたライブの楽曲をもとに、スタジオ録音し直したもの。ラストの一曲が追加になっている。グートシェンク+ウルブリッヒによるサンプリング・ギターとサンプリング・キーボードのトランス・アンビエント。個人名義の『E2-E4』を除くと前作『Belle alliance』からは9年ぶりのリリース。タイトル通り砂漠をテーマにした叙景的な楽曲で、極めて儚く極めて美しい。特定の形式や歴史文脈に寄り掛かることなしに、一つの音響として構成された、個人的にはAshra名義では最高作だと思う。悠久の砂漠、砂と風の情景がありありと目に浮かぶ基底音にかぶさる詠うようなコーランの朗読。研ぎ澄まされたセンスは人知を越えている。
スリーブの黒はダンスのステップ図のような足跡、赤はピラミッドだろうか。このところの秋の夜長、エンドレスでループさせています。
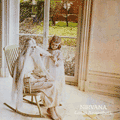
Local anaesthetic/Nirvana
あらかじめ…ですが、ニルヴァーナ違いということで。ちなみに80年代に存在したらしい有名? な方については聴いたことはおろか存在すら知らなかった。検索かけたらやたらヒットするんで、「おかしいなぁ」「そんなにメジャーだったっけ?」と疑問に思ったらやっぱり違った。紛らわしい。後からやる人はきちんと調べて重ならないようにして欲しいものだ。CD探したりするときも本当に迷惑なのだ。
さて、こちらのニルヴァーナは60年代後半から70年代にかけて存在したようで、キャンベル-ライオンズ(Patrick Campbell-Lyons)という人が首領の二人組だった。タイトル『局部麻酔』と白く塗りたてられた凍りそうなジャケ写真(内スリーブ)が秀逸なこの4作目では実質一人ユニットと化しているようですが、LP各面一曲となって、それまでのエレガンスなサイケ・ビート・ポップの趣は完全に捨象された。歌ものやブルーズが適度に散りばめられたごった煮サウンド・コラージュで背景は別としてもファウストあたりに近い作法を感じる。
“nirvana”はそのままサンスクリットのニルヴァーナ、すなわち“涅槃”を意味し、煩悩の炎が燃え盛る情態からの解脱、本能的な精神の動揺がなくなった平衡状態を指す。寂滅、円寂等と同意で現象的には覚悟(つまり“さとり”)の結果(あるいは過程)訪れる状態であるらしい。個人的には惹かれるものもあるし、直感的に想像できないこともないのだが、どうにも“nirvana”などと云われてしまうと居心地が悪いというか気持ちが悪い。事物の総横文字化にみられるように、文化にもあまねくヒエラルキーが導入されてピラミッド化された状況の下では、より上位の文化でラベル化されると本質まで高質化しているみたいで便利なのはよくわかるけどね。

Jumbo/Grobschnitt
75年の三作目。CDはLPの英語盤とドイツ語盤が一枚に収められたお買得盤トータル・アルバム。まぁ、冗談なのだろうがラストには、アウフ・ヴィーダーゼーエン'98(Auf Wiedersehen '98)として将来できるかもしれないロシア語版用の同曲が収められている。トータル・アルバムとしての完成度、曲の出来、テクニック、アレンジ、録音とどれをとっても文句のつけどころのない極みに達している。その上で単なる楽曲の完成度の高さだけでない、旨みというかロマンティックな歌の善し悪しで評価してくれみたいな凄みすら感じられるほどだ。演劇風のコンセプトや曲展開、SEの入れ方はジェネシス風というよりはドイツの古典歌劇にその範をみることができるだろう。独特のユーモアと透明感ある明解さ、シニカルな悲哀感まで変幻自在の表現力に圧倒される。75年にコニー・プランクのスタジオで録音され、翌年ドイツ語盤を録り直し(アレンジも若干違う)て国内リリースしているようだ。
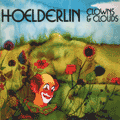
Clown & clouds/Hoelderlin
コニー・プランクのスタジオで録音された新生ヘルダーリンの二作目。前半は変拍子のリリカルでコミカルな歌もの。かなり意表を突く展開が新鮮だ。歌詞は下手糞な英語。後半の長曲「Streaming」、「Phasing」は前作と大きく趣が変わって、曲名通りループするリズムの上を繊細できらきら輝くような軽やかさが疾走する珠玉の人力ミニマル。ビオラと管楽器、エレピとクラビネットによる室内楽的なアプローチが目立つ。軽めでタイト、細かく刻まれるリズムと弾けるようなメロディが生む透明感が他に類をみない。前作でみられた妙な重暗さとの訣別が、良い意味でのオリジナリティを生み出した。
おそらくギターのグルンプコフ(Christian Grumbkow)が描いていると思われるスリーブ絵の水彩画も前作に続き良い味が出ていると思う。
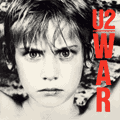
War/U2
既に過去のものとなってしまったが、U2が世界に羽ばたいた出世作。もちろん初っ端の「Sunday bloody sunday」があまりにも有名ではあるが、他曲もそれなりの出来でしょう。中身はそれなりに政治的であったりもするのだが、今思い返してみるとその認識や見識は思ったより甘く表層的でメディアの煽動に乗せられただけのものだ。例えばポーランドにとって称えられるべきはワレサではなく、時代の流れを読んで、ワレサの台頭を弾圧する振りをしながら是認したヤルゼルスキであろうに。当時も今もワレサは指導者の器ではないだろうに。
ということで歌詞は流してもよいのだが、音は歌メロの良さと重量感ある重暗さが如何にもU2なオリジナリティを形作り、悲痛なエレクトリック・バイオリンが冴え渡る。手元にあるのはアナログ盤ですが、プロデューサの見識なのかどうか、わざとざらついたようなレンジの狭い録音が目立つ。本来は西岸海洋性の緯度の割には暖かい土地柄で、ケルトに代表される湿った豊潤さが特徴ですがパンクっぽいカリカリ感を狙ったのだろう。
ライブで「白旗」を掲げてるのは有名だったが、どっちが先かは知らないが『沈黙の艦隊』と「どこにも属さない」という意味では同意なのだろう。「Sunday bloody Sunday」は、一般的には、英領北アイルランドのロンドンデリーでカトリックの公民権デモに英軍が発砲した「血の日曜日」事件を指すものととられ、事実ジ・エッジ(The Edge)は犠牲者の互助に多額の貢献をしているとか、追悼記念館にも関係しているのはWebを漁ればわかる。一方、プロテスタントであるボノ(Bono)はエニスケリンでIRAが起した爆弾テロ(注;ここではIRAが起すものをテロ、英軍、北アイルランド警察、アルスター同盟軍の起すものを鎮圧、取締り、報復攻撃という。もちろん起因する死者は後者によるものが圧倒的に多い)によるプロテスタント住民の殺傷事件を指していると公言していて食い違う。その後、どういう曲折があったのかは知らないが、結果的にかつて一世を風靡したラストナンバーも幕間にエッジが一人で弾き語りするだけというのが定番だったらしい(2000年代は情勢変化に合わせて復活?)。まぁ、時代が変われば思想も変わるし、いわんや個人の思想なんてものは“何か”持ってる気がするだけで本質は気紛れだからね。どっちにしても植民地経営ってのは、するほうも、されるほうも気苦労が多くていろいろ大変だな。ご苦労さん。
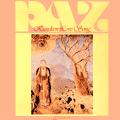
Kandeen love song/Paz
詳細はよくわからないのだが、エスニック・ラテン風ジャズ・ロック。というよりもちょっとロック風のジャズといった方が正確だろう。パーカッションのディック・クロウチ(Dick Crouch)なるお方のジャズ・ユニットのようで、ギターにフィル・リー(Phil Lee)の名前がクレジットされている。他の名前は見覚えがないのだが、演奏を聴く限り完全にジャズの人たちのようですね。個々のテクニックもアンサンブルも申し分ないです。
タイトルにもなっている「Kandeen love songs」は千年前?のトラッドだそう。スリーブはルドン(Odilon Redon;1840-1916 フランス象徴主義の画家)の「Le Bouddha」。 もちろん彼の有名なゴータマ・シッダールタさんのことですね。「The Buddha」なるちょっと神秘的でエスニックな曲が入っております。ちなみに“Paz”はスペイン語(だと“パス”)で“平和”“鎮静”“安らぎ”の意。
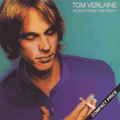
Words from the front/Tom Verlaine
ソロ三作目。タイトルは『最前線からの手紙』という意味らしく、アメリカ市民戦争(?南北戦争のこと?)の従軍者から家族へ宛てたものらしい。他にも「Postcard from Waterloo」なる、こっちはWW1のフランスでマスタード・ガスに怯える塹壕の兵士からの手紙らしい。曲名以外ほとんど何も書いていないどうしようもない廉価盤CDなもので、探しているのだけれど歌詞がなくてようわからん。ゆったりとした曲調のミドル・テンポの曲が多いのだけれど、神経症的で刹那的なボーカルと突き放したようなギターは相変わらず。ベースはTV時代の同僚フレッド・スミス(Fred Smith)。リズムマシン風の単調なリズムの上を、淡々と展開されていくラストの9分に及ぶ長曲「Days on the mountaine」だけ、今までとちょっと毛色が違っているな。
このところ、ちょろちょろと入手不能盤の再発が出始めているようで良かった。ジャケットは写真ではなくて、キャンソンかマーメイドにアクリルかガッシュで描かれたイラスト。
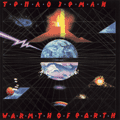
Warmth of Earth/Eduard Artemiev
旧ソ連の現代音楽家エデュアルド・アルテミエフによるトータル・アルバム。極東チュコト族とエスキモーの古伝説を元にした叙事詩みたいなものらしい。解説は英語。Jeanne Rozhdestvenskaya(読めん)というロシア語女性ボーカルと“ブーメラン”というアンザンブルが演奏しているようです。Synthy 1000 という独自開発のシンセサイザの冷やっこい音色と、びっくりするほどタイトなリズム、ボーカルから楽器音までかなり凝った音響処理がなされていておもしろい。怜悧で耽美なセンスとロシアのお母さんみたいなロシア語の響きが北極圏風の絶望的な広漠感に巧くとけこんでいるかな。むしろ西側風のタイトで媚びたリズムに妙な違和感を感じてしまうくらいだな。元々、基礎的な素養が深いせいか、70年代後期ぐらいから他にもゴリゾントとかレイニィ・シーズンとか、それなりに高質でかつ(資本に)媚びなくてもすんだものが転がっているのだなぁ。つくづくロシア語とっておけばよかったと今更ながらに後悔しております。
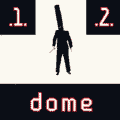
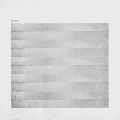
『1』

『2』
1981
1,2/Dome
ワイアの過激志向のブルーズ・ギルバート(Bruce C Gilbert)とグラハム・ルイス(Graham Lewis)によるユニット。ワイアが活動停止した80年から以降、断続的に新作がリリースされています。これは当初、LPで発売された『1』と『2』のカップリングCD。ワイアの経験とは180度正反対の“自然体”がドームの存在理由だそう。う~む、それはそれでかなり問題があるな。『2』の方が若干リズム感があったりもするのだが、ノイズ+インダストリアル+アンビエントへの傾倒が著しく、火の気のない凍りついた透明な風景が寒々しい。身を隠すものなどなにもない真冬の吹きさらしに放り出されたソリッド、あるいは結晶。その冷酷な壊れっぷりというか、異形さはワイアではまだそこそこだった一般受けとは完璧に無縁だろう。
すっぽりと顔を覆う高さ1mもの目だし帽をかぶったこの人たちは“ダグラス兄弟”というらしいが、右手に鋏?、左手にやっとこを握り締めている。なんとなく記憶の底を掠めるものがあるのだがどこで見たのだろう。