あと、エドワードの部分は使われた試しがないそうで、普通はベンジャミン・ブリテンで通ってますにゃー。
そこそこの音楽ファンでないと作品はおろか名前も聞いたことないかもですけど、『青少年のための管弦楽入門』て作品が中学あたりの音楽教材になってるので、聴けば「ああこれか」と心当たりもあるかも。
別名を『パーセルの主題による変奏曲とフーガ』(なんかどっかで聞いたようにゃ)と言って、前半が変奏曲、後半がフーガになってます。
そんな知名度ですから日本語の伝記とかもろくすっぽなくて(この文章書き終わった途端に一冊出たけど)、音楽史の本とかでもイギリス音楽の文脈で1ページくらい割いてればいい方ですにゃ。
なので今回のお話は八割方マイケル・オリバー著の伝記『Benjamin Britten』によるものですにゃー。
今回は、山田耕筰のときに書いた紀元二千六百年奉祝演奏会つながりです。
この演奏会にブリてんが『シンフォニア・ダ・レクイエム』を寄せたもんだから、受け取った日本側で揉めたのは前に書いたとおり。まずはそこに至るところから始めますかにゃ。
●スペイン内戦
ブリてんは学生時代から根っからの反戦主義者というか平和主義者で、それは少なからず師であるフランク・ブリッジの影響によるものでした。ブリッジは第一次大戦で親友を亡くしたりしてるんですにゃ。
1936年4月にブリてんはスペインのバルセロナで開かれた音楽祭、ISCMフェスティバルに参加してます。これが終わってイギリスに帰ってみると、まさにそのスペインで内戦が勃発。ピカソが『ゲルニカ』を描いたアレですにゃ。
スペイン内戦はドイツがフランコ将軍の反乱軍、ソ連が共和国派の人民戦線政府について、それぞれの陣営に義勇軍と称して軍隊を送り込んで介入、戦火を拡大していきました。今日的には第二次大戦の序章とか前哨戦みたいな位置づけになってるくらいで、その後のヨーロッパはナチス・ドイツの勢力拡大とともに、どんどんきな臭くなって行きますにゃー。
内戦に心を痛めたブリてんは音楽祭で知り合ったレノックス・バークレーと一緒に、この翌年にかけて『モンジュイック組曲、オーケストラのためのカタルーニャ舞曲』を作曲します。その第三曲『ラメント』には「バルセロナ1936」の副題が付けられ、内戦での死者を悼む沈痛な雰囲気の曲となってますにゃ。
また、生涯の伴侶となるテノール歌手、ピーター・ピアーズと知り合ったのもこの頃ですにゃ。
●アメリカン、いざ
ブリテンとピアーズは1939年の4月、アメリカに移住します。
これについてはよく兵役忌避が目的だったみたいなことが言われますけど、どうもそう言う意味合いは薄いみたいですにゃ。そもそもこの時期はまだドイツのポーランド侵攻(9月1日)とそれに伴うイギリスの対独宣戦布告より前だし。
渡米の理由は、まず第一には自作のピアノ協奏曲がタイムズやミュージカル・タイムズなんかの新聞で貶されて、さらにそのことでフランク・ブリッジ門下の仲間内で陰口をたたかれてるのに気付いて落ち込んだこと。
二つ目には前の冬の間に何度か不意に失神したことがあって、「過労だから少し休め」と医者や友人に言われていたこと。
それから、1938年に今度はロンドンで開かれたISCMフェスティバルで知り合ったアメリカの作曲家アーロン・コープランドから、アメリカに来ないかと誘われたこと。
さらにブリッジ先生の作品が本国よりもアメリカでうけてること、その他もろもろの個人的な理由の積み重ねですにゃ。
ブリてん自身が語ったように「我々若者の多くはヨーロッパはどっちみちもうダメだと思っていた」みたいな世相への絶望感も、もちろんあったようですけどにゃー。
二人の出立をブリッジ先生も見送ってましたけど、これが師弟の今生の別れとなりました。
●新世界にて
アメリカに渡ったブリてんとピアーズは、当初はコープランドの住まいの近く、ニューヨーク州のウッドストックに居を定め、後にロングアイランドのアミティヴィルに移ります。これがちょうどヨーロッパでの第二次大戦勃発の頃ですにゃ。
アミティヴィルでは、精神科医のメイヤー夫妻の家にやっかいになります。ナチスの勃興するドイツから逃れてきた一家で、やがてブリてんはこのメイヤー家を第二の家族と考えるくらい親しくなったそうですにゃ。
メイヤー家の交際範囲には、地元のセミアマチュアオーケストラの監督を勤める商店主デビッド・ロスマンがいて、ロスマン家が第三の家族みたいな存在になります。
ロスマンはアルバート・アインシュタインとその従兄弟で音楽学者のアルフレッド・アインシュタインと知り合いで、ブリてんは彼らと即興で作曲を楽しんだりしてますにゃー。
そんな環境でアメリカでの音楽活動を始めたブリてんですけど、やがて英国政府が通貨ポンドの海外での流通に制限を加え始めたりしたので、だんだん手元のお金に困ってきますにゃ。
作曲家としては(特にアメリカでは)まだ名が通ってないので、アマチュアオーケストラの指導とかで糊口をしのいでました。
そんな折り、彼は日本政府からアメリカとイギリスの政府宛てに件の『紀元二千六百年奉祝曲』の依頼が来てることを聞きつけ、イギリスの分を引き受けます。もともとこの依頼に冷淡だった政府筋から話が来たわけじゃなくて、ブリてんの方からやるやると手を挙げたわけですにゃ。
日本からの依頼は1939年9月頃に来てて、「交響的作品ならば580ポンド(≒1万円(当時))、序曲や行進曲なら、その半分から3分の1の委嘱料を支払う。1940年5月までに東京に送れ」と言うような内容だったそうです。
それからちょうど同じ時期に、パウル・ヴィトゲンシュタインから左手だけで弾くピアノ曲の依頼も受けてます。『主題と変奏(ディヴァージョンズ)』作品21ですにゃ。
●左手のための
ちょっと脱線してヴィトゲンシュタインのお話にゃ。
パウル・ヴィトゲンシュタインはオーストリアのピアニストで、哲学者のルートヴィヒ・ヴィトゲンシュタインの兄ですにゃ。
この人は1913年にデビューしたんですけど、その翌年に第一次世界大戦が始まってしまい、ポーランド戦線で従軍中に負傷して右手を失ってます。それでも演奏活動を諦めなかったヴィトゲンシュタイン、ピアノ曲を自分で左手用に編曲したほか、多くの作曲家に左手だけで演奏できる作品を書いてくれるよう依頼しました。
彼の依頼に応じた作曲家は、彼の盲目の師ラボールを始めとして、リヒャルト・シュトラウス、プロコフィエフ、コルンゴルト、ヒンデミット、ラヴェルと結構な豪華メンバーですにゃ。そしてブリてんもまたその列に加わることになったわけですにゃー。
就中ラヴェルの『左手のためのピアノ協奏曲』は有名で、右手が不自由ではないピアニストにとっても重要なレパートリーとして、今日でも頻繁に演奏されてます。
●シンフォニア・ダ・レクイエム
さて、一つ目のレクイエムに戻りますにゃ。
日本政府の依頼を受けたはいいものの、ブリてんは1940年の春先にインフルエンザにやられ、続いて連鎖球菌に感染して、六週間ばかりベッドから出られない状態に陥っちゃいますにゃ。
メイヤー夫妻の娘ビータによる看病のおかげでなんとか回復したブリてん、猛烈な勢いで作曲を進め、夏の前には『シンフォニア・ダ・レクイエム』作品20を完成させました。
しかし、それから日本に送ったのでは、やぱし少々遅すぎて、依頼の期限が五月までだったのに到着したのが九月に入ってから。結局この作品は年末の演奏会では取り上げられずに終わってしまいますにゃ。
作品自体は受領されて、委嘱料もちゃんと支払われて、これでブリてんは金銭的に一息ついたみたいですにゃ。
日本側がボツにした理由は、公式には「練習の時間が十分に取れないから」てことで、それはそれで嘘とまでは言えないんですけど、「祝いの席に鎮魂曲とは何事か」とか「レクイエムとはキリスト教色が強すぎる」とかいろいろ問題視された挙げ句の決定らしいですにゃ。
それにイタリアのピエッティの作品が届いたのはブリテンより後だったみたいだし。
ただ、事前に「シンフォニア・ダ・レクイエム」て言葉を使って大まかな構想を説明した時点では、日本側から特に文句も言われなかったって話もありますけどにゃ。
で、この作品については追々時期を見て演奏する、てことになったみたいですけど、その後の日本は戦争にまっしぐら。それっきり立ち消えになってしまいます。前回の敵性音楽の話もありますしにゃー。
この曲が日本で演奏されるのは、なんと戦後もだいぶ経った1956年2月18日。ブリてんが来日したときに作曲者自らNHK交響楽団で指揮棒を振っての演奏ですにゃ。
世界初演はもっと早く、作曲翌年の1941年3月31日、バルビローリの指揮でニューヨーク・フィルによって行われてます。
この曲はブリテンにとって最初の大規模な管弦楽曲で、世が世なら交響曲第一番に仕立てられてもおかしくないような位置づけですにゃ。(これより前に弦楽だけの『シンプル・シンフォニー』があるけどにゃ)
作品には「両親の思い出に寄せて」と言う副題があって、それをあえて日本向けにしたことには、平和主義者として当時の日本の拡張主義的な日中戦争への批判もあったとも、単に病気などで時間がなかったからしかたなくとも言われます。
その両親ですけど、父のロバート・ヴィクター・ブリテンは歯科医でそこそこ成功した人でした。でも子どもはあまりかまってやらなかったようで、1934年に亡くなった時の遺言でも四人の子ども達(Barbara、Bobby、Beth、Benjamin)をまとめて「the 4B's」で片付けてたくらいにゃ。
母のエディスはアマチュアながらピアノや作曲などたしなむ人で、幼いブリてんに音楽の手ほどきしたのもこの人にゃ。ブリてんには、音楽史の三大B(Bach、Beethoven、Brahms)と例の4B'sになぞらえて、「あなたが音楽史上四人目のBになれるといいわね」みたいによく言ってたそうですにゃ。
母も1937年に姉のベスと共にインフルエンザで亡くなってて、いわば先だった家族への鎮魂として書かれたのがこの『シンフォニア・ダ・レクイエム』なのですにゃ。
●参考CDと楽曲解説『シンフォニア・ダ・レクイエム』
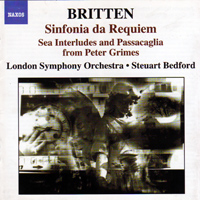 マイナー曲ならナクソスてことで、CD番号は8.557196ですにゃ。交響組曲『グロリアーナ』と、ブリテンの代表作でイギリスオペラの代表作でもある『ピーター・グライムズ』からの抜粋が一緒に入ってます。
マイナー曲ならナクソスてことで、CD番号は8.557196ですにゃ。交響組曲『グロリアーナ』と、ブリテンの代表作でイギリスオペラの代表作でもある『ピーター・グライムズ』からの抜粋が一緒に入ってます。
指揮はスチュアート・ベッドフォード、ロンドン交響楽団の演奏ですにゃー。
レクイエム、てのはキリスト教会の典礼音楽で、日本語に訳す場合は「死者のためのミサ曲」となりますにゃ。原則として形式が決まっていて、作品によって多少の異同はあるものの必要な曲目があって、歌われるべきラテン語(一部ギリシャ語)の典礼文があります。
でもブリてんのシンフォニア・ダ・レクイエムの場合はレクイエムよりシンフォニアの方に重点があって、「鎮魂曲としての交響楽」くらいに受け取った方が良いですにゃ。そもそもボーカルがありませんし。
全体は三つの楽章に分かれていて、
第一楽章:Lacrymosa(ラクリモサ、涙の日)
第二楽章:Dies Irae(デイエス・イレ、怒りの日)
第三楽章:Requiem Aeternam(レクイエム・エテルナム、永遠の安息)
となってます。
各楽章は切れ目無く続けて演奏され、全部で20分くらいの長さになりますにゃ。
まず冒頭、ティンパニの強打とともに低音楽器がデーーと唸ります。この段階で、もはやお祝い気分もどこへやら、重苦しい雰囲気に押しつぶされますにゃ。
同じくティンパニの強打と銅鑼で始まるコープランドの『市民のためのファンファーレ』(1942年)を予感させるものもありますにゃー。
ティンパニが静まると、弦楽器で示される「たらーら」と言う音型を積み重ねるようにして、次第に楽器が増えて盛り上がります。その頂点で再びティンパニの強打が現れると、音楽は急速にしぼんで行きます。
涙の日、悲しみ、と言うよりは言いしれぬ不安に満ちた楽章ですにゃー。
音量が下がって木管の「てーっててってーっててっ」て動機が出てきたところからが第二楽章で、急なテンポの闘争の音楽になりますにゃ。ほぼ全編がこの動機に支配されてて、ミュートした金管の歪んだ響きが不気味な感じを煽ります。
一旦は完全終止っぽく「てーっててっ!」と終わったかと思うと、まだ怒り冷めやらず「てん、どん、だん」と当たり散らす、みたいなのを何度か繰り返しつつ、徐々に力尽きるようにして怒りの日は終息しますにゃ。
続いてどことなくストラヴィンスキーの『火の鳥』の終曲を思わせるメロディで、レクイエムの第三楽章に入ります。
ここは弦楽器を主体とした浄化の音楽で、一抹の哀愁も漂わせつつ、静かに天に昇っていくように全曲が閉じられますにゃー。わりと短めなので、エテルナムて言うわりにはあっさり終わる感じですかにゃ。
全体としては不安から闘争を経て浄化へ、みたいなわかりやすい構成で、ベートーヴェン的な苦悩を通じて歓喜へ式の手口にも通じるものがあります。現代ものでも難解な曲が好きな人には、明解すぎて物足りないくらいかもにゃー。
最後はすっきり綺麗に終わるので、実際に祝典で演奏したら、これはこれで良かったかもしれませんにゃ。
成立にまつわる因縁は置いといて、これはもっと評価されて良い作品じゃないですかにゃー。
●帰りなん、いざ
当初ブリてんはアメリカに永住するつもりもありました。それでアメリカの民間伝承にある巨人の木こり『ポール・バニヤン』の物語をオペラ化して、アメリカ英語のイントネーションを活かして曲を付けてみたりとか、現地に馴染む努力もしてますにゃ。
ちなみにこのポール・バニヤン、本人(?)はなにせミシシッピ川を作ったとか言われるくらいで、図体がでかすぎて舞台に収まらない、て設定になってて、オペラでも姿を見せずに歌声だけの出演になるとか、なかなか奇抜な演出だったそうですにゃ。
しかし、あるときイギリスはサフォーク州オールドバラの詩人、ジョージ・クラッベの作品に触れたことから、「やはり自分のルーツはイギリスにあるのだ」と悟り、帰郷を決意します。このあたりは欧米を彷徨ったあげくに故郷のロシア(ソ連)に舞い戻ったプロコフィエフと良く似てますにゃ。
イギリスに帰るとは言っても今は戦争中。大西洋ではドイツが無制限潜水艦戦"Paukenschlag"と言うハイドンの交響曲『驚愕』みたいな作戦を展開中で、Uボートがうようよしてますにゃ。
プロコの時と違って日米開戦後は太平洋側も日本軍がうようよしてますから、安全な帰国ルートがありません。
イギリス政府からも在外邦人に対して「危ないから無理に帰ってくるな」という勧告も出ていたようですしにゃ。
それでもブリテンとピアーズは危険を冒して、護送船団「HX 183」の一隻、スウェーデンの商船アクセル・ジョンソンに便乗して、1942年4月に無事帰国しました。
ちょっと余談ですけど、護送船団と作曲家と言うと、同じイギリスのジョージ・ロイドが軍楽隊のメンバーとして巡洋艦トリニダード(HMS Trinidad)に乗り組んで、船団護衛にあたってますにゃ。政治家のロイド・ジョージじゃありません。
1942に「PQ 13」船団、てのはシベリウスのとこで出てきたムルマンスク鉄道の終点ムルマンスクに対ソ援助物資を届ける船団で、これを護衛してるとき、船団がドイツの駆逐艦に襲撃されました。トリニダードは僚艦と共に首尾良く敵を撃退しましたけど、この時に発射した三本の魚雷のうち一本が故障して、大きく弧を描いて戻ってきて、撃った本艦に命中してしまいます。
沈没こそ免れたものの、楽隊メンバーの戦闘時の配置が通信室とかのわりと艦底の方だったのもあって、この魚雷で32人が戦死。ロイドはなんとか生き残ったんですけど、この一件のせいでひどいシェルショックになって、日常生活にも不自由するほどになってしまいました。いわゆるPTSDてやつですにゃ。
その後の1951年、Festival of Britainて博覧会でやるオペラのコンペティションがあって、ロイドはエイジンコートの戦いのその後を描いた『ジョン・ゾックマン』を寄せたんですけど、残念なことに予算の関係で演奏されず、ブリてんの『ビリー・バッド』に舞台を持ってかれてますにゃー。余談終わり。
で、もういっこ余談ですけど、ドイツの無制限潜水艦作戦"Paukenschlag"いわゆる「太鼓連打」作戦について。
ハイドンの作品に交響曲103番『太鼓連打』、英語で『Drum roll』て訳すやつがあるので、私はそれがドイツ語では『Paukenschlag』なのかと思っていたら、実はそうじゃなかったんですにゃ。
『Paukenschlag』のニックネームが付いてるのは交響曲94番の『驚愕』あるいは『びっくり交響曲』、英語で『Surprise』の方でした。
じゃ103番はなにかと言うと『Paukenwirbel』なのですにゃ。
対空戦車ヴィルベルヴィントの"wirbel"で、「渦」の意味から来てる用語ですにゃ。"schlag"は単に「打つ」とか「叩く」とかそんな意味にゃー。
となると、潜水艦戦を「太鼓連打」と訳すのはあましよろしくないのではあるまいかと思うわけです。
「太鼓叩き」作戦とか……平仮名混じりだと迫力に欠けますかにゃ。もしハイドンの曲を念頭においた作戦名だとしたら「驚愕」作戦とか、いっそ「びっくり大作戦」とか。
ちょっと意訳して「太鼓強打」くらいは奢ってもいいですかにゃ。連打も意訳と言えばそうなのかもだけどにゃ。
ちなみに英語で潜水艦の方をどう訳すかというと"Drumbeat"で、やぱし"Drumroll"じゃありません。日本語訳でどこから「連」の字が出てきたのか謎ですにゃー。
●帰ってみれば
ブリテンが留守の間、イギリスでの評判がどうだったかというと、なんかもう敵前逃亡でもしたかのような扱いで、作品の演奏をボイコットされたりとかしてましたにゃ。
もともと仲間内の陰口が嫌で出国したわけですから、残った連中があることないこと触れ回ったのかも知れませんにゃー。どうも兵役拒否のために渡米した、みたいな話はこの頃の本国での噂が出どこみたいです。
帰国後のブリてんは、ピアーズと一緒にジョージ・クラッベゆかりのオールドバラに腰を落ち着け、なんとか良心的兵役拒否者(conscientious objector)として扱ってもらうことができました。まあ結局のところ兵役拒否はするんですけど、そのためにわざわざアメリカに渡る意味は無いというわけですにゃ。
良心的兵役拒否とは言っても、戦争に出なくていい代わりに銃後での勤労奉仕(農業生産とか)が義務づけられたりするわけですけど、作曲家にそれはあんまりだってことで、裁判所にかけあって「CEMA(Council for the Encouragement of Music and the Arts 音楽及び芸術奨励協会とでも訳すのかにゃ)のために公演を引き受けること」て条件で折り合います。
要はドサ回りの慰安演奏会をやれ、ってことで、いわば山田耕筰のとこに出てきた音楽挺身隊やドイツの歓喜力行団のイギリス版ですにゃ。平和主義者であっても落ち着くところは似たようなもんになっちゃうのは皮肉ですにゃー。
てゆーかどの国も同じようなことやってますにゃ。アメリカのグレン・ミラーも慰問公演の巡業中に命を落としてますしにゃ。
この時期の戦争がらみの作品としては、ミュンヘン郊外のアイヒシュテットにある将校捕虜収容所VII-Bに捕まってるリチャード・ウッドが収容所内で企画した音楽会のために、『小姓マスグレイブとバーナード夫人のバラード』(The Ballad of Little Musgrave and Lady Barnard)と言う合唱曲を1943年に書いてます。
それからオペラの代表作『ピーター・グライムズ』の作曲もこの時期(1944年)ですにゃ。
もう一つ重要なのは1945年の4月、ヴァイオリニストのユーディ・メニューインと一緒に解放直後のベルゲン・ベルゼン強制収容所で慰問演奏会を開くため赴いたこと。
ベルゲン・ベルゼンは当初、「交換ユダヤ人」と呼ばれるユダヤ人の収容所でした。連合国側に取り残されたドイツ人と交換するための、連合国の国籍を持っていたり、なにかしら重要人物と目されるユダヤ人のことですにゃ。
しかしそういう「交換」はなかなか思うようには進まず、後に他の収容所で発生した病人を集めておく休養収容所に変わっていきます。休養と言っても碌に手当をするわけでもなく、逆に重病人はフェノール注射で殺害したりしてたそうですし、チフスが蔓延して解放時には大変ひどい有様だったようです。
ちなみにこの収容所はアンネ・フランクが亡くなったところとしても知られてますにゃー。
ブリテンにとってここでの体験は非常に鮮烈であったようで、あまり人には語りたがらなかったみたいですけど、これ以後の諸作品に色濃く影響を与えている、と後年になって本人も認めているそうですにゃ。
●コヴェントリー大聖堂と『戦争レクイエム』
1962年、イングランドはウェスト・ミッドランズ州のコヴェントリーにある聖マイケル聖堂(コヴェントリー大聖堂)が再建され、ブリテンにその献堂式で歌う記念ミサの作曲依頼がやってきました。
コヴェントリーはイギリス中部の工業都市であることから、1940年8月からたびたびドイツ軍の爆撃に曝されることになります。
なかでも11月14日の大空襲はひときわ烈しく、11世紀のベネディクト派の修道院を母体として14世紀に建てられた大聖堂も、外壁の一部を残して焼け落ちてしまいましたにゃ。
このことから「爆撃で破壊する」と言う意味の"coventrate"て単語が生まれたくらいだそうで、大きな辞書には載ってるようですにゃ。日本で言えば「ヒロシマ・ナガサキ」とカタカナで並べたら原爆のことを指すようなもんですかにゃー。
ちなみにこの聖堂跡と広島の平和祈念公園とには、同じ銅像が置かれてるそうですにゃ。
こっちがコヴェントリーのやつで、こっちは広島の。
新聖堂は破壊された聖堂の遺跡を残したまま、その横の敷地に建てられました。ぐぐるマップで見ると、現在の聖堂の南側に壁だけとなった旧聖堂が残されているのがわかりますにゃ。
ブリテンは記念ミサのために、全ての戦争による犠牲者を悼む鎮魂曲として、そして平和を祈る歌として、ブリてんとしては初の大規模声楽曲となる『戦争レクイエム』作品66を書き上げました。
シンフォニア・ダ・レクイエムが両親の思いでに捧げられたのと同様に、こちらも先の戦争で亡くなったブリテンとピアーズの友人4人を弔う意味がありました。
フランスの巨砲潜水艦シュルクーフに乗っていて撃沈されたロジャー・バーニー、ノルマンディー上陸作戦で負傷して捕虜となり、戦後に自殺したピアーズ・ダンカリー、地中海で戦死したデビッド・ギル、従軍中に行方不明になったマイケル・ハリディですにゃ。
●作品解説
ブリテンの『戦争レクイエム』は6曲構成で、以下のようになってます。
I. 永遠の安息 (Requiem aeternam)
II. 怒りの日 (Dies irae)
III. 奉献唱 (Offertrium)
IV. 聖なるかな (Sanctus)
V. 神羊誦 (Agnus Dei)
VI. 我を解き放ち給え (Libera me)
最大の特徴は、ラテン語の典礼文の他にイギリスの戦争詩人ウィルフレッド・オーウェンの詩(もちろん英語)を取り入れたところですにゃ。どの詩をどこに使うかとか、構成についてはピアーズと相談しながら作曲を進めました。
オーウェンは第一次大戦に従軍して、西部戦線で迫撃砲に吹き飛ばされて負傷、イギリスに後送されて療養中に文学サークルで詩人のジークフリード・サスーンと出会い、自作の添削をしてもらったりして数々の作品を残してます。その後、回復した彼は戦場に戻り、第一次大戦が休戦となる一週間前にあえなく戦死してしまったのですにゃ。
歌い手はソプラノ、テノール、バリトンのソロに、混声合唱と児童合唱が加わって、結構な大人数になりますにゃー。
伴奏に当たるオーケストラも、オルガンを伴う三管編成(木管楽器が三人ずついて、その他も楽器編成もそれに見合う規模になるもの)の大オーケストラと室内楽規模の小オーケストラに分かれて、大が典礼文、小がオーウェンの詩を担当、この二つが入れ替わり立ち替わり歌い継ぐようになってますにゃ。
歌手の方は合唱とソプラノが伝統的な典礼文を受け持ち、テノールとバリトンがオーウェンの詩を歌います。
二つのオーケストラは最後のリベラ・メに至って初めて一緒に演奏し、それまでは対立軸として置かれていた典礼文と反戦詩が融和していく様子を表しています。
以下、各曲のラテン語部分は概ねレクイエムの型通りなので、オーウェンの詩との関係を書いてみますにゃ。
一曲目、低音の不安な響きに乗って、鐘の音とともに入祭唱の「永遠の安息」が合唱によって歌われます。一定の音階で抑揚も無く、歌と言うよりもほとんど呪文のようにとなえられますにゃ。繰り返される呪文の音階は短四度の音程で、典型的な不協和音となる間隔ですにゃ。鐘の音も弔鐘と言うより警鐘のように聞こえます。
だんだん音楽が激しさを増して児童合唱に引き継がれ、再び静まってきたところで、テノールの独唱によりオーウェンの詩『悲運の青年への頌歌 (Anthem for Doomed Youth)』が歌われます。「家畜の如く死にゆく兵士らにどんな弔鐘があるというのか?」で始まる詩には、理不尽な死に対する無力感が漂いますにゃ。
最後に「キリエ」が合唱によって歌われて、静かにこの曲を閉じます。
二曲目の「怒りの日」は全曲中最も長く、全体の約1/3にあたる25分ほどを占めてますにゃ。
ここではどこか遠くで呼び交わす信号ラッパのようなトランペットに導かれ、合唱によって「怒りの日」「奇しきラッパの音」「恐るべき御稜威の王」「思い出したまえ」「呪われたもの」「涙の日」と歌い継がれます。その合間合間に独唱によるオーウェンの詩が挟まる構造ですにゃ。
オーウェンの詩は、ここでは四編も動員されてます。就寝ラッパの下でやがて来る明日に怯えて眠る少年兵の姿を描く『少年兵たちの声は (Voices)』、大義や国旗のためになら自分を殺しにかかる死神をも味方にすると語る『次の戦争 (The Next War)』、禍々しく巨大な大砲を頼もしく思いつつ、それに神の呪いがあらんことをと願う『ソネット:戦闘に駆り出された我らの大砲を見て (Sonnet: On Seeing a Piece of Our Artillery Brought into Action)』、大地を目覚めさせる太陽の光も死者を蘇らせはしないことを嘆く『むなしさ (Futility)』、の四つですにゃー。
オーウェンの詩は相前後する典礼文と内容的に呼応するように選ばれていますにゃ。
「怒りの日」から「奇しきラッパ」にかけて次第に金管が厚みを増して、かっこいいファンファーレの如くにさえ聞こえた音楽も、「少年兵」のところでは哀れを誘う惨めな響きとなり、裁くものとして畏怖の対象である「御稜威の王」に続いて、やけに威勢のいい「次の戦争」。ことごとく裏と表のように配置されていますにゃ。
静かな合唱の「呪われたもの」から一転してバリトンの「我らの大砲」になると、冒頭のラッパの響きが帰ってきて、それが再び合唱の「怒りの日」を呼び起こすあたりは構成の妙ですにゃー。
「涙の日」に入ってからは、ラテン語一節ごとにオーウェンの『むなしさ』が割り込むようになります。
三曲めの「奉献唱」では、典礼文が神がアブラハムに約束した死後の復活に言及していることを踏まえて、オーウェンの『アブラハムとイサクの寓話 (The Parable of the Old Man and the Young)』が使われてます。
旧約聖書では神がアブラハムに息子のイサクを生け贄として捧げるよう命じ、それに従ったアブラハムが刃物を振り下ろす寸前で神の御使いに止められて、イサクの代わりに雄羊を捧げることになるんですにゃ。それを嘉した神が前述の約束をするわけですけど、奉献唱の歌詞にはこの辺のいきさつについては出てきません。
ところがオーウェンの方ではこの物語をなぞった後で、アブラハムが天使も雄羊もお構いなしにイサクを殺してしまい、それがすなわち「ヨーロッパの子孫の半分を屠ったのである。一人また一人と」と続くのですにゃ。
これが奉献唱のど真ん中に居座ることで、本来の意味合いを完全にひっくり返してしまってますにゃ。その点では全曲中の白眉とも言えるところですにゃー。
音楽の方は、まず最初に神秘的なオルガンと児童合唱によって主イエスへの祈りが静かに歌われ、次に合唱がシュプレヒコールのように復活の約束を叫ぶと、その勢いに乗ってテノールとバリトンによるオーウェンの詩が始まります。
最初は景気が良かったオーウェンの詩もたちまち雲行きがおかしくなってきて、話が進むにつれて怒りの日のラッパまで見え隠れしますにゃ。
最後に「ヨーロッパの子孫……」を繰り返すところから冒頭の児童合唱がかぶさってきて、さらに合唱が例の約束を繰り言のように何度もつぶやいて曲を閉じます。
四曲目、「聖なるかな」は万軍の主なる神を讃えるラテン語に続いて、「本当に神は死と涙を、すべて取り消して下さるのだろうか?」と反語で語る『終末(東方から、稲妻が、トランペットの爆音を轟かせ)(The End (After the blast of lightning from the east))』が置かれてます。
出だしの鐘の乱打とソプラノに導かれて沸き上がる合唱の不気味な空気と、それをぬぐい去る輝かしい金管の響き、荘重な行進曲風のラテン語パートは伝統的な「聖なるかな」にふさわしいと言えますにゃ。
そうして盛り上がったところをオーウェンの詩でクールダウンして、最後は消え入るように終わります。
五曲目「神羊誦」では一転してオーウェンの詩の方がメインとなり、その合間に伝統的レクイエムの歌詞「この世の罪を取り除く神の小羊よ、彼らに安息をお与えください」が割って入る構成になります。
ここで歌われる『アンクル川のゴルゴタ (At a Calvary near the Ancre)』では、宗教的に弾圧されたことを自慢する司祭や国家への忠誠を強いる律法学者(つまり銃後で煽り立てる連中ですにゃ)と、戦場で命を投げ出す兵士たちとが対比されています。それら全ての人々に「安息をお与えください」と祈るわけですにゃ。
波打つように上昇下降を繰り返す音型が基本となっていて、合唱はその音型に沿って歌います。しかしおよそ安息とはほど遠い恨み節の雰囲気に終止する楽章になってますにゃ。
最終曲となる「我を解き放ち給え」は、まずソプラノと合唱による典礼文で始まり、続いて『奇妙な会合 (Strange Meeting)』の前半をテノールが、後半をバリトンが歌って、再び典礼文が戻って来て終わりますにゃ。
典礼文の部分は、半音階的なメロディーで「リベラ・メ」を繰り返し唱えつつ打楽器に彩られながら次第に大きくなり、ソプラノが加わると怒りの日のラッパも現れます。まるっきり闘争の音楽みたいなとこまで発展した音楽が不意に静かになると、オーウェンの詩の出番ですにゃ。
テノールは、戦闘から逃げて潜り込んだいずことも知れぬ穴の中で、どうやら戦争が終わったらしいことを知り、そこにいた人に「見知らぬ友(strange friend)よ、もう悲しむことはない」と語りかけますにゃ。
しかしそれを受けたバリトンは、戦争による破壊、虚しさ、それを退ける意志を語ったあと、「私はお前が殺した敵なのだ、友よ。昨日、君は私を刺し殺したのだ」と衝撃の事実を告げるのですにゃー。そして相手を赦すでも赦さぬでもなく、また恨むでもなく、ただ「さあ眠ろうじゃないか」と続けて、再び合唱による典礼文へと移ります。
最後にテノールとバリトンが共に「さあ眠ろうじゃないか」と歌い、合唱が「安らかに眠れ。アーメン」と加わり、鐘の音に送られて全曲を締めくくります。
男声ソロと合唱、ソプラノが一緒に歌うのはこの最後の部分だけで、ここに伝統的レクイエムと現代詩と、両者の和解を象徴しているようにも思えますにゃー。
『戦争レクイエム』全体として、平和を希求する祈りに満ちていて、戦争という悲劇を忘れそうになる人々への警告という意味でショッキングでもあり、感動的な作品に仕上がっています。
ブリテンが楽譜の巻頭に置いたオーウェンからの引用も、やはり警告としての意味が強いことを示してます。
- My subject is War, and the pity of War.
- The Poetry is in the pity...
- All a poet can do today is warn.
- The Poetry is in the pity...
しかし反戦的なメッセージとはまた別に、宗教(直接にはキリスト教)に対する皮肉というかアイロニーも聞き取れます。反戦と共に反宗教とも取れるオーウェンの詩を並べて見せることで、宗教の無力さとか、救済の約束への当てこすりみたいな含みがそこかしこに浮かび上がってきますにゃ。
教会堂の再建記念としてそんな作品を持ってくるのは、皇紀2600年記念に「レクイエム」を差し出したブリテンの面目躍如てとこですかにゃー。実際に爆撃で破壊された聖堂がすぐ横にある環境での初演は、さぞかし説得力があったことでしょうにゃ。
それはそれとして、この作品は初演当時からなかなかの好評を博し、大本山のウエストミンスター寺院での演奏も含め、立て続けに再演されてます。
それにはこの1960年代の、キューバのミサイル危機とかで今にも第三次大戦に発展するのでは、という危機感に覆われた時代背景も大きかったんでしょうにゃー。
●初演
ブリテンの構想としては、歌手陣のテノールをイギリスのピアーズ、バリトンをドイツのディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ、ソプラノはソ連のガリーナ・ヴィシネフスカヤを考えてました。第二次世界大戦の欧州戦線における主要交戦国の歌手が平和を祈って一緒に歌う、て趣向ですにゃ。
ところが初演の前の週までイギリスはコヴェントガーデンで「アイーダ」の公演を行っていたヴィシネフスカヤが、ソ連当局の命令で「急用のため」に帰国させられちゃうんですにゃ。どうもコンセプト的に冷戦さなかのソビエトの癇に障ったみたい。
やむなくソプラノはイギリスのヘルタ・テッパーが歌いました。以下メンバーはこんな感じ。
- 総指揮:メレディス・デイヴィス
- 室内楽指揮:作曲者(ブリテン)
- ソプラノ:ヘルタ・テッパー
- テノール:ピーター・ピアーズ
- バリトン:ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ
- 管弦楽:バーミンガム市交響楽団
- 室内楽:メロス・アンサンブル
- 合唱:コヴェントリー祝祭合唱団
- 児童合唱:ストラトフォード聖トリニテ教会児童合唱団
- 室内楽指揮:作曲者(ブリテン)
日時は1962年5月30日、会場はもちろんコヴェントリー大聖堂ですにゃ。
ちなみにヴィシネフスカヤは同年秋のエジンバラ音楽祭に来て歌ってますから、まあ露骨な妨害ではありますにゃ。
このヴィシネフスカヤはチェリストのムスティスラフ・ロストロポーヴィチの奥さん(夫婦別姓)で、ブリてんと知り合ったのは前年の1961年にオールドバラ音楽祭に呼んだときですにゃ。そのきっかけはさらに前年、ロンドンでショスタコーヴィチのチェロ協奏曲第1番の西側初演が行われたときに遡ります。
そのコンサートには作曲者のショスタコーヴィチ自身が来ていました。そしてチェロのソロを取ったのが、この曲を献呈されていたロストロポーヴィチだったのですにゃ。
ブリてんは学生時代にタコさんの『ムツェンスク郡のマクベス夫人』のイギリス初演を聞いて以来、タコさんに傾倒と言うか私淑していました。
タコさんの方でもブリテンの作品にはかなり早くから注目していたようで、この時の出会いで意気投合、お互い鉄のカーテンを越えて盟友とも言うべき関係になります。タコさんは『戦争レクイエム』について、「この時代において最も偉大な作品」と評価していたそうですにゃ。
後にブリてんはタコさんに歌劇『放蕩息子』を献呈、タコさんはブリてんに交響曲第14番『死者の歌』を献呈してますにゃ。
ロストロポーヴィチについてもブリテンはその見事な演奏に感服、大いに刺激を受けて彼のためにチェロ交響曲(Symphony for Cello and Orchestra)やチェロソナタを書きます。オールドバラ音楽祭にも度々招き、親交を深めてますにゃ。
ロストロポーヴィチは英語が話せないので、共通言語としてお互い片言のドイツ語で話したそうです。ところがこれがドイツ語をネイティブで話す人には通じないもんだから、「オールドバラドイツ語」と呼ばれたらしいですにゃ。
ロストロポーヴィチ夫妻は、作家のソルジェニーツィンを擁護したことから当局に睨まれ、1974年にイギリスに亡命してくることになります。
●参考CD
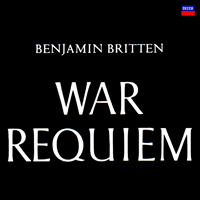 話が逸れましたけど、ブリてんはなんとかして当初の構想に沿ったソリスト陣での演奏を模索、それは1963年の1月、キングスウェイ・ホールで実現します。この演奏はレコード会社デッカの録音が目的で、それがこのCDですにゃ。
話が逸れましたけど、ブリてんはなんとかして当初の構想に沿ったソリスト陣での演奏を模索、それは1963年の1月、キングスウェイ・ホールで実現します。この演奏はレコード会社デッカの録音が目的で、それがこのCDですにゃ。
さすがにこの時代になると、作曲者の自作自演が録音として残ってるんですにゃー。
CDのナンバーはUCCD-3633/4、演奏時間約82分で二枚組ですにゃ。内容は……もういいですよにゃ。
このCDではプロデューサーがこっそり録音してたリハーサル風景が一緒に入ってます。ブリテンは隠し撮りされたのが気にくわなかったみたいですけどにゃー。
- 総指揮:作曲者(ブリテン)
- ソプラノ:ガリーナ・ヴィシネフスカヤ
- テノール:ピーター・ピアーズ
- バリトン:ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウ
- 管弦楽:ロンドン交響楽団
- 室内楽:メロス・アンサンブル
- 合唱:バッハ合唱団、ロンドン交響楽団合唱団
- 児童合唱:ハイゲート学校合唱団
- オルガン:サイモン・プレストン
- ソプラノ:ガリーナ・ヴィシネフスカヤ
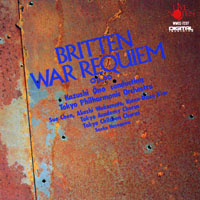 もう一枚、日本人の演奏で。
もう一枚、日本人の演奏で。
1993年2月18日のオーチャードホールで行われた東フィルの定期演奏会の録音で、ライヴ・ノーツてレーベルのWWCC-7237となってますにゃ。
こちらのCDでは全曲79分で、CDの収録限界を超えんばかりの長さですけど、なんとか一枚に収めてます。
ソプラノが中国、テノールが日本、バリトンが韓国、昨今なにかと騒がしい三国を代表して歌ってます。
- 指揮:大野和士
- ソプラノ:陳素娥
- テノール:若本明志
- バリトン:金寛東
- 管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団
- 合唱:東京アカデミー合唱団
- 児童合唱:東京少年少女合唱隊
- 児童合唱指揮:長谷川冴子
- ソプラノ:陳素娥
●オールドバラ卿
ブリてんはアメリカから帰国以後の後半生を、北海に面したオールドバラにある通称レッドハウスで送ります。
そしてこの町で、ピアーズと脚本家のエリック・クロージャーと一緒に、既に何度か出てきたオールドバラ音楽祭を1948年から始めますにゃ。そのためのホールの建設なんかにも尽力してます。
主に現代音楽や舞台作品を紹介する場として、今では名の通った音楽祭となってますにゃー。
そうした音楽界へのブリテンの功績が認められ、1953年にコンパニオンズ・オブ・オナー(CH)に叙せられ、1965年にはメリット勲章(OM)を授与されました。メリット勲章は外国人に授与されることもあって、日本でも日英同盟の頃に山縣有朋、大山巌、東郷平八郎と三人の軍人がもらってますにゃ。
さらにブリテンの死の直前となる1976年には、オールドバラ男爵(Baron Britten of Aldeburgh)として叙爵されてますにゃー。一代限りの名誉称号としての爵位ですけど、音楽家としてこの栄誉に浴したのはブリテンが初めてとなりますにゃ。
そんなわけでブリテンのお話はここまで。次は紀元二千六百年つながりでもう一人、ドイツのリヒャルト・シュトラウスですにゃ。
目次