


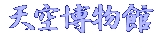
 |
 |
 |
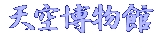
|

|
江戸時代の大気光象の記録日本テレビ系列の番組「世界一受けたい授業」の 2015/9/12 放送回に 「かわら版で見るお江戸ミステリー!」という授業があり、 そこで「金環日蝕を報じたかわら版」として紹介された文献があります。 そこに描かれた図は日蝕ではなく、ちょっと大気光象を知っている人が見れば即、 暈の類だと判るものでした。 所蔵元に問い合わせたところ閲覧可能とのこと、実物を見て、 どういう記録なのかを調べてみました。
※ 詳細についての記事を日本気象学会機関誌「天気」に寄稿しました。
文献の概要左の画像がその文献です。 尾張藩士の安井重遠という人物による風聞書 (かわら版や風説などを書き留めた資料) 「鶏肋集」の第四巻、七丁 (7ページ) に、これが折り畳まれ挟み込まれています。 文章部分、まだきちんと読めていない^^;部分もあるのですが、 以下現時点で判ったことを説明します。
まずは全般的な内容から…
何が見えていたのか? (四月二十四日)
こちらの画像は図の部分に強調処理を掛け、現象ごとに番号を振ってみたものです。
番号はおおよそ文章中で言及されている順序です。
中央の赤い丸は太陽です。四月二十四日の記述を見ていきます。 このあたり、どの番号のものを指しているのか判別しづらい文もあるので、 何か新たに判ったら随時更新します。 「庄内で見られたものの報告を書き写したもの」ということで、元の記録がどこかに残っていないだろうか、というのも気になるところです。 何が見えていたのか? (四月二十五日)四月二十五日については、一行ほどの記述に留まります。 正午を挟んで、太陽の周りに二重の輪が見えていた、という記述なのですが、 一つは内暈でよいとして、もう一つが外接ハロなのか、 9度暈なのかは不明です。 旧暦の四月ということで、庄内辺りでも外接ハロが見える太陽高度ではあったと思われます。 ヨーロッパでの古い記録さて、ヨーロッパのほうの同時期の図による記録というと、 1820年 4月8日の William Edward Parry のスケッチが有名です。 さらに時代を遡ると、 1661年 2月20日の Hevelius のスケッチ、 1629/1630年のローマでの記録 や 1535年のストックホルムの記録 などがあります。 日本にも、このような大気光象のさらに古い記録が、 他にもそれと気づかれずにまだまだ眠っているかもしれません。 何か良い手段があれば探してみたいものです。 (2017/09/16)
関連項目
|
 |
Contact:
aya@ |
Copyright 1998-2025, AYATSUKA Yuji |