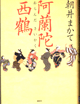| ●「実さえ花さえ」● ★★ 小説現代長編新人賞奨励賞 (文庫改題:花競べ-向嶋なずな屋繁盛記-) |
|
|
2011年12月
|
江戸は向嶋で種苗屋“なずな屋”を営み始めた新次とおりんの若夫婦を描いた時代小説。 市井小説というと人情ものという連想が浮かびますし、ましてや町人の若夫婦が主人公となれば市井の出来事あれこれがストーリィの中心と思うもの。 本作品も確かにそうなのですが、新次とおりんのどちらが主人公とも言いかねますし、そのストーリィの中心題材と言えば、やはり種苗屋、花師の仕事そのものなのです。 文庫背表紙の紹介文に「江戸市井の春夏秋冬をいきいきと描く傑作“職人小説”」ありますが、まさにそのとおり。 最初こそ些か硬いところがあるかなと思ったものの、ストーリィが順調に進み始めてしまえば、もう気になることなし。 細かい部分では、善良なる登場人物に対してその運命は厳し過ぎるよなぁと思うこともあるものの、ストーリィ運びはしっかり出来上がっていて、デビュー作としては驚くべき完成度という評価も当然のことと感じます。 登場人物は新次とおりんの他、2人の元に預けられた「雀」ことしゅん吉9歳。夫婦喧嘩が絶えない大工の留吉とお袖、なずな屋に目をかけてくれる太物問屋の隠居=上総屋六兵衛、その孫で変わり者の辰之助。それら人々と関わる中で様々な出来事が起こりますが、花師として新次の覚悟が問われるのは、因縁ある理世との再会部分。 新次がかつて修行したのは、江戸城お出入の植木商=霧島屋。理世は、その霧島屋主人の六代目伊藤伊兵衛の跡取り娘で、新次と競って修行した仲だったという次第。 江戸市井小説に加えて江戸時代の“お仕事小説”という趣向が、本作品をきりりとした男前に仕上げています。 時代小説好きの方にお薦め。 1.春の見つけかた/2.空の青で染めよ/3.実さえ花さえ、その葉さえ/4.いつか、野となれ山となれ/終章.語り草の、のち |