| トップページへ | 研究指針の目次 |
目次
210.1 はじめに
210.2 用語の定義と資料
210.3 気温変動の特徴と解析方法
210.4 気温上昇率の季節ごとの比較
1971~2020年(50年間)
1920~2019年(100年間)
1994~2019年(25年間)
210.5 最低気温の都市化昇温との関係(考察)
まとめ
文献
付録 気温上昇率の一覧表
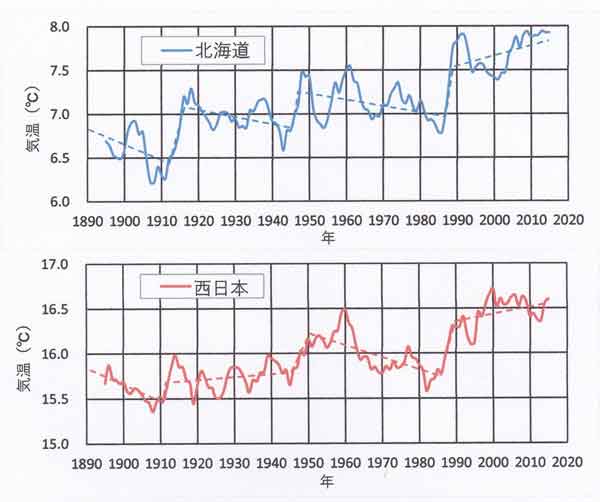
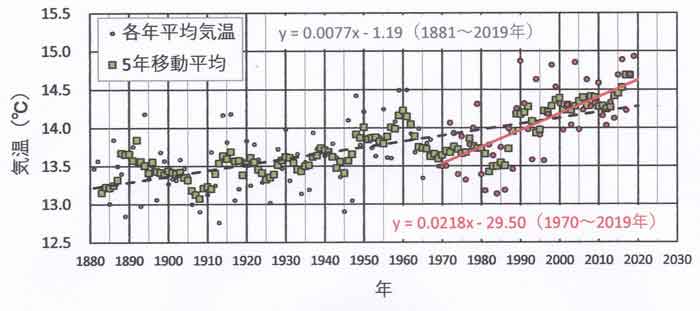
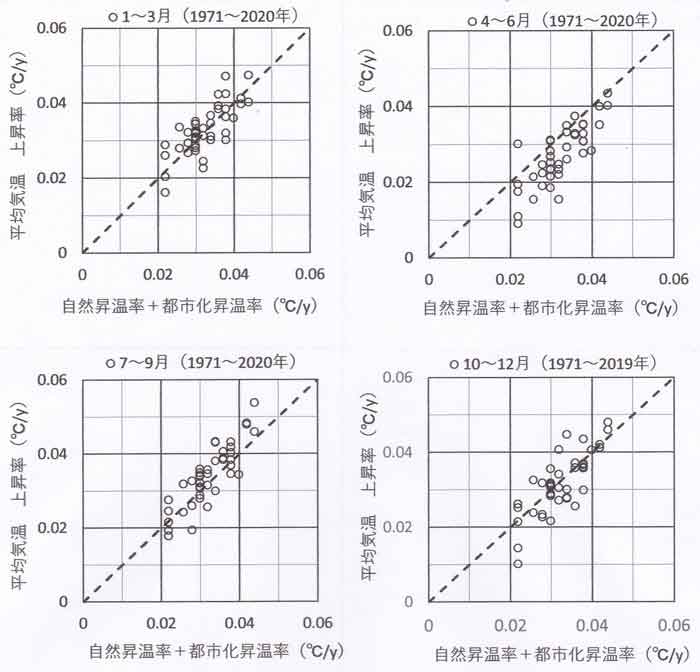
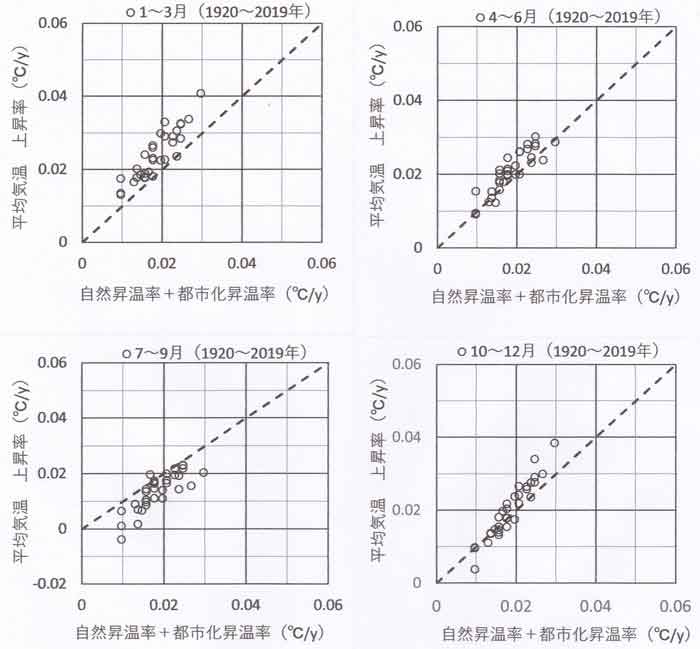
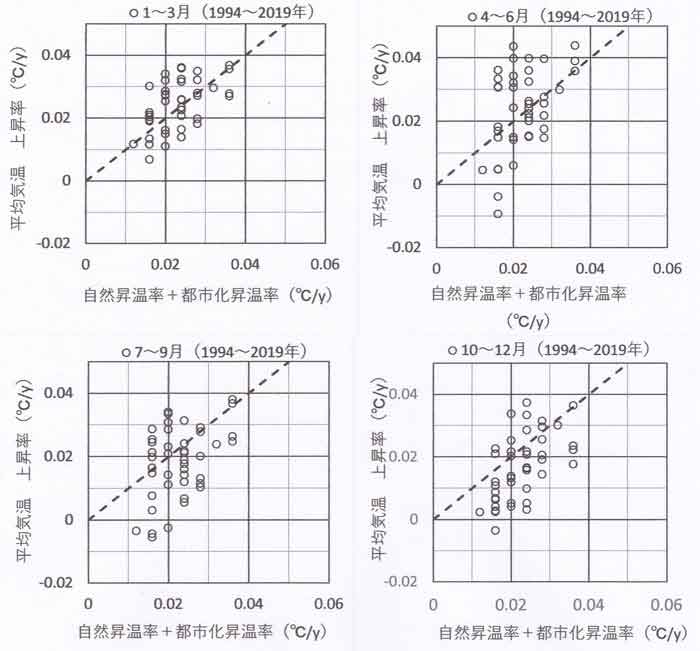
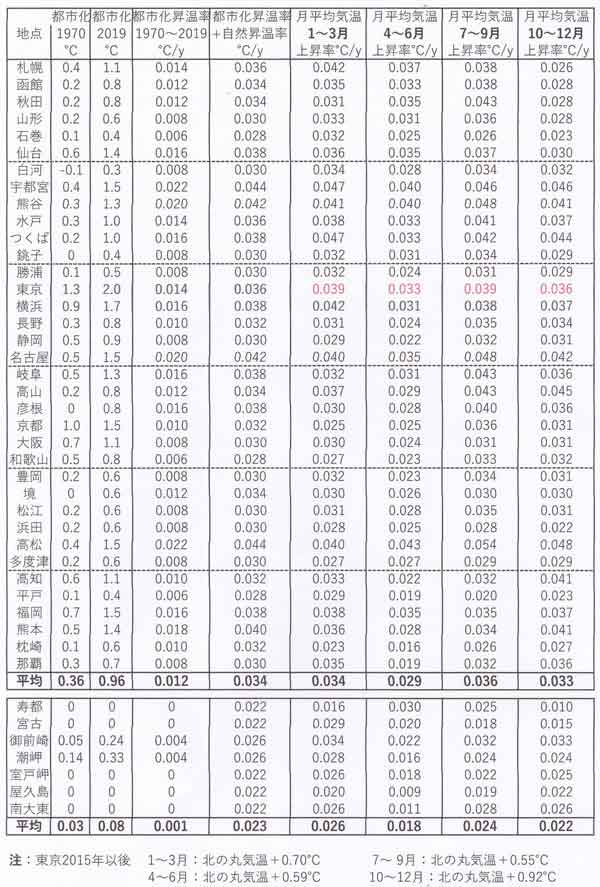
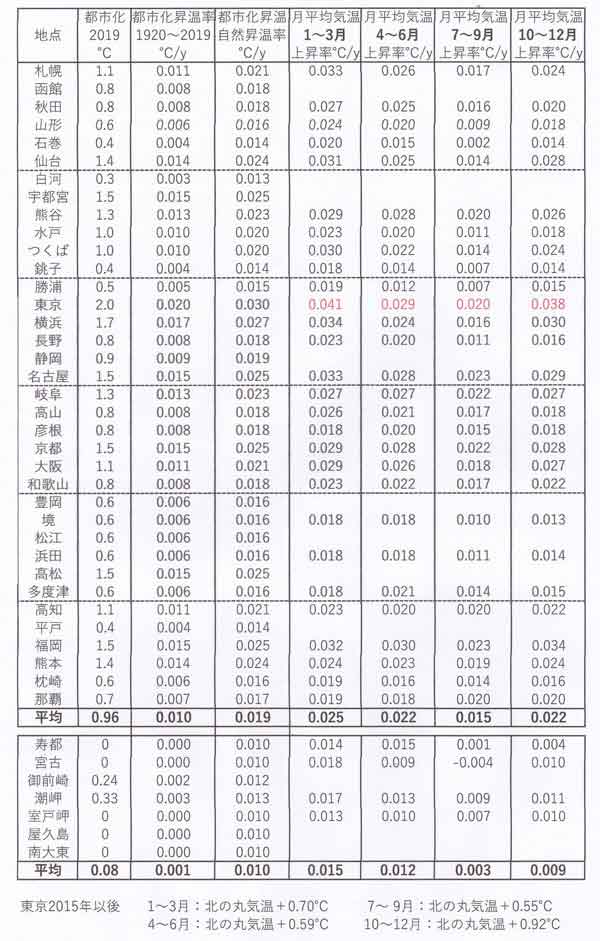
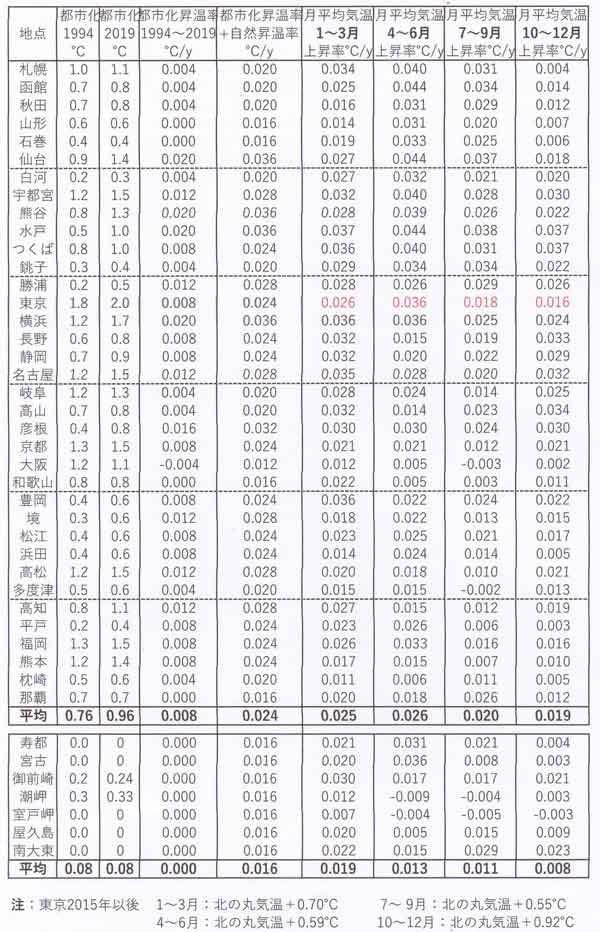
| トップページへ | 研究指針の目次 |